法人税等調整額とは?調整対象や計算方法をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
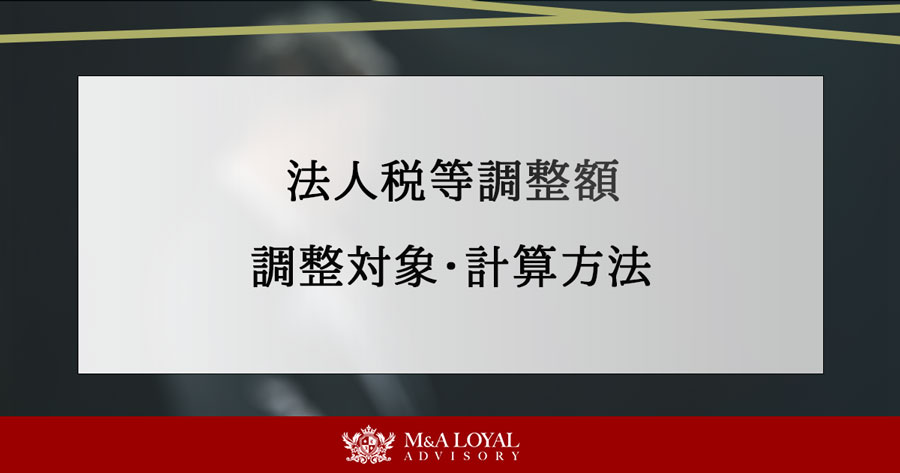
法人税等調整額とは、税務上の所得と会計上の利益の間に生じる差異を調整するための勘定科目です。企業の損益計算書において、税引前当期純利益に対する法人税の負担を適切に表示するため、税効果会計の仕組みを通じて計算されます。中小企業の経営者にとっても法人税等調整額とは、財務諸表の理解や事業承継、M&A検討時に重要な概念となります。 本記事では、法人税等調整額とはどういうものか、その基本的な仕組みから計算方法、具体的な調整対象まで、専門用語を交えながらもわかりやすく解説します。
目次
法人税等調整額の基本概念などをわかりやすく解説
法人税等調整額を理解するためには、まず税効果会計の基本的な考え方を把握することが重要です。企業の会計処理では、会計上の利益と税務上の所得に差異が生じることが一般的で、この差異を適切に調整する仕組みが税効果会計となります。
税効果会計とは、企業が計上する法人税等の額を、その期の会計上の利益に対応させる会計処理方法です。つまり、会計上の利益に見合った法人税負担額を損益計算書に表示することで、財務諸表の利用者にとってより理解しやすい情報を提供することを目的としています。
会計上の利益と税務上の所得の違い
会計上の利益と税務上の所得は、基準の違いにより一致しないことが一般的です。この差異は、会計と税務の目的や考え方の違いから生じるものです。
会計上の利益は、企業の経営成績を株主や債権者などのステークホルダーに適切に報告することを目的として算出されます。一方、税務上の所得は、公平な課税を実現するために法人税法の規定に従って計算されるものです。両者の目的が異なるため、同一の取引であっても会計処理と税務処理で異なる扱いを受けることがあります。
例えば、減価償却費については、会計上は企業の実態に応じて合理的な償却方法を選択できますが、税務上は法人税法で定められた方法に従って計算する必要があります。このような処理の違いが、会計上の利益と税務上の所得の差異を生み出す要因となっています。
法人税等調整額が発生する仕組み
法人税等調整額は、会計上の利益と税務上の所得の差異に法定実効税率を乗じて計算されます。この調整額により、損益計算書上の法人税等の負担額が会計上の利益に対応したものとなります。
法人税等調整額の発生により、企業は実際に納付する法人税額と損益計算書に計上する法人税等の額を区別して管理することができるようになります。これにより、財務諸表の利用者は企業の真の収益力をより正確に把握することが可能となります。
具体的には、会計上の利益が税務上の所得よりも大きい場合、将来的に税負担が軽減される要因があることを示し、繰延税金資産が計上されます。逆に、会計上の利益が税務上の所得よりも小さい場合、将来的に追加的な税負担が発生する要因があることを示し、繰延税金負債が計上されます。これにより、企業は将来の税務リスクを適切に評価できるようになります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



一時差異と永久差異の種類と特徴
法人税等調整額の計算において、会計上の利益と税務上の所得の差異は、一時差異と永久差異の二つに分類されます。この分類は、税効果会計を適用する上で極めて重要な概念となります。
一時差異とは、会計上の資産や負債の帳簿価額と税務上の資産や負債の帳簿価額との間に生じる差異のうち、将来の会計期間において解消されることが見込まれるものです。一方、永久差異は、将来にわたって解消されることがない差異を指します。
一時差異の具体例と費用の計算方法
一時差異の代表的な例として、減価償却費の差異があります。会計上の減価償却費と税務上の減価償却費(減価償却限度額)が異なる場合、その差額は一時差異として扱われます。
例えば、取得価額100万円の設備について、会計上は定額法で5年償却(年間20万円)、税務上は定率法で償却する場合を考えてみましょう。1年目の税務上の償却額が25万円だった場合、会計と税務の差異は5万円となり、この5万円が一時差異として認識されます。
| 項目 | 会計処理 | 税務処理 | 一時差異 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費(1年目) | 20万円 | 25万円 | 5万円(将来加算) |
| 貸倒引当金 | 実質基準 | 法定繰入率 | 超過分(将来減算) |
| 賞与引当金 | 発生主義 | 支給時損金 | 全額(将来減算) |
| 退職給付引当金 | 退職給付債務 | 支給時損金 | 全額(将来減算) |
貸倒引当金についても一時差異が生じる典型例です。会計上は債権の回収可能性を個別に検討して引当金を設定しますが、税務上は法定繰入率による計算が原則となります。会計上の引当金が税務上の損金算入限度額を上回る場合、その超過分は将来減算一時差異として認識されます。
一時差異は将来の会計期間において解消されるため、税効果会計の適用対象となり、繰延税金資産または繰延税金負債として貸借対照表に計上されます。この処理により、将来の税負担の変動を適切に財務諸表に反映することが可能となります。
永久差異の特徴と主な項目
永久差異は、会計と税務の処理方法の根本的な違いから生じる差異で、将来にわたって解消されることがありません。そのため、税効果会計の適用対象外となり、法人税等調整額の計算には含まれません。
永久差異の代表的な項目には、交際費の損金不算入があります。会計上は必要な経費として計上された交際費であっても、税務上は損金不算入とされる部分があります。この損金不算入額は将来の会計期間においても解消されることがないため、永久差異として扱われます。
その他の永久差異の例として、以下のような項目があります。
- 受取配当金の益金不算入額
- 罰金や過料などの損金不算入額
- 寄附金の損金不算入額
- 法人税等の損金不算入額
- 住民税均等割の損金不算入額
これらの永久差異は、会計上の利益と税務上の所得の恒久的な差異として認識され、税効果会計の対象とはなりません。企業の財務分析や税務計画を立案する際には、永久差異の存在を十分に考慮することが重要となります。
勘定科目の繰延税金資産・負債の計算と仕訳処理
繰延税金資産と繰延税金負債は、一時差異に税効果会計を適用することで生じる勘定科目です。これらは将来の税負担の変動を現在の財務諸表に適切に反映させるための重要な仕組みとなります。
繰延税金資産は、将来の会計期間において税負担が軽減される要因がある場合に計上される資産項目です。一方、繰延税金負債は、将来の会計期間において追加的な税負担が発生する要因がある場合に計上される負債項目です。
繰延税金資産の計算方法と計上要件
繰延税金資産は、将来減算一時差異に法定実効税率を乗じて計算されます。将来減算一時差異とは、将来の会計期間において税務上の所得を減少させる効果を持つ差異のことです。
具体的な計算例として、賞与引当金100万円を設定した場合を考えてみましょう。この賞与引当金は会計上は当期の費用として計上されますが、税務上は実際に賞与を支給した期に損金算入されます。法定実効税率を30%とすると、繰延税金資産は100万円×30%=30万円となります。
繰延税金資産の計上には、将来の税負担軽減効果を享受できる可能性が高いという要件があります。つまり、将来において十分な課税所得が見込まれ、繰延税金資産を回収できる可能性が高い場合にのみ計上が認められます。
繰延税金資産の回収可能性は、以下の要素で判断します。
- 将来の事業計画に基づく課税所得の見込み
- 繰越欠損金の存在とその消化可能性
- 将来加算一時差異との相殺効果
- 企業の収益体質や事業環境の変化
回収可能性に疑義がある場合は、繰延税金資産の計上額を減額する必要があり、この減額部分は評価性引当額として処理されます。
繰延税金負債の計算と会計処理
繰延税金負債は、将来加算一時差異に法定実効税率を乗じて計算されます。将来加算一時差異とは、将来の会計期間において税務上の所得を増加させる効果を持つ差異のことです。
代表的な例として、圧縮記帳による一時差異があります。国庫補助金を受けて固定資産を取得し、圧縮記帳を適用した場合、会計上の固定資産簿価と税務上の簿価に差異が生じます。この差異は将来の減価償却を通じて解消されますが、その過程で税務上の所得が会計上の利益を上回ることになります。
例えば、1,000万円の設備について200万円の圧縮記帳を行った場合、会計上の簿価は1,000万円、税務上の簿価は800万円となります。この200万円の差異に法定実効税率30%を乗じた60万円が繰延税金負債として計上されます。
繰延税金負債の仕訳処理は以下のようになります。
- 圧縮記帳時:法人税等調整額 60万円 / 繰延税金負債 60万円
- 減価償却時(毎期):繰延税金負債 6万円 / 法人税等調整額 6万円
繰延税金負債は将来の税負担増加を表すため、原則として全額を計上する必要があり、繰延税金資産のような回収可能性の判断は不要です。ただし、企業が清算予定である場合など、特殊な状況では計上額の調整が検討される場合もあります。
法人税等調整額の仕訳例と別表4との関係
法人税等調整額の仕訳は、繰延税金資産・負債の増減によって決定されます。期末において、繰延税金資産が増加する場合は法人税等調整額を借方に計上し、繰延税金負債が増加する場合は法人税等調整額を貸方に計上します。
具体的な仕訳例を示します。例えば、当期に賞与引当金200万円を新たに設定し、退職給付引当金が100万円増加、設備の税務上の減価償却超過額が50万円発生した場合(法定実効税率30%)の処理は以下のようになります。
- 賞与引当金に係る繰延税金資産:200万円×30%=60万円
- 退職給付引当金に係る繰延税金資産:100万円×30%=30万円
- 減価償却超過に係る繰延税金資産:50万円×30%=15万円
この場合の法人税等調整額は、60万円 + 30万円 + 15万円 = 105万円となります。もし繰延税金資産が増加する場合、仕訳は以下のようになります。
- 繰延税金資産 105万円 / 法人税等調整額 105万円
法人税申告書の別表4は、会計上の利益を税務上の所得に調整するための明細書です。別表4に記載される加算・減算項目が一時差異に該当する場合、それらが税効果会計の計算対象となります。別表4の作成と税効果会計の適用は密接な関係があるため、両者を整合的に処理することが重要です。
法人税等調整額の計算実務と注意点
法人税等調整額の計算実務では、理論的な理解に加えて、実際の計算手順や注意すべきポイントを把握することが重要です。 特に中小企業においては 、税理士との連携や適切な会計システムの活用が効率的な処理につながります。
法定実効税率の適用や繰越欠損金の取扱い、現金の出入りとの関係など、実務上で発生する様々な論点について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。
法定実効税率の計算と適用方法
法人税等調整額の計算において、法定実効税率は最も重要な要素の一つです。 法定実効税率は、法人税、住民税、事業税を総合した実質的な税負担率を表し、地域や企業規模によって異なります。
法定実効税率の基本的な計算式は以下のとおりです。
- 法定実効税率 = {法人税率 × (1 + 住民税率) + 事業税率} ÷ (1 + 事業税率)
例えば、法人税率23.2%、住民税率20.7%、事業税率7%の場合、法定実効税率は約30.62%となります。この税率を一時差異に乗じることで、繰延税金資産・負債の計算を行います。
法定実効税率は税制改正により変更される可能性があるため、将来の一時差異解消時点の税率を適用する必要があります。税率が変更される場合は、既に計上されている繰延税金資産・負債についても税率変更の影響を反映させ、その差額を法人税等調整額として処理します。
繰越欠損金の税効果と注意事項
繰越欠損金については、将来の課税所得との相殺により税負担軽減効果をもたらすため、一定の要件を満たす場合に繰延税金資産として計上することができます。 ただし、繰越欠損金に係る繰延税金資産は、特に慎重な回収可能性の判断が必要となります。
繰越欠損金の繰延税金資産を計上する際の主な考慮事項は以下のとおりです。
- 将来5年間の課税所得見込みとの整合性
- 繰越期限内での消化可能性
- 事業環境の変化や業績の安定性
- 将来加算一時差異との相殺効果
- グループ法人税制による通算効果
例えば、当期に1,000万円の繰越欠損金が発生し、翌期以降の課税所得見込みが年間200万円の場合、5年間で消化可能な金額は1,000万円となります。法定実効税率30%を適用すると、300万円の繰延税金資産計上が理論的には可能ですが、 回収可能性を慎重に判断する必要があります。
繰越欠損金の税効果については、企業の継続企業の前提や将来の収益計画の実現可能性を十分に検討し、保守的な判断を行うことが重要です。過大な繰延税金資産の計上は、財務諸表の信頼性を損なう恐れがあるため注意が必要です。
税効果会計と現金の出入りの関係
法人税等調整額の理解において重要なポイントの一つは、税効果会計が現金の出入りを伴わない会計処理であるということです。実際の法人税の納付額と損益計算書上の法人税等の金額は一致せず、この差額が法人税等調整額として表示されます。
例えば、当期の会計上の利益が1,000万円、税務上の所得が800万円、法定実効税率が30%の場合を考えてみましょう。
- 実際の法人税納付額:800万円×30%=240万円
- 会計上の法人税負担額:1,000万円×30%=300万円
- 法人税等調整額:300万円-240万円=60万円(借方)
この場合、実際には240万円の現金支出となりますが、損益計算書上は300万円の税負担として表示され、60万円の法人税等調整額が計上されます。この60万円は現金の出入りを伴わない純粋な会計上の調整項目となります。
税効果会計の適用により、期間損益の平準化効果が期待できます。一時的な大きな差異が生じた年度においても、税効果会計により適切な期間配分が行われ、企業の収益力をより正確に把握することが可能となります。
M&Aにおける法人税等調整額の影響と評価
M&Aの実行時において、法人税等調整額は企業価値評価に重要な影響を与える要素となります。買収価格の算定や財務デューデリジェンスの過程で、繰延税金資産・負債の妥当性や将来の税負担見込みを適切に評価することが必要です。
特に中小企業のM&Aでは、税効果会計の適用状況や一時差異の内容が企業価値に大きく影響する場合があります。 売り手企業としては適切な税効果会計の適用により企業価値の向上を図り、買い手企業としては潜在的な税務リスクを適切に評価することが重要となります。
企業価値評価における税効果の考慮
DCF法による企業価値評価では、将来キャッシュフローの算定において税効果を適切に反映させる必要があります。繰延税金資産・負債の解消により、将来の実際の税負担額が損益計算書上の税費用と異なる可能性があるためです。
例えば、大幅な繰延税金資産を計上している企業の場合、将来における税負担軽減効果により、実際のキャッシュフローは損益計算書から推定される金額よりも大きくなる可能性があります。逆に、繰延税金負債が多額に計上されている場合は、将来の追加的な税負担により、キャッシュフローが圧迫される要因となります。
M&Aの価格算定では、繰延税金資産の回収可能性や繰延税金負債の解消時期を詳細に分析し、将来キャッシュフローへの影響を適切に織り込むことが重要です。特に繰越欠損金に係る繰延税金資産については、買収後の事業計画との整合性を慎重に検討する必要があります。
また、買収により事業統合が行われる場合、一時差異の内容や解消パターンが変化する可能性があります。例えば、買収に伴い資産の時価評価が行われる場合、新たな一時差異が発生し、税効果会計の適用対象となることがあります。
デューデリジェンスでの税効果検証ポイント
財務デューデリジェンスでは、対象企業の税効果会計適用状況について詳細な検証を行います。主な検証ポイントは、計算の正確性、回収可能性の妥当性、将来の税負担見込みなどです。
繰延税金資産の回収可能性については、以下の観点から検証を行います。
- 将来の課税所得見込みの合理性
- 事業計画の実現可能性と過去の計画達成率
- 一時差異の解消スケジュールの妥当性
- 税率変更や税制改正の影響
特に中小企業の場合、税効果会計の適用が不十分である可能性もあります。適切な税効果会計を適用した場合の財務諸表の修正再表示や、それに伴う企業価値への影響を評価する必要があります。
また、対象企業に特殊な税務上の取扱いがある場合、それらが一時差異として適切に認識されているかを確認します。例えば、研究開発税制や設備投資税制の適用により生じる税務上の優遇措置については、会計上の処理との差異を適切に把握することが重要です。
デューデリジェンスの結果、重要な税効果の修正が必要となった場合は、買収価格への影響を定量的に評価し、条件交渉に反映させることが必要です。また、買収実行後の税務統合計画についても、税効果会計の観点から検討を行うことが望ましいといえます。
事業承継における税効果の活用
事業承継の場面においても、法人税等調整額の理解は重要な意味を持ちます。後継者への事業承継を検討する際、企業の財務体質の改善や税負担の最適化を図る観点から、税効果会計の活用を検討することができます。
例えば、退職給付制度の見直しや設備投資計画の調整により、一時差異の発生パターンをコントロールし、税負担の平準化を図ることが可能です。また、事業承継税制の適用を検討する際には、繰延税金資産・負債が企業の財政状態に与える影響を適切に評価することが必要となります。
M&A仲介会社やファイナンシャルアドバイザーとしては、これらの税効果に関する専門知識を活用し、クライアントの利益最大化に向けた適切なアドバイスを提供することが求められます。
まとめ
法人税等調整額は、企業の会計上の利益と税務上の所得の差異を調整し、適切な期間損益を表示するための重要な仕組みです。税効果会計の適用により、繰延税金資産・負債を通じて将来の税負担変動を財務諸表に適切に反映させることができます。
一時差異と永久差異の区別、繰延税金資産の回収可能性判断、法定実効税率の適用など、法人税等調整額の理解には多くの専門知識が必要となります。特にM&Aや事業承継の場面では、税効果会計が企業価値評価に重要な影響を与えるため、適切な理解と活用が不可欠です。
中小企業の経営者様におかれましては、税理士や会計士などの専門家と連携し、自社の税効果会計の適用状況を定期的に見直すことをお勧めいたします。適切な税効果会計の運用により、財務諸表の信頼性向上と企業価値の最大化を図ることが可能となるでしょう。法人税等調整額の理解を深め、戦略的な経営判断にお役立ていただければ幸いです。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。












