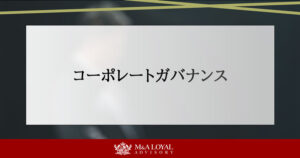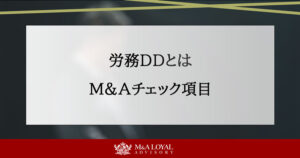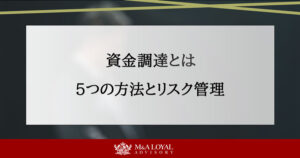コンプライアンス違反とは?事例や罰則、パワハラとの関係を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
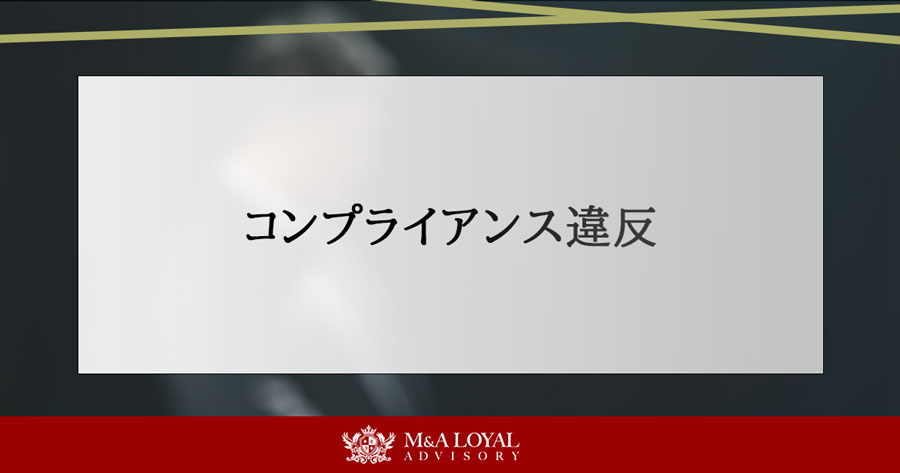
企業における信頼と持続的成長の鍵となるのが「コンプライアンス(法令遵守)」です。コンプライアンス違反とは、法律や社内規程、社会的倫理に反する行為を指し、発覚すれば企業価値やブランドの大きな損失につながります。
近年では、情報漏えいや不正会計、ハラスメントなど、多様な分野でコンプライアンス違反が問題視されています。経営層や社員一人一人の意識不足や教育体制の欠如が、その背景にあります。
本記事では、コンプライアンス違反の定義や具体例、発生原因、リスク、そして防止のための仕組みづくりまでを解説します。企業経営における重要な基礎知識として、理解を深めましょう。
目次
コンプライアンス違反とは
まず、コンプライアンス違反に関する基本的な知識について解説します。
コンプライアンス違反の意味をわかりやすく解説
コンプライアンス違反とは、企業や個人が法令や社会的規範、または社内規定に反する行為を指します。単なる法律違反だけでなく、倫理やモラルに反する行動も含まれるため、その範囲は非常に広いです。
具体的な例としては、情報漏えいや贈収賄、不正会計、ハラスメントなどが挙げられます。これらの行為は企業の信頼を失墜させ、社会的評価の低下や法的制裁を招く恐れがあります。
コーポレートガバナンスとの違い
コンプライアンス違反とは、企業や個人が法令や倫理、社内規定などに反する行為を行うことを指します。法律違反だけでなく、不正会計やハラスメントなど社会的信用を損なう行動も含まれます。
一方、コーポレートガバナンスとは、企業が健全で透明な経営を行うための仕組みや体制のことです。経営陣の暴走を防ぎ、株主や利害関係者の利益を守る役割を果たします。
つまり、コンプライアンスは「守るべきルール」、ガバナンスは「守らせる仕組み」です。ガバナンスが適切に機能していれば、コンプライアンス違反の未然防止につながるといえます。
コンプライアンス違反の基準
コンプライアンス違反の基準には、次のものがあります。
- 法令違反
- 社内規程違反
- 社会規範違反
それぞれを解説します。
法令違反
法令違反とは、企業や個人が国や自治体が定めた法律・条例・規則などに反する行為を行うことを指します。コンプライアンス違反の中でも最も基本的で、社会的影響が大きいものです。
具体的には、脱税や独占禁止法違反、労働基準法違反、環境規制の無視などが挙げられます。これらは刑事罰や行政処分の対象となり、企業の信用失墜や事業停止を招くことがあります。
社内規程違反
社内規程違反とは、企業が独自に定めた就業規則や行動基準、倫理規定などに反する行為を指します。法令違反に至らなくても、企業秩序や信頼を損なう重要な問題とされています。
具体的な例としては、無断欠勤や情報の不正持ち出し、職務上の不正行為、ハラスメントなどが挙げられます。これらは懲戒処分の対象となり、組織全体の士気低下を引き起こす恐れがあります。
社会規範違反
社会規範違反とは、法律や社内規程に反しなくても、社会的常識や倫理に背く行為を指します。人として守るべき価値観や公正さを欠く行動は、企業の信頼を大きく損なう原因となります。
例えば、顧客を軽視する発言や環境への無責任な対応、差別的な態度などが該当します。こうした倫理に反する行動は、法的制裁がなくても企業のイメージを著しく悪化させます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



コンプライアンス違反の具体例
コンプライアンス違反は次のように分類できます。
- 労務・人事関連
- 情報管理・知的財産関連
- 財務・取引関連
- 経営・役員行動関連
- 社会的責任関連
それぞれの具体例を分かりやすく解説します。
労務・人事関連
長時間労働・残業代未払い
長時間労働や残業代未払いは、労働基準法に違反する典型的なコンプライアンス違反です。過重労働は社員の健康を損ない、企業の社会的信用を失う要因です。
残業代を適切に支払わない行為は、法令違反に加えて労使関係の悪化を招きます。結果として離職率の上昇や訴訟リスクの増大にもつながります。
防止には、労働時間の適正な管理と労務制度の見直しが重要です。企業は働き方改革を推進し、健全で公正な労働環境の整備に努める必要があります。
パワハラ・セクハラ・マタハラ
パワハラやセクハラ、マタハラは、職場でのハラスメント行為として重大なコンプライアンス違反です。被害者の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させます。
威圧的な言動や性的発言、妊娠・育児を理由とした不当な扱いが典型例です。放置すれば組織の信頼を失います。
防止には、研修や相談窓口の整備が重要です。企業は早期対応と再発防止に努め、安心して働ける職場づくりを進めます。
採用差別・不当解雇・労働契約違反
採用差別や不当解雇、労働契約違反は、労働法に反する重大なコンプライアンス違反です。公平な雇用機会を損ない、企業の社会的信用を失う原因です。
具体的には、性別や年齢、国籍などを理由にした採用拒否や、正当な理由のない解雇が該当します。契約内容を守らないことも違反に当たります。
防止には、公正な採用基準の策定と契約内容の明確化が重要です。企業は法令を遵守し、誰もが平等に働ける職場環境を整える必要があります。
労働安全衛生法違反(危険作業の放置など)
労働安全衛生法違反は、労働者の安全を守る義務を怠る重大なコンプライアンス違反です。危険作業の放置や管理不足は、事故や災害を招く恐れがあります。
保護具の未着用を黙認したり、過剰な労働を強いたりする行為も問題です。企業の安全意識の欠如が原因となります。
防止には、安全教育と現場点検の徹底が重要です。企業は安心して働ける環境を整え、健康と安全を守る責任を果たす必要があります。
情報管理・知的財産関連
個人情報・顧客情報の漏えい
個人情報や顧客情報の漏えいは、企業の信頼を著しく損なう重大なコンプライアンス違反です。情報管理の不備や不正利用が原因で発生します。
具体的には、データの誤送信やサーバーの不正アクセスなどが挙げられます。漏えいが起これば、顧客被害や損害賠償に発展する恐れがあります。
防止には、情報の暗号化やアクセス権限の管理が重要です。社員一人一人が情報保護の意識を持ち、厳重な管理体制を維持することが求められます。
機密情報・営業秘密の持ち出し
機密情報や営業秘密の持ち出しは、企業の競争力を脅かす重大なコンプライアンス違反です。意図的な流出や管理不足によって発生し、経営に深刻な影響を与えます。
具体的には、退職者による情報の持ち出しや、外部との不正共有などが挙げられます。漏えいすれば取引先との信頼関係も損なわれます。
防止には、情報の管理体制を強化し、アクセス制限や監視を徹底することが必要です。
著作権・商標権の侵害
著作権や商標権の侵害は、他者の知的財産を不正に利用する行為であり、重大なコンプライアンス違反です。企業の信頼やブランド価値を損なう恐れがあります。
無断で画像や文章を使用したり、他社のロゴを模倣したりする行為が該当します。発覚すれば法的措置を受ける可能性があります。
防止には、知的財産の正しい理解と確認体制の整備が重要です。
無断コピー・不正ソフトウエア利用
無断コピーや不正ソフトウエアの利用は、著作権法に違反する重大なコンプライアンス違反です。企業の信頼を失い、法的責任を問われる恐れがあります。
具体的には、ライセンスを取得せずにソフトを使用したり、正規品を複製して共有したりする行為が該当します。発覚すれば罰金や損害賠償が発生します。
防止には、使用ソフトの管理徹底とライセンス確認が重要です。
財務・取引関連
不正会計・粉飾決算
不正会計や粉飾決算は、企業の財務情報を意図的に偽る重大なコンプライアンス違反です。投資家や取引先を欺く行為であり、社会的信用を失う原因です。
具体的には、売り上げや利益を水増ししたり、損失を隠したりする操作が該当します。発覚すれば法的処罰や上場廃止に至ることもあります。
防止には、内部統制の強化と監査体制の厳格な運用が必要です。経営陣が透明性を重視し、誠実な会計処理を徹底することが求められます。
補助金・助成金の不正受給
補助金や助成金の不正受給は、公的資金を不正に得る重大なコンプライアンス違反です。企業の社会的信用を失い、返還命令や刑事罰を受ける恐れがあります。
具体的には、虚偽の申請書を提出したり、経費を水増しして報告したりする行為が該当します。悪質な場合は詐欺罪に問われることもあります。
贈収賄・キックバック・利益供与
贈収賄やキックバック、利益供与は、公正な取引を妨げる重大なコンプライアンス違反です。金品や便宜の授受により、不当な利益を得る行為を指します。
具体的には、契約の見返りに金銭を渡したり、取引先から不正な報酬を受け取ったりするケースが該当します。発覚すれば刑事罰の対象となります。
インサイダー取引・相場操縦
インサイダー取引や相場操縦は、金融市場の公正性を損なう重大なコンプライアンス違反です。企業の内部情報を不正に利用し、利益を得る行為を指します。
具体的には、未公開情報を基に株を売買したり、虚偽情報で株価を操作したりする行為が該当します。発覚すれば厳しい刑事罰が科されます。
経営・役員行動関連
役員や管理職の異性トラブル・不正接待
役員や管理職の異性トラブルや不正接待は、企業の倫理に反する重大なコンプライアンス違反です。組織の信用を失い、内部統制の信頼性にも影響します。
具体的には、職権を利用した不適切な関係や、取引先への過度な接待・贈答などが該当します。発覚すれば社会的批判や処分の対象となります。
防止には、倫理規程の徹底と管理職への教育強化が重要です。企業は公私の区別を明確にし、誠実で透明な行動を求める姿勢を示す必要があります。
利益相反行為(私的ビジネス関与など)
利益相反行為は、役員や社員が自らの利益を優先し、企業の利益を損なう行為を指します。特に経営層による私的ビジネス関与は重大なコンプライアンス違反です。
具体的には、取引先への便宜供与や、自身が関係する会社への優遇取引などが該当します。企業の公正性や信頼を大きく損ないます。
防止には、取引の透明化と利益相反の申告制度が重要です。企業は明確なルールを設け、役員の行動を適正に管理する体制を整える必要があります。
社用車・備品・経費の私的利用
社用車や備品、経費の私的利用は、企業資産の不正使用にあたるコンプライアンス違反です。小さな行為でも発覚すれば信用を失い、懲戒処分の対象となります。
具体的には、社用車を私用で使用したり、個人的な支出を経費として申請したりする行為が該当します。組織のモラル低下にもつながります。
防止には、経費申請ルールの明確化と監査体制の強化が重要です。
企業倫理・ガバナンス方針への違反
企業倫理やガバナンス方針への違反は、経営の根幹を揺るがす重大なコンプライアンス違反です。経営層が方針を軽視すれば、組織全体の倫理意識が低下します。
具体的には、透明性を欠いた意思決定や、不正を見逃す行為などが該当します。企業の信頼性を損ない、社会的批判を招く恐れがあります。
社会的責任関連
SNS・インターネット上での不適切発言・炎上
SNSやインターネット上での不適切発言や炎上は、企業や社員の信用を損なう重大なコンプライアンス違反です。個人の投稿でも企業全体に影響します。
差別的な発言や顧客への中傷、内部情報の漏えいなどが該当します。拡散すれば社会的批判を招く恐れがあります。
防止には、SNS利用ルールの明確化と教育が重要です。社員は公の発言に責任を持ち、節度ある利用を心がける必要があります。
顧客・取引先への虚偽説明・誇大広告
顧客や取引先への虚偽説明や誇大広告は、公正な取引を損なう重大なコンプライアンス違反です。事実と異なる情報提供は、信頼を失う原因となります。
具体的には、商品性能を誇張した広告や、契約内容を偽って説明する行為が該当します。発覚すれば行政処分や損害賠償の対象となります。
防止には、表示内容や説明文の確認体制を整えることが重要です。
差別的言動・社会通念に反する発言
差別的言動や社会通念に反する発言は、人権や多様性を軽視する重大なコンプライアンス違反です。企業の評判を損ない、職場環境の悪化を招く恐れがあります。
具体的には、性別や国籍、年齢などに基づく差別発言や、社会的に不適切な表現が該当します。SNS上での発言も問題となります。
環境法令違反(廃棄物処理、排出規制違反など)
環境法令違反は、企業が廃棄物処理や排出規制などの環境基準に反する行為を行う重大なコンプライアンス違反です。社会的信頼を失う原因となります。
具体的には、不法投棄や排水・排ガスの基準超過、リサイクル義務の不履行などが該当します。発覚すれば行政処分や罰金が科されます。
防止には、環境管理体制の整備と定期的な監査が重要です。
コーポレート・ソーシャル・リスポンシビリティ(CSR)軽視行為
CSR軽視行為は、企業が社会的責任を怠り、利益を優先することで信頼を損なうコンプライアンス違反です。社会からの評価低下を招きます。
具体的には、環境保護や地域貢献を無視したり、従業員や取引先への配慮を欠いたりする行為が該当します。
コンプライアンス違反のリスク
コンプライアンス違反にはさまざまな種類がありますが、いずれでも発覚すると、次のようなリスクがあります。
- ブランドイメージが悪くなる
- 採用が難しくなる
- 資金調達が難しくなる
- 法的責任を負う
- ステークホルダーへ悪影響が波及する
それぞれを詳しく解説します。
ブランドイメージが悪くなる
ブランドイメージの悪化は、コンプライアンス違反によって生じる重大なリスクの一つです。企業の不正や不祥事が報道されると、社会的信用が失われ、長年築いた信頼が一瞬で崩れます。
特にお客様や取引先からの評価が下がり、商品やサービスの利用を避けられる可能性があります。新規取引の機会を失い、既存の関係も断たれるなど、経営への影響は深刻です。
採用が難しくなる
コンプライアンス違反が発生すると、企業の評判が低下し、採用活動にも大きな影響を及ぼします。不祥事を起こした企業は、求職者から敬遠されやすくなり、人材確保が難しくなります。
また、既存社員の士気が下がり、組織への信頼を失うことで離職率の上昇を招く恐れがあります。優秀な人材ほど、倫理意識の高い職場を求めて離れていく傾向があります。
資金調達が難しくなる
コンプライアンス違反が起こると、金融機関や投資家からの信頼を失い、資金調達が難しくなります。企業の信用力が低下すれば、融資や出資の対象から外される恐れがあります。
特に金融機関は、法令違反や不正行為に厳しく対応するため、取引条件の悪化や融資停止といった事態を招くことがあります。結果として、事業の継続にも支障が生じます。
法的責任を負う
コンプライアンス違反は、企業や関係者が法的責任を負う重大なリスクを伴います。内容によっては、行政処分や罰金などの厳しい措置を受ける可能性があります。
また、被害者や取引先から損害賠償を請求されることもあります。さらに、悪質な場合には刑事罰の対象となり、経営者や社員個人が処罰されるケースもあります。
ステークホルダーへ悪影響が波及する
コンプライアンス違反は、企業単体の問題にとどまらず、子会社や親会社、株主など幅広いステークホルダーへ悪影響を及ぼします。信頼低下はグループ全体の評価に直結します。
子会社の不正が親会社の責任として問われることもあり、株主からの批判や訴訟リスクが高まります。経営全体へのダメージは計り知れません。
コンプライアンス違反が発生する原因
コンプライアンス違反が発生する原因には、次の点が挙げられます。
- そもそもコンプライアンスを経営者が理解していない
- コンプライアンス遵守のルールが制定されていない
- ルールはあっても法改正や現場に対応できていない
- ルールはあってもチェック体制・運用が不十分
- 社員の教育ができていない
それぞれを解説します。
そもそもコンプライアンスを経営者が理解していない
コンプライアンス違反の大きな原因の一つに、経営者自身がコンプライアンスの意義を正しく理解していないことがあります。形だけのルール遵守にとどまってしまう場合です。
経営者が法令や倫理を軽視すれば、組織全体にその姿勢が浸透し、社員の意識も低下します。結果として、不正や隠蔽(いんぺい)が常態化する危険性があります。
コンプライアンス遵守のルールが制定されていない
コンプライアンス違反が起こる背景には、企業内で明確な遵守ルールが定められていないことがあります。基準が曖昧だと、社員が判断に迷い、不正を見逃すリスクが高まります。
ルールがなければ、違反行為が発生しても責任の所在が不明確になり、再発防止も困難です。特に急成長企業では体制整備の遅れが問題となります。
ルールはあっても法改正や現場に対応できていない
コンプライアンス違反は、ルールが存在していても内容が古く、法改正や現場の実情に対応していない場合にも発生します。形だけの規程では実効性がありません。
現場での業務が複雑化する中、古いルールを放置すると、知らぬ間に法令違反につながることがあります。特に労務管理や個人情報保護ではリスクが高まります。
ルールはあってもチェック体制・運用が不十分
コンプライアンス違反は、ルールが整備されていてもチェック体制や運用が不十分な場合に発生します。形式的な仕組みだけでは、実際の不正を防げません。
監査や報告制度が形骸化していると、違反の兆候を見逃しやすいです。管理職の監督不足や内部通報の機能不全も、問題の長期化を招く要因です。
社員の教育ができていない
コンプライアンス違反の原因として、社員教育の不足が挙げられます。教育が行き届かないと、法令や社内規程の理解が浅く、遵守意識が低いまま業務を行うことになります。
意識が低い社員が増えると、小さな不正や誤りが見逃され、結果的に組織全体のモラル低下につながります。悪意がなくても、知らずに違反を犯すリスクも高まります。
コンプライアンス違反を防ぐ方法
コンプライアンス違反全般を未然に防ぐため企業ができることには次のようなものがあります。
- 制度・運用体制を強化する
- 教育・啓発を徹底する
- 組織文化・評価制度を見直す
- 外部・第三者と連携する
- デジタルテクノロジーを活用する
それぞれを詳しく解説します。
制度・運用体制を強化する
コンプライアンス違反を防ぐには、制度と運用体制の強化が不可欠です。
主な取り組みとして次のような施策が挙げられます。
- 内部通報制度(ホットライン・匿名相談窓口)の整備
- コンプライアンス委員会や専任部署の設置
- 定期的な内部監査・外部監査の実施
- リスクアセスメントやセルフチェックの定期化
- ルール・マニュアル・就業規則の最新化と公開
- 契約書・業務委託先の遵法条項(コンプライアンス条項)整備
これらを継続的に運用することで、組織全体の遵法意識を高められます。
教育・啓発を徹底する
コンプライアンス違反を防ぐには、教育と啓発を継続的に徹底することが重要です。
具体的な取り組みとして次の施策が効果的です。
- 新入社員・管理職・役員向けの階層別コンプライアンス研修
- eラーニング・ケーススタディなど実践的な教育手法の導入
- 定期的なテストや理解度確認による知識定着
- 社内ポスターや社報・イントラでの啓発活動
- 倫理ハンドブックやチェックリストの配布
これらにより社員の意識を高め、違反を未然に防ぐ企業文化を育てられます。
組織文化・評価制度を見直す
コンプライアンス違反を防ぐには、組織文化と評価制度の見直しが欠かせません。特に経営層の姿勢と公正な評価が重要です。
具体的には次の施策が効果的です。
- トップマネジメントによる遵法メッセージ発信(トーン・アット・ザ・トップ)
- コンプライアンス遵守を評価指標・人事評価に反映
- 「報告・相談しやすい職場風土」の醸成
- 違反発生時の迅速・公正な懲戒対応と再発防止策公表
- 倫理的行動をたたえる制度(表彰・インセンティブ)
これにより、法令遵守を重んじる健全な企業文化を定着させられます。
外部・第三者と連携する
コンプライアンス違反を防ぐには、外部や第三者との連携を強化し、客観的な視点で体制を点検することが重要です。
主な取り組みは次のとおりです。
- 外部専門家(弁護士・公認会計士)による定期診断・助言
- グループ企業・取引先へのコンプライアンス教育・契約管理
- 業界団体・行政との情報共有・ガイドライン遵守
- CSR/ESG視点での社会的説明責任を果たす広報活動
外部との連携により、透明性と信頼性の高い経営体制を維持できます。
デジタルテクノロジーを活用する
コンプライアンス違反を防ぐには、デジタル技術を活用して監視・教育・管理を効率化することが重要です。
主な施策は次のとおりです。
- 不正検知システム・アクセスログ監視ツールの導入
- コンプライアンス教育をオンライン化・データ分析で改善
- AIを活用したリスク予兆分析・内部通報の匿名化処理
- 契約・承認フローを電子化し、改ざん防止と透明性を確保
テクノロジーの活用で、早期発見と継続的改善が可能です。
コンプライアンス違反の有名企業の事例
豊田自動織機社
豊田自動織機は、フォークリフトや建設機械用エンジンの排出ガス認証に関して不正を行いました。特別調査委員会の報告により、出力試験で量産用と異なるソフトを使用して数値を安定化させていたことが判明しました。
トヨタ自動車は以上の報告を受け、該当エンジンおよび搭載車両の出荷を一時停止しました。対象は国内外10車種ですが、量産品は基準を満たしており、安全性に問題はないとされています。
以上の不正が発生した背景には、品質よりも効率を優先する企業体質や、法規遵守への意識の欠如があったと指摘されています。
三井住友信託銀行
三井住友信託銀行株式会社の元社員が、インサイダー取引を行っていた疑いで起訴されました。これは金融商品取引法違反にあたる事案であり、2024年11月の発覚以降、大きな社会的注目を集めています。
調査委員会の報告によると、社内管理体制や倫理意識に課題があったことが指摘されました。同社は報告書を受けて、役員報酬の減額と再発防止策の検討を進めています。
信託銀行として高い倫理性が求められるなか、今回の事件は組織の信頼を大きく揺るがしました。同社は内部管理の強化と信頼回復に全力で取り組む姿勢を示しています。
TBSテレビ
TBSテレビは、芸能関係者と社員の関係を調査する中で、過去の番組出演者によるハラスメント事案を確認したと発表しました。当時の対応が不十分であり、「社員を守れなかった」として謝罪しています。
調査では、女性アナウンサーが番組出演者からキスを求められたり、交際を迫られたりする被害が複数確認されました。いずれも上司が適切な対応を取らなかったとされています。
被害者の証言を受け、TBSは人権教育やハラスメント講習を実施しました。今後、重大なコンプライアンス違反が確認された場合は、速やかに公表するとしています。
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJフィナンシャル・グループは、顧客情報の不適切な共有などを理由に、社長を含む21人に社内処分を行いました。役員報酬の減額や退任役員の報酬返上などの措置が取られています。
同社の銀行と証券会社は、情報共有を制限する「ファイアウオール規制」に抵触し、金融庁から業務改善命令を受けていました。法令違反が認定された形です。
再発防止策として、AIによる不正検出や研修強化、罰則の厳格化を実施。三菱UFJは法令遵守の徹底と信頼回復に取り組む姿勢を示しています。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、型式指定申請で不正手続きが発覚し、国土交通省から是正命令を受けました。経営の関与不足やデータ管理の不備など、認証制度に深刻な問題が指摘されました。
再発防止策として、経営層の現場巡視や手順の明確化、内部監査の強化を実施し、経営と現場が連携し、体制の再構築を進めています。
また、教育やデジタル技術の活用を通じて認証業務の透明化を図り、法令遵守意識の徹底を目指す方針です。トヨタ自動車は信頼回復と再発防止に全社で取り組むとしています。
川崎重工業
川崎重工業は、潜水艦乗組員への金品提供問題に関する調査の中間報告を公表しました。不正は約40年前から続いており、下請け会社との架空取引で得た資金が物品購入などに使われていたことが判明しました。
同社は、社外からの指摘で発覚したことを重く受け止め、社長と役員が報酬を返上して謝罪しました。閉鎖的な職場風土が不正を長年見過ごしてきたとしています。
防衛費に税金が使われていることから、同社は不適切な費用を国庫に返還する方針を表明しました。再発防止策を講じ、信頼回復に努めるとしています。
日本郵便
日本郵便では、全国の郵便局で配達員への法定点呼が適切に実施されていなかった問題が発覚しました。国土交通省は、約2500台の貨物車両を対象に自動車運送事業の許可を取り消す方針を固めています。
点呼は運転手の健康状態や飲酒の有無を確認する義務があり、全国3188局のうち75%にあたる2391局で不適切な実施が判明。飲酒運転の事例も複数確認されました。
国交省は特別監査を実施し、厳しい行政処分を検討中です。日本郵便は「社会的インフラを担う事業者として極めて重大な事案」として、再発防止策の検討を進めています。
日清食品
日清食品は、公正取引委員会から独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の疑いで警告を受けました。カップ麺「カップヌードル」など5商品について、小売店に販売価格の引き上げを要請していたとされています。
同社は謝罪し、警告内容を受け入れる姿勢を示しました。法令遵守体制の強化を進めるとしています。
今後は、取締役会での再発防止策の決議を経て、営業活動や社員教育、監査体制の改善を実施し、同様の違反を防ぐ方針です。
三菱ケミカル
三菱ケミカルグループは、子会社の三菱ケミカルが製造・販売する繊維「ソアロン」で認証の不備があったと発表しました。安全性に関わる認証の更新を怠り、虚偽の認証書を顧客に渡して販売していたことが判明しました。
問題は担当者が試験や申請を行わず、認定がないまま販売を続けていたことが原因です。社内の引き継ぎ作業で発覚しました。
同社は「ご迷惑をおかけしたことを深くおわびする」と謝罪。品質や安全性には問題ないと説明し、再発防止に全力で取り組むとしています。
日本航空
日本航空(JAL)の国際線機長が乗務前に飲酒し、3便に遅延を発生させた問題で、国土交通省は同社を厳重注意としました。再発防止策の提出を求め、安全管理体制の不備を指摘しています。
問題の機長は、滞在先のホテルで飲酒した上、アルコール検査の記録を改ざんしていたことが判明しました。過去にも複数回ルールを破っていたことが明らかになりました。
日本航空は2018年以降も飲酒問題を繰り返しており、教育体制や管理の甘さが問われています。国交省は、安全意識の徹底と体制の抜本的な改善を求めています。
コンプライアンス違反に関するQ&A
最後に、コンプライアンス違反に関するよくある質問とその回答を紹介します。
コンプライアンス違反と法律違反は同じか
コンプライアンス違反と法律違反は、似ているようで必ずしも同じではありません。法律違反は明確に法令に反する行為を指し、罰則が科される場合があります。
一方でコンプライアンス違反は、法律だけでなく、社内規程や社会的倫理、企業の行動指針などに反する行為も含み、より広い概念といえます。
つまり、全ての法律違反はコンプライアンス違反ですが、コンプライアンス違反の中には法的罰則がないものもあります。
コンプライアンス違反が発覚した場合、個人はどの程度責任を負うか
コンプライアンス違反が発覚した場合、違反の内容や関与度に応じて、個人にも重大な責任が問われます。特に法令違反を伴う場合は、刑事罰や懲戒処分の対象となります。
また、故意でなくても、注意義務を怠った結果として損害が発生した場合には、懲戒や損害賠償を求められることがあります。役職者には管理責任も発生します。
企業の看板を背負う以上、社員一人一人が高い倫理観を持つことが重要です。日常業務で迷ったときは、上司や相談窓口に確認する姿勢が求められます。
上司や経営層のコンプライアンス違反を見つけた場合はどうすべきか
上司や経営層のコンプライアンス違反を見つけた場合は、感情的に対応せず、客観的な証拠を整理することが大切です。まず事実関係を冷静に確認しましょう。
その上で、社内の内部通報制度や匿名相談窓口を利用し、適切な手段で報告することが重要です。直接指摘することは、トラブルを拡大させる恐れがあります。
企業には、通報者を保護する仕組みが義務付けられています。報復を恐れずに正しい行動を取ることが、組織全体の信頼と健全性を守る第一歩です。
取引先や協力会社のコンプライアンス違反を見つけた場合はどうすべきか
取引先や協力会社のコンプライアンス違反を見つけた場合は、まず、自社内で上司やコンプライアンス担当部署に報告し、独断で行動しないことが重要です。事実確認を慎重に行いましょう。
直接相手を追及すると、関係悪化や情報漏えいのリスクがあります。社内手続きを通じて、正式に対応方針を決定することが望まれます。
企業としては、取引先にも遵法意識を求める姿勢が大切です。契約時にコンプライアンス条項を設け、違反時の対応を明確化することで、再発防止につなげられます。
不正のトライアングルとは何か
「不正のトライアングル」とは、不正行為が発生する三つの要因を示す概念で企業不祥事の分析にも用いられます。
三つの要因とは「動機(プレッシャー)」「機会」「正当化(言い訳)」です。例えば、業績への圧力、監視の甘さ、自分を正当化する心理が重なると不正が起こります。
防止には、過度なノルマを避け、内部統制を強化し、倫理意識を高めることが重要です。企業はこの三要素を抑える仕組みを整える必要があります。
コンプライアンス違反とパワハラの関係とは何か
パワハラは職場での優越的な地位を背景に、業務の適正な範囲を超えて他人に精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。
これは労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)で明確に禁止されており、企業には防止措置義務が課されています。パワハラはコンプライアンス違反の一種です。
まとめ
コンプライアンス違反は、法律や社内規程、そして社会的な期待を裏切る行為です。企業にとって信頼を失うリスクとなり、経済的損失やブランドイメージの低下を招く可能性があります。特に、情報漏えいや不正会計、ハラスメントなどの問題が多発している現代では、コンプライアンス意識の向上が急務です。企業の持続的な成長のためには、適切なルールの制定と社員教育、そして日々の業務におけるチェック体制の強化が必要です。コンプライアンス違反を防ぐために、自社の体制を見直し、必要ならば専門家の協力を得ることも考慮しましょう。これにより、企業はより健全な成長を遂げることができるでしょう。ぜひ、今すぐに行動に移し、コンプライアンス強化の第一歩を踏み出してください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。