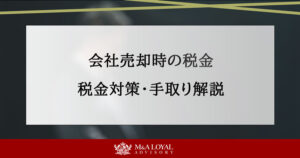暦年課税とは?対象者や相続時精算課税との違い、活用法を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
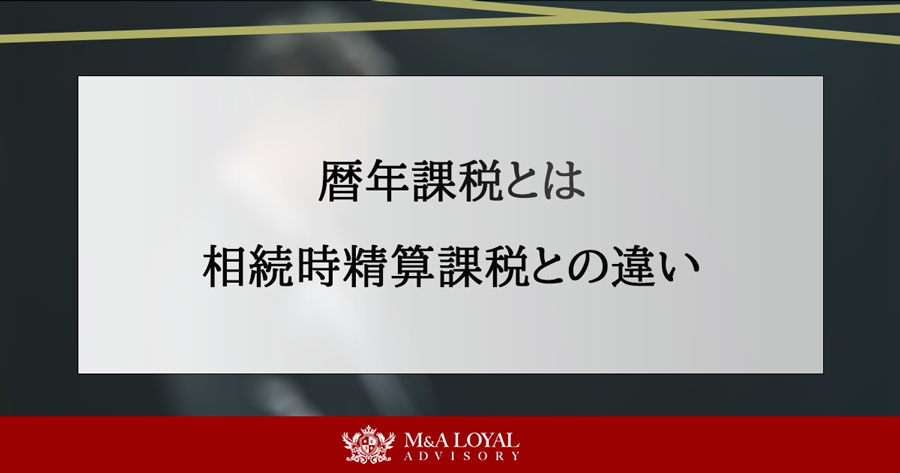
暦年課税とは、年間110万円の基礎控除を活用して財産を移転できる贈与税の課税制度です。多くの方がこの制度を耳にしたことはあるものの、具体的な仕組みや効果的な活用方法については十分に理解していないのが現状です。
2024年の税制改正により生前贈与加算期間が7年に延長されるなど、暦年課税を取り巻く環境は変化しています。一方で、適切に活用すれば中小企業の事業承継やM&A戦略において大きな節税効果を生み出すことが可能です。
本記事では、暦年課税の基本的な仕組みから最新の改正内容、実際の活用事例まで、経営者や資産家の方が知っておくべき重要なポイントを体系的に解説します。
目次
暦年課税とは?基本的な仕組みと特徴
暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税される制度です。中小企業の事業承継やM&A戦略において、長期的な資産移転の基盤となる重要な仕組みといえます。
暦年課税は年間110万円の基礎控除を活用することで、贈与税を支払うことなく財産を移転できる点が最大の特徴です。この基礎控除枠を効果的に活用することで、将来の相続税負担を軽減しながら、計画的な資産移転が可能になります。
暦年課税の定義と年間110万円の基礎控除
暦年課税制度では、受贈者(財産を受け取る人)1人あたり年間110万円の基礎控除が認められています。これは、1年間に受け取った贈与の総額が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も不要であることを意味します。
基礎控除の重要なポイントは、「受贈者1人につき年間110万円」という点です。例えば、父親から80万円、母親から50万円の贈与を同じ年に受けた場合、合計130万円となり、110万円を超えた20万円に対して贈与税がかかります。複数の贈与者から受け取った場合でも、受贈者側で合算して判断される仕組みです。
一方、贈与者側には制限がありません。父親が3人の子どもにそれぞれ110万円ずつ贈与した場合、合計330万円の贈与が可能になります。この仕組みを理解することで、効率的な財産移転戦略を立てることができます。
暦年課税の対象者は誰でもOK|年齢・関係性の制限なし
暦年課税制度には、贈与者・受贈者ともに年齢や関係性による制限がありません。親子間はもちろん、祖父母と孫、夫婦間、さらには血縁関係のない第三者との間でも利用可能です。
これは相続時精算課税制度と大きく異なる点です。相続時精算課税制度が「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与」に限定されているのに対し、暦年課税は誰でも自由に利用できます。
中小企業の事業承継では、後継者以外の親族への配慮や、幅広いステークホルダーへの財産分散が必要になる場合があります。暦年課税の柔軟性は、このような複雑な事業承継シーンでも活用しやすい制度といえるでしょう。
暦年課税が適用される贈与の種類
暦年課税制度が適用される財産に制限はありません。現金や預貯金はもちろん、有価証券、不動産、車両、貴金属、各種権利など、経済的価値のあるあらゆる財産が対象となります。
中小企業の事業承継においては、自社株式の贈与が重要な要素となります。非上場株式であっても、適切な評価を行った上で暦年課税の対象として贈与することが可能です。株式の評価額が年間110万円以下であれば、贈与税をかけることなく株式の移転が実現できます。
ただし、財産の評価には注意が必要です。現金以外の財産については、贈与時の時価で評価されるため、専門家による適切な評価が欠かせません。特に不動産や非上場株式については、評価方法によって大きく金額が変わる可能性があります。
暦年課税の税率と計算方法
暦年課税では、年間110万円の基礎控除を超えた部分に対して贈与税が課されます。税率は累進課税制度を採用しており、贈与額が多いほど税率が高くなる仕組みです。
贈与税の計算式は以下の通りです。
| 贈与税額 = (贈与財産の価額の合計額 – 110万円)× 税率 – 控除額 |
税率には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率は、18歳以上の子や孫が父母・祖父母から贈与を受けた場合に適用され、一般税率より低く設定されています。例えば、基礎控除後の課税価格が1,000万円の場合、特例税率では30%(控除額90万円)、一般税率では40%(控除額125万円)となります。
中小企業の事業承継では、株式評価額によっては高額な贈与税が発生する可能性があります。そのため、複数年にわたって段階的に贈与を行うか、他の節税制度との組み合わせを検討することが重要です。
※参照:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



暦年課税と相続時精算課税制度の違い
贈与税には暦年課税と相続時精算課税制度の2つの課税方式があり、それぞれ異なる特徴を持っています。2024年の税制改正により相続時精算課税制度に大幅な見直しが行われたため、両制度の使い分けがより重要になっています。中小企業の事業承継やM&A戦略においても、これらの違いを正しく理解することが効果的な税務戦略の基盤となります。
非課税枠の違い:年110万円 vs 累計2,500万円
暦年課税と相続時精算課税制度の最も大きな違いは、非課税枠の設定方法です。暦年課税では受贈者1人につき年間110万円の基礎控除が毎年利用できます。一方、相続時精算課税制度では贈与者1人につき累計2,500万円の特別控除があります。
2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までは贈与税も相続税もかからない非課税枠となりました。
例えば、父親から子どもへの贈与を考える場合、暦年課税なら毎年110万円ずつ10年間で1,100万円、相続時精算課税制度なら初年度に2,500万円の一括贈与が可能です。さらに、2024年以降は相続時精算課税制度でも年間110万円の追加控除が利用できるため、制度の魅力が大幅に向上しています。
利用条件の違い:制限なし vs 60歳以上の親族限定
暦年課税には利用条件がありません。年齢、関係性を問わず、誰でも自由に利用できます。これに対し、相続時精算課税制度には厳格な要件があります。
相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫の場合に限定されています。また、一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。
中小企業の事業承継では、後継者以外の親族や役員への配慮も必要になる場合があります。暦年課税の柔軟性は、このような複雑な関係者への財産分散において重要な役割を果たします。一方、相続時精算課税制度は、直系の家族間での大規模な財産移転に適しているといえるでしょう。
相続時の扱いの違い:7年分加算 vs 全額加算
暦年課税と相続時精算課税制度では、相続発生時の扱いが大きく異なります。この違いは、それぞれの制度の本質的な特徴を表しています。
暦年課税では、相続開始前7年以内に行われた生前贈与が相続財産に加算されます(2024年1月1日以降の贈与から適用)。ただし、この改正には重要な緩和措置があり、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が加算の対象となります 。7年より前の贈与は加算されないため、長期的な贈与計画が有効です。
相続時精算課税制度では、制度を利用して贈与されたすべての財産が相続時に加算されます。ただし、2024年の改正で新設された年間110万円の基礎控除分は加算対象外となります。既に支払った贈与税は相続税額から控除されるため、実質的には課税の繰り延べ効果があります。
※参照:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
2024年改正で変わった相続時精算課税の基礎控除
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この改正により、相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に向上しています。
従来の相続時精算課税制度では、少額の贈与でも申告が必要でしたが、改正後は年間110万円以下の贈与については申告不要となりました。また、この基礎控除分は相続財産への加算対象からも除外されるため、真の非課税枠として機能します。
この改正により、特に高齢の贈与者が子や孫に財産を前倒しで移転したい場合、相続時精算課税制度が有利になるケースが増えています。暦年課税では7年以内の贈与が相続財産に加算されるのに対し、相続時精算課税制度の基礎控除分は亡くなる直前の贈与でも加算されないためです。
※参照:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
暦年課税を活用した中小企業M&Aの税務戦略
中小企業のM&A実行前における株式移転戦略として、暦年課税制度は重要な役割を果たします。M&Aでは株式譲渡による対価を受け取る際、通常20.315%の税率が適用されますが、事前に暦年課税を活用した株式贈与を行うことで、M&A後の税負担を大幅に軽減することが可能です。
特に2024年の税制改正により生前贈与加算期間が7年に延長されたため、より長期的で戦略的なアプローチが求められるようになりました。M&Aを検討している中小企業経営者は、この変更を踏まえた税務戦略の見直しが必要です。
M&A実行の7年以上前から株式贈与を開始する戦略
2024年の改正により、相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産に加算されるようになりました。この「7年ルール」を踏まえると、M&A実行時期から逆算して、少なくとも7年以上前から計画的な株式贈与を開始することが重要です。
例えば、将来的にM&Aを予定している経営者が、後継者や親族に対して年間110万円相当の自社株式を贈与し続けた場合、10年間で1,100万円分の株式を非課税で移転できます。M&Aの対価は通常、会社の全株式に対して支払われます。事前の株式贈与による節税効果は、創業者である親が一人で受け取るはずだった譲渡所得(キャピタルゲイン)を、贈与を受けた子や親族に分散させることで生まれます。これにより、親個人の高額な所得税負担が軽減され、親族全体で見た税負担を最適化できる可能性があります 。
自社株式の評価額が年々上昇する成長企業の場合、早期の株式贈与により将来の値上がり分も含めて節税効果を享受できます。株式評価の専門知識を持つ税理士と連携し、適切な評価タイミングでの贈与実行が成功の鍵となります。
複数の親族に分散して年間最大限の非課税枠を活用する戦略
暦年課税の基礎控除110万円は受贈者1人につき年間で適用されるため、複数の親族に株式を分散贈与することで、年間の非課税移転額を大幅に拡大できます。
- 配偶者、子ども2人、孫2人に贈与する場合:年間550万円(110万円×5人)
- 10年間継続した場合:総額5,500万円の非課税移転が可能
この戦略では、受贈者それぞれの将来の相続税負担軽減効果も期待できます。M&A実行時には、各親族が保有する株式について、それぞれが株式譲渡所得税の対象となりますが、分散により各人の税負担を軽減できる場合があります。
ただし、名義株主とならないよう、各受贈者が株式の実質的な権利を行使できる体制を整えることが重要です。株主名簿の適切な管理と、贈与契約書の作成・保管は必須要件といえます。
M&A後の税負担を考慮した段階的な持分移転戦略
M&A実行時の税負担を最小化するためには、売却時の株式保有割合を戦略的にコントロールすることが重要です。暦年課税を活用した事前の株式移転により、経営者個人の保有株式を段階的に減少させることで、M&A時の譲渡所得を圧縮できます。
M&A対価が数億円規模になる場合、株式譲渡所得税だけで数千万円の税負担が発生する可能性があります。事前に30〜50%の株式を親族に移転しておくことで、この税負担を大幅に軽減できます。
さらに、M&A後の税務上の取り扱いも考慮する必要があります。買い手企業は通常、対象企業の株式100%の取得を目指します。そのため、親族などに株式が分散している状況は、取引の複雑性を増す要因と見なされ、交渉が難航したり、不利に働いたりするリスクも伴います 。少数株主の存在が交渉上有利に働くのは限定的なケースであり、慎重な判断が必要です。親族保有分については、別途買い取り条件を設定することで、分散された税負担でM&A対価を受け取ることが可能になります。
暦年課税による事業承継の成功パターン
中小企業の事業承継において、暦年課税を効果的に活用した成功パターンが数多く報告されています。これらの成功事例に共通するのは、早期からの計画的な取り組みと、複数の手法を組み合わせた戦略的なアプローチです。2024年の税制改正により生前贈与加算期間が7年に延長されたことで、より長期的な視点での承継計画が重要になっています。
10年計画で後継者に自社株式を段階移転する
後継者への事業承継で、一般的かつ効果的な成功パターンは、10年以上の期間をかけて段階的に株式を移転する手法です。この手法では、年間110万円の基礎控除を最大限活用し、長期にわたって株式を分散移転します。
例えば、自社株式の評価額が1株1万円の場合、年間110株を後継者に贈与できます。10年間継続すれば1,100株、15年間では1,650株の移転が可能です。株式評価額が成長とともに上昇する企業の場合、早期の贈与により将来の値上がり分も含めて節税効果を享受できます。
成功のポイントは、毎年確実に贈与を実行することです。贈与契約書の作成、株主名簿の変更、議事録の整備など、法的な手続きを適切に行い、税務署に対して贈与の事実を明確に示すことが重要です。また、後継者が株主としての権利を実際に行使できる体制を整えることで、名義株主の問題を回避できます。
複数の後継者候補に均等に株式を分散する
中小企業では、複数の子どもがいる場合や、親族以外の役員にも配慮が必要な場合があります。このような状況では、暦年課税を活用して複数の後継者候補に株式を分散する戦略が有効です。
- 子ども3人に均等分散:年間330万円(110万円×3人)の非課税移転
- 配偶者と子ども2人に分散:年間330万円の非課税移転
- 親族と役員に分散:より広範囲な関係者への配慮
この手法では、将来の相続争いを防ぐ効果も期待できます。事前に株式を分散しておくことで、相続時の遺産分割がスムーズに進む可能性が高まります。ただし、経営権の分散により意思決定が困難になるリスクもあるため、議決権の集約方法や株主間契約の締結を検討することが重要です。
限界税率を下回る金額で毎年贈与を続ける
相続税の限界税率が高い場合、基礎控除110万円を超えても暦年課税による贈与が有利になるケースがあります。例えば、相続税の限界税率が45%の場合、贈与税率が30%以下であれば節税効果が期待できます。
相続税の実効税率より低い税率で贈与を行う戦略は有効です。計算例は、贈与者と受贈者の関係で税率が変わるため注意が必要です。
- 年間300万円の贈与(課税価格190万円): 贈与税は19万円(税率10%)
- 年間500万円の贈与(課税価格390万円): 特例税率(18歳以上の子・孫へ)なら贈与税は48.5万円(税率15%、控除額10万円)、一般税率なら53万円(税率20%、控除額25万円)
この戦略では、贈与税を支払っても相続税の軽減効果が上回る場合に適用されます。税率の比較分析を行い、最適な贈与額を決定することが成功の鍵となります。専門家による綿密な試算が不可欠です。
事業承継税制と暦年課税を組み合わせる
事業承継税制(特例措置)は2027年12月末までの期間限定制度ですが、暦年課税と組み合わせることで、より効果的な承継戦略を構築できます。
事業承継税制では、株式の100%について贈与税・相続税の納税猶予が受けられますが、一度適用すると暦年贈与による段階的移転ができなくなります。そのため、事業承継税制適用前に暦年課税による部分的な株式移転を行い、残りの株式について事業承継税制を適用するハイブリッド戦略が注目されています。
- フェーズ1:暦年課税で30-40%の株式を段階移転(5-7年間)
- フェーズ2:事業承継税制で残りの60-70%を一括承継
この手法では、事業承継税制の要件(雇用維持など)に縛られる株式数を減らしながら、税負担軽減効果を最大化できます。この制度を利用するには、2つの異なる期限に注意が必要です。まず、「特例承継計画」の提出期限が2026年3月31日までに延長されています 。しかし、より重要なのは、制度の対象となる贈与・相続の実行期限が2027年12月31日までである点です 。計画提出だけでなく、期限内の承継実行が必須です。
暦年課税の注意点とリスク対策
暦年課税を活用した財産移転では、適切な手続きを怠ると税務署から否認され、予期しない課税が発生するリスクがあります。特に定期贈与の認定、名義預金の判定、生前贈与加算の適用といった問題は、多くの中小企業経営者が直面する課題です。これらのリスクを回避するためには、事前の準備と継続的な証拠保全が不可欠です。
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与とは、最初から一定期間にわたって一定額を贈与する契約を結んでいたとみなされる状況を指します。例えば「毎年110万円を10年間贈与する」という約束があったと判断された場合、初年度に1,100万円全額を贈与したものとして贈与税が課される可能性があります。
定期贈与の認定を回避するための対策として、以下の点が重要です。
- 毎年独立した贈与契約書を作成:同一の契約書で複数年の贈与を取り決めない
- 贈与額を毎年変更:1年目110万円、2年目100万円、3年目105万円など金額を変動させる
- 贈与時期をずらす:毎年同じ月日ではなく、春、秋、冬など時期を分散する
- 贈与方法を工夫:現金、株式、不動産など財産の種類を変える
特に重要なのは、各年の贈与が独立していることを明確に示すことです。「今年は○○万円贈与する」という単年度の意思表示であり、将来の贈与については未定であることを契約書に明記することが効果的です。
生前贈与加算の7年ルールへの対応
2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産に加算されるようになりました。この改正により、従来の3年ルールと比較して、暦年課税による相続税軽減効果は一定程度制約を受けることになります。
7年ルールへの対応策として、以下の戦略が有効です。
- 早期開始による長期計画:7年を大幅に超える期間での贈与計画を立案
- 非相続人への贈与活用:孫や義理の子など、相続人以外への贈与を積極活用
- 相続時精算課税との使い分け:2024年改正で新設された基礎控除を活用
延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、その4年間の合計額から、総額で100万円を一度だけ控除できます 。100万円÷4年間で年間25万円の控除枠があるという誤解が生じることがありますが、この解釈は誤りであり、税額計算を大きく誤る原因となります。
贈与契約書の作成と証拠保全
暦年課税を成功させるためには、贈与の事実を客観的に証明できる証拠の確保が不可欠です。贈与契約書は、贈与者と受贈者の合意があったことを示す最も重要な証拠となります。
効果的な贈与契約書作成のポイントは以下の通りです。
- 契約書の必要記載事項:贈与者・受贈者の住所氏名、贈与財産の詳細、贈与実行日、署名捺印
- 毎年作成の徹底:面倒でも毎年新しい契約書を作成し、独立性を証明
- 実印の使用:認印ではなく実印を使用し、印鑑証明書も添付
- 公証役場での確定日付取得:契約書の作成日を公的に証明
さらに、贈与の実行についても適切な証拠保全が必要です。現金贈与の場合は必ず銀行振込を利用し、振込記録を保管します。手渡しによる現金贈与は、証拠が残らないため税務調査で否認されるリスクが高くなります。
株式贈与の場合は、株主名簿の変更、株式移転手続きの完了、議決権行使の記録など、受贈者が実質的に株主となったことを示す証拠を整備することが重要です。名義だけの株主とならないよう、受贈者が株主としての権利を実際に行使できる体制を構築する必要があります。
暦年課税の実務手続きと申告方法
暦年課税による贈与では、年間110万円の基礎控除を超えた場合に贈与税の申告が必要となります。中小企業の株式贈与では、株式評価額によって申告の要否が決まるため、適切な評価と申告手続きの理解が重要です。申告漏れや手続きミスは追徴課税のリスクを伴うため、正確な手続きが求められます。
贈与税申告書の作成手順
贈与税の申告には「贈与税申告書第一表」を使用します。暦年課税のみの申告であれば、この第一表のみで申告が完了します。申告書の作成手順は以下の通りです。
まず、申告書の基本情報を記入します。提出先税務署名、提出年月日、申告する年分を正確に記載し、申告者(受贈者)の住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、マイナンバーを記入します。
次に、贈与財産の明細を記載します。「Ⅰ暦年課税分」の欄に、贈与者の氏名・住所・続柄、贈与を受けた年月日、財産の種類・数量・所在地、財産の評価額を詳細に記入します。複数の贈与者から財産を受けた場合は、それぞれについて記載が必要です。
最後に税額計算を行います。贈与財産の価額合計から基礎控除額110万円を差し引き、課税価格を算出します。課税価格に応じた税率を適用し、控除額を差し引いて最終的な納税額を計算します。
株式贈与の場合は、特に評価額の算定に注意が必要です。非上場株式の評価は複雑で、会社の規模や業績によって評価方法が異なります。正確な評価額の算定には専門知識が必要なため、税理士への相談を検討することが重要です。
必要書類と提出期限
贈与税の申告時に必要な書類は以下の通りです。
- 贈与税申告書(第一表)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号確認書類+身元確認書類)
- 贈与財産の価額を証明する書類(株式の場合は評価明細書など)
- 贈与契約書の写し(任意だが添付推奨)
申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に申告書を提出し、同時に納税も完了させる必要があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるため、早めの準備が重要です。
申告書の提出方法は、税務署への持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3つから選択できます。e-Taxを利用する場合は、事前に電子証明書の取得が必要ですが、24時間いつでも申告でき、控えの受領も電子的に行えるため便利です。
税理士に依頼すべきケース
以下のような場合は、税理士への依頼を検討することをお勧めします。
- 非上場株式の贈与:株式評価は専門的で複雑なため、適正な評価額算定には専門知識が必要
- 複数年にわたる継続的な贈与計画:長期的な税務戦略立案と年次管理が重要
- 贈与額が高額な場合:数百万円を超える贈与では、計算ミスによる影響が大きい
- 他の税制との併用検討:事業承継税制や相続時精算課税制度との比較検討が必要
特に中小企業の事業承継においては、株式評価、贈与戦略、相続税対策を総合的に検討する必要があります。税理士に依頼することで、適切な申告だけでなく、長期的な税務戦略の立案も可能になります。
税理士報酬は贈与財産の価額や複雑さによって異なりますが、申告ミスによる追徴課税のリスクを考慮すると、専門家への依頼は有効な投資といえるでしょう。
まとめ|暦年課税を活用して中小企業の事業承継を成功させよう
暦年課税は、中小企業の事業承継やM&A戦略において重要な税務ツールです。年間110万円の基礎控除を活用した計画的な財産移転により、将来の相続税負担を大幅に軽減できます。
2024年の税制改正で生前贈与加算期間が7年に延長されましたが、長期的な戦略により改正の影響を最小限に抑えることが可能です。成功の鍵は、定期贈与の回避と適切な証拠保全の徹底にあります。複雑な税務論点については、専門家に相談することをお勧めします。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。