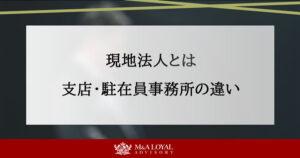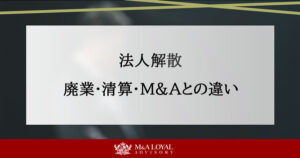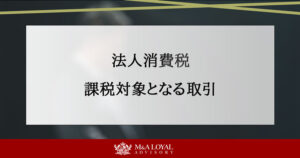法人とは?株主会社や合同会社などの種類と個人事業主との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
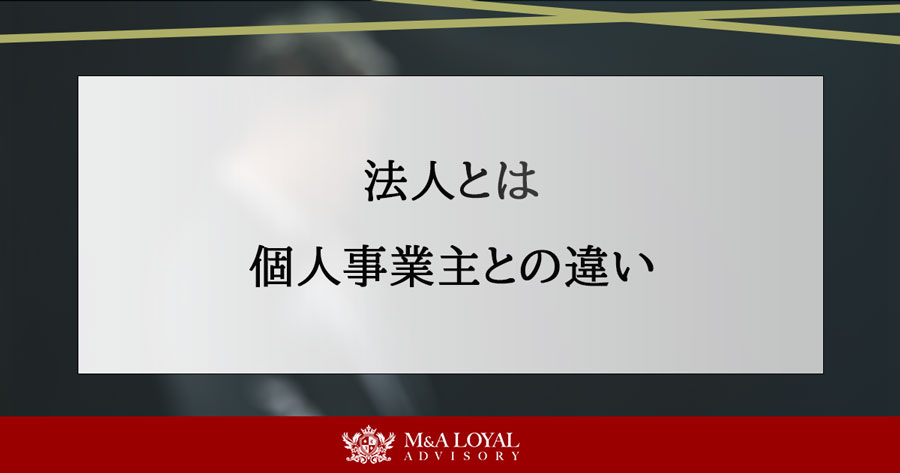
「法人とは、そもそも何?会社とどう違うの?」と感じたことはありませんか?ニュースや契約書などで頻繁に耳にする言葉ですが、法人とは何か、その定義や種類を正確に説明できる人は意外と少ないものです。しかも、法人と個人では法律上の扱いや税金の仕組みが異なるため、理解が曖昧なままだと経営判断を誤るリスクがあります。
本記事では、法人とはどういうものか、基本的な意味や種類、設立の流れなどを分かりやすく解説します。
目次
法人とは
まず、法人の概要について紹介します。
法人の概要
法人とは、定款(会社の基本ルール)などで定められた目的の範囲内で、契約を結んだり財産を持ったりすることが法律で認められている組織や団体のことです。個人とは異なり、法人は登記によって成立し、独立した「法律上の人格(法人格)」を持ちます。これにより、法人名義で契約や取引を行え、代表者が変わっても法人そのものは継続して存続します。
個人事業主との違い
個人事業主とは、会社を設立せずに、自分の名前で事業を行う人のことをいいます。
法人の場合、契約や財産の所有者は経営者本人ではなく、法人そのものです。法人名義で契約を結び、資産を持つ、借金を負う、経営者個人とは法律的に切り離された存在として扱われます。そのため、会社が負った債務は原則として法人の資産から支払えばよく、経営者の私有財産で返済する必要はありません。
個人事業主は、全ての権利や義務が本人に直接帰属します。つまり、事業で得た財産も負債も全て個人のものです。事業の借金を個人の貯金から返済することもあれば、逆に私生活の負債を事業資金から支払うこともあり得ます。法人と比べると、事業と個人の境界がない点が大きな違いです。
自然人との違い
法人とよく比較される言葉が自然人です。自然人とは、生まれながらに法律上の権利や義務を持つことが認められている「人間」のことをいいます。私たち一人一人が自然人にあたります。
一方で、法人は人間ではなく、法律によって「人」としての地位(法人格)を与えられた組織です。前述したように登記によって成立し、その法人名義で契約を結んだり、財産を所有したり、責任を負えます。
つまり、自然人が生まれることで権利能力を得るのに対し、法人は法律上の手続きを経て「人」として認められる点が異なります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



法人の種類
法人の種類はまず私法人と公法人に大別されます。そして私法人はさらに営利法人と非営利法人に分けられます。それぞれを分かりやすく解説します。
営利法人(私法人)
営利法人とは、事業で得た利益を構成員(出資者など)に分配することを目的とする法人です。株式会社や合同会社、合名会社、合資会社などが代表的な形態として知られています。営利法人は、経済活動を通じて利益を生み出し、その収益を事業拡大のために再投資したり、株主や出資者に配当として分配したりする仕組みです。
営利法人は利益の追求を活動の中心に据え、経済的な価値を創出することを目的とした組織といえます。
非営利法人(私法人)
非営利法人とは、利益を構成員に分配せず、社会的・公共的な目的のために活動する法人のことです。代表的な例として、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などがあります。これらの法人は、教育や福祉、環境保全など、社会貢献を目的とした活動を行い、得られた収益は全て事業の運営や次の活動に生かされます。
非営利法人は「利益の追求」よりも社会への貢献や持続的な活動の実現を重視する組織です。
公法人
公法人とは、国や地方公共団体など、公共の利益を目的として設立される法人のことです。法令に基づいて設立され、行政や社会基盤を支える重要な役割を担っています。営利を目的とせず、国民生活の安定や公共サービスの提供など、社会的使命の遂行を目的とする点が特徴です。
国や自治体の機能を補完し、社会全体の福祉や利益の増進を目指して活動する法人といえます。
営利法人の種類
営利法人の種類は、次のとおりです。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
それぞれを分かりやすく解説します。
株式会社
株式会社は、日本で最も多く設立されている法人形態です。株主が出資者となり、出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任制度」が採用されています。株主は経営の意思決定に直接関与せず、取締役や代表取締役などの役員が会社の運営を担います。多くの資金を集めやすく、大規模な事業展開が可能です。
また、株式を自由に譲渡できる点も特徴で、成長段階に応じた資金調達や経営体制の変更が容易です。企業の規模にかかわらず設立できるため、個人事業から法人化するケースでもよく選ばれます。
合同会社
合同会社は、2006年の会社法改正で導入された比較的新しい法人形態で、出資者全員が経営にも関われる柔軟な会社です。株式会社のように株主と経営者が分かれておらず、出資者自身が意思決定や業務執行に直接関わる点が大きな特徴です。
ここでいう「社員」とは、一般的な従業員のことではなく、会社に出資している構成員(オーナー)のことを指します。社員は出資者であり、経営者でもある立場です。例えば社員が1人しかいない場合でも、その人が出資し、経営を担うことで合同会社を設立できます。
設立費用も株式会社より低く、登記手続きも簡単なため、小規模事業やスタートアップ、専門家グループなどに適した法人形態といえます。
合資会社
合資会社は、「無限責任社員」と「有限責任社員」の両方で構成される法人です。会社法においては「持分会社」に分類され、出資者(社員)が出資比率に応じて会社の利益や損失を分担します。無限責任社員は、会社の債務について自分の財産全てをもって責任を負う立場であり、原則として会社の経営を担います。一方、有限責任社員は出資した金額の範囲内でのみ責任を負うため、経営には直接関与しないことが多く、資金提供の役割を果たします。
無限責任を負う社員が存在するため、近年は新規設立件数が少なく、よりリスクの少ない合同会社や株式会社を選ぶケースが増えています。
合名会社
合名会社は、全ての出資者(社員)が無限責任を負う法人であり、会社法で定められた「持分会社」の中で最も古い形態の一つです。社員全員が経営に直接関わり、会社の債務に対しては個人の財産をもって無制限に責任を負う点が大きな特徴です。リスクが高い反面、社員同士の信頼関係と経営への一体感が非常に強くなる傾向があります。
ただし、無限責任制によるリスクが大きいため、現在では新たに設立されるケースは少なく、より柔軟で責任範囲が限定される「合同会社」や「株式会社」を選ぶ事業者が増えています。
非営利法人の種類
非営利法人の種類は、次のとおりです。
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- NPO法人(特定非営利活動法人)
それぞれを詳しく解説します。
一般社団法人
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される法人です。共通の目的を持つ人々が集まり、営利を目的とせずに活動します。出資は必要なく、2人以上の社員(構成員)がいれば設立可能です。設立の際は、定款を作成して公証人の認証を受け、理事などの役員を選任した上で、法務局に登記を申請をします。得た収益は社員に分配せず、全て法人の目的達成や活動の継続に充てられます。
業界団体や地域振興、文化活動など、人を中心に非営利で社会貢献を行う団体に広く活用されている法人形態です。
一般財団法人
一般財団法人は、寄付や出資などによって集められた財産を基盤に、社会や地域のために活動する非営利法人です。組織の中心となるのは「人」ではなく「財産」であり、資金を運用しながら教育支援や文化振興、スポーツ推進、研究助成などの公益的な事業を行います。
設立には一定額以上の資金と、理事や評議員、監事といった複数の役員が必要です。運営においては、拠出された財産を適切に管理し、目的に沿って活用しなければなりません。また、遺言によって新たに一般財団法人を設立することも可能で、生前の意思を社会貢献として形に残す手段としても利用されています。
公益社団法人・公益財団法人
公益社団法人および公益財団法人も、社会や人々の利益につながる活動を行う非営利法人です。教育や文化、福祉、環境保全などの公益事業を目的としており、内閣府や都道府県の認定を受けて設立されます。これらの法人は、2008年施行の「公益法人認定法」に基づく制度の下、透明性の高い運営と情報公開が求められています。
公益社団法人は、共通の目的を持つ個人や法人が集まって設立される団体であり、出資を必要としません。公益財団法人は、拠出された財産を基盤に運営される組織で、奨学金や文化事業などに資金を活用します。どちらも公益性の高い活動を通じて社会貢献を目指し、税制優遇などの支援を受けられます。
NPO法人(特定非営利活動法人)
NPO法人とは、営利を目的とせず、社会的課題の解決や地域の発展を目指して活動する民間の非営利法人です。正式には「特定非営利活動法人」と呼ばれ、1998年に制定された「特定非営利活動促進法」に基づいて設立されます。
設立には、共通の目的を持つ10人以上の社員が必要で、所轄庁(都道府県または内閣府)の認証を受けることで法人格を得ます。活動分野は、福祉や教育、環境保全、まちづくり、国際協力など幅広く、得た収益は構成員に分配せず、全て事業の継続や社会貢献のために活用されます。
市民が主体となって社会に貢献する仕組みとして、全国各地で地域づくりや支援活動に生かされている法人形態です。
公法人の種類
公法人の主な種類は、次のとおりです。
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人
それぞれを分かりやすく解説します。
地方公共団体
地方公共団体とは、国から独立した存在として、地域の住民による自治を行う団体のことです。日本では「地方自治体」とも呼ばれ、都道府県や市町村などがこれにあたります。
地方公共団体は、地域の実情に応じた行政サービスを提供し、住民の福祉向上を目的として活動します。法律に基づいて設立され、独自の条例を制定したり、予算を編成したりする権限を持っています。
国が全国的な施策を行うのに対し、地方公共団体は地域密着型の行政を担う存在であり、教育・福祉・都市計画・環境保全など、住民生活に直結する分野で重要な役割を果たしています。
独立行政法人
独立行政法人は、国の行政機能の一部を切り離し、より効率的かつ専門的に業務を行うために設立された公的法人です。研究・医療・文化など多様な分野で国の政策実施を支えています。代表的な例として、科学技術振興機構(JST)や国立病院機構、国立美術館などがあります。
これらの法人は、国の監督を受けつつも、自らの判断で柔軟に事業運営を行える独立性を持つ点が特徴です。効率性と透明性の両立を目指し、公共サービスの質向上を図るための仕組みといえます。
特殊法人
特殊法人は、個別の特別法によって設立される公的法人で、行政機関では対応が難しい公共的な事業を、より効率的に実施するために設けられています。通常の行政組織では制度上の制約が多く、迅速な経営判断が難しい場合に、国が監督を行いながらも一定の経営の自主性と柔軟性を持たせて運営されます。
代表的な法人には、日本放送協会(NHK)や日本年金機構、日本中央競馬会(JRA)などがあり、放送や福祉、年金、公益活動など多様な分野で公共サービスを提供しています。行政の補完的な役割を担いつつ、企業的な手法で効率的な運営を行うことを目的とした法人形態です。
法人を設立するメリット
個人事業主が法人を設立するメリットは、次のとおりです。
- 社会的信用が高まる
- 節税の選択肢が増える
- 資金調達がしやすい
- 人材採用に有利
- 社会保険に加入できる
- 事業承継がスムーズ
それぞれを分かりやすく解説します。
社会的信用が高まる
法人は登記によって法的に独立した存在となるため、会社名義で契約や取引を行えます。これにより、金融機関・取引先・自治体などからの信頼が高まり、大口の契約や官公庁案件への参入といったビジネスチャンスが拡大します。
また、法人は決算書の提出や登記情報の公開など、事業実態を客観的に確認できる仕組みを備えている点も取引先からの安心感につながります。個人事業主の場合、事業と個人の信用が一体化しており、与信枠や契約内容に制約を受けることもありますが、法人化すれば「責任の所在が明確で継続性のある組織」として評価されやすい点も大きなメリットです。
さらに、法人名義でのオフィス契約や仕入れ、リース契約などもスムーズに進むため、経営の安定性と社会的信用の両面を強化できます。
節税の選択肢が増える
法人化すると、税金の計算方法や控除の仕組みをより戦略的に活用できます。法人税は、所得税のように所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」ではなく、一定の税率で課されるため、利益が大きくなるほど税負担を抑えやすい点が特徴です。
さらに、法人では役員報酬や退職金、福利厚生費、出張旅費、交際費など、事業運営に関する幅広い費用を損金(経費)として認められる範囲が広い点も大きなメリットです。家族を役員や従業員として雇い、適正な給与を支払う場合も、法人ならその分を経費化できます。
法人化は単なる節税手段にとどまらず、経営を安定的・持続的に発展させる仕組みとして機能します。
資金調達がしやすい
法人は登記や決算によって経営の実態が明確に示されるため、金融機関や投資家からの信用を得やすく、融資審査で有利に働きます。また、法人化によって利用できる補助金・助成金、信用保証制度、制度融資などの対象が広がり、資金調達の手段が増えるのもメリットです。さらに、株式や出資を通じた外部資金の調達も可能になり、個人事業主では難しい大規模な投資や新規事業への展開が実現しやすいといえます。
このように、法人化は単に融資を受けやすくするだけでなく、中長期的な資金計画の自由度を高め、事業の成長を支える基盤を作れます。
人材採用に有利
法人化すると、社会的信用や雇用の安定性が高まり、求職者からの信頼も得やすいです。個人事業主よりも「将来性のある組織」という印象を与えられるため、優秀な人材の採用につながります。また、法人としての登記や社会保険の整備により、福利厚生や労働環境の面でも安心感を提供できる点も強みです。
さらに、求人媒体や採用支援サービスの利用条件を満たしやすくなるため、採用活動の幅が広がり、長期的な人材確保にも効果があります。
社会保険に加入できる
法人は、従業員が1人でもいれば社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられています。
社会保険制度により、役員や従業員が安定した保障を受けられるため、安心して働ける職場環境を整えられる点も大きなメリットです。社会保険への加入は、従業員にとって将来の安心につながるだけでなく、取引先や顧客からの信頼度を高める効果もあります。
また、福利厚生を充実させることで、優秀な人材の定着や採用競争力の向上にもつながります。
企業などの事業承継がスムーズ
法人化の大きなメリットの一つが、事業承継のスムーズさです。法人は、代表者が交代しても法人そのものが存続するため、経営者の引退や世代交代が発生しても、契約や資産、取引関係をそのまま引き継げます。これにより、顧客や取引先との信頼関係を維持したまま、事業の継続が可能です。
一方、個人事業主の場合は、事業主の死亡や廃業によって事業そのものが終了してしまうリスクがあり、取引の再契約や資産の名義変更といった手続きが必要です。法人であれば、株式の譲渡や役員交代などの法的手続きを通じて、形式的にも実質的にもスムーズな承継が可能です。
このように法人化は、事業の永続性と安定性を確保し、後継者が安心して経営を引き継げる体制づくりに有効な手段といえます。
法人を設立するデメリット
個人事業主が法人を設立するデメリットは、次のとおりです。
- 設立・維持にコストがかかる
- 事務・会計処理が複雑になる
- 利益が少ないと税負担が重くなることもある
- 資金や利益の自由な使途が制限される
設立・維持にコストがかかる
法人を設立するには、定款の作成・認証費用や登録免許税などの初期費用が必要です。株式会社であれば、一般的に最低でも約20万円前後かかります。
また、設立後も毎年の決算申告、顧問税理士への依頼料、登記の更新手続き、社会保険料の会社負担分など個人事業主よりもランニングコストが高い傾向にある点がデメリットです。特に、従業員を雇う場合は社会保険や労働保険の負担も増えるため、年間を通して固定的な支出が発生します。
事業が安定して利益を生み出すまでの間は、コストが経営を圧迫するケースもあるため、法人化を検討する際には初期投資と維持費の両方を見込んだ資金計画を立てることが重要です。
事務・会計処理が複雑になる
法人は、法律上「独立した事業体」として扱われるため、会計処理や税務申告の手続きが個人事業主より格段に複雑です。法人税・消費税・地方税などの複数の税区分に対応し、複式簿記による帳簿の作成や決算書の提出が義務付けられています。個人事業主のように簡単な確定申告で済むわけではなく、正確な処理を行うためには税理士や会計士など専門家のサポートが必要になるケースがあります。
また、取引先への請求書や契約書も法人名義で発行するため、文書管理・印鑑管理・登記書類の整備など、事務作業の手間も増えます。法人化は信頼性向上につながる一方で、運営面での事務負担が増す点はあらかじめ理解しておく必要があります。
利益が少ないと税負担が重くなることもある
法人は、赤字であっても「法人住民税の均等割」として毎年最低7万円程度の税金を支払う義務があります。さらに、法人税申告には顧問税理士のサポート費用も発生するため、事業規模が小さいうちは個人事業主よりもコストがかかることがあります。また、社会保険料も法人としての負担が発生するため、利益が少ない時期には経営を圧迫する要因になりがちです。従って、安定した売り上げや利益が見込めるタイミングでの法人化が望ましいといえます。
資金や利益の自由な使途が制限される
法人化すると、会社の資金は「法人の財産」として管理されるため、経営者個人が自由に使えません。個人事業主であれば、事業の利益を生活費に回すことも容易ですが、法人では会社と個人の資金を厳格に区別する必要があります。経営者が資金を引き出す場合は、役員報酬や配当金として支給され、その際に所得税などの課税が発生します。
一方で、私的利用が疑われる支出を経費に計上すると、税務調査で否認される可能性もあるため、資金の使途管理には慎重さが求められます。法人では、会計上の透明性を保つ代わりに、資金運用の自由度が制限される点がデメリットといえるでしょう。
法人を設立するための手続き
株式会社を設立する主な流れは、次のとおりです。
- 会社設立に必要な基礎情報を決定する
- 会社用の印鑑(会社実印)を作成する
- 定款を作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 登記申請書類を用意し登記申請する
それぞれを解説します。
会社設立に必要な基礎情報を決定する
会社を設立する際は、まず会社の基本事項を決定します。具体的には、会社の種類(株式会社・合同会社など)や商号、事業目的、本店所在地、資本金、決算期、役員・株主構成などです。これらは全て定款に記載されるため、将来的な事業拡大も見据えて慎重に設定する必要があります。
商号には使用可能な文字や符号に制限があり、事業目的は「具体的かつ継続的に行う内容」を明確に記載することが求められます。
資本金は1円からでも設立できますが、信用力や運転資金を考慮すると、初期費用+数カ月
分の経費を確保しておくと現実的です。
会社用の印鑑(会社実印)を作成する
商業登記法の改正により、登記書類への押印義務は原則として撤廃されましたが、実務上は印鑑が依然として必要不可欠です。
契約書の締結、金融機関での口座開設、行政手続きなど、印鑑の使用機会は多く残っています。登記に登録する会社実印(代表者印)は、1辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズでなければならず、法務局への届出が必要です。印鑑は専門店で作成し、価格は5,000円〜5万円前後、納期は通常5日〜1週間です。
併せて、銀行印(金融取引用)や角印(請求書・見積書用)を同時に作成しておくと、事務処理を効率化できます。
定款を作成する
定款は、会社の目的・構成・運営ルールなどを定めた法人の憲法とも呼ばれる重要書類です。商号や事業目的、本店所在地、出資金額、発起人情報などの「絶対的記載事項」が欠けると無効となるため、慎重に内容を確認する必要があります。
作成方法には紙定款と電子定款の2種類があり、紙定款では印紙税4万円が課税されます。一方、電子定款を作成し、電子署名を付与して申請すれば印紙税が不要です。
定款は通常3部(原本・法務局提出用・会社保管用)を作成し、ホチキスで製本した上で契印をします。
公証役場で定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合、定款は作成しただけでは効力を持たず、公証人による認証を受けて初めて法的に有効となります。
手続きは本店所在地を管轄する公証役場で行い、予約が必要です。持参する書類は、定款3部、発起人全員の印鑑証明書(各1通)、発起人の実印、手数料(約5万円以内)、定款謄本代、収入印紙4万円(電子定款の場合は不要)などです。
代理人が手続きを行う場合は委任状も提出します。電子定款はオンライン申請が可能で、全国どの公証役場でも認証が受けられます。事前にFAXやメールで内容確認を依頼しておくと、修正や訂正を防げるためスムーズです。
資本金の払い込みを行う
定款の認証後、発起人は会社の資本金を払い込みます。登記前はまだ法人名義の口座が開設できないため、発起人個人の口座への振り込みが一般的です。払い込み後は、通帳の表紙・表紙裏(銀行名・支店名が確認できる部分)と入金明細ページをコピーして「払込証明書」を作成し、登記申請時に添付します。
払い込みが確認できなければ登記ができないため、通帳の写しや入金証跡は厳重に保管しましょう。
登記申請書類を用意し登記申請する
全ての準備が整ったら、法務局で会社設立の登記申請を行います。提出書類は、登記申請書や定款、発起人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書などです。
登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)で、収入印紙により納付します。登記完了までには通常10日前後かかり、登記簿謄本で成立を確認します。登記が完了すると法人番号が付与され、正式に会社が成立します。
以後、税務署・年金事務所への届出や社会保険の加入、法人口座開設など、開業後の各種手続きを速やかに行う必要があります。
法人を設立する際に知っておくべきこと
法人を設立する際に重要な次の3点について解説します。
- 法人化すべきタイミング
- 法人化にかかる費用
- 法人化にかかる期間
法人化すべきタイミング
法人化を検討すべきタイミングは、年間所得が900万円を超えた頃が一つの目安です。年間所得が900万円を越えると、個人事業主の所得税率は最大45%まで上がるのに対して、法人税率は中小企業であれば15%(800万円以下)または23.2%と一定で、税負担を抑えやすくなるためです。
また、年間売り上げが1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生するため、その前に法人化すれば免税期間を新たに確保できる可能性もあります。さらに、事業の拡大や従業員の雇用、取引先との信頼関係の構築を進めたい段階も法人化の好機です。
利益・売り上げ・成長計画の3点を踏まえて判断することが重要といえるでしょう。
法人化にかかる費用
個人事業主が法人化する際にかかる初期費用は、株式会社で約20万〜25万円前後、合同会社で約10万円前後が一般的な目安です。個人事業主が法人化する際には、主に「定款費用」「登記費用(登録免許税)」「資本金」の三つを用意します。
定款は会社の基本ルールを定める書類で、公証人による認証を受ける場合は約5万〜9万円(印紙代含む)が相場です。登記費用は、株式会社で資本金×0.7%または15万円のいずれか高い方、合同会社で6万円以上が必要です。資本金は1円から設定可能ですが、運転資金や信用面を考慮すると100万〜300万円程度が目安といわれています。
この他、会社実印の作成(約2万〜6万円)や社会保険・税理士報酬など、設立後の維持費も発生する点に注意が必要です。
法人化にかかる期間
会社を設立して法人化するまでの期間は、通常およそ2〜3週間程度が目安です。ただし、登記申請そのものは必要書類が全て整っていれば数日で完了するケースもあります。一方で、定款の作成や資本金の入金、印鑑の準備といった事前作業に時間がかかるため、全体では2〜3週間前後を見込むと良いでしょう。
また、設立手続きの流れは会社形態によって異なり、合同会社は定款認証が不要な分、株式会社よりも短期間で設立可能です。自分で手続きを進める場合は法的確認に時間を要しますが、専門家へ依頼すれば必要書類の作成や申請がスムーズに進み、最短で事業開始までを整えられます。
法人に関するQ&A
最後に、法人に関するよくある質問とその回答を紹介します。
法人を設立できない場合はあるか
法人そのものを設立することは制限されることは少ないですが、法人の役員(取締役など)には法律上の制限が存在する場合があります。
かつては、破産者(復権を得ていない者)や成年被後見人・被保佐人が役員となることは欠格事由とされていましたが、現在の会社法では破産歴だけでは欠格事由とはされていません。ただし、取締役在任中に破産手続き開始決定を受けた場合は民法653条により委任関係が終了し、退任扱いとなります。
また、成年被後見人や被保佐人が役員に就任するには、成年後見人・保佐人の同意が必要とされる規定があります。さらに、刑罰・営業許可などの法律で定められた欠格事由(禁錮以上の刑を受け、その執行後一定期間経過していない者など)は残っています。
一人でも法人化できるか
一人で設立できる会社(法人)形態は、株式会社と合同会社、合名会社です。合資会社は必ず2名以上の社員(無限責任社員と有限責任社員)が必要なため、単独では設立できません。
一方、合名会社は一人でも設立可能ですが、全社員が無限責任を負う仕組みのため、負債が発生した際には出資額に関係なく個人資産で返済義務を負います。そのため、現実的には一人で法人を設立する場合、株式会社または合同会社のいずれかを選ぶケースが圧倒的に多いです。
株式会社は社会的信用度が高く、対外的な取引に有利な一方、合同会社は設立費用が安く、経営の自由度が高いという特徴があります。目的や事業規模に応じて、どちらの形態が適しているかを検討することが重要です。
法人化して経費になるものは何か
個人事業主時代には「生活費との区別が難しい」とされる支出でも、法人としての支出であれば事業関連性が明確に証明できるため、損金算入(経費化)が可能になるケースが増えます。
主な経費項目(損金として認められるもの)は、次のとおりです。
- 役員報酬・役員退職金
- 福利厚生費
- 会議費・交際費
- 地代家賃・光熱費
- 旅費交通費
- 広告宣伝費
- 消耗品費・備品費
- 専門家報酬
経費として認められるかどうかの判断基準は、「支出が会社の利益を生むためのものか」という点です。曖昧な場合は、領収書・契約書・議事録などをきちんと保管し、業務との関連を説明できるようにしておくと安心です。
法人化すると社会保険の加入は必須か
法人を設立した場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が原則として義務です。会社の規模や従業員の有無に関係なく、法人として登記した時点で適用対象となるため、「社長1人だけの会社」でも社会保険に加入する必要があります。
社会保険には、次の2種類の公的保険が含まれます。
- 健康保険(病気やケガ、出産などに備える保険)
- 厚生年金保険(将来の年金給付のための保険)
これに加えて、従業員を雇う場合は、
- 雇用保険(失業時の給付など)
- 労災保険(業務中の事故・ケガの補償)
の加入も必要です。
加入手続きは、登記完了後に年金事務所やハローワークへ届け出ることが基本です。未加入のまま放置すると、さかのぼって数年分の保険料を請求される場合があるため注意が必要です。
法人化すると確定申告はどう変わるか
法人化した場合、個人事業税の取り扱いには注意が必要です。
個人事業税は地方税法で定められた法定業種に課される税で、個人事業主は毎年2月16日〜3月15日に所得の確定申告を行います。法人化によって個人事業を廃止した際は、都道府県税事務所へ「個人事業税の事業開始(廃止)等申告書」を提出します。
提出期限は自治体により異なり、東京都では廃止日から10日以内です。また、通常は翌年に経費計上する個人事業税も、廃業により翌年の所得がない場合は、事業廃止年に課税見込み額を経費として計上可能です。
さらに、法人化した年は「個人事業主としての期間」と「法人としての期間」を分けて、それぞれ確定申告を行う必要があります。
法人は複数作れるか
法人は複数設立できます。同一人物が複数の会社を所有し、代表取締役や役員を兼任することも法律上問題ありません。複数法人を持つことで、事業ごとにリスクを分散できる他、軽減税率や少額減価償却資産の特例などを会社単位で活用でき、資金効率の向上にもつながります。
ただし、実態のない形式的な分社は「租税回避」と判断される恐れがあり、税務署から否認されるリスクがあります。また、法人ごとに会計処理や税務申告、社会保険の手続きが必要となるため、コストや事務負担も増加します。複数法人を設立する際は、事業目的の明確化と独立性の確保が重要です。
法人から個人事業主に戻れるか
法人から個人事業主に戻ること(個人成り)は可能です。ただし、単に「会社をやめて個人で続ける」という簡単なものではなく、会社を正式に解散・清算した上で、個人として新たに開業するという2段階の手続きが必要です。
まず、法人を終了させるために株主総会で解散を決議し、法務局で「解散登記」と「清算人選任登記」を行います。清算人が債権・債務を整理し、財産目録や貸借対照表を作成した上で、債権者保護の公告や税務申告(解散確定申告・清算結了確定申告)を実施します。これらが完了すると「清算結了登記」により法人格が消滅します。
その後、税務署に「個人事業の開業届出書」を提出すれば、個人事業主として再スタートできます。ただし、法人名義の資産・契約・口座などは個人に引き継げないため、譲渡や名義変更の手続きが別途必要です。
なお、解散・清算には登録免許税約3万9,000円と官報公告費用約4万円がかかり、一般的に完了までに数カ月を要します。
まとめ
法人の基本的な仕組みや種類を理解することは、事業を始める上で非常に重要です。法人とは、法律上1つの独立した存在として認められる組織であり、個人事業主とは異なる多くのメリットとデメリットがあります。
法人化を考えている方は、まず自分のビジネスの規模や目的に合った法人の種類を選び、その設立手続きや維持費用をしっかりと把握しましょう。また、法人化のメリットとして社会的信用の向上や税金の優遇措置が挙げられますが、設立や維持にはコストや手間も伴います。もし法人化についてさらに詳しく知りたい場合や具体的な手続きに進みたい場合は、ぜひ専門家へ相談してみましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。