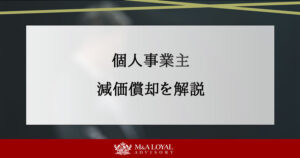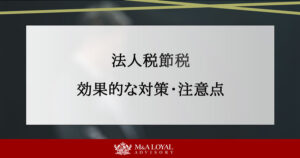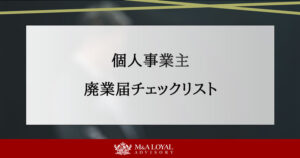個人事業主におすすめの節税対策とは?経費や控除から裏ワザまで解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型

個人事業主として事業を営むと、毎年の税負担は経営に直結する大きな課題です。売り上げが伸びても、適切に節税対策を行わなければ手元に残る資金は少なくなります。逆に、正しい知識を持って工夫すれば、資金繰りを改善し将来の投資につなげられます。
本記事では、そもそも「節税」とは何か、どのように税額が決まるのかを整理した上で、個人事業主が経費や控除を活用する節税対策の具体的な方法から、青色申告や法人化といった応用的な手段まで幅広く解説します。
さらに、節税に潜むリスクや注意点についても触れることで、個人事業主が安全かつ効果的に節税対策に取り組むための視点を提供します。
目次
節税とは
まず、そもそも節税とは何なのかを分かりやすく解説しましょう。
節税の概要
節税とは、法律の範囲内で税金の負担を軽くする工夫を行うことです。
国や自治体が定める税制には、特定の条件を満たすことで税負担が軽くなる仕組みがあります。主に所得から差し引ける「控除」(収入のうち税金がかかる部分を減らす仕組み)、特定のケースで適用される「特例」(特別に用意された優遇ルール)、そして投資や地域貢献を後押しする「優遇制度」(税金が安くなるよう設けられた制度)などです。これらを正しく活用することで、納める税金を減らし、手元に残る資金を増やせます。
節税は「脱税」と混同されがちですが、両者は全く異なります。脱税は本来納めるべき税金を不正に免れる違法行為であり、罰則の対象です。一方、節税は制度上認められた合法的な方法であり、正しく行えば安心して資金計画に役立てられます。
納税額の計算方法
税金額の主な計算の方法は、次のとおりです。
- 収入額 − 必要経費 = 所得額
- 所得額 − 所得控除 = 課税所得額
- 課税所得額 × 税率 = 基本税額
- 基本税額 − 税額控除 = 申告納税額
まず、収入から事業や生活に必要な経費を差し引きます。この金額が、実際のもうけである「所得額」です。
次に、所得から扶養控除や基礎控除、医療費控除などの「所得控除」を差し引き、税金の対象となる「課税所得額」を求めます。
課税所得額が出たら、課税所得に応じて定められた税率を掛け合わせ、基本となる税額を計算します。
最後に、住宅ローン控除や配当控除などの「税額控除」を差し引いた金額が、実際に納める税金(申告納税額)です。
節税の方法
節税するには、主に次の4パターンが挙げられます。
- 収入を減らす
- 必要経費を増やす
- 所得控除を利用する
- 税額控除を利用する
まず、収入を減らす方法です。個人事業主の場合は青色申告特別控除を利用した赤字繰越などが該当します。当たり前ですが、収入を減らせば、もうけとなる所得額を少なくできます。
次に、事業に関連する支出を正しく経費として計上することで、所得額を圧縮できます。仕事用の通信費や消耗品費、研修費などが代表例です。
また、医療費控除や小規模企業共済などを活用すれば課税所得額を減らせます。
さらに、住宅ローン控除や配当控除、外国税額控除など税額控除を利用する方法も有効です。
個人事業主は全て確定申告で行う
個人事業主は毎年確定申告を通じて所得と税額を計算し、各種控除を適用して節税を行います。
サラリーマンと違って年末調整がないため、自分で手続きをして控除を反映させなければなりません。
控除を申告しなければそのまま課税されてしまうため、領収書や証明書をそろえ、申告書に反映させることがとても重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



個人事業主が支払う税金の種類
個人事業主が支払う主な税金の種類は、次のとおりです。
- 所得税および復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
それぞれを分かりやすく解説します。
所得税および復興特別所得税
個人事業主の最も基本的な税金が所得税です。事業から得た「課税所得」に応じて、累進課税と呼ばれる仕組みで税率が上がっていきます。所得が高いほど税率も高くなる点が特徴です。
さらに、東日本大震災の復興財源として「復興特別所得税」が加算されています。復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するために2011年12月に創設された税金です。2013年から2037年までの25年間、所得税を納める個人は全員対象となり、通常の所得税に上乗せして納めます。
住民税
住民税は、一定額以上の所得がある人が居住地の自治体に納める税金です。住民税には、都道府県が課す「道府県民税」と、市区町村が課す「市町村民税」がありますが、一般的にはまとめて「住民税」と呼ばれます。
課税は1月1日時点での居住地で行われ、計算方法は二つの仕組みを組み合わせます。一つは住民が均等に負担する「均等割」、もう一つは前年の所得に応じて金額が決まる「所得割」です。
所得が少ない場合には非課税となることもあり、経済状況に配慮した制度です。
個人事業税
個人事業税は、個人で事業を行っている人に課される地方税の一つで、都道府県に納めます。ただし、全ての事業が対象となるわけではなく、法律で定められた約70種類の業種(卸売業・小売業・飲食業・医師・弁護士など)に限られます。農業や漁業、作家業などは対象外です。
課税の基準となるのは「事業所得」です。前年の事業所得から 事業主控除(年間290万円) を差し引いた金額に、業種ごとに決められた税率(3~5%)をかけて計算します。つまり、所得が290万円以下であれば非課税となり、事業規模が一定以上になって初めて納税義務が発生します。
消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供といった取引に広く課される税金です。最終的に消費者が負担し、事業者が国に納めます。
生産や流通の各段階で二重に税がかからない仕組みになっており、商品価格に上乗せされた消費税と地方消費税がまとめて課税されます。
課税対象は、国内で事業者が対価を得て行うほとんどの取引や輸入取引です。一方で、土地の譲渡や貸し付け、有価証券、保険料、医療・介護サービス、学校の授業料、住宅の貸し付けなどは非課税です。
消費税を納める義務があるのは課税売上高が1,000万円を超える事業者で、前々年や特定期間(個人は前年1~6月)で基準を超えた場合も課税事業者です。
個人事業主の節税対策【経費】
経費における個人事業主の節税対策は、次のとおりです。
- 経費を正しく計上する
- 家事按分
- 事業専従者への給与支払い
- 少額減価償却資産の特例
- 短期前払費用の特例
- 年払い
- 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
- 租税公課
それぞれを詳しく解説します。
経費を正しく計上する
個人事業主が節税するための基本は、事業に必要な支出をきちんと経費として申告することです。
交通費や書籍、セミナー代など業務遂行に関係する支出は漏れなく記録します。領収書・レシートを保存し、私用と混同することを防ぎましょう。
また、必要経費として認められるかどうかは「業務との関連性」がポイントであり、税務署からの調査時にも説明できるようにしておくことも重要です。
家事按分
自宅を業務の一部に使っている場合は、家賃や光熱費、通信費などの支出を業務用と生活用に按分(按分率を決めて按分する)して経費にできる制度です。
例えば、住宅全体のうち仕事で使う部屋の面積比や使用時間などを基準にするやり方があります。
ただし、按分率が高すぎたり、根拠が不明確だったりすると、税務署に否認されることもあります。合理的な計算根拠を帳簿に残すことが重要です。
事業専従者への給与支払い
個人事業主が家族に手伝ってもらった場合は、労働に対して給与を支払うことで節税が可能です。これを「事業専従者給与」と呼び、支払った金額を経費にできます。
ただし、白色申告では控除額に上限があり、配偶者は年間86万円、それ以外の親族は一人当たり50万円までと決められています。一方、青色申告を行えば「青色事業専従者給与」として、実際に支払った給与額を全額経費にできる点が大きなメリットです。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、労務内容や給与水準が社会的に妥当であることが条件です。
少額減価償却資産の特例
「少額減価償却資産の特例」は、中小企業者等が30万円未満の資産を取得した際に、その金額を一括で損金(経費)にできる制度です。本来、パソコンや設備などの減価償却資産は耐用年数に従って分割して経費化しますが、この特例を使えば取得した年度に全額計上できます。
対象となるのは、2006年4月1日から2026年3月31日までに取得し、事業に使用した資産で、青色申告をしている中小企業者や農業協同組合等です。中小企業者とは、常時使用する従業員が500人以下(特定法人は300人以下)の法人を指し、この範囲内であれば制度を利用可能です。
なお、少額減価償却資産の特例を利用する場合、資産の取得価格が30万円未満である必要がありますが、特例の適用を受けるためには、青色申告を行っていることが条件です。また、取得した資産が事業に使用されることが前提となります。
資産購入時点や利用開始時点での従業員数で判定されるため、制度を利用する際には従業員数や事業形態が条件を満たしているか確認する必要があります。
短期前払費用の特例
短期前払費用の特例とは、法人が支払った前払費用のうち、支払日から1年以内に提供を受けるサービスに関するものを支払時点で一括して損金算入できる制度です。
例えば、家賃や保険料、リース料などを月払いではなく年払いに切り替えて、年末に翌年分をまとめて支払うと、支払った全額を当期の経費にできます。これにより当期の利益を圧縮し、法人税や所得税の節税につながります。
ただし、毎年継続して同じ処理を行うことが条件であり、一度だけ利用することは認められません。また、利子など収益との対応が必要な費用は、年払いであっても対象外です。さらに、特例の適用を受けるには、前払費用の金額が一定の基準を超えないことも求められます。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産した際の連鎖倒産を防ぐために設けられた国の制度です。
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、取引先が支払不能となった場合に無担保・無保証で掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで借り入れが可能です。中小企業倒産防止共済の大きな特徴は、掛金が「全額必要経費」として算入できる点です。
掛金は月5,000円から20万円まで自由に設定でき、累計で800万円まで積み立てることが可能です。積み立てた掛金は解約時に原則として返還されるため、実質的には「将来の資金繰り対策」と「当面の節税」を両立できる仕組みといえます。
ただし、共済金の受け取りには一定の条件があり、例えば掛金を一定期間以上納付する必要があります。また、解約時には解約手数料がかかる場合もあるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。
租税公課
租税公課とは、国税や地方税といった「租税」と、国・自治体・公共団体などに納める会費や負担金などの「公課」を合わせた費用を処理する勘定科目です。
個人事業主にとっては、事業に関わる税金や公的負担を経費として計上する際に使う科目であり、所得を圧縮して節税につなげられます。例えば、事業用の固定資産税や自動車税、個人事業税、収入印紙代などは租税公課に含まれ、必要経費として認められます。
一方で、所得税や住民税の他、延滞税や加算税といった罰則的性格を持つ支出は経費にできません。
個人事業主のおすすめの節税対策【所得控除】
所得控除には次の15種類があります。
- 基礎控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 医療費控除
- ふるさと納税
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
それぞれを分かりやすく解説します。
基礎控除
基礎控除とは、確定申告や年末調整で所得税額を計算する際に、全ての納税者が利用できる代表的な控除です。
2020年分以降は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わる仕組みに改正されました。
合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超〜2,450万円以下なら32万円、2,450万円超〜2,500万円以下では16万円と段階的に縮小し、2,500万円を超えると適用されません。高所得者ほど控除額が小さくなる仕組みです。
生命保険料控除
生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に応じて、一定額を所得から差し引ける制度です。
対象となるのは、納税者本人が支払った保険料で、控除を受けるには保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」が必要です。
2012年1月以降の契約(新契約)と平成23年以前の契約(旧契約)で控除額の計算方法が異なります。新契約では、各区分ごとに最大4万円、旧契約では最大5万円が控除されます。ただし、新旧契約を合わせた場合は、区分ごとに最大4万円までとされます。3区分(一般・介護医療・個人年金)の合計で、所得税では最大12万円、住民税では最大7万円が控除可能です。
なお、控除額は年ごとに変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。また、控除を受ける際には、確定申告または年末調整を行う必要があります。
地震保険料控除
地震保険料控除は、納税者が地震保険の保険料や掛金を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。これは、地震保険の加入を促し、万一の災害への備えを支援する目的で設けられています。
控除額は、その年に支払った地震保険料が5万円以下であれば全額が控除され、5万円を超える場合は一律5万円が上限となります。また、2006年の税制改正により損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす旧長期損害保険契約についても控除対象となります。
例えば、2006年12月31日までに契約され、保険期間が10年以上で満期返戻金があるものが該当します。この場合、旧長期契約による控除は最大1万5千円であり、地震保険料控除との合計で上限は5万円です。
また、地震保険料控除を受けるためには、確定申告または年末調整を通じて手続きを行う必要があります。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者・親族のために支払った社会保険料をその年の所得から全額差し引ける制度です。
対象となるのは、健康保険料や国民年金、厚生年金の保険料、国民健康保険税、介護保険料、雇用保険料、国民年金基金や農業者年金の掛金、公務員共済の掛金など幅広く、給与から天引きされた金額も含まれます。
控除額は支払った金額の全額であり、上限はありません。確定申告や年末調整の際には、保険料額を証明する書類(控除証明書や領収書など)が必要です。また、租税条約に基づき海外の社会保障制度へ支払った一定の保険料も条件を満たせば控除の対象となります。
ただし、控除の対象となるためには、納税者が実際に支払った保険料であることが必要です。したがって、他人が支払った保険料は控除の対象にはなりません。
配偶者控除
配偶者控除は、納税者に所得税法上の「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる所得控除です。
控除対象配偶者とは、法律上の配偶者であり、生計を共にしていて、年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)である人を指します。内縁関係の相手や、専従者給与を受け取っている場合は対象外です。
控除額は、納税者本人の所得と配偶者の年齢によって変わります。本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上の「老人控除対象配偶者」の場合は48万円)、900万円超~950万円以下では26万円(老人32万円)、950万円超~1,000万円以下では13万円(老人16万円)です。本人の所得が1,000万円を超えると適用は受けられません。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えて配偶者控除を受けられない場合でも一定の範囲内であれば適用される所得控除です。
対象となるのは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下のケースです。
適用を受けるには、配偶者が法律上の婚姻関係にあり、生計を共にしていて、専従者給与を受け取っていないことなどの条件を満たす必要があります。控除額は本人の所得と配偶者の所得の両方に応じて段階的に変動し、最大で38万円が認められます。
夫婦の双方が同時にこの控除を受けることはできません。所得状況に応じて配偶者控除と組み合わせて検討することが重要です。
ひとり親控除
ひとり親控除は、2020年分の所得税から導入された制度で、ひとり親世帯の税負担を軽減するための控除です。
控除額は一律35万円で、対象となるのはその年の12月31日時点で婚姻していない、または配偶者の生死が不明である人のうち、一定の要件を満たす場合です。
具体的には、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
- 事実婚を含め同居するパートナーがいないこと。
- 生計を一にする子どもがいること(子どもが18歳未満であること、または高校卒業年度の3月31日までの子どもであること、子どもの所得が48万円以下で、他の人の扶養に入っていない場合に限る)。
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること。
このように、ひとり親控除は特定の条件を満たすひとり親世帯に対して税負担を軽減するための重要な制度です。
寡婦控除
寡婦控除とは、納税者本人が「寡婦」に該当する場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。
2020年分以後の控除額は27万円と定められています。対象となるのは、「ひとり親控除」に該当しない人のうち、以下の条件を満たす場合です。
- 夫と離婚後に再婚しておらず、扶養親族がいて、合計所得が500万円以下の人。
- 夫と死別または生死不明の状態で再婚していない人(扶養親族の有無は問わず)で、合計所得が500万円以下の人。
このように、寡婦控除は特定の条件を満たす納税者に対して税負担を軽減するための制度です。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。
控除額は親族の年齢や同居の有無で異なり、一般は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は同居していない場合48万円、同居の場合58万円です。
扶養親族になるには、配偶者以外の一定の親族や里子などで、生計を一にし、所得が48万円以下(給与収入103万円以下)、かつ事業専従者でないことが条件です。控除対象扶養親族は16歳以上で、令和5年分以降の非居住者については、年齢や留学・障害の有無、仕送り額に応じて限定されています。
勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者本人が学生であり、一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。
控除額は27万円です。対象となるのは、まず給与所得など勤労による所得がある人で、次に合計所得金額が75万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下である人です。
例えば、給与のみの人の場合、収入が130万円以下であれば該当します。ただし、130万円の収入には、勤労に基づく所得の金額が含まれるため、実際には給与所得控除を考慮する必要があります。
さらに、学校教育法に基づく小・中・高・大学や高等専門学校、専修学校、職業訓練法人などの「特定の学校」に在籍している必要があります。
医療費控除
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を共にする家族のために医療費を支払い、その額が一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。
対象となるのは、実際に支払った医療費で、保険金などで補填された分は差し引かれます。控除額は「支払った医療費-補填金額-10万円(所得200万円未満なら所得の5%)」で計算し、上限は200万円です。
また、通常の医療費控除と選択して適用できる「セルフメディケーション税制」もあり、特定の一般用医薬品を購入した費用のうち、12,000円を超える部分(上限88,000円)を控除できます。
障害者控除
障害者控除とは、納税者本人や同一生計の配偶者・扶養親族が「障害者」に該当する場合に受けられる所得控除です。
扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族が障害者である場合も対象です。控除額は、一般の障害者は27万円、重度の障害に該当する特別障害者は40万円、同居している特別障害者がいる場合は75万円です。
対象となるのは、精神や知的障害の認定を受けた人、身体障害者手帳で1・2級に該当する人、高齢で障害の認定を受けた人、戦傷病者や被爆者として認定を受けた人、または寝たきりで複雑な介護が必要な人などです。
寄附金控除
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附を行った際に受けられる所得控除のことです。
代表的な制度に「ふるさと納税」があり、地方自治体への寄附を通じて地域を応援しつつ、収めた税金が控除対象です。
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCoや企業型DCの「マッチング拠出」で拠出した掛金は、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除できます。
また、iDeCoと企業型DCのどちらも、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
非課税で運用しつつ、さらに受取時にも控除を受けられます。
雑損控除
雑損控除は、災害や盗難、横領によって資産に損害を受けたときに利用できる所得控除です。
対象となる資産は、納税者本人や同一生計の配偶者・親族(所得48万円以下)の所有のもので、生活に通常必要な資産に限られます。控除額は次の計算式のうち大きい方が適用されます。
- 損害金額 + 災害関連支出 – 保険金等 – 総所得金額等の10%
- 災害関連支出 – 保険金等 – 5万円
損害金額は資産の時価を基準に計算され、災害関連支出には住宅や家財の取り壊し・除去費用などが含まれます。控除対象となる損害原因は、地震や風水害などの自然災害、火災や爆発といった人為災害、害虫被害、盗難、横領です。
ただし、詐欺や恐喝による損害は対象外です。
個人事業主の節税対策【税額控除】
主な税額控除は次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 配当控除
- 寄附金特別控除
- 外国税控除
それぞれを詳しく解説します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、住宅の新築・取得や一定の増改築をした場合に利用できる税額控除です。
住宅ローンの年末残高を基準に計算した金額を、一定期間にわたり所得税から差し引けます。控除を受けるには確定申告で必要書類を添付する必要があり、給与所得者は1年目に申告すれば2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
また、バリアフリーや省エネ、多世帯同居、耐久性向上といった特定の増改築をした場合もローン残高を基にした控除が最長5年間適用されます。増改築をした場合、通常の住宅ローン控除との選択制です。さらに、災害で住宅が被害を受けた場合には、適用期間の延長や再取得に関する特例も設けられています。
配当控除
配当控除は、総合課税として申告した配当所得に適用できる制度です。
控除額は、配当所得の金額に応じて原則10%または5%が差し引かれます。ただし、この制度を利用できるのは、日本国内に本店を持つ法人から受け取る配当や証券投資信託の収益分配などで、確定申告において総合課税を選択した場合に限られます。
また、基金利息や特定の投資信託からの分配金、投資法人や特定目的会社からの配当なども控除の対象にはなりません。従って、配当所得がある場合には、課税方式を慎重に選ぶことが大切です。
寄附金特別控除
寄附金特別控除とは、国や地方公共団体、特定の団体などに寄附をした際に、通常の「寄附金控除(所得控除)」に代えて選択できる制度です。
対象となるのは、政党や政治資金団体への寄附、認定NPO法人や公益社団法人等への寄附などで、それぞれ次の算式に基づいて控除額が決まります。
● 政党等寄附金特別控除 (寄附額 − 2,000円)× 30%
● 認定NPO法人等寄附金特別控除/公益社団法人等寄附金特別控除 (寄附額 − 2,000円)× 40%
いずれも100円未満は切り捨てられます。限度額は「所得金額の40%」または「所得税額の25%」のいずれか低い方が適用されます。
寄附金特別控除は税額から直接差し引けるため、所得控除よりも節税効果が大きくなる場合があります。そのため、寄附の種類や自身の所得状況に応じてどちらを選択するかを検討することが大切です。
外国税控除
外国税額控除は、日本の居住者が海外で得た所得に対して現地で所得税を納めた場合、納めた税額を日本の所得税から一定限度まで差し引ける制度です。
これは二重課税を防ぐための仕組みで、控除できる上限は「所得税額 × (国外所得 ÷ 所得総額)」で計算されます。限度を超えた分については、復興特別所得税の控除や3年間の繰越控除が可能です。
対象となるのは、外国の法令に基づく所得課税に限られ、租税条約に基づいて免除された税などは控除の対象外です。
ただし、外国税額控除を利用する際には、適用を受けるための要件や手続きがあるため、事前に税務署や専門家に相談することが重要です。
個人事業主の節税対策【その他】
その他の個人事業主の節税対策は、次のとおりです。
● 青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、青色申告者が一定の条件を満たした場合に、所得金額から控除できる制度です。控除額は55万円・65万円・10万円のいずれかで、要件によって異なります。
青色申告者とは、事業所得や不動産所得などがある人が、正しい帳簿を作成し、一定の要件を満たして「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受けた人のことです。
55万円控除は、不動産所得や事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を申告期限内に提出する場合に受けられます。65万円控除は、55万円控除の要件に加え、電子帳簿保存の利用やe-Taxでの申告が条件です。10万円控除は、これらの要件を満たさない場合でも青色申告者であれば適用可能です。
消費税の計算方式の変更
事業者が消費税を申告する際の計算方法には「原則課税(一般課税)」と「簡易課税」の2種類があります。
原則課税は、実際の仕入や経費に含まれる消費税を差し引いて計算する方法で、正確ですが事務負担が大きい点が特徴です。一方、簡易課税は業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて仕入控除を計算するため、手続きが簡単で小規模事業者に向いています。
事業の実態によって有利・不利が分かれるため、適切な方式を選択し、必要に応じて届出により切り替えることで節税につながる可能性があります。
法人化
法人化とは、個人事業主が事業を株式会社や合同会社などの「法人」として運営することを指します。
法人にすると役員報酬として所得を分散できるため、所得税の累進課税を抑えやすくなり、社会保険料の面でも最適化が可能です。また、法人税率は一定水準に抑えられているため、利益が増えるほど個人事業より税負担が軽減される場合があります。
ただし、コストが増えるデメリットもあります。法人化すれば必ず節税になるわけではなく、「増える経費」と「減る税負担」のバランスを見極めることが重要です。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは「控除」ではありませんが、結果的に節税効果を得られる仕組みです。
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Savings Account)」の略称で、個人が株式や投資信託などに投資した際の利益(配当や売却益)に対して、一定額まで非課税になる制度です。
通常の投資では、株式や投資信託の利益に約20%の税金がかかります。例えば100万円の利益が出ても、20万円は税金として差し引かれ、実際に手元に残るのは80万円です。しかし、NISAを利用すれば利益全額に税金がかからず、そのまま100万円を受け取れます。
個人事業主が節税する際の注意点
個人事業主が節税する際の注意点は、次のとおりです。
● 経費を増やしすぎると手元資金が減る 節税のために無理に経費を増やすのは注意が必要です。
確かに経費を増やせば課税所得は減り、税金を抑えられます。しかし、その分、実際に支出したお金は手元から出ていくため、資金が減少します。資金繰りが悪化すれば、仕入れや広告、設備投資など事業成長に必要なお金が不足し、経営を圧迫する可能性があります。
節税は利益を守る手段であって、それ自体を目的化してはいけません。必要な経費と不要な出費をきちんと分け、将来につながる支出を意識することが大切です。
● 過度に節税しすぎると不信感を抱かれる 節税は大切ですが、やりすぎると税務署や取引先から不信感を抱かれるリスクがあります。
特に不自然な経費計上や実態のない支出が多いと税務調査の対象になりやすく、追徴課税につながる可能性もあります。また、数字に透明性が欠けると金融機関からの信用が下がり、融資や取引条件に悪影響を及ぼすこともあります。
節税は「信頼を損なわない範囲」で行うことが重要です。
● 専門家に相談すべき場合も多い 税制には多くの控除や特例がありますが、中には重複して使えないものも存在します。
例えば、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べませんし、寄附金控除も「所得控除」と「税額控除」の選択が必要です。知識不足のまま申告すると、本来受けられるはずの控除を逃したり、逆に誤って適用して後で修正を求められることもあります。
こうしたリスクを避けるには、税理士などの専門家に相談し、自分の状況に最も有利で正しい控除を選ぶことが重要です。
個人事業主の節税に関するQ&A
最後に、個人事業主の節税に関するよくある質問とその回答を紹介します。
個人事業主が節税のために、まず取り組むべきことは何か
節税の第一歩は「経費の正しい計上」です。
事業に関連する支出を漏れなく経費として処理することで、課税対象となる所得を減らせます。特に、交通費や通信費、事務用品費など日常的な支出は見落としがちです。
また、青色申告に切り替えると最大65万円の控除や赤字の繰越控除などのメリットを受けられるため、会計ソフトを利用して帳簿付けを習慣化することがおすすめです。
経費として認められやすいものは何か
認められやすいのは、事業と直接結びつきが明確な支出です。例えば、次の項目が典型例です。
- 交通費・旅費:打ち合わせや出張に伴う電車代・宿泊費
- 通信費:電話代、インターネット代
- 消耗品費:文具やプリンターインクなど短期で使い切る物品
- 広告宣伝費:チラシ印刷、ウェブ広告掲載料
一方で、飲食代や交際費は「業務目的」を証明できなければ否認されやすいため、相手や目的を記録に残すことが重要です。
節税と資金繰りを両立させるにはどうすべきか
節税のために多額の支出や掛金を行うと、手元資金が減って資金繰りを悪化させる恐れがあります。
両立のポイントは、次のとおりです。
- 短期的に現金が必要かを見極める
- 無理のない範囲で積立制度を利用する
- 必要経費は計画的に購入する(パソコンや設備の更新など)
一方、経費による節税を最小限に抑えなるべく多くの資金を手元に残すことで、銀行融資を有利に進め資金繰りを安定させるという戦略も有効です。
インボイス制度は節税に影響あるか
インボイス制度は、消費税の納税義務や仕入税額控除の扱いに影響します。
免税事業者のままだと、取引先が仕入税額控除を使用できなくなるため、取引先の負担が増加し、結果として仕事を失うリスクが高まります。一方で、課税事業者として登録すると、売上に応じて消費税を納める必要が出てきます。
ただし、課税事業者になることで経費や仕入にかかる消費税を差し引けるため、実際の納税額は思ったより少なくなる場合もあります。つまり、取引関係や売上規模に応じて「免税のままが有利か」「課税事業者としての節税策を取るか」を判断することが重要です。
また、インボイス制度の導入により、取引先との関係性や契約形態も見直す必要が生じるため、事前にしっかりとした検討が求められます。
まとめ
個人事業主にとって節税は、事業の継続と成長を支える重要な要素です。適切な節税対策を行うことで、税負担を軽減し、事業資金を有効活用することができます。この記事で紹介したように、経費の正しい計上や控除の活用は基本です。また、青色申告や法人化の検討など、より高度な対策も視野に入れると良いでしょう。しかし、節税にはリスクも伴うため、無理のない範囲で行うことが大切です。
もし自分だけで判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することで、より適切な節税方法を見つけることができます。まずは自分の事業の現状をしっかり把握し、本記事で学んだことを実践することで、無理なく節税を進めてください。この機会にぜひ一歩を踏み出し、賢い節税を実現しましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。