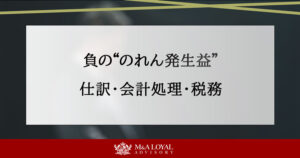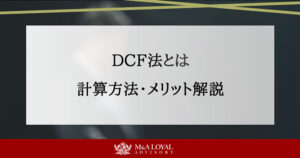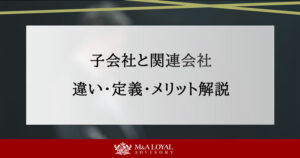非支配株主持分とは?勘定項目が純資産はなぜ?M&Aでの影響も解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
非支配株主持分とは企業会計における重要な概念で、親会社以外の株主が子会社を所有する場合、その持分を指します。これは親会社の株主に帰属しないため、純資産の部に計上されます。連結財務諸表では、親会社株主と非支配株主持分が区分され、グループ全体の財務状況を正確に示します。また、M&Aで非支配株主持分とは企業価値評価において重要な要素となり、企業全体の価値から親会社株主に帰属する価値を算出する際に考慮されます。本記事では、非支配株主持分とは何か、その基礎とその実務的なポイントを解説します。
目次
非支配株主持分とは
まず非支配株主持分の基本的な知識について紹介します。
非支配株主持分の概要
非支配株主持分とは、連結子会社の資本のうち「親会社が保有していない部分」を指します。つまり、グループ全体の連結財務諸表において、子会社に出資している少数株主(非支配株主)の持分です。
例えば、ある企業が子会社の株式を75%取得した場合、その75%は親会社の持分になりますが、残りの25%は親会社以外の株主に帰属します。この親会社が保有していない25%が、少数株主持分(非支配株主持分)として計上されます。
要するに、非支配株主持分は「子会社における親会社以外の株主の取り分」を表すものであり、連結会計においては重要な概念の一つです。
勘定項目「非支配株主持分」は純資産の部に表示
非支配株主持分は、連結貸借対照表において「純資産の部」に表示される勘定項目です。これは子会社の資本のうち、親会社に帰属しない部分を指し、外部の少数株主が保有する持分に相当します。非支配株主も子会社の所有者である点に変わりはなく、グループ全体の財政状態を正しく示すためには、彼らの持分も純資産の一部として扱うことが適切とされています。
かつては「少数株主持分」と呼ばれ、貸借対照表上では負債の部と資本の部の中間に独立した区分として表示されていました。これは、返済義務がある負債ではない一方、親会社株主に帰属する資本でもないため、中間的な位置付けが採用されていたためです。しかし、2005年(平成17年)に公表された会計基準の改正により、この中間区分は廃止され、非支配株主持分は純資産の部に含めて表示することとなりました。
このように、非支配株主持分は「純資産の一部」として扱われることが明確に定められたため、連結財務諸表では、親会社持分と非支配株主持分を区分して表示することが不可欠です。
非支配株主持分の増減
非支配株主持分は、子会社の純資産や持分比率の変動に応じて増減します。
基本的には、子会社の資本が増減すれば、それに比例して非支配株主持分も変動します。例えば、子会社が利益を計上すれば純資産が増加し、その結果として非支配株主持分も増加します。逆に損失を計上すれば純資産が減少し、非支配株主持分も減少します。
また、子会社が配当を行えば、その配当部分に対応する非支配株主持分は減少します。一方で、子会社が株主割当増資を行った場合には純資産が増えるため、非支配株主持分も増加することになります。さらに、評価・換算差額等に含まれるその他有価証券評価差額金などが変動した場合にも、持分比率に応じて非支配株主持分は増減します。
加えて、子会社の資本総額に変動がない場合でも、持分比率が変動すると非支配株主持分は増減します。親会社が子会社株式を追加取得すれば、親会社の支配比率が高まるため非支配株主持分は減少します。逆に、親会社が子会社株式の一部を売却すれば、外部株主の比率が高まり、非支配株主持分は増加します。
このように、非支配株主持分は「子会社の資本の変動」と「持分比率の変動」の双方によって影響を受ける仕組みです。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



そもそも連携会計とは
次に、そもそも連結会計とは何なのかをわかりやすく解説します。
連結修正仕訳とは
連結修正仕訳とは、親会社と子会社の個別財務諸表を単純に合算するだけでは企業集団の実態を正しく示せないため、その不整合を解消する目的で行われる仕訳を指します。
例えば、親会社の資産である「子会社株式」と、子会社の純資産である「資本金」や「利益剰余金」は、グループ全体としては二重に計上されてしまいます。そのままでは、グループとして実際には存在しない資産や資本が貸借対照表に残ることになります。このような二重計上を解消し、あたかも一つの会社のように表示するために加えられる調整仕訳が連結修正仕訳です。
連結修正仕訳には、投資と資本の相殺消去や内部取引の消去、未実現利益の消去、非支配株主持分の計上などが含まれます。これらは全てをグループ内の取引と外部との取引に区別し、財務諸表の利用者に対して企業集団の実態をより忠実に伝えることを目的としています。
開始仕訳と修正仕訳の違い
連結修正仕訳は、その性格に応じて「開始仕訳」と「修正仕訳」に区分されます。
開始仕訳とは、連結会計期首に行う処理で、前期末に実施された連結修正の内容を翌期に引き継ぐために用いられます。例えば、前期末の連結貸借対照表で計上されていた非支配株主持分やのれんを、そのまま当期首の残高として設定する仕訳が開始仕訳です。開始仕訳を行うことで、当期の財務諸表が前期末の状態から正しくスタートすることが保証されます。
これに対して修正仕訳は、当期に発生した取引や事象を調整するために行う仕訳です。例えば、子会社が当期に計上した利益を親会社と非支配株主持分に配分する処理、あるいは子会社が親会社へ配当を支払った際の処理は修正仕訳に該当します。また、期中に親会社が子会社株式を追加取得した場合や一部を売却した場合も、非支配株主持分の増減を反映させる修正仕訳が必要です。
このように、開始仕訳は「期首残高を整える」ためのもの、修正仕訳は「当期の成果を反映させる」ためのものであり、その目的とタイミングが明確に異なります。
資本連結と成果連結の違い
資本連結と成果連結は、どちらも連結修正仕訳の中核をなす処理ですが、その目的と対象が明確に異なります。
資本連結は、親会社の投資(子会社株式)と、子会社の株主資本を相殺消去することで、企業グループ全体を一つの経済主体として表すための仕訳です。このとき生じた差額は「のれん」として振り替えられ、最長20年の定額法で償却されます。また、支配獲得日の子会社の資産や負債を時価に評価替えし、その差額を評価差額として処理することも行われます。
さらに、子会社の当期純損益のうち親会社に帰属しない部分は「非支配株主持分」として振り替えられ、子会社が配当を行った場合も、親会社への配当は相殺、非支配株主への配当は「非支配株主持分当期変動額」に反映させるなど、グループ全体としての資本構成を正しく表すことが資本連結の役割です。
一方で成果連結は、グループ内で生じた取引を相殺消去し、外部との取引による成果だけを残すための仕訳です。親子会社間やグループ内で発生した売上高や売上原価、債権債務といった内部取引は、そのままでは二重計上となり、実態を正しく表せません。そのため、これらを相殺消去した上で、外部から得た実現利益だけを計上します。
加えて、内部取引に関連して計上された貸倒引当金は修正仕訳で取り消され、棚卸資産や固定資産に含まれる未実現損益も外部に販売されるまでの間は消去されます。成果連結は、グループ内部の利益や費用を取り除くことで、正確な損益計算を実現する役割を担います。
つまり、資本連結が「投資と資本の関係を整理し、グループ全体の資本構成を正しく表示する」処理であるのに対し、成果連結は「内部取引を消去し、外部との取引から得られた実際の成果だけを計上する」処理である点に違いがあります。
非支配株主持分の仕訳(連結修正仕訳)の流れ
非支配株主持分の仕訳(連結修正仕訳)の流れを解説します。
支配獲得日の連結修正仕訳
親会社が子会社(資本金8,000万円、利益剰余金3,000万円)株式の70%を8,500万円で取得し、子会社の支配を獲得した場合の支配獲得日の連結修正仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 資本金 | 8,000 | 子会社株式 | 8,500 | 連結修正 |
| 利益剰余金 | 3,000 | 非支配株主持分 | 3,300 | 連結修正 |
| のれん | 800 | 連結修正 | ||
単位:万円
親会社による子会社株式の取得に伴う連結修正仕訳では、まず親会社が保有する「子会社株式」(8,500万円)と、子会社の資本金(8,000万円)および利益剰余金(3,000万円)を相殺して消去します。その上で、子会社純資産合計11,000万円のうち親会社が保有しない30%分、すなわち3,300万円を「非支配株主持分」として貸方に計上します。
この調整の結果、借方と貸方の差額として800万円の「のれん」が発生します。こののれんは、子会社の純資産額を超えて支払った投資額を意味し、将来的に償却や減損の対象となる可能性があります。
連結第1事業年度の連結修正仕訳
連結第1事業年度では、まず親会社と子会社の個別財務諸表を作成し、単純に合算してグループ全体の数値を算出します。その後、親子会社間の債権・債務や内部取引を調整するため、連結修正仕訳を行います。
この時期に行う修正仕訳は、大別して次の3つに分けられます。
開始仕訳
修正仕訳の中心となるのが「開始仕訳(支配獲得日の再現)」です。これは期首残高を正しく示すための処理で、支配獲得時の連結関係を再現する役割を担います。支配獲得日の仕訳をそのまま再度行い、勘定科目には「当期首残高」などを付けて当期発生分と区別することが一般的です。
親子会社の連結第1事業年度の開始仕訳例は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 資本金当期首残高 | 8,000 | 子会社株式 | 8,500 | 連結修正・開始 |
| 利益剰余金当期首残高 | 3,000 | 非支配株主持分当期首残高 | 3,300 | 連結修正・開始 |
| のれん | 800 | 連結修正・開始 | ||
単位:万円
資本連結の連結修正仕訳
連結第1事業年度では、当期に生じた変動を反映させるため、資本連結に関する修正仕訳を行います。対象となるのは、のれんの償却、子会社の当期純利益の配分、そして子会社が支払った配当金の処理です。これらの仕訳により、親会社株主持分および非支配株主持分を正しく表示し、グループ全体の純資産の動きを的確に把握できます。
例として、次の条件を前提とします。
- のれん償却額:80万円(10年定額法)
- 子会社の当期純利益:1,000万円
- 子会社の配当金総額:50万円
- 親会社持株比率:70%
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| のれん償却 | 80 | のれん | 80 | 連結修正・のれん償却 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 300 | 非支配株主持分 | 300 | 連結修正・子会社当期純利益振替 |
| 受取配当金 | 35 | 利益剰余金 | 50 | 連結修正・子会社配当金 |
| 非支配株主持分 | 15 | 連結修正・子会社配当金 | ||
単位:万円
のれんについては定額法で10年償却する前提の下、80万円を「のれん償却費(借方)」として計上し、同額を「のれん(貸方)」から減額します。
次に、子会社の当期純利益1,000万円を親会社持分(70%)と非支配株主持分(30%)に分配します。非支配株主に帰属する利益は300万円(1,000万円 × 30%)であり、「非支配株主に帰属する当期純利益(借方)」と「非支配株主持分(貸方)」に振り替えて計上します。
最後に、子会社の配当金50万円について調整します。親会社に帰属する35万円(50万円 × 70%)の受取配当金を消去(借方)し、非支配株主持分に対応する15万円(50万円 × 30%)は「非支配株主持分(借方)」を減額します。その相手勘定は「利益剰余金(貸方)」となり、配当支出による純資産の減少を反映します。
これらの修正仕訳により、親会社株主持分および非支配株主持分が正しく表示され、連結財務諸表における資本連結の整合性が確保されます。
成果連結の連結修正仕訳
連結第1事業年度では、親会社と子会社の間で内部取引が発生します。そのため、成果連結に関連する部分については、連結修正仕訳を行う必要があります。
ここでは、親会社が子会社に対して50,000円の売り上げを計上し、対応する売掛金が5,000円、買掛金が5,000円、さらに貸倒引当金が100円計上されているケースを想定します。また、子会社側の期末商品には、親会社の未実現利益100円が含まれていると仮定します。
この条件の下で行う連結修正仕訳は、次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 売上高 | 50,000 | 売上原価 | 50,000 | 連結修正・売上仕入相殺 |
| 買掛金 | 5,000 | 売掛金 | 5,000 | 連結修正・債権債務相殺 |
| 貸倒引当金 | 100 | 貸倒引当金繰入 | 100 | 連結修正・貸倒引当金調整 |
| 売上原価 | 100 | 商品 | 100 | 連結修正・未実現利益調整 |
単位:万円
連結第2事業年度以降の連結修正仕訳
連結第2事業年度以降においても、連結修正仕訳は引き続き重要な役割を果たします。
まず、開始仕訳として支配獲得日の連結修正仕訳を再現し、前連結事業年度からの残高を正しく引き継ぎます。これにより、連結財務諸表が一貫して作成される基盤が整います。
その上で、当期に新たに発生した資本連結に関する修正仕訳や、親子会社間取引の成果を調整する成果連結の修正仕訳を追加していきます。
連結第1事業年度の資本連結にかかる開始仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 資本金当期首残高 | 8,000 | 子会社株式 | 8,500 | 連結修正・開始 |
| 利益剰余金当期首残高 | 3,000 | 非支配株主持分当期首残高 | 3,300 | 連結修正・開始 |
| のれん | 800 | 連結修正・開始 | ||
| 利益剰余金当期首残高 | 80 | のれん | 80 | 連結修正・開始 |
| 利益剰余金当期首残高 | 300 | 非支配株主持分当期首残高 | 300 | 連結修正・開始 |
| 利益剰余金当期首残高 | 35 | 利益剰余金当期首残高 | 50 | 連結修正・開始 |
| 非支配株主持分当期首残高 | 15 | 連結修正・開始 | ||
単位:万円
連結第1事業年度の成果連結にかかる開始仕訳
連結第2事業年度以降における開始仕訳では、前期の成果連結の修正仕訳のうち「貸倒引当金の調整」と「棚卸資産に含まれる未実現利益の消去」の2点を再度仕訳する必要があります。これらは前期末残高として翌期首に引き継がれるためです。
一方で、親子会社間の内部取引や債権・債務の相殺仕訳は毎期発生する項目であり、開始仕訳には含めず、その期の連結修正仕訳として改めて処理されます。この点を区別することが重要です。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 貸倒引当金 | 100 | 利益剰余金当期首残高 | 100 | 連結修正・開始 |
| 利益剰余金当期首残高 | 100 | 商品 | 100 | 連結修正・開始 |
単位:万円
資本連結・成果連結の連結修正仕訳
連結第2事業年度でも、資本連結および成果連結に関する修正仕訳は引き続き必要です。基本的な仕訳内容は第1事業年度と同様ですが、成果連結における「未実現利益」の処理が大きなポイントとなります。
まず、前期末に発生した未実現利益については、当期首において繰り戻し処理を行い、利益剰余金などを調整することで、当期の期首財務諸表に正しく反映させます。これにより、当該商品が当期中に外部に販売されたものとみなし、利益を実現済みとして扱います。
一方で、当期末に新たな未実現利益が発生した場合には、その金額を連結上で消去する仕訳が必要です。例えば、子会社の期末商品に300円の未実現利益が含まれる場合、これを売上原価と棚卸資産から控除する仕訳を行い、連結財務諸表に正しく反映させます。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 商品 | 100 | 売上原価 | 100 | 連結修正・未実現利益調整 |
| 売上原価 | 300 | 商品 | 300 | 連結修正・未実現利益調整 |
単位:万円
このように、未実現利益の処理は「前期分の取崩し」と「当期分の消去」という二段階の仕訳で構成される点が、第1事業年度と異なる特徴です。仕訳自体はシンプルですが、期末棚卸資産にどれだけ親会社の利益が含まれているかを正確に把握する必要があり、実務上は注意を要する項目です。
非支配株主持分のM&Aのバリュエーションでの影響
非支配株主持分がM&Aでどのような影響をもたらすのかを解説します。
「デットライクアイテム」として控除
M&Aの場面では、買収対象企業の価値を正しく測定することが重要です。その際によく用いられる手法がDCF法やマルチプル法などによるバリュエーションです。これらの手法では、まず企業全体としての価値であるEV(Enterprise Value:企業価値)を算出し、そこから有利子負債などを控除して株主に帰属する株式価値を計算します。
このとき注意が必要な項目が非支配株主持分です。非支配株主持分は、連結子会社の純資産のうち親会社に帰属しない部分を指すため、買収後に親会社株主が自由に活用できる資本ではありません。つまり、連結財務諸表上では純資産に含まれるものの、実質的に買収側にとっては利用できない価値といえます。従って、バリュエーションにおいては有利子負債などと同じように「デットライクアイテム」と位置付け、企業価値から控除する必要があります。
その他のデットライクアイテムになり得る項目
M&Aのバリュエーションにおいては、非支配株主持分以外にも「デットライクアイテム」として控除が必要な項目が存在します。デットライクアイテムとは、有利子負債と同様に、将来の支出や損失、あるいは収益の減少につながる可能性が高い項目を指します。これらは、実際には株主が自由に活用できる資本を減少させる要因となるため、EVから控除して株式価値を算定することが一般的です。
代表的なものとしては、退職給付債務やリース債務があります。退職給付債務は、従業員の退職に備えて将来支払うべき義務であり、実質的に大きなキャッシュアウトを伴います。また、リース取引によって生まれるリース債務は経済的実態を「資産の割賦購入」と捉えた場合、デットライクアイテムとして扱うことが妥当と考えられます。その他、役員退職慰労引当金や未払配当金、資産除去債務、偶発債務なども控除対象に含まれることがあります。
連結子会社を含む子会社の種類
非支配株主持分とは、連結子会社の資本のうち、親会社が保有していない部分を指します。連結財務諸表では、非支配株主持分を区分して表示し、企業グループ全体の財務状況を正しく示すよう調整が行われます。
一方、子会社や関連会社には、以下のような分類があります。
子会社の種類
1.完全子会社
完全子会社とは、親会社が発行済株式のすべて、すなわち議決権の100%を直接または間接的に保有している会社を指します。 外部の株主が存在しないため、親会社は子会社の経営方針や業務執行を完全にコントロールできます。この場合、連結財務諸表上では非支配株主持分が発生しません。
完全子会社は、親会社の戦略に基づいて特定の事業領域や地域に特化した運営を担うことが多く、例えば製造部門を切り出して生産拠点としたり、海外進出のための拠点会社として設立されるケースがあります。
2.連結子会社
連結子会社とは、親会社が議決権の過半数(50%超)を保有している、または株式保有割合が過半数未満であっても取締役の派遣や実質的な経営支配を通じて「支配力」を有している会社を指します。
連結財務諸表は企業グループ全体を一つの経済主体とみなして作成されるため、連結子会社の資産・負債・収益・費用はすべて親会社と合算されます。その際、親会社の持分と非支配株主持分を区分して表示します。
例えば、親会社が80%を保有し、残り20%を外部株主が持っている子会社は、連結子会社に該当し、連結財務諸表上では非支配株主持分が明記されます。
その他の会社の分類
1.規模が小さい子会社(連結対象外)
子会社であるものの、規模が非常に小さく連結しても財務情報に与える影響が軽微である場合や、特殊な事情により支配が実質的に制限されている場合には、連結財務諸表の対象外となることがあります。これらは「重要性が乏しい子会社」として扱われます。
なお、これらの子会社に対しては、持分法が適用されることがあります。
2.関連会社(持分法適用会社)
関連会社とは、親会社が議決権の20%超50%以下を保有し、支配権はないものの、一定の影響力を及ぼす会社を指します。この影響力は、持株比率のほか、取締役の派遣状況や経営方針への関与度合いによって判断されます。
関連会社は、連結財務諸表には含まれず、持分法による会計処理が適用されます。持分法では、親会社がその会社の利益や損失の一部を自社の財務諸表に反映させる方法が採用されます。
持分法の概要
持分法とは、「投資会社が被投資会社の純資産および損益のうち、投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法」をいいます。
持分法は、原則として、規模が小さい子会社や関連会社への投資に適用され、これらの会社を「持分法適用会社」と呼びます。
非支配株主持分以外の純資産の部の項目
非支配株主持分以外の純資産の部の項目は次のとおりです。
- 株主資本(資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式)
- その他包括利益累計額
- 新株予約権
それぞれをわかりやすく解説します。
株主資本
株主資本は、純資産の中でも最も中心的な要素であり、親会社株主に帰属する部分を表します。企業にとっては返済義務のない資金であり、長期的に事業を支える安定的な基盤を構成します。構成要素は「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」「自己株式」に分かれます。
資本金
資本金は、会社が設立時や増資時に株主から払い込まれた出資金のうち、資本金として計上された金額を指します。会社の存立基盤を表すものであり、債権者保護の観点から重要な位置付けを持っています。法律上、資本金を減少させる際に公告など厳格な手続きを要し、債権者が不利益を被らないように保護されています。
現在では1円会社の設立が可能ですが、配当規制において純資産が300万円未満の場合、剰余金があっても株主に配当できません。
また、資本金の払込みのうち半額は資本準備金として処理でき、節税の観点から実施される場合があります。
資本剰余金
資本剰余金とは、株主からの出資など株主との資本取引によって得られた資金のうち、資本金に組み入れられなかった部分の総額を指します。構成要素は資本準備金とその他資本剰余金の二つで、株主配当や自己株式取得の原資として用いられる場合がありますが、利益剰余金のように事業活動から生じた利益ではありません。
資本準備金は、株主からの払込額の一部を資本金ではなく準備金として計上したもので、将来に備えて内部に留保され、外部への分配が制限されます。一方、その他資本剰余金は、減資や組織再編による資本取り崩しで発生した差益や、自己株式を処分した際の差益など、資本準備金以外の資本取引から生じたものを指します。
このように資本剰余金は、企業の財務基盤を支える重要な内部留保として位置付けられています。
利益剰余金
利益剰余金は、企業の営業活動や投資活動によって生み出された利益のうち、株主への配当などで外部に還元されずに内部に留保された部分を指します。利益剰余金はさらに「利益準備金」「その他利益剰余金(任意積立金、繰越利益剰余金)」に区分されます。
利益準備金は、会社法で配当を行う際に一定割合を積み立てることが義務付けられている法定準備金です。これは債権者保護のために設けられています。
任意積立金は、将来の設備投資や研究開発、事業拡大などに備えるために会社が自主的に積み立てる内部留保です。繰越利益剰余金は、過去から繰り越された利益をまとめたもので、配当の原資となるほか、企業活動を支える資金としても利用されます。
利益剰余金が積み上がっている企業は、内部留保によって安定的な経営が可能であり、金融機関や投資家からも財務体質が健全と評価されやすいです。
自己株式
自己株式は、会社が一度発行した株式を市場などから買い戻した場合に計上される項目です。自己株式は資産ではなく、株主資本の控除項目として純資産から差し引かれる形で表示されます。
買い戻しの目的には、株価の安定や株主への利益還元、敵対的買収の防止、将来のストックオプションの原資として活用するなど、さまざまな戦略的な意図があります。ただし、自己株式を保有していても会社自身に議決権や配当請求権はなく、実質的には「存在しない株式」と同じ扱いです。
そのため、自己株式は資本としての機能を持たず、純資産を減少させる要素です。また、過度な自己株式取得は資金の社外流出を招き、企業の成長投資余力を減少させる可能性があるため、バランスの取れた活用が求められます。
その他包括利益累計額
その他包括利益累計額は、当期純利益には含まれないが資本取引以外の純資産の変動を示すものです。代表的には、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定、退職給付に係る調整累計額などがあります。
その他有価証券とは、売買目的有価証券と満期保有目的の債権、子会社株式、関連会社株式以外の有価証券を指します。その他有価証券評価差額金の会計処理には、全部純資産直入法と部分純資産直入法の二つがあります。
これらは「まだ実現していない利益や損失」である点が特徴です。例えば、保有している株式の時価が上昇しても、売却するまでその利益は確定していません。しかし、投資家や債権者にとっては将来の財政状態に影響を与える可能性があるため、情報として開示する必要があります。従って、損益計算書には計上せず、純資産の部で「その他包括利益累計額」として表示されます。これは、企業の財務状況をより包括的に捉え、将来キャッシュフローに与える影響を透明化する役割を果たしています。
新株予約権
新株予約権とは、将来あらかじめ決められた条件で株式を取得できる権利を指します。会社が役員や従業員にインセンティブとして付与するケースや、資金調達の一環として投資家に発行するケースがあります。
新株予約権は返済義務のある負債ではなく、現時点では株主の資本でもないという中間的な性質を持っています。そのため、純資産の部において株主資本やその他包括利益累計額とは独立した区分として表示されます。
権利が行使されれば株式が発行され、資本金や資本剰余金に組み入れられることになりますが、行使されなければ失効して消滅します。従って、新株予約権は「潜在的な資本」として位置付けられる点が特徴です。
非支配株主持分に関するQ&A
非支配株主持分に関するよくある質問とその回答を紹介します。
非支配株主が存在する子会社が債務超過に陥った場合どうなるか
子会社が累積損失を計上して純資産がマイナスとなった場合でも、非支配株主持分は通常マイナスにはなりません。これは、株式会社の株主が有限責任を負う仕組みに基づき、非支配株主の責任が出資額の範囲内に限定されるためです。従って、非支配株主が自己の持分を超えて損失を負担する必要はありません。
一方で、親会社は子会社の主要株主として、債権者に対する保証債務の存在や、グループ全体の信用維持・経営責任の観点から、子会社の債務を肩代わりするケースが少なくありません。そのため、非支配株主持分は出資額を限度とする扱いが妥当と考えられています。
ただし、例外的に非支配株主と親会社などの間で特別な取り決めがあり、出資を超えて損失を負担する合意がある場合には、その範囲で非支配株主持分がマイナスに計上されることがあります。このようなケースは、契約内容や法的拘束力に基づいて慎重に判断されます。
その後、子会社が黒字化して利益を計上した場合、親会社が負担した過去の欠損を回収する形で親会社の持分に加算され、残額が非支配株主持分に帰属することがあります。ただし、具体的な処理方法は適用される会計基準に基づいて決定されます。
非支配株主持分ものれん償却額を負担するか
子会社の資本は、連結財務諸表上では親会社持分と非支配株主持分に分けて表示されます。ただし、のれんは親会社が子会社株式を取得した際の投資額から発生するものであるため、親会社持分にのみ反映され、非支配株主持分には配分されません。そのため、のれんの償却も非支配株主持分に影響を及ぼさず、親会社持分のみで処理されます。
なお、日本基準ではのれんを定額法で償却しますが、国際会計基準(IFRS)では償却せず、毎期減損テストを実施します。この違いに注意が必要です。
また、追加取得により増加した親会社持分は、実際に支払った追加投資額と相殺され、両者の差額は資本剰余金として計上されます。従来は、この差額をのれんあるいは負ののれんとして処理していました。しかし、平成25年の会計基準改正により、子会社株式の追加取得は「支配株主と非支配株主との間の資本取引」と位置付けられるようになりました。その結果、追加取得に伴う差額はのれんではなく資本剰余金に計上する方法に改められています。
この処理により、連結財務諸表上の子会社株式の取得に伴う影響は、資本の変動として整理されることになります。
親会社説と経済的単一体説の違いは何か
親会社説では、連結財務諸表はあくまで親会社株主の立場から作成されるものと考えます。この立場では、子会社の資本のうち親会社に帰属しない非支配株主持分は、親会社株主から見れば返済義務のある負債ではないものの、株主資本ともいえない中間的な位置付けです。そのため、かつての会計基準では非支配株主持分(当時の呼称は少数株主持分)は「負債の部と資本の部の間」に独立して表示されていました。
一方で経済的単一体説では、連結財務諸表は企業集団全体を一つの経済主体とみなし、その成果や財政状態を全ての株主(親会社株主と非支配株主)に帰属させるべきだと考えます。この理論に立てば、非支配株主持分も子会社の正当な所有者である株主に帰属する資本の一部であり、株主資本の中に含めて表示することが自然だといえます。
現行の日本会計基準では、この二つの考え方の折衷に近い形が採られています。すなわち、非支配株主持分は返済義務を負う負債には該当せず、また親会社株主に帰属する株主資本とも異なるため、「純資産の部」において株主資本とは区分して表示されます。これにより、親会社株主と非支配株主の持分が明確に区分されつつ、企業グループ全体の財務実態を適切に示せるようになっています。
未実現利益(未実現損益)とは何か
未実現利益とは、企業グループ内部で行われた取引において計上された利益のうち、グループ外部への販売や処分がまだ行われていないため、グループ全体の視点では実際に獲得していない利益を指します。
例えば、親会社が子会社に商品を販売し、その商品がまだ外部顧客に販売されていない場合、親会社には売り上げと利益が計上されますが、連結グループ全体としては在庫を内部に移動させただけであり、外部からの収益は生じていません。このような利益は「未実現利益」とされます。
連結財務諸表は、グループ全体を一つの経済主体とみなして作成されます。そのため、内部取引によって発生した未実現利益を残したままでは、売り上げや利益が過大に表示されてしまい、実態を正しく反映できません。そこで、棚卸資産や固定資産に含まれる未実現利益は、連結修正仕訳で消去されます。そして、その資産がグループ外に販売される、あるいは償却・処分される時点で、初めてグループ全体として実現利益が認識されます。
「アップストリーム」「ダウンストリーム」とは何か
未実現利益の消去は、取引の方向によって「アップストリーム取引」と「ダウンストリーム取引」に分けられます。
アップストリーム取引とは、子会社から親会社への販売を指し、この場合の未実現利益は親会社と非支配株主持分の両方に配分して調整されます。ダウンストリーム取引とは、親会社から子会社への販売を意味し、親会社の株主に帰属する利益に対してのみ修正が行われます。この区別は、どの株主が未実現利益の影響を受けるのかを明確にするために重要です。
未実現利益の消去は、親会社株主だけでなく非支配株主に帰属する利益にも影響します。アップストリーム取引では、子会社が親会社に販売して計上した利益のうち未実現部分は、非支配株主持分に帰属する当期純利益からも減額する必要があります。これは、連結財務諸表が企業グループ全体の成果を外部株主に正しく示すための調整であり、親会社持分と非支配株主持分のいずれも、公平な形で未実現利益の影響を反映させる必要があるからです。
なぜ、税効果会計が必要か
親会社が子会社に棚卸資産を販売した場合、個別財務諸表では通常の販売として利益を計上し、その利益に対応する法人税等も課税されます。しかし、連結財務諸表の観点では、この取引はグループ内部での移動に過ぎないため、当該利益は未実現利益として消去されます。
もし、税効果を考慮せずに処理すると、利益は消去されたのに税金だけが残り、連結上の利益が過少に表示されてしまいます。この不整合を解消するため、連結会計では個別で計上された税金を将来に繰り延べる形で税効果会計の仕訳を行い、損益と税金の対応を整える必要があります。
まとめ
非支配株主持分についての理解が深まったでしょうか。この概念は、企業の財務状況を正確に把握するために重要です。特に、複数の企業が絡む連結決算やM&Aの場面では、非支配株主持分の理解が欠かせません。本記事を通じて、なぜ非支配株主持分が純資産として扱われるのか、またどのような影響を与えるのかが明確になったのではないでしょうか。
もしさらに詳しく知りたい方は、実際の決算書を見てみることや、専門家に相談するのも良いでしょう。理解を深めることで、企業の財務戦略や投資判断に役立てることができます。これを機に、非支配株主持分を含む企業会計の知識をさらに広げ、実務にお役立てください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。