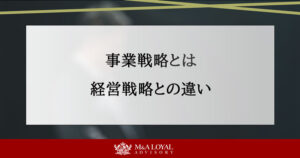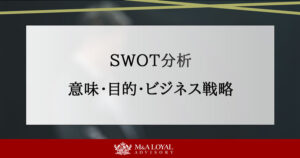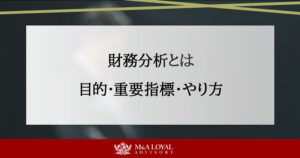新規事業におすすめのフレームワーク37選!使用する順番で徹底紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
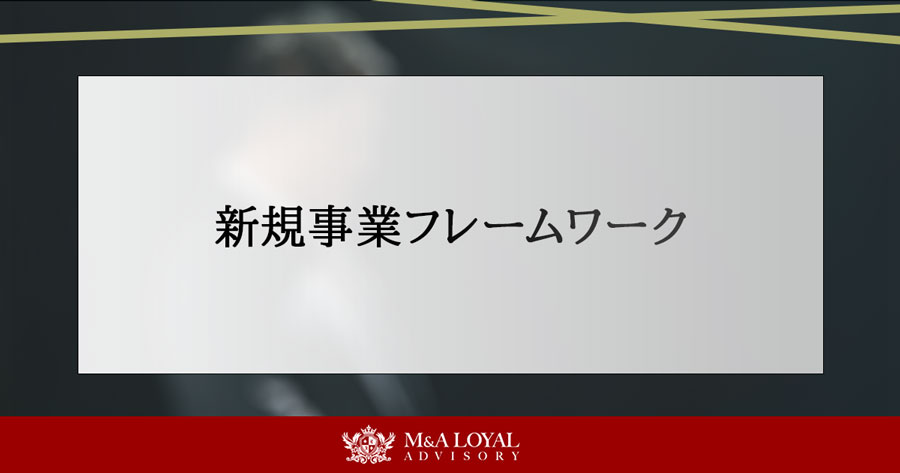
フレームワークは複雑な課題や状況を整理し、効果的に意思決定を進めるための枠組みです。ビジネスやITにおいて広く用いられ、戦略策定から実務まで幅広く役立ちます。
新規事業においては、アイデア発想や市場調査、事業構築、改善、戦略立案など、あらゆる局面でフレームワークが活用可能です。体系的に思考を整理し、意思決定の質や効率性を高める効果があるため、新規事業には適しています。
一方で、形式主義に陥ると柔軟な発想を妨げるため、適切な理解と応用が重要です。本記事では、新規事業に役立つ代表的なフレームワークと活用上の注意点を紹介します。
目次
フレームワークとは
まず、フレームワークに関する基本的な知識について解説します。
フレームワークの意味
ビジネスにおけるフレームワークとは、課題解決や意思決定、戦略立案を効率的かつ体系的に行うための思考の枠組みや手法を指します。複雑な状況を整理し、重要な要素を見極めるための道具として用いられます。
代表的なものには、SWOT分析や3C分析、PDCAサイクルなどがあり、状況把握から改善まで一貫したプロセスを支援します。これにより、属人的な判断を避け、客観的かつ再現性の高い結論を導きやすくなります。
また、フレームワークはチーム間で共通言語として機能し、認識のずれを防ぎます。限られた時間や資源を有効に使い、合理的に意思決定を進めるための指針として、ビジネス現場で広く活用されています。
スキームとの違い
スキームは、ビジネスにおいて事業や施策を実際に進めるための具体的な計画や仕組みを意味します。例えば資金調達スキームや販売スキームなどがあり、目的を実現するための手順や流れを明確にします。
これに対してフレームワークは、考え方や分析のための型を提供し、意思決定や戦略立案の精度を高める役割を果たします。実務そのものではなく、思考を整理する道具として機能します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



新規事業にフレームワークが有効な理由
新規事業にフレームワークが有効な理由として、次の点が挙げられます。
- 思考を整理できる
- コミュニケーションを円滑化する
- 学習と改善を促進する
それぞれを解説します。
思考を整理できる
新規事業の検討では、市場要因や競合状況、顧客ニーズといった多様な情報が複雑に絡み合い、思考が散漫になりがちです。そこでフレームワークを活用することで、情報を整理し、全体像を体系的に把握できます。
論点を抜け漏れなく、かつ重複なく分解することで重要な視点を見逃さず、検討の効率と精度を高められる点が大きな強みです。
さらに、基準を持って選択肢を比較できるため、属人的な判断に偏らず論理的な意思決定が可能です。
コミュニケーションを円滑化する
新規事業では多様な立場の関係者が関与するため、認識のずれが生じやすいです。フレームワークを活用すれば、共通の枠組みがあることで関係者間の理解がそろいやすくなります。
また、抽象的な概念も可視化され、議論が進めやすくなる点も有効です。言葉だけでは曖昧になりがちなアイデアや課題を整理し、具体的に共有できるため、建設的な議論が可能です。
学習と改善を促進する
新規事業では試行錯誤を繰り返す中で、多くの成功や失敗が生じます。フレームワークを用いれば、成果や失敗をフレームワーク上で振り返ることで学びを蓄積でき、経験を組織知へと変えられます。
さらに、その知見は他の場面や新しい課題にも転用しやすい点が特徴です。同じ枠組みに当てはめることで、異なる状況でも一貫した検討が可能となり、学習効果が広がります。
新規事業に役立つフレームワーク【アイデア出し】
新規事業を立ち上げる際に、そのアイディア出しのために役立つフレームワークとして次の方法があります。
- オズボーンのチェックリスト
- マンダラート
- SCAMPER法
- 5W1H
- 6W3H
- リーンキャンバス
- 9セルフレームワーク
- ビジネスモデルキャンバス
- 強制連想法
- KJ法
それぞれを分かりやすく解説します。
オズボーンのチェックリスト
オズボーンのチェックリストは、新規事業のアイデア出しに活用できる発想支援のフレームワークです。「用途転用」「応用」「変更」「拡大」「縮小」「代用」「置換」「逆転」「結合」の九つの視点から対象を捉え直し、新しい発想を促します。
この方法を使うと、思いつきに頼るのではなく、多面的な切り口で体系的にアイデアを広げられます。特に行き詰まりや偏りを解消し、多様な可能性を網羅できる点が大きな強みです。
マンダラート
マンダラートは、発想を広げるためのフレームワークで、3×3のマス目を活用してアイデアを展開する手法です。中央にテーマを置き、その周囲に関連する要素やキーワードを記入していきます。
さらに、周囲に書いた要素を新たな中心に据えて再び展開することで、思考が連鎖的に広がります。直感的に発想できるため、特別な知識やスキルがなくても誰でも取り組める点が特徴です。
新規事業においては、漠然としたテーマから多様なアイデアを効率的に生み出せる点で有効です。網羅的に検討しつつ、隠れた着想を引き出すことで、革新的な発想につなげられます。
SCAMPER法
SCAMPER法は、既存の製品やサービスを基に新しい発想を生み出すフレームワークです。名前は七つの視点「Substitute(代替)」「Combine(結合)」「Adapt(応用)」「Modify(修正)」「Put to other uses(転用)」「Eliminate(削除)」「Reverse(逆転)」の頭文字から構成されます。
これらの視点を順番に当てはめることで、発想を広げるための具体的な問いかけが得られます。思考が停滞した際にも、体系的にアイデアを探索でき、偶発的な発見を促す点が特徴です。
5W1H
5W1Hは、物事を整理し発想を広げるための基本的なフレームワークで、「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の六つの観点で検討を行います。
この枠組みを使うことで、アイデアを多角的に掘り下げられるだけでなく、検討の抜け漏れを防げます。特に新規事業では曖昧になりやすい前提条件を明確化し、論点を整理する助けとなります。
6W3H
6W3Hは、基本となる5W1Hを拡張したフレームワークです。従来の「Who・What・When・Where・Why・How」に加え、「Whom(誰に)」「How much(いくらで)」「How many(どれくらい)」を取り入れています。
この追加により、対象顧客や提供価値の受け手を明確化できるだけでなく、コストや数量といった実行に直結する要素まで検討可能です。より現実的で具体性の高いアイデア出しを支援します。
9セルフレームワーク
9セルフレームワークは、新規事業のビジネスモデルを整理するための思考法で、事業の構成要素を九つに分けて検討します。これにより複雑な構想をシンプルに分解し、全体像を可視化できます。
具体的には「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「顧客関係」「収益の流れ」「主要リソース」「主要活動」「主要パートナー」「コスト構造」の九項目を整理します。網羅的に検討できるため抜け漏れを防ぎます。
ビジネスモデルキャンバス
ビジネスモデルキャンバスは、9セルフレームワークと同様に事業を九つの要素に分けて整理するフレームワークです。ただし、視覚的に一枚のキャンバスに描き出す形式を採用しており、全体の関係性を直感的に理解できる点に特徴があります。
「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「顧客関係」「収益の流れ」「主要リソース」「主要活動」「主要パートナー」「コスト構造」の九要素をキャンバス上に配置し、相互のつながりを見える化します。
つまりビジネスモデルキャンバスは、9セルフレームワークをさらに実用的に進化させたツールといえます。
リーンキャンバス
リーンキャンバスは、新規事業のビジネスモデルを簡潔に整理するためのフレームワークです。一枚のシートに「課題」「顧客セグメント」「独自の価値提案」「ソリューション」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」「圧倒的な優位性」の九つの要素を記入して検討します。
これにより、複雑になりがちな事業構想をシンプルに可視化でき、重要な前提や仮説を明確に整理できます。特に初期段階では、仮説検証を繰り返すことで方向性を柔軟に調整できる点が特徴です。
リーンキャンバスはビジネスモデルキャンバスをスタートアップ(ITベンチャー)向けにアップデートしたものといえます。
強制連想法
強制連想法は、通常は結びつかない要素を意図的に組み合わせ、新しい発想を得るためのフレームワークです。無関係に見える対象を関連付けることで、固定観念を崩し斬新なアイデアを生み出します。
具体的には、ランダムに選んだ言葉やモノをテーマと関連付けて考えます。思考の枠を越える問いを投げかけることで、従来の延長線上では得られないユニークな発想が促されます。
KJ法
KJ法は、多様な情報や意見を整理し、新しいアイデアや方向性を導き出すためのフレームワークです。考えや事実をカードや付箋に書き出し、意味の近いものをグループ化していく手法を取ります。
グループをさらに統合・整理することで、情報の関係性や全体構造が明確になり、潜在的なテーマや新しい発想が浮かび上がります。複雑で散らばった情報を整理できる点が特徴です。
新規事業に役立つフレームワーク【市場調査・参入】
新規事業を立ち上げる際に、市場調査、参入のために役立つフレームワークとして次の方法があります。
- STP分析
- 3C分析
- PEST分析
- VRIO分析
- アドバンテージマトリクス
- SWOT分析
- クロスSWOT分析
- ファイブフォース
- TAM・SAM・SOM
- POD・POP・POF
それぞれを分かりやすく解説します。
STP分析
STP分析は、新規事業の市場戦略を考える際に用いられるフレームワークで、「Segmentation(市場細分化)」「Targeting(標的市場の選定)」「Positioning(自社の立ち位置の明確化)」の三段階で構成されます。
まず市場を属性やニーズごとに分け、次に最も有望なターゲットを選定します。そして競合との差別化を意識しながら、自社が提供する価値をどのように位置付けるかを検討します。
STP分析は、誰にどのような価値を届けるのかを明確にする仕組みといえます。
3C分析
3C分析は、市場環境を把握し戦略を立てるための基本的なフレームワークで、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の三つの視点から検討を行います。
顧客のニーズや市場規模を分析し、競合の強み・弱みを把握した上で、自社の資源や能力を整理します。これにより、自社が優位に立てるポジションを見つけやすくなります。
3C分析は、外部環境と内部資源をバランスよく評価し、参入戦略の方向性を導く枠組みです。
PEST分析
PEST分析は、マクロ環境を把握するためのフレームワークで、「Politics(政治・法規制)」「Economy(経済動向)」「Society(社会・文化)」「Technology(技術革新)」の四つの視点から外部環境を整理します。
これにより、自社の努力では変えられない外部要因が新規事業に与える影響を明確化できます。機会となる要素やリスク要因を早期に把握することで、戦略立案に現実性と説得力を持たせられます。
PEST分析は、事業を取り巻く大きな流れを捉える仕組みです。
VRIO分析
VRIO分析は、自社の経営資源や強みを評価し、競争優位性を見極めるためのフレームワークです。四つの観点「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Imitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」で資源を分析します。
例えば、顧客に価値を提供できるか、他社にはない希少な資源か、模倣されにくい仕組みか、そして活用できる組織体制があるかを検討します。これにより、強みが持続的競争優位につながるかを判断できます。
VRIO分析は、自社の資源を戦略的に生かすためのフレームワークです。
アドバンテージマトリクス
アドバンテージマトリクスは、事業の競争優位の源泉を整理し、適切な戦略を検討するためのフレームワークです。「持続期間の長さ」と「競争優位の種類」の二軸で分類し、事業の位置付けを明確化します。
具体的には、差別化やコスト優位などの優位性が短期的か長期的かを評価します。これにより、一時的な優位に依存するのか、模倣されにくい強みで長期的に勝負できるのかを見極められます。
SWOT分析
SWOT分析は、事業環境を整理し戦略の方向性を導くためのフレームワークです。内部環境の「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」と、外部環境の「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」の四つを検討します。
これにより、自社が持つ資源や能力を把握しつつ、市場や競合の動向を踏まえた戦略立案が可能です。強みをどう生かし、弱みや脅威をどう補うかを体系的に考えられる点が特徴です。
クロスSWOT分析
クロスSWOT分析は、SWOT分析で整理した「強み・弱み・機会・脅威」を掛け合わせ、具体的な戦略を導くためのフレームワークです。単なる要素整理にとどまらず、行動指針を導き出せる点が特徴です。
具体的には「強み×機会」で積極的に生かす戦略、「強み×脅威」でリスクを回避する戦略、「弱み×機会」で改善を通じた成長戦略、「弱み×脅威」で最悪事態を避ける戦略を検討します。
クロスSWOT分析は、SWOTを実際の施策に落とし込むための応用手法です。
ファイブフォース
ファイブフォース分析は、業界の競争環境を評価するためのフレームワークで、SWOT分析よりも外部要因を詳細に捉えられる点が特徴です。市場参入の魅力度や収益性を見極める際に有効です。
具体的には「既存競合の敵対関係」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」という五つの力を分析し、業界の競争圧力を体系的に整理します。ファイブフォース分析は、競争の強さを定性的に理解するための仕組みです。
TAM・SAM・SOM
TAM・SAM・SOMは、新規事業の市場規模を段階的に把握するためのフレームワークです。市場の可能性を数値で整理することで、事業の魅力度や成長余地を客観的に評価できます。
TAM(Total Addressable Market)は理論上の最大市場規模、SAM(Serviceable Available Market)は自社のビジネスモデルで狙える範囲、SOM(Serviceable Obtainable Market)は実際に獲得可能な現実的市場を指します。
TAM・SAM・SOMは、アイデアを机上の空論にせず、市場性を裏付けるフレームワークです。
POD・POP・POF
POD・POP・POFは、市場における自社の立ち位置を整理するためのフレームワークです。競合との差別化要因や共通点、さらに避けるべき要素を明確にすることで、ブランドや事業の戦略を磨き上げます。
POD(Point of Difference)は競合にはない独自の強み、POP(Point of Parity)は競合と同等である必要のある基準、POF(Point of Failure)は満たしていないと選ばれない致命的な弱点を指します。
POD・POP・POFは、差別化と標準化、リスク回避のバランスを取るための枠組みです。
新規事業に役立つフレームワーク【事業構築・顧客理解】
新規事業を立ち上げる際に、事業構築・顧客理解のために役立つフレームワークとして次の方法があります。
- ペルソナ
- カスタマージャーニー
- 4C分析
- 4P・7P分析
- ビジネスモデルキャンバス
- AISAS
- AARRR
- バリュープロポジション
- サービスブループリント
それぞれを分かりやすく解説します。
ペルソナ
市場調査段階のペルソナ分析が「狙う顧客層を明確にする」ことを目的とするのに対し、事業構築段階のペルソナは「顧客体験を具体的に設計する」ために活用されます。
詳細なプロフィールに加えて、行動パターンや課題、利用シーンを描き出すことで、サービス設計やUI/UXの検討に直結します。顧客の視点から一貫性ある体験を構築できる点が特徴です。
つまりペルソナは、調査から構築へと役割をシフトし、事業全体を顧客中心に進めるための核となります。新規事業においては、アイデアを実際の顧客価値に結びつける重要なフレームワークです。
カスタマージャーニー
カスタマージャーニーは、顧客が商品やサービスを認知し、購入・利用し、継続するまでの一連の体験プロセスを可視化するフレームワークです。顧客の行動や感情を時系列で整理します。
接点ごとに顧客が抱く期待や不満を把握することで、改善すべき課題や新たな価値提供の機会を発見できます。ペルソナで設定した顧客像をより具体的な体験に落とし込む点が特徴です。
つまりカスタマージャーニーは、事業を顧客視点で設計するための枠組みです。新規事業においては、顧客満足を高め、長期的な関係を築く戦略立案に役立ちます。
4C分析
4C分析は、顧客視点で事業を設計するためのフレームワークです。「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客負担)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の四つの要素から検討します。
これは従来の4P分析を企業視点から顧客視点に置き換えたものであり、顧客にとってのメリットや体験を中心に事業を考えられる点が特徴です。新規事業における価値提案の明確化に有効です。
つまり4C分析は、顧客理解を深めることで事業の方向性を最適化する仕組みです。新規事業においては、顧客の期待に即した製品・サービス設計を実現する重要なフレームワークです。
4P・7P分析
4P分析は、企業視点でマーケティング戦略を整理するフレームワークで、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の四つを軸に事業を設計します。
さらにサービス業を中心に発展した7P分析では、「People(人材)」「Process(プロセス)」「Physical Evidence(物的証拠)」の三要素を加え、顧客体験全体を包括的に検討します。
4P・7P分析は、提供価値をどのように市場に届けるかを体系的に考える仕組みです。新規事業においては、戦略の具体化や実行プランの策定に役立つ重要なフレームワークです。
AISAS
AISASは、インターネット時代の消費者行動を説明するフレームワークで、「Attention(注意)」「Interest(関心)」「Search(検索)」「Action(行動)」「Share(共有)」の五段階で構成されます。
従来の購買行動モデルに検索と共有を加えることで、デジタル環境における顧客行動をより現実的に捉えられます。特にSNSや口コミが購買に影響する現代に適した枠組みです。
AISASは、顧客が情報に触れてから行動・拡散するまでの流れを理解する仕組みです。新規事業においては、効果的な顧客接点の設計やマーケティング戦略に役立ちます。
AARRR
AARRRは、スタートアップの成長を測定・改善するためのフレームワークで、「Acquisition(獲得)」「Activation(利用開始)」「Retention(継続利用)」「Referral(紹介)」「Revenue(収益)」の五段階から構成されます。
顧客がサービスを知り、使い始め、定着し、他者に広め、収益へとつながる流れを整理できるため、課題がどの段階にあるのかを明確化できます。数値指標と組み合わせやすい点も特徴です。
AARRRは、顧客体験のライフサイクルを定量的に管理する仕組みです。新規事業においては、成長のボトルネックを特定し、改善を繰り返すことで持続的な成長を実現する有効な手法です。
バリュープロポジション
バリュープロポジションは、顧客に提供する価値を明確化するためのフレームワークです。自社の製品やサービスが「誰の」「どんな課題を」「どのように解決するのか」を整理し、差別化要素を打ち出します。
顧客のニーズやペインポイントを起点に、自社の強みや独自性を結びつけることで、他社との違いを明確にできます。これにより、顧客が選ぶ理由を一言で伝えられます。
つまりバリュープロポジションは、新規事業における価値提案の核を定義する仕組みです。顧客理解を踏まえた明確なメッセージを構築することで、戦略やマーケティング全体の方向性をそろえられます。
サービスブループリント
サービスブループリントは、サービス提供の流れを顧客体験と内部プロセスの両面から可視化するフレームワークです。顧客行動、フロント業務、バックエンド業務を一枚の図で整理します。
これにより、顧客がどの場面で価値を感じ、どこに不満を抱くかを把握できるだけでなく、裏側の業務や仕組みとのつながりも明確になります。サービス全体の改善点を発見しやすい点が特徴です。
サービスブループリントは、顧客中心の視点と業務設計を統合する枠組みです。新規事業においては、体験価値を高めながら効率的な運営を実現するための有効なフレームワークです。
新規事業に役立つフレームワーク【事業改善】
新規事業を立ち上げる際に、事業改善のために役立つフレームワークとして次の方法があります。
- PDCA
- PLC
- ECRS
- バリューチェーン分析
- RFM分析
それぞれを分かりやすく解説します。
PDCA
PDCAは、業務やプロジェクトを継続的に改善するためのフレームワークで、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Act(改善)」の四段階を循環させる仕組みです。
計画を立て、実行し、結果を評価し、改善につなげるサイクルを繰り返すことで、試行錯誤を体系的に進められます。小さな改善を積み重ねることで、大きな成果へと発展させられる点が特徴です。
PDCAは、学びを行動に結びつけ、組織に定着させる仕組みです。新規事業においては、不確実性の高い環境で柔軟に方向修正し、成長を持続させるための基本フレームワークです。
PLC
PLC(Product Life Cycle)は、製品やサービスが市場に投入されてから衰退するまでの流れを「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の四段階で捉えるフレームワークです。各段階で戦略の重点が異なります。
導入期は認知拡大と初期顧客獲得、成長期は市場シェア拡大、成熟期は差別化や効率化、衰退期は撤退や再投資判断が重要です。時期ごとの課題を整理できる点が特徴です。
PLCは、事業や製品の寿命を見据えて最適な打ち手を考える思考法です。新規事業においては、市場投入後の成長管理や改善の指針として活用できる有効なフレームワークです。
ECRS
ECRSは、業務改善を進めるための基本原則を示したフレームワークで、「Eliminate(排除)」「Combine(統合)」「Rearrange(順序変更)」「Simplify(簡素化)」の四つの視点で検討します。
無駄な作業をなくし、関連作業をまとめ、手順を見直し、仕組みを簡単にすることで、効率性と生産性を高められます。誰でも使いやすく、現場レベルの改善から経営戦略まで幅広く活用可能です。
ECRSは、改善の着眼点を明確にすることで行動に直結させる仕組みです。新規事業においては、限られた資源を有効に使い、スピード感のある成長を支える重要なフレームワークです。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業活動を「価値を生み出すプロセス」として分解し、競争優位の源泉を明らかにするフレームワークです。
活動は「購買物流・製造・出荷物流・販売・サービス」といった主活動と、「人事・技術開発・調達」などの支援活動に分けられます。各段階がどのように価値を生み、コストに影響しているかを整理します。
バリューチェーン分析は、強みと弱みを事業プロセスごとに可視化する仕組みです。新規事業においては、どこで差別化できるか、改善や投資の重点領域を明確にするために有効です。
RFM分析
RFM分析は、顧客を購買行動に基づいて分類し、優先的にアプローチすべき層を特定するフレームワークです。Rは「Recency(最新購買日)」、Fは「Frequency(購買頻度)」、Mは「Monetary(購買金額)」を指します。
顧客をこれら三つの指標で評価することで、ロイヤル顧客や離反リスクの高い顧客などを見分けられます。マーケティング施策を最適化し、効率的に収益を高められる点が特徴です。
RFM分析は、顧客データを活用して関係性を強化する仕組みです。新規事業においては、限られた資源を効果的に投入し、成長のスピードを高めるために有効なフレームワークです。
新規事業に役立つフレームワーク【事業戦略・計画】
新規事業を立ち上げる際に、事業戦略、計画立案のために役立つフレームワークとして次の方法があります。
- アンゾフの成長マトリクス
- ピラミッドストラクチャー
- MVV
- エレベーターピッチ
それぞれを分かりやすく解説します。
アンゾフの成長マトリクス
アンゾフの成長マトリクスは、事業の成長方向性を検討するためのフレームワークです。「製品」と「市場」を軸に、既存か新規かの組み合わせで四つの戦略を示します。
具体的には「市場浸透(既存製品×既存市場)」「新市場開拓(既存製品×新市場)」「新製品開発(新製品×既存市場)」「多角化(新製品×新市場)」の四類型に整理されます。
つまりアンゾフの成長マトリクスは、リスクと成長のバランスを可視化する仕組みです。新規事業においては、どの方向性で成長を目指すかを明確にし、戦略立案を支援する有効なツールです。
ピラミッドストラクチャー
ピラミッドストラクチャーは、情報や主張を階層的に整理するフレームワークです。結論を頂点に置き、その根拠や具体例を下位に配置することで、論理の流れを明確にします。
これにより、複雑な情報も一目で理解しやすくなり、説得力のある戦略立案やプレゼンテーションを可能にします。特に新規事業では、多様な関係者に短時間で納得感を与えるのに有効です。
つまりピラミッドストラクチャーは、思考を整理し伝達力を高める仕組みです。新規事業においては、意思決定を効率化し、計画を実行可能な形に落とし込む重要なフレームワークです。
MVV
MVVは、組織や事業の根幹を定義するフレームワークで、「Mission(存在意義)」「Vision(将来像)」「Value(価値観・行動指針)」の三要素で構成されます。
Missionはなぜ事業を行うのかを示し、Visionは将来どうなりたいかを描き、Valueは日々の判断基準や行動様式を定めます。この三つを明確にすることで、一貫性ある戦略と組織文化を形成できます。
MVVは、方向性と判断基準を共有するための土台です。新規事業においては、関係者の意識をそろえ、迷いなく行動できる組織づくりを支える重要なフレームワークです。
エレベーターピッチ
エレベーターピッチは、短時間で事業やアイデアの魅力を伝えるためのフレームワークです。名前の由来は「エレベーターに乗る短い時間で説明する」ことから来ています。
限られた時間で相手の関心を引くために、解決する課題や提供価値、ターゲット、独自性などを簡潔にまとめます。特に投資家や経営層との対話で活用されることが多い手法です。
つまりエレベーターピッチは、アイデアを端的に表現する訓練であり、新規事業においては、支援者や協力者を獲得するための重要なコミュニケーション手段です。
新規事業にフレームワークを活用する際の注意点
新規事業にフレームワークを活用する際には次の注意点があります。
- 形式にとらわれてしまう
- 使うデータが不正確
- 表面的な理解しかしていない
- 適用範囲を間違える
- 実行と乖離(かいり)がある
それぞれを詳しく解説します。
形式にとらわれてしまう
新規事業にフレームワークを活用する際には、形式主義と硬直化に注意が必要です。
枠組みに当てはめること自体が目的化すると、実際の状況との乖離(かいり)が生じてしまいます。また、フレームに収まりきらない要素を軽視してしまうと、環境変化に柔軟に対応できなくなり、結果的に事業の可能性を狭めるリスクがあります。
そのため、フレームワークはあくまで思考を整理するための手段と捉え、現実の変化や例外的な要素を見落とさない姿勢が大切です。
使うデータが不正確
フレームワークは情報を整理しやすくしますが、入力するデータが不正確であれば、どんな枠組みを使っても誤った結論に導かれる危険があります。前提が誤れば戦略全体が揺らぎます。
また、定性的な要素を無理に数値化することで、本質をゆがめてしまうリスクもあります。数字に依存しすぎると、顧客心理や市場の文脈といった重要な要素を見落とす可能性があります。
つまりフレームワークを使う際には、データの正確性と解釈のバランスが不可欠です。新規事業では、数値と直感を組み合わせ、本質を捉えた判断を下すことが重要です。
表面的な理解しかしていない
フレームワークは整理の道具にすぎず、キーワードや図だけが共有されても本質的な議論が深まらないことがあります。形だけ整っていても、背景や意図が理解されなければ意味を持ちません。
また、フレームワークを使っただけで「検討が進んだ」と錯覚し、実際の戦略や行動に結び付かないケースも少なくありません。表面的な利用では施策に具体性が欠け、成果につながりにくいのです。
つまり重要なのは、枠組みを適切に使いこなし、実際の意思決定や行動に落とし込むことです。
適用範囲を間違える
フレームワークにはそれぞれ想定された前提や意図があります。これを無視して別の課題に安易に流用すると、状況に合わない分析結果となり、誤った結論に導かれる危険があります。
また、一つのフレームワークに万能性を期待してしまうことも誤解の一つです。実際には対象や目的に応じて使い分ける必要があり、単独で全ての問題を解決できるものではありません。
適用範囲を正しく理解し、状況に応じて選択・組み合わせることが重要です。新規事業においては、柔軟な視点で活用しなければ、かえって意思決定を誤るリスクが高まります。
実行と乖離(かいり)がある
フレームワークは思考を整理する強力なツールですが、分析や計画に偏りすぎると行動が遅れ、競争環境の変化に対応できなくなる危険があります。スピードが求められる新規事業では致命的です。
また、検討内容を実務に落とし込めず、形だけ整えて形骸化して終わるケースも少なくありません。机上の戦略にとどまれば、現場の動きや成果には結びつきません。
つまり重要なのは、フレームワークを実行と一体で運用することです。新規事業においては、分析から行動への橋渡しを意識し、実践で検証しながら改善を繰り返す姿勢が欠かせません。
まとめ
新規事業を成功させるためには、しっかりとした計画と戦略が必要です。そこでフレームワークを活用することで、複雑な状況を整理し、意思決定をスムーズに進めることができます。記事で紹介したさまざまなフレームワークは、アイデアの発想から市場調査、事業構築、改善、戦略立案まで幅広い場面で役立ちます。重要なのは、フレームワークに頼りすぎず、柔軟な発想を持ち続けること。次に新規事業を考える際は、ぜひこれらのフレームワークを試してみてください。そして、実際に使ってみて、どのフレームワークが自分のプロジェクトに最も適しているかを見極めましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。