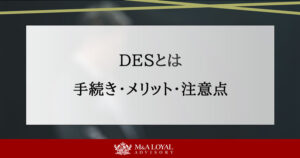零細企業とは?定義や中小企業との違い、M&Aのポイントと注意点
着手金・中間金無料 完全成功報酬型

零細企業とは、従業員数や売上高が非常に少ない規模の企業を指します。日本の企業の84.5%が零細企業であり、地域経済を支える重要な存在です。しかし、零細企業を経営しているオーナーの多くは、「自社のような小規模な会社でも本当にM&Aができるのだろうか」といった疑問を抱いています。
本記事では、零細企業の明確な定義や中小企業との違いを解説した上で、M&Aを成功させるための具体的なポイントや注意点について詳しく説明します。後継者不在や個人保証の問題に悩む経営者にとって、次のステップを踏み出すための判断材料となる情報をお届けします。
目次
零細企業とは?定義と基準を簡単に解説
零細企業という言葉は日常的に使われていますが、言葉の意味を正確に理解している方は少ないものです。まずは零細企業の正確な定義と、日本経済においてどのような位置を占めているのかを確認していきましょう。
法的定義と従業員数の基準
零細企業には法律上の独立した定義は存在せず、中小企業基本法における「小規模企業者」に該当する企業を一般的に零細企業と呼んでいます。小規模企業者の基準は業種により異なります。製造業・建設業・運輸業では従業員20人以下、卸売業・サービス業・小売業では従業員5人以下と定められています。(宿泊業・娯楽業は例外的に20人以下)この基準は常時使用する従業員数で判断され、パートやアルバイトも含まれます。
従業員数の基準は、社長を含めた全従業員数ではなく、役員を除いた従業員数で判断されます。例えば、社長と役員2名、従業員18名という構成であれば、従業員数は18名となり零細企業に該当します。一方、サービス業や小売業では5人以下という基準のため、より小規模な企業が対象となります。
この基準に該当する企業は日本全体で約285万3,000社であり、全企業数の84.5%を占めています。つまり、日本経済を支える企業の大多数が零細企業であり、特殊な存在ではありません。地域の雇用を守り、地域経済を支える重要な役割を担っているのが零細企業なのです。
零細企業と中小企業の違いを比較
零細企業と中小企業の関係を正しく理解することは、自社の位置づけを把握する上で重要です。中小企業は中小企業基本法によって定義されており、業種ごとに資本金と従業員数の基準が設けられています。零細企業は中小企業の中に含まれる、より小規模な企業群を指す概念です。
中小企業の定義を見ると、製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5,000万円以下または従業員50人以下となっています。これらの基準を満たす企業が中小企業であり、その中でも特に小規模な企業が零細企業と呼ばれています。
| 企業区分 | 製造業等の基準 | 小売業の基準 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 資本金3億円超かつ従業員301人以上 | 資本金5,000万円超かつ従業員51人以上 | 約1万364社 |
| 中小企業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 | 約336万5,000社 |
| 零細企業 | 従業員20人以下 | 従業員5人以下 | 約285万3,000社 |
上記の表からわかるように、日本企業の99.7%が中小企業であり、そのうち84.5%が零細企業です。零細企業は日本経済の主流を成す企業形態であり、地域密着型ビジネスや専門的な技術を持つ企業として、経済活動に重要な役割を担っています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



零細企業におけるM&Aの実態と可能性
零細企業のオーナー様から「こんな小さな会社を買いたいと思う企業があるのだろうか」というご相談をよくいただきます。しかし、実際には零細企業のM&Aは活発に行われており、多くの成功事例が存在します。ここでは零細企業のM&A実態と、なぜ買い手企業が関心を持つのかを解説します。
M&A実施状況と市場動向
近年、小規模M&Aの件数が増加しています。中小企業庁の調査によれば、後継者不在の経営者は約127万人にのぼり、そのうち多くが零細企業です。一方で、事業拡大や新規参入を目指す企業にとって、既存の顧客基盤や技術、人材を持つ零細企業の買収は効率的な成長戦略となっています。
特に、零細企業同士のM&Aや、地域の有力企業による零細企業買収が増えています。大企業による大型M&Aだけでなく、同じ地域で事業を展開する企業同士が統合することで、規模の経済を実現したり、サービスの幅を広げたりするケースが目立っています。これは零細企業のM&Aが現実的な選択肢として認識されていることを示しています。
また、M&A仲介会社やマッチングプラットフォームの普及により、以前は情報が届きにくかった零細企業のM&A案件も、適切な買い手企業に届くようになりました。これにより、零細企業のオーナー様にとってもM&Aがより身近な選択肢となっています。実際に、従業員数名の企業であっても、独自の技術や顧客基盤を持っていれば、適切な価格で売却できる可能性は十分にあります。
買い手企業が注目する理由
買い手企業が零細企業を買収する理由は多岐にわたります。最も大きな理由は、既存の顧客基盤や取引関係、地域での信頼という目に見えない資産を短期間で獲得できることです。新規に事業を立ち上げる場合、顧客を獲得し信頼を築くまでに数年かかることも珍しくありませんが、M&Aによって既存企業を買収すれば、初日から事業を開始できます。
零細企業ならではの強みとして、以下のような点が買い手企業から評価されます。第一に、地域密着型のビジネスモデルです。長年の地域での営業活動により築かれた信頼関係や顧客ネットワークは、簡単には真似できない競争優位性となります。第二に、特定分野に特化した専門的な技術やノウハウです。このような技術を求める企業にとって、零細企業は魅力的な買収対象となります。
- 地域における確固たる顧客基盤と信頼関係
- 長年培われた専門技術やノウハウ
- 熟練した技術者や従業員の確保
- 新規参入に必要な許認可や資格の取得
- 既存の取引先ネットワーク
特に人材不足が深刻化している現在、熟練した技術者や従業員を雇用している零細企業は高く評価されます。また、許認可が必要な業種では、既に許認可を取得している企業を買収することで、参入障壁を一気に突破できるメリットもあります。これらの理由から、零細企業であっても十分にM&Aの対象となり得るのです。
零細企業M&Aの主要手法
零細企業のM&Aを検討する際には、具体的な手法と価格相場を理解しておくことが重要です。適切な手法を選択し、相場観を持つことで、より有利な条件での売却を実現できます。
株式譲渡と事業譲渡の選択基準
零細企業のM&Aで主に用いられる手法は、株式譲渡と事業譲渡の2つです。株式譲渡は会社の株式を買い手企業に譲渡する方法で、会社そのものが買い手企業の傘下に入る形となります。株式譲渡の最大のメリットは手続きが比較的シンプルであり、会社の資産や従業員との雇用契約、取引先との契約などがそのまま承継されることです。また、売却益に対する税率は所得税と住民税を合わせて約20%と、比較的低い税率が適用されます。
一方、事業譲渡は会社全体ではなく、特定の事業や資産のみを譲渡する方法です。売り手企業にとっては、複数の事業を営んでいる場合に一部の事業のみを売却できる柔軟性があります。また、簿外債務などのリスクを買い手企業に承継させないことができるため、売却後のトラブルを避けやすいというメリットもあります。ただし、個別の資産や契約を移転する必要があり、手続きが煩雑になる点や、消費税が課税される点に注意が必要です。
零細企業の場合、多くのケースで株式譲渡が選択されます。理由としては、会社全体の譲渡により手続きが簡素化されること、従業員の雇用が自動的に承継されること、取引先への説明が容易であることなどが挙げられます。ただし、個人保証や役員借入金の処理、簿外債務のリスクなどについては、事前に十分な確認と対策が必要となります。
売却価格相場と算定方法
零細企業の売却価格は、一般的に時価純資産に営業利益の2年から5年分を加えた金額が相場とされています。時価純資産とは、貸借対照表の純資産を時価評価したもので、帳簿上の価値と実際の価値の差を調整した金額です。営業利益の何年分を加えるかは、業種や収益の安定性、成長性などによって変動します。
具体的な計算例を見てみましょう。時価純資産が1,500万円、年間営業利益が250万円の零細企業の場合、売却価格は以下のように算定されます。
- 下限価格は1,500万円プラス250万円×2年分で2,000万円
- 上限価格は1,500万円プラス250万円×5年分で2,750万円
- 交渉により2,000万円から2,750万円の範囲で決定
実際の売却価格は、この相場をベースに様々な要素を考慮して決定されます。業績が安定しており将来性がある場合は高い倍率が適用され、逆に業績が不安定な場合は低い倍率となります。また、独自の技術や特許、固定客の存在、優秀な人材の確保状況なども価格に影響を与えます。
零細企業特有の評価ポイントとして、経営者への依存度も重要な要素です。経営者がいなくても事業が継続できる体制が整っている企業は高く評価される一方、経営者のスキルや人脈に強く依存している場合は、買収後のリスクとして価格が低くなる傾向があります。そのため、M&Aを検討する段階で、業務の標準化や従業員への権限委譲を進めておくことが、より高い価格での売却につながります。
零細企業M&Aのメリット
零細企業のM&Aには、売り手企業のオーナー様にとって多くのメリットがあります。同時に、成功させるためには押さえるべきポイントもあります。ここでは具体的なメリットと、実際に成功するための実践的なポイントを解説します。
売り手側の5つの主要メリット
零細企業のオーナー様がM&Aを実施することで得られる最も大きなメリットは、後継者不在という深刻な問題を解決できることです。日本の零細企業の半数以上が後継者不在という状況の中で、M&Aは事業を存続させながら経営者としての役割から退く現実的な選択肢となっています。親族や従業員に後継者候補がいない場合でも、買い手企業に経営を引き継ぐことで、長年築いてきた事業を継続させることができます。
第二のメリットは、個人保証からの解放です。多くの零細企業では、銀行借入に対して経営者が個人保証を提供しています。この個人保証は経営者にとって大きな精神的負担となっていますが、M&Aによって会社を売却すれば、買い手企業との交渉次第で個人保証から解放される可能性があります。特に株式譲渡の場合、経営者保証ガイドラインに基づいた交渉により、保証解除の道が開かれます。
第三のメリットは、創業者利益の実現です。長年の努力によって築いてきた企業価値を、適正な価格で売却することにより、まとまった資金を得ることができます。この資金は老後の生活資金として活用できるほか、新たな事業への投資や、家族への資産承継にも使えます。零細企業であっても、独自の強みを持ち業績が安定していれば、数千万円以上の売却価格となることも珍しくありません。
第四のメリットは、従業員の雇用維持と待遇改善です。事業を廃業してしまえば従業員は職を失いますが、M&Aによって事業が継続されれば雇用も維持されます。さらに、買い手企業が大きな資本力を持つ場合、従業員の待遇が改善される可能性もあります。長年支えてくれた従業員に対する責任を果たせることは、経営者にとって大きな安心材料となります。
第五のメリットは、会社基盤の強化による成長機会の提供です。買い手企業の経営資源や販売網、技術力などを活用することで、単独では実現できなかった事業拡大が可能になります。売却後も一定期間経営に関与する場合、自社の事業がさらに発展する様子を見守ることができ、経営者としての達成感を得られることもあります。
成功のための5つの実践ポイント
零細企業のM&Aを成功させるための第一のポイントは、自社の強みを明確にすることです。買い手企業が何を求めているのかを理解し、自社のどの部分が価値を持つのかを客観的に分析します。地域での知名度、リピーターの多さ、専門技術、優秀な従業員など、数字には表れにくい強みも整理しておきましょう。これらの強みを明確に訴求できれば、より高い評価を得られる可能性が高まります。
第二のポイントは、適切なタイミングでM&Aを実施することです。売却に最適なタイミングは、業績が好調で将来性を示せる時期であり、景気が良く買い手企業の買収意欲が高い時期です。業績が悪化してからM&Aを検討すると、価格交渉で不利になるだけでなく、買い手が見つからない可能性もあります。経営者が元気なうちに、前向きな理由でM&Aを実施することが成功の鍵となります。
第三のポイントは、零細企業の案件に強いM&A仲介会社を選ぶことです。大手仲介会社の中には最低報酬額が数千万円に設定されているところもあり、零細企業の案件を扱わないケースがあります。一方、零細企業や小規模M&Aに特化した仲介会社であれば、数百万円から数千万円規模の案件でも対応可能です。手数料体系や最低報酬額、実績などを確認し、自社に合った仲介会社を選びましょう。
第四のポイントは、相場観を持って価格交渉に臨むことです。先述の時価純資産プラス営業利益の2年から5年分という相場を理解したうえで、自社の強みや弱みを考慮して現実的な希望価格を設定します。相場から大きく外れた価格を提示すると、買い手が現れなかったり、交渉が長引いたりする原因となります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な価格設定を行いましょう。
第五のポイントは、早期に専門家へ相談することです。M&Aには税務、法務、財務など多岐にわたる専門知識が必要であり、準備から成約まで通常6ヶ月から1年以上かかります。思い立ったらすぐに相談を開始し、必要な準備を計画的に進めることが重要です。無料相談を実施している仲介会社も多いので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
零細企業M&Aにおける注意点
零細企業のM&Aを成功させるためには、メリットだけでなく注意すべきポイントも十分に理解しておく必要があります。特に零細企業特有の課題については、事前に対策を講じることでトラブルを回避できます。
デューデリジェンスと簿外債務への対応
M&Aのプロセスにおいて、買い手企業が実施するデューデリジェンスは最も重要な段階です。デューデリジェンスとは、買収対象企業の財務状況、法務状況、事業内容などを詳細に調査することで、買収後のリスクを事前に把握するための手続きです。零細企業の場合、財務管理が十分でないケースや、帳簿に記載されていない簿外債務が存在するケースがあるため、デューデリジェンスで問題が発覚すると売却価格の減額や契約破談につながる可能性があります。
簿外債務の典型的な例としては、未払いの残業代、社会保険料の未納、税金の滞納、取引先への未払金、訴訟リスク、環境汚染リスクなどが挙げられます。これらは通常の財務諸表には表れないため、買い手企業が後から発見すると大きな問題となります。売り手企業としては、M&Aを検討し始めた段階で、これらの問題がないか自己点検し、問題があれば早期に解決しておくことが重要です。
デューデリジェンスに備えて準備すべき書類としては、直近3期分の決算書、税務申告書、総勘定元帳、取引先リスト、従業員名簿と雇用契約書、就業規則、許認可証、不動産登記簿、保険証券、主要な契約書などがあります。これらを整理しておくことで、デューデリジェンスがスムーズに進み、買い手企業からの信頼を得ることができます。
情報管理と関係者への説明タイミング
M&Aを進めるうえで最も注意すべきことの一つが情報管理です。M&Aの検討を始めたことが社内や取引先に早期に漏れてしまうと、従業員の不安や取引先の信用不安を招き、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。特に零細企業の場合、経営者と従業員の距離が近いため、情報が漏れやすい環境にあります。
M&Aの情報管理の基本は、知る必要がある人にのみ、必要な段階で情報を開示することです。M&Aの検討初期段階では、経営者と信頼できる顧問税理士や弁護士など、最小限の関係者にのみ共有します。買い手候補との交渉が進み、基本合意が締結された段階で、経営幹部や重要な従業員に説明します。そして、最終契約が締結されて成約が確定した段階で、全従業員や取引先に説明するというのが一般的な流れです。
従業員への説明においては、雇用の継続が保証されていること、待遇に関する方針、今後の事業の方向性などを明確に伝えることが重要です。特に零細企業では経営者と従業員の信頼関係が強い場合が多いため、丁寧な説明と誠実な対応により、従業員の不安を軽減し、M&A後の円滑な事業継続につなげることができます。
取引先への説明も慎重に行う必要があります。M&Aによって取引条件が変わるのか、担当者は変わるのか、会社の方針はどうなるのかなど、取引先が懸念する点について明確に答えられる準備をしておきましょう。可能であれば、買い手企業の担当者と一緒に説明に回ることで、取引先の信頼を維持しやすくなります。
個人保証と役員借入金の処理方法
零細企業の経営者にとって、個人保証と役員借入金の処理は、M&Aにおける重要な関心事です。多くの零細企業では、銀行借入に対して経営者が個人保証を提供していますが、株式譲渡による会社売却では、原則として個人保証は買い手企業に承継されません。つまり、会社が売却されても個人保証は残る可能性があります。
この問題を解決するために活用できるのが、経営者保証ガイドラインです。このガイドラインに基づき、一定の条件を満たせば金融機関に保証解除を求めることができます。具体的には、法人と個人の資産や経理が明確に分離されていること、財務基盤が安定していること、適時適切な情報開示が行われていることなどが条件となります。M&Aの交渉において、買い手企業が新たな保証を提供するか、金融機関と保証解除の交渉を行うかについて、明確に取り決めることが重要です。
役員借入金については、処理方法が複数あります。第一の方法は、役員借入金をそのまま買い手企業に承継してもらい、買い手企業から返済を受ける方法です。第二の方法は、売却前に債権放棄を行い、役員借入金をゼロにする方法ですが、この場合は税務上の債務免除益が発生する可能性があるため注意が必要です。第三の方法は、DES(デット・エクイティ・スワップ)を活用し、役員借入金を資本金に振り替える方法です。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、税務上の影響も異なるため、税理士などの専門家と相談しながら最適な方法を選択することが重要です。特に役員借入金が多額の場合、処理方法によって手取り金額が大きく変わる可能性があるため、慎重な検討が必要となります。
まとめ
零細企業は日本企業の84.5%を占め、地域経済を支える重要な存在です。中小企業基本法における小規模企業者に該当し、製造業等では従業員20人以下、サービス業等では5人以下という基準が設けられています。零細企業であってもM&Aは十分に可能であり、後継者不在の解決、個人保証からの解放、創業者利益の実現、従業員の雇用維持など多くのメリットがあります。
M&Aの主要手法は株式譲渡と事業譲渡であり、零細企業では手続きが比較的シンプルな株式譲渡が多く選択されます。売却価格の相場は時価純資産に営業利益の2年から5年分を加えた金額が目安となり、自社の強みや業績の安定性によって変動します。成功のポイントは、自社の強みの明確化、適切なタイミングの選択、零細企業案件に強い仲介会社の選定、相場観に基づいた価格交渉、早期の専門家への相談です。
一方で、デューデリジェンスへの対応、簿外債務の事前解消、情報管理の徹底、従業員や取引先への適切な説明、個人保証や役員借入金の処理など、注意すべき点も多くあります。これらを適切に対応することで、零細企業のM&Aを成功に導くことができます。零細企業のM&Aは決して特別なことではなく、事業承継の現実的な選択肢として検討する価値があります。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、会社売却に関する豊富な実績とノウハウを活かし、経営者の皆様の悩みに寄り添った丁寧なサポートを提供しています。無料相談も行っておりますので、M&Aや経営課題に関するご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーにお気軽にお問い合わせください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。