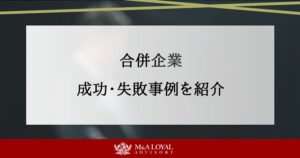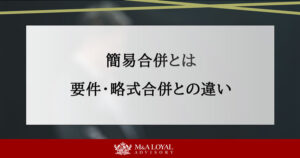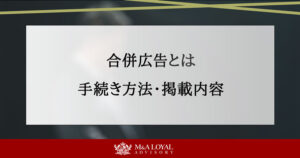吸収合併で契約はどう承継される?覚書や契約の結び直しは必要か解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
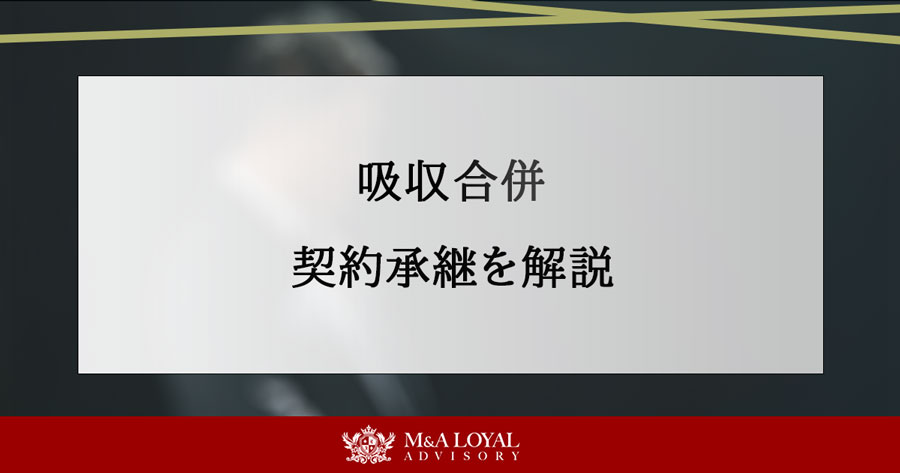
吸収合併では、消滅会社の契約上の地位が原則として存続会社に移転します。吸収合併で法人格が消滅しても契約関係は継続されるため、取引や業務への影響は通常限定的です。
ただし、契約書の内容次第では、こうした包括承継が例外的に認められない場合もあります。承継を前提とした楽観的判断は、後に重大な法的リスクを招く可能性があります。
本記事では、吸収合併における契約承継の基本的な仕組みと、実務上の注意点について分かりやすく解説します。
目次
吸収合併で契約は承継されるか
まず、吸収合併における契約の承継について解説します。
吸収合併では基本的に全て承継される
吸収合併では、消滅する会社が締結していた契約や債務などの権利義務は、原則として全て存続会社に包括的に承継されます。
会社法第2条第27号において、吸収合併は「会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう」と定義されています。
この定義に基づき、契約の種類や会社の規模にかかわらず、吸収合併に該当する場合には包括承継の効力が及ぶと解されています。
吸収合併で雇用や労働契約は承継されるか
吸収合併では、資産や債務、技術ノウハウ、取引契約などと同様に、従業員との雇用契約も存続会社に承継されます。民法では労働契約の譲渡に労働者の承諾が必要とされますが、会社法の規定により、合併に伴う包括承継が認められ、労働者から個別の同意を得る必要はありません。原則として、既存の雇用条件が維持されます。
ただし、消滅会社と存続会社の間で就業規則や人事制度に差がある場合、処遇の不公平感や労務管理の混乱が生じる可能性があります。合併後に労働条件を変更する場合には、労働契約法や労働基準法に基づき、従業員に対する説明や合意形成を含めた適切な手続きが必要です。合併前に雇用条件の整理や制度統一の方針を検討し、従業員に丁寧に説明することが望まれます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



吸収合併で承継される契約
吸収合併で承継される契約として、具体的には次のものが挙げられます。
- 取引先との取引基本契約
- ITシステム利用契約
- 賃貸借契約(賃貸物件を借りている場合)
- 特許権等の知的財産権のライセンス契約
それぞれについて解説します。
取引先との取引基本契約
吸収合併では、仕入先や供給先との取引基本契約は原則として存続会社に承継され、契約書の名義変更や再締結は通常不要です。ただし、契約書に「当事者変更時に自動解除する」などの条項がある場合、承継が認められない可能性があるため、事前に契約内容を確認する必要があります。
また、取引先との関係を維持するため、合併前後に丁寧な説明や合意形成を行うことが重要です。
ITシステム利用契約
ITシステムやクラウドサービスなどの利用契約も、吸収合併により包括的に承継されることが一般的です。ただし、契約によっては利用者の変更に制限がある場合があるため、契約内容を確認する必要があります。
特に、ベンダー側が利用者を限定している場合や、ライセンス契約が特定企業に紐付いている場合は、譲渡が禁止されていることがあり、再契約や通知が必要となる場合があります。
賃貸借契約(賃貸物件を借りている場合)
吸収合併により、賃貸物件の賃貸借契約も存続会社に包括的に承継されます。ただし、賃貸借契約書の内容によっては、賃貸人(貸主)の承諾が必要となる場合や、契約解除条項が影響する場合があります。そのため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて貸主の承諾を得ることが重要です。
特に事業用不動産では、合併後の使用目的変更や保証人の再確認を貸主から求められることがあります。このようなケースでは、合併前に契約条件の見直しや調整を行い、合併後の円滑な運用を確保することが不可欠です。
特許権等の知的財産権のライセンス契約
特許権や商標権などのライセンス契約は、吸収合併によって原則として存続会社に承継されます。ただし、契約書に譲渡制限条項や契約者変更時の承諾義務がある場合、事前承諾や通知が必要となることがあります。これを怠ると契約解除のリスクがあるため、合併前に契約内容を精査することが重要です。
特に独占的ライセンス契約では、再契約や条件変更が求められる可能性があるため、ライセンサーとの早期調整が不可欠です。
吸収合併での契約の承継に関する注意点
吸収合併での契約の承継に関する注意点として、次の点が挙げられます。
- 契約書の再締結は原則不要も、通知義務に注意
- 新たな契約書や覚書の作成も原則不要
- 銀行口座名義が変わる場合は変更の手続きが必要
- チェンジオブコントロール条項に注意
それぞれについて解説します。
契約書の再締結は原則不要も、通知義務に注意
吸収合併では、契約関係は全て存続会社に包括的に承継されるため、基本的には契約書を結び直す必要はありません。たとえ消滅会社名義で契約を締結していた場合でも、その効力は存続会社に引き続き及びます。
ただし、契約書に社名や代表者の変更時に通知する旨が記載されている場合、契約自体の再締結は不要でも、契約条項に基づいて速やかに通知を行う必要があります。また、合併に伴い契約内容と実態に乖離が生じる場合には、トラブル回避のため取引先と協議し、契約内容の見直しや修正契約の締結を検討することが重要です。
吸収合併で新たな契約書や覚書の作成も原則不要
吸収合併では、消滅会社が締結した契約書や覚書の内容も存続会社に承継されるため、通常は新たに契約書を作成したり、覚書を取り交わす必要はありません。
ただし、実務では相手方が社名変更に不安を覚えることもあり、形式的に新契約書や覚書の作成を求められることもあります。
とりわけ覚書は契約条件の補足や修正に用いられるため、内容の誤認を避けるために不要な書類作成は控えるべきです。ただし、取引上の信頼関係を重視する場合には例外的に応じることも必要です。
判断に迷う際は、法務部門や専門家と相談し、適切な対応を選択することが重要です。
吸収合併で銀行口座名義が変わる場合は変更の手続きが必要
契約の多くは包括的に承継されますが、銀行口座は自動的に名義変更されるわけではないため、別途手続きが必要です。具体的には、消滅会社の取引銀行に対して口座名義の変更を依頼するか、残高を存続会社の口座へ送金した上で旧口座を解約する手続きを行います。また、取引先に対して口座変更の通知を行うことも重要です。これを怠ると、入出金処理に混乱が生じる可能性があります。
さらに、金融機関との各種契約(融資契約や与信契約など)には、名義変更に加えて支配権変更に関する通知が必要な場合があります。契約書の条文を事前に確認し、必要な手続きを適切に行うことが求められます。
チェンジオブコントロール条項に注意
吸収合併の際に特に注意すべき点が、チェンジオブコントロール(COC)条項の存在です。これは、契約当事者の支配権に変化があった場合、取引先に通知義務や契約解除権を与える条項であり、M&A契約や銀行融資契約、賃貸借契約などに多く見られます。
合併によって経営権が移動したとみなされる場合、契約の相手方が契約を一方的に解除する法的根拠となる可能性があります。そのため、合併に先立って契約条項を精査し、必要に応じて相手方の同意や承諾を得ることが重要です。
吸収合併契約書とは
吸収合併契約書とは、存続会社と消滅会社が吸収合併を行う際に合併内容を明文化した契約書であり、会社法第749条に基づいて作成が義務付けられています。
契約書には、法定記載事項と任意的記載事項が含まれます。法定記載事項には合併の形式、効力発生日、資産・債務の承継内容などが含まれ、記載漏れがある場合、契約の有効性に影響を与える可能性があります。任意的記載事項には、取引先への配慮や特定の取り決めが含まれます。
法定記載事項
法定記載事項は、会社法第749条に基づき記載が求められ、内容が欠けている場合、契約の有効性に影響を及ぼす可能性があります。吸収合併契約書に記載する必要がある主な事項は以下のとおりです。
合併当事者の情報
存続会社および消滅会社の「商号」と「本店所在地(住所)」を契約書に正確に記載する必要があります(会社法第749条第1項第1号)。これらの情報は登記情報と一致している必要があります。
合併対価の支払いに関する取り決め
消滅会社の株主や新株予約権者に対する対価の内容(株式、社債、新株予約権などの種類、数、算定方法、割当方法)を詳細に記載します(会社法第749条第1項第2号・第3号・第4号)。100%子会社を吸収合併する場合は「無対価合併」となり、対価の記載は不要ですが、その旨を契約書に明記することが一般的です。
合併後の資本金と準備金に関する情報
合併によって存続会社の資本金または資本準備金が増加する場合、その増加額や方法を契約書に明記します(会社法第749条第1項第5号)。
期日
合併契約書には「効力発生日」を明記する必要があります(会社法第749条第1項第6号)。効力発生日から2週間以内に登記申請を行う必要があり、効力発生日前日までに株主総会を開催する必要があります。株主総会の招集通知は、非上場会社では開催日の1週間前、上場会社では2週間前までに行う必要があります(会社法第299条)。
任意的記載事項
任意的記載事項には、定款の変更や取締役の選任、配当の制限などがあり、当事者間の合意に応じて追加されます。
記載されることの多い内容は次のとおりです。
存続会社の定款
吸収合併によって存続会社の事業内容や組織構成が変わる場合、定款の一部変更が必要になることがあります。例えば、事業目的の追加や発行可能株式数の変更などが該当します。
定款は会社の基本規則であるため、変更する場合は明確に記載しておくことで、後の手続きや登記の円滑化につながります。
存続会社の取締役と役員の選任
吸収合併後に、消滅会社の役員を存続会社の取締役や監査役として迎える場合、その選任に関する事項を契約書に記載することがあります。
組織体制の変更が予想される場合には任意的記載事項に明示しておくことで、合併後の役員構成の透明性を確保でき、社内外の混乱を防げます。
消滅会社の株主の議決権の取り扱い
消滅会社が種類株式を発行している場合、吸収合併後における新会社(存続会社)での株主総会における議決権の取り扱いを明記しておくと良いでしょう。
特に、議決権制限株式や優先株式などが存在する場合には、合併後の権利関係に不明点が生じないよう、取り決めを具体的に明示する必要があります。
効力発生日までの増資・減資
合併の効力発生日までの間に、消滅会社が増資や減資を行う可能性がある場合、その旨と対応方法を契約書に記載します。これにより、資産・負債の変動による影響を受ける存続会社が、事前にその事実を把握・調整できるようになり、合併後の不整合を防止します。
人事に関する内容
吸収合併に伴い、消滅会社の役員や従業員の処遇について定める場合は、任意的記載事項として契約書に記載されます。
例えば、退任役員への退職慰労金の支給や従業員の承継、勤続年数の通算などです。これらを明記しておくことで、合併後の労務トラブルを防ぎ、円滑な統合を実現できます。
吸収合併契約書の承認
吸収合併契約書の効力は、関係各社の株主総会や官公庁からの承認を条件とすることが一般的です。そのため、承認が得られなかった場合には契約が失効する旨を、任意的に契約書に記載することがあります。
消滅会社の財産の承継
吸収合併により、消滅会社の資産・負債・権利義務など全てが存続会社に承継されますが、特に重要な資産や事業については、契約書に明記しておくことで、承継内容を明確化できます。
吸収合併契約書に規定がない事態について
合併実施までに新たな課題が生じた場合に備えて、「契約書に定めのない事項が発生した場合は、当事者間で協議の上決定する」といった条項を盛り込むことがあります。
この文言により、未確定事項への柔軟な対応が可能となり、契約の実効性を高められます。
吸収合併契約書の一般的な構成
吸収合併契約書の一般的な構成は以下のとおりです。
タイトル
会社法では特段の定めはありませんが、実務上「吸収合併契約書」または「合併契約書」と記載されることが一般的です。タイトルは契約の趣旨を明確にするため、正確な名称を用いることが推奨されます。
前文
前文では、契約当事者である存続会社と消滅会社の「商号」を明記し、それぞれ「甲」「乙」として定義します。また、契約の目的や背景、会社法に基づいて吸収合併を行う意思を簡潔に記載します。この部分は契約全体の趣旨や法的根拠を示す重要な役割を果たします。
契約内容の定義
契約内容は、法定記載事項(会社法第749条)と必要に応じた任意的記載事項を条文形式で構成します。一般的な条項の例として、次のような構成が挙げられます:
- 第1条:合併の形式
- 第2条:効力発生日
- 第3条:資産・債務の引き継ぎ
- 第4条:従業員の処遇
- 第5条:契約変更・解除
- 第6条:合併契約書に定めのない事項
これらの条項は、利害関係者への配慮や実務上の透明性を確保するために適切に記載されることが重要です。
結び
契約書の末尾には「結び」として、作成部数、保管場所、締結日を明記します。各社が署名・押印することで契約が成立します。作成部数は関与会社の数に応じて等しく作成し、各社が1通ずつ保管するのが一般的です。なお、電子契約システムを利用して署名を行うケースもあり、デジタル化が進む実務においてはこれが採用される場合もあります。
吸収合併契約書に関連する提出書類など
印紙
吸収合併契約書には、収入印紙の貼付が必要です。吸収合併の場合、原則として契約書1通につき4万円の印紙税が課されます。
ただし、登記申請の際に添付する契約書については、原本1通があれば他は写しで足りるため、印紙代は1通分に抑えられます。親会社と子会社の合併など、関係性が明確な場合は1通の原本を共有することで節約できます。
一方で、存続会社と消滅会社がグループ企業ではない場合は、それぞれが原本を保有することが望ましく、その場合は2通分の印紙代(計8万円)が必要です。
株式会社合併による変更登記申請書
吸収合併の効力が発生した後、存続会社は法務局へ「株式会社合併による変更登記申請書」を提出する必要があります。
この申請書には、吸収合併契約書をはじめとする複数の添付書類が必要であり、登記事項の変更に関する内容(商号や本店所在地、資本金、役員変更など)を正確に記載します。
申請時には書類の記載漏れや不備がないよう、あらかじめ必要書類をチェックリストなどで整理しておくことが重要です。特に複雑な合併では、専門家の関与が推奨されます。
吸収合併契約書のひな形
吸収合併契約書のひな形を紹介します。
記載例やひな型を活用すれば、記載漏れや誤記の防止に役立ちますが、契約内容は当事会社の状況によって異なるため、画一的なひな形にそのまま当てはめることはできません。
そのため、吸収合併契約書を作成する際には、専門家の助言を受けながら内容を調整することを強く推奨します。
〇〇株式会社(以下「甲」という。)および〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、吸収合併(以下「本合併」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(合併の方式)
甲および乙は合併し、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とし、乙は解散するものとする。
(1)甲(存続会社)
商号:〇〇株式会社
住所:〇県〇市〇町〇番〇号
(2)乙(消滅会社)
商号:〇〇株式会社
住所:〇県〇市〇町〇番〇号
第2条(発行株式および割当比率)
甲は本合併に際し、普通株式〇株を発行し、合併効力発生日の前日における乙の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する乙の株式〇株に対して甲の株式〇株の割合で割当交付する。
2 本条の割当比率により交付する株式に1株未満の端数が生じた場合、甲はその端数を切り上げ、または一括売却し、代金を案分して支払うものとする。
第3条(資本金等の増加)
本合併に伴い甲が増加すべき資本金および準備金は、以下のとおりとする。
(1)資本金 金〇〇円
(2)資本準備金 金〇〇円
(3)その他剰余金 会社計算規則に基づき算出
第4条(効力発生日)
本合併の効力発生日は、令和〇年〇月〇日とする。ただし、必要に応じて甲および乙が協議の上変更できる。
第5条(財産および義務の承継)
甲は、乙の全ての資産、負債および権利義務を効力発生日に包括的に承継する。
2 乙は、効力発生日前日までの変動について、明細を添付して甲に通知する。
第6条(業務の遂行)
甲および乙は、本契約締結日から効力発生日までの間、善良な管理者の注意をもって業務を遂行し、重要事項は相手方の事前承諾を得るものとする。
第7条(従業員の承継)
甲は、効力発生日において乙の従業員を引き継ぎ、勤続年数を通算する。細部の取り扱いは、甲および乙が協議の上定める。
第8条(株主総会の承認)
甲および乙は、それぞれ令和〇年〇月〇日までに株主総会を開催し、本契約の承認決議を行う。
第9条(契約の変更および解除)
天災、重大な資産変動等により、本合併の条件に影響が生じた場合は、甲および乙の協議により契約内容を変更または解除できる。
第10条(未定事項の協議)
本契約に定めのない事項または解釈上疑義が生じた事項については、甲および乙が誠意をもって協議の上解決する。
第11条(契約の失効)
株主総会の承認または関係官庁の認可が得られない場合、本契約は効力を失うものとする。
第12条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲および乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)〇〇株式会社
所在地:〇県〇市〇町〇番〇号
代表取締役 〇〇 〇〇(記名押印)
(乙)〇〇株式会社
所在地:〇県〇市〇町〇番〇号
代表取締役 〇〇 〇〇(記名押印)
吸収合併の手続きの流れ
吸収合併の手続きの流れは次のとおりです。
- 吸収合併契約書の作成
- 取締役会および株主総会での承認
- 株主と債権者の利益確保
- 債権者の異議申し立て
- 効力の発生
- 合併効力発生日の到来
- 承継
それぞれについて順番に解説します。
吸収合併契約書の作成
吸収合併を行うには、まず当事会社間で吸収合併契約書を作成します。会社法第748条では、合併契約の締結が法的要件とされており、契約書には第749条に定める法定記載事項を盛り込む必要があります。なお、契約書に記載すべき内容は、前述の項目で解説したとおりです。
吸収合併契約書は、存続会社と消滅会社の双方が合意した内容に基づいて作成します。契約締結後は、合併に向けて両社が法的義務を負うため、内容の確認と合意形成は慎重に進めなければなりません。
取締役会および株主総会での承認
吸収合併を実施するには、取締役会および株主総会での承認が必要です。まず、両社の取締役会で合併契約を決議し、その後株主総会で特別決議によって承認を得ます(会社法第783条、795条)。特別決議には、議決権を有する株主の過半数の出席と、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。
株主総会の招集通知は、非上場会社では1週間前、上場会社では2週間前までに発送する必要があります。なお、一定の要件を満たす場合、「簡易合併」や「略式合併」により株主総会の開催を省略できます(会社法第796条、784条)。
株主と債権者の利益確保
吸収合併では、株主や債権者を保護するため会社法に基づく手続きが求められます。
株主には、株主総会での決議を経て反対株主に株式買取請求権を通知します。ただし、簡易合併(合併対価が純資産額の5分の1以下)や略式合併(存続会社が消滅会社の全株式を保有)では株主総会が不要です。
債権者には官報公告と個別催告を行い、公告は効力発生日の1カ月前までに実施し、異議申し立て期間は公告後1カ月以上保障されます。
債権者の異議申し立て
会社法第789条に基づき、公告や個別催告を受けた債権者は、期間内であれば異議申し立てが可能です。異議があった場合、存続会社はその債権を弁済するか、担保を提供するなどの方法で債権者を保護する必要があります。
また、合併が債権者に不利益を及ぼさないと認められる場合、裁判所の許可を得ることで合併を進めることができます。異議申し立てがない場合は、債権者が合併に同意したものとみなされます。
効力の発生
吸収合併契約に定められた効力発生日をもって、合併の効力が生じます。これにより、消滅会社は解散し、全ての資産・負債・契約関係が存続会社に承継されます。また、存続会社は消滅会社の株主に対し、株式や金銭など合併対価を交付します。
効力発生日以降、存続会社は会社法第801条に基づき合併に関する書類を作成し、本店に6カ月間備え置く義務があります。
合併に伴う変更登記の申請
合併の効力発生日から2週間以内に、存続会社は法務局にて合併による変更登記を行う必要があります。また、同時に消滅会社の解散登記も行います。
登記の際には、変更登記申請書を提出する必要があります。なお、この申請には、吸収合併契約書や株主総会議事録、債権者保護手続きに関する書類、公告証明、資本金計上に関する証明書などの添付が求められます。
提出書類に不備や記載漏れがあると登記が受理されないため、専門家と連携し、正確かつ漏れのない準備が不可欠です。
承継
吸収合併により、存続会社は消滅会社の資産や債務、契約、従業員、知的財産など全ての権利義務を包括的に承継します。
ただし、業種によっては行政上の許認可の承継や独占禁止法に基づく届出など、別途手続きが必要なケースもあります。特に許認可事業では、承継の可否や届出の時期を慎重に検討し、必要があれば専門家の支援を受けることが望ましいです。
吸収合併のメリット
吸収合併のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 組織統合による効果をすぐに発揮できる
- 事業に関する権利義務を包括的に承継できる
- 買収に資金調達を必要としない
- 節税効果を得られる可能性がある
それぞれを分かりやすく解説します。
組織統合による効果をすぐに発揮できる
吸収合併では、株式譲渡のように別会社のままグループに加える手法とは異なり、両社の法人格が一本化されます。そのため、経営資源の共有や業務の一体化が早期に実現でき、統合効果を迅速に得られる点が大きなメリットです。
また、人材やシステムの共通化により重複業務を削減し、業務効率化やコスト削減につながります。特にグループ内再編では、法人格の一本化によって意思決定のスピードが向上し、戦略実行力を強化する手法として有効です。
事業に関する権利義務を包括的に承継できる
吸収合併では、消滅会社の権利義務・契約関係・資産負債などが存続会社に包括的に承継されます。事業譲渡のように契約ごとに移転手続きを行う必要がなく、手間や時間を大幅に削減できます。
特に、雇用契約や取引基本契約、知的財産権などが多数存在する場合には、個別に承継するよりも吸収合併の方が効率的です。ただし、一部の契約では譲渡制限条項や承諾義務が含まれる場合があるため、事前に契約内容を確認することが重要です。
買収に資金調達を必要としない
吸収合併では、合併対価として株式や社債、新株予約権が用いられます。これにより、現金による買収を前提とする株式譲渡や事業譲渡と異なり、大規模な資金調達を必要としない点が強みです。
特に買収側が手元資金に余裕がない場合でも、自社株を活用することでM&Aを実現できます。また、株価の評価が高い企業ほど、対価として提供する株式の価値が高まり、交渉面でも有利に働くことがあります。
節税効果を得られる可能性がある
吸収合併が「適格合併」に該当する場合、消滅会社の繰越欠損金を存続会社が引き継ぐことが可能です。適格合併では、税務上の資産や負債を簿価で引き継ぐことが認められ、合併に伴う時価評価課税が発生しません。このため、法人税の繰延が可能となり、税務上の負担を軽減する効果が得られます。
特に赤字を抱える企業を統合する場合、繰越欠損金を活用し、合併後の黒字との相殺が可能となり、大きな節税効果を得られます。ただし、適格合併の認定には、合併の目的が事業継続であることや関係会社間の合併であることなど、税法上の要件を満たす必要があります。適用条件を確認しながら、税務専門家の助言を受けることが重要です。
吸収合併のデメリット・リスク
吸収合併のデメリット・リスクとして、次の点が挙げられます。
- 膨大かつ複雑な手続きが求められる
- 経営統合(PMI)に大きな負担がかかる
- 買収側株主の持株比率が低下する恐れがある
- 簿外負債などの承継リスクがある
それぞれについて解説します。
膨大かつ複雑な手続きが求められる
吸収合併は、会社法で定められた多くの手続きを要するため、株式譲渡などの他の手法と比べて手間がかかります。
例えば、合併契約書の作成・開示や株主総会での承認、債権者保護手続き、反対株主への対応、さらには解散登記など、煩雑な工程が発生します。こうした事務的負担は、特に中小企業にとって大きな障壁となる場合があります。
また、手続きを誤ると合併無効の訴訟リスクが生じるため、慎重かつ確実な対応が必要です。
経営統合(PMI)に大きな負担がかかる
吸収合併では、法的効力発生日から単一企業として事業を開始するため、統合作業(PMI)を迅速かつ確実に進める必要があります。
統合対象には、企業文化や業務プロセス、人事制度、ITシステムなど広範な領域が含まれ、社内の混乱や従業員のモチベーション低下を招く恐れがあります。
また、PMIの実行には現場レベルの調整が不可欠であり、本来の事業運営に支障をきたすリスクもあります。
買収側株主の持株比率が低下する恐れがある
吸収合併で株式を対価として新株を発行する場合、存続会社の既存株主の持株比率が下がり、いわゆる「株式の希薄化」が発生します。特に、合併比率が消滅会社側に有利に設定された場合、存続会社側の株主にとっては相対的な影響が大きくなり、経済的な不利益となる恐れがあります。
上場企業では、こうした希薄化を懸念して株価が下落した事例もあり、株主や投資家からの反発を招くリスクがあるため、慎重な対価設計が求められます。
簿外負債などの承継リスクがある
吸収合併では、消滅会社の全権利義務を包括的に承継するため、帳簿上に表れていない負債(簿外負債)などを引き継ぐリスクがあります。
例えば、係争中の訴訟や潜在的な環境負債など、将来的に損失となり得る事項が合併後に顕在化する可能性もあります。このため、事前にデューデリジェンスを徹底し、必要に応じて合併契約に補償条項などのリスクヘッジ策を講じることが重要です。
吸収合併以外の事業承継方法
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 会社分割
それぞれについて解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、会社の株式を第三者に譲渡することで経営権を移転させる手法です。会社の法人格や契約関係、従業員との雇用契約は原則として維持されるため、日常業務への影響は最小限に抑えられます。ただし、経営方針の変更が従業員や取引先に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が必要です。
手続きが比較的簡易である一方、買い手側が簿外債務や法的リスクを引き継ぐ可能性があるため、事前のデューデリジェンス(企業調査)が重要です。中小企業のM&Aでは、法人格を維持しつつ経営権を移転できる点が評価され、株式譲渡が広く活用されています。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を個別に売買契約によって移転する方法です。譲渡対象や範囲を柔軟に設定できるため、不採算事業を除外するなど戦略的な承継が可能です。
一方で、取引先との契約や雇用契約などを個別に移転させる必要があるため、手続きや関係者の同意が多数求められます。
会社分割
会社分割とは、会社の一部事業や資産・負債を別会社に移転する再編手法です。「新設分割」では新会社を設立し、既存会社から事業を切り出して承継します。「吸収分割」では既存の他社に分割対象を承継させ、承継先の会社が権利義務を包括的に引き継ぎます。
会社分割は、特定の部門単位での移転に適しており、特定の事業のみを承継させたい場合に有効です。どちらの方法でも元の法人格は消滅せず、他の事業の継続が可能です。また、権利義務の承継が包括的に行われるため、事業譲渡より手続きが簡便である場合もあります。ただし、会社分割には法律に基づく手続きが必要であり、状況に応じて事業譲渡との比較検討が求められます。
吸収合併における契約の承継に関するQ&A
最後に、吸収合併における契約の承継に関するよくある質問とその回答を紹介します。
吸収合併と新設合併の違いは何か
吸収合併と新設合併はいずれも会社の合併手法であり、資産・負債・契約関係などの包括承継が行われる点は共通しています。ただし、吸収合併では存続会社が残り、消滅会社の権利義務を承継します。一方、新設合併では全ての会社が消滅し、新たな会社が設立される点が大きな違いです。
許認可の承継においても差があり、吸収合併では存続会社が許認可を承継できますが、新設合併では業種や法律によって新会社が再取得を求められる場合があります。また、吸収合併では存続会社が上場企業であればそのまま上場が維持されますが、新設合併では一度上場廃止となり、新会社として再上場申請が必要です。さらに、登録免許税は新設合併の方が課税対象が広く、費用が高くなる傾向があります。
チェンジオブコントロール条項はどんな目的で設定されるか
チェンジオブコントロール条項は、契約当事者の経営支配に変更が生じた際に契約の見直しや解除を可能とする条項で、主に情報・技術流出の防止と敵対的買収への防衛を目的として設定されます。
例えば、自社の取引先が競合に買収された場合、秘密保持契約やライセンス契約を継続すれば機密情報が流出する恐れがあります。この条項があれば、契約解除の条件が事前に明確化されているため、リスクを未然に防ぐことが可能です。
また、敵対的買収を抑制する効果もあります。買収によって契約が一方的に解除されるリスクがあるため、買収を試みる企業にとって経済合理性が失われ、買収を断念する動機につながります。一方で、この条項は契約相手にとって負担となる場合があるため、慎重に設計することが重要です。企業防衛策としても機能する重要な条項です。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
本記事では、吸収合併における契約承継の基本的な仕組みと、実務上の注意点について解説しました。
なお、M&A(合併・買収)や経営課題に関してご検討されている方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。