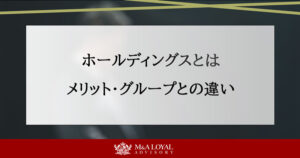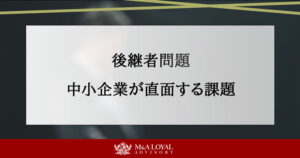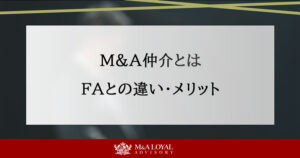警備会社の大手ランキング&M&A動向2025|業界再編の現在地と未来
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
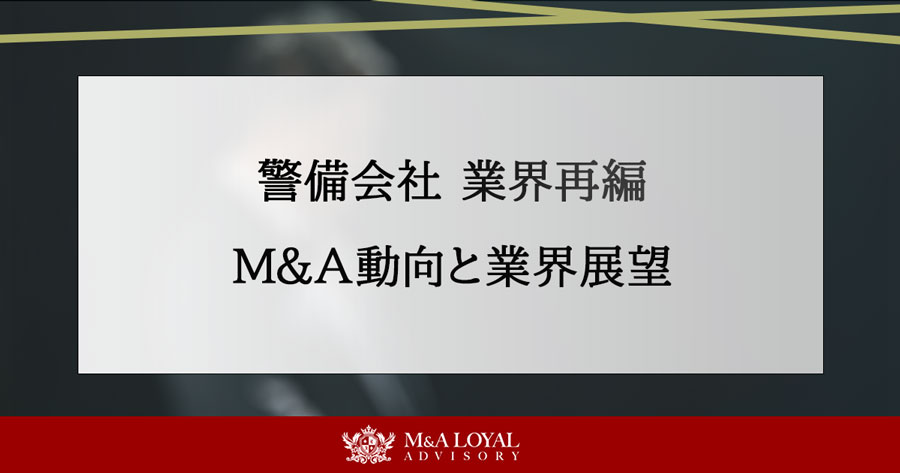
警備業界は今、かつてない転換期を迎えています。社会の高齢化、犯罪の多様化、災害対策の強化といった社会的背景に加え、2025年現在では「大手による寡占化」と「中小警備会社のM&Aによる再編」が急速に進行中です。
本記事では、最新の警備会社の売上高ランキングや業界トップを走る大手企業の戦略を紐解きながら、注目されるM&A動向についても徹底的に解説していきます。特に、中小企業の事業承継や異業種からの参入、最新のテクノロジー導入が警備業界にどのような影響を与えているのかに焦点を当てます。
「警備会社の業界地図はどう変わるのか?」「中小企業や異業種プレイヤーにチャンスはあるのか?」──そうした疑問に対して、最新データと事例を交えながら解説していきます。これからの警備業界の未来を読み解く一助となる内容です。
目次
警備会社とは?業界構造と成長背景
警備業の定義と法的分類
警備業とは、警備業法に基づき、他人の需要に応じて人的・物的手段により生命・身体・財産を保護する業務を指します。大きく分けて以下の4種に分類されます。
- 1号警備(施設警備):ビルや商業施設、空港などの常駐警備。出入口の管理や巡回、監視カメラの操作などを通じて施設の安全を確保します。
- 2号警備(交通誘導・雑踏警備):道路工事現場や駐車場、イベント会場などで交通や人流を安全に誘導する業務です。事故の未然防止やスムーズな流れの確保が求められます。
- 3号警備(貴重品運搬警備):現金輸送車による金銭や貴重品の輸送・護衛業務。金融機関・企業間の現金移送、重要書類の保護移送などが含まれ、武装・GPS管理などの高度な技術も伴います。
- 4号警備(身辺警備):いわゆるボディーガード。要人・著名人・企業経営者などの身の安全を守ることを目的とした業務です。近年ではストーカー被害者の保護など民間支援の範囲も広がっています。
警備業のすべての形態は、警備業法に基づき公安委員会への届け出が必要であり、業務内容や教育制度、装備品の基準まで厳格に規定されています。業態の多様性と法規制の両面が、警備業界のビジネスモデルを複雑かつ専門的なものにしています。
国内市場規模と成長要因
警備業界の市場規模(売上高総額)は約3.3兆円とされ、景気の波に左右されにくい安定産業と見なされています。その背景には、以下のような社会的要因があります。
- 少子高齢化と治安意識の向上:高齢世帯や単身者の増加により「安心・安全」へのニーズが高まり、常駐警備やホームセキュリティの需要が拡大しています。
- 大規模イベントや自然災害への備え:国際スポーツイベントや自然災害の頻発に伴い、雑踏警備・避難誘導などの業務需要が増加。
- インフラ老朽化と建設工事の増加:再開発・都市整備事業における工事現場の交通誘導需要が長期的に見込まれています。
- セキュリティ技術の高度化:監視カメラ、AI監視システム、顔認証技術などの導入が進み、施設警備の効率化と新サービス創出が進行中。
特に、高齢化社会と防犯意識の高まりは、今後も継続的な需要を生む要因であり、警備業は成長余地のある業種と位置づけられています。
警備業界における大手と中小の棲み分け
日本国内には警備業を営む企業が1万社以上存在しますが、そのほとんどが中小規模であり、セコム株式会社と綜合警備保障株式会社(ALSOK)の2社が市場全体の約34%を占める寡占構造となっています。
大手企業の特徴:
- 全国展開と大手顧客基盤(金融、医療、行政など)
- IT・セキュリティ機器との連携による高度サービス
- 自社教育体制や人材プールの厚み
- 高度なブランド認知と信用力、入札案件への対応力
- 海外展開や異業種連携による多角化
中小企業の特徴:
- 地域密着型で柔軟な対応
- 特定の業態(例:建設現場専門、イベント警備)に特化
- 家族経営や個人事業形態も多く、事業承継問題を抱えやすい
- 一部には特定の業界に強みを持つ“隠れた優良企業”も存在
- 働き手の高齢化や若手採用の困難さが慢性的な課題
中小警備会社は、長年築いた地域の顧客基盤や信頼関係を強みとする一方で、営業・採用・教育体制など経営資源の制約を抱えることが多く、こうした理由から大手企業によるM&A対象となりやすい状況にあります。
また、近年では異業種(人材派遣・清掃業・建設業など)からのM&Aによる警備業参入も目立っています。これは、業界周辺領域とシナジーが見込まれる点、定期収入を生むストック型ビジネスとして魅力がある点、そして高齢化社会において安定した需要が期待できる点などが理由です。
さらに、警備業務の一部は法定資格や公安委員会の認定を必要とするため、ゼロからの新規参入は難易度が高く、M&Aによって事業基盤を取り込むことが最も効率的な手段とされています。こうした流れは今後さらに加速し、地域密着の中小企業と広域展開を目指す大手との連携・再編が今後のカギとなるでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



警備会社大手 売上高ランキング2025最新版
トップ8ランキング(セコム・ALSOK・セントラル警備など)
2025年最新の警備会社の売上高ランキングは以下のようになっています(※直近の企業公開資料および業界紙調査を基に編集)
- セコム株式会社
- 売上高:約1.19兆円(2025年3月期)
- 特徴:機械警備・医療・ITとの融合による多角化が進行中。
- 綜合警備保障株式会社(ALSOK)
- 売上高:約5519億円 (2025年3月期)
- 特徴:公共案件・施設警備に強く、福祉・介護事業にも注力。
- テイケイ株式会社
- 売上高:約918億円 (2024年6月期)
- 特徴:建設現場に特化した2号警備(交通誘導)を主力とする実務型企業。
- セントラル警備保障株式会社(CSP)
- 売上高:約714億円(2025年2月期)
- 特徴: オフィスビルや商業施設への常駐警備を中心とする首都圏型モデル。
- アサヒセキュリティ株式会社
- 売上高:約507億円 (2024年3月期)
- 特徴:輸送警備(3号)に特化し、流通業向けのサービスを展開。
- 株式会社全日警
- 売上高:約394億円 (2025年3月期)
- 特徴:地域密着型で各地域の特性や顧客のニーズに応じたサービスを提供。
- 株式会社セノン
- 売上高:約389億円 (2025年3月期)
- 特徴:総合安全サービス企業として事業を展開。
- 東洋テック株式会社
- 売上高:約349億円 (2025年3月期)
- 特徴:関西の警備会社で唯一上場。
このように、大手警備会社の中でも各社が特化分野や地域性を活かして差別化を図っています。売上高の規模だけでなく、「どの領域に注力しているか」が警備会社の戦略を読み解くうえで重要なポイントとなります。
次節では、これらの上位企業の戦略と、なぜトップ企業が業界のシェアを独占し続けているのかについて掘り下げていきます。
大手3社の売上推移と収益構造分析
警備業界における大手3社──セコム、ALSOK、セントラル警備保障(CSP)は、それぞれ独自の収益構造と経営戦略を持っています。売上構成比の分析から、彼らの経営資源の重点や事業の方向性を読み解くことができます。
- セコム:売上の約70%を機械警備・施設警備が占め、残りは医療・介護・情報通信・海外事業などの多角化部門から構成。高収益体質で、営業利益率は業界トップクラス。クラウド・IoTセキュリティとの統合が加速しています。
- ALSOK:公共施設や企業向け常駐警備の比率が高く、施設警備と人材派遣の融合に注力。警備以外にも、介護福祉事業や学校安全支援など社会貢献型サービスへの展開を進め、リスク分散型の収益構造を構築しています。
- セントラル警備保障(CSP):売上の大部分を首都圏のオフィスビルや大型商業施設の施設警備が占め、IT関連の遠隔警備サービスの導入にも積極。収益の安定性を保ちながら、高付加価値サービスへの移行を進めています。
3社ともに労働集約型の人材依存からの脱却を掲げており、テクノロジーによる業務効率化と顧客満足度向上を目指した構造改革が進行中です。
なぜ大手3社が圧倒的シェアを維持できるのか
警備業界において大手3社が強固な市場シェアを維持できる理由には、以下のような要素が挙げられます。
- 全国対応力とブランド信頼性:セコムやALSOKは全国ネットワークを有しており、どの地域でも均質なサービスを提供可能。企業や自治体など大口顧客との長期契約を保持しやすく、ブランド力が新規案件獲得にも寄与します。
- 人材教育・研修制度の充実:自社の教育センターを持ち、独自の研修カリキュラムを通じて高品質な警備員を育成。警備品質の一貫性が評価され、リピート率の高さに繋がっています。
- 高度な警備技術とシステム化:AI監視カメラ、遠隔警備、顔認証など最先端の技術をいち早く導入。これにより人件費削減と24時間体制の強化が可能になり、競合との差別化を実現しています。
- 資本力とM&A戦略:大手は新規拠点の開設やM&Aにも積極。中小企業との業務統合や拠点取得により、商圏拡大と人材確保を同時に実現しています。
こうした多面的な競争優位性により、大手3社は警備業界の中でも圧倒的なプレゼンスを保持し続けているのです。
大手警備会社の成長戦略と競争優位性
セコム:海外・IT・医療との統合モデル
セコムは、警備業界の枠を超えた「社会システム産業」への転換を標榜し、事業を多角化しています。国内最大手として、以下のような戦略を展開中です。
- 海外展開:アジア・ヨーロッパを中心に、海外子会社や提携企業を通じて事業を拡大。日本式警備サービスの輸出モデルとして注目を集めています。
- IT活用:自社開発のセキュリティプラットフォームを通じて、遠隔監視・AI解析・クラウド警備を一体化。IoT機器との連携やデータ解析によって、予兆保全型のセキュリティモデルを構築。
- 医療・介護との融合:セコム医療システムでは、在宅医療・高齢者ケアとの連携を図り、「安全・安心・健康」を包括的に支えるサービス群を提供。
これらの取り組みによって、単なる「警備会社」ではなく、社会全体のインフラとしての存在感を高めています。
ALSOK:買収と福祉分野への拡大
ALSOKは、常駐警備に強みを持つ一方、M&Aや新規分野への進出によって多角化を進めています。
- M&A戦略:直近では情報システム関連企業や地域警備会社を買収し、IT・地方拠点の強化を図っています。また、施設管理・人材派遣など周辺業種との連携を強化。
- 福祉・介護への進出:グループ内に介護事業会社を持ち、高齢者施設への警備連携や見守りシステム導入を進め、社会的課題の解決に貢献するモデルを構築。
- 公共性の高さ:災害時支援・避難誘導・自治体との連携など、公共インフラの一部としての役割も担い、信頼性と持続性の高い企業価値を構築しています。
ALSOKの戦略は、セキュリティと福祉という2大社会テーマを融合することにより、今後も成長可能性の高いポートフォリオを形成しています。
セントラル警備保障・テイケイ・アサヒセキュリティ:業務特化型モデル
これら中堅大手は、それぞれ特定分野に集中することで差別化を図っています。
- セントラル警備保障(CSP):都市型施設警備に強み。警備ロボット・顔認証ゲートなどの導入にも積極で、DX対応が進む。
- テイケイ株式会社:交通誘導警備に特化したオペレーション体制を構築。短期案件にも対応できるフットワークが強み。
- アサヒセキュリティ:流通・金融業界向けの現金輸送に特化。安全性・正確性を追求したマニュアル管理・GPS連携により高評価を獲得。
これらの企業は規模でこそ大手3社に及ばないものの、専門性を武器に高い収益性とリピート率を維持しており、大手にない柔軟性・即応性という独自の価値を発揮しています。
警備業界のM&A動向|大手企業による再編
警備会社におけるM&Aの目的
警備業界におけるM&Aの背景には、人材確保、商圏拡大、ノウハウ獲得、経営効率化といった多様な経営課題の解決ニーズがあります。特に以下のような点が主要な目的となっています。
- 人材不足の解消:警備業は労働集約型産業であり、経験者を含む人材の獲得が困難です。M&Aによって即戦力の現場スタッフや管理者を獲得できる点は極めて大きなメリットです。
- 商圏拡大と拠点補完:地場の警備会社を買収することで、既存の営業ネットワークに加えて新たな地域をカバーできる体制を構築できます。
- 契約・取引先の継承:長期にわたって構築されてきた官公庁・企業・施設との契約を維持することは、M&Aにおいて継続的な売上と信頼の確保に繋がります。
- 管理・教育ノウハウの共有:警備業は属人的なスキルに依存する面も多く、優れた教育制度やオペレーションノウハウを持つ企業を取り込むことで、全社的な品質向上に繋がります。
2023〜2025年の注目M&A事例とトレンド
近年の代表的なM&A事例として以下が挙げられます。
- セコムによるセノンの買収
セコム株式会社は2022年7月に株式会社セノンの発行株式約760万(55.1%)を取得し、子会社化しました。取得費用は約270億円と発表されています。
業界再編がもたらす構造的変化
警備業界では、今後ますます「2極化」「寡占化」「異業種参入」が進むと予想されます。
- 上位数社による寡占構造の強化:売上高・契約件数ともにシェア集中が進み、中堅以下は再編圧力を強く受ける構図となっています。中小企業の単独生存は難しく、業界全体として「生き残り」ではなく「再編参加」が重要なキーワードとなります。
- 中堅企業同士の統合連携(ホールディングス化):価格競争や人材確保におけるスケールメリットを求めて、グループ化によるブランド力強化と採用力向上を図る。ホールディングス体制によって、地域密着型と全国展開のバランスを取る動きが増加傾向にあります。
- 不動産、建物管理、ICT系企業の参入:自社サービスの付加価値として警備業を取り込む動きが加速し、業際融合が進行中です。たとえば、スマートビル管理を手がける建物管理会社が、警備部門を内製化することで運用コストの最適化と収益多角化を実現する事例が増えています。
- 「M&Aを前提とした創業」も視野に:近年では、創業当初から数年後のM&Aによる売却を前提とした「出口戦略ありきの起業」も警備業界で見られるようになっており、ファンドや投資家との連携によって、短期成長+売却益を狙うケースが増えています。
このような構造的変化により、M&Aは「単なる事業承継の手段」ではなく「成長戦略の中核」として位置づけられる時代となりました。企業規模の拡大だけでなく、テクノロジー導入、業種間融合、新規市場への参入といった変革を促す「業界内イノベーションの起点」として、M&Aは今後さらに活発化することが予想されます。
中小警備会社におけるM&Aの現実と戦略
中小企業の課題とM&Aニーズ
日本全国に点在する中小規模の警備会社は、多くが地域密着型の営業スタイルを採用し、地元の顧客に根ざしたサービスを提供しています。しかし、以下のような共通課題を抱える企業が多く存在します。
- 後継者不在による事業承継リスク:創業者や経営者が高齢化しつつある中、次世代へのスムーズなバトンタッチが困難になっており、廃業を余儀なくされる事例も増加しています。
- 人材不足と高齢化:警備業は夜間業務や長時間勤務など身体的負担が大きく、若年層の採用が難しい構造的課題を抱えています。
- 大手との価格競争による収益圧迫:スケールメリットのある大手企業と価格面で競争するのは難しく、薄利多売型のビジネスに追い込まれるケースが見られます。
- IT・機械警備への対応遅れ:人手による警備からAI・センサー等を活用した効率的な警備への移行が求められる中、設備投資が困難な中小企業では対応が遅れがちです。
このような状況から、「企業価値があるうちに売却したい」「顧客や従業員を守れる相手に引き継ぎたい」というニーズが高まり、M&Aが中小企業にとって重要な経営戦略のひとつとなっています。特に、家業的な経営体制の見直しと、従業員・顧客の未来を見据えた選択肢として注目されています。
買い手が重視するポイントとは?
大手企業や異業種プレイヤーが中小警備会社を買収する際、次のような点を重視しています。
- 営業基盤と既存契約の継続性:地域に根付いた信頼関係や自治体・商業施設との契約の安定性が評価されます。
- 現場スタッフの継続雇用意欲:即戦力となる人材の確保は買い手にとって大きな魅力。雇用維持への意欲が高い企業は評価が高くなります。
- エリア戦略との合致:未進出地域や戦略的に重要なエリアに拠点を持つ企業は、買い手の拡大戦略に合致する場合が多いです。
- 過去の法令違反・トラブルの有無:警備業は公安委員会の認可が必要な業種のため、法令順守・トラブル歴の有無は重要な判断材料となります。
また、福利厚生や教育体制といった社内制度の整備度合いも、買収後の統合のしやすさという観点で注目されます。
成功するための準備とパートナー選び
中小企業のM&A成功の鍵は「準備」と「相手選び」にあります。具体的には、
- 自社の強みと弱みを客観的に把握し、資料化する:財務・人材・顧客基盤・地域ブランドなどを整理し、買い手に伝えやすい資料を準備。
- 従業員や主要顧客との信頼関係維持策を事前に用意する:引継ぎに関するQ&AやFAQを社内用・顧客用に用意し、不安を和らげる体制を整える。
- 第三者の専門家(M&A仲介会社・顧問税理士など)に相談し、戦略を立てる:適切なマッチング先を探すだけでなく、税務・法務・心理面のケアも含めて支援してもらうことが望ましい。
- 譲渡後の統合(PMI)を意識した事前設計を行う:引継ぎ時期の決定、オペレーションや人材評価制度の統合方針などを明確にすることが重要です。
特に、買い手と売り手の企業文化や経営哲学のミスマッチを避けることが、M&A後の軋轢を防ぐために非常に重要です。事前に経営者同士が理念やビジョンを共有できるかを確認し、円滑なPMI(Post Merger Integration)へとつなげていく必要があります。自社の大切にしてきた価値観を守れる相手を選ぶことが、従業員や顧客にとっても最良の選択になります。
警備業界の未来予測とM&Aがもたらす影響
労働環境・人材確保の展望
少子高齢化が進行する中、警備業界では慢性的な人手不足が今後も続くと予想されます。これに伴い、業界全体として以下のような対応が求められています。
- 高齢者・外国人材の活用:定年後の再雇用制度や、在留資格「特定技能」を活用した外国人材の受け入れが進展。
- DXによる省力化:警備ロボット、顔認証システム、ドローン巡回などが実用段階に入り、マンパワー依存型の業務からの脱却が進む。
- 待遇改善と職業イメージの向上:業界内で賃上げや労働時間の短縮、資格取得支援などの動きが加速し、若年層の呼び込みを狙う。
こうした労働環境改善は、単なる雇用問題の解消にとどまらず、警備業全体のサービス品質と社会的信用を向上させる土台となります。
M&Aによる業界構造の変化
M&Aの進展により、警備業界の業態は次のように変化すると考えられます。
- 大手寡占の加速:市場上位企業でのシェア集中がさらに進み、安定収益モデルを確立。
- 地域の中小企業の淘汰と集約:一定規模以下の企業は自立継続が難しくなり、M&Aによって系列化・ネットワーク化されていく。
- 異業種融合モデルの出現:不動産、医療、IT、防災など隣接業界との統合により、「複合型安全インフラ企業」への進化が進む。
このような構造変化により、従来の“人が守る”警備から“仕組みで守る”警備への転換が進み、業界の位置づけそのものが変容していくでしょう。
経営者・投資家にとってのチャンスと留意点
今後の警備業界は、“縮小産業”ではなく、“再定義される成長産業”として評価される局面を迎えています。事業承継や地域密着の資産を持つ企業は、以下のような視点での経営判断が必要です:
- 早期の事業価値評価と出口戦略の設計
- テクノロジー導入・多角化への投資意欲の有無
- 文化適合・従業員保護を重視した買い手の選定
一方、買収側となる企業や投資家にとっては、他業界と比べても「ストックビジネス」「社会性の高さ」「安定収益」という特徴が魅力です。M&Aを通じて新たな付加価値創出を狙う戦略は、今後ますます注目されるでしょう。
警備会社の経営課題と持続可能性戦略
コンプライアンスと労務管理体制の強化
警備業界では、労働環境の厳しさから労務トラブルや法令違反が起こりやすく、コンプライアンス体制の強化が喫緊の課題です。特に、労働時間管理や社会保険の整備、安全教育の徹底などが求められています。また、警備員が関与する事故や事件が起きた際の対応マニュアルの整備、報告体制の透明化も、企業の信用維持に直結します。
さらに、業務委託契約の増加や多重下請け構造により、実際の就労環境が把握しづらくなる問題もあり、透明性の高い契約管理体制と内部監査制度の整備も求められます。行政指導や法改正への対応力も企業の評価を左右し、業界全体としてガバナンス強化が不可避の課題となっています。
女性・高齢者の活用と多様な人材戦略
警備業界ではこれまで男性中心、かつ中高年層に偏った人材構成が多く見られましたが、近年では女性や若者、高齢者、外国人材の活用が進みつつあります。特に、ショッピングモールや病院、学校などにおいては、きめ細かな対応力を持つ女性警備員のニーズが高まっています。また、柔軟な勤務体系や業務分担によって、65歳以上のシニア層の活躍も拡大しており、ダイバーシティ経営が競争力に直結する時代に突入しています。
持続可能なビジネスモデル構築のために
少子高齢化、都市集中、自然災害リスクの増加など、社会の変化に対し、警備会社が持続可能性を保つにはビジネスモデルの転換が不可欠です。AIやIoTを活用した警備の効率化、顧客とのサブスクリプション型契約の導入、地域防災・見守りサービスへの転換など、継続的な価値提供がカギとなります。
さらに、BtoC型警備(個人宅向け)、BtoG型(行政向け)、BtoBtoC型(企業と住民を繋ぐ)のような多様なモデルが登場しつつあり、収益構造の再設計が求められます。顧客ニーズに応じたカスタマイズ型警備やリモート対応型警備の導入なども今後の潮流です。
また、企業の「ESG経営」への関心が高まる中、警備業も環境・社会・ガバナンスに配慮した経営姿勢を求められるようになっています。省エネ機器の導入、フードロス防止警備、見守り・福祉との連携など、新しい社会価値を生む取り組みが、M&Aにおけるブランド評価にも大きな影響を及ぼすでしょう。
このように、経営課題に向き合いながら持続可能な戦略を描くことが、企業価値の向上とM&Aにおける評価向上の両面で極めて重要です。
まとめ:警備会社業界の行方とM&A戦略の重要性
2025年現在、警備業界は人材難・技術革新・法制度対応など複数の課題を抱えつつ、再編と成長を同時に進めるダイナミックな局面を迎えています。大手警備会社はIT・医療・介護といった他分野との融合によって多角化を推進し、中小企業は事業承継と地域基盤を活かしたM&Aによって、新たな道を模索しています。
このような業界構造の変化を前提としながら、警備会社に求められるのは、経営ビジョンの再設計と外部環境への柔軟な対応力です。単なる“安全”の提供から、社会インフラの一部としての存在へと進化する警備業の中で、M&Aはその進化を支える重要な手段となっています。
これからM&Aを検討する中小警備会社にとっては、「自社の価値をどう伝えるか」「誰に託すか」という戦略的視点が極めて重要です。逆に、買い手となる企業や投資家にとっても、警備会社は社会性・収益性の両面で有望な投資対象となりえます。
警備業界の未来を読み解き、自社の持つ価値を最大限に活かした選択ができるよう、本記事がその一助となれば幸いです。 M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。