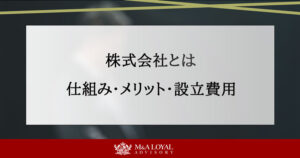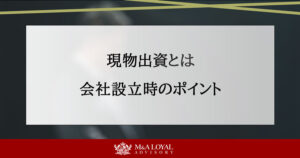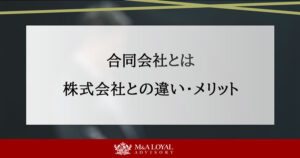合資会社とは?合同会社・株式会社との違いとメリットをわかりやすく
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
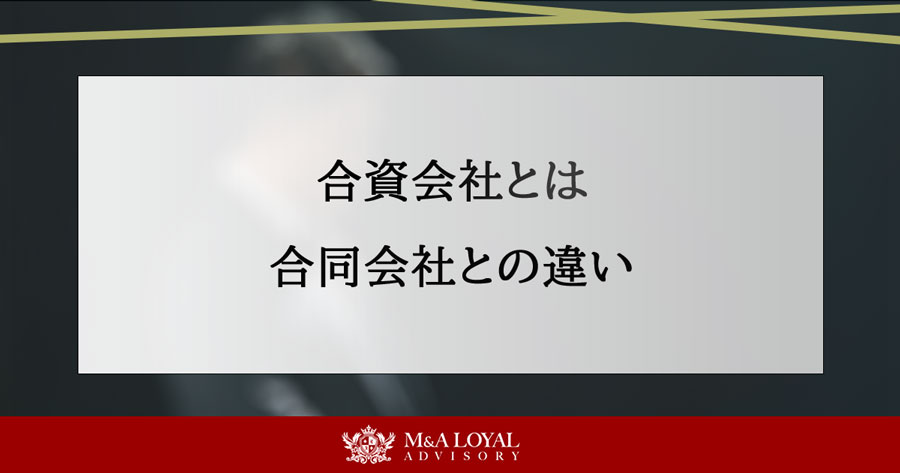
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される持分会社の一種です。株式会社や合同会社と比べて設立件数は少ないものの、低コストで定款自治の自由度が高い特徴を持っています。
中小企業のオーナーや事業承継を検討している方にとって、会社形態の選択は経営戦略上の重要な判断です。本記事では、合資会社の仕組みや他の会社形態との違い、メリット・デメリットを解説します。合資会社の特徴を理解し、事業承継やM&Aを見据えた経営判断の参考としてご活用ください。
目次
合資会社の定義
合資会社を正確に理解するためには、まず持分会社としての位置づけと、責任区分の仕組みを把握する必要があります。ここでは合資会社の定義と構造について解説していきます。
合資会社とは何か
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上、計2名以上で構成される持分会社です。持分会社とは、株式を発行せず、社員が出資持分を保有する会社形態を指します。会社法に基づく4つの会社形態のうち、合資会社は責任の異なる社員が混在する唯一の形態となっています。
- 株式会社:有限責任社員1名以上
- 合同会社:有限責任社員1名以上
- 合名会社:無限責任社員1名以上
- 合資会社:有限責任社員1名以上+無限責任社員1名以上
合資会社を含む持分会社の社員は、株式会社の従業員とは異なり、出資者であると同時に経営者でもあります。株式会社のように所有と経営が分離されていないため、意思決定をスピーディに行える特徴があります。この構造は小規模な事業や家族経営に適しています。
また、合資会社は法人格を持つため、個人事業主とは異なり、契約の主体や財産の所有者は会社自体となります。取引先や金融機関との関係においても、法人としての信用を活用できる点は重要です。
無限責任社員と有限責任社員の違い
合資会社の最大の特徴は、責任範囲の異なる2種類の社員で構成される点にあります。この責任区分を理解することが、合資会社を選択する際の重要な判断材料となります。
無限責任社員は、会社の債務について私財を含めた全財産で弁済する義務を負います。会社が倒産して負債が残った場合、出資額を超えても個人の資産で返済しなければなりません。この責任は連帯責任であり、債権者は任意の無限責任社員に全額を請求できます。
一方、有限責任社員は出資額を上限として責任を負います。会社が倒産しても、出資した金額以上の負担を求められることはありません。この点は株式会社の株主や合同会社の社員と同じ責任範囲です。
この二重構造により、資金を提供したいが経営リスクは限定したい投資家と、経営権を持ちたい事業家が協力する形態として活用できます。ただし現代では、リスク回避の観点から合資会社を選択するケースは極めて少なくなっています。
持分会社としての位置づけ
合資会社は合同会社、合名会社とともに持分会社に分類されます。持分会社は株式会社と対比される会社形態であり、その特徴を理解することで合資会社の性質がより明確になります。
持分会社の最大の特徴は、所有と経営が一致している点です。株式会社では株主総会で選任された取締役が経営を担いますが、持分会社では社員自身が業務を執行します。このため法定の機関設計や手続きが簡素化されており、運営コストや事務負担が軽減されます。
持分会社では定款自治の範囲が広く、議決権の配分や利益分配の方法を柔軟に設定できます。株式会社のように出資比率に応じた配当ではなく、社員間の合意に基づいて自由に利益配分を決められる点は、小規模事業における柔軟な運営を実現します。
また、持分の譲渡には原則として全社員の同意が必要です。この仕組みにより、望まない第三者が社員となることを防ぎ、信頼関係に基づいた事業運営を維持できます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



合資会社と株式会社・合同会社・合名会社との違い
会社形態を選択する際には、それぞれの特徴を比較検討することが重要です。ここでは合資会社と他の会社形態の違いを、設立要件、コスト、ガバナンス構造の観点から詳しく見ていきます。
会社形態別の出資者構成と責任範囲
各会社形態は出資者の構成と責任範囲によって明確に区別されます。この違いが経営リスクや資金調達の可能性に直接影響するため、事業の性質に応じた選択が必要です。
| 会社形態 | 出資者の構成 | 責任範囲 | 最低人数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 株主 | 有限責任 | 1名 |
| 合同会社 | 社員 | 有限責任 | 1名 |
| 合資会社 | 無限責任社員+有限責任社員 | 両者混在 | 各1名以上 |
| 合名会社 | 社員 | 無限責任 | 1名 |
株式会社と合同会社は全員が有限責任であるため、個人資産を保護しながら事業を展開できます。特に合同会社は設立コストも低いため、近年普及が進んでいます。2024年の設立件数は合同会社が41,774件に対し、合資会社は19件です。
合資会社を選択する場合は、必ず無限責任を負う社員が必要となるため、そのリスクを十分に理解した上での判断が求められます。合名会社も全員が無限責任を負うため、現代の事業環境ではほとんど選択されない形態です。
設立コストと手続きの比較
会社設立にかかる費用と手続きの負担は、会社形態によって大きく異なります。初期投資を抑えたい起業家にとって、この違いは重要な判断要素となります。
株式会社を設立する場合、定款の認証のために公証役場で手続きが必要です。この認証手数料として1.5万円~5万円、さらに謄本代として約2,000円が必要になります。加えて登録免許税は最低15万円かかるため、合計で約20万円以上の初期費用が発生します。
一方、合資会社を含む持分会社は定款認証が不要です。登録免許税も6万円となっており、株式会社の半分以下のコストで設立できます。電子定款を利用すれば印紙代4万円も節約できるため、実質的な費用はさらに抑えられます。
手続きの流れも持分会社の方が簡素です。定款を作成し、出資金を払い込み、登記申請を行うという基本的なステップは同じですが、公証役場での認証手続きがない分、時間も短縮されます。株式会社は設立に3週間程度が一般的ですが、持分会社の場合は2週間程度で設立が完了します。
意思決定とガバナンス構造の違い
会社の意思決定プロセスとガバナンス構造は、日常的な経営活動に直接影響します。事業規模や成長戦略に応じて、適切な構造を選択することが重要です。
株式会社では所有と経営が分離されており、株主総会が最高意思決定機関となります。取締役会を設置する場合は、重要事項の決定や業務執行の監督を取締役会が担います。この構造は、多数の株主や投資家から資金を調達し、専門経営者に経営を委ねる場合に適しています。
持分会社では所有と経営が一致しているため、社員総会での意思決定が原則となります。業務執行についても社員全員が権限を持つのが原則ですが、定款で業務執行社員を定めることで、実質的な経営者を限定することも可能です。
最高意思決定における議決権も、株式会社と持分会社では異なります。株式会社は原則として一株一議決権ですが、持分会社は原則として一人一議決権です。ただし定款で別段の定めをすれば、出資比率に応じた議決権配分も可能です。この柔軟性が、少人数での密接な協力関係を前提とした事業に適している理由です。
利益配分と議決権の設定
利益配分の方法は、事業パートナー間の関係性や貢献度の評価に直結します。会社形態によって設定できる自由度が異なるため、事業の実態に合わせた選択が求められます。
株式会社では、利益配分は原則として出資比率に応じて行われます。1,000万円出資した株主と100万円出資した株主では、配当金も10倍の差が生じます。この仕組みは公平性が高い一方で、実際の貢献度を反映しにくい側面があります。
持分会社では定款で自由に利益配分を決められます。出資額が少なくても、経営に多大な貢献をしている社員により多くの利益を配分することが可能です。例えば、資金提供者である有限責任社員が70%を出資し、実際の経営を担う無限責任社員が30%を出資している場合でも、定款で利益配分を50%ずつと定めることができます。
この柔軟性は、資金力と経営能力を持つ者が異なる場合に、双方の貢献を適切に評価する手段として機能します。ただし、配分方法は明確に定款に記載し、後の紛争を避けることが重要です。
合資会社のメリット
合資会社には他の会社形態にはない独自のメリットがあります。ここでは設立コスト、手続きの簡便性、定款自治の自由度、運営の柔軟性という4つの観点からメリットを詳しく解説します。
設立・維持コストが低い
起業時の資金負担を最小限に抑えることは、特に小規模事業者にとって重要な要素です。合資会社は設立コストの面で大きなメリットがあります。
合資会社の設立には資本金や定款認証が不要であり、公証役場での手続きとそれに伴う費用が一切かかりません。資本は現金以外にも、現物出資や労務出資も可能です。また、株式会社では必須となる定款認証手数料約5万円と謄本代が不要となるため、この時点で大きなコスト削減につながります。
登録免許税についても、合資会社は最低6万円で済みます。株式会社の場合は最低15万円必要となるため、この差額9万円も無視できない金額です。電子定款を利用すれば、紙の定款に必要な収入印紙代4万円も節約できるため、トータルの設立費用は6万円程度に抑えることが可能です。
設立後の維持コストも合資会社は有利です。株式会社では決算公告が義務付けられており、官報掲載なら約6万円、新聞掲載ならさらに高額な費用が毎年発生します。合資会社にはこの義務がないため、継続的なコスト負担も軽減されます。
設立手続きが簡便
事業をスタートする際、複雑な手続きや長期間の準備期間は機会損失につながります。合資会社は手続きの簡便性という点でも優れています。
合資会社の設立は基本的に3つのステップで完了します。まず定款を作成し、次に出資金を払い込み、最後に法務局で設立登記を申請するという流れです。株式会社のように公証役場での定款認証という中間ステップがないため、時間と手間が大幅に削減されます。
定款の作成も比較的自由度が高く、必要最低限の事項を記載すれば足ります。絶対的記載事項は、目的、商号、本店所在地、社員の氏名・住所、社員の責任区分、社員の出資の目的・価額などです。これらを明確にすれば、あとは事業の実態に合わせて柔軟に設定できます。
出資金の払込に関して、無限責任社員と有限責任社員によって方法が異なります。有限責任社員は金銭だけでなく現物出資も可能です。無限責任社員は金銭および現物出資に加えて、労務や信用を出資することもできます。
定款自治の自由度が高い
事業の実態や社員間の関係性は千差万別です。合資会社では定款によって、会社運営の多くの側面を自由に設計できる点が大きな魅力となっています。
業務執行の方法、利益配分の割合、持分譲渡の条件など、会社運営の根幹に関わる事項を定款で自在に設定できます。例えば、特定の社員にのみ業務執行権を与えたり、出資比率とは無関係に利益配分を決めたり、持分譲渡に必要な同意の範囲を調整したりすることが可能です。
議決権の配分も柔軟に設定できます。原則は一人一議決権ですが、定款で出資比率に応じた議決権や、特定の事項について特別な議決権を設けることもできます。これにより、資金提供者と経営者の役割分担を明確にしながら、それぞれの立場を尊重した運営が実現します。
定款変更についても、株式会社のような特別決議ではなく、原則として社員全員の同意で行えます。ただしこの点も定款で「過半数の同意」などと緩和することが可能です。事業環境の変化に応じて柔軟に会社の仕組みを調整できる点は、小規模事業における大きな強みとなります。
決算公告義務がない
会社運営における継続的なコストと手間を削減できることは、経営資源の限られた中小企業にとって重要な要素です。決算公告義務がない点は、合資会社の隠れたメリットと言えます。
株式会社は毎年の決算後、貸借対照表などの財務情報を公告する義務があります。官報掲載の場合でも約6万円、日刊新聞紙への掲載ならさらに高額な費用が発生します。電子公告を選択する場合も、調査機関への委託費用として年間数万円が必要です。
合資会社にはこの決算公告義務がありません。財務情報を外部に開示する必要がないため、公告費用が不要であるだけでなく、手続きの手間も省けます。経理担当者の業務負担軽減にもつながり、本業に集中できる環境が整います。
ただし、決算公告義務がないことは、取引先や金融機関に対する情報開示を拒否できるという意味ではありません。融資を受ける際や大口取引先との契約時には、財務情報の提出を求められることが一般的です。義務がないだけで、必要に応じた開示は適切に行うことが、信用構築の観点から重要です。
合資会社のデメリット
メリットだけでなくデメリットも正確に理解することが、適切な会社形態の選択には不可欠です。ここでは合資会社が抱える構造的な課題と、実務上直面する問題について解説します。
無限責任社員のリスク
合資会社の最大のデメリットは、無限責任社員が負う経済的リスクの大きさです。このリスクが、合資会社の選択を躊躇させる最大の要因となっています。
無限責任社員は会社の債務について、私財を含めた全財産で弁済する義務を負います。会社が倒産して債務が残った場合、出資額を大きく超える負担を個人で背負うことになります。例えば100万円を出資した無限責任社員でも、会社に3,000万円の負債があれば、その全額について弁済責任を負います。
この責任は連帯責任であるため、複数の無限責任社員がいる場合でも、債権者は任意の一人に対して全額を請求できます。他の社員が資力を失っていれば、一人の社員に負担が集中する可能性もあります。この構造は、信頼関係のある者同士でないと成立しにくい仕組みと言えるでしょう。
現代では個人保証を求められることも多く、中小企業経営者は既に相当のリスクを負っています。その上で法的に無限責任を負う立場を選択することは、よほどの理由がない限り合理的とは言えません。この点が、合資会社の設立件数が極めて少ない主な理由となっています。
株式発行・上場ができない
事業の成長段階に応じた資金調達手段の確保は、企業経営において重要な要素です。合資会社は資金調達の面で大きな制約を抱えています。
合資会社は持分会社であるため、株式を発行できません。したがって、合資会社は株式による資金調達や株式上場による大規模な資金獲得は構造的に不可能です。事業が成長し、まとまった資金が必要になった場合、銀行借入や社債発行、補助金など、株式会社と比較すると調達手段が限定されます。
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受ける場合も、合資会社では難しいケースがほとんどです。投資家は投資した資金を株式上場などで回収することを想定しているため、株式を発行できない会社形態では投資対象となりにくいのです。
合資会社が事業拡大を目指す場合、途中で株式会社への組織変更が必要となることもあります。組織変更には手続きとコストがかかるため、当初から成長を見込んでいるなら、株式会社または合同会社でスタートする方が合理的です。合資会社は、限定的な規模での事業継続を前提とする場合に適した形態と言えます。
社会的認知度の低さと信用面の課題
取引先や金融機関との関係構築において、会社形態が持つイメージは実務上無視できない要素です。合資会社は認知度の低さから、信用面で不利になる可能性があります。
2024年の統計では、合資会社の新規設立はわずか19件に過ぎません。対して合同会社は41,774件、株式会社に至っては年間10万件近くが新たに設立されています。この圧倒的な少なさが、合資会社に対する一般的な認知度の低さにつながっています。
取引先の与信審査では、会社形態も評価要素の一つとなります。担当者が合資会社について十分な知識を持っていない場合、説明に時間を要したり、誤解を招いたりする可能性があります。大企業との取引開始時には、会社形態について質問を受けることも少なくありません。
金融機関からの融資を受ける際も、合資会社であることがマイナス要因となる可能性があります。無限責任社員の存在は理論上は信用力を高める要素ですが、実際には会社形態自体の珍しさから、慎重な審査対象となることもあります。実績を積むまでは、信用構築に通常以上の努力が必要となるでしょう。
合同会社が主流となっている理由
現在の日本では、持分会社を選択する場合のほとんどが合同会社となっています。合資会社との設立件数の差は2,000倍以上に達しており、この圧倒的な違いには明確な理由があります。ここでは合同会社が支持される背景を解説します。
全社員が有限責任というメリット
合同会社が広く選ばれる最大の理由は、全社員が有限責任であるという安全性にあります。この特徴が、リスク管理を重視する現代の起業家に支持されています。
合同会社では、すべての社員が出資額を限度として責任を負います。会社が倒産しても、個人の住宅や預貯金などの私財まで差し押さえられることはありません。出資した金額を失うリスクはありますが、それ以上の負担は発生しないため、起業のハードルが大きく下がります。
この有限責任制は、複数人で事業を始める場合に特に重要です。共同出資者全員がリスクを限定できるため、安心して資金を出し合うことができます。合資会社のように、誰かが無限責任を引き受けなければならないという不公平感もありません。
家族経営や親族での事業承継を考える場合も、合同会社なら次世代に過大なリスクを引き継がせずに済みます。事業の失敗が子や孫の人生に致命的な影響を与えるリスクを回避できることは、長期的な事業計画において重要な要素です。
合資会社と同等のメリットを享受できる
合同会社は有限責任というメリットを持ちながら、合資会社が持つコスト面や柔軟性の利点もほぼ同様に享受できます。この「いいとこ取り」の構造が、合同会社の人気を支えています。
設立コストは合資会社と同じく低く抑えられます。定款認証は不要で、登録免許税も6万円からと、株式会社の半分以下です。電子定款を利用すれば、さらにコストを削減できます。設立手続きも簡素で、公証役場を経由せずに法務局への登記申請だけで完了します。
定款自治の自由度も合資会社と同等です。業務執行社員を定めて経営者を限定したり、利益配分を出資比率と無関係に設定したり、議決権の配分を柔軟に決めたりすることが可能です。小規模な事業で求められる柔軟性は、合同会社でも十分に実現できます。
決算公告義務がない点も同じです。毎年の公告費用や手続きの手間が不要であり、経営資源を本業に集中できます。つまり、合同会社は合資会社のメリットをほぼすべて備えながら、無限責任というデメリットを回避できる形態なのです。
設立件数から見る選択の実態
統計データは、実務における選択の実態を明確に示しています。2024年の数字を見ると、合同会社と合資会社の間には歴然とした差があります。
2024年に設立された合同会社は41,774件に達しました。一方、合資会社はわずか19件(総数2,853件)に過ぎません。この2,000倍以上の差は、両者の実用性や選択メリットの違いを如実に表しています。株式会社(98,671件)と比較しても、合同会社は約4割の設立件数を誇り、新しい会社形態として完全に定着しています。
合資会社が選ばれる19件のケースは、特殊な事情があると推測されます。既存の合資会社からの事業承継、特定の業界慣習、または法的・税務的な特別な理由などが考えられます。新規に起業する場合や通常の事業承継では、合資会社を選択する合理的理由は見出しにくいのが実情です。
この傾向は今後も続くと予想されます。会社法が施行された2006年以降、合同会社の認知度は着実に高まっており、アマゾンジャパンやApple Japan、P&Gジャパンなど、大企業の日本法人でも合同会社形態を採用する事例が増えています。こうした実績が、合同会社の信頼性をさらに高めています。
まとめ
合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成される持分会社であり、低コストで高い定款自治を実現できる会社形態です。設立費用は約6万円から、定款認証も不要で手続きが簡便、決算公告義務もないなど、中小規模の事業運営に適した特徴を持っています。しかし無限責任社員が私財まで含めた責任を負うリスク、株式発行による資金調達ができない制約、社会的認知度の低さなどのデメリットがあります。
現代では合同会社が持分会社の主流となっており、2024年の設立件数は合同会社41,774件に対し合資会社は19件です。合同会社は全社員が有限責任でありながら、合資会社と同等の低コスト・高い自由度を実現できるため、多くの起業家に選ばれています。
会社形態の選択は、事業の将来性や資金調達計画、リスク管理の観点から総合的に判断する必要があります。特に合資会社の事業承継を検討する際には、無限責任のリスクを次世代に引き継がせないために、合同会社や株式会社への組織変更を考慮することをおすすめします。
M&Aや事業承継に関するご相談や具体的なアドバイスをお求めの方は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーまでお問い合わせください。経験豊富なアドバイザーが貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。