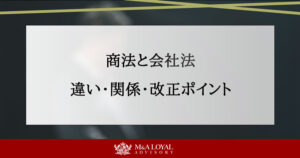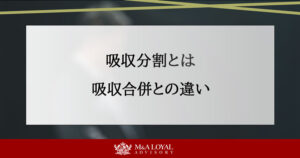労働契約承継法とは?会社分割で失敗しない手続きの流れも解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
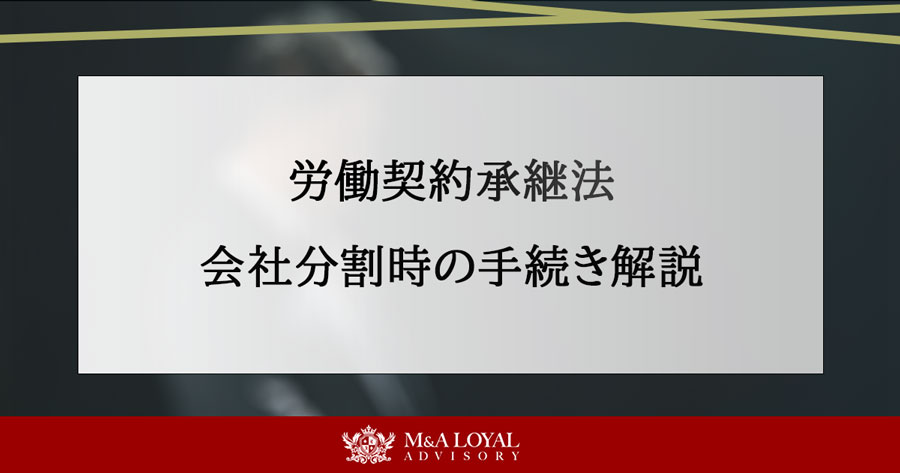
労働契約承継法とは、事業承継の中でも会社分割時の従業員の引継ぎに関する規定を定めた法律です。中小企業のM&Aにおいて会社分割を検討する際、労働契約承継法の適切な理解と遵守は成功の鍵を握る重要な要素です。この法律は労働者の権利を守るために制定されており、手続きを怠ると会社分割が無効となるリスクも潜んでいます。
近年、事業承継や組織再編のニーズが高まる中で、労働契約承継法への対応が不十分なために思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。特に中小企業では、限られたリソースの中で複雑な法的手続きを進める必要があるため、事前の準備と正確な知識が不可欠です。
本記事では、労働契約承継法の全体像から具体的な手続きの流れ、実務上の注意点まで、会社分割を成功に導くために必要な情報を体系的に解説します。
目次
労働契約承継法の基本を理解する
労働契約承継法は、中小企業のM&Aや企業再編において会社分割を実施する際に必ず理解しておくべき重要な法律です。この法律は労働者の権利を守るために制定されており、適切な手続きを経ずに会社分割を進めると重大な法的リスクを招く可能性があります。ここでは、労働契約承継法の基本的な概要について詳しく解説します。
労働契約承継法が制定された背景と目的
労働契約承継法(正式名称:会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)は、平成12年に制定された法律です。この法律が制定された背景には、会社法における会社分割制度の導入があります。会社分割では、分割会社の権利義務が承継会社に包括的に承継されるため、労働者の労働契約も自動的に移転する仕組みとなっています。
この法律制定の直接的な背景には、2000年の商法改正(現・会社法)による会社分割制度の導入があります。会社分割では、事業に関する権利義務が承継会社へ包括的に移転するため、労働者の個別同意なく労働契約が承継され得ることになりました。これは従来の労働法の原則とは異なるため、この新しい枠組みの中で労働者の雇用と労働条件を保護するための特別な手続きを定める目的で、本法が制定されました。
この法律の主な目的は、会社分割によって労働者の雇用関係が変更される際に、労働契約の承継を確実に行い、労働者が不利益を被らないようにすることです。
労働契約承継法の対象となる労働者の範囲
労働契約承継法の対象となるのは、分割会社が雇用している全ての労働者です。この範囲は非常に広く、正社員だけでなく契約社員、パートタイム労働者、アルバイトなど、雇用形態に関わらず分割会社と労働契約を締結している全ての労働者が含まれます。
また、労働者の職種や勤続年数、労働時間の長短なども問わず、分割会社に雇用されている限り労働契約承継法の保護対象となります。この包括的な対象範囲により、会社分割時における労働者の権利が幅広く保護されているのです。
会社分割における労働契約承継法の重要性
会社分割を実施する中小企業にとって、労働契約承継法の遵守は極めて重要です。
この法律の手続きに違反した場合、特に5条協議を怠ったり不十分に実施したりすると、影響を受けた個々の労働者が、自らの労働契約の承継の効力を争うことが可能になります。これにより、承継されるはずの労働者が会社に残留したり、残留するはずの労働者が承継されたりする事態が生じ、計画通りの人員配置ができなくなるという重大な運営上のリスクを招きます。
労働契約承継法は全8条で構成されており、主要な内容は以下の通りです。
- 目的:労働者保護のための制度趣旨
- 労働者への通知義務:書面による事前通知
- 労働契約の承継規定:承継条件と手続き
- 労働協約の承継:団体との合意事項
- 理解協力手続き:全労働者への説明義務
これらの規定を適切に理解し、実務に反映させることで、労働者とのトラブルを回避し、円滑な会社分割を実現することができます。
中小企業のM&Aにおいては、労働契約承継法を遵守することで労働者の不安を軽減し、事業承継後の組織運営を安定させる効果も期待できます。そのため、会社分割を検討する際には、早期段階から労働契約承継法の要件を満たすための準備を進めることが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



労働契約承継法における会社分割の種類と取扱い
会社分割には複数の手法があり、それぞれで労働契約承継法の適用方法や労働者への影響が異なります。中小企業のM&Aを成功させるためには、各分割方法の特徴を理解し、自社の状況に最適な手法を選択することが重要です。
吸収分割・新設分割における労働者への影響
吸収分割は既存の会社に事業を承継させる方法で、新設分割は新たに設立する会社に事業を承継させる方法です。どちらの方法を選択するかによって、労働者への影響や手続きの複雑さが変わります。
吸収分割では、承継先企業が既に存在するため、労働者にとって転籍先の会社概要や労働条件を事前に把握しやすいメリットがあります。一方で、承継先企業の既存労働者との労働条件の統一や組織文化の融合に課題が生じる可能性があります。新設分割では、新たに設立される会社での労働条件を柔軟に設計できる反面、労働者にとって転籍先の不透明性が不安要因となりやすいです。
労働契約承継法の観点では、どちらの分割方法でも労働者保護のための基本的な手続きは同じですが、新設分割の場合は新会社設立のタイミングと労働契約承継の調整が必要になります。
人的分割・物的分割の違いと労働契約の取扱い
人的分割と物的分割は、会社分割の対価を誰が受け取るかによって区別されます。人的分割では分割会社の株主が対価を受け取り、物的分割では分割会社自体が対価を受け取ります。
労働契約承継法の適用の観点からは、本法が定める手続き(7条措置、5条協議、2条通知)は、事業の承継とそれに伴う労働契約の移転があるかどうかによって決まるため、どちらの分割方法でも等しく適用されます。
人的分割の場合、承継会社の株主構成が変化するため、経営方針の変更により労働条件に影響が及ぶ可能性があります。物的分割では、分割会社が承継会社の株主となるため、比較的安定した雇用関係を維持しやすい傾向があります。
どちらの分割方法でも、労働契約承継法で定められた7条措置、5条協議、2条通知の手続きを適切に実施することで、労働者の不安を軽減し、円滑な事業承継を実現できます。なお、2006年の会社法改正により、人的分割は廃止され、物的分割に一本化されました。
中小企業のM&Aで選ぶべき会社分割の方法
中小企業のM&Aにおいて最適な会社分割の方法を選択する際は、以下の要因を総合的に考慮する必要があります。
承継先企業との関係性では、既存の取引先や関係会社への事業承継であれば吸収分割が適しており、独立性を重視した事業分離であれば新設分割が有効です。また、買収資金の調達可能性も重要な判断材料となります。現金での買収が困難な場合は、株式を対価とした会社分割が現実的な選択肢となります。
労働者への配慮という観点では、雇用の継続性と安定性を最優先に考えることが重要です。労働者の多くが承継先での継続勤務を希望する場合は吸収分割を、一部の労働者が独立した環境での勤務を希望する場合は新設分割を検討します。いずれの場合も、労働契約承継法に基づく十分な説明と協議を通じて、労働者の理解と協力を得ることが成功の鍵となります。
労働契約承継法に基づく会社分割手続きの流れ
会社分割を成功させるためには、会社法に定められた手続きと労働契約承継法に基づく労働者保護手続きを適切なタイミングで実施することが不可欠です。手続きの順序を間違えると法的リスクが生じるため、詳細なタイムラインに沿って進める必要があります。
吸収分割における手続きの期間
吸収分割では、分割会社と承継会社との間で吸収分割契約を締結する必要があるため、契約交渉のプロセスが含まれます。まず分割の基本方針について両社で基本合意を締結し、秘密保持契約を結んだ後、具体的な分割条件の協議に入ります。
労働契約承継法に関する手続きは、契約締結前の早期段階から開始する必要があります。
労働契約承継法に関する手続きは、それぞれが関連し合っており、統合されたプロセスとして進める必要があります。一般的に、まず7条措置として全労働者への説明を開始し、プロセスを通じて継続します。並行して、対象労働者とは5条協議を個別に行い、これは2条通知の期限日までに完了させる必要があります。そして、協議がある程度進んだ段階で、2条通知として労働者へ書面で正式に通知します。これらは厳格なステップではなく、相互に連携させながら進めることが重要です。
その後、株主総会での承認決議、債権者保護手続き、反対株主の買取請求対応を経て、最終的に分割の効力が発生します。会社分割の手続きには約2ヶ月程度、早いと1.5ヶ月で終わることもあります。
新設分割における手続きのタイムライン
新設分割では承継先企業が存在しないため、分割会社単独で新設分割計画を作成することから手続きが始まります。吸収分割と比較して、新たに法人を設立する必要があるため、手続きが煩雑となる傾向があります。
労働契約承継法に関する手続きは吸収分割と基本的に同じですが、新設される会社の概要や労働条件について労働者に十分な説明を行う必要があります。7条措置では新設会社での勤務条件や将来展望について詳細に説明し、5条協議では労働者の不安や疑問に丁寧に対応することが重要です。
新設分割計画の作成と並行して労働者との協議を進め、計画の承認後に2条通知を実施します。株主総会での承認決議を経て分割の効力が発生すると同時に新会社が設立され、対象労働者の労働契約が新会社に承継されます。新設分割では会社設立手続きも含むため、登記申請などの事務手続きにも十分な時間を確保する必要があります。
手続きにおける労働契約承継法の位置づけ
労働契約承継法に基づく手続きは、会社分割の成否を左右する重要な要素です。特に5条協議は労働者との個別協議であり、この手続きを怠ったり不十分に実施したりすると、労働契約の引継ぎが無効となるリスクがあります。
手続きの実施にあたっては、形式的な対応にとどまらず、労働者の理解と納得を得ることに重点を置く必要があります。協議の記録を適切に残し、労働者からの質問や要望に対して誠実に対応することで、トラブルの発生を防ぐことができます。また、労働組合が存在する場合は、労働組合との協議も並行して進め、団体交渉の申し入れがあれば誠意をもって対応しなければなりません。
中小企業のM&Aにおいては、労働者との信頼関係の維持が事業承継後の成功に直結するため、労働契約承継法の手続きを通じて労働者の不安を解消し、新体制への協力を得ることが極めて重要です。
労働契約承継法で定められた3つの重要手続き
労働契約承継法では、会社分割時に労働者を保護するための3つの重要な手続きが定められています。これらの手続きは相互に関連しており、適切な順序とタイミングで実施することが法的リスクの回避と円滑な事業承継の実現に不可欠です。
7条措置:全労働者の理解と協力を得る努力義務
7条措置は労働契約承継法第7条に基づく手続きで、分割会社が雇用する全労働者の理解と協力を得るよう努める義務を定めています。この措置は努力義務とされていますが、会社分割手続きの前提となる重要な手続きです。
具体的な実施方法として、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協議を行います。協議では会社分割を行う背景や理由、分割の概要、労働者への影響などについて詳細に説明し、理解を求めます。
7条措置の実施にあたっては、説明会の開催、質疑応答の機会提供、個別相談窓口の設置などの方法が効果的です。形式的な説明に留まらず、労働者の不安や疑問に真摯に対応し、十分な理解を得ることが重要です。この手続きは5条協議を開始する前までに開始し、その後も必要に応じて継続的に実施する必要があります。
5条協議:対象労働者との個別協議の実施方法
5条協議は平成12年商法等改正法附則第5条に基づく協議で、労働契約承継法と密接に関連する重要な手続きです。対象となるのは承継される事業に従事している労働者と、主従事労働者以外で分割契約等に労働契約承継の定めがある労働者です。
協議では会社分割後の勤務先、労働契約の履行見込み、業務内容の変更などについて労働者に十分説明し、本人の意見を聴取します。その上で労働契約の承継の有無や今後の処遇について協議を行います。協議は一方的な説明ではなく、労働者の希望や懸念を十分に聞き取り、可能な限り労働者の意向を尊重する姿勢が求められます。
5条協議の実施時期は2条通知の通知期限日までに十分な協議ができるよう、余裕をもって開始する必要があります。協議内容については書面による合意書の作成は義務付けられていませんが、後のトラブルを避けるため、協議の内容や結果を書面で記録しておくことが推奨されます。この協議を怠ると会社分割の無効原因となる可能性があるため、特に注意深く実施する必要があります。
2条通知:書面による通知の内容と期限
2条通知は労働契約承継法第2条に定められた書面による通知義務で、対象労働者に対して会社分割の具体的内容を正式に通知する手続きです。通知の対象となるのは承継事業主要従事労働者、承継事業非従事労働者、そして労働協約を締結している労働組合です。
通知には以下の事項を明記する必要があります。
- 分割契約等における労働契約承継の定めの有無
- 労働者が主従事労働者に該当するか否か
- 異議申出期限日とその手続き方法
- 労働条件の維持に関する説明
- 承継先企業の概要と予定業務内容
これらの情報は労働者が異議申立てを行うかどうかの判断材料となるため、正確かつ詳細に記載することが重要です。
2条通知の通知期限は、株主総会承認が必要な場合は株主総会開催日の2週間前の日の前日まで、承認が不要な場合は分割契約が締結された日又は分割計画が作成された日から起算して、2週間を経過する日までと定められています。
期限を過ぎてからの通知は法律違反となり、労働者は会社分割後に地位の確認や保全を求めることができるため、期限の管理は厳格に行う必要があります。2条通知は7条措置と5条協議を適切に実施した後に行うため、これらの手続きとの連携とタイミングの調整が重要になります。
労働契約承継法における労働者の異議申立て制度
労働契約承継法では、会社分割によって労働者が不利益を被ることを防ぐため、異議申立て制度が設けられています。この制度は労働者の重要な権利であり、適切に理解し運用することで労働者保護と円滑な事業承継の両立を図ることができます。
異議申立てができる労働者の条件
異議申立てができる労働者の権利は、労働契約承継法第4条と第5条に明確に定められています。具体的には、承継される事業に主として従事する労働者(主従事労働者)が分割会社に残留する旨の定めがある場合と、承継される事業に主として従事していない労働者(非主従事労働者)が承継会社等に承継される旨の定めがある場合です。
主従事労働者に該当するかどうかは、分割契約の締結日または作成日時点で、承継事業を主に担っているかどうかで判断されます。複数の事業に従事している場合は、それぞれの事業に従事している時間や役割、業務の量や質などから総合的に判断されます。この判断は承継される事業ごとに行われるため、複数事業が分割される場合は事業ごとに検討が必要です。
異議申立てができる根拠は、労働者が慣れ親しんだ業務から強制的に引き離されることを防ぐためです。主従事労働者が元の会社に残ることや、非主従事労働者が新しい会社に移ることは、その労働者にとって大きな環境変化を意味するため、労働者自身の意思を尊重する制度として設けられています。
異議申立ての手続きと期限
異議申立ては書面により行う必要があり、厚生労働省が提供する「異議申出書」の様式を使用するのが一般的です。申立書には労働者の氏名、所属部署、異議の内容、申立ての理由などを明記し、分割会社に提出します。
異議申出期限日は分割会社が設定しますが、2条通知がなされた日から13日間以上の期間を置く必要があります。株主総会承認が必要な場合は通知日から株主総会開催日の前日まで、承認が不要な場合は分割効力発生日の前日までの範囲内で設定されます。この期限は厳格に管理されており、期限を過ぎてからの異議申立ては受理されません。
企業側は異議申立ての手続きについて労働者に十分説明し、申立てを希望する労働者が適切に権利を行使できるよう配慮する必要があります。また、異議申立てがあったからといって、当該労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。異議申立ての検討期間を確保するため、早期からの情報提供と丁寧な説明が重要です。
異議申立てがあった場合の法的効果
異議申立てがあった場合の法的効果や範囲も労働契約承継法で定められています。主従事労働者が分割会社に残留する旨の定めに対して異議を申し出た場合、その労働者の労働契約は労働条件を維持したまま承継会社等に承継されます。これにより、労働者は慣れ親しんだ事業と共に新しい会社で勤務することができます。
一方、非主従事労働者が承継会社等に承継される旨の定めに対して異議を申し出た場合、その労働者は労働条件を維持したまま分割会社に残留することができます。この場合、労働者は環境変化を避けて元の会社で継続勤務することが可能になります。
異議申立ての効果は会社分割の効力発生と同時に生じるため、申立てがあった労働者については分割契約等の記載に関わらず、異議の内容に従った労働契約の承継または残留が実現されます。企業は異議申立てがあった労働者について、人員配置や組織運営の計画を見直す必要があります。
また、異議申立てにより予定していた人員配置が変更になる場合は、関係部署との調整や追加の人員確保などの対応が必要になることもあります。中小企業のM&Aにおいては、このような変更への柔軟な対応が円滑な事業承継の鍵となります。
労働契約承継法と労働組合への対応
労働組合が存在する企業で会社分割を実施する場合、労働契約承継法に基づく特別な手続きと配慮が必要です。労働組合は労働者の代表として重要な役割を果たすため、適切な対応を行うことで労使関係を維持し、円滑な事業承継を実現することができます。
労働組合への事前通知と団体交渉
労働契約承継法では、分割会社との間で労働協約を締結している労働組合に対して、2条通知を行うことが義務付けられています。通知には承継会社等が承継する労働協約の内容を記載した書面を用いる必要があり、この通知を事前通知と呼びます。通知の内容には労働契約の承継に関する事項に加えて、労働協約がどのように承継されるかについても詳細に記載します。
分割会社との間で労働協約を締結していない労働組合であっても、通知後の団体交渉の進展によって労働協約が締結される可能性があることから、通知することが望ましいとされています。実務上は、すべての労働組合に対して通知を行うことでトラブルを未然に防ぐことができます。
労働組合から会社分割によって発生する労働条件の変更等に関する団体交渉の申入れがあった場合、分割会社は必ずこれに応じなければなりません。承継指針では「労働組合と誠意をもって交渉に当たらなければならない」と明記されており、形式的な対応では不十分です。交渉では会社分割の必要性、労働者への影響、今後の労働条件などについて十分に説明し、労働組合の理解を得るよう努力する必要があります。
労働協約の承継に関する注意点
労働協約の承継については、その内容に応じて取扱いが異なります。労働協約の債務的部分については、分割契約等に記載することで承継会社等に引き継ぐことができますが、分割会社と労働組合の間で合意があることが前提となります。債務的部分とは、ユニオンショップ協定、組合事務所の設置、団体交渉の規定、非組合員の範囲などの使用者と労働組合間の個別ルールを指します。
一方、賃金や労働時間などの規範的部分や、債務的部分のうち労使間の合意がされない部分については、当該労働組合員の労働契約が承継されれば、承継会社でも同一の労働協約が締結されたとみなされます。この結果、承継会社には既存の労働協約と分割会社の労働協約の両方が併存する可能性があります。
複数の労働協約が併存する状況では、労働条件が異なる労働者が同一会社内に混在することになります。この場合、承継会社は将来的な労働条件の統一や労働組合間の調整について慎重に検討する必要があります。中小企業においては、このような複雑な労使関係の管理が事業運営に大きな影響を与える可能性があるため、会社分割の計画段階から労働組合との十分な協議を行い、可能な限り労働条件の統一や組織の簡素化を図ることが重要です。
参考:会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)の概要
労働契約承継法違反のリスクと対策
労働契約承継法に違反した場合、会社分割手続きの無効化や労働者からの法的請求など深刻なリスクが発生します。中小企業のM&Aにおいては、これらのリスクが事業承継計画全体の破綻につながる可能性があるため、適切な予防策と対処法を理解することが極めて重要です。
労働契約承継法違反による会社分割無効のリスク
労働契約承継法違反の中で最も深刻なリスクは、5条協議違反による会社分割手続きの無効化です。5条協議は対象労働者との個別協議を定めた規定であり、この協議を怠ったり不十分に実施したりした場合、裁判所によって会社分割自体が無効と判断される可能性があります。会社分割が無効となれば、これまでの手続きがすべて無駄になり、M&Aや組織再編の計画が完全に破綻することになります。
5条協議違反の判断基準は明確に示されていませんが、協議内容の不十分さ、協議時間の短さ、労働者の意見を聞く姿勢の欠如などが問題となります。特に形式的な説明のみで労働者の質問や懸念に対応しなかった場合や、一方的に会社の方針を伝えるだけで真の協議を行わなかった場合は、協議違反と認定されるリスクが高くなります。
7条措置違反については努力義務違反に留まるため、直接的に会社分割の効力に影響を与えることはありませんが、5条協議の十分性を判断する際の考慮要素となります。2条通知違反の場合は、通知を受けなかった労働者が会社分割後に承継会社に対して地位の保全や確認を求めることができ、組織運営に混乱をもたらす可能性があります。
労働契約承継法違反を防ぐ5つの実務対策
労働契約承継法違反を防ぐための実務対策として、以下の5つのポイントが重要です。
- 早期からの手続き開始:会社分割の検討段階から労働契約承継法の要件を意識し、十分な時間を確保して手続きを進めます。急いで手続きを進めると協議が不十分になりがちです。
- 十分な協議期間の確保:5条協議では労働者一人一人と丁寧に協議する時間を確保し、労働者の不安や疑問に真摯に対応します。複数回の協議が必要な場合もあります。
- 詳細な記録の保持:すべての協議内容、通知の実施状況、労働者の反応などを詳細に記録し、適切な手続きを実施したことを証明できるようにします。
- 専門家との連携:労働法に精通した弁護士やM&Aアドバイザーと連携し、手続きの適法性を確認しながら進めます。
- 労働者目線での配慮:労働者の立場に立って情報提供や説明を行い、一方的な通告ではなく対話を重視した姿勢で臨みます。
労働契約承継法違反が発覚した場合の対処法
労働契約承継法違反が発覚した場合は、迅速かつ適切な対応が必要です。まず、違反の内容と範囲を正確に把握し、影響を受ける労働者を特定します。その上で、不足していた手続きを補完するための措置を講じます。
5条協議が不十分だった場合は、対象労働者と改めて十分な協議を行い、これまでの説明不足を補います。2条通知に漏れがあった場合は、該当する労働者に対して遅滞なく正式な通知を行います。ただし、これらの事後措置では完全なリスク回避は困難な場合もあります。
重大な違反が発覚した場合は、会社分割手続きの一時停止や見直しを検討する必要があります。場合によっては、労働者との間で和解契約を締結し、法的紛争を回避する方法も考えられます。いずれの場合も、労働法とM&Aの両方に精通した専門家の助言を得て、最適な解決策を見つけることが重要です。違反の早期発見と迅速な対応により、事業承継への影響を最小限に抑制することが可能になります。
まとめ:労働契約承継法を遵守した円滑な会社分割の実現
労働契約承継法は、中小企業のM&Aにおける会社分割を成功に導くための重要な法的基盤です。この法律を適切に理解し遵守することで、労働者の権利を保護しながら円滑な事業承継を実現することができます。
労働契約承継法で定められた7条措置、5条協議、2条通知の3つの手続きは、それぞれが労働者保護の重要な役割を果たしています。これらの手続きを形式的に実施するのではなく、労働者の理解と協力を真に得ることを目指して丁寧に進めることが成功の鍵となります。特に5条協議については、協議違反が会社分割の無効原因となる可能性があるため、十分な時間と労力をかけて実施する必要があります。
異議申立て制度や労働組合への対応についても、労働者の権利を尊重する姿勢で臨むことが重要です。異議申立てがあった場合でも、それを労働者の当然の権利として受け入れ、柔軟に対応することで信頼関係を維持できます。労働組合が存在する場合は、早期から情報共有と協議を行い、労使協調の下で会社分割を進めることが効果的です。
中小企業のM&Aにおいては、労働契約承継法の遵守が単なる法的義務にとどまらず、事業承継後の組織運営や企業文化の継承にも大きく影響します。労働者の不安を解消し、新体制への協力を得ることで、M&A後のシナジー効果を最大化することが可能になります。そのためには、会社分割の検討段階から労働契約承継法の要件を考慮し、十分な準備期間を確保することが不可欠です。
労働契約承継法を遵守した円滑な会社分割を実現するためには、労働法とM&Aの両方に精通した専門家のサポートを得ることを強く推奨します。複雑な法的手続きと労働者との繊細なコミュニケーションを両立させるには、豊富な経験と専門知識が必要だからです。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。