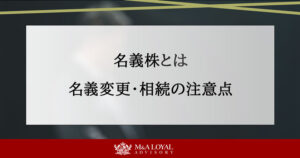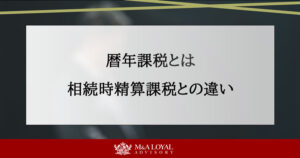株式の相続手続き|評価方法や相続税の計算ををわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
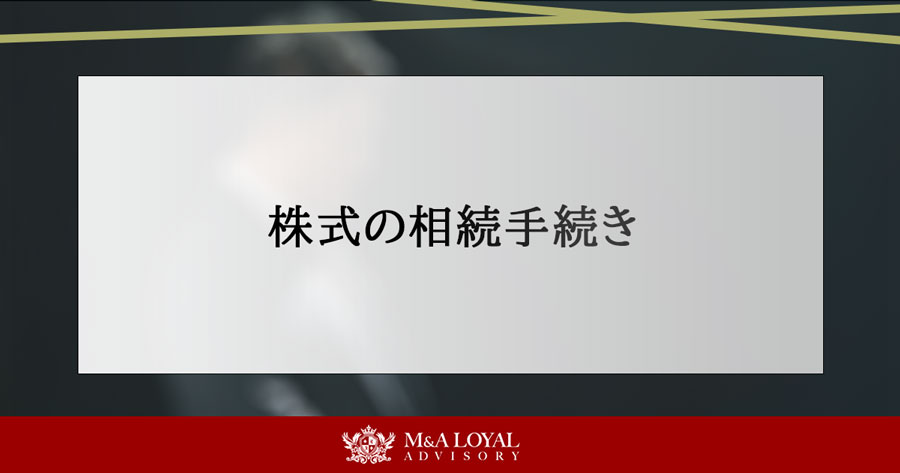
株式を相続する際は、上場株式と非上場株式で手続きや評価方法が大きく異なります。相続人の確定から遺産分割協議、証券会社での名義変更まで、複数のステップを適切に踏む必要があります。本記事では、株式相続に必要な手続きや注意点を分かりやすく解説し、相続トラブルを避けるためのポイントをご紹介します。
目次
株式の相続とは?基本知識をわかりやすく解説
株式相続を円滑に進めるためには、まず基本的な仕組みを理解し、必要な準備を整えることが重要です。株式相続は現金相続とは異なる複雑な手続きが必要になるため、事前の準備が成功の鍵を握ります。
株式の相続の基本的な仕組み
株式の相続とは、被相続人が保有していた株式を相続人が引き継ぐ手続きのことです。株式相続では、上場株式と非上場株式で手続きや評価方法が大きく異なるため、保有株式の種類を正確に把握することが必要です。上場株式の場合は証券取引所での市場価格があるため評価が比較的簡単ですが、非上場株式の場合は専門的な評価が必要になります。
また、株式の相続には「現物分割」「換価分割」「代償分割」という3つの方法があります。現物分割は株式をそのまま相続人が引き継ぐ方法、換価分割は株式を売却して現金化してから分配する方法、代償分割は一人の相続人が株式を取得して他の相続人に現金等で代償を支払う方法です。
株式相続開始前に確認すべき重要事項
株式相続の手続きを始める前に、相続財産の全体像を正確に把握することが必要です。まずは被相続人が保有していた株式の詳細を確認しましょう。証券口座の取引残高報告書や株式証明書を通じて、保有銘柄、株数、取得価格、取得時期を調べます。
次に、遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書がある場合は、株式の相続に関する具体的な指示があるかを確認し、遺言執行者が指定されているかも調べます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
さらに、株式以外の相続財産も併せて確認し、相続税の概算を把握しておくことが大切です。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数で計算されるため、この金額を超える場合は相続税申告が必要になります。
相続人の確定と必要書類の準備
株式相続手続きを進めるためには、まず相続人を正確に確定する必要があります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を漏れなく特定します。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合は第一順位、子がいない場合は直系尊属(父母など)が第二順位、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
必要書類の準備も並行して進めましょう。一般的に必要となる書類には以下があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
- 株式口座の取引残高報告書
- 株券(券面株式の場合)
これらの書類は名義変更手続きに必要なため、早めに準備することで手続きを円滑に進められます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



上場株式の相続手続き
上場株式の相続は、証券取引所で日々取引されているため市場価格での評価が可能で、比較的手続きが分かりやすいのが特徴です。ただし、証券会社での名義変更手続きや相続税評価には独特のルールがあるため、正確な理解が必要です。
証券会社での名義変更手続き
上場株式を相続する場合、まず被相続人が口座を開設していた証券会社に相続の事実を連絡し、相続手続きを開始します。証券会社から相続に関する書類一式が送付されるので、必要事項を記入して提出します。証券会社によって必要書類や手続きの流れが若干異なるため、早めに連絡を取って具体的な手続き方法を確認することが重要です。
遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが完了してから証券会社に提出します。遺言書がない場合は、相続人全員で署名・押印した遺産分割協議書が手続き方法の一つとして挙げられます。遺産分割協議書には、どの相続人がどの株式をどれだけ相続するかを明確に記載する必要があります。
相続により上場株式を取得した場合、名義変更手続きが完了すると、相続人がすでに同じ証券会社に自分名義の証券口座を持っている場合、被相続人の株式はその口座に移管されます(口座自体の名義変更は行われません)。複数の相続人が上場株式を相続する場合、証券口座を持っていない相続人は、それぞれが証券口座を新たに開設する必要があります。
上場株式の相続税評価額の計算方法
上場株式の相続税評価は、相続開始日(被相続人の死亡日)における株価をもとに計算されます。ただし、株価は日々変動するため、相続人にとって有利になるよう、複数の価格から最も低い価格を採用できる仕組みになっています。
具体的には、以下の4つの価格のうち最も低いものを評価額として採用します。
| 評価基準 | 計算方法 |
|---|---|
| 相続開始日の終値 | 死亡日の終値×保有株数 |
| 相続発生月の毎日の終値の平均額 | 死亡した月の終値平均×保有株数 |
| 相続発生月前月の毎日の終値の平均額 | 前月の終値平均×保有株数 |
| 相続発生月前々月の毎日の終値の平均額 | 前々月の終値平均×保有株数 |
参考:国税庁|上場株式の評価
上場株式の相続税評価においては、相続開始日が土曜・日曜・祝日など証券取引所の休場日にあたる場合、その日の終値は存在しないため、直前または直後の取引日の終値を用いるのが一般的であり、3連休中であれば前後の終値の平均を採用することもあります。
評価基準の一つである月平均終値については、相続開始日の属する月の取引日ごとの終値平均、あるいは課税時期の属する月の終値平均を用い、日本取引所グループが公表する月間相場表で確認できます。さらに、上場株式の評価は複数の基準価格のうち最も低い価格を選択してよいとされており、この仕組みにより相続財産の評価額を抑え、結果的に相続人の税負担を軽減することが可能です。
売却時の税務上の取り扱い
相続した上場株式を売却する場合、譲渡所得に対して20.315%の税金がかかります。譲渡所得は以下の計算で算出します。
| 譲渡所得=株式の売却益-(取得費+売却時の手数料) |
取得価格は、相続開始時の時価(相続税評価額)ではなく、被相続人が実際に株を購入した費用を引き継ぐのが原則です。ただし、取得価格が不明な場合は、売却価格の5%を取得価格とみなして計算します。
相続した株式の売却による譲渡所得は申告分離課税の対象となり、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%の合計20.315%の税率が適用されます。売却時期によっては大きな利益が出る可能性もあるため、税務上の影響を慎重に検討してから売却を決定することが重要です。
非上場株式の相続手続き
非上場株式の相続は、上場株式と比べて手続きが複雑で、評価方法も専門的な知識が必要になります。市場価格がないため、会社の規模や特性に応じて適切な評価方式を選択し、正確な評価額を算出する必要があります。
非上場株式特有の手続きと注意点
非上場株式を相続した場合、まず会社に連絡して株主名簿の名義変更を行います。名義変更には株券や請求書、相続人の印鑑証明書などが必要になることがあります。相続による株式移転は自由ですが、相続後の売却には定款に定める譲渡制限が関わります。承認が得られない場合でも会社に買い取り義務はなく、必ず会社や指定第三者に売却しなければならないわけではありません。
また、非上場株式には株券が発行されていない場合が多く、株主の地位は株主名簿によって確定されます。相続手続きでは、会社が定める手続きに従って必要書類を提出し、株主名簿の名義変更を行う必要があります。
非上場株式の3つの評価方式
非上場株式の相続税評価は、会社の規模や株主の地位に応じて、「純資産価額方式」「類似業種比準方式」「配当還元方式」の3つの方式から適切なものを選択します。それぞれの方式には特徴があり、評価結果に大きな差が生じる場合があります。
純資産価額方式は、会社の純資産をもとに株式価値を算定する方法です。会社が保有する資産を時価評価し、負債と法人税等相当額を差し引いた純資産価額を発行済株式数で割って1株あたりの価額を算出します。この方式は、資産の含み益が大きい会社では高い評価額となる傾向があります。
類似業種比準方式は、同じ業種の上場企業の株価を基準として非上場株式を評価する方法です。配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を類似業種の平均と比較し、会社の規模に応じた調整率を乗じて算出します。
配当還元方式は、主に少数株主に適用される簡便な評価方法です。年間配当金額を一定の還元利率で割り戻して株式価値を算定します。一般的に他の方式よりも低い評価額となるため、経営権のない少数株主の株式評価に用いられます。
非上場株式売却時の考慮事項
相続した非上場株式を売却する場合、買い手を見つけることが最大の課題となります。非上場株式は市場で自由に売買できないため、会社や他の株主、第三者への売却を検討する必要があります。
売却価格の決定も重要な問題です。相続税評価額と実際の売買価格は必ずしも一致しないため、適正な価格での売却を実現するためには、専門家による企業価値評価が必要になる場合があります。
非上場株式の売却では、M&A手法を活用することで、より高い価格での売却が実現できる可能性があります。特に、事業価値の高い会社の株式の場合、戦略的買収者による買収により、相続税評価額を大幅に上回る価格での売却が期待できることがあります。
株式相続の実務
株式相続では、相続人間での適切な遺産分割が重要な課題となります。株式は現金と異なり分割が困難な財産であるため、相続人全員が納得できる分割方法を見つけることが円滑な相続手続きの鍵となります。
株式相続における遺産分割の方法
株式相続の遺産分割には、主に現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法があります。現物分割は、株式をそのまま相続人間で分配する方法で、株式の種類や株数に応じて分割します。ただし、株式は1株単位でしか分割できないため、完全に公平な分割は困難な場合があります。
換価分割は、相続した株式を売却して現金化してから相続人間で分配する方法です。この方法では、株式の評価や分割の問題を回避でき、公平な分配が可能になります。ただし、売却時の市場環境や税務上の影響を慎重に検討する必要があります。
代償分割は、特定の相続人が株式を取得し、他の相続人に対して現金等で代償を支払う方法です。この方法は、事業承継が関わる場合に特に有効で、経営の継続性を保ちながら他の相続人の相続権も尊重できます。ただし、代償金を支払う相続人に十分な資力があることが前提となります。
遺産分割協議書の作成ポイント
株式相続に関する遺産分割協議書を作成する際は、株式の特定を正確に行うことが重要です。銘柄名、株式数、発行会社名を明確に記載し、複数の銘柄がある場合はそれぞれについて詳細に記載します。非上場株式の場合は通常、株式の発行会社と株式数を記載します。
分割方法についても具体的に記載する必要があります。現物分割の場合は、どの相続人がどの株式をどれだけ取得するかを明確にします。換価分割の場合は、売却の方法や分配割合を明記します。代償分割の場合は、代償金の金額、支払方法、支払期限を詳細に定めます。
相続トラブルを防ぐための対策
株式相続では、評価額の相違や分割方法を巡って相続トラブルが発生しやすいため、予防策を講じることが重要です。まず、被相続人が生前に遺言書を作成し、株式の処分について明確な意思を示しておくことが有効です。遺言書では、事業承継者への株式集中や、他の相続人への代償措置についても具体的に定めておきます。
株式の評価については、複数の専門家による評価を実施し、客観的な価値の把握に努めることが大切です。特に非上場株式の場合は、評価方法によって大きく結果が異なるため、税理士や公認会計士等の専門家に依頼して適正な評価を行います。
相続人間の合意形成を円滑に進めるためには、早期から関係者間でのコミュニケーションを密にし、それぞれの希望や事情を理解し合うことが重要です。必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家を交えた話し合いの場を設けることも有効な対策となります。
相続した株式の税務上の注意点
株式相続では、相続税の計算や申告において特別な注意が必要です。株式の評価額が相続税の総額に大きく影響するため、適正な評価と申告手続きを行うことが重要です。また、相続税以外にも各種の税務上の取り扱いを正しく理解しておく必要があります。
相続税の計算と申告期限
相続税の計算は、相続や遺贈、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。計算方法は以下で求めます。
| ➀ 相続財産+みなし相続等により取得した財産ー非課税財産+相続時精算課税適用財産ー債務や葬式費用=純資産価額 ② 純資産価額+加算対象となる暦年課税にかかる贈与財産の価額=各人の課税価格 |
次に、これらの各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額(正味の遺産額)を算出します。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数で計算され、この金額以下であれば相続税はかかりません。
| 正味の遺産額ー基礎控除額=課税遺産総額 |
課税遺産総額を民法に従って法定相続人に分配したときの相続人の取得金額を算出し、これに税率をかけて各人の相続税額を求めることができます。さらに相続税額から税額控除額を差し引いて納付税額を計算します。
| 課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各法定相続人の取得額 各法定相続人の取得額×税率-税額控除額=各法定相続人の納税額 |
相続税の税率は以下の表のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
株式の評価額は相続税の総額に直結するため、正確な評価が不可欠です。上場株式は前述の方法で比較的簡単に評価できますが、非上場株式の評価は複雑で専門的な知識が必要です。評価額に不安がある場合は、税理士に相談して適正な評価を行うことをおすすめします。
準確定申告の手続き
被相続人が亡くなった年の所得について、相続人が代わって所得税の申告を行う必要があります。これを準確定申告といい、相続開始を知った日から4ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。株式を保有していた被相続人の場合、配当所得や株式の譲渡所得がある可能性があります。
その他の税務上の注意事項
株式相続では、相続税や所得税以外にも注意すべき税務上の問題があります。まず、未受領の配当金がある場合、これも相続財産として評価する必要があります。配当金の支払基準日は過ぎていますが、まだ受け取っていない配当金は相続財産に含まれます。
非上場株式の場合、事業承継税制の適用を検討することも重要です。認定承継会社の株式については、相続税の納税を猶予する制度があり、適用要件を満たす場合は大幅な税負担軽減が可能です。ただし、厳格な要件があるため、専門家による詳細な検討が必要です。
まとめ
株式相続は現金相続と比べて複雑な手続きが必要で、上場株式と非上場株式では評価方法や手続きが大きく異なります。証券会社での名義変更手続きから相続税申告まで、各段階で適切な対応が求められるため、早めの準備と専門家のサポートが重要です。
特に非上場株式を多く保有する経営者の方には、事業承継の観点からM&Aによる株式譲渡も有効な選択肢となります。生前にM&Aを実行することで相続税対策になるだけでなく、企業の継続性確保や従業員の雇用維持にもつながります。M&Aは複雑な手続きを伴いますが、専門家に委ねることで円滑に進めることができ、相続問題の根本的な解決につながる可能性があります。
M&Aや経営課題に関するお悩みはぜひ一度、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。