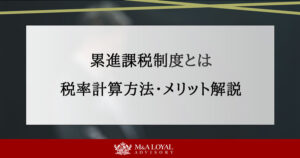預貯金相続の手続き完全ガイド!必要書類から期限、税金まで解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
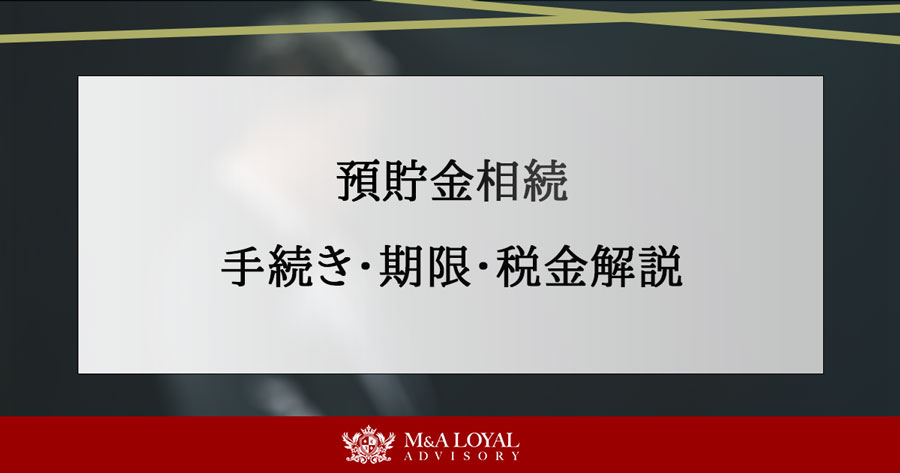
家族が亡くなった際、預貯金の相続手続きは多くの方が直面する重要な課題です。「どこから手を付ければいいのか」「必要な書類は何か」「期限はあるのか」など、初めて経験する方にとって不安や疑問は尽きません。
預貯金の相続は、適切な知識と準備があれば順調に進めることができます。しかし、手続きを誤ると口座凍結が長期化したり、相続人間でトラブルが発生したりする可能性もあります。また、相続税の申告期限や仮払い制度など、知っておくべき重要なポイントも多数存在します。
この記事では、預貯金相続の基本的な流れから具体的な手続き方法、必要書類、税金対策まで、実際の相続手続きで役立つ情報を包括的に解説します。中小企業経営者特有の注意点も含め、円滑な相続手続きの実現をサポートします。
目次
預貯金相続で知っておくべき基本知識
家族が亡くなった際、預貯金の相続手続きは多くの遺族が直面する重要な課題です。ここでは、相続手続きを円滑に進めるために必要な基本知識について詳しく解説します。
口座凍結のタイミングと影響
被相続人の預金口座は、金融機関が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。口座凍結は自動的に行われるものではなく、通常は相続人や親族からの連絡、新聞の訃報欄、葬儀場の案内看板などを通じて金融機関が死亡事実を把握した際に実施されます。
口座が凍結されると、キャッシュカードによる出金、振込、口座引き落としなど全ての取引が停止されます。これは相続財産を確定させ、相続人間のトラブルを防ぐために必要な措置です。公共料金の自動引き落としも停止されるため、引き落とし口座の変更手続きを速やかに行う必要があります。
相続人の範囲と法定相続分
被相続人の預金は、死亡と同時に相続人全員の共有財産となります。相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、その他に子、親、兄弟姉妹の順で相続権が発生します。
法定相続分は、配偶者と子がいる場合は配偶者が2分の1、子が2分の1を人数で分割します。配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分割します。ただし、実際の相続では遺産分割協議により、この割合と異なる分割も可能です。
遺言書がある場合とない場合の違い
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言の内容を実現するための手続きを担います。遺言執行者は、遺言書の内容に基づく範囲で必要な手続きを進めることができますが、全ての手続きが単独で完了するわけではありません。
遺言執行者が指定されている場合、一部の手続きでは相続人全員の実印や印鑑証明書を省略できることがあります。ただし、金融機関や法務局での手続きでは、遺言執行者の印鑑証明書や被相続人の死亡を確認するための戸籍謄本、遺言書の検認証明書(公正証書遺言の場合は不要)など、法定書類が求められることが一般的です。
また、相続人の一人が遺言執行者になる場合、他の相続人から「手続きが不透明だ」などの不満が出てトラブルに発展する可能性があります。このようなリスクを避けるため、弁護士や司法書士などの中立的な専門家を遺言執行者として指定することも有効な選択肢です。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。協議では預金を誰がどのように相続するかを話し合い、全員の合意を得る必要があります。協議がまとまらない場合や相続人に行方不明者がいる場合は、問題が解決するまで口座凍結は解除できません。この違いを理解し、事前に適切な準備をしておくことが重要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



預貯金相続の手続き5つのステップ
預貯金の相続手続きは複雑に感じられがちですが、基本的な流れを理解すれば着実に進めることができます。ここでは、実際の手続きを5つのステップに分けて詳しく解説します。
STEP1.被相続人の預金口座を調査する
相続手続きの第一歩は、被相続人がどの金融機関にどのような口座を持っていたかを正確に把握することです。通帳やキャッシュカード、取引明細書などを確認し、預金口座のリストを作成しましょう。
最近はインターネット銀行や通帳レスサービスの利用も増えており、物理的な証拠が残っていないケースもあります。パソコンやスマートフォンのメール履歴、郵送物なども確認してください。全店照会ができる金融機関もあるため、不明な口座がないか各金融機関に問い合わせることも重要です。
STEP2.金融機関へ連絡して口座を凍結する
被相続人の預金口座を特定したら、各金融機関に被相続人の死亡を連絡します。この連絡により口座は即座に凍結され、入出金や振込などすべての取引が停止されます。
連絡方法は金融機関によって異なり、電話での連絡を受け付ける場合と窓口への訪問が必要な場合があります。事前に各金融機関のホームページで確認するか、直接問い合わせましょう。この時点で、今後の相続手続きの流れや必要書類について詳しい案内を受けることができます。
STEP3.必要書類を収集・準備する
相続手続きには多くの書類が必要となります。基本的な必要書類には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などがあります。
戸籍謄本の収集は特に時間がかかるため、早めに着手することが重要です。複数の市区町村にわたって戸籍を取得する必要がある場合もあります。法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと、各金融機関での手続きが効率的に進められます。
STEP4.遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、預金を誰がどのように相続するかを決定します。協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。預金については金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人を正確に記載し、誰がその口座を相続するかを明確にします。複数の相続人で一つの口座を分割する場合は、分割割合や代表者による手続き方法も記載しておきます。
STEP5.金融機関で相続手続きを行う
必要書類がすべて揃ったら、各金融機関の窓口で相続手続きを行います。金融機関所定の相続届出書に必要事項を記入し、準備した書類とともに提出します。
書類に不備がないか事前にしっかりと確認し、原本とコピーを適切に準備しておきましょう。金融機関によっては郵送での手続きを受け付けている場合もあります。
書類が受理されてから払い戻し等が完了するまでには、金融機関や相続の状況にもよりますが、通常2週間から4週間程度、場合によってはそれ以上を要するのが一般的です。この期間を念頭に、相続税の納税資金などを計画することが重要です。手続きが完了すると、預金の払い戻しを受けるか、相続人名義の口座への名義変更を選択できます。
預貯金相続に必要な書類一覧
預貯金の相続手続きでは、相続の状況や金融機関によって必要書類が異なります。ここでは、基本的な必要書類から特殊なケースまで、包括的に解説します。
基本的な必要書類
ほぼすべての相続手続きで共通して必要となる基本書類があります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続人を確定するために必須です。除籍謄本や改製原戸籍も含め、すべての戸籍を漏れなく取得する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本も必要で、被相続人との関係を証明します。また、相続人全員の印鑑証明書は、実印とセットで本人確認と同意の証明に使用されます。手続きを行う人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も準備しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続き者の本人確認書類
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
ケース別の追加書類
相続の方法により、基本書類に加えて追加書類が必要になります。遺言書がある場合は、遺言書の原本を提出します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要で、検認調書または検認済証明書も必要です。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
遺産分割協議を行った場合は、相続人全員が署名・実印押印した遺産分割協議書を提出します。家庭裁判所での調停や審判により相続が決定した場合は、調停調書謄本または審判書謄本(確定表示のない審判書の場合は審判確定証明書も必要)を提出します。
法定相続情報一覧図の活用方法
相続手続きを効率化するため、法定相続情報証明制度の活用を強く推奨します。法務局で「法定相続情報一覧図」を取得すると、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりに利用できます。
この制度を利用すれば、複数の金融機関で手続きを行う際に、戸籍謄本を何度も取得する必要がありません。一覧図の写しは無料で必要部数を取得でき、相続手続き全体の時間短縮とコスト削減につながります。
金融機関ごとの必要書類の違い
基本的な必要書類は共通していますが、金融機関によって独自の書類が必要な場合があります。多くの金融機関では所定の相続届出書や相続手続依頼書への記入が必要です。これらの書類は各金融機関の窓口で入手するか、ホームページからダウンロードできます。
一部の金融機関では、残高証明書の提出を求められることもあります。また、ネット銀行など特殊な金融機関では、通常とは異なる手続きが必要な場合があるため、事前に各金融機関に確認することが重要です。必要書類は金融機関ごとに微妙に異なるため、手続き前に必ず問い合わせて正確な情報を確認しましょう。
預貯金相続の期限と手続きのタイミング
預貯金の相続手続きには法的な期限は定められていませんが、早期に手続きを行うことが重要です。ここでは、手続きのタイミングとその重要性について詳しく解説します。
相続手続きに法的期限はないが早めが重要な理由
金融機関での相続手続き自体に法律で定められた申告期限のようなものはありません。しかし、手続きを長期間放置すると、権利そのものが消滅したり、手続きが非常に煩雑になったりする重大なリスクがあります。具体的には、以下の2つの法的期限を認識しておく必要があります。
預金債権の消滅時効:2020年4月の民法改正により、預金債権は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」で時効により消滅する可能性があります。
休眠預金化:2009年1月1日以降の取引から10年以上入出金がない預金は、「休眠預金等活用法」に基づき休眠預金となり、預金保険機構へ移管される可能性があります。移管後も引き出しは可能ですが、手続きがより複雑になります。
手続きをしないまま預金を相続した相続人が亡くなると、その預金が再度相続財産となり、新たな遺産分割協議が必要になります。時間が経つにつれて相続人の数が増加し、手続きがより複雑になるリスクがあります。また、相続人間の関係が疎遠になることで、協議自体が困難になる場合もあります。
相続税申告期限との関係
預貯金の相続手続きと相続税の申告は密接に関連しています。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と法律で定められています。この期限内に正確な申告を行うためには、預貯金の残高を確定させる必要があります。
相続税の申告が必要な場合、預貯金の残高証明書や取引履歴が必要書類となります。金融機関での相続手続きが完了していないと、これらの書類取得や正確な財産評価が困難になる可能性があります。申告期限に遅れると延滞税や加算税が課されるため、余裕を持った手続きが重要です。
手続きが遅れることによるリスク
預貯金の相続手続きが遅れることで、いくつかの具体的なリスクが生じます。まず、2009年1月1日以降の取引から10年以上入出金のない預金は休眠預金として扱われ、預金保険機構へ移管される可能性があります。
公共料金や各種料金の自動引き落としが設定されている場合、口座凍結により引き落としができなくなり、未払いが発生する恐れがあります。これにより信用情報に影響を与える可能性もあります。
さらに、時間の経過とともに相続人の記憶が曖昧になり、被相続人の預金口座の存在を忘れてしまうリスクもあります。特にネット銀行など物理的な証跡が残りにくい口座は、発見が困難になる場合があります。また、相続人間での感情的な対立が時間とともに深刻化し、円滑な遺産分割協議が困難になることも考えられます。これらのリスクを避けるため、被相続人の死亡後は速やかに相続手続きに着手することが賢明です。
※参照:金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」
預金相続で使える仮払い制度
遺産分割協議が完了する前でも、一定の条件下で被相続人の預金を引き出すことができる仮払い制度があります。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合に活用できる重要な制度です。
仮払い制度が利用できる条件
遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)は、2019年7月1日から施行された制度で、相続人が単独で預金の一部を引き出すことができます。この制度を利用するための主な条件は、相続人であること、遺言書がないこと、そして家庭裁判所の仮処分が不要な範囲内であることです。
仮払い制度には二つの方法があります。一つは家庭裁判所の仮処分を経ない方法で、金融機関に直接申請できます。もう一つは家庭裁判所の仮処分を経る方法で、より高額な払戻しが必要な場合に利用されます。一般的には、葬儀費用や当面の生活費程度であれば、前者の方法で対応できることが多いでしょう。
払い戻し可能な金額の計算方法
家庭裁判所の仮処分を経ない場合の払戻し可能額は、「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを受ける相続人の法定相続分」で計算されます。ただし、一つの金融機関について150万円が上限となります。
具体例で説明すると、預金額が600万円で相続人が配偶者と子2人の場合を考えてみましょう。配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分はそれぞれ1/4となります。配偶者が仮払いを受ける場合、「600万円×1/3×1/2=100万円」が払戻し可能額となります。子が仮払いを受ける場合は、「600万円×1/3×1/4=50万円」となります。
仮払い制度の申請手続き
仮払い制度を利用するには、金融機関に必要書類を提出する必要があります。主な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、手続きする人の印鑑証明書です。これらは通常の相続手続きと同様の書類ですが、金融機関によって追加書類が必要な場合があります。
手続きの流れとしては、まず金融機関に仮払い制度の利用を申し出て、必要書類の案内を受けます。書類を準備して提出し、金融機関による審査を経て払戻しが実行されます。なお、仮払いで引き出した金額は、最終的な遺産分割において相続分から差し引かれるため、使途を明確にしておくことが重要です。
預貯金相続のトラブル回避方法
預貯金の相続手続きでは、適切な対応を怠ると思わぬトラブルに発展する可能性があります。ここでは、よくあるトラブルとその回避方法について詳しく解説します。
相続放棄への影響を避ける方法
相続が発生した際、被相続人に多額の借金があることが判明し、相続放棄を検討する場合があります。しかし、被相続人の預金を引き出して使用してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、口座凍結前であってもATMからの出金は避けるべきです。
やむを得ず葬儀費用等で預金を使用する場合、判例では社会通念上、不相当に高額でない限り、その支払いは相続財産の「処分」にはあたらないと解されており、相続放棄が認められる傾向にあります。必ずしも相続人全員の合意は法的な要件ではありませんが、後のトラブルを避けるため、使用目的と金額を明確にし、領収書を保管しておくことが賢明です。相続放棄の申述期限は相続開始を知った日から3か月以内のため、早期に専門家に相談することが重要です。
休眠預金になることを防ぐ対策
2009年1月1日以降の取引から10年以上入出金がない預金は休眠預金として扱われ、預金保険機構に移管されます。休眠預金になると引き出し手続きが複雑になるため、事前の対策が重要です。
被相続人が生前から長期間使用していない口座がある場合は、早めに相続手続きを行いましょう。金融機関からの通知が届くように住所変更を確実に行い、定期的に取引履歴を確認することも大切です。休眠預金になった場合でも引き出しは可能ですが、通常の相続手続きより時間がかかるため、予防が最善の対策です。
相続人間のトラブル防止策
相続人間でのトラブルを防ぐためには、透明性と公平性を保つことが重要です。預金の相続について話し合う際は、すべての相続人が参加できる場を設け、十分な情報共有を行いましょう。
遺産分割協議では感情論に陥らず、客観的な事実に基づいて話し合うことが大切です。各相続人の生活状況や被相続人への貢献度を考慮しつつ、法定相続分を基準とした公平な分割を心がけましょう。協議の内容は記録に残し、決定事項は遺産分割協議書として明文化します。
- 定期的な相続人会議の開催
- 財産状況の透明な開示
- 専門家による客観的なアドバイス
- 感情的な議論の回避
ネット銀行の相続手続きを確実に行う方法
ネット銀行の相続手続きは、従来の銀行とは異なる特徴があります。通帳やキャッシュカードが発行されないことが多く、口座の存在を見落としやすいのが最大の問題です。
被相続人のメールアカウントや郵送物を確認し、ネット銀行からの通知がないか調査しましょう。パスワード管理アプリやブラウザの保存履歴からも口座情報を発見できる場合があります。ネット銀行の相続手続きは郵送やオンラインで行われることが多いため、手続き方法を事前に確認し、必要書類を正確に準備することが重要です。
また、セキュリティが厳格なため、本人確認に時間がかかる場合があることも考慮して、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
預貯金相続にかかる税金と節税対策
預貯金を相続する際には相続税が課される場合があります。ここでは、相続税の基本的な仕組みと効果的な節税対策について詳しく解説します。
相続税の基礎控除と計算方法
相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続税の計算は複雑で、まず課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の取得金額に税率を適用します。相続税の税率は10%から55%までの累進課税で、課税遺産総額が多いほど高い税率が適用されます。実際に相続税が課税される人の割合は、令和5年分で9.9%にのぼります。
これは2015年の基礎控除額引き下げにより、課税対象者が改正前の約4%から倍以上に増加した結果であり、もはや「一部の富裕層のみの税金」ではなく、いわゆる「中間層」にとっても身近な問題となっています。
預貯金の評価方法と申告の注意点
預貯金の相続税評価は、被相続人の死亡日における残高で評価されます。普通預金や当座預金は死亡日の残高がそのまま評価額となり、定期預金は死亡日現在の残高に経過利子を加算した金額で評価されます。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に正確な申告を行うため、金融機関から残高証明書を取得し、預貯金の正確な評価額を把握する必要があります。申告期限に遅れると延滞税や加算税が課されるため、早めの準備が重要です。
生前贈与による節税対策
預貯金の相続税対策として、生前贈与が効果的です。暦年贈与では年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。複数の受贈者に贈与することで、「110万円×受贈者の人数分」を非課税で贈与できます。
2024年1月1日から、生前贈与に関するルールが大きく変更されました。従来の知識のまま対策を行うと、想定外の税金が発生する危険性があります。
1.暦年贈与の持ち戻し期間が「7年」に延長
従来、相続開始前「3年以内」の贈与が相続財産に加算されていましたが、2024年1月1日以降の贈与については、この期間が「7年」に延長されました。これにより、より長期的で計画的な贈与が不可欠となります。(※延長された4年間の贈与については、合計100万円までが控除されます。)
2.相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」を新設
2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が新たに創設されました。この年間110万円までの贈与は、贈与税の申告が不要な上、相続時の財産への加算(持ち戻し)もされません。これは前述の「7年ルール」を回避できる極めて強力な選択肢となるため、専門家と相談の上、暦年贈与との比較検討が必須です。
3.その他の非課税制度
教育資金贈与(最大1,500万円)や結婚・子育て資金贈与(最大1,000万円)といった特例制度も引き続き活用できますが、これらも適用条件や期限があるため注意が必要です。
また、生前贈与により相続時の財産を減らすことで、相続税の累進税率の軽減効果も期待できます。
※参照
・国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
・国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
中小企業経営者の預貯金相続における注意点
中小企業の経営者にとって、預貯金の相続は個人の相続とは異なる複雑な要素を含んでいます。事業の継続性を考慮した相続対策が必要です。
事業用口座と個人口座の区別
中小企業経営者の相続で最も重要なポイントは、事業用口座と個人口座を明確に区別することです。経営者個人名義であっても、実質的に会社の資金として使用されている口座は、相続時に問題となる可能性があります。
事業用口座の預金は会社の財産であり、経営者個人の相続財産には含まれません。しかし、名義が個人である場合は相続財産として扱われる恐れがあるため、生前に法人口座への移行や貸付金としての整理が必要です。また、会社への貸付金として処理されている場合は、その債権が相続財産となることも理解しておきましょう。
- 個人口座:相続財産として課税対象
- 事業用口座(法人名義):会社財産のため非課税
- 会社への貸付金:債権として相続財産に含まれる
事業承継を見据えた資産管理
中小企業の事業承継においては、預貯金の相続と株式の承継を一体的に考える必要があります。後継者に事業を円滑に承継するため、事業に必要な資金を確保しつつ、相続税負担を軽減する戦略が重要です。
事業承継税制の活用により、会社株式の贈与税や相続税の納税が猶予される場合がありますが、個人預金についてはこの恩恵を受けられません。そのため、事業用資金は法人に集約し、経営者個人の預金は計画的な生前贈与により後継者に移転することが望ましいでしょう。
また、経営者保証がある場合、後継者が保証を引き継ぐ際に十分な個人資産が必要となります。事業承継のタイミングを見据えて、後継者の資金力を考慮した預金の移転計画を立てることが重要です。このような複雑な事業承継対策については、税理士などの専門家と連携し、総合的な観点から最適な相続戦略を策定することが成功の鍵となります。
まとめ|預貯金相続を円滑に進めよう
預貯金の相続手続きは複雑に感じられがちですが、基本的な流れと注意点を理解すれば、確実に進めることができます。最も重要なのは、早期の着手と十分な準備です。
手続きには法的な期限はありませんが、時間が経つにつれて相続人の状況が変化し、手続きがより困難になる可能性があります。被相続人の死亡後は速やかに預金口座の調査を行い、金融機関への連絡と必要書類の準備を始めましょう。
相続人間のトラブルを避けるため、透明性と公平性を保った話し合いを心がけ、決定事項は必ず書面に残すことが大切です。複雑なケースや不明な点がある場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。適切な対応により、預貯金の相続を円滑に完了させ、新しい生活のスタートを切ることができるでしょう。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。