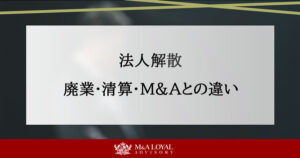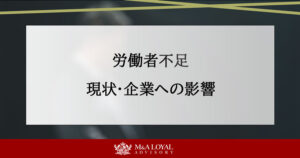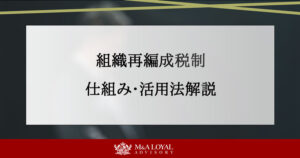病院の赤字経営の実態とは?潰れない理由は?割合や原因、対策も解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
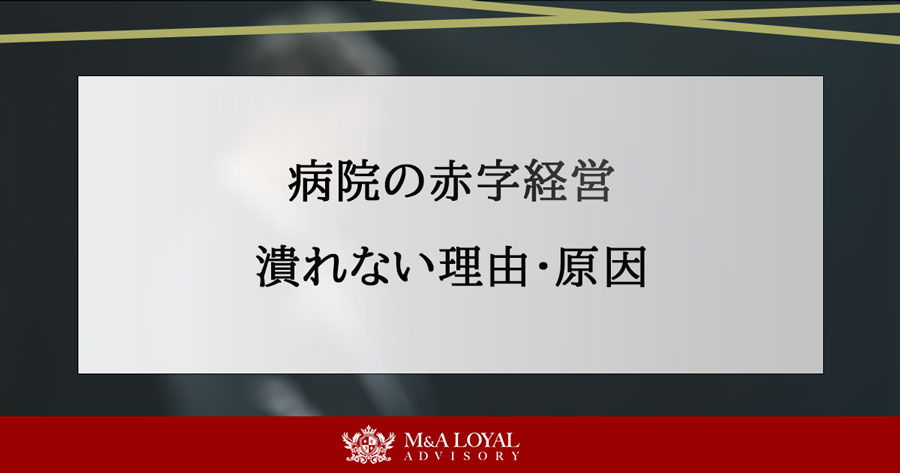
病院経営は地域医療を支える重要な役割を担う一方で、現実には多くの病院が赤字に直面しています。
医療費抑制政策や人件費の高騰、患者数の減少といった要因が重なり、経営環境は年々厳しさを増しています。
本記事では、赤字経営の病院がどの程度存在するのか、その割合や主な原因を整理し、経営改善のために求められる対策について分かりやすく解説します。
目次
病院経営の状況
まず、病院経営の現状について紹介します。
赤字経営の割合
2024年度の一般社団法人日本病院会の調査では、医業利益・経常利益共に赤字割合が増加しており、医業利益では69.0%、経常利益では61.2%の病院が赤字でした。
さらに、全国自治体病院協議会が実施した令和6年度決算状況調査では、有効回答を得た657病院のうち86%にあたる562病院が経常損失を計上しており、黒字はわずか14%にとどまりました。
これら2つのデータは調査主体や対象が異なるものの、いずれも共通して「多くの病院が赤字経営に直面している」という深刻な実態を示しています。今後は医療提供体制を維持するために、収益改善策や国・自治体による支援強化が不可欠であるといえます。
医療機関倒産の件数推移
2000年以降の医療機関倒産件数は年ごとに増減を繰り返しながら推移してきました。直近では2024年に64件(上半期34件)、そして2025年上半期(1〜6月)だけで既に35件が発生しており、年間では70件を超えそうなペースで進んでいます。
背景には、物価高や人件費の上昇による収益悪化、経営者の高齢化や建物の老朽化などがあり、事業継続を断念するケースが相次いでいます。
このままのペースで推移すると、2025年の医療機関全体の倒産件数は過去最多となる70件に達する可能性が高まっています。
収入源の内訳(医業収入・その他収入)
病院の収入源は主に「医業収益」と「医業外収益」に分かれます。医業収益には入院診療収入、室料差額収益、外来診療収入、その他医業収入が含まれます。近年は入院診療収入に依存した収益構造となりつつあり、黒字を維持している病院においても、医業収益だけでは利益が出にくく、寄付金や助成金、投資収益などの医業外収益に依存しているケースが多いことが明らかになっています。例えば、黒字病院でも医業利益率は1%台にとどまることが多く、医業外収益によってようやく経常黒字を確保している状況です。
このように、病院経営における収益構造は、医業収益の増加が重要である一方で、医業外収益の活用も必要不可欠であることが示されています。
医療機関別の休廃業・解散・倒産数
2024年に休廃業・解散した医療機関は722件に達し、過去最多を更新しました。内訳は病院17件、診療所587件、歯科医院118件で、特に診療所が8割以上を占めています。背景には、経営者の高齢化や後継者不足が大きく影響しています。
一方、前述のとおり、2025年上半期の倒産件数は既に35件に達しており、内訳は病院9件、診療所12件、歯科医院14件です。
休廃業・解散に加えて倒産も増加傾向にあり、医療機関の経営環境は一層厳しさを増しています。地域医療の持続性に対する懸念が高まっており、早急な対策が求められています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



病院が赤字になる原因
病院が赤字に陥る原因、また病院経営が難しいとされる理由は次のとおりです。
- 感染症の流行
- 人口減少
- 人件費・人材確保コストの増加
- 医療設備のコストの増加
- 診療報酬のマイナス改定
- 経営戦略の欠如
それぞれを解説します。
感染症の流行
感染症の流行は、病院経営にとって突発的かつ大きなリスクです。
特に新型コロナウイルスのような大規模感染症では、感染拡大防止のために外来診療や計画的な手術、検査などが大幅に制限されました。これにより、本来であれば安定して収益を生むはずの診療分野からの収入が激減し、病院の経営基盤が大きく揺らぎました。
さらに、感染症対応に必要な防護具や消毒液の購入費、発熱外来や隔離病床の整備など、新たなコストも急増しました。結果として、収益が減少する一方で支出が膨らみ、赤字に直結する要因となりました。
人口減少
日本全体で進む人口減少は、医療需要の減少や医療体制の維持に影響を与え、病院経営に長期的かつ深刻な影響を及ぼします。特に地方では、若年層の流出と急速な高齢化が進み、入院患者数や外来患者数の減少が地域医療に直結しています。小児科や産婦人科など診療科の維持が困難になるケースも増えています。
高齢者向け医療需要は現在高水準を保っていますが、今後は人口全体の減少に伴い、医療需要が縮小することが予測されています。特に、2040年には高齢者人口がピークを迎えるとされており、その後は高齢者人口の減少が見込まれています。このため、高齢者医療に依存している病院経営に対して影響が懸念されることがあります。医療提供体制やサービスの見直しが必要となる可能性があるため、病院は将来的な需要の変化に対応した戦略を立てることが重要です。
人件費・人材確保コストの増加
医療業界では慢性的な人手不足が課題で、医師や看護師、専門スタッフの採用は容易ではありません。そのため、病院は優秀な人材を確保するために給与や福利厚生を引き上げざるを得ず、固定費である人件費が増加します。
また、医療従事者の報酬や労働環境が十分ではないため離職しやすい点が採用コストをさらに引き上げています。加えて、病院によっては24時間365日稼働する体制を維持する必要があり、深夜勤務や休日勤務の手当も人件費を押し上げます。
こうした人材確保に関わる費用は避けられない一方で、収益の増加がそれに追いつかない場合、赤字の大きな要因です。
医療設備のコストの増加
医療の高度化に伴い、診断や治療に使われる医療機器はますます高性能化しています。MRIやCT、ロボット手術システムなどの先端機器は、導入に数千万〜数億円単位の投資を必要とします。例えば、MRIやCTの導入には機器本体の費用だけでなく、設置工事や保守契約費用も含めて総額数億円に達することがあります。それだけでなく、これらの機器を維持・更新するための保守契約や修繕費も毎年かかります。
こうした設備投資は医療の質を向上させ、患者からの信頼を得るためには不可欠ですが、短期的には収益を圧迫する要因です。特に中小規模の病院では、自己資金だけでなく補助金や融資を活用して設備投資を行うことが一般的ですが、回収までには長い時間を要します。そのため、設備投資は経営に重い負担としてのしかかる場合があります。
さらに、築年数が30年以上の病院では、耐震性能が現在の基準を満たしていない場合があり、改修工事や建て替えが課題となるケースが多く見られます。また、空調や給排水設備の老朽化が進行し、患者の快適性や安全性を確保するための設備更新が急務となる場合もあります。
診療報酬のマイナス改定
診療報酬のマイナス改定は、病院が赤字経営に陥る大きな要因の一つです。
国の医療費抑制策により、診療報酬は全体として引き下げ傾向が続いており、個々の診療点数が下げられるだけでなく、算定要件も厳格化される傾向にあります。その結果、従来と同じ診療を行っていても収入が減少しやすく、病院経営を直撃します。
さらに近年は診療報酬の算定ルール自体が年々複雑化しており、全てを正確に理解して適切に請求することは容易ではありません。請求漏れや誤った算定による返戻が発生すれば、本来確保できるはずの収入を失い、赤字を一層拡大させることにつながります。
改定内容を正確に把握し、医事課スタッフの育成や請求業務の精度を高める体制を整えなければ、収益の低下は避けられず、慢性的な赤字体質に陥るリスクが高まります。
経営戦略の欠如
医療機関は地域の医療ニーズを正しく把握し、競合する病院との差別化を図る明確な戦略を持つことが求められます。しかし経営戦略が欠けている場合、患者が求める診療科やサービスを十分に提供できず、結果として患者数の減少を招きます。
特に注意すべきことは、医師として高い臨床実績を持ち開業に至った場合でも、経営者としての素質や戦略眼が備わっているとは限らない点です。診療能力と経営能力は必ずしも一致せず、経営戦略を軽視すれば、優れた医療技術を持ちながらも経営難に直面する可能性があります。
病院経営の赤字対策
病院の赤字対策は次のとおりです。
- コストの改善
- ITシステムの導入
- 新しいサービスの提供
- 集患施策の見直し
- 患者とのコミュニケーションの強化
- 人材育成への投資
- 同地域の医療機関との連携
それぞれを詳しく解説します。
コストの改善
赤字経営の改善において最初に着手すべきはコスト構造の見直しです。
病院経営では人件費や医療材料費、設備維持費、光熱費といった固定費が大きな割合を占めており、これらの支出が収益を圧迫する原因です。
調達ルートの再検討や共同購買の導入によるコスト削減、エネルギー管理システムを活用した光熱費の最適化、さらに非効率な業務を外部委託するなどの工夫によって、無駄な支出を抑えられます。
コストの削減はすぐに効果が表れる対策であり、収益改善の第一歩です。
ITシステムの導入
IT活用は、経営改善とサービス品質向上を同時に実現できる重要な手段です。
電子カルテやオーダリングシステムの導入は、診療情報の一元管理を可能にし、診療効率と正確性を大幅に向上させます。また、オンライン予約や自動精算機を取り入れることで待ち時間が短縮され、患者満足度が高まると同時に業務効率も改善します。
さらに、データ分析ツールを用いて患者数や診療科別の収益構造を可視化すれば、どの分野に経営資源を重点配分すべきかが明確になり、戦略的な経営判断が可能です。
新しいサービスの提供
病院が赤字を脱却するためには、従来の入院・外来診療に加えて新しいサービスを展開し、収益源を多様化することが重要です。
在宅医療や訪問診療、オンライン診療を導入することで、患者の利便性を高めながら新たな需要を取り込めます。
また、近年は医療ツーリズムや美容医療・先進医療といった自由診療へのニーズも拡大しており、これらは公的医療保険に依存しない収益源となるため、診療報酬改定の影響を受けにくい強みがあります。
ただし、導入に際しては専門人材の確保や広報戦略が欠かせず、地域特性に合わせた慎重な取り組みが求められます。
集患施策の見直し
病院の経営は患者数の増減に大きく左右されます。
集患のためには、地域住民に病院の特徴や強みを知ってもらうことが重要です。病院のホームページを分かりやすく整備し、SNSを通じて診療科や医師の情報を発信することは、患者の安心感と信頼につながります。
また、診療時間の拡大や夜間・休日診療の導入といった柔軟な体制づくりも、患者数の増加に直結します。地域密着型のイベントや健康相談会を実施することも、住民との接点を増やし病院の利用促進につながります。
患者とのコミュニケーションの強化
患者満足度の向上はリピーターの確保や口コミによる新規患者獲得に直結します。
診療時に丁寧で分かりやすい説明を行い、不安や疑問にしっかり応えることで患者からの信頼を得られます。さらに、診療後のフォロー体制を整えることで安心感を高め、病院全体の評価を向上させられます。
こうした取り組みは患者の定着率を高めるだけでなく、地域における病院のブランド力強化にもつながります。
人材育成への投資
病院経営の安定には人材の質と定着が不可欠です。
医師や看護師だけでなく、事務職員や医療技術者に対しても継続的な教育・研修を行い、スキルアップを図ることで業務の精度と効率が向上します。
また、働きやすい職場環境を整備することで離職率を下げ、人材の定着を促せます。人材流出が減れば採用コストも削減でき、長期的な収益改善につながります。
同地域の医療機関との連携
単独の病院が全てのニーズに対応することは困難であり、地域内での連携は欠かせません。
地域包括ケアシステムの一環として他の医療機関や介護施設、行政と協力することで、患者の紹介や診療科の役割分担がスムーズに行われ、効率的な医療提供が可能です。共同で医療設備を利用したり、専門診療を特定の病院に集約したりすることで、コスト削減とサービス向上を同時に実現できます。
こうした地域連携は、病院の信頼性向上と持続的な経営基盤の確立につながります。
赤字病院の立て直しにM&Aを活用すべき理由
赤字病院の立て直しには、第三者継承が有効な手段の一つです。その主な理由は次のとおりです。
- 経営資源・収益基盤の強化
- 後継者の確保
- 地域医療の維持
- 売却益の獲得
クリニックM&Aのメリットを分かりやすく解説していきます。
経営資源・収益基盤の強化
M&Aによって大きな資本を持つ医療法人や法人グループの一員となることで、赤字病院でも資金調達が容易になる場合があり、負債の圧縮や老朽化した設備の更新といった課題の解決が期待できます。ただし、資金調達力の向上には法人グループの経営戦略や信用力に依存する部分もあります。
また、共同購買や設備の共同利用によりコスト削減が可能となり、効率的な経営が実現します。例えば、MRIやCTといった高額な医療機器の共同利用や、医薬品の一括購入による価格交渉力の向上などが挙げられます。
さらに、買収企業(譲受医院)の得意分野や専門性を取り入れることで診療体制を地域ニーズに合わせて強化することが可能です。これにより、自由診療やオンライン診療といった新しいサービスの導入が促進され、患者層の拡大や収益性の向上につながる場合があります。
結果として、医療機関は安定的かつ多角的な収益基盤を構築できる可能性があります。例えば、複数施設間での患者紹介体制の整備や、専門分野の拡充により、収益の分散と安定化を図ることができます。
後継者の確保
病院経営者や理事長、院長が高齢で後継者がいない場合、長期的な経営改善は困難です。M&Aによって新しい経営陣を迎え入れられれば、経営を継続しつつ将来にわたって安定した運営体制の維持が可能です。
さらに、医師や看護師などの人材不足が課題となっている場合でも、買収したグループから人材を派遣してもらえるため、医療の質を保ちながら診療を継続できます。
後継者不在問題を根本的に解決できる点は、M&Aの大きな利点です。
地域医療の維持
赤字が続く病院が閉鎖に追い込まれると、その地域の住民は必要な医療を受けられなくなる恐れがあります。
M&Aを通じて第三者に承継されれば、経営を継続しながら医療提供を続けられ、地域医療を守ることにつながります。また、大規模なグループに属することで、地域包括ケアシステムや他の医療機関とのネットワークに参画しやすく、患者の紹介や役割分担も円滑に行えます。
これにより、地域における医療提供体制の安定化が実現します。
売却益の獲得
赤字病院であっても病院を第三者に売却することで、経営者や株主はまとまった資金を得られる場合があります。
これにより、経営に伴う赤字リスクや将来的な債務負担から解放され、医業に集中したり、セカンドライフを謳歌(おうか)することもできます。
経営から身を引きたいと考えている医師にとって、M&Aは経済的にも心理的にも大きなメリットをもたらす選択肢です。
赤字病院が改善すべき病院経営管理指標
病院経営管理指標は次の三つに大別されます。これらを分析・改善することが赤字経営から抜け出す近道です。
- 収益性
- 安全性
- 機能性
それぞれを詳しく解説します。
収益性
収益性は、病院が提供する医療サービスによってどれだけ利益を生み出しているかを示す指標です。
医業利益率や経常利益率などが代表的で、収入と支出のバランスを把握することで経営の健全性を評価します。
収益性が低い場合、診療報酬改定やコスト構造の見直し、サービス内容の拡充など、収益改善に向けた取り組みが求められます。
具体的な項目は次のとおりです。
- 医業利益率
- 総資本医業利益率
- 経常利益率
- 償却前医業利益率
- 病床利用率
- 固定費比率
- 材料費比率
- 医薬品費比率
- 人件費比率
- 委託費比率
- 設備関係費比率
- 減価償却費比率
- 経費比率
- 金利負担率
- 総資本回転率
- 固定資産回転率
- 常勤医師人件費比率
- 非常勤医師人件費比率
- 常勤看護師人件費比率
- 非常勤看護師人件費比率
- 常勤その他職員人件費比率
- 非常勤その他職員人件費比率
- 常勤医師1人当たり人件費
- 常勤看護師1人当たり人件費
- 職員1人当たり人件費
- 職員1人当たり医業収益
- 1床当たり医業収益
安全性
安全性は、病院が将来にわたり安定的に経営を続けられるかを示す指標で、財務基盤の健全性を測るために用いられます。
自己資本比率や流動比率、借入金比率などが該当し、資金繰りや債務返済能力を評価します。
安全性が低い場合、過度な借り入れや資金不足によって経営継続が困難となるリスクが高まるため、財務構造の強化や資金調達の安定化が必要です。
具体的な項目は次のとおりです。
- 自己資本比率
- 固定長期適合率
- 借入金比率
- 償還期間
- 流動比率
- 1床当たり固定資産額
- 償却金利前経常利益率
機能性
機能性は、病院が限られた経営資源をどれだけ効率的に活用しているかを測る指標です。
平均在院日数や医師・看護師1人当たりの患者数といった稼働率や生産性に関する数値が含まれます。
機能性が高い病院は、人材や設備を効率的に活用して多くの患者にサービスを提供でき、結果として収益性や地域貢献度の向上につながります。
具体的な項目は次のとおりです。
- 平均在院日数
- 外来/入院比
- 1床当たり1日平均外来患者数
- 患者1人1日当たり入院収益
- 患者1人1日当たり入院収益※2
- 外来患者1人1日当たり外来収益
- 医師1人当たり入院患者数
- 医師1人当たり外来患者数
- 看護師1人当たり入院患者数
- 看護師1人当たり外来患者数
- 職員1人当たり入院患者数
- 職員1人当たり外来患者数
- 紹介率
- 逆紹介率
赤字病院の経営戦略に役立つフレームワーク
病院の経営戦略の策定に有効なフレームワークは次のようなものがあります。
- SWOT分析
- PDCA
- BSC(バランスト・スコアカード)
- ベンチマーキング
- PEST分析
それぞれを分かりやすく解説します。
SWOT分析
SWOT分析とは、組織の内部要因である「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」、外部要因である「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」を体系的に整理する手法です。
病院経営に応用することで、自院が持つ診療科の専門性や長年にわたる地域での信頼、医師・スタッフの技術力といった強みを改めて確認できます。一方で、老朽化した設備や採用難による人材不足や財務基盤の脆弱(ぜいじゃく)さといった弱点も浮き彫りになります。
さらに、地域の高齢化や医療需要の変化、新しい医療技術の進展、政策支援といった外部の機会を捉え、逆に診療報酬改定や競合病院の台頭などの脅威も整理できます。
これにより、単に問題を羅列するのではなく、強みをどう生かし弱みをどう補うか、そしてチャンスをつかみリスクを回避するかという戦略的視点が得られ、経営の方向性を明確にできます。
PDCAサイクル
PDCAサイクルとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の流れを繰り返しながら、組織を持続的に改善していく手法です。
病院経営は医療サービスの質だけでなく、事務作業や人材管理、設備運用など多岐にわたる要素に支えられており、一度の施策で全てを改善することは困難です。
そこでPDCAを導入すると、例えば「病床利用率を上げる施策」「外来予約システムの改善」「人件費抑制のための勤務体制の見直し」などを小さな単位で実行し、結果を検証して改善策を加えながら継続できます。
こうした積み重ねにより、組織全体の効率性とサービスの質が徐々に高まり、経営基盤の安定化に直結します。特に、変化の激しい医療制度や地域ニーズに対応するためには、PDCAサイクルを日常的に組み込むことが欠かせません。
BSC(バランスト・スコアカード)
BSC(バランスト・スコアカード)は、企業や組織の成果を財務指標だけでなく、「顧客満足」「内部プロセスの効率」「学習と成長(人材育成や組織力)」といった複数の観点から総合的に評価・管理するフレームワークです
病院経営では、単に黒字を出すことだけでなく、患者に信頼される医療を提供し、働きやすい環境で職員が力を発揮できる状態をつくることが重要です。
BSCを導入すると、財務的な成果と非財務的な成果をバランスよく可視化でき、経営層が掲げる目標と現場の取り組みを一致させられます。例えば「患者満足度調査の改善」「看護師の離職率低下」「診療プロセスの標準化」といった具体的な指標を設定することで、財務と医療の質を両立する経営が可能です。
PEST分析
PEST分析は、外部環境を「政治(Policy)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の四つの観点で整理する手法です。
病院を取り巻く環境は大きく変化しており、政治面では診療報酬制度の改定や医療政策、経済面では医療費抑制や地域経済の影響、社会面では人口減少・高齢化、技術面ではICTやAI、ロボット手術などの導入が進んでいます。
こうした外部要因は病院経営に直接影響を及ぼすため、PEST分析を行うことで将来のリスクとチャンスを体系的に把握できます。
例えば「人口減少による患者数減少」という脅威を認識した上で、「在宅医療やオンライン診療へのシフト」という機会を取り込むといった戦略が可能です。
ベンチマーキング
ベンチマーキングとは、他の優れた組織や業界標準と比較することで、自社や自組織の強みや弱点を客観的に把握し、改善のヒントを得る手法です。
病院経営においては、病床利用率や平均在院日数、人件費比率、紹介率などの経営指標を同地域や同規模の病院と比較することで、自院の位置付けを客観的に把握できます。
数値を基にした比較は「どこが非効率で、どこに改善余地があるのか」を明確にする上で非常に有効です。また、他院の先進的な取り組みを学び、自院に取り入れることで、経営改善やサービスの質向上につなげられます。
ベンチマーキングは単なる比較ではなく、学習と革新の出発点として病院経営に役立ちます。
赤字病院が実施すべき集患施策【オンライン】
集患(しゅうかん)とは、病院やクリニックが患者を集めるための活動を指します。適切な集患施策を打つことは黒字化を実現するために不可欠です。
主なオンラインの集患施策は次のとおりです。
- ウェブサイト最適化
- SEO対策、MEO対策
- SNS運用
- リスティング広告
それぞれを詳しく解説します。
ウェブサイト最適化
病院のウェブサイトは、患者の病院への第一印象を左右します。
診療科目や診療時間、担当医師の情報、アクセス方法などの基本情報を分かりやすく整理して掲載することは不可欠です。
さらに、スマートフォン対応やオンライン予約フォーム、問い合わせ機能の充実など、患者が利用しやすい仕組みを整えることが求められます。また、写真や動画を活用して院内の雰囲気を伝えることも、安心感や信頼感の醸成につながります。
ユーザビリティーを意識したデザインや操作性を改善し、必要な情報にすぐにアクセスできる環境を整えることで、患者の受診意欲を高められます。
SEO対策・MEO対策
検索エンジン最適化(SEO)は、患者が「地域名+診療科」といった具体的なキーワードで検索した際に、自院のウェブサイトが上位に表示されるようにするための取り組みです。
検索結果の上位に表示されれば、認知度向上とともに新規患者の来院につながりやすくなります。
また、Googleマップ上での表示順位を改善するマップエンジン最適化(MEO)も非常に重要です。正しい施設情報の登録、診療時間や連絡先の更新、口コミへの対応、写真や投稿の充実などを行うことで、地域住民に見つけてもらいやすくなります。
SEOとMEOを組み合わせることで、検索エンジンと地図検索の両面から効果的に集患を実現できます。
SNS運用
X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、LINEといったSNSを活用することで、病院は患者や地域住民と直接的なコミュニケーションを図れます。
診療科の専門性や季節ごとの健康情報、院内イベント、職員の取り組みなどを定期的に発信することで、病院の認知度を高めるとともに、患者からの信頼感を得られます。
さらに、SNSは双方向性が特徴であり、コメントやメッセージを通じた交流は患者に「身近で相談しやすい病院」という印象を与えます。
若年層から高齢層まで幅広い層に情報を届けられるため、来院のきっかけを増やし、リピーターの獲得にもつながります。
YouTube運用
YouTubeは動画を通じて病院の魅力や専門性を分かりやすく伝えられる強力なツールです。
テキストや写真だけでは伝わりにくい医師の人柄や診療の雰囲気、院内設備の様子を映像で発信することで、患者に大きな安心感を与えられます。例えば、院長や専門医による健康情報の解説動画、手洗いや生活習慣病予防など啓発コンテンツ、院内ツアー動画などを制作することで、地域住民に親しみやすい病院という印象を持ってもらえます。
また、YouTube動画はGoogle検索にも表示されやすいため、SEOの観点からも効果的です。さらに、SNSやウェブサイトと連携して活用すれば、より多くの潜在患者にリーチでき、集患につながります。
長期的にコンテンツを蓄積することで、病院のブランディングや専門性のアピールにも大きく貢献します。
リスティング広告
リスティング広告は、Google広告やYahoo!広告を通じて検索結果に広告を表示させる仕組みであり、集患において短期間で効果を出せる施策の一つです。
患者が「地域名+内科」「夜間診療+〇〇市」といった具体的なニーズを持って検索した際に広告が表示されるため、来院意欲の高い層に直接的にアプローチできます。
広告の配信地域や時間帯、年齢層などを細かく設定できるため、効率的にターゲットを絞り込めます。
SEO対策と組み合わせれば長期的・安定的な集患を図れる一方、リスティング広告は即効性があるため、新規開院や特定診療科の強化を図りたい場合にも有効に活用できます。
赤字病院が実施すべき集患施策【オフライン】
病院は地域密着型のビジネスであるため、オフラインの施策も重要です。主なオフラインの集患施策は次のとおりです。
- チラシや媒体広告
- 看板や街頭広告
- イベントやセミナー
- 紹介制度
それぞれを解説します。
チラシや媒体広告
地域住民に直接届けられるチラシや、新聞・フリーペーパーなどの媒体広告は、ターゲット層へダイレクトに訴求できる手法です。
特に医療機関では、診療科目や診療時間、アクセス情報といった実用的な情報を分かりやすく伝えることが重要です。
また、地域特性に合わせたデザインやメッセージを盛り込むことで、認知度向上や来院動機の形成につながります。継続的に配布することで信頼感を積み重ねる効果も期待できます。
看板や街頭広告
医院の周辺や交通量の多い場所に設置する看板や街頭広告は、通行人や通勤者の目に繰り返し触れることで認知を高められる施策です。
特に地元密着型の医療機関にとっては、存在を強く印象付ける効果があり、初めての患者でも場所を見つけやすくなるという利点があります。
診療科目や診療時間を明記しておくと利便性が伝わりやすく、来院のきっかけづくりとして有効です。
イベントやセミナー
健康相談会や予防啓発セミナー、地域イベントへの参加は、医療機関の専門性や地域貢献姿勢を住民に直接アピールできる貴重な機会です。
イベントを通じて来場者とコミュニケーションを取りながら信頼関係を築くことで、将来的な受診につながるケースは少なくありません。
また、地域の行政や企業と連携することで、幅広い層へのアプローチが可能になり、病院やクリニックのブランド価値向上にも寄与します。
紹介制度
既存患者や地域住民からの紹介は、信頼性の高い集患手段の一つです。
紹介を促進するためには、サービスの質を高めるだけでなく、紹介カードや特典を用意するなど仕組みを整えることも効果的です。
口コミは費用を抑えながら新規患者を獲得できる強力なチャネルであり、特に医療分野では「知人の紹介だから安心できる」という心理が働きやすい傾向があります。
紹介制度を整備することで、自然な形で新規患者層を広げていけます。
赤字病院の経営に役立つ資格
病院の経営に役立つ主な資格は次のとおりです。
医療経営士
医療経営士とは、医療と経営の双方に関する幅広い知識を身につけ、医療機関が抱える課題の解決や実践的な経営運営に携わる力を備えた人材を対象に、一般社団法人日本医療経営実践協会が認定する民間資格です。
医療経営士という資格は、医療機関の経営を持続的に発展させるため、経営者や管理者を支える存在として機能します。実務を担う補佐役としてだけでなく、時には経営の方向性を示す参謀役としても活躍し、医療経営の専門家としての立場から経営を支援する役割を担います。
医業経営コンサルタント
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する資格であり、医療・介護・福祉分野における経営の専門家です。医療機関等が関連法令を順守し、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に貢献できるよう、プロフェッショナルとして連携と協働を図りつつ、効率的で効果的な医業経営を支援します。
また、顧客の経営課題の解決や新たな機会の創出に向けて具体的な対策を提案し、その実践を後押しすることで、医療・介護・福祉および社会の発展に寄与することを使命としています。
病院経営管理士
病院経営管理士は、一般社団法人日本病院会が認定する資格であり、病院の管理運営を円滑かつ積極的に推進する能力と適応力を備えた人材です。
年々厳しさを増す医療環境の中で、職員一人ひとりの能力とモチベーションを最大限に引き出し、組織力を発揮して病院の目的達成を支えるマネジメントが求められています。
病院経営管理士は、多職種との緊密な連携を通じて病院経営を担うスペシャリストであり、自己研さんと継続的な努力を重ねることが不可欠です。その活躍の有無が病院の盛衰に直結するほど、重要な役割を担っています。
赤字病院に関するQ&A
最後に、病院の赤字に関するよくある質問とその回答を紹介します。
赤字の病院はどこに相談すべきか
赤字に悩む病院が相談できる先としては、複数の選択肢があります。
まず、地域の医師会や自治体の医療政策部門は、経営改善の支援や補助制度の情報提供を行っています。次に、金融機関は資金繰りや再建計画に関してアドバイスできる立場にあります。
また、M&A仲介会社も重要な相談先です。M&A仲介会社は、同業他社や医療法人、外部資本との統合・譲渡の選択肢を提示し、赤字病院が単独で経営を続けるよりも安定した運営体制を築ける可能性を提供します。特に、後継者問題や規模の小さい地域病院では、M&Aを通じた存続の道が現実的な解決策となるケースが増えています。
赤字の病院がつぶれない理由は何か
病院は地域医療を担う公共性が高いため、自治体や国からの補助金や交付金が支給されるケースが多くあります。
さらに、金融機関も地域医療の維持を重視して、赤字が続いても追加融資や返済条件の緩和に応じることがあります。
そのため、一般企業であれば倒産につながる赤字でも、病院の場合は地域医療インフラを守る観点から存続するケースが少なくありません。
東京都では赤字の病院は少ないのか
2025年版の全国赤字ワースト病院ランキングをみると、東京都23区の病院も多く含まれており、東京都都心部の病院だから経営が安定しているとはいえません。
医師や看護師の人件費、建物の維持費など都市特有のコスト負担が重く、収益構造が赤字に転じやすい要因となっています。
まとめ
病院が赤字に直面する背景には、医療費抑制政策や人件費の増加、患者数の減少傾向など、多くの要因があります。これらの課題は病院経営を厳しいものにしており、適切な対策が求められています。本記事では、赤字の原因やその改善策について詳しく解説してきました。
赤字問題に悩む病院は、まずは患者とのコミュニケーションを強化し、人材育成や地域の医療機関との連携を図ることが大切でしょう。また、M&Aや経営指標の見直しも有効な手段です。具体的な取り組みを始める前に、医業経営コンサルタントなどの専門家に相談するのも一つの方法です。これらのステップを通じて、病院の経営を健全に保ち、地域医療の維持に貢献できるよう努めていくことが重要と言えます。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。