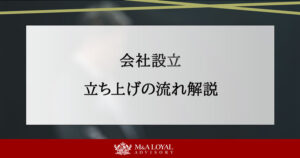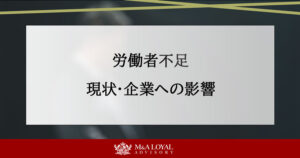フリーランスとは?仕事や年収、なる方法、個人事業主との違いを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型

会社に属さず個人のスキルで仕事を請け負うフリーランスが、働き方改革やテレワークの普及により近年注目を集めています。
しかし、自分のスキルを生かして自由に働ける一方で「収入が不安定そう」「社会保障はどうなるの?」と不安を感じる人も少なくありません。
本記事では、フリーランスの基本的な仕組みから、主な職種、フリーランスで働くメリット、デメリットまでを丁寧に解説します。
目次
フリーランスとは
まず、フリーランスについて基本的な情報を紹介します。
フリーランスの概要
フリーランスとは、企業や組織に雇用されず、自らのスキルや専門知識を生かして個人で仕事を請け負う働き方のことを指します。
語源は「free(自由な)」と「lance(やり)」で、中世ヨーロッパの「雇い主に縛られない傭兵(ようへい)」を意味する言葉から生まれました。
現代では、会社などに所属せず自由に働く独立した職業人という意味で使われています。
フリーランスの契約形態
フリーランスの契約形態は主に「業務委託契約」です。依頼内容に応じて「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類に分類されます。
委任契約は弁護士業務のように法律行為を委託するもので、準委任契約はコンサルティングやIT保守など、法律行為以外の事務を委託する契約です。請負契約は成果物の完成をもって報酬が支払われる契約で、プログラマーやライターなどが該当します。
フリーランスの就業実態
フリーランスの就業実態は、近年大きく変化しています。
総務省統計局によると、本業としてフリーランスで働く人は約209万人で、有業者全体の3%程を占めます。一方、副業を含む広義のフリーランス人口は1,500万人を超えるとの調査もあり、年々増加傾向にあります。
フリーランスの平均年収
フリーランス全体の年収は「200〜400万円未満」が最も多く、全体の約3割を占めています。次いで「200万円未満」「400〜600万円未満」がそれぞれ約2割であり、平均年収は300〜400万円前後と推定されます。
職種別では、エンジニア・技術開発系やコンサルティング系の約8割が年収400万円以上で、他職種に比べて高収入傾向にあります。一方で、クリエイティブ系や通訳・出版系では年収400万円以上が約4〜5割です。
なお、国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」によると、正社員の平均年収は508万円、非正規社員は198万円であり、フリーランスの収入はその中間水準に位置しています。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



フリーランスと似た言葉との違い
フリーランスと似た言葉の違いを分かりやすく解説します。
個人事業主
個人事業主とは、「継続的に自らの責任で事業を行う個人」を指します。
勤務先と雇用契約を結ぶ会社員とは異なり、税務署に開業届を提出して独立して事業を営む人が税法上「個人事業主」です。事業主が1人で行う場合だけでなく、家族や従業員を雇って経営していても、法人化していなければ個人事業主といえます。
一方で、「フリーランス」は案件ごとに契約を結び、業務を請け負う働き方のことをいい、フリーランスが開業届を提出すると税務上は個人事業主として扱われます。
自営業
自営業とは、自らの責任で事業を経営している人全般を指す言葉です。
飲食店の経営者や美容院の店主、個人商店のオーナーなど、店舗や事務所を構えてビジネスを運営する人が典型的な例です。自営業には、税務署に開業届を提出して個人として事業を行う「個人事業主」だけでなく、法人化して会社を設立している経営者も含まれます。
フリーランス=自営業ではありません。フリーランスは個人のスキルや専門知識を生かして案件ごとに契約を結ぶ働き方であるのに対し、自営業は自らの店舗や事業を継続的に運営して収益を得る点が特徴です。
フリーター
フリーランスとフリーターは、どちらも企業に正社員として雇われていない点では共通していますが、働き方の性質が大きく異なります。
フリーターはアルバイトやパートなど、雇用契約に基づいて働く労働者を指します。仕事内容や労働時間、給与は雇用先の指示に従う必要があり、独立性はありません。
フリーランスは「自分の責任で仕事を受ける働き方」、フリーターは「雇用されて働く形態」であり、法的な立場や契約関係が全く異なります。
ギグワーカー
フリーランスとギグワーカーはいずれも「雇用されずに働く」という点で共通しますが、仕事の期間や契約形態に明確な違いがあります。
ギグワーカーはスマートフォンアプリやオンラインプラットフォームを通じて、短期・単発(ギグ=一回限り)の仕事を受ける働き方です。代表例はUber Eats配達員などで、1件ごとに報酬が発生します。
フリーランスは「契約ベースの独立事業者」、ギグワーカーは「アプリ経由で単発業務をこなすワーカー」という点が異なります。
フリーランスの代表的な職種15選
フリーランスの代表的な職種は、次のとおりです。
プログラマー
プログラマーは、企業やクライアントから業務を請け負い、アプリケーションやシステムを開発する専門職です。
JavaやPython、JavaScript、C#などのプログラミング言語を使って実装を行います。スキルや経験によって報酬は大きく異なります。
近年は、ウェブサービスやスマホアプリ開発など案件の幅が広がっており、基礎的なプログラミング知識と開発実績を積むことで未経験からの独立が可能です。
システムエンジニア
システムエンジニア(SE)は、クライアントの要望に基づいてシステムの設計・開発・運用を行う専門職です。
プログラマーがスムーズに実装できるよう、詳細な設計書を作成し、全体の品質と進行を管理します。フリーランスとして活動する場合、要件定義から設計、開発チームの管理、納品後の保守までを一貫して担うことも珍しくありません。
経験を積めば企業のIT顧問やコンサルタントとして独立し、高単価案件を獲得することも可能です。
ヘルプデスク
ヘルプデスクは、企業や顧客からの問い合わせに対応し、IT機器やシステムのトラブルを解決する職業です。
主な業務は、パソコンやネットワーク、ソフトウエアの操作方法や不具合に関するサポートです。
フリーランスの場合、IT企業の外部サポートとして在宅で契約を結ぶケースも多く、リモートワークに適した職種です。技術知識に加えて、丁寧な説明力と顧客対応スキルが評価されます。
ウェブデザイナー
ウェブデザイナーは、企業サイトやECサイト、LP(ランディングページ)などのデザインを手がける職種です。
クライアントの目的やターゲットを踏まえて、見やすく使いやすいレイアウトや配色を設計します。PhotoshopやIllustrator、Figmaなどのデザインツールを扱う他、HTMLやCSSなどのコーディング知識も必要です。
在宅で複数案件を同時に進める人も多く、SNSやポートフォリオサイトを通じて直接仕事を獲得するケースも増えています。
ウェブライター
ウェブライターは、企業のウェブサイトやブログ、ニュースメディアなどに掲載する記事やコンテンツを執筆する職業です。
商品紹介やコラム、SEO記事、取材記事などテーマに応じて文章を構成し、読者に分かりやすく情報を伝えます。
フリーランスの場合、クラウドソーシングや直接契約を通じて複数メディアから仕事を受けることが一般的です。
動画編集者
動画編集者は、YouTubeやSNS、企業のPR映像などに使われる動画コンテンツを編集・加工する職業です。
撮影された素材を基に、カット編集やテロップ挿入、BGMや効果音の調整などを行い、視聴者に伝わりやすい映像を作り上げます。演出力やストーリー構成のセンスが重視されます。
フリーランスの場合、YouTuberや企業、広告代理店から案件を請け負うことが多く、企画構成やサムネイル制作まで対応できれば高単価化も可能です。
SNSインフルエンサー/コンテンツクリエイター
SNSインフルエンサー/コンテンツクリエイターは、SNSや動画プラットフォームを通じて情報や価値を発信し、影響力を基に収益を得る職業です。
InstagramやYouTube、TikTok、X(旧Twitter)などで、自身のライフスタイルや専門知識、エンタメコンテンツを発信し、フォロワーとの信頼関係を築きます。収益源は企業案件や広告収入、ライブ配信、グッズ販売など多岐にわたります。
独自の世界観や発信テーマを確立し、継続的なコンテンツ制作と分析が成功の鍵です。
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナーは、広告やパッケージ、ポスター、雑誌、ロゴなどの印刷物やデジタル媒体のデザインを手がける職業です。
クライアントの要望を基に、色彩やレイアウト、フォントなどを組み合わせて、視覚的にメッセージを伝えるデザインを制作します。IllustratorやPhotoshopなどのデザインソフトを使いこなす技術が必須です。
広告代理店や企業から直接依頼を受けることも多く、ブランディング案件や商品デザインなどを通じて高収入を得るチャンスがあります。
カメラマン(フォトグラファー)
カメラマン(フォトグラファー)は、広告・雑誌・商品・人物などを撮影する専門職です。
被写体やシーンに応じて、最適な構図・照明・レンズを選択し、クライアントの意図を的確に表現します。撮影後のレタッチ(画像補正)や色調整などの編集技術も不可欠です。
フリーランスの場合、スタジオ撮影やロケ撮影を組み合わせながら、SNSを通じた作品発信や口コミで顧客を増やすケースが一般的です。
イラストレーター
イラストレーターは、書籍・広告・ゲーム・ウェブサイトなどに使用されるイラストを制作する職業です。
依頼内容に応じて、キャラクターデザインや背景画、アイコン、装画などを描きます。PhotoshopやCLIP STUDIO PAINTなどのデジタルツールの活用が一般的で、作風やジャンルに応じて得意分野の有無が重要です。
ポートフォリオサイトやSNSを通じて作品を発信し、企業や出版社から直接依頼を受けるケースも多く見られます。
ハンドメイドクリエイター
ハンドメイドクリエイターは、アクセサリーや雑貨、インテリア小物などを手作りし、オンラインやイベントで販売する職業です。
近年ではBASEやminne、CreemaなどのECサイトを活用し、自身のブランドとして作品を販売する人が増えています。デザイン力や手先の器用さに加え、商品の撮影や宣伝、販売管理などマーケティングスキルも求められます。
SNSで制作過程や作品の魅力を発信することでファンを増やし、リピーターを獲得できる点も大きな特徴です。
コンサルタント
コンサルタントは、企業や組織の課題を分析し、最適な改善策を提案・実行支援する専門職です。
業務内容は経営戦略や人事、財務、IT、マーケティングなど、専門分野によって担当領域は多岐にわたります。フリーランスとして活動する場合、顧問契約やプロジェクト単位で企業と契約し、経営改善や業務効率化をサポートします。
1案件当たりの報酬は数十万〜数百万円と高水準で、実績と信頼がキャリア形成の鍵です。
翻訳・通訳者
翻訳者・通訳者は、異なる言語間でのコミュニケーションを円滑にする専門職です。
映画や書籍の翻訳、国際会議での同時通訳、企業の技術マニュアルや契約書の翻訳など、活躍の場は幅広く存在します。
AI翻訳の発展により、機械翻訳後の校正やクリエイティブ要素を重視したナレーション翻訳など、新しい需要も増えています。
税理士・会計士
税理士・会計士は、企業や個人事業主の財務・会計・税務をサポートする国家資格職です。
税務申告や決算処理だけでなく、経営分析や節税対策、資金繰りなどのコンサルティング業務も担います。
顧問契約を通じて複数のクライアントを支援するケースが多く、安定した収入を得やすい点が特徴です。
講師・オンライン講師
講師・オンライン講師は、自身の専門スキルや知識を他者に教える教育系の職業です。
語学やプログラミング・デザイン・ビジネススキルなど、扱う分野は幅広く、オンラインスクールや学習プラットフォーム、SNSを活用して授業を行うケースが増えています。
動画講座の販売やライブレッスン配信など、オンライン化によって活動の自由度が高まり、人気講師は個人ブランドを確立して安定した収益を得ています。
フリーランスが増加している社会的背景
フリーランスが増加している社会的背景は、次のとおりです。
- 働き方の多様化と価値観の変化
- IT技術の発展とオンライン化の加速
- 企業側の人材戦略の変化
- 政府の後押しと制度整備
- コロナ禍による働き方の意識転換
- 副業からの独立・スモールビジネス化
それぞれを分かりやすく解説します。
働き方の多様化と価値観の変化
近年は「安定よりも自由」を重視する価値観が広がり、柔軟な働き方を求める人が増えています。
特に20〜30代の若い世代を中心に、「自分の得意を生かして働きたい」「複数の仕事を持ちたい」と考える人が多くなりました。こうした価値観の変化により、企業に依存せず、自分のペースで仕事や生活をデザインできるフリーランスという選択肢が注目されているのでしょう。
働く目的が「キャリアアップ」から「やりがい」へと移行している点が大きな特徴です。
IT技術の発展とオンライン化の加速
IT技術の進化とオンライン化の加速も、フリーランス拡大の重要な要因です。
近年では、クラウドソーシング(例:クラウドワークス、ランサーズ)やオンライン商談ツール(例:Zoom、Slack)の普及により、個人でも全国、さらには海外のクライアントと直接取引できる環境が整いました。リモートワーク体制やオンライン決済の一般化によって、自宅にいながら業務を完結できる仕組みも確立されています。
こうした変化により、企業に所属せずとも自身のスキルを生かして働く機会が増え、特にエンジニア、デザイナー、ライターなどのデジタル職種では、独立のハードルが大幅に下がりました。
さらに、新型コロナウイルスの流行を契機としてリモートワークが急速に普及したことも、フリーランスという働き方を社会的に定着させる大きな転機となりました。
企業側の人材戦略の変化
企業は近年、固定費削減と専門性の確保を目的に、正社員に限定せず外部人材を活用する動きを強めています。
特にIT・デザイン・マーケティング・ライティングなど、プロジェクト単位で完結する業務では、フリーランスへのアウトソーシングが急速に拡大しました。少子高齢化による人材不足もこの流れを後押ししており、企業は「必要なときに必要なスキルを持つ人を起用する」ジョブ型の働き方へシフトしています。
また、フリーランスへの報酬は外注費として経費処理できるため、消費税の負担軽減にもつながる点が企業側のメリットです。
政府の後押しと制度整備
政府は「働き方改革」の一環として、雇用関係にとらわれない多様な働き方の推進を進めています。副業・兼業の解禁や、個人事業主向けの融資・補助金制度の拡充などにより、制度面の後押しもフリーランスが増加している社会背景の一つといえます。
2024年には「フリーランス新法(フリーランス保護法)」が施行され、企業との取引条件を明確化し、報酬の支払い遅延や不当な契約変更を防ぐ仕組みを導入しました。
フリーランス新法によりフリーランスの取引環境が法的に保護され、安心して事業を続けられる基盤が強化されています。制度面の整備が進むことで、フリーランスという働き方は一時的な流行ではなく、社会に根付く新たな職業形態となりつつあるといえるでしょう。
副業からの独立・スモールビジネス化
近年では、副業からフリーランスへと独立する人も増えています。
副業で培ったスキルや実績を基にクライアントを獲得し、安定した収入のめどが立った段階で独立する流れが一般的です。SNSや個人サイト、ポートフォリオサービスなどを活用すれば、自分の専門性を発信しながら顧客の獲得が可能です。特にデザイナーやライター、動画編集者などはオンラインで完結できる仕事が多く、ひとり法人化するケースも増えています。
副業解禁の流れにより、個人でも企業並みの発信力を持てる時代となったことで、スモールビジネスが新しいキャリアの形として定着しつつあります。
フリーランスとして働くメリット
フリーランスとして働くメリットは、次のとおりです。
- 時間と場所に縛られない
- 得意分野や好きな仕事を選べる
- 実力次第で高収入を目指せる
- 複数の収入源を持てる
- 定年退職がない
それぞれを詳しく解説します。
時間と場所に縛られない
フリーランス最大の魅力は、働く時間や場所を自分で選べる自由さにあります。
決められた出勤時間や勤務地がなく、自宅やカフェ、コワーキングスペース、地方、海外など好きな場所で働けます。そのため、通勤のストレスや職場の人間関係に悩まされず、自分のペースで仕事を進められる点が大きなメリットです。
さらに、家事や育児、介護との両立もしやすく、ライフスタイルに合わせて柔軟に働けます。どこで・いつ働くかを自分で選べる自由さが、フリーランスの最大のメリットといえます。
得意分野や好きな仕事を選べる
自分の得意分野や興味のある仕事を自由に選べる点もフリーランスの魅力の一つです。
会社員のように上司の指示や部署異動に縛られず、情熱を持って取り組める分野に集中できます。
例えば、デザインやライティング、プログラミング、翻訳、動画制作など自分のスキルを最大限に生かせる領域を選び、専門性を高められる点もメリットです。
実力次第で高収入を目指せる
フリーランスは、努力とスキルがダイレクトに収入へ反映される働き方です。
会社員のように年功序列や固定給の仕組みに縛られず、実績や能力に応じて報酬を自由に伸ばせます。得意分野で高単価案件を受注したり、複数のクライアントと継続契約を結ぶことで、年収1,000万円以上を達成する人も少なくありません。
「頑張った分だけ成果を得たい」人にとって、フリーランスは理想的な働き方といえるでしょう。
複数の収入源を持てる
フリーランスは、一つの会社や契約に依存せずに働けるため、複数の収入源を確保できる点も大きな強みです。
例えば、ライターが執筆と講師業を兼ねたり、デザイナーがクライアント案件とデジタル素材販売を並行したりするなど、複数の柱を持つことで景気変動や契約終了のリスクを分散できます。
複数の収入源を持つことは、経済的な安心感を得るだけでなく、キャリアの幅を広げる手段でもあります。
定年退職がない
フリーランスには会社員のような定年制度がないため、年齢を問わず働き続けられる点も大きなメリットです。
健康と意欲さえあれば、何歳でも現役として活躍でき、仕事を通して社会と関わり続けられます。特に、知識や経験が評価されるコンサルタントや士業、講師などの分野では、年齢を重ねるほど信頼が厚くなり、安定した収入を得られる傾向があります。
会社員のように「退職後の再雇用先を探す」という不安がなく、自分のペースで働ける点も大きな安心材料となるでしょう。
フリーランスとして働くデメリット
フリーランスとして働くデメリットは、次のとおりです。
- 収入が不安定になりやすい
- 社会保障や福利厚生が限定される
- 仕事とプライベートの境目が曖昧になる
- 全ての業務を自分でこなす必要がある
- 社会的信用を得にくい
それぞれを詳しく解説します。
収入が不安定になりやすい
フリーランスは、案件ごとに報酬が発生する成果型の働き方であるため、月によって収入に大きな差が出やすい点がデメリットです。
契約が急に終了したり、クライアントの予算削減や景気の変動によって仕事量が減少したりする場合があります。特に独立したばかりの時期は、固定の取引先が少なく、安定収入を得るまでに時間がかかるケースも珍しくありません。
そのため、生活費3〜6カ月分の貯蓄や固定費の見直しなど、リスクに備えた資金計画が不可欠です。
社会保障や福利厚生が限定される
会社員のような社会保障や福利厚生を受けられない点もフリーランスの大きなデメリットといえます。
厚生年金や社会保険、傷病手当金などの制度的なサポートは原則対象外であり、代わりに自ら国民健康保険や国民年金へ加入する必要があります。
さらに、病気やケガで働けなくなると収入が途絶えるリスクが高いため、所得補償保険や小規模企業共済などの自助的制度の活用が重要です。
仕事とプライベートの境目が曖昧になる
フリーランスは、働く時間や場所を自由に選べる反面、仕事と私生活の境界が曖昧になりやすい点が課題です。
自宅やカフェなどで作業を行うことで、仕事モードと休息モードの切り替えが難しくなり、気付けば休日や夜間も働き続けてしまうケースも少なくありません。長時間労働してしまう傾向があり、健康面やメンタル面の負担につながることもあります。
仕事時間を明確にして休息や趣味の時間を意識的に確保する「自己管理力」が、長く働く上で欠かせないスキルです。
全ての業務を自分でこなす必要がある
フリーランスは、自分の専門分野の仕事以外にも経理や営業、事務など全ての業務を自分でこなさなければならない点がデメリットです。
クライアントとの契約書作成や請求書の発行、入金管理、確定申告といった事務処理に加え、新規案件を獲得するための営業活動やポートフォリオの更新など、業務範囲は非常に広いです。これらを怠ると、トラブルや収入の不安定化につながるリスクもあります。
フリーランスとして長く活動を続けるためには、専門スキルだけでなく、経営者としての総合的なビジネススキルも求められます。
社会的信用を得にくい
フリーランスは、収入の変動が大きく安定性に欠けると見なされやすいため、社会的信用を得にくいデメリットもあります。
住宅ローンや賃貸契約、クレジットカードの審査では、安定した給与証明がない分、会社員よりも厳しく評価される傾向があります。多くの場合、確定申告書や契約書、入金履歴などの提出を求められ、審査に時間がかかるケースも珍しくありません。
社会的信用を得るためには、複数年にわたる収入実績の提示や屋号・事業用口座の開設、定期的な確定申告の実施など、信頼を積み重ねる工夫が重要です。
フリーランスが仕事を獲得する方法
フリーランスが仕事を獲得する方法は、次のとおりです。
- クラウドソーシングサイトを活用する
- SNSやブログで情報発信する
- 企業や知人からの紹介してもらう
- 営業を行う
- 専門コミュニティ・イベントに参加する
それぞれを詳しく解説します。
クラウドソーシングサイトを活用する
クラウドソーシングは、フリーランスとしての第一歩に最適な仕事獲得方法です。
代表的なプラットフォームには「クラウドワークス」「ランサーズ」「ココナラ」などがあり、スキルや実績を登録すれば、全国・海外のクライアントと直接つながれます。ライティングやウェブデザイン、プログラミング、動画編集などジャンルを問わず多様な案件が募集されている点が特徴です。
最初は低単価の案件からスタートしても、納期を守り、クオリティの高い成果を提供すると評価が蓄積し、徐々に単価の高い仕事を受注できます。
メール・飛び込み営業を行う
フリーランスとして安定的に仕事を得るためには、自ら営業活動を行う積極性が重要です。
特に、メール営業(ダイレクト営業)や飛び込み営業は、自分のスキルを必要としている企業や個人に直接アプローチできます。営業メールでは、自己紹介に加えて「相手の課題をどう解決できるか」を具体的に伝えることがポイントです。
一方で、訪問型の飛び込み営業は、地元企業や中小事業者とのつながりを築くのに有効です。最初は断られることもありますが、誠実な対応や継続的なフォローによって関係を深めれば、長期的な取引につながるケースもあります。
SNSやブログで情報発信する
SNSやブログでの情報発信は、自分のスキルを「見つけてもらう」ための営業手段として非常に有効です。
X(旧Twitter)やInstagram、YouTube、noteなどを活用して、専門分野の知識や制作実績、日々の取り組みを発信すれば、自分の強みや世界観を自然に伝えられます。継続的に発信を行うことで、フォロワーや見込みクライアントからの信頼が高まり、企業や個人から直接依頼を受けるチャンスも増えます。
また、ブログではSEOを生かして検索経由の集客を狙え、SNSでは投稿の拡散力によって認知度を一気に高められます。
企業や知人からの紹介してもらう
フリーランスにとって「紹介案件」は信頼性が高く、安定した収入につながる仕事獲得方法の一つです。
実績を積み重ねて信頼を築くと、企業の担当者や既存クライアント、知人などから新しい案件を紹介されることは珍しくありません。紹介案件は、初対面のクライアントよりも契約までの流れがスムーズで、報酬単価が高くなる傾向があります。
そのため、日頃から丁寧な仕事と誠実なコミュニケーションを心がけることが不可欠です。
専門コミュニティ・イベントに参加する
業界セミナーや勉強会、オンラインサロン、交流会などの積極的な参加は、信頼できる人脈を築き、仕事のチャンスを広げる有効な手段です。
コミュニティ内では、スキルや実績を共有しながら仲間同士で刺激を受け合える他、仕事を紹介し合ったり、共同でプロジェクトを立ち上げたりするケースもあります。
信頼は出会いの数よりも関係の深さで生まれるため、参加後も継続的に交流を重ねる姿勢が大切です。
フリーランスになるための手続き
フリーランスとして活動を始めるには、税務・保険・事業運営に関する複数の手続きを順序立てて行う必要があります。主な手続きは、次のとおりです。
- 開業届を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
- 事業用の口座とクレジットカードを作る
- 健康保険・年金関係の手続きを行う
それぞれを分かりやすく解説します。
開業届を提出する
フリーランスとして活動を始める際は、まず税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出しましょう。「個人で事業を始める」という意思を税務署に届け出るためのもので、正式に個人事業主として認められる重要な手続きです。
開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告による確定申告を行う場合には提出が必須です。また、開業届を提出しておくと屋号付き口座の開設や事業用クレジットカードの発行がスムーズになるなど、ビジネス上の信用にもつながります。
手続きは、居住地を管轄する税務署で行うか、e-Taxを利用してオンラインでの提出が可能です。
青色申告承認申請書を提出する
フリーランスとして開業する際は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」の提出をおすすめします。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けられるなど、税制面でメリットです。
提出期限は青色申告を適用したい年の3月15日までです。1月16日以後新たに業務を開始した場合は、その開始の日から2カ月以内に提出する必要があります。
なお、青色申告を行うためには、帳簿の作成や記録管理が必要です。
事業用の口座とクレジットカードを作る
フリーランスとして独立したら、事業専用の銀行口座とクレジットカードを用意しましょう。
生活費と事業資金を同じ口座で管理していると、経費の仕訳や確定申告時の帳簿付けが複雑になり、ミスが発生しやすいです。事業用口座を分けておけば、入出金の流れを明確に把握でき、会計処理や確定申告がスムーズに行えます。
金融機関によっては事業名(屋号)を登録した屋号付き口座をの開設が可能です。
健康保険・年金関係の手続きを行う
会社員からフリーランスへ転身した場合は、社会保険から脱退し、国民健康保険と国民年金に切り替える手続きが必要です。
加入手続きは、居住地の市区町村役場で行います。手続きの際には退職証明書やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要となるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
退職後も前職で加入していた健康保険を「任意継続」する選択肢もあります。ただし、退職後2年間に限り、保険料は全額自己負担です。負担額を確認した上で判断すると良いでしょう。
ホームページまたはSNSを開設する
フリーランスとして活動する上でホームページやSNSの開設は、集客と信頼性向上の両面で非常に有効です。
自身の実績や得意分野、サービス内容を明確に発信できる場を持つことで、クライアントに安心感を与え、仕事の依頼につながります。さらに、専門知識やノウハウを継続的に発信するブログは、検索エンジン(SEO)を通じて新規顧客にアプローチできる点も魅力です。
また、ホームページを運営していると事業の実態が明確になり、銀行口座の開設や融資の審査で信頼性が高まります。
確定申告の準備を始める
フリーランスとして働く場合、毎年の所得を自分で計算し、税務署に申告・納税する「確定申告」が必要です。
確定申告では、1年間の売り上げから経費を差し引いた所得を基に、所得税や住民税の金額が決まります。会社員のように源泉徴収や年末調整が行われないため、自分自身での管理が必須です。
申告時に慌てないためには、日々の帳簿付けやこまめな領収書の整理が大切です。
フリーランスに関するQ&A
最後に、フリーランスに関するよくある質問とその回答を紹介します。
フリーランス新法(フリーランス保護法)とは何か
フリーランス新法(フリーランス保護法)とは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」のことで、フリーランスが安心して働ける環境を整えるために制定された法律です。2024年秋に施行されました。
主な内容は次の7項目です。
- 取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・支払の義務
- 不当行為の禁止
- 募集情報の的確表示
- 育児・介護との両立への配慮
- ハラスメント防止体制の整備
- 中途解除や契約終了時の予告・理由開示
フリーランスが確定申告をしないとどうなるか
フリーランスが確定申告を行わない場合、税務上のペナルティや信用低下のリスクが発生します。
まず、申告漏れや遅延があった場合には、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。追徴課税は本税に上乗せされ、支払い負担が大きくなるため注意しましょう。
また、融資・住宅ローン・クレジット審査の際に収入証明が出せず、不利になるケースもあります。フリーランスとして信頼を得るためにも、毎年の確定申告は重要です。
フリーランスでも消費税を払う必要があるか
消費税は、商品やサービスに対して課される間接税であり、最終的には消費者が負担するものですが、実際に税務署へ納めるのは事業者です。
そのため、フリーランスも事業者として活動している場合、消費税を「預かる立場」として国に納税する義務が発生する場合があります。
納税義務があるのは、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。また、前々年に1,000万円以下でも、前年の1月1日〜6月30日までの課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、その年から課税事業者になる「特定期間」の判定もあります。
フリーランスが法人化するタイミングはいつが良いか
一般的には、年間利益が600〜800万円を超えた頃が法人化を検討する目安とされています。これは、法人化によって受けられる節税効果が、設立や維持のコストを上回るラインです。
法人化すれば、給与所得控除の活用や家族への役員報酬支給など、個人事業主では難しい節税ができます。
事業規模の拡大を見据えている人や安定した利益を継続して得られるようになった人は、税理士に相談しながら最適な法人化のタイミングを見極めると良いでしょう。
まとめ
この記事を通じて、フリーランスの基本的な働き方や、そのメリット・デメリットについて理解を深めることができたでしょうか。フリーランスとして働くことには、自由さややりがいがある一方で、収入の不安定さや社会保障の課題が伴います。このような課題に対して、クラウドソーシングの活用や、必要な手続きをしっかりと行うことが重要です。また、フリーランスに関する法律や税金の知識を持つことも、長期的に成功するために欠かせません。
これからフリーランスとしての一歩を踏み出そうと考えている方は、まずは自分の得意分野を活かせる職種を選び、必要な準備を進めていきましょう。具体的な行動としては、開業届の提出や、SNSでの情報発信、そしてコミュニティへの参加などがあります。ぜひ、次のステップに進むための行動を始めてみてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。