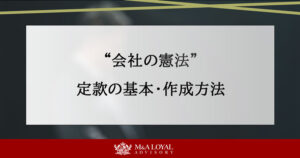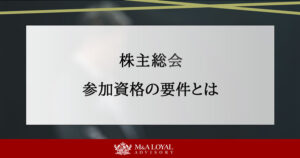株主総会の特別決議とは?要件や決議事項、注意点を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
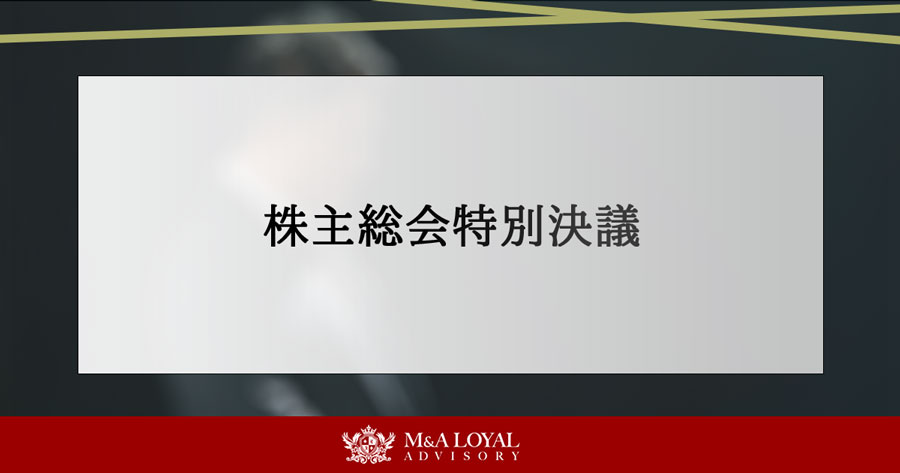
株主総会は、会社の重要事項を決議する場です。株主総会の決議には主に「普通決議」と「特別決議」の2種類があり、案件の重要度に応じて使い分けられています。特に会社の根幹に関わる重要事項は「特別決議」が必要となりますが、M&Aや事業譲渡などの局面で、この特別決議の要件を見落としてしまうと、せっかくの取引が無効になるリスクもあります。
本記事では、株主総会の特別決議の要件や対象となる決議事項、実務上の注意点について解説します。会社の意思決定をスムーズに進める株主総会について、本記事をぜひご参照ください。
目次
株主総会の特別決議とは – 基本的な理解
株主総会は株式会社の最高意思決定機関であり、会社法に基づいて様々な重要事項が決議されます。その中でも、会社の基本的な枠組みを変更するような特に重要な事項については、通常よりも厳格な手続きが求められます。これが「特別決議」です。
特別決議は、会社の存続や株主の権利に大きな影響を与える決議事項に適用される厳格な決議方法です。普通の決議よりもハードルが高く設定されているため、慎重な検討と手続きが必要になります。
株主総会の特別決議の法的根拠
特別決議の法的根拠は会社法309条第2項に規定されています。この条文では、特別決議の成立要件として「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要」と定めています。この「過半数」は、全株主の議決権の過半数を指し、出席株主の議決権の過半数ではありません。
この規定は強行規定であり、定款で要件を緩和することはできませんが、加重(例:出席株主の議決権の4分の3以上)することは可能です。特別決議が必要な具体的な案件には、定款の変更、合併、解散などがあります。
株主総会と普通決議との違い
「普通決議」と「特別決議」の主な違いは、決議要件の厳しさにあります。普通決議は、出席株主の議決権の過半数(50%超)の賛成で成立しますが、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
この違いは、決議される事項の重要性を反映しています。日常的な経営判断に関わる事項は普通決議で十分ですが、会社の基本構造や株主の権利に大きく影響する事項については、より慎重な判断が求められるため特別決議が必要とされています。
| 決議の種類 | 定足数 | 決議要件 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 議決権の過半数を有する株主の出席 | 出席株主の議決権の過半数 |
| 特別決議 | 議決権の過半数を有する株主の出席 | 出席株主の議決権の3分の2以上 |
上記の表からわかるように、特別決議は普通決議よりも高いハードルが設定されています。これは会社の根幹に関わる重要事項については、より多くの株主の合意が必要という考え方に基づいています。
特別決議の重要性
特別決議が求められる事項は、会社の組織再編や基本的な枠組みの変更など、株主の利益に直接影響を与える重要な案件です。このような重要事項については、多数の株主の賛同を得ることで意思決定の正当性を担保し、少数株主の保護も図っています。
特に中小企業の経営者にとっては、M&Aや事業承継などの局面で特別決議が必要になるケースが多いため、その要件や手続きを正しく理解しておくことが重要です。特別決議の要件を満たさない決議は無効となる可能性があり、後々のトラブルを避けるためにも正確な知識が必要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株主総会の特別決議が必要な主な決議事項
特別決議が必要となる事項は、会社法に明確に規定されています。これらは会社の根幹に関わる重要な決定事項であり、株主の権利や会社の基本的な枠組みに大きな影響を与えるものです。ここでは、主な特別決議事項を分野別に整理して解説します。
特別決議事項を把握しておくことで、重要な経営判断を行う際に適切な手続きを踏むことができます。特に中小企業の経営者にとっては、M&Aや事業承継などの局面で関わることが多い項目なので、しっかりと理解しておきましょう。
組織再編関連の決議事項
会社の組織再編に関する事項は、会社の存続形態そのものに関わるため、特別決議が必要とされています。組織再編行為は会社の基本的な枠組みを変更し、株主の権利義務関係にも大きな影響を及ぼすため、慎重な判断が求められるのです。主な組織再編関連の特別決議事項には以下のようなものがあります。
- 合併契約の承認
- 事業譲渡(重要な一部の事業譲渡を含む)の承認
- 解散の決議
これらの組織再編行為は、M&Aの際に頻繁に用いられる手法でもあります。特に事業譲渡については「重要な一部」の判断基準が曖昧な場合があるため、念のため特別決議を経ておくことが安全です。
資本政策に関する決議事項
資本政策に関する重要事項も特別決議が必要です。これらは会社の財務基盤や株主構成に直接影響を与えるため、慎重な判断が求められます。主な資本政策関連の特別決議事項は以下の通りです。
- 株式の併合
- 減資
- 剰余金の配当(現物配当の場合は特別決議が必要)
- 種類株式の内容の変更
- 新株予約権の発行(有利発行の場合、特別決議が必要)
- 自己株式の有利処分
特に中小企業の経営者が事業承継や資金調達を検討する際に、これらの資本政策は重要なツールとなります。例えば、後継者に対する株式の移転を円滑に進めるために種類株式を活用するケースや、事業拡大のための資金調達として新株予約権の発行を行うケースなどが考えられます。
定款変更に関する決議事項
定款は会社の基本規則であり、その変更は会社の根幹に関わる重要事項です。そのため、定款変更はすべて特別決議事項となります。定款変更が必要となる主なケースには以下のようなものがあります。
- 会社の目的の変更
- 商号の変更
- 発行可能株式総数の変更
- 役員の任期や定数の変更
- 株主総会や取締役会の運営方法の変更
定款変更は、事業拡大や組織再編に伴って必要になることが多いです。例えば、新規事業に参入する際には会社の目的を追加する定款変更が必要になりますし、M&Aに伴って商号を変更する場合も定款変更が必要です。
役員・株主の権利に関する決議事項
役員の責任や株主の権利に関わる重要事項も特別決議によって決定されます。これらは会社のガバナンスや株主保護に直結する事項です。主な決議事項は以下の通りです。
- 取締役・監査役の責任の一部免除を可能とする定款変更
- 株主以外の者に対する新株・新株予約権の発行
- 全部取得条項付種類株式の取得
- 株式の併合により端数株式が生じる場合の処理
特に取締役の責任免除に関する規定は、優秀な人材を役員として招聘する際に重要な要素となります。また、株主以外への新株発行は既存株主の持株比率を変動させるため、慎重な判断が求められます。
特株主総会の特別決議の手続きと流れ
特別決議を行うためには、法定の手続きを正確に踏む必要があります。手続きの不備は決議の無効や取消事由となる可能性があるため、慎重に進めることが重要です。ここでは、特別決議を行うための一連の流れと各段階での注意点を解説します。
特別決議の手続きは、株主総会の招集から決議の実施、そして決議後の対応まで複数のステップから構成されています。それぞれのステップで法定の要件を満たす必要があります。
株主総会招集前の準備一覧
特別決議を行うための株主総会を開催するには、事前に十分な準備が必要です。特別決議は普通決議よりも高いハードルが設定されているため、株主の出席率や賛成率を事前に予測し、必要に応じて株主への説明や説得を行うことが重要です。主な準備事項は以下の通りです。
- 議案の詳細な検討と資料作成
- 主要株主への事前説明と賛同の取り付け
- 株主名簿の確認と更新
- 議決権行使書面の準備
- 取締役会での株主総会招集の決議
特に中小企業では、経営者が大株主であることが多いため、特別決議のハードルは低く感じられるかもしれません。しかし、同族間での意見の相違や、少数株主の存在を考慮すると、事前の準備は怠れません。
株主総会の招集通知
株主総会を開催するためには、法定の期間内に株主に対して招集通知を発送する必要があります。特別決議事項を含む株主総会では、招集通知の内容や発送時期に特に注意が必要です。
- 招集通知の発送期限:株主総会の日の2週間前まで
- 特別決議事項の記載:議案の要領を明記
- 参考書類の添付:議案の詳細説明資料を添付
- 議決権行使書面の同封:出席できない株主のための対応
株主総会の開催と決議
株主総会当日は、特別決議の要件を満たすために出席株主数や議決権数を正確に把握する必要があります。特別決議の成立要件を再確認しておきましょう。
- 定足数: 議決権を行使できる株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数が必要です。
- 決議要件: 出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
株主総会では、議長が特別決議事項について十分な説明を行い、株主からの質問に丁寧に回答することが重要です。また、議決権行使書面による事前の議決権行使を含め、賛否の集計を正確に行います。事前の議決権行使は、出席できない株主の意向を反映させるために重要です。
決議後の手続き
特別決議が成立した後も、必要な手続きがあります。特に登記が必要な事項については、法定期間内に登記申請を行う必要があります。主な決議後の手続きは以下の通りです。
- 議事録の作成:特別決議の内容を正確に記録
- 登記申請:定款変更や組織再編などの登記事項の変更手続き
- 公告:法定公告が必要な場合の対応
- 反対株主への対応:株式買取請求に対する対応
特に議事録は重要な証拠書類となるため、特別決議の要件が満たされたことが明確にわかるよう、出席株主数や議決権数、賛成の割合などを正確に記載することが重要です。
特別決議の実務上の注意点とリスク対策
特別決議は普通決議よりも厳格な手続きが求められるため、実務上様々な注意点があります。ここでは、特別決議を行う際に特に注意すべきポイントとリスク対策について解説します。
特別決議に関する手続きの不備は、後になって決議の無効や取消しの原因となり、M&Aなどの重要な取引に悪影響を及ぼす可能性があります。そのようなリスクを避けるために、実務上の注意点を押さえておきましょう。
定款による特別決議要件の加重
会社の定款で特別決議の要件を法定よりも加重している場合があります。例えば、定款で「特別決議は出席株主の議決権の4分の3以上の賛成で行う」と規定している場合、法定の3分の2ではなく、その加重された要件を満たす必要があります。事前に自社の定款を確認することが重要です。
定款で特別決議の要件を厳しくすると、合併や資本政策などの重要事項について慎重な判断が確保できる一方、意思決定が滞る原因にもなりかねません。自社の状況に合わせて適切な要件を検討することも大切です。
反対株主の株式買取請求への対応
組織再編行為や重要な事業譲渡などの特別決議事項には、反対株主に株式買取請求権が認められています。この権利は少数株主保護のための重要な制度ですが、会社側としては財務面での影響を考慮する必要があります。
- 買取請求が可能な期間の確認: 特別決議の通知を受けてから通常1ヶ月内に買取請求を行う必要があります。
- 買取価格の算定方法の検討: 買取価格は時価や簿価、専門家による評価などの方法で算定します。
- 買取資金の準備: 必要な資金を事前に確保しておくことが重要です。
- 必要に応じた専門家への相談: 株式価値算定のために、評価士や弁護士などの専門家に相談することを検討します。
特に中小企業のM&Aの際には、少数株主からの買取請求に備えて、事前に資金計画を立てておくことが重要です。また、買取価格について争いが生じた場合の対応策(例えば、仲裁や調停の利用)も検討しておくべきでしょう。
みなし決議(書面決議)の活用
株主が少数の会社では、実際に株主総会を開催せずに「みなし決議」(書面決議)を活用することで、手続きを簡略化できる場合があります。みなし決議は、株主全員の同意があれば総会を開催せずに決議したものとみなす制度です。
みなし決議を行う場合の手順は以下の通りです。
- 議案の内容を株主全員に通知
- 株主全員から書面による同意を取得
- 株主総会の議事録に代わる書面を作成
- 必要に応じて登記申請などの手続きを実施
特に同族経営の中小企業では、みなし決議の活用により手続きの簡略化が図れますが、株主全員の同意が必要なため、少数でも反対株主がいる場合は通常の株主総会を開催する必要があります。
M&A・事業承継における特別決議の重要性
M&Aや事業承継の場面では、特別決議が必要となる場面が多く、その手続きの適正さが取引の有効性に直結します。特に以下のような点に注意が必要です。
- デューデリジェンス(財務・税務・法務等の観点から詳細調査)時の過去の特別決議の確認
- 取引スキームに応じた必要な特別決議事項の検討
- クロージングまでのタイムラインに特別決議の手続きを織り込む
- 特別決議の要件を満たせない場合の代替スキームの検討
M&Aの対象会社を検討する際には、過去の特別決議事項が適正に処理されているかを デューデリジェンスで確認することも重要です。 手続き上の瑕疵があった場合、将来的に取引の有効性が否定されるリスクがあります。
まとめ
株主総会の特別決議は、会社の根幹に関わる重要事項を決定するための厳格な手続きです。通常の普通決議よりも高いハードルが設定されており、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
特別決議が必要となる主な事項としては、合併や会社分割などの組織再編行為、定款変更、重要な事業譲渡、減資などが挙げられます。これらは会社の基本的な枠組みや株主の権利に大きく影響する事項であり、慎重な判断が求められます。
特に中小企業のM&Aや事業承継の場面では、特別決議が必要となるケースが多く、その手続きの適正さが取引の有効性に直結します。自社の定款の確認、事前の株主への説明、必要に応じた専門家への相談など、入念な準備が重要です。
会社の重要な意思決定を適法かつスムーズに進めるために、特別決議の要件と手続きについての正確な理解は必須です。本記事が皆様の実務の一助となれば幸いです。
組織再編やM&Aを検討されている企業経営者の方々は、特別決議の要件を含む法的手続きについて専門家に相談することをお勧めします。適切なアドバイスにより、スムーズな取引実現が可能です。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。