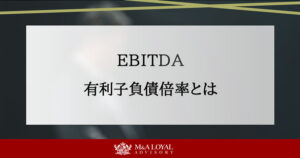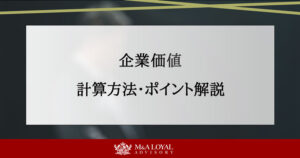EBITDAとは?計算方法や営業利益との違い、読み方を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
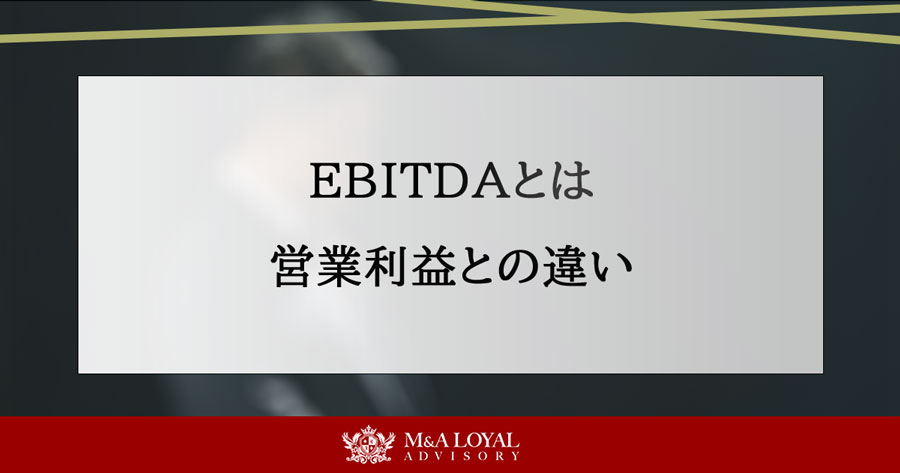
企業の買収や投資判断の場面で「EBITDA」という言葉を耳にしたことはありませんか。EBITDAの読み方は「イービットディーエー」と読まれることが一般的で、この指標は、企業の稼ぐ力を評価できる優れた財務指標として、特にM&Aの現場で重宝されています。
しかし、単純に計算するだけでは企業の真の価値は見えてきません。適切な計算方法の選択、関連指標との組み合わせ、そして中小企業特有の調整項目への対応が不可欠です。本記事では、EBITDAの基礎知識から実践的な活用術、注意すべき落とし穴まで、M&Aで失敗しないための知識を体系的に解説します。
目次
EBITDAとは?基本知識と重要性
M&Aの世界で頻繁に使われる「EBITDA」という指標をご存知でしょうか。中小企業の経営者や買収を検討している企業にとって、EBITDAは企業価値を正確に評価するための重要な指標となっています。営業利益や当期純利益とは異なる角度から企業の収益力を測るこの指標について、基本的な知識から実践的な活用方法まで詳しく解説していきます。
利払前・税引前・減価償却前利益の意味
EBITDAとは、「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization」の略語で、日本語では「利払前・税引前・減価償却前利益」と呼ばれます。これは企業の最終的な利益から、支払利息、税金、減価償却費を足し戻した利益を意味します。
EBITDAの構成要素を分解すると以下のようになります。
- Earnings Before:考慮する前の利益
- Interest:支払利息
- Taxes:税金
- Depreciation:有形固定資産の減価償却費
- Amortization:無形固定資産の減価償却費
企業の本質的な収益力を把握するため、これらの要素を除外して計算することで、事業そのものが生み出すキャッシュベースの利益を明確にできるのです。
EBITDAの読み方
EBITDAの読み方については、実は統一された呼び方が存在しません。一般的には「イービットディーエー」と読まれることが多いですが、「イービッタ」「エビーダ」「イービットダー」など、様々な読み方が用いられています。
どの読み方でも意味は同じですので、相手に合わせて使い分けることが重要です。M&Aの現場では「イービットディーエー」が最も一般的ですが、「イービッタ」という短縮形も頻繁に使われています。英語の頭文字を取った略語であることを理解していれば、読み方の違いに戸惑うことはないでしょう。
営業利益との違いを理解する
営業利益とEBITDAの最大の違いは、減価償却費の扱いにあります。営業利益は企業の本業で稼いだ利益を示しますが、減価償却費を差し引いた後の金額です。一方、EBITDAは営業利益に減価償却費を加え戻すため、よりキャッシュフローに近い実質的な利益を把握できます。
設備投資が多い製造業などでは、減価償却費の負担が大きく、営業利益だけでは実際のキャッシュ創出能力が見えにくくなる場合があります。しかし、EBITDAを用いることで、現金の支出を伴わない減価償却費の影響を除外し、事業が実際に生み出している利益を正確に評価することが可能になります。
中小企業M&Aで重視される3つの理由
中小企業のM&AでEBITDAが重視される理由は複数ありますが、特に重要な3つの理由があります。
1.簡便な計算と客観的評価
財務諸表から比較的簡単に算出でき、専門業者に依頼せずとも企業価値の目安を把握できる
2.投資回収期間の判断
買収価格をEBITDAで割ることで、何年で投資を回収できるかの目安がわかる
3.業界を超えた比較
設備投資の多寡や会計方針の違いに左右されず、異なる業種の企業とも比較可能
中小企業M&AのEBITDA倍率は一般的に2倍から10倍程度が目安とされており、特に3倍から5倍での成約が多いとされています。これは上場企業の8倍から10倍と比較して低い水準であり、中小企業の方が短期間での投資回収を求められる傾向があることを示しています。
※参照:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



EBITDAの5つの計算方法と実践例
EBITDAには統一された計算式が存在せず、企業の状況や分析の目的に応じて複数の計算方法が用いられています。どの方法を選択するかによって、企業の収益力をより正確に把握できるかが変わってきます。特に中小企業のM&Aでは、オーナー企業特有の費用調整も必要になるため、適切な計算方法を理解することが重要です。
営業利益+減価償却費の基本公式
最も一般的で簡便なEBITDAの計算方法が、営業利益に減価償却費を加える方法です。営業利益は企業の本業で稼いだ利益を示し、そこに現金支出を伴わない減価償却費を加えることで、キャッシュベースの収益力を把握できます。
例えば、製造業A社の営業利益が500万円、減価償却費が200万円の場合、EBITDA = 500万円 + 200万円 = 700万円となります。この計算方法は財務諸表から簡単に算出でき、企業間比較や初期的な企業価値評価に適しています。設備投資が多い業種では、減価償却費の影響を除外することで、より実態に近い収益力を評価することが可能です。
当期純利益から逆算する実践的手法
当期純利益を起点とした計算方法は、最終的な利益から全ての控除項目を足し戻す手法です。計算式は「当期純利益 + 法人税等 + 支払利息 + 減価償却費」となり、企業の全体像を把握しながらEBITDAを算出できます。
この方法の利点は、決算書の最終数値から出発するため、会計処理の影響を包括的に調整できることです。例えば、B社の当期純利益が300万円、法人税等が100万円、支払利息が50万円、減価償却費が150万円の場合、EBITDA = 300 + 100 + 50 + 150 = 600万円となります。税金や金利の影響を排除できるため、国際的な企業比較に特に有効です。
経常利益ベースの計算で精度を高める
経常利益を基準とした計算方法では、「経常利益 + 支払利息 – 受取利息 + 減価償却費」の公式を用います。経常利益は本業の営業利益に営業外損益を加えた指標であり、企業の包括的な収益力を反映しています。
金融関連の取引が多い企業や、投資収益が重要な収益源となっている企業では、この計算方法がより実態を反映します。例えば、不動産会社C社の経常利益が800万円、支払利息が120万円、減価償却費が280万円の場合、EBITDA = 800 + 120 + 280 = 1,200万円となります。営業外収益も含めた総合的な収益力を評価できるため、多角化している企業の分析に適しています。
税引前利益を起点とした詳細計算
税引前当期純利益から計算する方法は、「税引前当期純利益 + 支払利息 – 受取利息 + 減価償却費 + 特別損失 – 特別利益」の公式を用います。この手法では、災害損失や資産売却損などの特別損益の影響も調整対象に含まれます。
特別損益は一時的な要因で発生することが多く、企業の継続的な収益力を評価する際には除外することが適切です。例えば、D社が災害により100万円の特別損失を計上した年でも、その影響を除外することで、正常時の収益力を正確に把握できます。M&Aにおける企業価値評価では、このような一時的要因の調整が重要な意味を持ちます。
中小企業特有の調整項目を反映する方法
中小企業では、オーナー経営者の判断により、役員報酬や保険料などが通常の水準と異なる場合があります。正確なEBITDAを算出するには、これらの影響を調整した「正常化EBITDA」を計算することが重要です。
具体的には、過大な役員報酬を適正水準に調整したり、節税目的で計上された保険料を除外したりする作業が必要です。例えば、E社の役員報酬が相場より200万円高く、節税保険料が50万円計上されている場合、これらを調整してEBITDAを再計算します。中小企業M&Aでは、このような正常化調整により、企業の真の収益力を把握することが可能になります。
EBITDA関連指標で企業価値を評価
EBITDAそのものの数値も重要ですが、それを基にした関連指標を活用することで、企業の収益性、成長性、財務健全性をより多角的に評価できます。これらの指標は、M&Aにおける企業価値算定や投資判断において、実務的な判断基準として広く活用されており、特に中小企業の評価では欠かせないツールとなっています。
収益性を示すEBITDAマージンの活用法
EBITDAマージンは、「EBITDA ÷ 売上高 × 100」で計算される指標で、売上高に占めるEBITDAの割合を表します。この指標により、企業が売上からどれだけ効率的にキャッシュフローを生み出しているかを把握できます。
例えば、売上高100億円、営業利益5億円、減価償却費2億円の企業では、EBITDAマージン = (5億円 + 2億円) ÷ 100億円 × 100 = 7%となります。このマージンが高いほど収益性が優れており、同業他社との比較や経年変化の分析に有効です。設備投資の変動が大きい企業では、営業利益率よりもEBITDAマージンの方が、実質的な収益力を正確に反映します。
M&A価格の目安となるEBITDA倍率
EBITDA倍率(EV/EBITDA倍率)は、企業価値(EV)をEBITDAで割った値で、簡易買収倍率とも呼ばれます。この指標は、買収にかかる投資を何年分のEBITDAで回収できるかを示し、M&Aの価格妥当性を判断する重要な基準となります。
中小企業M&Aでは、非上場であることのリスクなどを考慮して3〜5倍程度が目安とされることが多く見られます。
例えば、類似企業のEBITDA倍率が平均6倍で、対象企業のEBITDAが1億円の場合、企業価値の目安は6億円となります。ただし、業界特性や成長性、リスク要因などにより倍率は大きく変動するため、単純な計算だけでなく、総合的な判断が必要です。投資回収期間が短いほど割安と判断され、買収の魅力度が高まります。
財務健全性がわかるEBITDA有利子負債倍率
EBITDA有利子負債倍率は、「(有利子負債 – 現預金) ÷ EBITDA」で計算され、企業の負債返済能力と財務健全性を評価する指標です。現在の収益力で有利子負債を何年で返済できるかを示し、倍率が低いほど財務状況が良好と判断されます。
一般的に、3倍以下であれば健全、5倍を超えると財務リスクが高いとされていますが、業種によっては10倍以下なら健全とされる場合もあり、目安は業界・業種によって異なります。
例えば、有利子負債5,000万円、現預金1,000万円、EBITDA800万円の企業では、EBITDA有利子負債倍率 = (5,000万円 – 1,000万円) ÷ 800万円 = 5倍となります。この倍率を改善するには、EBITDAの向上(収益性改善)または有利子負債の削減が有効です。金融機関の融資判断や信用力評価においても重要視され、M&Aでは買収後の財務リスクを評価する際の判断材料として活用されます。
EBITDAとEBITの違いと使い分け
EBITDAと類似の指標として「EBIT(Earnings Before Interest and Taxes)」があります。両者は企業価値評価において重要な役割を果たしますが、計算方法や適用場面が異なるため、その特徴を理解して適切に使い分けることが重要です。特にM&Aや投資判断の現場では、対象企業の特性に応じた指標選択が、正確な評価につながります。
減価償却費を含むか含まないかの差
EBITとEBITDAの最も基本的な違いは、減価償却費の取り扱いにあります。EBITは「税引前当期純利益 + 支払利息 – 受取利息」で計算され、減価償却費は含まれません。一方、EBITDAは「EBIT + 減価償却費」または「営業利益 + 減価償却費」で計算されます。
この違いにより、EBITは企業の純粋な収益力に焦点を当て、EBITDAはキャッシュフローに近い指標となります。設備投資が少ないサービス業では両者の差は小さくなりますが、製造業では大きな差が生じることがあります。
設備投資が多い業種での使い分け方
設備投資の規模や業種特性により、EBITとEBITDAの使い分けが重要になります。製造業、インフラ業、宿泊業など、大規模な設備投資を要する業種では、減価償却費の影響が大きくなるため、EBITDAがより実態を反映します。
一方、コンサルティング業、IT系サービス業、小売業など、設備投資が相対的に少ない業種では、EBITでも十分に企業の収益力を評価できます。M&Aにおいては、スタートアップ企業や成長初期の企業で、多額の借入により資金調達を行っている場合、支払利息の影響を除外できるEBITが有効です。対象企業の業種特性や成長ステージを考慮した指標選択により、より正確な企業価値評価が可能になります。
国際比較で威力を発揮する理由
EBITDAが国際的な企業比較で広く活用される理由は、税制、金利水準、会計基準の違いを効果的に排除できることにあります。各国で異なる法人税率、借入金利、減価償却方法の影響を受けずに、企業の本質的な収益力を比較評価できます。
例えば、日本企業と海外企業を比較する際、日本の法人税率が約30%、対象国が20%であっても、EBITDAであれば税率差の影響を受けません。また、金融政策の違いにより借入金利が大きく異なる場合でも、支払利息を除外することで公平な比較が可能です。
グローバルなM&Aや投資判断では、このような標準化された指標として、EBITDAの有用性が特に高く評価されています。多国籍企業の各拠点の業績評価や、国際的な同業他社との競争力分析においても、EBITDAは欠かせない指標となっています。
※参照:国税庁「No.5759 法人税の税率」
EBITDA活用時の落とし穴と対策
EBITDAは企業価値評価において非常に有用な指標ですが、万能ではありません。特に中小企業のM&Aでは、オーナー企業特有の会計処理や経営判断により、EBITDAが企業の真の収益力を正確に反映しない場合があります。これらの落とし穴を理解し、適切な対策を講じることで、より正確な企業評価が可能になります。
役員報酬の過大計上で利益が見えなくなる問題
中小企業では、オーナー経営者の意向が強く反映されるため、役員報酬が市場水準から大きく乖離することがあります。過大な役員報酬が計上されている場合、本来の収益力があるにも関わらず、EBITDAが小さく算出され、企業価値が過小評価される恐れがあります。
例えば、同業他社の役員報酬相場が年間800万円であるのに対し、対象企業が1,500万円を計上している場合、実質的に700万円の利益が役員報酬として処理されていることになります。この調整を行わずにEBITDAを計算すると、企業の真の収益力を見誤ってしまいます。
M&Aの際には、適正な役員報酬水準を調査し、過大部分を利益に加え戻した「正常化EBITDA」を算出することが重要です。逆に、役員報酬が極端に少ない場合も、将来的な人件費増加を見込んだ調整が必要になります。
節税保険料がEBITDAを歪める理由
中小企業では、節税対策として役員向けの生命保険や退職金準備のための保険に加入するケースが多く見られます。これらの保険料は会計上は費用として処理されるため、EBITDAを押し下げる要因となり、企業の実質的な収益力が見えにくくなります。
節税目的の保険料は、本業の収益力とは直接関係のない会計処理上の調整であり、企業の継続的な稼ぐ力を評価する際には除外すべき項目です。例えば、年間300万円の節税保険料を計上している企業では、この金額を調整することでより正確なEBITDAを算出できます。
ただし、保険料の中でも従業員の福利厚生に関わる部分は、事業運営に必要な費用として扱う必要があるため、保険の目的と内容を詳細に検討することが大切です。正常化の際には、保険の種類、目的、市場水準との比較を行い、適切な調整額を決定する必要があります。
減価償却後の設備更新コストを見落とすリスク
EBITDAの最大の弱点の一つは、過剰な設備投資による損失や将来の設備更新コストを適切に反映できないことです。減価償却費を除外するため、効果的でない設備投資を行った企業でも、短期的には良好なEBITDAを示すことがあります。
特に製造業では、生産設備の老朽化により将来的に大規模な設備投資が必要になる場合があります。EBITDAだけを見ていると、このような将来負担を見落とし、企業価値を過大評価してしまう危険性があります。対策としては、設備の耐用年数、更新計画、過去の設備投資効果を詳細に分析することが重要です。
また、同業他社と比較して異常に高いEBITDAを示している場合は、設備投資の妥当性や持続可能性を慎重に検証する必要があります。M&Aデューデリジェンスでは、技術的な設備調査と合わせて、将来の設備投資計画とその資金需要を十分に検討することが求められます。
EBITDAを使った企業価値の算定実例
EBITDAを活用した実際の企業価値算定では、「類似企業比較法(マルチプル法)」が最も実務的で効果的な手法として広く採用されています。この手法を具体例とともに解説し、実際のM&A現場でどのように活用されているかを見ていきましょう。中小企業M&Aでは、この手法により迅速かつ客観的な企業価値評価が可能になります。
類似企業比較法(マルチプル法)の具体的手順
類似企業比較法は、対象企業と事業内容や規模が類似する上場企業のEBITDA倍率を参考に、対象企業の企業価値を算定する手法です。まず、複数の類似上場企業のEV(企業価値)とEBITDAを調査し、EV/EBITDA倍率の平均値を算出します。次に、この平均倍率を対象企業のEBITDAに乗じることで企業価値を求めます。
例えば、製造業のA社の企業価値を評価する場合を見てみましょう。同業の上場企業3社のEBITDA倍率がそれぞれ6倍、7倍、8倍だった場合、平均は7倍となります。A社のEBITDAが1億円であれば、企業価値は7億円と算定されます。
さらに、この企業価値から有利子負債2億円を差し引き、現預金5,000万円を加えることで、株式価値6億5,000万円が導き出されます。この手法の利点は、市場で実際に取引されている企業の評価水準を反映できることです。
自社の適正価値を3ステップで計算する方法
自社の適正価値を算定する際は、以下の3ステップで進めます。第1ステップでは、自社のEBITDAを正確に算出します。営業利益に減価償却費を加え、必要に応じて正常化調整を行います。第2ステップでは、類似企業のEBITDA倍率を調査し、業界平均を算出します。第3ステップでは、自社EBITDAに業界平均倍率を乗じて企業価値を算定します。
具体例として、年商5億円のサービス業B社を考えてみましょう。B社のEBITDAが7,000万円、類似企業の平均EBITDA倍率が5倍の場合、企業価値は3億5,000万円となります。ただし、B社が業界平均を上回る成長性や収益性を持つ場合は、プレミアムを考慮して倍率を調整することもあります。
また、逆に特定のリスク要因がある場合は、ディスカウントを適用します。重要なのは、算定結果を鵜呑みにせず、企業の個別要因を十分に検討することです。
業界別EBITDA倍率の目安と活用法
業界ごとのEBITDA倍率には明確な特徴があり、これを理解することでより精度の高い企業価値評価が可能になります。
主要業界のEBITDA倍率目安
- IT・サービス業:8〜12倍(成長性が高く安定した収益構造)
- 製造業:6〜10倍(設備投資負担が大きい)
- 建設業:3〜6倍(景気変動の影響を受けやすい)
ただし、同じ業界内でも企業の成長ステージや競争優位性により倍率は大きく異なります。業界のリーディングカンパニーや特許技術を持つ企業は高い倍率で評価される一方、成熟市場で競争が激しい分野では低い倍率となる傾向があります。
M&A実務では、これらの業界特性を踏まえつつ、対象企業の個別要因を加味した総合的な評価を行います。また、中小企業の場合は、上場企業より一般的に低い倍率が適用されることが多く、規模や流動性の違いを考慮したディスカウントが必要になります。
まとめ|EBITDAを理解して納得のM&Aを
EBITDAは、企業の本質的な収益力を把握し、公正なM&A取引を実現するための重要な指標です。利払前・税引前・減価償却前利益として、設備投資や会計方針の違いに左右されない企業の稼ぐ力を示すことで、買い手と売り手双方にとって納得のいく企業価値評価を可能にします。
特に中小企業M&Aでは、EBITDAの計算方法や関連指標の活用法を正しく理解することが、適正な取引価格の実現につながります。一方で、役員報酬や節税保険料の調整、設備投資の影響など、EBITDAの限界も理解した上で、他の財務指標と組み合わせた総合的な評価を行うことが重要です。これらの知識を武器に、皆様のM&Aが成功することを願っています。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。