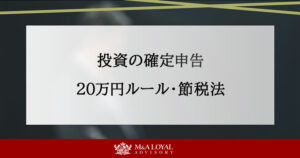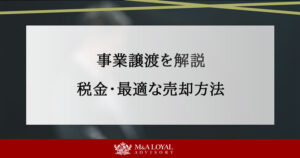配当金の税金と確定申告の完全ガイド!4つの節税条件と配当控除
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
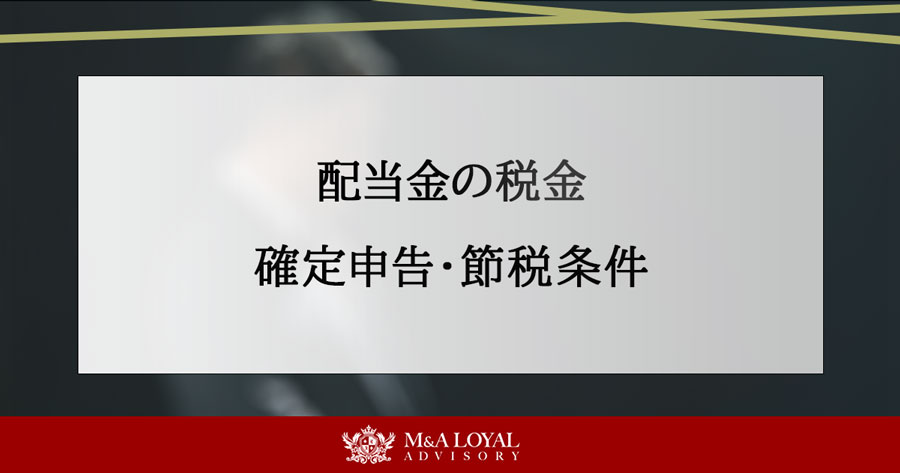
株式投資で配当金を受け取った際、「税金はどうなるの?」「確定申告は必要?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。配当金には複雑な税制が適用され、知らないまま放置していると思わぬ税負担を強いられたり、逆に大きな節税機会を逃してしまう可能性があります。
特に、M&Aで事業を譲渡した経営者や投資収益が増加している方にとって、配当金の税務処理は資産形成戦略の重要な要素となります。源泉徴収だけで終わらせるのか、確定申告で節税を図るのか、適切な判断により年間数十万円の税負担差が生まれることも珍しくありません。
本記事では、配当金の税制から確定申告の要否、効果的な節税テクニックまで、投資家が知っておくべき税務知識を体系的に解説します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



目次
配当金の税金の基本的な仕組み
株式投資を始めると、保有する株式から配当金を受け取る機会があります。配当金は投資家にとって嬉しい収入ですが、税制について正しく理解していないと、思わぬ税負担や手続きの漏れに繋がる可能性があります。特に、M&A後の資産運用を検討している中小企業経営者の方にとって、配当金の税制を理解することは効率的な資産形成を実現するための重要な要素となります。
配当金にかかる税率と源泉徴収制度
配当金には所得税と住民税が課税され、支払い時に源泉徴収される仕組みとなっています。上場株式の配当金(大口株主以外)の場合、源泉徴収される税率は合計20.315%で、内訳は所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。
この源泉徴収制度により、配当金を受け取った時点で税金が自動的に差し引かれるため、基本的には確定申告をする必要がありません。これを「申告不要制度」と呼び、投資家の手続きの負担を軽減する重要な仕組みです。
例えば、10万円の配当金を受け取った場合、源泉徴収税額は20,315円となり、実際に受け取る金額は79,685円となります。証券会社から送付される支払通知書で、この源泉徴収税額を確認することができます。
上場株式と非上場株式の税率の違い
配当金の税率は、株式が上場しているかどうかによって異なります。上場株式の場合は上記の通り20.315%ですが、非上場株式の配当金については所得税のみが源泉徴収され、税率は20.42%となります。
また、上場株式であっても発行済み株式総数の3%以上を保有する大口株主の場合は、非上場株式と同様の扱いとなり、所得税20.42%のみが源泉徴収されます。この場合、住民税については別途申告が必要となるため注意が必要です。
・上場株式(一般株主):20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
・非上場株式・大口株主:20.42%(所得税のみ)
・NISA口座:非課税
なお、少額配当に該当する場合(1回に受け取る配当が年換算で10万円以下など)は、所得税の確定申告は不要とすることができますが、住民税には申告不要制度が存在しないため、原則として市区町村への申告が別途必要です。
NISA口座での配当金の非課税メリット
NISA(少額投資非課税制度)口座で保有している株式の配当金は、完全に非課税となります。源泉徴収されることもなく、確定申告も不要です。ただし、この非課税メリットを享受するためには、金融庁や日本証券業協会も注意喚起している通り、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。
株式数比例配分方式を選択すると、配当金は株式を保有している証券口座に直接入金されます。他の受取方式(登録配当金受領口座方式や個別銘柄指定方式など)を選択すると、NISA口座で保有していても課税されてしまうため、事前に受取方法を確認しておくことが重要です。
NISA口座での投資は、中小企業経営者の方がM&A後の資金を効率的に運用する際の有力な選択肢となります。年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円となっており、配当収入の非課税メリットを最大限活用することで、長期的な資産形成を効率化できます。
配当金の確定申告が必要な3つのケース
配当金は基本的に源泉徴収により税務処理が完了しますが、株式の種類や受取状況によっては確定申告が義務となるケースがあります。特に中小企業の経営者や投資家の方は、自社株や取引先企業の非上場株式を保有することも多く、これらの配当金については注意深く税務処理を行う必要があります。確定申告を怠ると、追徴課税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、該当するケースを正確に把握しておくことが重要です。
非上場株式の配当金を受け取った場合
非上場株式から配当金を受け取った場合は、原則として確定申告が必要となります。非上場株式の配当金は上場株式とは異なる税務上の取り扱いを受け、所得税20.42%のみが源泉徴収されます。住民税については源泉徴収されないため、別途確定申告での納税が必要です。
ただし、「少額配当」に該当する場合は所得税の確定申告が不要となります。少額配当とは、1回に受け取る配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」で計算した金額以下のものを指します。
例えば、年1回配当を行う企業(配当計算期間12か月)の場合、配当金額が10万円以下であれば所得税の申告は不要です。しかし、少額配当に該当する場合でも住民税の申告は必要であり、市町村への申告書提出を忘れないよう注意が必要です。
中小企業の経営者がM&A後に関連企業の非上場株式を保有している場合、配当金の受取状況を適切に管理し、税務処理を確実に行うことが求められます。
大口株主として配当金を受け取った場合
上場株式であっても、発行済み株式総数の3%以上を保有する大口株主に該当する場合は、確定申告が必要となります。大口株主の配当金は、非上場株式と同様に所得税20.42%のみが源泉徴収され、住民税については別途申告が必要です。
大口株主の判定は、国税庁の定めるルールに基づき、2023年10月1日以降に支払われる配当からより厳格になりました。従来は個人が直接保有する株式数のみで判定されていましたが、新ルールでは個人株主本人の保有分に加え、その個人が支配する同族会社が保有する株式数も合算して3%以上かどうかを判定します。このため、資産管理会社などを通じて株式を保有している経営者の方は、意図せず大口株主と認定され、総合課税での確定申告が義務付けられる可能性があるため、特に注意が必要です。
給与所得以外の所得が20万円を超える場合
給与所得者であっても、給与・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。この「給与所得以外の所得」には、上場株式の配当金、株式の譲渡益、不動産所得、副業収入などが含まれます。
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で配当金を受け取っている場合、その配当所得も20万円の判定対象となります。例えば、配当所得が15万円、副業による所得が8万円ある場合、合計23万円となり確定申告が必要です。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当金については、申告不要制度を選択している限り、この20万円の判定対象には含まれません。また、NISA口座での配当金は非課税のため、20万円の計算に含める必要はありません。
中小企業経営者の場合、複数の収入源があることが多いため、各種所得を正確に把握し、20万円基準を超えるかどうかを慎重に判断することが重要です。申告が必要にもかかわらず手続きを怠ると、本税に加えて無申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります。
配当金の確定申告で節税できる条件
配当金の確定申告は原則不要ですが、特定の条件下では確定申告を行うことで大幅な節税効果を得ることができます。特に中小企業経営者の方やM&A後の資産運用を検討している方にとって、これらの節税条件を理解することは重要な資産形成戦略の一部となります。ここでは、実際に税負担を軽減できる4つの主要な条件について、具体的な効果とともに詳しく解説します。
課税所得が695万円以下の場合
課税所得が695万円以下の方は、配当金について総合課税を選択し配当控除を適用することで、源泉徴収税率よりも低い実質税率で配当収入を得ることができます。
この695万円という基準は、令和4年度税制改正により2023年分所得(2024年の確定申告)から所得税と住民税の課税方式が統一されたことで、その重要性が増しています。従来は所得税で「総合課税」を選択し、住民税では税率の低い「申告不要制度(税率5%)」を選ぶという有利な組み合わせが可能でしたが、現在はできなくなりました。総合課税を選択すると、住民税率も源泉徴収の5%ではなく、配当控除(2.8%)を適用した後の実質7.2%となるため、この点を考慮して有利不利を慎重に判断する必要があります。
配当控除により、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、所得税から配当所得の10%、住民税から2.8%が控除されます。例えば、課税所得500万円の方が50万円の配当金を受け取った場合、源泉徴収税率20.315%では101,575円の税負担となりますが、総合課税で配当控除を適用すると実質税率は17.41%となり、税負担は87,050円に軽減されます。
・課税所得195万円以下:実質税率7.2%(源泉徴収20.315%との差13.115%)
・課税所得330万円以下:実質税率7.2%
・課税所得695万円以下:実質税率17.41%(源泉徴収20.315%との差2.905%)
なお、課税所得とは年収から給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の金額のため、年収に換算すると695万円よりもかなり高い金額になります。
株式の売却損失が発生している場合
株式の売却で損失が発生している年に配当金を受け取った場合、申告分離課税を選択することで損益通算により大幅な節税効果を得ることができます。損益通算とは、同一年内の利益と損失を相殺して最終的な課税所得を計算する制度です。
例えば、A証券で80万円の配当金を受け取り、B証券で100万円の譲渡損失が発生した場合、確定申告で申告分離課税を選択し損益通算を行うと、配当所得80万円と譲渡損失100万円が相殺されます。これにより、その年の課税対象となる所得は0円となり、配当金から源泉徴収された約16万円(80万円×20.315%)が全額還付されます。さらに、控除しきれなかった譲渡損失20万円は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越すことが可能です(繰越控除)。
損益通算の対象となる損失には、上場株式の譲渡損失、公募株式投資信託の譲渡損失、公社債の譲渡損失などが含まれ、配当所得と同じ申告分離課税の枠内で処理されます。ただし、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できないため、申告方法の選択に注意が必要です。
特定口座で配当と譲渡損が同一口座にある場合
特定口座(源泉徴収あり)で「配当等受入あり」の設定をしている場合、同一口座内で発生した譲渡損失と配当金が年末に自動的に損益通算されるため、確定申告をしなくても節税効果を享受できます。この仕組みは投資家の手続き負担を軽減する優れた制度です。
自動損益通算の条件は以下の通りです。
・特定口座(源泉徴収あり)を開設していること
・配当金等受入機能を「あり」に設定していること
・配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していること
・同一口座内で譲渡損失と配当収入が発生していること
例えば、同一の特定口座内で年間120万円の譲渡損失と30万円の配当収入があった場合、自動的に損益通算されて損失90万円となり、配当金から源泉徴収された約6万円が口座に還付されます。
ただし、繰越控除の適用を受けるためには確定申告が必要であり、また異なる証券会社間での損益通算は自動では行われないため注意が必要です。
過去3年以内に繰越可能な損失がある場合
過去3年以内に確定申告により繰り越した上場株式等の譲渡損失がある場合、申告分離課税を選択することで、配当所得と繰越損失を損益通算し、節税効果を得ることが可能です。繰越控除制度は、上場株式等や特定公社債等の譲渡損失を、翌年以降の課税所得から控除する仕組みで、最大3年間繰り越して利用できます。
繰越控除を適用するためには、損失が発生した年から連続して確定申告を行う必要があります。たとえ譲渡取引がない年であっても、繰越控除を継続するためには毎年確定申告書を提出する必要があります。
具体例として、2022年に確定申告により150万円の譲渡損失を繰り越し、2025年に配当所得100万円を得た場合を考えます。このとき、配当所得について申告分離課税を選択し、繰越控除を適用すると、配当所得100万円から繰越損失100万円を控除し、課税所得は0円となります。この結果、所得税について源泉徴収された約20万円が還付される可能性があります。ただし、住民税や他の所得の有無によって還付額は異なる場合があるため、正確な計算には注意が必要です。
- 繰越可能期間:損失発生年の翌年から3年間
- 必要手続き:連続した確定申告書の提出
- 適用対象:申告分離課税を選択した配当所得および譲渡益
- 控除順序:古い損失から順次控除
中小企業経営者がM&A後の投資で一時的な損失を計上した場合、この繰越控除制度を戦略的に活用することで、将来の配当収入や譲渡益に対する税負担を軽減することが可能です。ただし、この制度は上場株式等や特定公社債等の譲渡損失に限定されるため、非上場株式やその他の金融商品の損失は対象外であることに留意してください。
配当金の税金を軽減する配当控除の活用法
配当控除は、配当金にかかる税負担を軽減する重要な制度です。この制度を正しく理解し活用することで、中小企業経営者やM&A後の資産運用を行う方々は、配当収入に対する税負担を大幅に軽減することができます。配当控除の背景、選択基準、具体的な計算方法について詳しく解説し、実際の投資戦略への活用方法をご紹介します。
配当控除が設けられた背景と二重課税の回避
配当控除制度は、配当金に対する二重課税を調整するために設けられた重要な税制上の仕組みです。企業が株主に配当金を支払う際、その原資となる企業利益には既に法人税が課されています。その上で配当金を受け取った個人投資家が所得税を支払うと、同一の経済価値に対して二重に税金が課されることになります。
この不公平を是正するため、配当控除制度により個人投資家の税負担が軽減されています。具体的には、国内に本店を持つ法人から受ける配当所得について、総合課税を選択した場合に限り、配当所得の一定割合を所得税額および住民税額から直接控除できる仕組みです。
配当控除の対象となるのは以下の配当等です。
・国内上場株式の配当金
・非上場株式の配当金
・国内株式投資信託の普通分配金
・日本株ETFの分配金
一方、外国株式の配当金、J-REITの分配金、外国株式投資信託の分配金は配当控除の対象外となるため注意が必要です。また、確定申告不要制度や申告分離課税を選択した配当所得についても配当控除は適用されません。
総合課税と申告分離課税の選択基準
配当金の確定申告では、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択でき、選択肢によってメリットが異なります。配当控除を受けるには総合課税を選択する必要があり、どちらが有利かは課税所得や投資状況によります。
総合課税では、配当所得が他の所得と合算され累進税率(所得税5%~45%)で課税されますが、配当控除により税負担が軽減されるため、課税所得が低い場合に有利になることがあります。ただし、課税所得が増えることで社会保険料や控除額に影響が出る可能性があります。
申告分離課税では、配当所得が一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で課税され、配当控除は適用されませんが、株式譲渡損失との損益通算が可能です。このため、株式投資で損失がある場合や課税所得が高い場合に有利となることが多いです。
どちらが有利かは配当金額や所得状況によるため、税額のシミュレーションを行うことが重要です。また、住民税については申告不要制度を活用することで負担軽減が可能な場合もあります。
配当控除額の具体的な計算例
配当控除額の計算は、課税総所得金額と配当所得の金額により決まります。課税総所得金額が1,000万円以下の場合、配当所得に対して所得税10%、住民税2.8%の控除率が適用されます。一方、1,000万円を超える部分については、所得税5%、住民税1.4%の控除率となります。
具体例1:課税総所得金額800万円(うち配当所得80万円)の場合 課税総所得金額が1,000万円以下のため、配当控除額は以下のように計算されます。
- 所得税の配当控除額:80万円 × 10% = 8万円
- 住民税の配当控除額:80万円 × 2.8% = 2.24万円
- 合計控除額:10.24万円
この結果、配当所得80万円に対する実質的な税負担は軽減されます。総合課税における所得税率20%(復興特別所得税を含む)、住民税率10%から配当控除を差し引くと、実質税率は所得税10.21%、住民税7.2%となり、合計17.41%です。
具体例2:課税総所得金額1,200万円(うち配当所得100万円)の場合 課税総所得金額が1,000万円を超えているため、配当控除率は以下のように適用されます。
- 1,000万円以下の部分(配当所得のうち80万円分):80万円 × 10% = 8万円(所得税)、80万円 × 2.8% = 2.24万円(住民税)
- 1,000万円超の部分(配当所得のうち20万円分):20万円 × 5% = 1万円(所得税)、20万円 × 1.4% = 0.28万円(住民税)
- 合計控除額:所得税9万円、住民税2.52万円
このように、高所得者の場合は配当控除の効果が限定的となるため、申告分離課税の方が有利となる場合があります。申告分離課税を選択した場合、配当所得に定率の税率(所得税15.315%、住民税5%)が適用されますが、配当控除は適用されません。
中小企業経営者がM&A後の資産運用を検討する際は、配当控除の効果と申告分離課税のメリットを比較し、自身の所得水準に応じて最適な申告方法を選択することが重要です。
M&A後の配当金戦略と税務対策
M&Aによる事業譲渡や株式譲渡で大きな資金を手にした中小企業経営者にとって、その後の資産運用戦略は重要な課題です。特に配当収入を中心とした資産運用を検討する際は、税務効率を最大化する戦略的なアプローチが求められます。ここでは、M&A後の資金を活用した配当金戦略と効果的な税務対策について詳しく解説します。
事業譲渡後の投資収益を最大化する方法
M&Aにより事業を譲渡した経営者が配当収入を重視した投資戦略を構築する際は、まず投資資金の性質と税務上の取り扱いを理解することが重要です。株式譲渡の場合、個人が受け取る譲渡益に対しては20.315%の分離課税が適用されますが、事業譲渡の場合は法人が受け取る譲渡益に約34%の法人税が課されます。
事業譲渡後の配当金戦略では、分散投資による安定的な配当収入の確保が基本となります。国内株式の配当金には配当控除が適用されるため、課税所得が695万円以下の場合は総合課税を選択することで実質税率を大幅に軽減できます。一方、外国株式の配当金は配当控除の対象外ですが、外国税額控除により二重課税を回避できます。
投資ポートフォリオの構築においては以下の配分を検討することが有効です。
・国内高配当株式:50-60%(配当控除の恩恵を最大活用)
・外国株式・ETF:20-30%(分散効果と成長性重視)
・REIT・インフラファンド:10-15%(安定的なインカムゲイン)
・債券・現金:10-15%(リスク調整とポートフォリオの安定化)
また、NISA口座の最大活用も重要な戦略です。年間投資枠(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)を活用することで、配当収入を完全に非課税とできます。M&A収益が大きい場合でも、長期的な視点で年間投資枠を継続活用することで、相当な節税効果を得ることができます。
法人化による配当金の税務メリット
M&A後の資産運用において、一定の投資規模になった場合は法人化による税務メリットを検討することが重要です。個人投資家が法人化を検討する基準として、年間投資収益が700~800万円を超える場合が一般的な目安とされています。ただし、法人化の判断には収益規模だけでなく、経費計上の範囲、資産規模、事業計画などを総合的に考慮する必要があります。
法人化による配当金の税務メリットは多岐にわたります。法人が受け取る配当金については、益金不算入制度が適用され、非支配目的株式(持株割合5%以下)の場合でも配当金の20%が益金不算入となり、実質的な税負担を軽減できます。一方、支配目的株式(持株割合25%以上)の場合は配当金が全額益金不算入となります。
個人の場合、配当金には20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用されます。一方、法人が非支配目的株式(議決権を3分の1未満保有)の配当金を受け取る場合、配当金の80%部分が益金不算入となり、残りの20%部分に法人税が課されます。法人実効税率を約30%と仮定すると、配当金全体に対する実効税率は約6%(20% × 30%)となります。これにより、法人化することで個人よりも税負担が軽減される場合があります。
さらに、法人化により経費計上の範囲が大幅に拡大します。投資関連の情報収集費用、セミナー参加費、書籍代、パソコンや投資ソフトの購入費用、事務所賃料、交通費などを必要経費として計上できるため、課税所得を圧縮することが可能です。
損益通算の面でも法人化は有利です。個人の場合、株式投資の損益通算は株式投資の利益に限定されますが、法人の場合、事業活動全体の損益通算が可能です。ただし、損益通算の範囲については税務上の制約があるため、事業所得や不動産所得などの範囲内で適用される点に留意が必要です。
また、損失の繰越制度においても法人が有利です。個人の場合、繰り越しができるのは「上場株式等の譲渡損失」に限定され、期間も最大3年間です。一方、法人の場合は事業活動全体で生じた赤字(欠損金)を最大10年間繰り越すことができます。株式投資の損失も他の事業の利益と相殺した後の赤字として繰り越せるため、より柔軟で強力な税務戦略が可能となります。
中小企業経営者の資産運用と配当戦略
中小企業経営者がM&A後に配当戦略を構築する際は、既存事業とのリスク分散と安定性を重視することが重要です。事業経営により既に十分なリスクを取っているため、投資ポートフォリオでは安定的な配当収入を重視した保守的なアプローチが適しています。
配当戦略の中核となるのは、連続増配企業や配当利回りが安定している優良企業への投資です。特に生活必需品、公益事業、通信、金融業界の企業は、景気変動に対する耐性があり、安定的な配当を期待できます。また、配当性向(利益のうちどれだけを配当に回すか)が持続可能な水準(一般的には50%以下)にある企業を選択することで、長期的な配当収入の安定性を確保できます。
税務効率を考慮した配当戦略では、所得の平準化も重要な要素です。配当控除を最大限活用するためには、配当収入を総合課税として申告し、課税所得が695万円以下となるよう調整することが有効です。例えば、大きな配当収入が見込まれる場合は、複数年にわたり投資を分散し、毎年の配当収入を均等化することで、税負担を最適化できます。一方、申告分離課税を選択する場合は配当控除が適用されない点に注意が必要です。
また、相続対策の観点からも配当戦略は有効です。安定的な配当収入を生み出す資産を保有することで、将来の相続税負担を軽減しつつ、次世代への資産承継をスムーズに行うことができます。特に法人化している場合、株式の一部を後継者に段階的に承継することで、相続税の負担を分散することが可能ですが、法人化に伴うコストや手続き上の複雑さも考慮する必要があります。
中小企業経営者にとって、M&A後の配当戦略は単なる投資収益の追求ではなく、長期的な資産形成と事業承継を見据えた総合的な戦略として位置づけることが重要です。
まとめ|配当金の税金と確定申告を理解して賢く節税しよう
配当金の税制は複雑ですが、正しく理解することで大幅な節税効果を得ることができます。課税所得695万円以下の方は総合課税で配当控除を活用し、株式投資で損失がある場合は申告分離課税で損益通算を検討しましょう。非上場株式の配当金や大口株主に該当する場合は確定申告が必要となるため、該当状況を正確に把握することが重要です。
M&A後の資産運用を検討している中小企業経営者の方は、投資規模に応じて法人化による税務メリットも視野に入れ、NISA口座の活用と併せて総合的な配当戦略を構築することをお勧めします。配当金の税務は個人の所得状況や投資環境により最適解が異なるため、具体的な節税対策については税理士などの専門家にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。