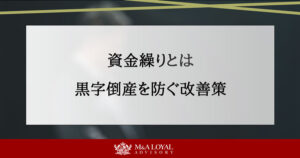減価償却の節税メリット|中小企業が知るべき5つの実践法と活用術
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
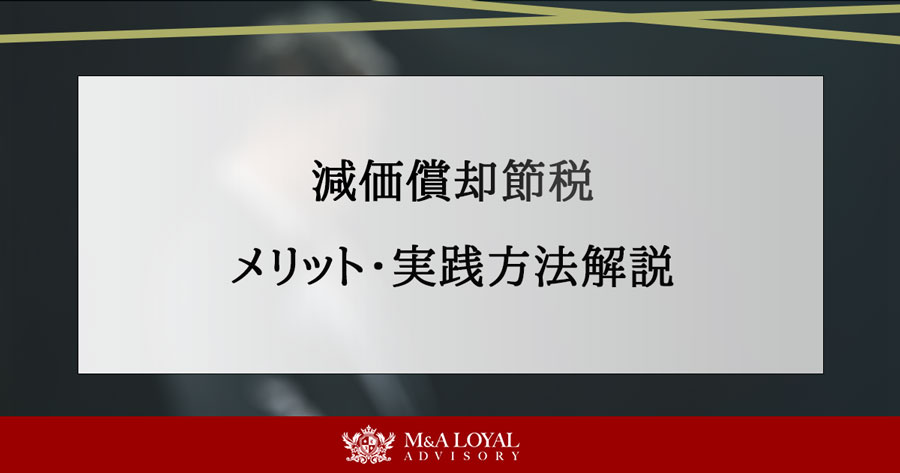
中小企業の経営者にとって、税負担の軽減は事業継続と成長のための重要な課題です。数ある節税手法の中でも、減価償却を活用した節税は効果を期待できる方法として注目されています。
設備投資や機械購入を検討する際、「どうせ必要な投資なら、税務面でも最大限のメリットを得たい」と考える経営者は多いでしょう。しかし、「減価償却は本当に節税になるのか」「具体的にどのような手法があるのか」「自社に最適な方法はどれか」といった疑問を抱える方も少なくありません。
実際、減価償却による節税には様々な誤解や見落としがちなポイントが存在します。適切な知識なしに取り組むと、期待した効果が得られないばかりか、税務調査でのリスクを招く可能性もあります。
本記事では、減価償却による節税の真の効果から実践的な活用術まで、中小企業が知るべき全ての知識を体系的に解説します。
目次
減価償却の節税効果はある?基本的な仕組みを解説
中小企業の経営者にとって、減価償却による節税効果は非常に関心の高いテーマです。設備投資を行う際に「減価償却で節税できる」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、減価償却がなぜ節税につながるのか、その具体的な仕組みを正しく理解している経営者は意外に少ないのが現状です。
減価償却は単に「税金を減らす」だけでなく、適切な期間損益計算を実現し、事業の財務状況を正確に把握するための重要な会計手法でもあります。この章では、減価償却の基本的な仕組みから節税効果、中小企業特有のメリットまで、体系的に解説していきます。
減価償却費が節税になる理由と条件
減価償却が節税効果を発揮する理由は、固定資産の取得費用を複数年にわたって経費計上できる点にあります。通常の経費は支払った年度に全額を計上しますが、10万円以上の固定資産については、その取得価額を法定耐用年数に応じて分割し、毎年減価償却費として経費に計上していきます。
例えば、500万円の機械設備を購入し、耐用年数が10年の場合、毎年50万円ずつ減価償却費を計上できます。この50万円は現金の支出を伴わない経費であるため、利益を圧縮して税負担を軽減する効果があります。
節税効果を得るための主な条件は以下の通りです。事業に直接使用する固定資産であること、正当な事業目的があること、適切な耐用年数で計算されていることが重要な要件となります。これらの条件を満たした減価償却費の計上により、継続的な節税効果を実現できます。
中小企業における減価償却の節税効果
中小企業にとって減価償却による節税効果は、資金繰りの改善と事業成長の促進という二つの側面で特に大きなメリットをもたらします。
まず資金繰りの観点では、減価償却費は現金支出を伴わない経費であるため、設備投資を行った年度以降、継続的にキャッシュフローの改善効果を期待できます。設備投資により一時的に現金が減少しても、その後の減価償却費計上により税負担が軽減され、実質的な資金回収が可能になります。
また、中小企業には少額減価償却資産の特例が適用されます。青色申告を行っている中小企業者は、30万円未満の固定資産について、年間300万円までを一括で経費計上することが可能です。この特例により、通常は複数年にわたって減価償却する固定資産を購入した年度に全額を経費として計上できるため、即効性の高い節税効果を実現できます。ただし、この特例を利用するためには、資産の種類や購入目的が事業に関連していることなど、いくつかの条件がありますので、詳細を税理士や専門家に相談することが推奨されます。
このように適切な設備投資と減価償却の活用を行うことで、生産性向上と税負担軽減を同時に達成できます。
一般的な経費との違いとメリット・デメリット
減価償却費は一般的な経費と比較して、独特の特性とメリット・デメリットを持ちます。
最大の違いは、現金支出のタイミングと経費計上のタイミングが異なる点です。通常の経費は支払いと同時に経費計上されますが、減価償却費は資産購入時に現金が減少し、その後複数年にわたって経費が計上されます。
メリットとしては、長期間にわたる安定した節税効果があげられます。定額法による減価償却では毎年同額の経費を計上でき、予測可能な税負担軽減効果を得られます。また、事業に必要な設備投資を行いながら同時に節税も実現できるため、企業の成長と税務効率の両立が可能です。
一方でデメリットとして、設備投資を行った初年度は多額の現金支出に対して経費計上額が限定的となり、一時的に税負担が重くなる可能性があります。また、設備の実際の価値減少と会計上の減価償却が必ずしも一致しないため、財務状況の把握が複雑になる場合もあります。
これらの特性を理解した上で、事業計画と連動した適切な設備投資と減価償却の活用が、中小企業の持続的な成長と効率的な税務管理の鍵となります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



減価償却の節税でよくある誤解と正しい判断基準
減価償却による節税については、多くの中小企業経営者の間で誤解が生じています。特に「減価償却は節税にならない」という考えや、赤字時の処理方法、各種特例の使い分けについて、正しい理解を持つことが重要です。
この章では、これらの誤解を解消し、適切な判断基準を提供することで、効果的な節税戦略の構築をサポートします。正しい知識に基づいた減価償却の活用により、中小企業の財務効率を最大化できます。
「減価償却は節税にならない」という誤解を解く
「減価償却は節税にならない」という誤解が生じるのは、主に初年度の現金支出と経費計上額のバランスから生じています。確かに設備投資を行った初年度は、多額の現金が出費される一方で、減価償却費として計上できる経費は購入価額の一部に限られます。
しかし、この見方は短期的視点に偏っています。減価償却の真の節税効果は、現金支出を伴わない経費を継続的に計上できる点にあります。例えば500万円の機械を購入した場合、初年度は現金が減少しますが、その後の耐用年数期間中は毎年継続して減価償却費を計上でき、その都度現金支出なしで税負担を軽減できます。
また、法人の場合は減価償却の計上が任意であるため、利益状況に応じて柔軟に調整可能です。これにより、赤字回避や税負担の平準化といった戦略的な財務管理が実現できます。
赤字の年に減価償却すべきかの判断基準
赤字の年における減価償却の取り扱いは、多くの経営者が迷う問題です。「赤字なのに経費を計上しても意味がない」と考える方もいますが、これは誤解です。
法人の場合、赤字年度に計上した減価償却費により増加した欠損金は、将来の黒字と相殺できます。この繰越期間は、欠損金が生じた事業年度の開始日によって異なり、2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金は10年間、それ以前に開始した事業年度の欠損金は9年間となります。この繰越欠損金は将来の黒字年度において利益と相殺でき、継続的な節税効果を発揮します。したがって、赤字年度であっても減価償却を計上することが一般的に推奨されます。
判断基準として重要なのは、将来の収益見込みと税務戦略です。継続的な成長が見込まれる企業では、赤字年度の減価償却計上により将来の税負担軽減を図れます。一方で、金融機関との融資交渉を控えている場合は、帳簿上の赤字拡大が評価に影響する可能性も考慮する必要があります。
※参照:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
一括償却資産と少額減価償却資産の使い分け方法
取得価額が10万円以上の資産については、金額に応じて特例の選択肢があります。特に10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」(中小企業者等のみ)のいずれかを選択できます。この使い分けが節税効果を左右する重要なポイントです。
少額減価償却資産の特例は、青色申告を行う中小企業者が年間300万円まで利用でき、購入年度に全額を即座に経費計上できます。即効性の高い節税効果を得られる一方で、償却資産税の課税対象となる点に注意が必要です。
一括償却資産は、取得価額を3年間で均等償却する制度で、償却資産税が非課税となるメリットがあります。また、年間利用額に制限がないため、大量の資産購入時に有効です。
- 即時節税を重視する場合:少額減価償却資産の特例を活用
- 償却資産税の負担軽減を重視する場合:一括償却資産を選択
- 利用額が300万円を超える場合:一括償却資産の併用を検討
資産ごとに個別選択が可能であるため、税務状況と事業計画に応じた戦略的な使い分けが重要です。
※参照
・中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
・国税庁「一括償却資産とは」
減価償却の節税を成功させる5つの実践方法
減価償却による節税効果を最大化するためには、基本的な仕組みを理解するだけでなく、実践的な手法を戦略的に活用することが重要です。中小企業が利用できる様々な制度や計算方法を組み合わせることで、大幅な節税効果を実現できます。
この章では、即効性のある方法から長期的な戦略まで、実際に活用できる5つの実践方法を詳しく解説します。これらの手法を適切に組み合わせることで、企業の財務状況と事業計画に最適化された節税戦略を構築できます。
中古資産の購入による償却期間の短縮
中古資産の購入は、減価償却による節税効果を短期間で最大化する最も効果的な手法の一つです。中古資産は既に使用されているため、新品と比較して大幅に短縮された耐用年数で償却できます。
中古資産の耐用年数は簡便法により計算されます。計算式は記事の通りですが、重要なルールがあります。算出した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、計算結果が2年未満になった場合は耐用年数を2年とします。例えば、法定耐用年数6年の普通自動車で7年落ちの中古車を購入した場合、「6年×20%=1.2年」となります。計算結果が2年未満のため、ルールに基づき耐用年数は2年となります。
この場合、新品であれば6年かけて償却する資産が中古では2年で完了でき、年間の減価償却費を増加させることができます。特に決算期前の設備投資において、即効性の高い節税効果を実現できる優れた手法です。
少額減価償却資産の特例活用
少額減価償却資産の特例は、中小企業が活用できる最も即効性の高い節税制度です。青色申告を行う中小企業者は、30万円未満の固定資産について年間300万円まで即座に全額経費計上できます。
この特例の最大のメリットは、通常であれば複数年にわたって償却する資産を購入年度に一括で経費化できる点です。例えば、耐用年数5年のパソコンを25万円で購入した場合、通常は年間5万円ずつ5年間で償却しますが、特例を適用すれば初年度に25万円全額を経費計上できます。
- パソコン、プリンター、ソフトウェア:業務効率化と節税の両立
- 事務用家具、什器:オフィス環境改善と税負担軽減
- 小型機械設備:生産性向上と即時償却効果
年間300万円の上限を効果的に活用するため、複数の資産購入を計画的に組み合わせることが重要です。
定率法と定額法の使い分け戦略
償却方法の選択は、節税効果のタイミングを大きく左右する重要な戦略です。定率法は初年度に最大の償却額を計上でき、定額法は毎年均等な償却額で安定した節税効果を得られます。
定率法では初年度の償却率が定額率の約2倍(200%定率法)となり、早期の資金回収効果が期待できます。特に設備投資による現金支出が大きい年度において、定率法の選択により税負担を大幅に軽減できます。一方、定額法は予算計画が立てやすく、長期的な財務管理に適しています。
使い分けの基準として、資金繰りが厳しい年度や大型投資を行う年度では定率法を、安定的な経営を重視する場合は定額法を選択することが効果的です。なお、建物に加え、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物についても、定額法が強制適用となる点に注意が必要です。
事業供用のタイミング調整
減価償却の開始時期である事業供用日のタイミング調整は、年間の償却額を最適化する重要な技術です。減価償却費は月割計算されるため、期首に近いタイミングで事業供用することで年間償却額を最大化できます。
例えば、3月決算の企業が4月初旬に設備を導入すれば4月から翌年3月までの12か月分の償却費を計上できますが、翌年3月の導入では1か月分しか計上できません。同じ設備投資でも、供用開始タイミングにより初年度の節税効果は12倍の差が生じます。
計画的なタイミング調整により、事業年度の利益状況と設備投資時期を最適に組み合わせ、効率的な税負担管理を実現できます。ただし、実際の事業開始前の供用開始は認められないため、適切な事業使用が前提となります。
計画的な設備投資による長期節税効果
持続的な節税効果を実現するためには、事業計画と連動した戦略的な設備投資が不可欠です。単発的な節税目的の投資ではなく、生産性向上と税務効率を両立させる長期的なアプローチが重要です。
効果的な設備投資計画では、耐用年数の異なる複数の資産を組み合わせ、毎年安定した償却費を確保します。例えば、耐用年数5年の機械設備と10年の建物附属設備を組み合わせることで、長期間にわたる継続的な節税効果を創出できます。
また、事業の成長段階に応じて設備投資の規模とタイミングを調整し、利益増加と税負担軽減のバランスを最適化することが重要です。将来の事業拡大を見据えた計画的な投資により、企業成長と効率的な税務管理を同時に実現できます。
中小企業が活用できる減価償却の節税優遇措置
減価償却による節税効果をさらに高めるため、政府は中小企業向けの特別な税制優遇措置を用意しています。これらの制度を活用することで、通常の減価償却を大幅に上回る節税効果を実現できます。
特に設備投資やDX化、脱炭素化への取り組みを支援する制度が充実しており、事業の近代化と節税を同時に達成する絶好の機会となっています。この章では、中小企業が実際に活用できる主要な優遇措置について、最新の改正内容も含めて詳しく解説します。
中小企業投資促進税制の具体的な活用方法
中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を支援する代表的な制度で、適用期間は2027年3月31日まで延長されています。この制度では、160万円以上の機械装置等を取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかを選択できます。
対象となる事業者は、資本金1億円以下の法人または従業員1,000人以下の個人事業主で、青色申告を行っていることが条件です。対象業種も幅広く、製造業、建設業、農業、卸売業、小売業に加え、2021年改正により不動産業や物品賃貸業も追加されました。
- 機械装置:1台160万円以上
- 器具備品:1台120万円以上(複数合計可)
- ソフトウェア:1つ70万円以上
税額控除を選択できるのは資本金3,000万円以下の中小企業に限定されますが、7%の直接的な税額減額効果は非常に大きな節税メリットをもたらします。例えば500万円の設備投資を行った場合、35万円の税額控除を受けることができ、実質的な投資負担を大幅に軽減できます。
中小企業経営強化税制による即時償却
中小企業経営強化税制は、より強力な節税効果を提供する制度で、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が対象となります。この制度の最大の特徴は、設備取得価額の全額を即時償却できる点にあります。
適用を受けるためには、事前に中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を策定し、認定を受ける必要があります。この計画では、生産性向上や収益力強化の具体的な目標を設定し、その達成手段として設備投資を位置づけます。
対象設備は主に以下の類型に分類されます(2025年度税制改正後)。
- A類型(生産性向上設備):生産効率等の指標が年平均1%以上向上する設備。
- B類型(収益力強化設備):投資利益率が年平均7%以上の投資計画に含まれる設備。
- D類型(経営資源集約化設備):M&Aなど経営資源の集約化に資する設備。
- E類型(拡充枠):(新設)売上高100億円超を目指す成長意欲の高い中小企業を対象とし、一定の要件下で建物も対象となる拡充措置。
即時償却により初年度に設備投資額を全額経費計上できるため、大規模な設備投資を行う年度において劇的な節税効果を実現できます。
カーボンニュートラル投資促進税制の活用
脱炭素化という現代の重要課題に対応する「カーボンニュートラル投資促進税制」という特別な税制が用意されています。
カーボンニュートラル投資促進税制では、脱炭素化と付加価値向上を両立する設備投資に対して、最大10%の税額控除(中小企業は最大14%)または50%の特別償却を適用できます。対象設備は生産工程効率化設備等で、投資上限は500億円です。
この制度は、税額控除の合計で法人税額の20%が上限となりますが、現代の経営課題解決と大幅な節税を同時に実現できる非常に魅力的な制度です。申請には専門的な計画策定と長期間の審査が必要なため、早期の準備と専門家との連携が成功の鍵となります。
※参照:経済産業省「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」
減価償却による節税の注意点とリスク回避
減価償却による節税は効果的な手法ですが、適切な処理を行わなければ税務調査での指摘や予期せぬリスクを招く可能性があります。特に中小企業では、知識不足による誤った判断が後に大きな問題となるケースが少なくありません。
この章では、減価償却を活用した節税において特に注意すべきポイントと、それらのリスクを回避するための具体的な対策を解説します。適切な知識と準備により、安全かつ効果的な節税を実現できます。
資金繰り悪化を防ぐための対策を実行する
減価償却による節税の最大のリスクは、設備投資による一時的な現金支出と税務上の経費計上のタイミングずれによる資金繰り悪化です。特に大型の設備投資を行った年度は、多額の現金が流出する一方で、減価償却費として計上できるのは取得価額の一部に限られます。
このリスクを回避するためには、事前のキャッシュフロー計画が不可欠です。設備投資計画を策定する際は、投資年度の現金流出と複数年にわたる減価償却費による節税効果を総合的に評価し、各年度の資金需要を正確に予測する必要があります。
また、設備投資のタイミング調整も重要な対策です。利益が十分に確保できる年度や、他の大きな現金支出予定がない時期に投資を集中させることで、資金繰りへの負担を最小化できます。
- 金融機関との事前相談:大型投資前の融資枠確保
- 段階的投資:一度に全額投資せず複数年に分散
- 緊急資金の確保:予期せぬ資金需要への備え
さらに、減価償却の特例制度を活用することで、初年度の節税効果を最大化し、実質的な資金負担を軽減することも効果的な対策となります。
耐用年数を正確に把握して計算ミスを避ける
耐用年数の誤認定は税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。国税庁の耐用年数表は細かく分類されており、同じような資産でも用途や構造により大きく異なる年数が設定されています。
資産の正確な分類には、「何から作られているか」「何の目的で使用するか」を明確に把握することが重要です。例えば、同じコンピューターでも事務用と制御用では耐用年数が異なり、建物についても構造材料と用途により大幅に変わります。
判断が困難な場合は、実務問答集や国税庁の通達を参照し、類似事例を確認することが有効です。また、中古資産の場合は、簡便法による耐用年数の短縮計算を正確に行う必要があります。
税務調査では、事業供用日の記録も重要な確認事項となります。購入日と実際の使用開始日が異なる場合は、使用開始日の証拠書類(作業日報、入居者管理簿など)を整備し、適切な償却開始時期を証明できるよう準備することが必要です。
税務調査で指摘されないための準備を行う
税務調査における減価償却関連の指摘を避けるためには、日常的な証拠書類の整備と正確な会計処理が不可欠です。調査官は特に取得価額の範囲、修繕費との区分、少額減価償却資産の判定について詳細に確認します。
取得価額については、本体価格以外の付随費用(運搬費、据付費、設計費など)も含める必要があります。これらの費用を誤って支出時に経費処理していると指摘される可能性が高いため、設備投資時は関連するすべての支出を洗い出し、適切に取得価額に算入することが重要です。
修繕費と資本的支出の区分も頻繁に指摘される項目です。原状回復を超える改良・改修は資本的支出として減価償却の対象となるため、工事内容を詳細に記録し、判断根拠を明確にしておく必要があります。
- 領収書・契約書の整理:取得関連費用の完全な記録保存
- 事業供用日の証明:使用開始を示す客観的証拠の準備
- 資産台帳の整備:取得から除却まで一貫した管理記録
また、少額減価償却資産の特例適用時は、30万円未満の判定を慎重に行い、関連資産との一体性も考慮する必要があります。応接セットのように複数資産で構成される場合は、合計額で判定することも重要なポイントです。
定期的な税理士との打合せにより、処理方法の確認と最新の法改正情報の把握を行うことで、税務調査でのリスクを大幅に軽減できます。
減価償却の節税効果を最大化するための実践的なポイント
減価償却による節税効果を真に最大化するためには、単発的な設備投資ではなく、長期的な視点に立った戦略的なアプローチが必要です。事業の成長段階、利益状況、将来展望を総合的に勘案し、計画的な減価償却活用により持続的な節税効果を実現できます。
この章では、減価償却の節税効果を最大化するための3つの核心的なポイントを詳しく解説します。これらの実践により、単なる節税を超えて、企業の競争力強化と財務効率化を同時に達成できます。
事業計画と連動した設備投資戦略を立てる
減価償却の節税効果を最大化するためには、事業計画と設備投資を一体的に捉えた戦略的なアプローチが不可欠です。中長期的な事業展開、収益予測、投資計画を統合的に検討することで、最適なタイミングと規模での設備投資を実現できます。
事業計画との連動においては、まず5年から10年程度の中期的な利益予測を行い、各年度の税負担と投資資金需要のバランスを詳細に分析します。利益が大きく増加する年度には積極的な設備投資により税負担を軽減し、利益が低調な年度には投資を控えて資金を温存するという動的な調整が重要です。
また、耐用年数の異なる複数の資産を組み合わせることで、長期間にわたる安定した減価償却費を確保できます。例えば、機械設備(耐用年数10年)、IT設備(耐用年数4-5年)、建物附属設備(耐用年数15年)を計画的に組み合わせることで、毎年一定の減価償却費を計上し続けることが可能になります。
さらに、事業の成長段階に応じた投資戦略も重要です。創業期や急成長期には生産性向上に直結する設備への集中投資、成熟期には効率化や省力化設備への投資というように、事業ニーズと節税効果を両立させる戦略的な設備選択が求められます。
税理士と効果的に連携して節税プランを作成する
減価償却による節税効果の最大化には、税務の専門知識と最新の法改正情報が不可欠です。税理士との効果的な連携により、個社の状況に最適化された節税プランを構築できます。
税理士との連携においては、定期的な業績レビューと税務計画の見直しが重要です。四半期ごとに業績動向を確認し、年間の利益予測に基づいて設備投資計画を調整することで、過不足のない最適な節税対策を実施できます。
また、税制優遇措置の活用についても税理士の専門的なサポートが欠かせません。中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、DX投資促進税制などの複雑な要件と手続きについて、税理士と緊密に連携することで確実な適用を実現できます。
- 月次業績確認:利益動向と投資タイミングの最適化
- 制度活用支援:税制優遇措置の要件確認と申請サポート
- 税務リスク管理:適正な処理による税務調査対策
さらに、税理士との連携により、グループ全体での税務最適化も可能になります。複数の事業所や関連会社がある場合、全体最適の観点から減価償却戦略を調整することで、より大きな節税効果を実現できます。
同業他社の成功事例を分析して自社に応用する
業界内の成功事例や同規模企業のベストプラクティスを分析することで、自社の減価償却戦略をさらに洗練させることができます。他社の取り組みから学ぶことで、見落としていた節税機会や効率的な手法を発見できる可能性があります。
同業他社の分析においては、設備投資のタイミング、投資対象の選択、税制優遇措置の活用状況などを多角的に検討します。特に、同じような事業規模や成長段階にある企業の事例は、自社への応用可能性が高く、具体的な参考になります。
業界団体や商工会議所などが発行する事例集、税理士法人の発表する成功事例、同業者との情報交換会などを通じて、幅広い情報収集を行うことが重要です。また、競合他社の決算書分析により、減価償却費の計上状況や設備投資の傾向を把握することも有効な手法です。
ただし、他社事例を自社に適用する際は、事業内容、財務状況、将来計画の違いを十分に考慮する必要があります。表面的な模倣ではなく、自社の実情に合わせたカスタマイズが成功の鍵となります。
また、成功事例の継続的な収集と分析により、減価償却戦略を常にアップデートし続けることが重要です。税制改正や技術革新により最適解は変化するため、柔軟な戦略見直しが持続的な節税効果の実現には不可欠です。
まとめ|減価償却を活用して持続的な節税効果を実現しよう
減価償却による節税は、正しい知識と戦略的な活用により、中小企業にとって極めて有効な税負担軽減手法です。本記事で解説した5つの実践方法と各種優遇措置を組み合わせることで、大幅な節税効果を実現できます。
特に重要なのは、中古資産の活用、少額減価償却資産の特例、税制優遇措置の積極的な利用です。これらを事業計画と連動させた長期的な視点で実行することで、単年度の節税を超えた持続的な効果を得られます。
ただし、資金繰りへの影響や税務調査でのリスクを避けるため、正確な知識に基づいた適切な処理が不可欠です。不明な点は税理士に相談し、自社の状況に最適化された節税戦略を構築しましょう。減価償却を味方につけて、企業の成長と税務効率の両立を実現してください。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。