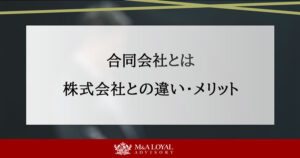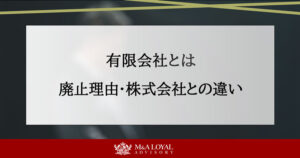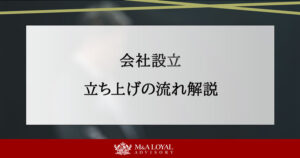株式会社とは?仕組みとメリット、設立費用や方法をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
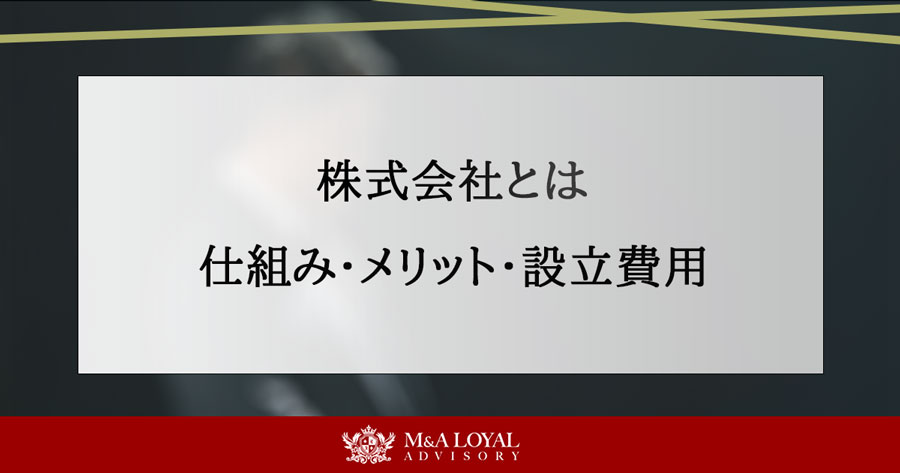
「株式会社とは何か?」と聞かれると、なんとなく知っていても、具体的な仕組みや特徴までは説明しづらいものです。個人事業主や合同会社との違いや株式会社設立のメリット・デメリットも気になるところですよね。本記事では、株式会社の基本的な仕組みや役割をはじめ、設立にかかる費用や方法、他の法人形態との違いまでをわかりやすく解説します。
目次
株式会社とは|定義と仕組みをわかりやすく解説
まず、株式会社の基本的な仕組みについて、わかりやすく解説します。
株式で資金調達をする
株式会社とは、株式を発行して多くの人や企業から資金を集め、集めた資金を事業運営に活用する会社形態です。株式は会社の「持分」を表す証券であり、株主は出資者として会社の一部を所有します。
株主は出資額に応じて議決権を持ち、配当という形で利益の一部の受け取りが可能です。株式の発行によって形成される資金は「資本金」として扱われ、会社の基盤を支える重要な要素の一つです。また、株式は売買が可能で、投資家は市場を通じて自由に取引を行える点も株式会社ならではの特徴といえます。
所有と経営の分離
株式会社は、「所有」と「経営」が明確に分かれている点が大きな特徴です。会社の所有者は株主であり、出資によって会社の一部を保有します。一方で、実際の経営は株主から選任された取締役が行い、日々の経営判断や業務執行を担います。このように、株主は経営の意思決定を直接行うのではなく、株主総会を通じて取締役を選任し、間接的に会社の運営に関わる仕組みです。
近年では、コーポレートガバナンス(企業が健全で公正な経営を行うための企業統治)の観点から、経営の中でも「監督」と「実行」を分ける体制を採用する企業が増えています。取締役が経営全体の監督や方針決定を担い、執行役員が実際の業務を実行するという仕組みです。これにより、経営の透明性や健全性を確保しつつ、会社運営の効率化が可能です。
株式の上場ができる
株式会社は、一定の条件を満たすことで、自社の株式を証券取引所に上場できます。上場とは、会社の株式を一般の投資家が市場で自由に売買できるようにすることです。上場により、株式を通じてより多くの投資家から資金を集めることが可能になり、企業の成長や事業拡大を支えられます。
上場には、東京証券取引所をはじめとする証券取引所が定める厳しい基準を満たす必要があり、財務状況の健全性やガバナンス体制、情報開示の透明性が重要です。また、上場企業は投資家の信頼を得るために、経営状況や業績を定期的に公表する義務があります。
株式の上場は資金調達の手段であると同時に、社会的な信用を示す制度です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



株式会社と他の法人形態との違い
日本の会社は、まず「株式会社」と「持分会社」に大別されます。
株式会社は株式を発行して資金を集める仕組みを持ち、出資者(株主)は出資額の範囲でのみ責任を負います。一方、持分会社は出資者が経営にも直接関わる形態であり、「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3種類があります。
合同会社
合同会社は、出資者全員が「社員」として経営にも参加できる会社形態です。
株式会社のように出資者と経営者が分かれておらず、出資者自らが意思決定や業務執行を行う点が特徴です。出資者は全員「有限責任社員」であり、会社が債務を負っても、出資した額を超える責任を負うことはありません。
さらに法人格を持つため、会社名義で契約や取引を行うことが可能です。また、合同会社は「定款自治」が強く、利益の分配方法や経営方針などを社員間の合意で柔軟に決められます。役員任期の制限や決算公告の義務がないなど、運営上の自由度が高い点も特徴です。
合名会社
合名会社は、出資者全員が経営に関わり、会社の債務に対して無限の責任を負う会社形態です。
出資者と経営者が同じ立場であり、社員それぞれが意思決定や業務執行、会社を代表する役割を担います。会社が負債を抱えた場合には、社員は自らの財産を使って返済しなければならない点が特徴です。
株式会社は「有限責任」で所有と経営が分離しているのに対し、合名会社は「無限責任」で所有と経営が一致する点が異なります。
合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社形態で、それぞれ1名以上の社員が必要です。
無限責任社員は会社の債務に対して全額の責任を負い、有限責任社員は出資した額の範囲内でのみ責任を負います。合同会社や合名会社と同じ「持分会社」に分類され、出資者が経営にも関わる点が特徴です。
株式会社の出資者は全員が有限責任であるのに対し、合資会社では無限責任社員が存在するため、経営上のリスクと責任の重さが異なります。
有限会社
有限会社は、かつて中小企業向けに設けられていた会社形態です。社員全員が出資額の範囲でのみ責任を負う「有限責任社員」で構成されます。有限会社は社員(出資者)数が50人以内に制限され、株券の発行ができず、決算公告の義務がない点が株式会社との違いです。取締役の任期もなく、より簡素な運営ができます。このように、有限会社は少人数で安定した経営を行うことを目的とした会社形態です。
2006年の会社法施行により有限会社法が廃止され、新たに設立することはできなくなりました。現在は、当時設立された会社が「特例有限会社」として存続しています。特例有限会社は会社法上、株式会社として扱われるため、必要な手続きを踏むことで株券を発行することが可能となります。
株式会社のメリット【他の法人形態と比較】
他の法人形態と比較した株式会社のメリットは、次のとおりです。
- 社会的信用度が高い
- 資金調達がしやすい
- 出資者が有限責任である
- 経営と所有の分離ができる
- 事業承継・出資の譲渡が容易
それぞれを詳しく解説します。
社会的信用度が高い
株式会社は、日本で最も広く採用されている会社形態であり、社会的な認知度と信頼性が高い点が特徴です。
法律や会計制度が厳密に整備されているため、企業活動の透明性が確保され、取引先や金融機関、行政機関などから安心して取引できる存在として評価されます。さらに、株式会社には決算公告などの情報開示義務があり、経営状況を社会に公開することで健全な経営姿勢を示せます。
こうした透明性と制度的な信頼性が、株式会社の社会的信用を支える大きな要因であり、合同会社など他の持分会社にはない強みといえます。
資金調達がしやすい
株式会社は、株式を発行して出資を募れる仕組みを持ち、多様な方法で資金を集められる点も特徴です。
株式を通じて複数の投資家や法人から出資を受けられるため、経営規模の拡大や新事業への投資にも柔軟に対応できます。対して、合同会社や合名会社などの持分会社では、出資者の範囲が限られており、大規模な資金調達には向いていません。
さらに、株式会社は将来的に株式を証券取引所に上場させることで、一般投資家からも広く資金を集められます。
出資者が有限責任である
株式会社では、出資者である株主は「有限責任」となり、出資した金額の範囲でのみ責任を負います。会社が債務を抱えた場合でも、株主が個人の財産を使って返済する義務はなく、損失は出資額の範囲に限定されます。これは、出資者が経営リスクを過度に負わずに済む仕組みであり、安心して投資できる環境を整えています。
一方、合名会社や合資会社のように無限責任社員が存在する会社形態では、会社の負債を個人資産で弁済しなければならない場合もあります。
そのため、出資者の責任範囲が明確に限定されている株式会社は、他の法人形態と比べて安全性が高く、多くの事業者や投資家に選ばれています。
経営と所有の分離ができる
株式会社は、前述したように「所有」と「経営」が分離している点が大きな特徴です。
出資者である株主は会社の所有者として資金を提供し、実際の経営は株主から選任された取締役が行います。この仕組みにより、経営の専門知識や経験を持つ人材を登用でき、効率的かつ客観的な経営判断が可能です。また、株主は経営の方針や取締役の選任・解任を株主総会で決定することで、経営を間接的に監督します。
対して、合同会社や合名会社などの持分会社では出資者自身が経営を担うため、所有と経営が一体化しています。株式会社は、役割を明確に分けることで組織運営の透明性と安定性を高められる点が、メリットといえます。
事業承継・出資の譲渡が容易
株式会社では、株式を売買することで会社の所有権を簡単に移転できる仕組みが整っている点もメリットの一つです。
株式は個人や法人の間で自由に譲渡できるため、経営者の引退や後継者への事業承継、出資者の交代といった場面でも手続きを円滑に進められます。これにより、経営の継続性を保ちながら、次の世代へスムーズに会社を引き継げます。
合同会社や合名会社などの持分会社では、出資者全員の同意が必要になるケースが多く、所有権の移転が複雑になりがちです。一方、株式会社では株式を通じた所有の移転が法的にも制度的にも明確であり、出資の流動性が高い点が大きな強みといえます。
株式会社のメリット【個人事業主と比較】
個人事業主と比較した株式会社のメリットは、次のとおりです。
- 節税できる可能性がある
- 自由に決算時期を決められる
- 社会保険に加入できる
- 人材採用に有利
それぞれを詳しく解説します。
節税できる可能性がある
法人は、個人事業主に比べて経費として認められる範囲が広く、税務上の自由度が高い点が特徴です。
例えば、経営者自身の役員報酬を損金(経費)として計上できる他、自宅を社宅として扱い、一定割合の家賃を経費に含めることも可能です。これにより、所得を会社と個人に分散させ、全体の税負担を抑えられます。
また、個人事業主の所得税が所得額に応じて最大45%まで上がる「累進課税」であるのに対し、法人税は一律の「比例課税制度」を採用しています。
中小法人の場合、所得800万円以下は15%、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます(資本金1億円超は一律23.2%)。さらに、資本金1,000万円未満の法人は、原則として設立後2期の間、消費税の納税が免除されます(特定期間の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下の場合)。
自由に決算時期を決められる
個人事業主は、所得税法により会計期間が毎年1月1日から12月31日までと定められており、決算月を自由に変更できません。
対して、株式会社は設立時に任意の月を会計年度の末月(決算月)として定められます。例えば、繁忙期を避けて決算業務の負担を軽減したり、資金繰りや取引先の決算期に合わせて会計を組み立てることが可能です。
また、業績の見通しに応じて節税効果を高めるための決算期設定も行えます。さらに、期末在庫や設備投資の計上タイミングを調整しやすく、経営計画と税務戦略を一致させる柔軟な運営ができる点も大きな利点です。
社会保険に加入できる
株式会社を設立すると、会社単位での社会保険加入が法律により義務付けられます。
具体的には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類で、代表取締役を含む役員・従業員全員が加入対象です。経営者自身も「被保険者」として扱われるため、国民健康保険・国民年金のみの個人事業主に比べて、保障の内容と範囲が大きく広がります。
例えば、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増える他、健康保険では出産手当金や傷病手当金などの給付を受けられます。さらに、労災保険によって業務中や通勤中の事故も補償対象となるため、安心して事業運営を続けられる点もメリットです。
人材採用に有利
株式会社として法人登記を行うと、社会的信用力が向上し、採用活動の信頼性が高まります。
求人広告や採用サイトでは、法人格の有無が求職者の安心感に直結するため、個人事業主よりも応募数・質ともに向上しやすい傾向があります。特に正社員志望者にとっては、雇用契約や福利厚生の整備などが明確な株式会社の方が信頼されやすく、優秀な人材を長期的に確保しやすい点が大きなメリットです。
また、法人化によって社会保険への加入や企業としてのブランディングも進むため、採用のみならず取引先や金融機関からの評価向上にも寄与します。
株式会社のデメリット【他の法人形態と比較】
他の法人形態と比較した株式会社のデメリットは、次のとおりです。
- 設立費用が高い
- 決算公告の義務がある
- 役員に任期がある
- 運営ルールが複雑で手続きが多い
- 内部統制・管理コストがかかる
それぞれを詳しく解説します。
設立費用が高い
株式会社の設立には、定款認証費用や登録免許税などの初期費用が必要です。
定款は会社の基本ルールを記載した書類で、株式会社では必ず公証役場で認証を受ける必要があります。令和6年12月1日施行の公証人手数料令改正により、資本金100万円未満で一定の条件(発起人が自然人3人以下・全株式を引き受ける・取締役会を置かない)を満たす場合、手数料は1万5,000円に軽減されます。該当しない場合は、資本金100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、それ以上は5万円です。
さらに、登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)で、電子定款を利用すれば印紙代4万円を節約可能です。これらを合わせると、株式会社の設立費用はおおむね20万円前後が相場です。
一方、合同会社は定款認証が不要で、登録免許税も最低6万円と少額のため、株式会社は設立費用が高い点がデメリットといえます。
決算公告の義務がある
株式会社は、毎事業年度の決算報告を行う義務があります。
取締役は貸借対照表や損益計算書などの計算書類を作成し、株主総会で承認を受けた上で、公告(公開)しなければなりません。公告方法は、官報掲載の他、自社のウェブサイトで公開することも認められています。
一方、合同会社や合名会社などの持分会社にはこの公告義務がなく、株式会社は情報公開に伴う事務負担や費用が発生する点もデメリットの一つといえます。
役員に任期がある
株式会社では、会社法により取締役・監査役などの役員に任期が定められています。これは、ガバナンスの透明性を確保するためです。
取締役の任期は原則として2年、監査役は4年ですが、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、定款により最長10年まで延長が可能です。任期満了後は再任または交代の登記が必要で、登記を怠ると過料(罰金)が科される場合もあります。
対して、合同会社などの持分会社では役員の任期に制限がなく、変更登記の義務もありません。
運営ルールが複雑で手続きが多い
株式会社は、会社法に基づき株主総会や取締役会などの機関設計が義務付けられているため、運営ルールが複雑になりがちです。
株主総会の開催や議事録の作成、取締役会の開催記録など、定期的な手続きを怠れません。
意思決定や変更に関して書面手続きや登記を伴うため、少人数経営やスピード感を重視する事業では、合同会社などと比べて柔軟性に欠ける側面がデメリットです。
内部統制・管理コストがかかる
株式会社では、内部統制や書類管理に関する法的義務が多く、管理コストが高い点がデメリットとして挙げられます。
会社法により、会計帳簿や株主名簿、議事録などの作成・保存が義務付けられており、適切に管理しなければなりません。これらは税務調査や登記、監査などで提出を求められるため、専門家(税理士・司法書士・会計士など)への依頼費用が発生するケースが多いです。
また、上場を目指す場合や取締役会設置会社では、内部監査やコンプライアンス対応などガバナンス維持のための追加コストも必要です。こうした維持費用は、合同会社のような持分会社に比べて大きく、特に小規模経営では負担になることがあります。
株式会社のデメリット【個人事業主と比較】
個人事業主と比較した株式会社のデメリットは、次のとおりです。
- 赤字でも税金を支払う必要がある
- 経営上の自由度が低く、意思決定に時間がかかる
- 利益処分や資金の自由利用に制約がある
それぞれを詳しく解説します。
赤字でも税金を支払う必要がある
株式会社は、赤字であっても法人住民税の均等割を支払う必要があります。
法人住民税には「均等割」と「法人税割」があり、均等割は会社の所得に関係なく課される税金で、資本金や従業員数に応じて金額が決まり、最低でも年7万円(都道府県・市区町村の合計)の負担が発生します。
一方、個人事業主は所得がなければ所得税が課されないため、赤字の年は税負担を避けられます。法人化すると毎年の固定費として税負担が生じる点はデメリットの一つです。
経営上の自由度が低く、意思決定に時間がかかる
株式会社は、株主総会・取締役会などの機関設計が会社法で義務付けられており、重要な経営判断を迅速に下せないことがあります。
例えば、取締役会設置会社では、取締役会の決議を経なければ経営方針や大型投資などを実行できません。また、すべての株式会社は株主総会の定期開催および必要に応じた臨時開催が必要で、経営に関する重要な手続きにおいて意見が対立した場合には、意思決定を遅らせる要因にもなります。
一方、個人事業主は自らが経営の最終決定者であり、判断を即座に実行できる点で経営の自由度とスピードに優れるといえます。
利益処分や資金の自由利用に制約がある
個人事業主は、事業で得た利益をそのまま生活費や再投資に充てられますが、株式会社では会社の資金は法人の所有物であり、経営者個人が自由に使うことはできません。
会社の利益を経営者が受け取るには、役員報酬・賞与・配当金といった明確な手続きを経る必要があります。これらの支払いは、税務上の損金算入要件や取締役会決議の有無など、厳格なルールの下で処理しなければなりません。
そのため、個人事業主に比べると、資金の流用や私的利用が制限され、資金繰りや個人消費の自由度が下がる点もデメリットといえるでしょう。
株式会社の役員
会社法に記載されている株式会社の役員は、次のとおりです。
- 取締役
- 監査役
- 会計参与
それぞれを詳しく解説します。
取締役
取締役は、株式会社の経営の中核を担う存在であり、会社の業務方針を決定し、その遂行を監督する役割を持ちます。会社を設立するには、最低1名の取締役を置くことが法律で義務付けられています。
取締役が3名以上(さらに監査役または会計参与1名以上)いる場合は「取締役会」を設置でき、重要な経営判断や代表取締役の選定などを行います。代表取締役は会社の意思を外部に示す「会社の代表者」として契約締結などを行い、法人を法的に代表する立場です。
また、取締役は株主に対して経営責任を負っており、善管注意義務や忠実義務が課されています。任期は原則2年ですが、非公開会社では最長10年まで延長できます。
監査役
監査役は、会社の経営が適正に行われているかを監督する立場であり、取締役の業務執行をチェックします。
主な職務は、取締役会の議事を監視したり、会計帳簿を閲覧したりして、会社の不正や不適切な経営を防ぐことです。監査役は会社の番人とも呼ばれ、取締役に対して業務改善を求めたり、必要に応じて株主総会に報告する権限を持ちます。
上場企業や大会社では監査役または監査等委員会の設置が義務付けられており、企業統治(コーポレートガバナンス)の重要な柱を担っています。任期は原則4年で、独立性を保つために再任制限が設けられていません。
会計参与
会計参与は、取締役と共同で計算書類(決算書など)を作成する役職です。
税理士または公認会計士しか就任できず、専門的な会計知識を生かして、企業の財務内容の正確な開示を目的としています。会計参与が設置された会社では、計算書類に会計参与の署名が必要となり、外部監査のような信頼性向上効果があります。特に中小企業においては、税務や会計の透明性を高め、金融機関や投資家からの信用を得やすくする手段として活用されています。
任期は取締役と同様に2年以内で、会計参与の設置は任意ですが、信頼性を重視する企業では導入が進む傾向にあります。
株式会社の設立方法と一連の流れ
株式会社の設立は以下の流れで進みます。
- 会社設立に必要な基礎情報を決定する
- 会社用の印鑑(実印)を作成する
- 定款を作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 登記申請書類を用意し登記申請する
それぞれを分かりやすく解説します。
ステップ1.会社設立に必要な基礎情報を決定する
株式会社設立の第一歩は、会社の基本情報を決めることです。
会社形態や商号、事業目的、本店所在地、資本金、発行可能な株式総数、事業年度、機関設計など定款に記載する事項を定めます。商号は使用できる文字や符号に制限があり、事業目的は将来の展開を見越して明確に設定します。
資本金は1円からでも設立可能ですが、信用や運転資金を考慮すると、初期費用と3カ月分の資金の確保が望ましいです。また、会計年度や決算月を繁忙期と重ならないよう設定し、役員・株主構成を明確にしておくことが、後の運営トラブル防止にもつながります。
ステップ2.会社用の印鑑(実印)を作成する
2021年の法改正により、商業登記での押印義務は廃止されましたが、実際の事業運営では契約書や銀行取引などで印鑑が必要になる場面が多くあります。
法務局に登録する実印(代表者印)は、1辺1cm以上・3cm以内の正方形に収まるサイズでなければなりません。印鑑は専門業者に依頼して作成することが一般的で、価格は5,000円〜5万円ほど、完成まで約1週間かかります。
設立登記の準備段階から早めに手配しておくと安心です。また、角印や銀行印も同時に作成しておくと、開業後の手続きをスムーズに進められるでしょう。
ステップ3.定款を作成する
定款は「絶対的記載事項」が欠けると無効となるため、内容を慎重に確認する必要があります。
定款は、原本・法務局提出用・会社保管用の3部を作成し、ホチキス止め後に製本テープでとじて契印を押します。紙定款の他に電子定款で作成可能で、電子署名を付けてオンライン申請すれば、印紙税4万円を節約できます。
作成後は公証役場で認証を受ける必要があり、事前に予約して内容確認を依頼しておくとスムーズです。
ステップ4.公証役場で定款の認証を受ける
株式会社の定款は、公証役場で認証を受けなければ効力を持ちません。
認証手続きは予約制のため、本店所在地を管轄する公証役場に事前連絡を入れ、訪問日時を決めておきます。持参する書類は、定款3部、発起人全員の印鑑証明書(各1通)、実印、認証手数料1万5,000〜5万円、定款謄本代、収入印紙4万円(電子定款は不要)などです。
代理人が申請する場合は委任状も必要です。電子定款の場合は「登記・供託オンライン申請システム」で提出できます。事前にFAXで内容確認を依頼しておくと、当日の手続きが円滑です。
ステップ5.資本金の払い込みを行う
定款認証後、発起人は資本金を払い込みます。
登記前はまだ法人名義の口座を開設できないため、発起人個人の口座へ振り込みを行うことが一般的です。払い込み後は、通帳の表紙・表紙裏(銀行名・支店名・印影が確認できる部分)および入金明細ページをコピーし、登記時の証明書類として提出します。
資本金は会社の信用や運転資金の基礎となるため、初期費用と3~6か月分の運転資金を目安に設定すると良いでしょう。払い込みが完了していないと登記申請ができないため、証憑(しょうひょう)の保管と確認を怠らないことが重要です。
ステップ6.登記申請書類を用意し登記申請する
全ての準備が整ったら、法務局に登記申請を行います。
必要書類は、登記申請と、定款、発起人決定書、就任承諾書類、印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書、「登記すべき事項」を記載した書面またはCD-Rなどです。
登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)で、収入印紙で納付します。登記完了には10日程かかります。登記完了後は法人番号が付与され、正式に会社が成立します。税務署や年金機構への届出、社会保険・労働保険の加入、法人口座開設など、設立後の手続きも速やかに行いましょう。
株式会社設立を成功させるポイント
株式会社設立を成功させるポイントは、次のとおりです。
- 設立目的と事業計画を明確にする
- 信頼できる専門家に相談する
- 設立後の運営体制を整える
- 信用構築を意識する
それぞれを詳しく解説します。
設立目的と事業計画を明確にする
株式会社を設立する前に、「なぜ株式会社という形を選ぶのか」「どんな事業をどのように展開するのか」の明確化が成功の第一歩です。
例えば、将来的に外部投資を受けたい、従業員を雇って規模を拡大したいといった目的を整理すると、資本金額や株主構成、会計年度の設定方針が自然と定まります。また、事業内容・ターゲット・収益計画を具体的に書き出しておくと、定款の作成や融資申請の際にも役立ちます。
曖昧なまま設立を進めてしまうと、後から組織変更や定款修正が必要になることもあるため、設立前に事業の方向性をしっかり固めておきましょう。
信頼できる専門家に相談する
株式会社の設立には、法務・税務・社会保険など複数の分野にわたる専門知識が求められます。
登記申請書の不備や税務届出の遅れは、最悪の場合、登記の差し戻しや税務署からの指摘につながることもあります。そのため、司法書士・税理士・行政書士など、各分野の専門家に相談しながら進めると安心です。
特に資本金の設定や役員報酬の決め方は、税金や資金繰りに直結する重要なポイントです。設立前に税理士へ相談しておけば、節税面や将来の資金計画において有利に進められます。
設立後の運営体制を整える
株式会社設立後、会社を安定的に運営していくためには、会計・税務・労務といった内部管理体制の整備が大切です。
例えば、経理処理を効率化するためにクラウド会計ソフトを導入したり、社会保険や給与計算を専門家に委託する方法もあります。また、毎月の収支を可視化することで、資金繰りの改善や経営判断のスピード向上にもつながります。
特に初年度は、税務署への届出や社会保険加入など多くの手続きが発生するため、スケジュール管理を徹底し、抜け漏れのない体制を築くことが重要です。
信用構築を意識する
株式会社設立後、会社としての信頼を得る努力は欠かせません。
まずは法人名義の銀行口座を開設し、資金の流れを明確に管理しましょう。法人口座は、取引先や金融機関が信用判断を行う際の重要な基準です。入金用口座と出金用口座を分けると管理しやすく、融資を受ける際にも役に立ちます。
また、会社の公式ホームページや名刺、メールアドレスなどの整備も大切です。統一された情報として発信されることで、企業としての透明性と信頼性が高まります。
さらに、登記簿謄本や会社概要書を提示できる体制を整えておくと、契約や融資の際にもスムーズに対応できます。会社設立後は、信頼を「形」で示すことが継続的な成長への第一歩です。
株式会社に関するQ&A
最後に、株式会社に関するよくある質問とその回答を紹介します。
株主総会と取締役会の違いは何か
株主総会と取締役会は、いずれも株式会社の意思決定に関わる重要な機関ですが、役割が異なります。
株主総会は、株主が参加して会社の基本方針を決める「最高意思決定機関」であり、取締役の選任や解任、定款変更、利益配当など、会社の根幹に関わる事項を議決します。
一方、取締役会は株主総会で選ばれた取締役によって構成され、日々の経営方針や重要な業務執行を決定する「業務執行の決定・監督機関」です。代表取締役の選定や重要取引の承認、内部統制の整備など、実務に直結する意思決定を担います。
簡単にいえば、株主総会は「会社の方向を決める場」、取締役会は「その方針を実行する場」といえます。
株式会社の設立日はいつになるか
株式会社の設立日は、法務局に設立登記の申請をした日(申請書を法務局が受理した日)です。登記手続きが完了した日や登記申請書を提出した翌日が設立日になるわけではありません。
土日祝日は法務局が閉まっているため、会社の設立日にできない点に注意が必要です。
登記申請日は、会社の誕生日として登記簿や定款、税務署への届出書にも記載される大切な日です。設立日を「大安」「一粒万倍日」など縁起の良い日に合わせたい場合は、事前に法務局の営業日を確認し、休日や年末年始を避けて逆算する必要があります。
株式譲渡制限とは何か
株式譲渡制限とは、株式を第三者に自由に譲渡できないようにする制度のことです。
株式譲渡制限によって、経営権の維持や外部への支配権流出を防げます。特に中小企業や家族経営の会社では、経営の安定性を保つために「株式の譲渡には会社の承認が必要」とする定款を定めることが一般的です。
譲渡制限のない会社(公開会社)は、株主が自由に株を売買できる代わりに、経営が不安定になりやすいという特徴があります。
株式会社の役員報酬はどうように決められるか
役員報酬は「定款または株主総会の決議」で定める必要があります。金額や支給方法を自由に決めることはできず、取締役会で決定する場合も、株主総会で決議された範囲内に限られます。また、税務上は損金(経費)として認められる条件があり、「定期同額給与」や「事前確定届出給与」などのルールに従うことが重要です。
不適切な設定は経費として認められず、法人税負担が増える可能性もあります。
非上場企業でも株式を発行できるのか
非上場企業でも株式を発行できます。株式会社は、設立時または設立後の増資などで株式の発行が可能であり、「上場しているかどうか」に関係なく株式制度を利用できます。
上場企業は証券取引所を通じて不特定多数の投資家に株式を公開していますが、非上場企業(未上場会社)は株式を公開せず、特定の株主だけで所有する形をとります。多くの中小企業や家族経営の会社はこの「非上場株式会社」に該当します。
ただし、非上場企業が自由に株式を譲渡できるようにしてしまうと、意図しない第三者に経営権が移るリスクがあります。そのため、ほとんどの非上場企業は「株式譲渡制限」を定款に定め、株主総会や取締役会の承認を経なければ株式を譲渡できない仕組みにしています。
この制度により、非上場でも株式による出資・持分の管理が可能でありながら、経営の安定性も確保できます。
株式会社の設立にはどのくらいの期間がかかるか
会社設立にかかる期間は、株式会社でおおよそ3週間、合同会社で約2週間が一般的です。株式会社の場合は、合同会社と異なり定款の認証手続きが必要なため、その分だけ設立完了までに約1週間ほど多く時間を要します。
従って、できるだけ早く事業を開始したい場合は、手続きの簡略化が可能な合同会社の設立を検討することも一案です。
株式会社の設立に年齢制限はあるか
会社法自体には、会社を設立できる年齢について明確な制限は設けられていません。しかし、実際の手続きでは印鑑証明書の提出が求められるため、印鑑登録ができない15歳未満の人は手続きを進められません。従って、実務上は会社を設立できるのは15歳以上と考えることが一般的です。
なお、15歳以上であっても未成年の場合は、法定代理人(多くは親権者)の同意が必要です。その際は、通常の設立書類に加えて、親子関係を示す戸籍謄本や、親権者による同意書を提出する必要があります。これらの書類を整えることで、未成年でも正式に会社設立手続きを進められます。
まとめ
株式会社は、ビジネスを展開する上で多くのメリットを提供する法人形態です。資金調達のしやすさや信頼性の向上、責任の有限化などがその主なメリットといえます。しかし、設立には一定の費用と手続きが必要であり、運営には法的な義務も伴います。この記事で紹介した情報をもとに、他の法人形態と比較し、株式会社の設立が最適かどうかを判断する一助となれば幸いです。
なお、M&Aや経営課題に関するお悩みがありましたら、M&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。経験豊富なアドバイザーが貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。