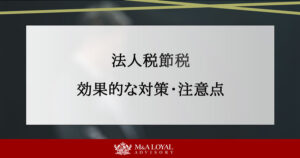法人税確定申告書とは?作成方法や必要書類、提出方法を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
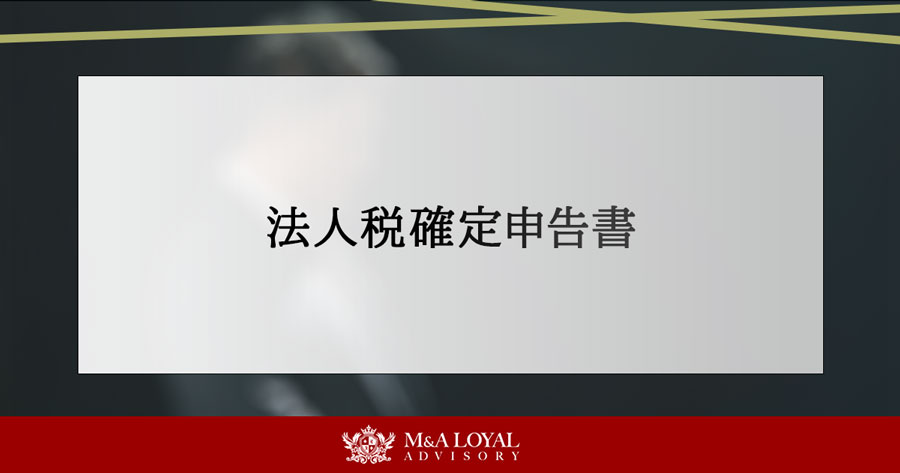
法人税確定申告書は、法人が一年間の事業活動で得た所得に対する法人税額を税務署に申告するための重要な書類です。株式会社をはじめとする法人は、事業年度終了から2か月以内にこの法人税確定申告書を作成・提出し、適正な納税を行わなければなりません。しかし、法人税申告書は別表一(申告書本体)から別表十九まで、19種類の書類で構成される複雑な仕組みとなっており、初めて作成する経営者の方にとっては難しく感じられることも多いでしょう。 この記事では、法人税確定申告書の基本的な仕組みから具体的な作成方法、必要書類の準備、提出方法まで、中小企業の経営者にも分かりやすく解説します。
目次
法人税確定申告書とは?基本的な仕組みと概要
法人税確定申告書とは、法人が一事業年度の間に得た所得金額を基に法人税額を計算し、税務署に申告・納税するための書類一式です。個人の確定申告とは異なり、法人の場合は事業年度の終了日から2か月以内に必ず申告を行う必要があります。
法人税は法人が得た利益に対して課税される国税であり、その税率は法人の規模や種類によって異なります。中小企業の場合、年800万円以下の所得については15%、800万円を超える部分については23.2%の税率が適用されることが一般的です。一方、大企業については所得の全額に23.2%の税率が適用されます。
法人税確定申告書の構成要素
法人税確定申告書は、メインとなる申告書本体(別表一)と、所得金額の計算過程や各種控除額を詳細に記載する付属書類(別表二から十九)で構成されています。これらの書類は相互に関連しており、一つの書類で計算した金額が他の書類にも反映される仕組みとなっています。
特に重要なのは別表一(法人税確定申告書本体)、別表四(所得金額の計算に関する明細書)です。これらの書類では、会計上の利益と税務上の所得の違いを調整し、最終的な法人税額を算出します。
申告書の作成にあたっては、決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)を基礎として、税務上の調整を加えていく作業が中心となります。このため、正確な決算書類の準備が申告書作成の前提条件となります。
青色申告と白色申告の違い
法人税の申告方法には青色申告と白色申告の2種類があります。 青色申告は税務署に「青色申告承認申請書」を事前に提出し、承認を受けた法人が利用できる申告方法です。 青色申告を選択した場合、欠損金の繰越控除などの税務上の特典を受けることができます 。
青色申告法人の場合、翌期以降に欠損金繰越が可能となり、将来の黒字と相殺することで税負担を軽減できます。
ただし、青色申告を行うためには、正規の簿記の原則に従った帳簿書類の作成と保存が義務付けられています。これには複式簿記による記帳や、会計帳簿・決算書類の保存などが含まれます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



法人税確定申告書に必要な書類と添付資料
法人税の確定申告では、申告書本体に加えて多くの添付書類の準備が必要となります。これらの書類は申告内容の根拠を示すものであり、税務調査の際にも重要な資料となります。数十種類にも及ぶ書類を準備する必要があります 。
法人税確定申告書の作成に必要な決算書類
法人が提出しなければならない決算書類には、一般的に貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書があります。これらの書類は、株式会社や有限会社などの法人が法人税申告書の基礎となる重要な資料であり、また株主や投資家、債権者などの利害関係者に対する情報提供の役割も果たします。
貸借対照表は決算日時点での法人の財政状態を示す書類で、資産、負債、純資産の構成を明らかにします。損益計算書は一事業年度の経営成績を示し、収益と費用を対比させて当期純利益を算出します。株主資本等変動計算書は、株主資本の各項目の当期における変動額を詳細に記載した書類です。
これらの書類は会計ソフトを適切に活用することで簡単にそして正確に作成できます。 多くの会計ソフトでは、日々の取引データを入力することで自動的に決算書類が作成される機能が搭載されています。
勘定科目内訳明細書の作成
勘定科目内訳明細書は、貸借対照表の主要な勘定科目について、その内訳を詳細に記載した書類です。現金預金、売掛金、買掛金、借入金などの主要科目について、取引先別や内容別の明細を作成します。
この書類は税務署が申告内容を審査する際の重要な資料となります。特に売掛金については取引先の会社名と金額を、借入金については金融機関名と残高を正確に記載する必要があります。勘定科目内訳明細書の記載漏れや誤記は税務調査の際に問題となる可能性があるため、慎重に作成することが重要です。
| 勘定科目 | 記載すべき内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金預金 | 金融機関名・口座番号・残高 | 通帳残高と一致させる |
| 売掛金 | 取引先名・取引内容・金額 | 回収予定日も記載 |
| 買掛金 | 仕入先名・取引内容・金額 | 支払予定日も記載 |
| 借入金 | 金融機関名・借入日・残高・利率 | 返済予定表と照合 |
法人事業概況説明書の重要性
法人事業概況説明書は、法人の事業内容や経営状況を税務署に報告するための書類です。この書類には、主要な事業内容、従業員数、売上高の月別推移、主要取引先などを記載します。
法人事業概況説明書は税務署が業務状況を把握する為に、確定申告の際に添付を義務付けており、記載内容の正確性が求められます。特に売上高の季節変動や特殊事情がある場合は、その理由を詳しく説明する必要があります。
この書類の作成にあたっては、月次試算表や売上管理資料を参考にして、正確な数値を記載することが重要です。また、前年度からの大きな変動がある場合は、その理由についても併せて記載することが推奨されます。
法人税確定申告書の具体的な作成方法(書き方)と手順
法人税確定申告書の作成は、まず会計上のルールに則って決算を確定することから始まり、次に会計上の利益を税務上の利益に適応させるための「税務調整」年間の法人所得を計算し、申告・納税するまでの一連の作業です。この作業を適切に行うためには、会計上の利益と税務上の利益が異なる点に留意し、それぞれの調整を行うための会計と税務の知識に加えて、別表1から19までで構成される法人税申告書の各別表ごとに書く内容や存在目的を正しく理解することが必要です。特に、別表の判定を誤ると追加で法人税が課税される可能性もあるため、正確な理解が重要です。
法人税確定申告書作成の手順は概ね決まっており、まず別表四で所得金額を計算し、その結果を別表一に転記して法人税額を算出するという流れになります。各段階での計算ミスが最終的な税額に影響するため、慎重な作業が求められます。
別表四による所得金額の計算
別表四(所得金額の計算に関する明細書)は、会計上の当期純利益を税務上の所得金額に調整するための書類です。この調整作業を「税務調整」と呼び、法人税申告書作成の中心となる作業です。
税務調整では、会計上は費用として計上されているが税務上は損金に算入されない項目(損金不算入項目)と、会計上は収益として計上されていないが税務上は益金に算入される項目(益金算入項目)を調整します。代表的な損金不算入項目には、交際費の限度超過額、減価償却超過額、役員賞与などがあります。
中小企業の場合、年間800万円までの交際費は損金算入が認められているため、この限度額を超える部分のみが損金不算入となります。また、減価償却費についても、法定耐用年数に基づく償却限度額を超える部分は損金に算入できません。
別表一での法人税額算出
別表一は法人税確定申告書の一部で、法人の基本情報や税額計算の概要を示します。別表四で計算した所得金額を基に法人税額を算出する際、所得金額に法人税率を乗じて算出した法人税額から、源泉所得税額や予定納税額などを差し引いて最終的な納付税額または還付税額を算出します。
法人税額の計算では、所得金額が800万円以下の部分については15%、800万円を超える部分については23.2%の税率を適用します(中小企業の場合)。
- 所得800万円以下の部分:15%(中小企業の軽減税率)
- 所得800万円超の部分:23.2%(標準税率)
- 大企業:所得全額に23.2%
- 協同組合等:所得全額に15%または19%(具体的な条件により異なる)
なお、法人税率は法改正により変更されることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。
その他の別表の記載方法
別表五(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)では、法人の利益積立金額の変動を管理します。この別表は繰越欠損金の管理や配当可能額の計算にも影響するため、正確な記載が重要です。
別表六(所得税額の控除に関する明細書)では、配当金や預金利息などから源泉徴収された所得税額を整理し、法人税額から控除する金額を計算します。源泉所得税の控除を適切に行うことで、過大な税負担を避けることができます。
別表七(欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書)では、過去の事業年度で発生した欠損金を当期の所得から控除する計算を行います。青色申告法人の場合、最大10年間の欠損金繰越が可能であり、この制度を活用することで税負担を大幅に軽減できる場合があります。
法人税確定申告書の提出方法と提出期限
法人税確定申告書の提出は、原則として事業年度終了の日から2か月以内に行わなければなりません。この提出期限は法律で厳格に定められており、期限を過ぎた場合は無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。提出方法には複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
提出方法の選択にあたっては、書類の量、緊急性、利便性などを総合的に考慮することが重要です。また、提出後の控えの管理についても事前に検討しておく必要があります。
税務署窓口での法人税確定申告書の直接提出
税務署の窓口に直接申告書を持参する方法は、最も確実な提出方法の一つです。 窓口では書類の受付印を押印してもらえるため、提出の事実を明確に証明できます 。
ただし、税務署の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっており、土日祝日は閉庁しています。 また、確定申告期限が近づくと窓口が混雑し、待ち時間が長くなる可能性があります。提出期限最終日は特に混雑するため、可能な限り余裕を持って提出することが推奨されます。
郵送による法人税確定申告書の提出方法
郵送による提出は、税務署に出向く時間を節約できる便利な方法です。
ただし、2025年1月からは申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されています。提出の事実や提出年月日の確認方法については、国税庁の案内をご確認ください。
郵送による提出の際は、以下の点に注意が必要です。
- 提出期限日の消印有効のため、余裕を持った投函
- 書留等の記録が残る郵送方法の利用
- 返送用封筒と切手の同封
電子申告(e-Tax)システムによる法人税確定申告書の提出方法
電子申告(e-Tax)は、インターネットを通じて申告書を提出するシステムです。24時間365日(メンテナンス時間を除く)利用可能であり、提出期限ギリギリでも確実に提出することができます。
e-Taxを利用するためには、事前に「開始届出書」の提出と利用者識別番号の取得が必要です 。これらの準備には時間がかかるため、初回利用時は余裕を持って準備を進めることが重要です。
e-Taxを利用した場合、添付書類の一部について提出を省略できる場合があり、事務負担の軽減につながります。 ただし、省略された書類についても法定保存期間中は適切に保管しておく必要があります。
提出期限の延長制度
やむを得ない理由により提出期限内に申告書を提出できない場合、一定の要件を満たすことで提出期限の延長が認められる場合があります。延長事由には、災害その他やむを得ない理由、会計監査人の監査を受ける必要がある場合などがあります。
延長を申請する場合は、原則として当初の提出期限までに「申告期限延長申請書」を税務署に提出する必要があります。延長が認められた場合でも、延長期間中は利子税が課される点に注意が必要です。
法人税確定申告書の修正申告手続きと納付方法について
法人税確定申告書を提出した後に誤りが発見された場合や、税務署から指摘を受けた場合は、修正申告手続きを行う必要があります。修正申告には期限後申告、修正申告があり、それぞれ適用される場面や手続きが異なります。適切な修正申告手続きを行うことで、追加の税負担や加算税の発生を最小限に抑えることが可能です。
また、法人税の納付には複数の方法があり、それぞれに特徴があります。納付方法の選択は資金繰りや事務処理の効率性を考慮して決定することが重要です。
修正申告の種類と手続き
期限後申告は、法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合に行う申告です。この場合、無申告加算税(原則として納付税額の15%)が課される可能性があります。ただし、期限後申告であっても、税務調査通知前の自主的な申告の場合は加算税の軽減措置があります。
修正申告は、既に提出した申告書の税額が過少であった場合に行う申告です。修正申告を行う場合、追加税額とともに過少申告加算税(原則として追加税額の10%)が課される場合があります。ただし、税務調査通知前の自主的な修正申告の場合は過少申告加算税は課されないため、誤りに気づいた段階で速やかに修正申告を行うことが重要です。
法人税の納付方法
法人税の納付方法には、金融機関窓口での納付、コンビニエンスストアでの納付、インターネットバンキングを利用した電子納税、クレジットカード納付などがあります。それぞれの方法には納付可能な金額や手数料に違いがあります。
金融機関窓口での納付は最も一般的な方法で、納付書を使用して現金または口座振替で納付します。領収書も発行されるため、納付の証明も確実に残ります。
| 納付方法 | 利用可能金額 | 手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 金融機関窓口 | 制限なし | 無料 | 最も確実で一般的 |
| コンビニ納付 | 30万円以下 | 無料 | 24時間利用可能 |
| 電子納税 | 制限なし | 無料 | インターネット経由 |
| クレジットカード | 制限なし | 決済手数料要 | ポイント還元あり |
延納制度の活用
法人税について、期限内に一時に納付することが困難な場合には、納税者からの申請に基づき税務署長の許可を受けることで、「納税の猶予制度」を利用して税額を分割して納付することができます。
法人税の納付において、期限内に一時に納付することが困難な場合には、「納税の猶予制度」を利用することで、税務署長の許可を受けて、原則として1年以内の期間に限り、税額を分割して納付することができます 。
中小企業が注意すべき法人税確定申告のポイント
中小企業の法人税確定申告では、大企業とは異なる特有の注意点や優遇措置があります。これらを正しく理解し活用することで、適正な税務処理を行いながら税負担を適切に管理することが可能です。特に、中小企業向けの軽減措置(例えば、所得800万円以下の部分に対する法人税軽減税率)や特例措置(例えば、特定の投資減税や雇用促進税制など)は、会社の財務に大きな影響を与える可能性があります。
また、中小企業では税務専門家のサポートを受けながら申告業務を進めることが多いため、専門家との連携方法や外部委託時の留意点(例えば、委託先の選定基準やコミュニケーションの取り方)についても理解しておくことが重要です。
中小企業向けの税制優遇措置
中小企業には様々な税制上の優遇措置が設けられています。最も基本的なものが中小企業の軽減税率であり、所得金額800万円以下の部分について15%の軽減税率が適用されます。この措置により、中小企業の税負担は大幅に軽減されています。
交際費の損金算入についても中小企業には優遇措置があります。中小企業の場合、年間800万円までの交際費について全額損金算入が認められており、営業活動に必要な接待交際費を有効活用することができます。一方、大企業の場合は接待飲食費の50%のみが損金算入となるため、中小企業にとって大きなメリットとなっています。
中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制などの設備投資減税制度を活用することで、設備投資に係る税負担を大幅に軽減することも可能です。これらの制度では、特別償却または税額控除を選択適用できるため、会社の状況に応じて最適な選択を行うことが重要です。
同族会社の特別規定
中小企業の多くは同族会社に該当するため、同族会社特有の規定についても理解しておく必要があります。同族会社とは、以下のいずれかに該当するものです。
- 3人以下の株主(同族関係者を含む)のグループが、発行済み株式の総数または出資の総額の50%超を保有している。
- 3人以下の株主(同族関係者を含む)のグループが、議決権の総数の50%超を保有している。
- 3人以下の社員(同族関係者を含む)のグループが、社員総数の半数超を占めている。
同族会社の場合、役員給与の損金算入について特別な規定が適用されます。具体的には、同族会社の使用人のうち、一定の株式を所有し経営に従事している者は「みなし役員」とみなされ、また、使用人として職務に従事する役員であっても、同族会社の株式を一定割合以上保有している場合は税務上「使用人兼役員」になれません。これらの者へ支払われる給与や賞与は役員と同様の取扱いとなり、損金に算入できない規定となっています。
また、同族会社の留保金課税についても理解が必要です。一定の要件を満たす同族会社では、留保所得に対して追加課税が行われる場合があります。
法人住民税申告書類との関連
法人税の確定申告と併せて、 法人住民税と法人事業税の申告手続きも必要となります。これらの地方税は法人税の申告内容を基礎として計算されるため、法人税申告書の内容が正確であることが前提となります。
法人住民税は道府県民税と市町村民税から構成され、それぞれに均等割と法人税割があります。均等割は赤字の場合でも課税されるため、資金繰りに注意が必要です。法人事業税は各都道府県に申告・納付しますが、所得割と付加価値割・資本割から構成される外形標準課税の対象となる場合があります。
- 法人住民税:都道府県民税+市町村民税(均等割+法人税割)
- 法人事業税:都道府県税(所得割が基本、一定規模以上は外形標準課税)
- 地方法人特別税:法人事業税に付加して課税(令和元年10月以降は法人事業税に統合)
- 申告期限:いずれも法人税と同じ(事業年度終了から2か月以内)
これらの地方税についても、法人税と同様に電子申告システムを利用することが可能です。eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用することで、複数の地方自治体への申告を一括して行うことができ、事務効率の向上が期待できます。
まとめ
法人税確定申告書は、法人が事業年度の所得に対する法人税を申告するための重要な書類であり、決算日から2か月以内の提出が法的に義務付けられています。申告書は別表一から十九まで多岐にわたる複雑な構成となっており、会計上の利益を税務上の所得に調整する税務調整作業が中核となります。
申告に必要な書類は決算書類、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書など多数あり、それぞれが相互に関連しているため正確性が求められます。提出方法には税務署窓口、郵送、電子申告があり、それぞれの特徴を理解して適切な方法を選択することが重要です。
中小企業には軽減税率や交際費の損金算入などの優遇措置があり、これらを適切に活用することで税負担の軽減が可能です。法人売却やM&Aを検討される際は、適正な税務申告の履歴が企業価値評価において重要な要素となります。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、税務面を含めた総合的な企業価値向上のサポートを提供しております。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。