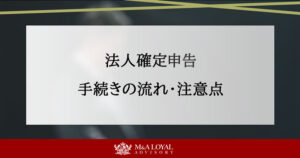法人税の計算方法は?税率とざっくりわかるシミュレーション
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
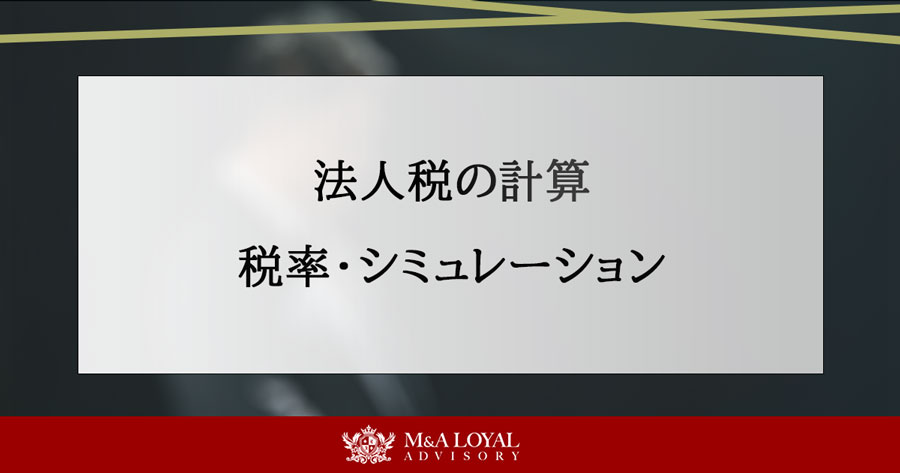
法人税の計算方法を正しく理解することは、企業経営にとって重要な要素です。特に中小企業の経営者の方にとって、法人税の仕組みや税率、実際の計算方法を把握しておくことで、適切な税務申告や節税対策、さらには資金繰りの予測が可能になります。 本記事では、法人税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、さらにはシミュレーションを通じて、分かりやすく解説していきます。税理士に相談する前に基礎知識を身につけたい方や、決算に向けて法人税の概算を知りたい方にとって役立つ内容となっています。
目次
法人税とは何か?基本的な仕組みを理解しよう
法人税とは、法人が事業活動によって得た利益に対して課税される国税です。個人の所得税に相当する法人向けの税金として位置づけられており、株式会社や有限会社、医療法人、協同組合などの営利法人が対象となります。
法人税の課税対象となる法人の種類
法人税は、原則として営利を目的とするすべての法人に課税されます。具体的には、株式会社、銀行、信用金庫、医療法人、協同組合などが含まれます。一方で、NPO法人や社団法人などの公益法人は原則として非課税ですが、営利事業を行った場合にはその部分について課税対象となることがあります。
また、外国法人についても、日本国内で事業を行っている場合には法人税の課税対象となります。この場合、国内源泉所得に対してのみ課税されるのが一般的です。
課税所得の基本的な考え方
法人税は、法人の課税所得に対して課税される税金です。課税所得とは、税務上の益金から損金を差し引いた金額のことで、会計上の当期純利益とは計算方法が異なるため必ずしも一致しません。益金には売上収益や受取利息などが含まれ、損金には売上原価や販売費及び一般管理費、支払利息などが含まれます。
重要なポイントとして、赤字の場合は原則として法人税は発生しませんが、法人住民税の均等割などの他の税金は発生する場合があります。これは、法人税が利益に対する課税であるのに対し、法人住民税の均等割は法人の存在自体に対する課税だからです。
繰越欠損金(赤字)による控除制度
法人税の計算において重要な制度の一つが、繰越欠損金による控除です。過去の事業年度で発生した欠損金(赤字)は、一定期間内であれば将来の黒字と相殺することができます。現在の制度では、最大10年間の繰越しが可能となっています。
ただし、中小企業以外の法人については、繰越欠損金の控除額に上限が設けられており、課税所得の50%までしか控除できません。中小企業については、この制限はありません。
法人税率の仕組みと資本金による割合の区分
法人税の税率は、法人の資本金額と所得金額によって異なる税率が適用されます。この仕組みは、中小企業に対する配慮として設けられており、小規模な法人ほど税負担が軽くなるよう設計されています。
資本金区分による法人税の税率割合の詳細
2019年時点での法人税率は以下のように設定されています。まず、資本金1億円以下の中小企業については、年800万円以下の所得部分に対して軽減税率の15%が適用されます。一方、年800万円を超える所得部分については23.2%の税率が適用されます。
| 資本金 | 所得金額 | 法人税率 |
|---|---|---|
| 1億円以下 | 800万円以下 | 15% |
| 1億円以下 | 800万円超 | 23.2% |
| 1億円超 | 全額一律 | 23.2% |
資本金1億円を超える大企業については、所得金額に関係なく一律23.2%の税率が適用されます。これは、中小企業支援の観点から、一定規模以上の企業には軽減措置を適用しないという政策的配慮によるものです。
中小企業軽減税率の適用条件
中小企業軽減税率の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、資本金が1億円以下であることが基本条件です。ただし、資本金が1億円以下であっても、大法人の100%子会社や、複数の大法人によって完全支配されている法人については、軽減税率の適用対象外となります。
また、同族会社の留保金課税や特定同族会社の特別税率など、特別な規定が適用される場合もあります。これらの詳細については、税理士などの専門家に相談することが重要です。
法人税の租税特別措置法による適用例
法人税の計算においては、租税特別措置法による各種の特例措置が適用される場合があります。例えば、研究開発税制や設備投資促進税制、中小企業投資促進税制などがあり、これらの制度を活用することで、実質的な税負担を軽減することが可能です。
特に中小企業向けの措置として、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例や、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例などがあります。これらの制度を適切に活用することにより、大幅な節税効果を得ることができる場合があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



法人税の具体的な計算方法とシミュレーション
法人税の実際の計算は、課税所得に対して適用される税率を段階的に適用することで行われます。特に中小企業の場合、800万円を境界として異なる税率が適用されるため、正確な計算方法を理解することが重要です。
法人税の基本的な計算式と手順
法人税の計算式は以下のようになります。資本金1億円以下の中小企業の場合、「法人税額 = 800万円以下部分×15% + 800万円超部分×23.2%」という計算式を使用します。
例えば、資本金5,000万円の会社で課税所得が1,000万円の場合、800万円×15% + 200万円×23.2% = 120万円 + 46.4万円 = 166.4万円が法人税額となります。この計算により、実際の納付すべき法人税額を算出することができます。
計算の際に注意すべき点として、課税所得は会計上の利益と必ずしも一致しないということがあります。 税務上の調整項目として、減価償却の差異や交際費の損金不算入、受取配当金の益金不算入などがあり、これらを適切に調整した上で課税所得を算出する必要があります。
ざっくり分かる具体的なシミュレーション事例
実際の法人税計算をより理解しやすくするため、いくつかのパターンでシミュレーションを行ってみましょう。まず、課税所得500万円の中小企業の場合、全額が軽減税率の対象となるため、500万円×15% = 75万円が法人税額となります。
次に、課税所得1,500万円の中小企業の場合、800万円×15% + 700万円×23.2% = 120万円 + 162.4万円 = 282.4万円が法人税額となります。一方、資本金1億円超の大企業で課税所得1,500万円の場合、1,500万円×23.2% = 348万円が法人税額となり、中小企業との差額は65.6万円となります。
これらのシミュレーション結果から分かるように、中小企業の軽減税率は相当な節税効果をもたらします。特に、課税所得が800万円以下の場合には、大企業と比較して約8.2%もの税率差が生まれることになります。
シミュレーションツールの無料利用可否について
法人税の計算には、インターネット上で提供されている無料のシミュレーションツールを活用することも可能です。これらのツールでは、基本的な課税所得や資本金額を入力することで、概算の法人税額を算出することができます。
ただし、これらのツールはあくまで概算であり、実際の税務申告では税理士などの専門家による詳細な計算と確認が必要です。特に、各種の税務調整項目や特例措置の適用については、専門的な知識が必要となるため、正確な申告のためには専門家のサポートを受けることをお勧めします。
法人に課される関連税金の全体像
法人税以外にも、法人には様々な税金が課されます。これらの税金を合わせた実質的な税負担率を「実効税率」と呼び、企業の税務戦略を考える上で重要な指標となります。主な関連税金として、地方法人税、法人事業税、法人住民税があります。
地方法人税の仕組みと計算方法
地方法人税は2014年に創設された比較的新しい税金で、国が徴収して地方交付金として各自治体に配分する仕組みになっています。税率は法人税額の10.3%(2019年10月以降)となっており、法人税額に対して課税されるため、赤字企業には課税されません。
例えば、先ほどの例で法人税額が166.4万円の場合、地方法人税は166.4万円×10.3% = 17.1万円となります。この税金は法人税とセットで考える必要があり、実質的な国税負担として捉えることができます。
法人事業税の所得割と外形標準課税
法人事業税は都道府県に納付する税金で、地域のサービス利用に対する経費負担という性格を持っています。 資本金1億円以下の法人については所得割のみが課税され、利益に応じた課税となります。一方、資本金1億円を超える法人については、所得割に加えて外形標準課税が適用されます。
外形標準課税は、付加価値割と資本割から構成され、利益の有無に関係なく課税される点が特徴です。付加価値割は報酬給与額や純支払利子、純支払賃借料などから算出され、資本割は資本金等の額に基づいて計算されます。
法人事業税の税率は各都道府県によって異なりますが、例えば東京都の場合、所得割の税率は3.5%から7%程度となっています。また、2019年以降は特別法人事業税との調整が行われており、より複雑な計算となっています。
法人住民税の法人税割と均等割
法人住民税は、道府県民税と市町村民税から構成されており(東京23区の場合は都民税のみ)、法人税割と均等割の2つの要素があります。法人税割は法人税額に対して一定の税率を乗じて計算されるため、赤字の場合には課税されません。
一方、均等割は、資本金額と従業員数を基準として課税される地方税であり、法人税額や利益の有無に関係なく、赤字であっても必ず課税される点が重要です。均等割の金額は自治体によって異なり、都道府県民税と市町村民税を合わせて最低でも年間7万円程度 の納税が必要となる場合があります。具体的な金額は法人の規模や所在地の自治体によって異なるため、詳細は自治体の税務担当窓口で確認するのが望ましいです。事業所が複数の自治体にまたがる場合には、それぞれの自治体に対して均等割を納付する必要があります。
実効税率の計算と節税対策のポイント
実効税率とは、法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、特別法人事業税を合算した実質的な税率のことです。この実効税率を正確に把握することで、企業の実際の税負担を理解し、適切な税務戦略を立てることができます。
実効税率の計算式と参考値
実効税率の計算は複雑です。法人事業税が損金算入されることを考慮する必要があります。一般的な計算式は以下のようになります。
実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率×(1-法人税率 ×(1+地方法人税率+法人住民税率))+特別法人事業税率×(1-法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率))}
東京23区に本社を置く中小企業の場合、実効税率は概ね33.58%程度となることが一般的です。これは、法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、特別法人事業税を合算した結果です。ただし、この数値は標準的な税率をもとにした概算であり、実際の税率は企業の規模や適用される税制優遇措置によって異なる場合があります。
実効税率を理解することで、利益計画と納付額の予測を適切に行うことができます。例えば、課税所得1,000万円の場合、実効税率33.58%を適用すると、総税額は約336万円となることが予想できます。この予測を活用することで、税務負担を踏まえた経営計画を立てることが可能です。
節税対策法人向けの基本的なアプローチ
法人向けの節税対策には様々な方法がありますが、基本的なアプローチとして以下のような対策が考えられます。まず、各種の税務上の特例措置を適切に活用することが重要です。研究開発税制や設備投資促進税制、中小企業投資促進税制などを活用することで、大幅な節税効果を得ることができる場合があります。
また、決算整理仕訳のポイントとして、減価償却の方法や繰延資産の処理、引当金の設定などを適切に行うことで、課税所得を適正な範囲で調整することができます。特に、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を活用することで、30万円未満の資産を一括で損金算入することができます。
会計仕訳と法人税の関係
会計仕訳と法人税の計算には密接な関係があります。会計上の利益と税務上の所得の差異を正確に把握し、適切な調整を行うことが重要です。主な調整項目として、交際費の損金不算入、減価償却の差異、受取配当金の益金不算入などがあります。
特に重要なのは、法人税の納付時における会計仕訳で、未払法人税等として適切に計上することが必要です。決算時には、「法人税等/未払法人税等」の仕訳を行い、納付時には「未払法人税等/現金預金」の仕訳を行います。これらの処理を適切に行うことで、正確な財務諸表の作成が可能となります。
申告手続きと納付の実務ポイント
法人税の申告手続きには、決算申告書の作成から納付書の書き方まで、様々な実務上のポイントがあります。適切な手続きを行うことで、スムーズな申告と納付が可能となり、税務調査のリスクも軽減することができます。
決算申告書作成方法の基本
法人税申告書は、企業の課税所得や法人税額を算出する重要な書類で、必要に応じて「別表一」「別表四」「別表五(二)」などを作成します。「別表一」では課税所得と法人税額を算出し、「別表四」では会計上の利益と税務上の所得の差異を調整します。
申告書作成には会計ソフトや税務ソフトが一般的に活用されますが、交際費の損金不算入や減価償却費の調整など、税務と会計の違いに留意する必要があります。適切な申告のためには、最新の税法を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
国税庁が運営する電子申告「e-Tax」の利用方法
現在では、国税庁が運営する電子申告システムe-Taxを利用することで、インターネット上で法人税の申告を行うことができます。e-Taxを利用することで、24時間いつでも申告が可能となり、申告期限延長手続きなども電子的に行うことができます。
e-Taxによる電子申告を行う場合には、事前の利用届出や電子証明書の取得が必要となります。また、申告データの作成には専用のソフトウェアや税務ソフトが必要となるため、初回利用時には十分な準備期間を確保することが重要です。
申告期限と延長手続きについて
法人税の申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2月以内となっています。ただし、定款で定めた場合や税務署長の承認を受けた場合には、申告期限を1月延長することができます。この延長手続きを行う場合には、事前に申請書を提出する必要があります。
申告期限を過ぎてしまった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。これらのペナルティを避けるためにも、適切なスケジュール管理と早めの準備が重要です。
まとめ
法人税の計算方法は、資本金額と課税所得に応じて適用される税率が決まる仕組みとなっています。中小企業については800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用され、それを超える部分及び大企業については23.2%の税率が適用されます。
実際の税負担を考える際には、法人税だけでなく地方法人税、法人事業税、法人住民税を含めた実効税率で検討することが重要です。東京23区の場合、実効税率は概ね30.62%程度となり、この数値を基準として資金繰りや利益計画を立てることができます。
適切な節税対策を行うためには、各種の特例措置の活用や決算整理仕訳の最適化が重要となります。ただし、税務は専門性が高い分野であるため、正確な申告と効果的な節税のためには、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。企業の成長段階や将来の事業計画を見据えた総合的な税務戦略を立てることで、健全な企業経営を実現することができるでしょう。
法人税の適切な管理は、M&A戦略においても重要な要素となります。企業価値の算定や買収後の統合計画において、税務面での検討は欠かせません。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。