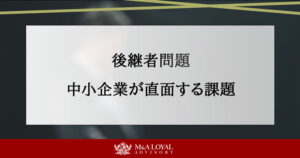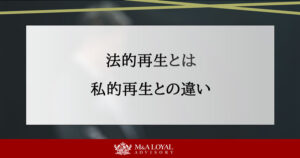会社をたたむ方法とは?手続きや費用、資産・借金の扱いについて解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
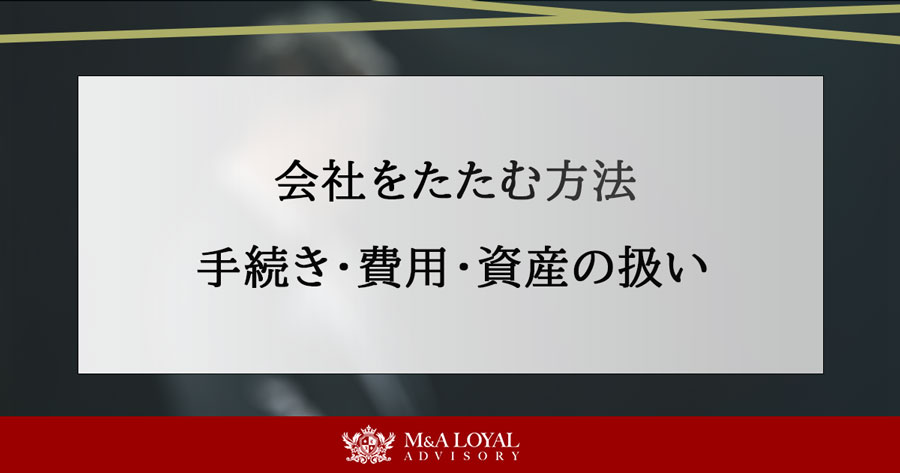
会社をたたむことを検討しているけれど、「何から始めれば良いのか分からない」「費用や手続きが複雑そうで不安」と感じていませんか?
準備不足のまま進めると、思わぬトラブルや金銭的な負担が発生することもあります。特に、債務の処理や従業員対応を誤ると、経営者個人にも責任が及ぶリスクがあります。
本記事では、会社をたたむ際の判断基準や具体的な流れ、必要な届出や費用、注意点までを網羅的に解説します。迷いを整理し、正しい選択ができるようサポートします。
目次
会社をたたむとは
「会社をたたむ」とは、事業活動を終了することです。単なる事業をしないだけでなく、法的な手続きを行い会社の存在が消滅します。「廃業」を意味することが多いですが、倒産や破産を指す場合もあります。
会社をたたむ理由は、経営の継続が難しくなった場合や新たな人生のステージへ進むタイミングなど、さまざまですが、会社をたたむという選択は、必ずしも後ろ向きなものではなく、再出発に向けた前向きな一歩ともいえるでしょう。
会社をたたむと似た言葉の意味
「会社をたたむ」と似た次の言葉の意味を解説します。
- 廃業
- 閉業
- 倒産
- 破産
- 解散
それぞれの意味と正しい使い方を解説します。
廃業
「廃業」とは、事業をやめること全般を指し、法人・個人を問わず広く用いられる言葉です。「会社をたたむ」とほぼ同じ意味で使われます。
ただし、廃業はやや形式的かつ中立的な表現であるのに対し、会社をたたむはより口語的で、感情や経営判断といった背景が感じられる表現です。例えば「会社をたたむ決断をした」という表現には、経営者の思いや事情がにじむことがあります。
一方で、公的な手続きや文書上では廃業という語が使われることが一般的であり、届出書類の名称も廃業届となっています。このことからも、廃業は汎用性と公式性に優れた表現であるといえます。
閉業
「閉業」とは、事業の営業活動を停止することを指し、法人格の有無にかかわらず用いられる実務的な言葉です。
「会社をたたむ」が事業活動および法人の終了までを含むのに対し、閉業は一時的な営業停止や店舗単位での営業終了を表す場合もあります。再開の可能性がある場合にも使われるため、閉業は必ずしも事業の終結を意味するわけではありません。
例えば、飲食店の1店舗を閉じる場合や、法人を休眠状態にする前段階としての活動停止も閉業と呼ばれることが多いです。 「会社をたたむ」と閉業は、規模や意図の違いにより使い分けられる表現といえます。
倒産
「倒産」とは、会社が資金繰りに行き詰まり、経済的に事業の継続が困難になった状態を広く指す言葉です。支払い不能や債務超過に陥り、経営が行き詰まった際に用いられます。
「会社をたたむ」が経営者の判断であるのに対し、倒産は追い込まれた末の事業終了という意味合いです。
倒産は、特定の法的手続きを指す言葉ではありませんが、破産や民事再生、特別清算、会社更生といった法的整理全般や、手形不渡りによる取引停止などを広く含む用語として用いられます。
破産
「破産」とは、会社や個人が債務超過や支払い不能に陥った際に、裁判所に申し立てて法的に財産を整理・処分する手続きです。
「会社をたたむ」が自主的かつ計画的な事業の終了であるのに対し、裁判所や破産管財人などの第三者が関与し、法的手続きに基づいて強制的に進められる点が大きな違いです。
法人が破産した場合、その資産は売却され、債権者に配当されたのち、最終的に会社は消滅します。 「会社をたたむ」ことが、ある程度余力のある段階で選択できる自主的な整理であるのに対し、破産は、まさに万策尽きた状態からの脱出手段といえます。
社会的信用への影響も大きく、厳格な法的措置として位置付けられます。
解散
「解散」とは、会社が今後の事業継続を継続しないことを法的に決定する手続きであり、「会社をたたむ」プロセスの第一段階にあたります。
株主総会での決議により解散が決定すると、通常の営業活動は停止され、清算人によって資産および負債の整理が行われる清算手続きへと移行します。 「会社をたたむ」とは違い、解散は法律用語として明確な定義を持ちます。
解散しただけでは法人格は残っており、清算結了登記が行われてはじめて、会社は完全に消滅します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



会社をたたむ判断とタイミング
会社をたたむ判断とタイミングは、次のとおりです。
- 継続的に赤字が続いている
- 人材・リソースの枯渇している
- 経営者の事情や後継者がいない
それぞれを詳しく解説します。
継続的に赤字が続いている
赤字が長期にわたって続いている場合は、会社をたたむか真剣に検討するタイミングです。
単月や一時的な赤字であれば立て直しの余地はありますが、資金繰りが慢性的に悪化し、借り入れや資産の取り崩しでしのぐ状態が続くと、いずれ限界が訪れます。
特にキャッシュフローが回らなくなった場合は、事業継続のリスクが急激に高まるため、極めて危険な状態といえます。
早期の見極めにより、清算処理や事業譲渡といった前向きな選択肢につなげられます。
人材・リソースの枯渇している
事業を継続するには、人材や技術、資金、仕入れルートなどの経営リソースが欠かせません。
例えば、社員の退職が相次ぎ業務が回らなくなったり、特定のスキルを持つ人材が確保できなくなった場合、それは組織としての限界を示すサインかもしれません。
また、資金調達が難航し、設備投資や在庫の確保ができない状態や、販売チャネルを喪失している状態では、いくら経営努力を重ねても、事業の基盤が成り立ちません。
このように、経営リソースの枯渇が長期化し、改善の見通しも立たない場合には、無理に事業を継続するよりも、撤退や廃業といった選択を検討する方が、結果的に合理的であるといえます。
経営者の事情や後継者の不在
経営者の年齢や体調の変化、家庭の事情により、これまでどおりの経営を続けることが難しくなる場面は少なくありません。
特に中小企業では、経営者が業務の多くを担っていることが多いため、健康状態の悪化やモチベーションの低下が、事業の継続に直結します。
また、後継者不在の問題も深刻です。社内に継承可能な人材がいない場合や、家族が事業を継ぐ意向を持っていない場合は、たとえ会社が黒字であっても、事業の継続は困難です。
会社をたたむメリット
会社をたたむメリットは、次のとおりです。
- 資産や信用を守れる可能性がある
- 精神的ストレスの軽減
- 従業員や取引先への迷惑を最小限にできる
それぞれを分かりやすく解説します。
資産や信用を守れる可能性がある
経営状態が悪化する前に自主的に会社をたたむことで、手元の資産を守れるのが大きなメリットです。
また、資産が残っているうちに清算を進めれば、債務の整理も計画的に行え、金融機関や取引先との関係も良好に保ちやすいといえます。
さらに、代表者個人が保証している借入金についても、適切な時期に事業を終了すれば、自己破産を回避できる場合もあります。
経営破綻寸前まで追い込まれると、選択肢は限られてしまいますが、余裕があるうちであれば、会社の売却や再起の道も模索可能です。
精神的ストレスの軽減
経営がうまくいかないと、経営者の精神的なストレスはとても大きくなります。
例えば、常に資金繰りに追われたり、従業員や取引先への責任に苦しんでいる場合、会社をたたむという選択は、経営者自身の心身を守る手段といえます。
事業を終了することで、プレッシャーや将来への不安から解放され、自分や家族の生活を立て直す余裕が生まれることもあるでしょう。
会社をたたむ決断は必ずしも逃げではなく、自分自身を守るための決断として捉えられます。
従業員や取引先への迷惑を最小限にできる
事業の終了が不可避な場合でも、早めに会社をたたむ判断をすれば、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられる点も大きなメリットです。
例えば、事前に従業員と協議し、退職のスケジュール調整や再就職の支援を行うことで、トラブルを防げます。
取引先にも余裕を持って通知できれば、未納や納品トラブルも回避可能です。
逆に、限界まで事業を続けると、支払い不能や契約不履行などによって、関係者に損害を与えてしまうリスクが高まります。
誠実な終わり方を選ぶことで、経営者自身の評価や信頼も損なわれず、将来の活動にも良い印象を残せるのです。
会社をたたむ手順【法人】
法人の場合の会社をたたむ手順は、次のとおりです。
- 事前準備と関係者への説明
- 株主総会での解散決議と清算人の選任
- 解散・清算人の登記
- 解散後に必要な手続きを行う
- 債権者への通知と公告をする
- 財産整理と債務の清算
- 決算書類の作成・確定申告
最も一般的な会社形態である株式会社を想定して解説します。
事前準備と関係者への説明をする
会社をたたむと決めた際に、最初に行うべきことは関係者への丁寧な説明と調整です。
従業員には、退職予定日や最終給与、退職金の有無、必要に応じて再就職支援の有無などを明確に伝える必要があります。
取引先に対しては、契約の終了時期や未払い債務の清算方法について事前に説明し、トラブルを防ぐよう努めましょう。
また、借り入れがある場合は、金融機関に対して廃業の理由や返済方針を説明し、誠意ある対応によって信頼を損なわないようにすることが重要です。
併せて、商工会・業界団体・保険などの脱退や契約解除の手続きも順次進めましょう。
こうした事前準備が、円滑な清算や信頼関係の維持につながります。
株主総会での解散決議と清算人を選任する
会社をたたむ際に最初に行う正式な手続きは、株主総会での解散決議です。
この決議は通常の議決とは異なり、特別決議として所定の出席率と賛成多数が求められます。具体的には、発行済株式の過半数の出席と、その出席株主の3分の2以上の同意が必要です。
併せて、会社の資産や負債を整理する責任者として、「清算人」も指名されます。
一般的には代表取締役がその役割を担いますが、清算人を複数置く場合は、その中から代表者を選任する必要があります。
清算人は、会社の財務整理や債権者対応など、清算に関する一連の業務を担う重要な立場です。
この決議が、法人を正式にたたむための第一歩といえます。
解散・清算人の登記をする
株主総会で決議がなされたら、2週間以内に解散手続きを行います。
ここでいう「解散」とは、会社が今後の事業を継続しないことを正式に決定し、法人としての活動を停止することを指します。
会社を解散した後は、2週間以内に法務局で解散および清算人の登記を行う必要があります。
この手続きを行わずに放置すると、法人格が存続しているとみなされ、住民税の均等割や確定申告などの義務が発生し続けるため、早めの対応が重要です。
登記にあたっては、次の書類を準備します。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主名簿(氏名・住所・持株数・議決権割合など)
- 定款(清算人に関する定めの有無を確認)
- 清算人の就任承諾書(取締役以外を選任した場合)
- 印鑑届出書(社印の使用を継続する場合)
登記は清算人自身でも手続き可能ですが、慣れない方は司法書士への依頼が一般的で、その際には委任状も別途必要です。
解散後に必要な手続きを行う
解散および清算人の登記が完了したら、「異動届出書」と「登記事項証明書」の作成・準備に取り掛かり、税務署や県税事務所、市町村役場へ提出します。
併せて、社会保険に関する手続きや、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書の提出も忘れずに行いましょう。
| 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
| 税務署 | 異動届出書、事業廃止届出書 | 速やかに |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 1カ月以内 | |
| 青色申告取りやめの届出書 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで | |
| 都道府県税事務所など | 異動届出書 | 速やかに |
| 日本年金機構 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、被保険者資格喪失届 | 5日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書 | 離職後の翌々日から10日以内 |
| 雇用保険適用事業所廃止届 | 事業所の廃止の翌日から10日以内 | |
| 労働基準監督署 | 確定保険料申告書、労働保険料還付請求書 | 保険関係が消滅した日から50日以内 |
債権者への通知と公告をする
会社の解散登記が完了した後は、取引先や金融機関など、会社に対して債権を有する者に対して通知を行うことが重要です。
これは、未払いの請求や貸付金などがある場合に、債権者から申し出てもらうための重要なプロセスで、いわゆる「債権者保護手続き」と呼ばれます。
まず、法定公告媒体である官報に解散の旨を掲載し、併せて、既に把握している債権者には個別に文書で通知する必要があります。
申し出期間は2カ月以上設ける必要があり、その間に届いた債務には、清算人が順次対応していきます。
この手続きを適切に行わないと、後から思わぬ請求や法的責任が発生する恐れがあるため、正確かつ誠実な対応が欠かせません。
財産整理と債務の清算
選任された清算人は、債権者からの請求を受け付けながら、会社の財産を現金化する作業に取りかかります。
具体的には、在庫や備品、所有している不動産などを市場価格で売却し、その売却資金を用いて、未払いの取引代金や借入金、税金、社会保険料などの債務を弁済します。
こうした債務の弁済が全て完了した後、なお会社に資産が残っている場合は、それが「残余財産」として株主に分配されます。
財産の処分や債務の整理が複雑な場合や、税務処理に不安がある場合は、手続きをより円滑に進めるためにも、専門の税理士などのサポートを受けることがおすすめです。
決算書類の作成・確定申告
会社の解散後は、通常の営業活動は停止しますが、法人としては「清算中の会社」として存続しているため、決算および確定申告の手続きが必要です。
まず、清算開始時点の財務状況を反映した貸借対照表や財産目録を作成し、それに基づいて解散事業年度の法人税・消費税の申告を行います。
提出先は税務署で、期限は解散日から2カ月以内です。その後、清算が完了した時点で再度決算を行い、清算確定申告書を提出する必要があります。
これにより、法人としての最終的な納税義務を果たせます。税額計算や書類作成が難しい場合は、税理士に依頼することで、申告ミスや期限遅れを防げるため、おすすめです。
会社をたたむ手順【個人事業主】
個人事業主が会社をたたむときの手順は、次のとおりです。
- 廃業日を決定する
- 税務署に「廃業届」を提出する
- 社会保険・雇用保険の手続きを行う
- 残務処理と契約・口座の整理
- 最後の確定申告を行う
それぞれを詳しく解説します。
廃業日を決定する
個人事業をたたむ際は、まず廃業日を明確に定める必要があります。この日付は、税務署への届出や社会保険・雇用保険の脱退手続きにおける基準日となる重要な日です。
実務面では、売り上げや経費の締め、請求書の発行タイミングなどを踏まえ、作業に区切りがつけやすい日を選ぶと良いでしょう。
月末や四半期末など、経理処理上の区切りが良い時期を選ばれることが多く、今後の申告や事務処理にも影響するため、慎重に決定する必要があります。
税務署に「廃業届」を提出する
個人事業を廃業する場合は、税務署に「個人事業の廃業等届出書」を提出する必要があります。
この届け出は、廃業日から1カ月以内に行うことが定められており、事業を廃業したことを正式に届け出る重要な手続きです。
青色申告を行っている場合は、これに加えて「青色申告の取りやめ届出書」も提出しなければなりません。
提出が遅れると、後の確定申告や税務処理に影響を及ぼす可能性があるため、廃業日を決定した段階で、早めに準備を進めましょう。
社会保険・雇用保険の手続きを行う
個人事業を廃業する際に従業員を雇用していた場合は、社会保険および雇用保険に関する脱退手続きを行う必要があります。
健康保険および厚生年金保険については、日本年金機構に「資格喪失届」を提出し、従業員の加入資格を終了させます。
同時に、ハローワークにも「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職証明書」を提出し、雇用保険の脱退手続きを進めます。
従業員だけでなく、事業主本人も社会保険から脱退します。そのため、市区町村役場で国民健康保険および国民年金への加入手続きを済ませておくことが重要です。
残務処理と契約・口座の整理
廃業を届け出た後も、事業に関連する細かな手続きや後処理が残ります。
まず、未収の売掛金があれば回収を進め、在庫や設備などの資産は処分や売却などの形で整理します。取引先には廃業の連絡を行い、契約終了に伴う支払いや受領の調整も必要です。
また、各種リース契約やサブスクリプションサービス、光熱費、インターネットなどの名義変更や解約の手続きも忘れずに行いましょう。併せて、事業専用で使用していた銀行口座やクレジットカードも早めに解約しておくと安心です。
最後の確定申告を行う
個人事業を廃業した場合でも、その年の収支については、翌年の確定申告期間中(通常2月16日〜3月15日)に「事業所得」として申告する必要があります。
廃業日までに得た売り上げや経費を集計し、必要に応じて減価償却費や棚卸資産も整理した上で、通常どおり申告書を作成します。
青色申告を選択していた場合、最終年度でも青色の特典(65万円控除など)を適用できますが、そのためには帳簿や決算書類の正確な管理が不可欠です。
また、必要に応じて「所得税の青色申告取りやめ届出書」も併せて提出しておくと良いでしょう。廃業後も税務手続きは続くため、計画的に準備を進めることが大切です。
会社をたたむ際に必要な費用
会社をたたむ際に必要な費用は、次のとおりです。
- 登記関連費用
- 官報公告の掲載費用
- 社会保険・雇用関係の清算費用
- 税務処理や専門家への依頼費用
それぞれを分かりやすく解説します。
登記関連費用
会社をたたむには、法務局での登記手続きが必要です。
まず、会社の解散と併せて行う清算人選任の登記には、登録免許税として合計3万9000円(解散登記3万円、清算人選任登記9000円)がかかります。
その後、清算手続きが完了した際に行う「清算結了登記」には、さらに2000円の登録免許税が必要であり、登記にかかる登録免許税は合計で4万1000円となります。
登記に必要な書類は自分で準備することも可能ですが、不備があると手続きが遅れるため、正確な処理が求められます。
書類作成や申請手続きを専門家に依頼する場合は、司法書士への報酬として5万〜10万円程度の追加費用がかかることが一般的です。
官報公告の掲載費用
会社を解散する際は、債権者保護のために解散公告を官報に掲載する義務があります。 この公告には、債権者に債権の申し出を促すため、2カ月以上の申出期間を設ける必要があります。
官報公告の掲載費用は、公告の文字数や行数によって異なりますが、一般的な解散公告の場合、おおむね3万〜4万円程度です。
官報公告は、債権者に債務の存在を申し出てもらうための法的手続きであり、省略できません。
公告原稿の作成や掲載手続きは、清算人が自ら行うことも可能ですが、内容に不備があるとやり直しになる可能性もあるため、必要に応じて専門家のチェックを受けると安心です。
社会保険・雇用関係の清算費用
従業員がいる状態で会社をたたむ場合、前述のとおり、社会保険や雇用保険の手続きが必要です。
これらの手続き自体には費用はかかりませんが、書類の取得や郵送費用が発生します。書類の作成や届け出が煩雑で手間もかかるため、社会保険労務士などの専門家に委託する選択肢もあります。 その場合は依頼費用も考慮する必要があります。
また、退職に伴って未払いの賃金や退職金が発生するケースもあるため、これらの人件費も清算費用として事前に計上しておくことが重要です。
税務処理や専門家への依頼費用
会社をたたむ際には、通常の会計業務に加え、解散時と清算完了時の2回にわたって法人税などの確定申告を行う必要があります。
これらの手続きは内容が複雑になりやすいため、税理士に依頼するケースが一般的です。
依頼費用は、業務量や会社の規模によって異なりますが、決算申告のみの場合、おおよそ15万〜30万円が目安とされています。
また、法務手続きを自力で行うことが難しい場合は、司法書士に登記を依頼することになり、その報酬として5万〜10万円程度が必要です。
全ての業務を専門家に任せた場合、合計で数十万円規模の支出となる可能性があります。しかし、手続きの正確性やトラブルの回避といった観点から見れば、それだけの費用をかける価値は十分にあるといえるでしょう。
会社をたたむときの注意点
会社をたたむときの注意点は、次のとおりです。
- 手続きの漏れや遅れに注意する
- 従業員・取引先への配慮を怠らない
- 債務や個人保証の扱いに注意する
それぞれを分かりやすく解説します。
手続きの漏れや遅れに注意する
会社をたたむ際には、上述したように、法務局への登記や税務署への届出、社会保険・労働保険の脱退手続きなど、多岐にわたる事務作業が発生します。
これらにはそれぞれ期限が定められており、提出が遅れるとペナルティや追加対応が発生することも珍しくありません。
特に法人税の清算申告や解散後の清算結了登記は、忘れやすい工程のひとつであるため注意が必要です。 スケジュール管理と正確な書類準備が、トラブルを避けるための基本です。
従業員・取引先への配慮を怠らない
会社をたたむ決断をした後は、事務手続きや財務整理に意識が向きがちですが、社内外の関係者への誠実な対応も欠かせません。
従業員に対しては、退職時期や給与・退職金の支払い予定を明確に伝え、不安を軽減する姿勢が求められます。
併せて、離職票の発行や就職支援の案内など、退職後の生活に配慮した対応も検討すると良いでしょう。
また、取引先には契約終了のスケジュールや未払い金の支払計画を丁寧に説明し、混乱や不信感を避けることが大切です。
突然の廃業が周囲に影響を及ぼすからこそ、最後まで誠意ある行動を心がけることが信頼の維持につながり、今後の再出発にも好影響を与えます。
債務や個人保証の扱いに注意する
会社の借り入れやリース契約などに代表者本人が個人保証をしている場合は、会社をたたんだ後も返済義務が残ることがあります。
特に、解散後に発覚する債務や未処理の契約があると、思わぬ負担が生じかねません。
清算の段階で、全ての債務と契約内容を確認し、支払い能力や処理方法を整理しておくことが重要です。
個人資産への影響が大きいと判断される場合は、事前に専門家に相談し、特別清算や破産手続きも視野に入れておくと安心です。
会社を閉じたあとにもリスクが残る可能性があることを念頭に置き、適切に対応しましょう。
会社をたたむ前に検討すべきこと
会社をたたむ前に検討すべきことは、次のとおりです。
- 事業の一部縮小
- 一時的に休眠する
- M&Aによる事業承継
- 借入金や契約の整理・交渉
それぞれを詳しく解説します。
事業の一部縮小
会社全体をたたむ前に、赤字の要因となっている一部の事業や拠点を見直すという選択肢もあります。
採算の取れないサービスを停止し、利益が見込める領域に資源を集中することで、経営の立て直しが図れることも少なくありません。
また、雇用形態の見直しや業務の外注化によって、固定費を抑える工夫も有効です。
経営の苦しさから「全てを終わらせたい」と感じることもありますが、部分的な整理だけで再生できる余地が残されている可能性もあります。
会社をたたむという結論を急がず、まずは縮小や再構築による再生の可能性を冷静に見極めることが大切です。
一時的に休眠する
今すぐに廃業を決めるのではなく、事業の再開を視野に入れて、会社を休眠状態にするという選択肢もあります。
休眠とは、会社の営業活動を一時的に停止することであり、法人自体は存続するため、解散や清算といった手続きは不要です。
必要な手続きは、税務署に事業休止の届出を提出するだけで済みます。
ただし、自治体によっては休眠中でも法人住民税の均等割が課されることがあるため、維持コストとの兼ね合いを事前に確認しておくことが大切です。
再起の可能性を残しておきたい、あるいは判断を先送りしたい場合には、会社の活動を一時的に停止し様子を見るという柔軟な選択肢も検討に値します。
M&Aによる事業承継
経営の継続が難しい場合でも、事業や顧客、従業員などに一定の価値がある場合は、M&Aによって他の企業へ引き継ぐ方法もあります。
自ら会社をたたむのではなく、買い手企業に株式取得してもらう、または事業譲渡することで、雇用や取引先との関係を維持しながら事業を継続させられる点がメリットです。
特に後継者の不在に悩む中小企業では、近年こうした事業承継が増えています。小規模事業者でも利用しやすいM&Aプラットフォームや支援サービスが登場しており、専門家のサポートを受けながら進められます。
廃業が唯一の選択肢ではないということを、改めて認識しておくことが大切です。
借入金や契約の整理・交渉
経営が厳しくなったときは、すぐに廃業を決断するのではなく、まずは借入金や契約の条件の見直しから始めてみるのもひとつの方法です。
資金繰りに余裕がない場合でも、金融機関と相談して返済スケジュールを見直したり(リスケ)、一時的な支払いの猶予を得ることで、事業継続の余地が生まれることもあります。
また、必要性の低いリース契約やサブスクリプションを解約するだけでも、毎月の固定費を削減できることがあります。
経費の棚卸しや財務の再構成を進めることで、廃業を回避できるケースもあります。やめる決断を下す前に、専門家とともに立て直しの道を探ってみることが大切です。
会社をたたむことに関するQ&A
最後に、会社をたたむことに関するよくある質問とその回答を紹介します。
借金が残ったままでも会社はたためるか
借金が残っていても、会社をたためます。
資産で債務を返済できる場合は通常の清算手続きで進められますが、債務超過で完済が難しい場合は、特別清算や破産といった法的手続きが必要です。
また、代表者が個人保証している借金がある場合は、会社の清算後も個人に返済義務が残る点にも注意しましょう。状況によって手続きが異なるため、専門家への相談をおすすめします。
黒字でも会社をたためるか
黒字であっても会社をたためます。
事業が利益を出していても、後継者がいない、経営者の健康や家庭の事情、別の道に進みたいといった理由から、あえて廃業を選ぶケースは少なくありません。
黒字廃業であれば、債務整理や清算もスムーズに進みやすく、従業員や取引先への影響も最小限に抑えられるという利点があります。
経営が順調だからこそ、余力のあるうちに前向きな撤退を選ぶという判断も十分に合理的といえます。
会社をたたむことを決めたあとに営業再開できるか
会社をたたむことを決めた後でも、解散登記を行う前であれば、営業再開は可能です。
例えば、株主総会で解散を決議した後に状況が変わり、事業を継続する判断に至った場合は、解散の手続きを取りやめて通常の営業に戻れます。
解散登記が完了すると、会社は営利目的の事業活動は原則としてできません。
この段階で営業を再開したい場合は、清算を中止し、法務局で「解散の取消登記」を行う必要があります。
ただし、この手続きは手間がかかり、既に進行している清算処理を巻き戻すことになるため、現実的に簡単ではありません。
会社をたたむと個人の信用情報に影響するか
会社をたたむだけで、直ちに代表者の個人信用情報に傷がつくことはありません。 法人の任意廃業は、個人の信用とは基本的に切り離されているためです。
ただし、代表者が会社の借り入れに個人保証をしていた場合で、その借り入れが返済できず延滞や債務整理となったときには、個人の信用情報に登録される可能性があります。
つまり、廃業の有無よりも、借金の返済状況の方が個人の信用情報に大きく影響します。
最後に、会社をたたむことは終わりではなく、新しいスタートを切るためのステップです。次のステージに向けて、必要な準備を整え、前向きに進んでいくことを目指してください。
M&Aや経営課題に関するお悩みがある場合は、M&Aロイヤルアドバイザリーへご相談ください。専門家があなたの新たな一歩をサポートします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。