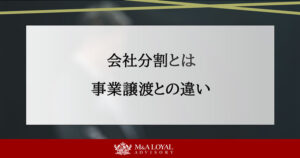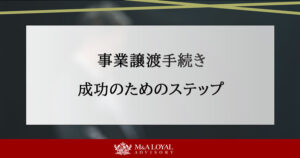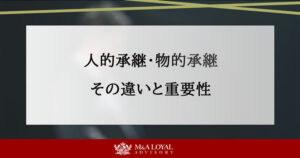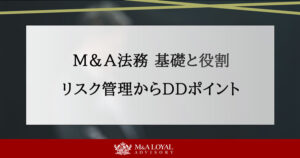事業譲渡で従業員はどうなる?同意・転籍・退職対応まで徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
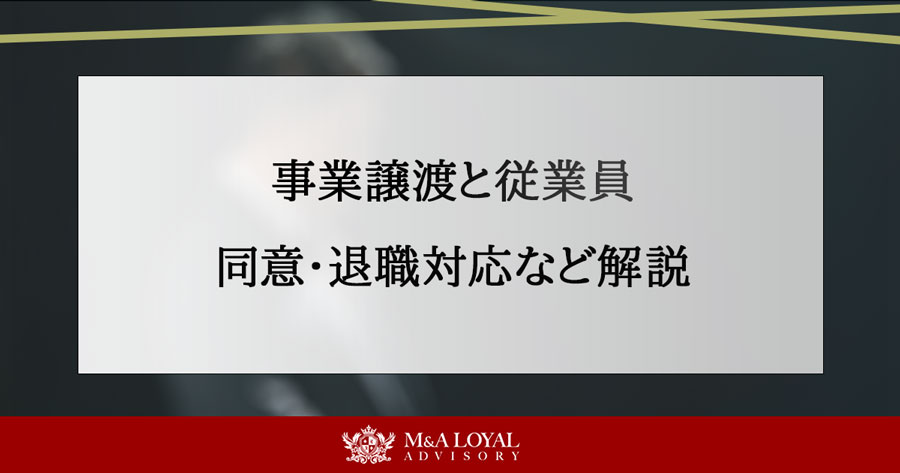
事業譲渡は、企業の一部門やサービス、店舗などの事業単位で資産・契約・顧客基盤などを譲渡するM&A手法の一つです。 株式譲渡や合併とは異なり、「法人格」自体は変わらない一方で、契約や雇用関係といった“人と人のつながり”を個別に移転させるという特徴を持ちます。
このため、譲渡対象となる「人材」、すなわち従業員の取り扱いこそが、事業譲渡の成否を大きく左右する要素といっても過言ではありません。
特に中小企業においては、創業期から勤めている社員や、属人的なスキルに依存しているケースも多く、「誰が残って、誰が移るのか」「条件は引き継がれるのか」「本人の同意は必要か」など、 法的にも感情的にも繊細なマネジメントが求められます。
しかし、現実には以下のようなトラブルが頻発しています。
- 譲渡後に主要人材が離職し、事業の継続性が損なわれる
- 従業員の同意取得に時間を要し、スケジュールが遅延
- 労働条件の相違による不満や誤解が社内に拡大
- 転籍・出向・引き抜きなど、法的リスクを伴う人事措置の混乱
本記事では、事業譲渡における従業員対応の全体像と実務上の注意点を、 労働法・労務マネジメント・M&A契約実務の観点からわかりやすく解説します。
目次
事業譲渡とは何か?──株式譲渡との違いと基礎知識を徹底理解
M&Aと一口にいっても、その手法には多様な形があります。なかでも「事業譲渡」は、企業の特定部門やサービス単位で資産・契約・人材を譲渡する柔軟な方法として、中堅・中小企業を中心に近年活用が進んでいます。
ただし、この「事業譲渡」というスキームには、他のM&A手法と異なる複雑な特徴があり、とくに従業員の取扱いにおいては、実務上極めて重要な配慮が求められます。
本章では、事業譲渡の基本概念と、よく比較される株式譲渡・会社分割などとの違い、そして実際のM&Aにおける使い分けについて詳しく解説していきます。
事業譲渡とは何か?──定義と法的構造
事業譲渡とは、企業が営む事業の全部または一部を、契約によって他者に譲渡することです。
ここで言う「事業」とは、単なる資産の集まりではなく、一定の経済的目的を持って継続的に営まれている組織的活動のまとまりを指します。
すなわち、単に「在庫を売る」「設備を売る」という単発の資産譲渡とは異なり、その事業に関わる資産・契約・従業員・ノウハウ・ブランド・顧客基盤などを包括的に譲渡対象とします。
▶ 参考:会社法上の規定
日本の会社法第467条では、「事業の全部または重要な一部の譲渡」は、株主総会の特別決議を要する行為とされています。 このことからも、事業譲渡は経営の根幹をなす取引であることがわかります。
株式譲渡・会社分割との違い
▷ 株式譲渡:法人のオーナーシップだけが変わる
株式譲渡は、企業の「所有者」である株主が、その保有する株式を第三者に売却する行為です。
この場合、会社自体の法人格は一切変わらず、契約関係・従業員・許認可・債権債務もそのまま継続されます。
つまり、中身(経営内容や従業員など)はそのまま、“所有者(株主)”だけが変わるというのが株式譲渡の特徴です。
▷ 会社分割:組織単位で移転する再編スキーム
一方、会社分割(特に吸収分割・新設分割)は、会社分割とは、法人の一部あるいはすべての事業部門や特定の資産・負債を切り離し、別の会社に承継させる法的手続きです。
こちらは法的承継効が認められるため、契約や労働契約も包括的に引き継がれます。
ただし手続きが煩雑で、裁判所や登記・公告なども関与するため、スピード感に欠けるケースがあります。
なぜ事業譲渡が選ばれるのか?──柔軟性とリスク管理
事業譲渡が選ばれる主な理由は、以下のとおりです。
- 譲渡する対象を自由に選べる(必要な資産・人材・契約だけを引き取る)
- 株主構成や持株会社化の複雑さを回避できる
- 不採算部門だけを切り離して譲渡できる
- 法人ごと移す必要がないため、税務・許認可面で有利なケースもある
特に中小企業やスタートアップにおいては、特定の技術やサービスのみを譲渡し、会社本体は維持することで、経営の柔軟性を確保するという活用が多く見られます。
事業譲渡の“盲点”──従業員は自動的に移らない
ここが最大の論点です。
事業譲渡では、従業員の雇用契約は自動的に譲渡先へは移りません。
これは「労働契約の当事者は労働者個人であり、企業間の契約では移せない」という原則によるもので、 譲渡元企業と譲受企業でどれだけ話がまとまっていても、従業員本人の“同意”がなければ転籍できないのです。
▷ 実務上の流れ
- 譲渡企業側での雇用契約終了(=退職扱い)
- 譲受企業側での新規採用(=内定・雇用契約)
- 従業員本人との条件交渉・同意取得
この過程において、従業員側が「条件が悪くなる」「勤務地が変わる」「譲渡に納得できない」などと感じれば、 退職してしまうケースもあり、事業継続性に大きなリスクが生じます。
雇用リスクが顕在化する典型的なシナリオ
- 主要人材が譲渡直前で退職を表明し、顧客対応が混乱
- 譲受企業側の待遇が不十分で、従業員の合意が取れない
- 労働組合や労働局から労働条件切り下げとして指摘を受ける
- 形式的な同意取得のみで実態を伴わず、後日トラブルに発展
このように、人の問題は「見えにくく、かつ最もダメージが大きい」のが事業譲渡の特徴です。
経営者・人事担当者が心得るべきこと
- 従業員には事前説明と十分な準備期間を設ける
- 労働条件の変化を最小限にし、納得のいく移行を設計する
- “退職・再雇用”ではなく“円滑な転籍”として受け止めてもらう工夫が必要
- 労働法・労基署・弁護士等と連携したリスクマネジメントが不可欠

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事業譲渡時における従業員の移籍──転籍・出向・新規雇用の違いと対応策
事業譲渡では、設備やノウハウだけでなく“人材”の引き継ぎが極めて重要です。特に従業員がスムーズに新しい環境へ移行できるかどうかは、譲渡後の事業安定に直結します。本章では、「転籍」「出向」「新規雇用」という3つの移籍パターンを軸に、法的要件・実務対応・注意点を具体的に解説します。
転籍とは何か?法的定義とプロセス
転籍とは、従業員が元の会社との雇用契約を終了させ、新たに譲渡先の会社と雇用契約を結ぶことを意味します。つまり、法律的には“完全に別の雇用”が成立するということです。
転籍には必ず、本人の書面による明確な同意が必要です。これは労働契約法第6条で、労働契約の一方的な譲渡が禁止されているためで、本人の意思を無視した転籍は無効となります。
実務上の流れは以下の通りです。
- 譲渡決定の通達と個別説明会の実施
- 雇用条件提示(待遇・勤務地など)
- 転籍同意書の取得
- 譲渡先企業との新雇用契約の締結
従業員にとっては、転籍により職場環境や文化が大きく変わる可能性があるため、不安の声も多く聞かれます。そのため、転籍交渉においては、給与・福利厚生の維持や、キャリア支援などの補償的施策を丁寧に提示することが不可欠です。
出向との違いと実務上の注意点
出向とは、従業員が元の企業に在籍したまま他の企業で働く形態で、法的には「在籍出向」と「転籍出向」の2種類がありますが、事業譲渡の場面では在籍出向が一般的です。
出向では、雇用契約の主体は元の企業に残り、給与の支払いや社会保険なども出向元が対応する場合が多いです。従業員としては元の会社との関係が継続するため、心理的な負担が小さく、受け入れやすい形式です。
出向のメリットと注意点:
- メリット: 一時的な人材移行が可能/適応期間を設けられる
- 注意点: 同意取得は依然として必要/契約書整備が重要(出向契約書・業務委託契約など)
また、指揮命令権の所在や評価制度の違いなどがトラブルを招く原因となるため、事前に明確なルール設計が求められます。
新規雇用としての採用とその留意点
事業譲渡に際して、あえて転籍や出向ではなく、譲渡先企業が新たに従業員を採用する形式を取るケースもあります。これは形式上、「従業員が元の会社を自己都合で退職し、新会社へ転職する」という構図になります。
この場合でも、譲渡の背景事情や経緯を踏まえた配慮ある採用対応が求められます。たとえば、
- 雇用条件の明文化と書面交付(給与・勤務地・試用期間など)
- 従業員が希望しない場合の退職金・失業給付の対応
- 新しい職場文化への適応支援(研修・オリエンテーション)
「新規雇用」だからといって自由な扱いをしてよいわけではなく、労務管理上は極めてセンシティブな領域であると理解する必要があります。
実務上の比較と戦略的選択
事業譲渡に伴う従業員の移籍方法には、「転籍」「出向」「新規雇用」の3つが主に選択肢となります。それぞれに法的な性質や従業員への影響、そして企業の狙いが異なります。ここでは、各手法を文章で比較しながら、どのような場面でどの選択肢が適しているかを実務的な観点で解説します。
まず、「転籍」は、譲渡元企業との雇用契約を終了させ、譲渡先企業と新たに雇用契約を結ぶ方法です。法律的には全く別の契約となるため、従業員の同意が必須であり、移籍にともなう雇用条件の提示や労働契約の整合性が極めて重要です。
転籍は、企業として人的リソースを正式に譲渡・統合したい場合に最も適しており、事業再編を明確に進めたいときに有効な手段です。ただし、従業員にとっては雇用先が完全に変わることになるため、待遇悪化や文化の違いによる離職リスクが伴う点に配慮が必要です。
一方、「出向」は、従業員が元の企業に籍を残したまま、譲渡先企業で勤務する形態です。法律上、労働契約の主体はあくまで出向元企業であるため、雇用継続性が維持され、心理的な不安が軽減されやすいとされています。
出向は、人的資源の一時的な移行や、将来的な転籍を見据えた試用期間として機能することが多く、従業員と企業双方にとって柔軟な選択肢となります。ただし、指揮命令系統や評価制度の混在に注意が必要であり、契約書の整備や責任分担の明確化が求められます。
さらに、「新規雇用」は、従業員が一度退職し、譲渡先企業に新たに入社する方式です。この形式は、譲渡先企業が人材を選別して採用したいときや、既存の制度・待遇体系に合わせて統一したい場合に用いられます。
ただし、従業員からすれば「自己都合退職」という扱いになるため、雇用保険や退職金の面で損をするリスクがあり、企業としてはその点のケアが求められます。また、新たな職場環境に馴染めるかどうかという適応課題もあるため、制度設計だけでなく受け入れ側の文化的配慮やフォローアップ体制も重要です。
実務的には、これらの手法を単独で使用するのではなく、状況に応じて併用することで、より円滑な人材移行が可能になります。たとえば、まずは出向という比較的ハードルの低い方法で従業員を受け入れ、その後に本人の希望や業務適応状況を見て、転籍へと切り替える「段階的移行モデル」は、多くの成功事例で採用されています。
このように、事業譲渡における従業員の移籍は、法的・心理的・実務的観点をバランスよく踏まえたうえでの戦略的判断が不可欠です。従業員の納得と安心を得ながら、事業の一貫性を保つためには、画一的な対応ではなく、個別事情に応じた柔軟かつ計画的な移行プロセスの構築が求められます。
労働条件の変更と同意取得──実務対応と注意点
労働条件の変更が必要となる背景
事業譲渡に伴って従業員が譲渡先企業へ転籍または新規雇用される場合、労働条件に一定の変更が発生することは避けられません。たとえば、以下のような項目が対象になります。
- 給与体系や賞与支給のタイミング
- 勤務時間・休憩時間・休日制度
- 勤務地や転勤の有無
- 役職や業務内容
- 福利厚生(退職金制度、社内制度など)
従業員の立場から見れば、これらは生活に直結する重要な要素であり、変更によって不利益が生じると感じた場合、転籍に同意しない選択もあり得ます。したがって、企業側は安易な一方的変更を避け、慎重に条件調整と説明を行う必要があります。
労働条件の「不利益変更」とは何か
労働契約法では、使用者が労働条件を変更する際、「合理的な理由」がなければ不利益変更は認められないとされています。 つまり、企業が一方的に給与を減額したり、勤務時間を延ばしたりといった措置を取る場合、労働者の個別同意または就業規則の変更手続きが必要となります。
同意取得の方法とポイント
労働条件の変更を伴う移籍を実現するためには、以下のようなステップで個別同意を取得するプロセスが必要です。
- 就業条件の提示(書面化)
労働条件通知書や新雇用契約書を用いて、給与・勤務形態・福利厚生などを明確に記載する。
- 説明会や個別面談の実施
対象従業員に対して、変更の背景や意図、内容を丁寧に説明し、質疑応答の場を設ける。
- 本人による署名・押印(または電子同意)
納得のうえで同意を得た証拠として、署名入りの書面または電子記録を残す。
- 同意取得後の社内通知と人事システム反映
正式な合意に基づき、給与計算や社会保険手続きなどの実務に反映する。
とくに注意すべきは「説明不足による不信感」です。従業員にとって不利益に映る変更がある場合は、代替措置(例:一時的な加算手当、試用期間の短縮、業績連動型賞与の導入など)を提示し、理解を得る工夫が重要です。
同意が得られなかった場合の対応
すべての従業員が必ずしも同意するとは限りません。とくに、待遇が低下する・勤務地が遠方になる・企業風土が合わないと感じる場合などは、本人の判断で転籍を拒否することもあります。
このような場合の企業側の対応としては
- 従業員に残留を促す(譲渡対象から外す)
- 退職を前提とした個別調整(退職金の上乗せや再就職支援など)
- 期間を設けた出向という代替措置を提案する
などが考えられます。
ただし、いずれの対応も「強制はNG」です。法的なトラブルや労使紛争を避けるためにも、あくまで当事者間の協議と合意形成をベースに進めるべきです。
事業譲渡に伴う雇用関連書類の整備──転籍・出向・雇用契約の実務対応
書類整備の重要性とリスク回避の基本
事業譲渡における従業員の移籍は、単なる人の移動ではなく、「契約関係の再構築」とも言えます。この再構築が適切に行われていない場合、以下のような法的リスクが発生する可能性があります。
- 労働条件の食い違いによるトラブル(例:給与や勤務時間の誤解)
- 社会保険・労働保険手続きの不備
- 従業員からの不当解雇・労働契約違反の申立て
- 雇用関係の不存在を主張されることによる損害賠償請求
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、書類の正確性・網羅性・法的整合性が極めて重要です。特に転籍や新規雇用といったケースでは、全ての手続きを“証拠が残る形で”行うことが求められます。
転籍に必要な主な書類
転籍の場合、労働契約を新たに結び直す必要があるため、以下の3点セットの書類整備が必須です。
① 転籍同意書
従業員が自発的に転籍することに同意した旨を記録した書面。以下を明記します。
- 現在の勤務先と転籍先の名称
- 転籍日(契約終了日と新契約開始日)
- 雇用契約が切り替わることへの理解と同意
② 新雇用契約書(または労働条件通知書)
譲渡先企業との間で結ばれる正式な雇用契約。以下の基本条件を記載します。
- 賃金、労働時間、休日、勤務地、職務内容
- 雇用形態(正社員・契約社員など)
- 試用期間の有無と内容
- 就業規則や懲戒規定の適用範囲
③ 秘密保持・競業避止に関する誓約書(必要に応じて)
譲渡元・先の事業領域が競合している場合、情報漏洩リスクに備えてあらかじめ取り交わしておくことが望ましい書類です。
出向に必要な主な書類
出向の場合は、基本的に雇用契約は出向元に残るため、以下の書類が中心となります。
① 出向契約書(企業間契約)
出向元と出向先の間で締結する法人間契約です。主に以下を記載。
- 出向の期間
- 給与負担(どちらの企業がどこまで負担するか)
- 業務内容と指揮命令系統
- 責任の所在(労災、トラブル時の対応)
② 出向通知書・同意書(従業員向け)
従業員に対して出向の開始と条件を通知し、同意を得る書類です。特に出向期間や勤務地、処遇変更の有無などが明示されている必要があります。
新規雇用の場合の注意点
従業員を新規雇用として受け入れる場合でも、通常の採用とは異なる配慮が必要です。以下の書類整備が基本となります。
- 雇用契約書(試用期間・給与・社保・退職金の明記)
- 労働条件通知書(法定項目の網羅)
- 前職との関係性を整理した誓約書(例:営業秘密保持など)
- 離職票や源泉徴収票の取得と事務手続き(譲渡元との連携)
特に、従業員が「元いた会社の一部が新会社に移る」という感覚を持っている場合には、「新会社との契約は新たに発生すること」を明確に伝える必要があります。
書類整備を支える社内体制
これらの書類作成・回収・保管をスムーズに行うには、次のような社内体制の構築が重要です。
- 労務・人事・法務が連携したプロジェクト体制
- 書類テンプレートの統一と法務レビューの実施
- 電子契約(クラウドサイン等)の導入による効率化
- 従業員への定期的なフォローアップと説明会の開催
成功事例・失敗事例に学ぶ従業員対応のリアルと教訓
成功事例①:段階的出向によるスムーズな移行
ある製造業のM&Aでは、国内の部品メーカーA社が欧州大手B社に事業譲渡を行いました。譲渡対象には製造ラインとともに約80名の従業員が含まれており、転籍を伴うスキームが課題となっていました。
背景と課題
譲渡先のB社はグローバル企業であり、社内言語や管理体制が大きく異なっていたことから、従業員の多くが「本当にやっていけるのか」「英語での報告体制についていけるのか」といった強い不安を抱いていました。加えて、地方都市にあるA社工場と、B社の管理部門が東京にあるという物理的距離も心理的ハードルを高める要因でした。
対応策
A社とB社は以下のような三段階移行ステップを設定しました。
- 在籍出向による「試行期間」(3ヶ月)
従業員は雇用元をA社に残しつつ、B社の業務システムやチームに実際に加わってもらう方式。給与はA社が全額負担。
- 適応支援制度の導入
出向期間中に語学研修、労務相談窓口、外部キャリアカウンセリングなどを提供し、不安の可視化と対応に注力。
- 希望者のみ転籍へ
出向終了後に個別面談を行い、同意を得た従業員のみ転籍契約を締結。条件差異を最小化するための交渉余地も残した。
成果と教訓
結果として、80名中72名が転籍に同意。退職者6名のうち3名は定年退職が近かったため、実質的な転籍拒否はわずか3名。出向中に従業員が自ら新たな職場環境を体験し、納得した上で意思決定できたことが、円滑な人材移行につながりました。
成功事例②:誠実な情報開示で信頼を獲得
あるIT企業C社は、大手システム開発企業D社へ開発部門を譲渡する形で事業再編を行いました。譲渡対象となったのは40代以上の中堅エンジニアが多い開発部門で、全体で45名。情報感度が高く、自分のキャリアへの影響を特に気にする層でした。
課題
- エンジニア職の人材流動性が高いため、雇用不安が高まると即時離職につながる
- 年齢的にも再転職リスクを避けたい中堅層が多く、対応を誤るとリテンションに失敗する
対応策
- M&A契約締結前から、「プロセス共有型説明会」を段階的に開催
- 人事担当が社内チャットでFAQ掲示板を開設し、社員の声を可視化
- 秘密保持契約の範囲内で最大限の情報開示を行い、移籍後の制度、評価、給与の変化を明確に提示
成果
- 45名全員が転籍に同意。さらに6ヶ月後のフォロー調査で、定着率98%という非常に高い水準を記録
- 「裏がないことが伝わった」「早期から誠実な姿勢で説明してくれた」といった声が多く寄せられた
失敗事例①:突然の通告で従業員の大量離職
反面教師となる事例として、ある物流業E社が行った事業譲渡では、従業員対応を軽視したため、大きな混乱を招きました。
問題の構造
- 事業譲渡を突如メールで通告し、翌週の月曜までに転籍同意書へのサインを求めた
- 新勤務先では勤務地変更(片道90分増)と給与減額(年収30万円減)が発生
- 社内に「不満相談窓口」や「質問受付体制」が存在せず、現場の上長も情報を知らされていなかった
結果
- 180名中78名が転籍を拒否し、事業継続が困難に
- 一部従業員が労働組合と連携して記者会見を行い、企業イメージが毀損
- 引継ぎ業務も不完全に終わり、譲渡先でもオペレーションが混乱
失敗事例②:書類不備による法的トラブル
G社では、事業譲渡後に労働条件の食い違いが表面化し、トラブルが発生しました。
実際の不備
- 転籍同意書には「年俸制」の明記があったが、新雇用契約書では月給制に
- 勤務地が変更される旨を、雇用条件通知書には書かずに口頭のみで伝達
- 労働基準監督署に従業員が相談した結果、「同意無効」の判断が下された
教訓
- 同意書・契約書・雇用条件通知書の整合性チェックが不可欠
- 弁護士・社労士のダブルレビューが必要な場面でも、「急ぎだから」と内部対応で済ませたのが原因
- 書面を交わしていても、説明の記録がなければ無効となるケースがある
成功と失敗から得られる教訓
これらの事例から導かれる教訓は、実務担当者・経営陣にとって極めて重要です。
◎ 1. 説明責任と透明性が最も重要
情報がないと、人は最悪のケースを想定します。だからこそ、丁寧な説明、情報開示、Q&Aの場が不可欠です。
◎ 2. 「段階的移行」が従業員の不安を和らげる
出向→転籍、面談→同意といったステップを設けることで、心理的ハードルを下げることができます。
◎ 3. 書類は“合意の証拠”として機能させる
単なる形式で終わらせず、整合性・説明記録・第三者レビューの3点を徹底すること。
◎ 4. 感情への配慮こそ最大のリテンション策
制度や金額よりも、「大事にされている」と感じられる対応こそが信頼と定着を生みます。
労働条件の調整と契約文書の整備実務
労働条件変更の原則と注意点
事業譲渡において従業員を引き継ぐ際、「労働条件が変更されるかどうか」は最もセンシティブなテーマの一つです。企業側としては、譲渡前と同水準の条件を維持したい一方、譲渡先企業の制度と完全に一致するとは限らないため、調整が必要となります。
労働条件変更の基本原則:
- 従業員本人の同意が必須
- 合意ない労働条件の不利益変更は原則不可(労働契約法第9条)
- 就業規則と雇用契約書の整合性が必要
たとえば、勤務時間のシフト、評価制度の違い、残業代の支払基準などは、譲渡元と譲渡先で制度設計が異なることが多く、その差異をどう埋めるかが実務上の論点となります。
注意点:
- 「名目は同じだが内容が違う」制度(例:役職手当、賞与評価基準)に要注意
- 同意取得プロセスは、形式的な署名だけでなく説明責任も伴う
- 書面での条件通知と口頭説明が食い違わないよう、ダブルチェックを徹底する
雇用契約書・転籍同意書・条件通知書の違いと整備ポイント
事業譲渡における文書整備は、企業の信頼性とコンプライアンスを支える“法的防波堤”です。特に下記3つの文書は、セットで準備する必要があります。
雇用契約書
譲渡先企業と新たに結ぶ正式な契約書であり、就業条件、給与体系、勤務地、職務内容などを明記。
- 必須記載事項:契約期間、有期/無期、就業場所、労働時間、給与、解雇規定
- 推奨対応:就業規則の適用についても言及
転籍同意書
譲渡元企業と従業員の間で交わす書面。転籍の意思を明示し、労働契約終了と再雇用への同意を示す。
- 書式には「説明を受け納得のうえ、自由意思で同意した」旨を記載
- 説明記録(面談メモ・同席者の記録など)を裏付け資料として保存
雇用条件通知書
新たな雇用契約に関する詳細情報を、労働者に対して書面で通知するもの。
- 賃金の内訳、支払方法、試用期間、手当の詳細、残業代の支払条件などを具体的に記載
- 電子化してもOKだが、本人確認と保存性が求められる
よくあるトラブルと予防策
ケース①:試用期間中の給与トラブル
→ 条件通知書に「試用期間中は別給与体系」と明記していなかったため、不利益変更とみなされ訴訟に発展。
◎ 対策: 試用期間の有無と条件差を明記する。なければ「試用期間なし」と書く。
ケース②:勤務地変更の記載漏れ
→ 転籍後に勤務地が変更となり、「合意していない」と主張され労基署から是正勧告を受けた。
◎ 対策: 「将来的に勤務地変更の可能性あり」と明記。または初期配属先を明示。
ケース③:口頭での説明と書面内容の相違
→ 面談では「年収据え置き」と説明したが、実際には賞与制度が変更され年収減に。
◎ 対策: 面談時の説明内容と書面の整合性を必ずチェック。録音や議事録を残す。
法務・人事・現場の三位一体で取り組むべき理由(文章版)
事業譲渡における従業員対応は、単なる法的手続きにとどまらず、「企業としての姿勢」として従業員に伝わる重要な局面です。だからこそ、法務・人事・現場部門が連携し、三位一体で進める体制構築が不可欠です。以下、それぞれの部門の役割と連携のポイントを、実務的な観点から解説します。
法務部門の役割:合法性とリスク回避の担保
まず法務部門は、事業譲渡に伴う文書の整備や、同意取得プロセスの合法性を担保する役割を担います。労働契約法や民法、またM&Aに付随する各種契約(譲渡契約、秘密保持契約、出向契約など)との整合性を確保し、書類の不備が後々のトラブルにつながらないようにするのが主な任務です。
とくに「転籍同意書」や「新雇用契約書」においては、文言一つの解釈次第で労使紛争につながることもあるため、曖昧さを排除し、明確で誤解のない表現に仕上げることが重要です。
また、労働条件の変更に関する説明責任を果たすための記録化(面談記録、議事録、説明スライドの保存など)も、法的リスク管理の一環として法務が主導すべき項目です。
人事部門の役割:感情面と制度面の橋渡し
一方、人事部門の役割は、書面上の手続きだけでなく、従業員の感情への配慮と、制度変更の橋渡しにあります。 人事部門が行う個別面談、説明会の設計、FAQの整備などは、従業員の安心感を醸成するうえで極めて重要です。特に転籍や勤務条件の変更が発生する場合には、「大切に扱われているかどうか」が従業員の転籍意思決定に直結します。
また、譲渡先企業との間で評価制度や福利厚生制度にギャップがある場合には、調整や補填措置の検討、納得性のある説明資料の作成を人事がリードしなければなりません。
従業員一人ひとりの人生に関わる変化であることを意識し、説明の一貫性と納得度を意識した対応が求められます。
現場部門の役割:実務の現実とギャップの可視化
そして、最も見落とされがちだが重要なのが、現場部門の関与です。現場のマネージャーやチームリーダーは、日々従業員と接しており、制度の変化が実際の業務にどう影響するか、現場感覚で理解している存在です。
たとえば「勤務地が変更になる」と書面に書かれていても、現場での対応体制が整っていなければ実際には混乱が生じます。また、異なる業務フローや文化を持つ譲渡先企業に溶け込むためには、引き継ぎ業務の精度やチーム間の橋渡しが極めて重要となります。
現場の声を無視して書類だけ整備しても、制度と運用の間にギャップが生まれ、最終的に従業員からの不信を招きかねません。だからこそ、現場部門を早期から巻き込み、「誰が何をどう引き継ぐのか」「どうすれば業務が止まらないか」を実務視点で洗い出す必要があるのです。
このように、法務がルールを整備し、人事が人に寄り添い、現場が業務を支えるという三位一体の体制を築くことが、従業員の信頼を得て事業譲渡を円滑に進める上で不可欠です。
単なる契約行為ではなく、人の感情と業務のリアルに寄り添った「実行支援型M&A」を実現するために、この連携は外せない視点だと言えるでしょう。
まとめ
事業譲渡における従業員対応は“信頼”のマネジメント
本記事では、「事業譲渡 従業員」というテーマを軸に、従業員の移籍方法(転籍・出向・新規雇用)から、法務・人事・現場の連携、そして実務対応まで網羅的に解説してきました。
ここで改めて強調したいのは、事業譲渡は単なる経営判断ではなく、“人の信頼”をいかに守るかという経営姿勢が問われる局面だということです。
- 曖昧な説明や情報不足は、不信・混乱・早期離職を招く
- 書類や手続きの形式が整っていても、“人の気持ち”が置き去りになっていれば意味がない
- 逆に、誠実で丁寧なコミュニケーションを徹底すれば、困難な移籍も「新しいスタート」として歓迎され得る
企業にとっての成長戦略であるM&Aも、それを支えるのは人の納得感と信頼関係です。法務・人事・現場が一体となり、制度と感情の両面を整備することこそが、真の成功の鍵となります。
おわりに──事業の未来は“人”に宿る
企業同士の資本移動や戦略連携は、紙の上では合理的でも、そこに「働く人の気持ち」が乗らなければ実現しません。事業譲渡とは、会社の未来をつくる選択であり、その未来を背負うのは“移籍する従業員一人ひとり”です。
「この会社に移って良かった」と思えるような移籍体験をつくること。それこそが、持続可能なM&Aの真髄であり、貴社のブランド価値を守る行為でもあります。
M&Aロイヤルアドバイザリーは、ただのM&A仲介ではなく、“人の側に立つM&A支援”をお約束します。 M&Aや経営課題に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。