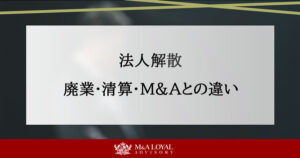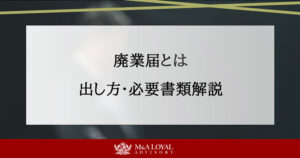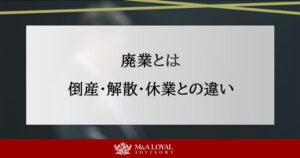閉業と廃業の違いは?手続きと回避するためのポイントを紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
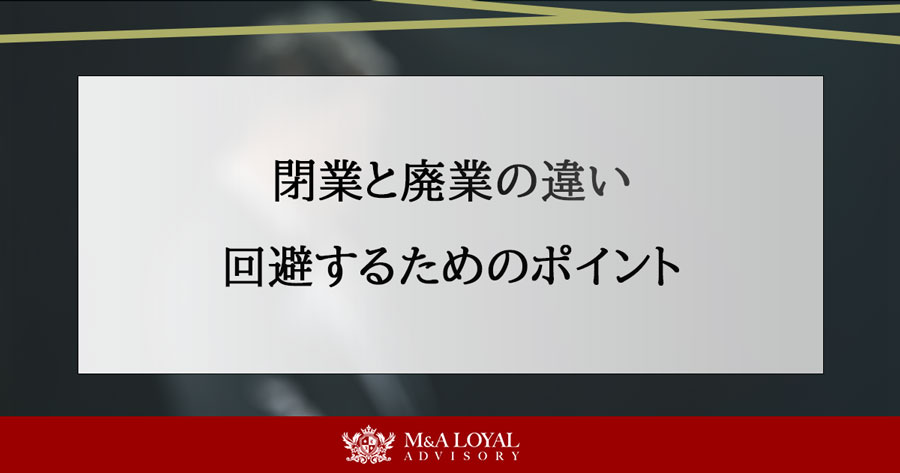
閉業と廃業の違いを理解することは経営を行う上で大切です。近年、経営者の高齢化や後継者不足により、多くの中小企業が事業継続の課題に直面しています。事業の終了を検討する際、「閉業」「廃業」「休業」などさまざまな選択肢が存在しますが、これらの違いを正確に理解している経営者は多くありません。
また、「倒産」や「解散」といった類似の概念との違いも曖昧になりがちです。本記事では、閉業と廃業の明確な違いから、それぞれの手続き方法、さらには事業継続のための廃業回避策まで、中小企業のオーナーが知っておくべきポイントを詳しく解説します。
目次
閉業と廃業の基本的な違いとは
経営者が事業の終了を検討する際、「閉業」と「廃業」という用語が使われますが、これらには明確な違いがあります。正しい理解なしに手続きを進めると、後から予期しない問題が発生する可能性があるため、まずは基本的な概念を整理しましょう。
閉業の定義と特徴
閉業とは、店舗や事業所の営業を停止することを指し、法人格そのものは存続している状態を表します。具体的には、店舗の営業を終了することや、特定の事業部門を停止することが閉業に該当します。
閉業の最大の特徴は、事業再開の可能性が残されていることです。法人登記は維持されており、必要に応じて再び営業を開始することができます。また、複数の店舗や事業を展開している企業の場合、一部の店舗や事業のみを閉業することも可能です。
税務上の取り扱いについても、閉業は一時的な営業停止として扱われるため、法人税の申告義務は継続します。ただし、実際の営業活動がない期間については、収益が発生しないため税額は最小限となります。
廃業の定義と特徴
廃業とは、会社や個人事業主が事業活動を完全に終了し、法的にも事業を消滅させることを指します。法律で厳密に定められた用語ではありませんが、一般的には事業の完全終了を意味する概念として使用されています。
廃業手続きを行うと、法人の場合は解散・清算手続きを経て法人格が消滅し、個人事業主の場合は税務署への廃業等届出書の提出により事業が正式に終了します。事業再開を考えている場合は、法人と個人事業主で異なるフローとなります。法人の場合、同じ法人を復活させることはできませんが、同じ代表者が新たに法人を設立することが可能です。個人事業主の場合、事業再開時には税務署へ開業届を再度提出することで、事業再開が可能です。
廃業の主な要因として、経営者の高齢化、後継者不足、経営環境の悪化などが挙げられます。特に近年では、コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し、自主的に廃業を選択する企業が増加している傾向にあります。
両者の使い分けと判断基準
閉業と廃業の選択は、将来の事業再開の可能性と経営者の意向によって決まります。業績悪化や市場環境の変化に対応するために営業を停止する場合は閉業を、完全に事業から撤退する意思が固まっている場合は廃業を選択することが一般的です。
判断の際に考慮すべき要素として、従業員の雇用継続の可能性、取引先との関係維持、資産の処分方法、税務上の影響などが挙げられます。特に従業員を抱えている企業の場合、閉業であれば将来的な雇用復活の可能性を残せますが、廃業では完全な雇用終了となるため、慎重な検討が必要です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



類似概念との違いを理解する
事業の終了に関連する用語は多岐にわたり、それぞれ異なる意味と手続きを持っています。経営者が適切な判断を下すためには、これらの概念を正確に理解し、自社の状況に最も適した選択肢を見極めることが重要です。
倒産との違い
倒産は債務超過や資金繰りの悪化により事業継続が不可能になった状態を指し、廃業とは発生原因と手続きが根本的に異なります。倒産の場合、債権者への対応や法的手続きが必要となり、経営者の意思だけでは解決できない複雑な状況に陥ります。
廃業は黒字経営でも経営者の判断で実行できますが、倒産は債務超過により発生します。また、廃業は基本的に自主的な選択である一方、倒産は外部からの圧力(債権者からの督促、資金調達の困難など)により余儀なくされるケースが多いのが特徴です。
手続き面では、廃業の場合は通常の解散・清算手続きで対応可能ですが、倒産の場合は破産、民事再生、会社更生などの法的倒産手続きや、債権者との協議による私的整理が必要となります。これらの手続きは時間と費用がかかり、経営者の負担も大きくなります。
休業との違い
休業は事業活動を一時的に停止することを指し、閉業よりもさらに短期的な営業停止を意味します。休業の場合、従業員との雇用関係は維持され、事業再開時には速やかに営業を復活させることが前提となっています。
休業と閉業の最大の違いは、事業再開までの期間と準備状況にあります。休業は数日から数ヶ月程度の短期間を想定しており、設備や在庫、従業員などの事業資源を維持したまま営業を停止します。一方、閉業はより長期的な営業停止を想定し、設備の処分や従業員の解雇なども検討される場合があります。
税務上の取り扱いも異なります。休業の場合は、税務署や労働基準監督署、各自治体に「休業届」の提出など必要な手続きを行うことで完了します。一方、廃業の場合は、会社・個人事業主ともに税務署への届け出が必要です。
解散・清算との違い
解散と清算は法人の廃業手続きにおける具体的なプロセスを指します。解散は法人が事業活動を停止し清算手続きに入ることを決定する段階で、清算は実際に資産を処分し債務を整理して法人格を消滅させる段階です。
廃業が事業終了の一般的な概念であるのに対し、解散・清算は法的手続きの具体的な名称です。株式会社の場合、株主総会での特別決議により解散を決定し、清算人を選任して清算手続きを進めます。この過程で債権者保護手続きや財産の処分、税務申告などを行い、最終的に清算結了登記により法人格が消滅します。
個人事業主の場合は解散・清算という概念はなく、税務署への廃業等届出書の提出により廃業手続きが完了します。このように、事業形態によって廃業の具体的な手続きは大きく異なるため、自社の状況に応じた適切な手続きを選択することが重要です。
廃業・閉業の手続き方法と流れ
廃業や閉業の手続きは事業形態によって大きく異なり、それぞれ複雑なプロセスを経る必要があります。手続きを誤ると法的・税務上の問題が発生する可能性があるため、事前に詳細な流れを理解しておくことが重要です。
法人の廃業手続き(解散・清算)
法人の廃業は解散と清算という二段階のプロセスを経て完了します。まず解散の準備段階では、取締役会での解散決議の検討、株主への事前説明、債権債務の調査などを行います。これらの準備が整った後、株主総会において特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)により解散を正式に決定します。
解散決議後は清算人の選任を行い、解散から2週間以内に法務局で解散登記を申請します。同時に税務署、都道府県、市町村への解散届出書の提出、社会保険事務所への適用事業所全喪届の提出、労働基準監督署やハローワークへの各種届出も必要です。
清算段階では、債権者保護手続きとして官報公告と個別催告を実施し、債権者に対して2ヶ月以上の期間を設けて債権の申出を求めます。並行して財産目録と貸借対照表を作成し、会社の資産と負債を明確にします。その後、会社財産の換価処分、債務の弁済、残余財産の株主への分配を行い、決算報告書を作成して株主総会の承認を得た後、清算結了登記を申請して法人格が消滅します。
個人事業主の廃業手続き
個人事業主の廃業手続きは法人と比べて比較的簡素ですが、税務上の手続きを適切に行うことが重要です。廃業日から1ヶ月以内に税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出する必要があります。
消費税の課税事業者である場合は、消費税の事業廃止届出書の提出も必要です。また、青色申告を行っていた場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書も提出します。
給与支払事務所等の開設届出書を提出していた場合は、給与支払事務所等の廃止届出書を提出し、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出していた場合は、その取りやめ届出書も必要です。都道府県税事務所や市町村にも個人事業税や住民税に関する廃業届を提出する必要があります。
閉業時の手続きと注意点
閉業の場合は事業再開の可能性を残すため、廃業ほど厳格な手続きは必要ありませんが、適切な届出と管理が重要です。税務署には休業届や営業停止に関する届出を提出し、営業を停止している期間中も法人税の申告義務は継続することを理解しておく必要があります。
従業員を雇用している場合は、雇用調整助成金などの活用を検討し、可能な限り雇用の維持に努めることが求められます。また、取引先への適切な説明と今後の取引に関する調整も重要で、事業再開時の円滑な取引復活のためにも丁寧な対応が必要です。
設備や在庫の管理についても、長期間の保管による劣化や盗難のリスクを考慮し、適切な保管方法や保険の継続について検討する必要があります。特に特殊な設備や高価な機械がある場合は、専門業者による保管サービスの利用も検討すべきでしょう。
近年の廃業動向と背景要因
日本の中小企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、廃業を選択する企業数も増加傾向にあります。この現状を正確に把握することは、経営者が自社の将来を検討する上で重要な判断材料となります。
統計データから見る廃業の現状
東京商工リサーチの調査によると、休廃業・解散件数は2015年の37,548件から2024年には62,695件へと大幅に増加し、過去最多を記録しました。これは中小企業の廃業が深刻な社会問題となっていることを示しています。
一方で、倒産件数は2015年の8,812件から2024年は1万144件と増加し、11年ぶりに1万件を超えていますが、長期的な視点で見ると減少傾向にあります。これは政府の資金繰り支援策や金融機関の柔軟な対応により、資金難による倒産は抑制されている一方で、経営者の自主的な判断による廃業が増加していることを意味します。
業種別に見ると、小売業、建設業、製造業での廃業が特に多く、これらの業界では後継者不足や市場環境の変化が深刻な影響を与えています。地域別では、地方圏での廃業率が高く、人口減少や経済活動の縮小が廃業増加の背景となっています。
※参考
経営者高齢化と後継者不足問題
廃業増加の最大の要因は経営者の高齢化です。2024年の帝国データバンクの調査では、中小企業経営者の平均年齢は60.7歳であり、34年連続で最高年齢を更新しています。多くの経営者が引退を検討する年齢に達している一方で、適切な後継者が見つからないケースが増加しています。
後継者不在の理由として、子どもの経営への関心の低さ、事業承継に伴う個人保証の問題、承継時の税負担の重さなどが挙げられます。また、従業員や外部からの後継者候補についても、経営責任の重さや個人保証への不安から承継を躊躇するケースが多く見られます。
この問題に対し、政府は事業承継税制の拡充や事業承継・引継ぎ支援センターの設置など様々な支援策を講じていますが、まだ十分な効果を上げていない状況です。経営者には早期からの事業承継準備と、多様な選択肢の検討が求められています。
コロナ禍の影響と今後の見通し
新型コロナウイルス感染症の拡大は、多くの中小企業に深刻な影響を与え、廃業を検討する企業の増加要因となりました。特に飲食業、宿泊業、小売業などの対面サービス業では、売上の大幅な減少により事業継続が困難になった企業が多数発生しました。
政府の各種支援策により一時的に廃業件数の増加は抑制されましたが、支援策の終了に伴い、今後は廃業件数の再増加が懸念されています。特に、持続化給付金や雇用調整助成金などの支援を受けて事業を継続してきた企業の中には、根本的な経営改善が進んでおらず、支援終了後に廃業を余儀なくされるケースが増加する可能性があります。
今後の見通しとしては、デジタル化の遅れや働き方改革への対応が困難な企業、事業承継の準備が整わない企業を中心に、廃業件数の増加が続くと予想されます。このような状況の中で、経営者には早期の経営改善と事業承継準備、さらには廃業回避のための様々な選択肢の検討が求められています。
廃業を回避するための具体的な対策
廃業を検討している経営者にとって、事業を継続し発展させるための選択肢を知ることは極めて重要です。特にM&Aや事業承継は、従業員の雇用を守り、これまで培ってきた事業価値を最大限に活用できる有効な手段として注目されています。
M&Aによる事業継続の可能性
M&Aは廃業を回避し事業を存続させる最も有効な手段の一つであり、売却により創業者利益を確保しながら従業員の雇用を維持できます。買収企業にとっても、既存の顧客基盤や技術、人材を一括で獲得できるメリットがあるため、適切な条件でのマッチングが実現しやすい環境が整っています。
M&Aを成功させるためには、まず自社の強みと価値を正確に把握することが重要です。独自の技術や特許、優秀な人材、安定した顧客基盤、良好な立地条件など、買収企業にとって魅力的な要素を明確にし、適切にアピールする必要があります。
また、M&Aの準備段階では、財務諸表の整備、法的リスクの洗い出し、従業員との調整など、デューデリジェンス(買収前調査)に耐えうる企業体制の構築が必要です。これらの準備を怠ると、買収価格の減額や取引の中止につながる可能性があるため、専門家のサポートを受けながら着実に進めることが重要です。
事業承継の選択肢と準備
事業承継には親族内承継、従業員承継、第三者承継の三つの選択肢があり、それぞれ異なる準備とアプローチが必要です。親族内承継の場合は、後継者の経営能力の育成と相続税対策が重要で、事業承継税制の活用により税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
従業員承継では、後継者となる従業員の選定と育成、株式取得資金の調達方法が課題となります。経営者保証の引継ぎ問題や個人資産による株式購入の負担軽減のため、MBO(マネジメント・バイアウト)の活用も検討すべき選択肢です。
第三者承継はM&Aと重複する部分もありますが、地域密着型の企業では同業他社や取引先企業への承継も有効な選択肢となります。いずれの方法を選択する場合も、5年から10年程度の準備期間を設け、段階的に権限移譲を進めることが成功の鍵となります。
政府・自治体の支援制度活用
政府は中小企業の事業承継を支援するため、様々な制度を整備しています。事業承継・引継ぎ支援センターでは、公認会計士や中小企業診断士などの専門家による無料相談を受けることができ、M&Aのマッチング支援も行っています。
事業承継・引継ぎ補助金では、専門家への報酬や設備投資費用の一部を補助しており、特にM&Aを活用した事業承継では最大800万円の補助を受けることができます。また、事業承継税制により、後継者が承継する株式に係る贈与税や相続税の納税が猶予され、一定の条件を満たせば免除される制度も整備されています。
日本政策金融公庫では事業承継・M&A資金の融資制度があり、後継者の株式取得資金や設備投資資金を低利で調達することができます。これらの支援制度を有効活用することで、廃業を回避し事業継続を実現できる可能性が大幅に高まります。
まとめ
閉業と廃業の違いを正確に理解することは、経営者が適切な選択を行う上で重要です。閉業は事業再開の可能性を残した一時的な営業停止であり、廃業は事業の完全終了を意味します。それぞれ異なる手続きと影響があるため、自社の状況と将来の展望を慎重に検討した上で判断する必要があります。
近年の廃業件数増加の背景には、経営者の高齢化と後継者不足という構造的な問題があります。しかし、M&Aや事業承継といった選択肢を活用することで、廃業を回避し事業価値を最大化することが可能です。政府も様々な支援制度を整備しており、これらを有効活用することで事業継続の可能性を大幅に高めることができます。
事業の将来に悩む経営者は、専門家のアドバイスを受けながら最適な選択肢を見極めることが重要です。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、中小企業のM&Aと事業承継について豊富な経験と専門知識を持つアドバイザーが、お客様の状況に応じた最適なソリューションをご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。