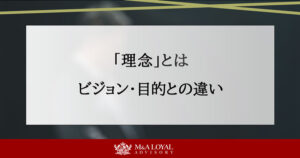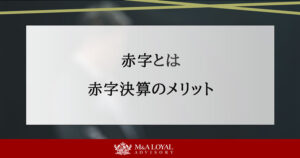5W1Hとは?意味と使い方、5W2Hや6W2Hとの違いを徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型

ビジネスシーンなどで「説明がうまくまとまらない」といった場面で、基本フレームワーク「5W1H」が役立ちます。
情報の抜け漏れを防ぎ、論理的に伝えるためのベースとして、ビジネス文書からプレゼン、問題解決まで幅広く活用されています。
本記事では、5W1Hの基本構造から、実践的な活用方法や他のフレームワークとの違いまで分かりやすく解説します。
目次
5W1Hとは?基本的な意味と使い方を解説
まず、5W1Hの概要を紹介します。
5W1Hの概要
5W1Hとは、物事を整理したり、説明を分かりやすくしたりするための基本的フレームワークです。
フレームワークとは、物事を整理して考えるための「枠組み」や「考え方の型」を指します。複雑な課題や情報を整理する際に、どんな順序や観点で考えれば良いかを示してくれる「道しるべ」のようなものです。
5W1Hは、英語の疑問詞 「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」 の頭文字を取った言葉で、情報を漏れなく整理するための手法として、ビジネス・教育・報道など幅広い分野で使われています。
5W1Hに「Which」は含まれないので注意
「5W1H」と聞くと、「Which(どれ)」も含まれるのでは?と思う方がいますが、含まれません。
「Which」も英語の疑問詞の一つですが、5W1Hは「情報を整理する」「説明を構造化する」ためのフレームワークです。「Which」は複数の選択肢から特定のものを選ぶ際に使われる表現であり、整理や構成を目的とした5W1Hの考え方とは異なります。混同しやすいポイントなので、注意しましょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



5W1Hを構成する単語
5W1Hを構成する単語は、次のとおりです。
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(だれが)
- What(なにを)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
それぞれを解説します。
When(いつ)
「When(いつ)」は、出来事の時間軸を整理し、全体像を時系列で理解するための基礎となる要素です。時間・日付・季節・期限などを具体的に示すことで、計画や説明に具体性を持たせます。
ビジネスでは、「いつ実施するのか」「いつまでに成果を出すのか」といったスケジュール管理や目標設定に関わる要素として重要です。文章や報告書で使用する場合も、「いつ起こったのか」を明確にすると、読者に状況が伝わりやすいです。
Whenは、あらゆる情報を整理する上で「時間」という軸を与える、5W1Hの中でも欠かせない要素です。
Where(どこで)
「Where(どこで)」は、出来事や行動が「どの場所で起こるのか」を明確にするための問いです。物理的な場所だけでなく、環境・組織・媒体など、行動が行われる「場」を特定することで、内容に具体性を与えます。
ビジネスの場面では、「どの店舗で開催するのか」「どの市場で展開するのか」「どの部署が担当するのか」など、実施場所や担当範囲を定義する要素として重要です。また、文章や報告書では「どこで発生した出来事なのか」を示すことで、読者が状況を正確にイメージしやすくなります。
Whereは、行動や出来事の「空間的な位置付け」を明確にし、全体の構成を立体的に理解するための重要な視点です。
Who(だれが)
「Who(だれが)」は、出来事や行動の主体を特定するための問いです。
「誰がその行動を起こしたのか」「誰が関係しているのか」を明確にすることで、責任の所在や関与する人物・組織の役割を整理できます。
ビジネスでは、「誰が担当するのか」「どのチームが実施するのか」「顧客は誰なのか」など、関係者を明確化することが成功の鍵です。また、報告書や企画書などの文章でも行動の主体をはっきり示すことで読者が内容を正しく理解しやすくなります。
Whoは、出来事の中心に「人」や「組織」という視点を置くことで、計画や説明に責任と具体性をもたらす要素です。
What(なにを)
What(なにを)は、出来事や行動の内容や対象を明確にするための問いです。
「何を行うのか」「何を伝えたいのか」「何が問題なのか」といった点を整理することで、目的や課題の本質を把握できます。
ビジネスでは、「何を提供するのか(商品・サービス)」「何を達成するのか(成果・目標)」を定義することが、プロジェクトの方向性を決める上で欠かせません。また、文章作成においても「何について書かれているのか」を明確にすると、読者に伝わるメッセージが一貫し、説得力が高まります。
Whatは、5W1Hの中心ともいえる要素であり、行動や目的の「核」を示す視点として最も重要な問いの一つです。
Why(なぜ)
「Why(なぜ)」は、行動や出来事の目的・理由・背景を明確にするための問いです。
「なぜその行動をとるのか」「なぜその問題が起きたのか」といった根拠を明らかにすることで、行動の意味や方向性を理解できます。
ビジネスでは、「なぜその施策を実施するのか」「なぜその戦略を選ぶのか」を問うことで、意思決定の裏付けや説得力を高められます。また、文章やレポートでも「なぜそれが重要なのか」を明確に書くことで、読者が納得しやすくなります。
Whyは、単なる事実を伝えるだけでなく、目的や意図を示してストーリーに深みを与える要素です。
How(どのように)
「How(どのように)」は、行動や目的をどの手段・方法で実現するのかを明確にするための問いです。
「どのように実行するのか」「どのように解決するのか」を考えることで、計画の実現性やプロセスを具体化できます。
ビジネスの場面では、「どのように販売を拡大するのか」「どのように顧客満足度を上げるのか」など、実行戦略やアプローチの設計に深く関わります。また、文章やプレゼンテーションでも「どのように進めるのか」を示すことで、相手に理解されやすく、行動を促すメッセージになります。
Howは、5W1Hの中で「実行の具体策」を担う視点であり、計画や説明を「行動に落とし込む」ための重要な要素です。
5W1Hを活用するメリット
5W1Hを活用するメリットは、次のとおりです。
- 思考の整理ができる
- 情報の漏れを防げる
- 行動に繋がる計画や解決策を導ける
それぞれを詳しく解説します。
5W1Hで思考の整理ができる
5W1Hを使うと、複雑な情報や漠然としたアイデアを体系的に整理できる点がメリットです。
「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように」という6つの視点を順に当てはめることで、考えるべき要素が明確になり、思考の抜けや重複を防げます。
特に企画書や報告書の作成時には、目的(Why)・内容(What)・実行方法(How)を整理することで、論点の流れがはっきりし、読んだ人が理解しやすい構成にまとめられます。
また、自分の頭の中にある情報を5W1Hの枠に沿って「見える化」することで、思考の偏りに気づいたり、曖昧だった部分を具体化できます。
5W1Hで情報の漏れを防げる
5W1Hを意識して整理すると、重要な情報の抜け落ちを防げます。
特に、会議の議事録や報告書などでは、一つの視点が欠けるだけで情報の正確性が損なわれることがあるため、5W1Hを使うことで全体の整合性を保つことが重要です。例えば、問題を分析するときに「Why(なぜ)」を見落とすと原因が不明瞭になり、「How(どのように)」を省くと対策が曖昧になります。六つの要素を順に確認すれば、説明の精度が高まり、誰が見ても理解できる構成を作れます。
5W1Hは、正確で信頼性の高い伝達や報告を実現するための有効なフレームワークです。
行動につながる計画や解決策を導ける
5W1Hは、思考を整理するだけでなく、具体的な行動計画を立てるための実践的なツールとしても役立ちます。
「なぜ(Why)」で目的を確認し、「何を(What)」で課題や目標を定め、「どのように(How)」で手段を明確にすることで、実行可能なアクションプランを構築できます。
また、トラブルや課題が発生した際にも、5W1Hを使って「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どうした」と整理すれば、原因の特定から再発防止策の立案までを効率的に行えます。このプロセスを踏むことで、感覚的な判断に頼らず、論理的かつ再現性のある問題解決が可能になる点もメリットです。
5W1Hは、考えるためのフレームであると同時に、行動を起こすための指針であるといえます。
5W1Hを活用するデメリット
5W1Hを活用するデメリットは、次のとおりです。
- 柔軟な発想を妨げになる
- 情報量が多くなり、冗長な印象を与える
- 表面的な整理にとどまり、深い分析がしづらい
それぞれを詳しく解説します。
仕事上で柔軟な発想を妨げる
5W1Hは「考える順序」を整えられる一方で、枠組みがあるがために思考の自由度を奪うことがあります。
特にアイデア発想や企画立案など、創造性が求められる場面では注意が必要です。先に枠を決めてしまうと、既存の考え方に縛られやすく、論理的だけど面白くない内容になってしまうこともあります。
柔軟な発想を引き出すには、まず自由に考え(発散)、後から5W1Hで整理(収束)する順番が効果的です。
情報量が多くなり、冗長な印象を与える
5W1Hは六つの要素(Who・What・When・Where・Why・How)を基に構成されているため、一度に伝える情報が多くなりやすい難点もあります。
全ての要素を盛り込みすぎると話が長くなり、聞き手が情報を整理しきれなくなることも珍しくありません・特にビジネスの場面では、限られた時間で要点を伝える必要があるため、目的と相手の理解度に応じて要素の取捨選択が大切です。
六つの要素を全て使うことにこだわらず、必要な情報だけを選び抜くことで、内容がより簡潔になり、受け手の理解度も高まります。
表面的な整理にとどまり、深い分析がしづらい
5W1Hは、「なにが」「なぜ」「どうやって」を整理するのに有効な手法ですが、複雑な問題の本質を深く掘り下げる分析には限界があります。
例えば、原因分析で「Why(なぜ)」を一度だけ考えて終えてしまうと、根本的な要因を見落とす恐れがあります。また、複数の要因が絡み合う課題では、5W1Hだけでは要素間の関係性や構造を十分に可視化できません。
そのため、問題の核心に迫りたいときは、要因を階層的に整理する「ロジックツリー」などといったフレームワークを併用すると効果的です。5W1Hを「整理の出発点」として、深掘りには他の分析手法と組み合わせて活用しましょう。
5W1Hを使う場面
5W1Hを使う場面は、次のとおりです。
- コミュニケーション(メール・プレゼンなど)
- マーケティング戦略
- アイデア想起
- 問題解決
それぞれを詳しく解説します。
コミュニケーション(メール・プレゼンなど)
メールや報告書、プレゼンテーションなどで5W1Hを意識すると、誰にでも伝わる論理的な構成を自然に作れます。
例えば、ビジネスメールで「だれが」「なにを」「いつまでに」を整理して伝えるだけで、返信の遅延や作業ミスを防げます。また、プレゼン資料を作成する際にも、5W1Hの流れで構成すると、ストーリーに一貫性が生まれ、聞き手が内容を理解しやすくなる点が特徴です。
伝達の目的と受け手の理解度を踏まえて要素を取捨選択すると、より簡潔で説得力のあるコミュニケーションを実現できます。
マーケティング戦略
マーケティングにおいて5W1Hは、戦略立案や顧客分析の基盤をつくるフレームワークとして非常に有効です。
ターゲットの設定から商品設計、販促手段の選定まで、六つの要素を当てはめることで、論理的で抜けのないマーケティング戦略を構築できます。また、マーケティング施策の効果測定や改善の際も、5W1Hの要素に沿って振り返ることで、どの部分に課題があるのかを特定しやすいです。
さらに、チームで企画を共有する際にも5W1Hは有効です。複数人で議論する場面では、意見の方向性がバラつきやすいものですが、5W1Hで整理して共有することで、共通認識を持った意思決定がスムーズに進みます。
アイデア想起
新しい企画やサービスを生み出すとき、5W1Hは発想を整理し、形にするための強力なフレームワークとして機能します。
特にブレインストーミングや企画会議の場では、出されたアイデアを5W1Hで整理することで、「実行できる企画」と「思いつきレベルの案」を明確に分けられます。
さらに、Why(なぜ)を中心に深掘りすることで、アイデアの意義や目的を明確にでき、本質的な価値のある提案へと発展させられます。一方で、How(どのように)を意識すれば、現実的な実行プランやプロトタイプ構想にもつなげられる点が5W1Hの強みです。
問題解決
問題解決の場面では、5W1Hは原因の特定から対策立案、実行までの全工程を論理的に整理する思考ツールとして役立ちます。
特にWhy(なぜ)の問いを繰り返すことで、表層的な対処ではなく根本的な原因解明につながる点が重要です。さらに、チームで課題を共有する際も、5W1Hの形式でまとめることで、情報共有の精度と解決スピードが格段に向上します。曖昧な説明が減り、再発防止策や責任の所在が明確になるため、組織的な問題対応にも有効です。
また、トラブル対応やクレーム処理などの緊急対応時にも、5W1Hで現場情報を整理すれば、上層部への報告や意思決定が迅速に行えます。
5W1Hの例
5W1Hの例を紹介します。
ビジネスメール
ビジネスメールでは、限られた文字数の中で「目的」「背景」「次の行動」を明確に伝えることが重要です。
メールの例:
営業企画部の中村です。明日10時より本社会議室Aにて開催される営業定例会議で、4月度の販売実績を口頭で報告いたします。売り上げ状況を共有し、今後の販売戦略を検討する予定です。資料は本日中に共有フォルダーへアップロードしますので、事前にご確認ください。ご意見や追加データのご要望があれば、会議前までにお知らせください。
- Who(誰が): 営業企画部の中村
- What(何を): 4月度の販売実績
- When(いつ): 4月12日10時
- Where(どこで): 本社会議室A
- Why(なぜ): 売り上げ状況を共有し、今後の販売戦略を検討するため
- How(どのように): 口頭報告
このように6つの要素を意識して構成すると、内容が整理され、伝えたいことが正確に届くメールの作成が可能です。また、5W1Hで情報を整理する習慣を持つと、件名や本文の構成にも一貫性が生まれます。
ビジネスでは、上司・取引先・チームメンバーなど、相手によって求められる情報が異なりますが、5W1Hを使えば、どの相手にも抜け漏れのない、行動につながるコミュニケーションが可能です。
新製品のプレゼン
プレゼンなどで相手の共感を引き出したい場合は、「Why(なぜ)」→「How(どのように)」→「What(何を)」の順に伝えることが効果的です。また、When・Where・Whoの情報は、Whatの説明に補足として加えることで、内容がより具体的で伝わりやすいです。
- Why(なぜ):私たち商品開発チームは、忙しい毎日の中でも手軽に健康を維持したいという多くのお客様の声に応えるため、健康ドリンクの新たな可能性を探ってきました。既存の栄養補助食品では、味や持ち運びの手間、継続のしづらさといった課題が多く寄せられており、より実用的で生活に寄り添う製品が求められていました。
- How(どのように):そこで私たちは、試作段階からモニター調査を行い、実際の利用シーンを想定しながら味や食感、容器の形状などを繰り返し検証しました。オフィスや外出先でも手軽に飲めるよう、保存性や開封のしやすさにも配慮し、試飲者からのフィードバックを基に何度も改良を重ねてきました。
- What(何を):その結果誕生したのが、1本で1食分の栄養をバランスよく摂取できるスムージータイプの健康ドリンク「FitGo」です。栄養価と携帯性を両立させ、忙しい現代人の食生活をサポートする新しい選択肢として開発しました。5月に本社会議室およびオンラインで開催される新商品発表会で正式に発表し、同時にオンライン販売とコンビニ展開を開始する予定です。
新規事業のアイデア想起・マーケティング分析
新規事業の企画では、思いついたアイデアをそのまま提案しても、説得力や実現性に欠けてしまうことがあります。5W1Hを活用すると、発想を論理的に整理し、ビジネスとして成立するかどうかを多角的に検討できます。
- Who(だれが):都市部で新しい食文化を楽しみたい消費者。
- What(なにを):全国の地方特産品や旬の食材を詰め合わせ、毎月自宅に届けるサブスクリプション型サービス。季節ごとに地域をテーマにし、食材だけでなく地域のストーリーも一緒に体験できる。
- When(いつ):2026年春に試験運用を開始し、秋の新米シーズンに正式リリース予定。
- Where(どこで):オンラインを通じて全国に展開。配送対応エリアは全国の主要都市を中心に設定。
- Why(なぜ):地方の生産者は販路拡大に課題を抱える一方で、都市部の消費者は本物の味や地域とのつながりを求めている。両者を結ぶことで、地域経済の活性化と消費者の満足度向上を実現する。
- How(どのように):オンラインプラットフォームで生産者と消費者を直接つなぎ、テーマ別の定期便を提供。SNSや動画で生産者のストーリーを発信し、ブランドファンを育成する。
このように5W1Hでアイデアを具体化することで、「誰に」「何を」「なぜ」提供するのかが明確になり、実現可能性の検証や市場分析にもつなげられます。
また、複数のアイデアを比較・検討する際にも、同じフォーマットで整理することで客観的に評価できます。
トラブル対応での問題認識
お客様や現場でのトラブルや不具合が起きたとき、感覚や憶測だけで判断すると再発のリスクが高まります。しかし、5W1Hで状況を構造的に把握すれば、原因の特定・責任の明確化・改善策の立案を体系的に進められます。
例えば、「端末の画面が割れた」というクレームは次のように整理します。
- Who(誰が):山田太郎様(男性、45歳)
- What(何を):購入したばかりの端末
- When(いつ):10月10日 午後2時〜3時
- Where(どこで):電車の中
- Why(なぜ):不明(これから事実確認・原因究明をし然るべき対応をする)
- How(どのように):強く床に落とした
問題解決に5W1Hを使うと、原因・経緯・対策を論理的に整理でき、再発防止策を立てやすいです。また、共有資料や報告書も明確になり、チーム全体の対応スピードを高められます。
5W1Hを使いこなすコツ
5W1Hを使いこなすコツを詳しく解説します。
5W1Hの順番の決め方
5W1Hの順番は固定ではありません。目的や相手の立場に合わせて、情報を最も理解しやすい順に並べることが重要です。
例えば結論や成果を中心に伝えたい場面では、「What → Why → How」の流れが効果的です。「何を」「なぜ」「どう行ったか」の順で説明すれば、報告やプレゼンの要点がすぐに伝わります。
一方、提案や企画などで相手の納得を得たい場合は、「Why → How →What」の構成が適しています。まず目的を明確に示し、続けて「どのように」「何を」実現したかを説明すれば、論理の流れが自然です。
相手が最も知りたい情報を先頭に置くことが、説得力ある構成づくりの基本です。
必要な要素を取捨選択する
6つ全ての要素を使う必要はありません。伝える目的が明確であれば、要点だけを選んで構成する方が伝わりやすいためです。
例えば、社内での共有事項や進捗(しんちょく)報告では、「What」「When」「Why」を中心にまとめれば十分です。逆に、外部向けの提案書では、背景や目的にあたる「Why」と、実行手段を示す「How」を丁寧に説明する方が効果的でしょう。
5W1Hの本質は「網羅」ではなく「焦点化」です。相手に必要な情報を見極め、簡潔に整理することで、理解されやすく実行につながるメッセージを作れます。
5W1Hで整理した情報を文章に落とし込む方法
5W1Hで情報を整理した後は、それを自然で読みやすい文章や資料構成に変換する工程が必要です。要素を単に並べるだけでは堅苦しくなるため、文の流れや接続語を工夫して、スムーズな文章に整えましょう。
例えば、次のような構成を意識します。
- 「Why(なぜ)」で目的や背景を示す
- 「How(どのように)」で実現方法や手順を具体化
- 「What(何を)」で取り組みや提案内容を説明
この流れを基に、文章として自然に組み立てれば、論理的で説得力のあるストーリーが作れます。また、箇条書きや表を使って各要素を整理すると、視覚的にも伝わりやすくなるでしょう。
5W1Hを発展させたフレームワーク
ビジネスやプロジェクト管理の現場では、さらに実行力や具体性を高めるために5W1Hを発展させたフレームワークが使われています。
代表的なフレームワークは、次のとおりです。
- 5W2H
- 5W3H
- 6W2H
それぞれ分かりやすく解説します。
5W2H
5W2Hは、5W1Hに「 How Much(いくら・どの程度)」 を追加したフレームワークです。
「How Much」を加えることで、コストや時間、労力といった「量的な管理」ができます。例えば、新しい広告施策を立てる場合、「広告予算はいくらか」「どの程度の期間実施するか」「必要な人員は何人か」など、費用対効果を具体的な見積もりが可能です。
5W2Hを活用することで、「アイデア段階」から「実行可能な計画」へと落とし込む力が高まります。企業の企画部門やマーケティング部門では、プロジェクト提案書や実施計画書の作成時に頻繁に利用されています。
5W3H
5W3Hは、5W2Hに 「How Many(どれくらい・いくつ) 」を加えた拡張版です。
「How Many」を加えることで、数量的な裏付けを持った計画立案やリソース管理ができます。例えば、イベントを開催する場合、「参加者は何人か」「必要な座席数はいくつか」「用意するパンフレットは何部か」などを明確にすることで、実務上の手戻りやコスト超過を防げます。
5W3Hは、定量的なデータを基に計画を検証し、実行リスクを最小限に抑えるフレームワークとして有効です。特に製造や販売、イベント運営、在庫管理などの現場では、精度の高い見積もりやリソース配分に役立ちます。
6W2H
6W2Hは、5W2Hに「 Whom(誰に)」 を追加したフレームワークです。
「Whom」を追加することで、行動や施策の「対象者」を明確にできる点が特徴です。
特にマーケティングや営業活動では、「Whom=誰に届けるのか」を定義することで、
顧客セグメントごとの最適なメッセージやアプローチ手法を設計できます。
例えば、販促企画を立てる際、「Whom=新規顧客」なのか「Whom=既存顧客」なのかを明確にすることで、広告媒体の選定やキャンペーン内容が大きく変わります。
6W2Hは、顧客中心の視点を組み込んだ戦略立案に最適です。ターゲティングや顧客満足度向上、CRM(顧客関係管理)など、顧客起点のビジネス施策で特に力を発揮します。
5W1H以外におすすめのフレームワーク
5W1Hは情報整理や説明の基礎として非常に優れたフレームワークですが、実際のビジネス現場では、目的に応じて他の思考法を組み合わせることが成果を高める鍵です。
目的別に使える代表的な四つのフレームワークは、次のとおりです。
- コミュニケーションならPREP法
- マーケティング戦略なら4P分析
- 問題解決ならロジックツリー
- アイデア想起ならSCAMPER法
それぞれを詳しく解説します。
コミュニケーションならPREP法
PREP法(プレップ法)は、ビジネスの報告・説明・プレゼンテーションなど、「短時間で分かりやすく伝える」ためのフレームワークです。
PREPは次の四つの要素で構成されます。
- Point(結論):最初に主張を明確に伝える
- Reason(理由):なぜそう考えるのかを説明する
- Example(具体例):根拠となる事実や事例を挙げる
- Point(再結論):最後にもう一度要点を強調する
この流れで話すと、聞き手が最初に全体像をつかめるため、理解度が高まります。また、話し方に一貫性が生まれるため、説得力や信頼感も高まります。
例えば、上司への報告であれば「結論→理由→実例→結論」で話すことで、冗長な説明を避け、短時間で意図を正確に伝えられます。PREP法は、論理的に話す力・聞き手を納得させる力を磨きたい人に最適なフレームワークです。
マーケティング戦略なら4P分析
商品やサービスを市場にどう展開するかを考えるときに有効なものが、4P分析です。マーケティングの基本理論の一つであり、戦略立案や新規事業開発の現場で幅広く使われています。
4Pとは、次の4つの視点を意味します。
- Product(製品):どんな価値や機能を持つ商品・サービスか
- Price(価格):どの価格帯で販売し、どんな収益モデルを取るか
- Place(流通):どのチャネル・場所で提供するか(EC、店舗など)
- Promotion(販促):どうやって顧客に認知させ、購入につなげるか
これらを体系的に整理することで、顧客ニーズと自社戦略の整合性を確認できます。また、競合との比較や市場ポジショニングを明確化することで、「どんな価値を、誰に、どのように届けるのか」というマーケティングの軸を明確にできる点が特徴です。
さらに近年では、顧客視点を重視した「4C分析(Customer、Cost、 Convenience、 Communication)」と併用し、より実践的な戦略設計に活用されるケースも増えています。
問題解決ならロジックツリー
課題の原因を整理したり、解決策を構築したりするときに役立つものが、ロジックツリーです。問題をツリー(木構造)のように階層的に分解し、要素間の関係を可視化することで、
複雑な課題を論理的に整理できます。
ロジックツリーには主に次の二つの型があります。
- Whyツリー(原因分析型):問題の根本原因を掘り下げる
- Howツリー(解決策探索型):目的達成のための手段を広げる
例えば「売り上げが下がっている」という問題をWhyツリーで分析すると、「来店数の減少 → 広告効果の低下 → ターゲット層のずれ」といった形で、原因を段階的に把握できます。
逆にHowツリーを使えば、「売り上げを上げるには?」という問いから、「新商品の投入」「広告改善」「販売チャネル拡大」など、複数の解決策を体系的な洗い出しが可能です。
このようにロジックツリーは、課題を構造的に分析し、納得感のある意思決定を支えるフレームワークとして、経営・企画・コンサルティングの現場で広く活用されています。
アイデア想起ならSCAMPER法
新しい発想を生み出す際に役立つフレームワークがSCAMPER法(スキャンパー法)です。既存のアイデアや製品を異なる視点で見直し、改良・転用・再構築できます。
SCAMPERは7つの発想パターンの頭文字を取ったもので、次の要素から構成されています。
- Substitute(置き換える):別の素材・方法・人に変えられないか
- Combine(組み合わせる):他の要素やアイデアと融合できないか
- Adapt(応用する):他業界のアイデアを生かせないか
- Modify(変形する):形・デザイン・用途を変えられないか
- Put to other use(転用する):別の使い方ができないか
- Eliminate(削除する):不要な部分を取り除けないか
- Reverse(逆転する):順番・構造・視点を反対にできないか
例えば、既存商品のリニューアルを考える場合、「素材を変える」「他製品と組み合わせる」「不要機能を削除する」といった発想を広げられます。
SCAMPER法は、ゼロから考えるのではなく「今あるものをどう変えるか」という柔軟な発想を促す点が特徴です。商品開発やデザイン、企画立案など、創造性が求められるあらゆる分野で活用できます。
5W1Hに関するQ&A
最後に、5W1Hに関するよくある質問と回答を紹介します。
5W1Hをチームで共有するときのコツはあるか
チームで5W1Hを共有する際は、全員が同じ視点で情報を整理できる仕組みを作ることが重要です。
おすすめは、共通フォーマットの作成です。例えば、会議メモやプロジェクト管理シートに「Who・What・When・Where・Why・How」の欄を設けておくと、メンバーがそれぞれのタスクや目的を同じ基準で記入できます。特に複数人で進行するプロジェクトでは、「Why(なぜ)」や「How(どうやって)」を明示することで、タスクの背景や意図が共有され、各メンバーが主体的に行動しやすくなります。
チームでの5W1H活用は、情報共有の精度を高める共通言語として機能させましょう。
学生でも5W1Hを使うメリットはあるか
5W1Hは社会人だけでなく、学生の学習や発表の場面でも非常に有効な思考整理のツールです。
レポートや論文を書くときに「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」を意識することで、内容の筋道が明確になり、論理的な構成が自然と整います。特に「Why(なぜ)」を明確にすることで、単なる事実の羅列ではなく、説得力のある考察ができます。
また、就職活動の自己PRやエントリーシート作成にも応用可能です。自分の経験を5W1Hで整理すると、具体性が増して伝えられます。5W1Hは「考える力・伝える力を磨く基礎トレーニング」として学生生活全般に役立つフレームワークといえるでしょう。
5W1Hは個人のタスク管理にも使えるか
5W1Hを活用すると、日々のタスクや目標を「誰が・何を・いつまでに・なぜ・どのように」整理できるため、曖昧な予定を具体的な行動に変えられます。
例えば、学業や仕事で「提出物を終わらせる」という漠然とした目標も、5W1Hで分解すれば行動が明確にできます。
- What(何を):レポートを完成させる
- Why(なぜ):評価に反映されるから
- When(いつまでに):金曜17時まで
- How(どうやって):午前中に構成を立て、午後に執筆する
このように整理すると、やるべきこと・期限・理由が一目で分かり、優先順位を付けやすいです。特に在宅ワークや個人学習など、自分で進捗(しんちょく)を管理しなければならない環境では、5W1Hは「自己管理の地図」として強力なサポートになるでしょう。
5W1Hとロジカルシンキングはどう違うか
5W1Hは「情報を整理する枠組み」であり、ロジカルシンキングは「筋道を立てて考える思考法」という点に違いがあります。
5W1Hは前述のとおり、主に「抜け漏れなく情報をまとめる」ことを目的としており、事実や状況を整理する段階で役立ちます。
一方、ロジカルシンキングは、集めた情報を基に因果関係を分析し、結論を導くための思考法です。例えば、「なぜ売り上げが下がったのか」「どうすれば改善できるのか」といった問いに対して、仮説を立てて論理的に検証していく点が特徴です。
つまり、5W1Hは「情報の整理」、ロジカルシンキングは「情報の活用・分析」に重点を置いたアプローチです。実務では、まず5W1Hで事実を整理し、その後ロジカルシンキングで原因や解決策を導くというように、両者を組み合わせることでより深い思考ができます。
まとめ
5W1Hは、情報を整理し、伝えたい内容を明確にするための基本的なフレームワークです。これを使うことで、様々な場面でのコミュニケーションがスムーズになり、ビジネスや学業においても役立つでしょう。
本記事で紹介したように、5W1Hは「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「なぜ」「どのように」といった質問に答えることで、情報の漏れを防ぎ、より論理的な思考を促します。もし、情報整理やプレゼン、問題解決において困っていることがあれば、まずは5W1Hを使ってみてください。それでも解決が難しい場合は、さらに発展したフレームワークや他の方法も検討してみると良いでしょう。まずは一度試して自分のスタイルに合った使い方を見つけてみると、あなたの思考やコミュニケーションスキルはさらに向上するはずです。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。