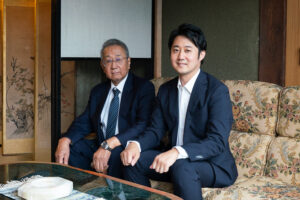運送・物流業界におけるM&Aの現状と事例【2025年版】
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
運送・物流業界でもM&Aの必要性が高まっています。EC市場の急成長に伴い、宅配物増加の一方で、ドライバーの人手不足や2024年問題など、多くの課題に直面していることが理由とされています。
こうした状況の中、M&A(企業の合併・買収)は、運送・物流業界の課題解決や事業拡大の手段として注目されています。
本記事では運送・物流業界の市場とM&Aの動向やメリット、注意点について事例とともに解説します。
目次
運送・物流業界のM&A成功事例
日本通運、パナソニックロジスティクスの株式取得
- パナソニックロジスティクス
- 大阪府
- 物流業・倉庫業
- 日本通運
- 東京都
- 物流・倉庫
2014年、日本通運はパナソニックの物流子会社であるパナソニックロジスティクスの買収を実現しました。総合的に物流の業務を行うパナソニックロジスティクスは電化製品の生産・販売に関する知識とノウハウを活かし、電機物流業界における高い納入品質を実現しています。
SBSホールディングス、リコーロジスティクスの株式の一部取得
- リコーロジスティックス
- 東京都
- 物流
- SBSホールディングス
- 東京都
- 物流・倉庫
2018年、リコーグループの物流子会社であるリコーロジスティックスの株式を一部取得したとSBSホールディングスは発表しました。複写機などの精密機器や機械部品、オフィス向け消耗品などのトラック配送事業を行います。
東部ネットワーク、東北三光を子会社化すると発表
- 東北三光
- 宮城県
- セメント輸送・販売
- 東武ネットワーク
- 神奈川県
- 陸運業
2022年、東武ネットワークは東北三光を子会社化すると発表しました。東部ネットワークは東北三光の基盤を受け継ぎ、東北地区の営業拡大・業容拡大を目指します。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



物流業と運送業
運送・物流業界の市場やM&Aについて紹介する前に、物流業界とは何か、運送業とはどういったものかについて触れていきます。
物流業界とは
物流業とは、製品を生産者から消費者に届ける一連の過程のことをいい、一般的に「輸送・配送」「保管」「荷役」「包装」「流通加工」「情報管理」の6つにカテゴリー分けされます。それぞれについて簡単に説明します。
| 輸送・配送 | トラック、列車、船舶、航空機などで製品を目的地に運ぶこと。物流センターや倉庫など拠点まで運ぶことを輸送、拠点から消費者や店舗など最終目的地まで運ぶことを配送という。 |
| 保管 | 預かり荷物を適正に管理しながら倉庫やセンターに保管すること。冷蔵冷凍が必要な製品の温度管理など品質維持も含まれる。 |
| 荷役 | 輸送機関からの荷物の積み込みや積み下ろし、倉庫への入荷・出荷作業。 |
| 包装 | 輸送時の製品の状態を維持し、安全に届けるための梱包作業。 |
| 流通加工 | ラベル貼り、値札付け、箱詰めなど製品を消費者に届けるための加工作業。 |
| 情報管理 | 荷物の追跡や輸送経路の確認、保管時の品質維持のための湿度温度管理など、システムを利用して各種情報を記録・管理すること。 |
運送業とは
運送とは、物流の一過程のことであり、法人または個人から預かった製品を目的地に届ける活動をいいます。なお、運送は主にトラックで運ぶ作業のことを指します。
「運送」「配送」「輸送」の違いについて簡単にまとめました。
| 運送 | 主に車やトラックを用いた中・長距離移動 |
| 配送 | 主に倉庫や物流センターから消費者のもとへ届ける近距離移動 |
| 輸送 | 主に列車、船舶、航空機などを用いた長距離移動 |
運送・物流業界の市場規模と動向
運送・物流業界のM&Aが急増している背景には、この業界の需要の増加と直面している課題が影響しています。
国土交通省「令和5年度交通動向」によると、2022年の交通事業の国内総生産は26.4兆円であり、全体の4.7%を占めています。また物流事業の全体の市場規模はおよそ30兆円、うち約65%の19兆6511億円をトラック運送業がシェアしています。
物流の大半を担っているトラック運送業ですが、トラックドライバーの高齢化や就業者数の減少が課題となっています。
トラック運送事業者数は、1900年の貨物自動車運送事業法の施行によって増加し、2007年には1.5倍になりましたが、翌年には事業者間の競争の激化により減少。その後横ばい状態が続いていましたが、近年は新規参入事業者数を退出事業者数が上回っている状態です。
国内の物流の市場規模
国内の貨物輸送量に関しては緩やかな減少傾向がみられますが、その理由として1件あたりの貨物量の低下が挙げられます。
1件あたりの貨物量が1990年は2.43トンであったのに対し、2021年は0.83トンと約1/3に減少する一方で、物流件数は1990年と比較して約2倍に増加しています。このことから石材やコンクリート、金属製品等の重量の大きい物資の物流が減少したことや個人によるEC通販での購入が増加したことが考えられます。
運送業界の現状と課題
2022年の国内の貨物輸送状況はトラックが91.9%と全体のほとんどを占めています。
また、宅配便の取扱実績は年々増加し、2022年は約50億個と5年間で23.1%増加しています。この背景にはEC市場の拡大も影響しています。
EC化率は2014年は全体の4.37%だったものが、2022年は9.13%に伸びていることから、インターネットで商品を購入する消費者が増加していることが物流件数の増加に関係しているとも考えられるでしょう。
しかし、物流件数が増加している一方で、ドライバー不足の問題を抱えているのが運送業界です。
2023年の交通業の就業者数は349万人であり、2015年の336万人に比べると増加はしているものの、全産業で比較すると就業者が不足しています。就業者不足の原因として挙げられるのが労働環境です。
トラックドライバーの年間の労働時間は2512時間と他の産業の労働時間と比べて約2割長い上に、年間の所得額は約1割低いという状況です。
道路貨物運送業のドライバーは1995年の98万人から20年間で21.3万人減少しており、2030年には51.9万人になると予想されています。(参考:国土交通省「物流を取り巻く現状と課題」)
また、従業員の高齢化と若年層の人材不足も課題です。
厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況」では、3年以内の離職率は高卒が36.4%、大卒が31.2%でした。全産業の離職率が高卒38.4%、大卒34.9%であることから著しく高いというわけではありませんが、就職率の増加と離職率低下の対策が今後必要と考えられます。
EC市場の拡大により運送業界の需要が増加
EC市場の拡大により、これまで店舗で購入していた日用品や衣料品、家電をインターネットで購入する消費者が増えたことで、運送業の需要が伸びています。当日・翌日配送や置き配、コンビニ受け取りなど利便性が高まったこともEC利用者が増えている背景として挙げられます。
特に、ラストワンマイル配送の需要が高まり、消費者の期待に応えるために迅速かつ効率的な配送網の整備が求められています。
ドライバーの高齢化と若手の人材不足
2023年のトラック運送業に従事している就業者数は約201万人、うちドライバーや輸送・機械運転従業者は約88万人と発表されています。年齢層の内訳は50代が30.3%、40代が25.4%、60代以上が19.4%で、男女比は88万人中85万人が男性です。
このことから、ドライバーの約75%が40歳以上の男性であり、20代、30代の割合は年々減少していることからも若手の人材不足が課題であることがわかります。(参考:日本のトラック輸送産業現状と課題2024)
若手の人材不足の背景には、運送業界特有の長時間労働や低賃金といった労働環境の問題が挙げられ、今後は労働時間規制の強化により、さらなる人手不足を招く可能性があります。
業界再編の必要性
中小企業が多い運送業界では、競争が激化し、資本力の弱い企業は競争力を維持するのが難しくなっています。このような背景から、業界再編の一環としてM&Aが注目されています。
ガソリン価格の高騰
物流業界の課題は人材不足だけではありません。
円安により燃料費の価格高騰も問題の一つです。特にガソリンは20年前から2倍近く高騰したことにより、運送会社の経営を圧迫しています。
物流・運送業界の2024年問題
2024年4月に適用されたトラックドライバーの時間外労働の上限規制と改正改善基準告示により、ドライバーノ労働時間短縮、人材不足により輸送量の減少や当日または翌日配送などのサービスが対応できなくなる事態が懸念されています。
この問題を乗り切るために、企業が運送会社を買収し、自社の輸送力を強化するという動きも見え始めました。
運送業界におけるM&Aの動向
物流における運送業界の実情からM&Aが活発に行われています。M&Aが行われる目的は様々です。
- 人材不足の解消:M&Aにより人材を確保し、運送効率を改善。
- 事業エリアの拡大:新たな地域に進出し、市場シェアを拡大。
- 物流効率化:物流網を強化し、コスト削減を図る。
人材不足の解消
運送業界ではEC市場の拡大による宅配便の増加に対し、就業者数の減少や高齢化、労働時間の規制などにより人材不足が課題となっています。
M&Aで運送業者を買収することにより、ドライバーを確保することができます。
事業エリアの拡大
他社の事業を買収することで新たな取引先や拠点を獲得することができ、事業エリアの拡大を狙えます。
物流効率化
DX化が進んでいる企業を買収することで、配送ルートの適正化や総輸送量の増加など業務の効率化を図ることもできます。
また、運送業許可の緩和により、新規参入を狙う企業にとってはすでに運送業許可を持ち、ドライバーや倉庫が確保できている運送業者を買収することでコストを抑えて物流・運送事業に参入することができます。
売却側としても高齢化が進んでいる従業員の雇用を守るだけでなく、廃業時にかかる営業所やトラックの廃車費用を削減することができ、売却益をもとに新たな事業の立ち上げや老後の資金にすることができます。
M&Aによる事業承継は単なる市場規模の拡大にとどまらず、運送業全体の効率化にも寄与しています。
運送・物流業界のM&Aにおけるメリット
売却側のM&Aのメリット
- 事業承継問題の解決
高齢化が進む中、後継者不足に悩む企業にとって、M&Aは有効な選択肢です。 - 経営基盤の安定
企業の売却益を活用して、経営基盤を強化できます。 - 従業員の雇用維持
大手企業との統合により、従業員の雇用を安定させることができます。
買収側のM&Aのメリット
- 市場シェアの拡大
他社の顧客基盤を取り込み、市場での競争力を向上させられます。 - 物流ネットワークの強化
地域特化型の運送会社を買収することで、広範囲にわたるネットワークを構築できます。 - ブランド価値の向上
信頼性の高い企業を買収することで、ブランド価値が向上します。
運送・物流業界のM&Aにおけるデメリット
売却側のM&Aのデメリット
- 売却額の不満足
市場価値に見合わない価格での売却リスクがあります。 - 顧客離れのリスク
買収後にサービス変更が生じた場合、顧客離れが起こる可能性があります。
買収側のM&Aのデメリット
- PMI(経営統合)の難航
買収後の統合がスムーズに進まない場合、業績に悪影響を及ぼすことがあります。 - 潜在的な債務リスク
簿外債務や法的リスクを引き継ぐ可能性があります。
運送業界のM&A成功のポイント
適切な相手先の選定
企業文化やビジョンが合致する相手を選ぶことが成功の鍵となります。これにより、統合後の混乱を最小限に抑えられます。
デューデリジェンスの徹底
買収前に、財務、法務、運用リスクを徹底的に調査することが重要です。特に、運送業界特有の労働環境や規制を考慮する必要があります。
PMI(経営統合)の計画と実行
買収後の経営統合が成功するかどうかは、M&A全体の成果を左右します。統合計画を事前に策定し、従業員への適切なコミュニケーションを図ることが重要です。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
運送業界におけるM&Aは、課題解決と成長を実現するための効果的な手段です。しかし、成功には慎重な計画と戦略的な実行が不可欠です。運送業界の現状を正しく理解し、適切な準備を進めることで、企業は持続的な成長を目指すことができます。
M&Aロイヤルアドバイザリーでは、M&Aや事業承継の初期的な関心でもご相談いただけます。事業承継には時間がかかるものなので、早い段階で情報収集を行い、M&Aを含めた最適な解決策を検討することが重要です。
今後のプランを考えるためにも、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。