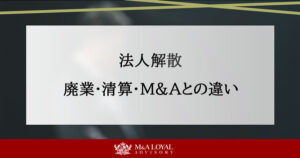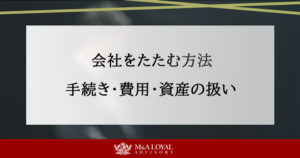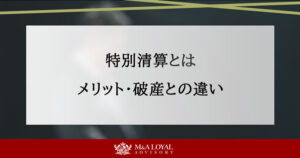清算人とは?選任・登記から会社解散時の役割までわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
清算人とは、会社が事業を終了し消滅する際に、解散後の「清算」という手続きを実行する役割を担う人物を指します。清算人は、会社の債権の回収や債務の弁済、残余財産の分配など、会社の最終的な整理業務を担い、会社が正式に消滅するまでの重要なプロセスを管理します。しかし、清算人の選任方法や具体的な職務内容、法的責任については、多くの経営者が詳しく理解していないのが現状です。
本記事では、清算人の基本概念から選任・登記手続き、具体的な役割まで、会社解散を検討している経営者が知っておくべき重要なポイントを網羅的に解説いたします。
目次
清算人とは?会社解散における基本的な役割
清算人とは、会社解散後の精算手続きにおいて、退任した取締役に代わって精算業務を執行する機関です。会社の法人格が消滅するまでの間、債権債務の整理や株主への財産分配などを担当します。
会社の消滅には「解散」と「清算」という2つの段階が必要です。まず株主総会の特別決議により解散が決定され、その後清算人による清算手続きが開始されます。解散はあくまで事業活動の停止を意味するものであり、会社の法人格そのものは清算結了まで存続します。
解散と清算の違いとプロセス
解散は会社が事業活動を停止することを決定する段階であり、清算は残存する財産や債務を整理して会社を完全に消滅させる段階です。解散決議後も会社の法人格は存続しており、清算結了登記が完了した時点で初めて会社は完全に消滅します。
清算手続きの基本的な流れは以下の通りです。まず解散決議と同時に清算人を選任し、清算人は現務の結了、債権の取り立て及び債務の弁済、残余財産の分配という順序で業務を進めます。すべての清算業務が完了した後、決算報告書を作成して株主総会の決議を経て、清算結了登記を行うことで会社が消滅します。
清算人会と代表清算人の仕組み
清算人が複数名選任される場合や監査役会設置会社の場合には、清算人会の設置が必要となります。清算人会設置会社では、清算人の中から代表清算人を選任しなければなりません。一方、清算人会を設置しない会社で複数の清算人が存在する場合は、定款の規定、株主総会の決議、または清算人の決定により代表者を定めることができます。
代表清算人は清算会社を代表して法律行為を行う権限を持ちます。清算人会を設置しない場合で代表者が定められていないときは、清算人全員が代表権を持つことになります。また、裁判所によって清算人が選任される場合には、裁判所が代表清算人を定めることもあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



清算人の選任方法と登記手続き
清算人の選任には複数の方法が存在し、それぞれ異なる条件や手続きが定められています。適切な選任方法を選択することで、スムーズな清算手続きの開始が可能となります。選任方法によっては登記手続きの内容も変わるため、事前に十分な検討が必要です。
清算人の選任は会社解散の決議と密接に関連しており、多くの場合、解散決議と同じ株主総会において清算人の選任も行われます。選任された清算人は就任承諾後、速やかに登記申請を行う必要があります。
定款指定による選任
定款に清算人となるべき者を予め規定している場合、解散と同時に自動的に清算人に就任します。ただし、この方法は実務上あまり活用されていません。定款指定の場合であっても、指定された者が就任を承諾しなければ清算人とはなりません。
定款指定による清算人の選任は事前準備が可能である一方、将来の状況変化に対応しづらいというデメリットがあります。そのため、多くの会社では他の選任方法を選択することが一般的です。
株主総会決議による選任
最も一般的な選任方法が株主総会決議による清算人の選任です。解散決議を行う株主総会において、同時に普通決議により清算人を選任します。解散決議には特別決議が必要ですが、清算人の選任は普通決議で足ります。
株主総会決議による選任では、会社の実情に応じて最適な人選が可能となります。取締役経験者や専門知識を持つ外部の者など、清算業務に適した人材を柔軟に選任できる点が大きなメリットです。選任決議においては、清算人の氏名・住所を明確に特定する必要があります。
法定清算人(取締役の自動就任)
定款の規定や株主総会決議による清算人の選任がない場合、解散時の取締役が自動的に清算人となります。これを法定清算人制度といいます。特別な手続きを要せず、解散と同時に取締役が清算人に移行するため、手続きの簡素化が図れます。
法定清算人制度により、解散決議のみで清算手続きを開始できるという特徴がありますが、株式総会の決議による任意清算が一般的であり、法定清算人が利用されるケースは多くはありません。
裁判所選任による場合
取締役全員が辞任や死亡により不存在となった場合など、法定清算人が存在しない特殊な状況では、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任します。この場合、弁護士などの専門家が選任されることが一般的です。
裁判所選任による清算人は、会社とは独立した立場から公平な清算業務を執行します。選任費用や報酬が発生するため、他の選任方法が利用できない場合の最終手段として位置づけられています。裁判所が代表清算人を同時に定めることもあり、複雑な清算手続きにも対応可能です。
清算人選任の登記手続き
清算人が選任された場合、就任から2週間以内に清算人選任の登記を行わなければなりません。登記申請書には清算人の氏名、住所、選任年月日、代表清算人の氏名(該当する場合)などを記載します。
| 登記事項 | 記載内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 清算人の氏名・住所 | 選任された清算人全員の情報 | 株主総会議事録、就任承諾書 |
| 代表清算人の氏名 | 代表権を有する清算人の特定 | 清算人会議事録(該当する場合) |
| 選任年月日 | 清算人就任の効力発生日 | 株主総会議事録 |
清算人の資格要件と欠格事由
清算人への就任には特定の資格要件が存在し、同時に法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。これらの要件を満たさない者は清算人になることができないため、選任時には十分な確認が必要です。
清算人の資格要件は取締役の要件とほぼ同様に規定されており、会社の最終的な整理業務を適切に執行できる能力と信頼性が求められます。欠格事由に該当する者が選任された場合、その選任は無効となり、清算手続きに支障が生じる可能性があります。
清算人になるための基本的資格
清算人は自然人である必要があり、法人は清算人になることができません。年齢や性別、国籍による制限はなく、会社法上の能力があれば誰でも清算人に就任することが可能です。ただし、実際の清算業務を適切に執行するためには、一定の業務知識と経験が必要となります。
清算人の資格に特別な免許や資格は不要ですが、会計知識や法律知識を有する者が望ましいとされています。特に複雑な債権債務を抱える会社の場合には、専門家への依頼や助言を求めることが重要です。
法律で定められた欠格事由
清算人には以下の欠格事由が定められており、これらに該当する者は清算人になることができません。まず法人は清算人になれないため、個人のみが対象となります。また、成年被後見人や被保佐人など、意思能力に制限がある者も欠格者となります。
刑事罰に関する欠格事由も存在します。会社法、金融商品取引法、民事再生法、外国為替及び外国貿易法などの規定に違反し、刑に処せられてから2年を経過しない者は清算人になれません。さらに、禁錮以上の刑の執行中である者も欠格者に該当します。
- 法人(株式会社、合同会社等)
- 成年被後見人及び被保佐人
- 会社法等の法令違反により刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過しない者
- 禁錮以上の刑の執行中である者
- 当該株式会社の監査役
監査役との兼任禁止
会社の監査役は同一会社の清算人を兼任することができません。これは監査役の独立性と清算人の業務執行機能が相反するためです。
監査役設置会社が解散する場合、監査役は清算手続き中も監査役として在任し続けるため、清算人との明確な役割分担が重要となります。監査役は清算人の職務執行を監査する立場にあり、利益相反を避けるために兼任が禁止されています。
清算人の具体的職務と手続きの流れ
清算人の職務は会社の完全な消滅を目的とした一連の業務から構成されており、法律で明確に規定されています。これらの職務は原則として順序立てて実行する必要があり、各段階で適切な手続きと判断が求められます。
清算業務は現務の結了から始まり、債権の取り立て及び債務の弁済、残余財産の分配へと進みます。最終的には決算報告書の作成と株主総会での承認を経て、清算結了登記により会社が消滅します。各段階において関係法令の遵守と適切な記録保存が必要です。
現務の結了
現務の結了とは、解散時点で継続中の契約や取引を適切に処理することです。清算人は既存の契約を履行または解約し、新規の契約締結は原則として禁止されています。ただし、現務の結了や債権の取り立て、債務の弁済に必要な契約については例外的に締結が認められます。
現務の結了では既存契約の整理が主な業務となり、賃貸借契約の解約や売買契約の履行など、解散前からの継続案件を適切に処理する必要があります。この段階で不適切な処理を行うと、後の債権回収や債務弁済に支障が生じる可能性があります。
債権の取り立て及び債務の弁済
債権の取り立ては会社が第三者に対して有する債権を回収する業務です。売掛金、貸付金、預け金などあらゆる債権を調査し、回収可能性を検討したうえで適切な回収手続きを実行します。回収困難な債権については法的手続きも検討する必要があります。
債務の弁済においては、まず債権者に対する公告と個別催告を行います。官報公告により債権の申出を求め、知られている債権者には個別に催告します。申出期間は2か月以上とし、この期間内に債権の申出がない債権者に対しては弁済の責任を免れることができます。
債務弁済の資金が不足する場合には、会社財産の売却を検討します。不動産、設備、在庫などを適正価格で売却し、弁済資金を確保します。債務超過の場合には特別清算への移行も検討する必要があります。
残余財産の分配
すべての債務を弁済した後に財産が残存する場合、株主に対して残余財産の分配を行います。分配額は各株主の持株比率に応じて計算し、出資金の返還と利益配当に相当する部分に区分されます。利益配当部分は税法上みなし配当として課税される場合があります。
残余財産の分配では適正な評価と公平な分配が求められ、株主間の利害対立を避けるために慎重な手続きが必要です。分配前には財産の評価額を確定し、分配計算書を作成して株主への説明を行います。
清算結了手続き
清算業務が完了した後、清算人は決算報告書を作成し、株主総会の承認を求めます。決算報告書には清算期間中の収支、財産の処分状況、債権の回収及び債務の弁済状況、残余財産の分配などを詳細に記載します。
株主総会での承認後、2週間以内に清算結了登記を申請する必要があります。清算結了登記が完了した時点で会社の法人格が消滅し、清算手続きが終了します。登記完了後は会社の印鑑や帳簿類を適切に保管または廃棄します。
| 清算人の職務 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現務の結了 | 既存契約の履行・解約 | 新規契約締結の原則禁止 |
| 債権の取り立て | 売掛金等の回収 | 回収可能性の適切な判断 |
| 債務の弁済 | 公告・催告・弁済実行 | 弁済順序と資金確保 |
| 残余財産分配 | 株主への財産分配 | 税務上の取扱いに注意 |
| 清算結了手続き | 決算報告・登記申請 | 期限内の手続き完了 |
清算人の義務・責任と報酬
清算人は会社の業務執行機関として、法令や定款に基づく各種の義務を負い、これらの義務に違反した場合には法的責任を負うことになります。同時に、清算業務の対価として適正な報酬を受け取る権利も有しています。
清算人の義務は取締役の義務とほぼ同様に規定されており、忠実義務をはじめとする厳格な行動規範が求められます。義務違反があった場合の責任も重く、個人財産による賠償責任を負う可能性があります。
清算人の法的義務
清算人は善管注意義務として、善良な管理者としての注意をもって清算業務を執行する義務を負います。この義務は単なる注意義務にとどまらず、清算会社の利益を最優先に考えて行動することを求めています。また、法令、定款、株主総会決議を遵守する忠実義務も課せられています。
清算人は競業避止義務により、清算会社と同種の事業を自ら営むことや、同種事業を営む会社の役員等に就任することが制限されています。競業取引を行う場合には、事前に会社(株主総会または清算人会)の承認を得る必要があります。
利益相反取引の制限も重要な義務の一つです。清算人が清算会社との間で取引を行う場合、または第三者のために清算会社と取引を行う場合には、事前に会社の承認を得なければなりません。承認を得ずに行った利益相反取引は無効となり、清算人が損害賠償責任を負う可能性があります。
監督責任と報告義務
代表清算人以外の清算人は、代表清算人の職務執行を監督する義務があります。代表清算人が法令や定款に違反する行為を行っていることを発見した場合には、株主や監査役に報告する義務があります。
また、清算人は清算会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに株主または監査役に報告しなければなりません。また、株主からの求めがあった場合には、清算の状況について報告することが求められます。
清算人の損害賠償責任
清算人がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。また、任務を怠ったときは、清算会社に対して損害賠償責任を負います。
清算人の責任は個人責任であり、清算会社の財産では賠償しきれない損害については清算人の個人財産で賠償する必要があります。そのため、清算業務の執行にあたっては慎重かつ適切な判断が求められます。
清算人の報酬決定と支払い
清算人の報酬については取締役の報酬規程を準用すると定められており、清算株式会社の場合は定款または株主総会によって決められます。清算持分会社の場合は委任契約の内容に従って柔軟に決定されます。なお、裁判所が定めた清算人への報酬額は裁判所が決定します。
- 善管注意義務:善良な管理者としての注意義務
- 忠実義務:法令・定款・株主総会決議の遵守義務
- 競業避止義務:同業他社との取引制限
- 利益相反取引の制限:個人的利害関係のある取引の事前承認
- 監督義務:他の清算人の職務執行監督
- 報告義務:重要事項の株主などへの報告
通常清算と特別清算の違いと清算人による選択基準
会社の清算には通常清算と特別清算の2つの方法があり、会社の財産状況や債権者との関係によって適切な方法を選択する必要があります。通常清算は債務超過ではない会社で用いられる一般的な清算方法であり、特別清算は債務超過や清算の遂行に著しい支障がある場合に裁判所の監督下で行われる清算方法です。
清算方法の選択は清算手続きの効率性や費用、債権者保護の観点から重要な決定となります。誤った選択により清算手続きが長期化したり、追加費用が発生したりする可能性があるため、慎重な判断が求められます。
通常清算の特徴と適用条件
通常清算は清算会社が債務超過でない場合に適用される清算方法です。清算人が自主的に清算業務を執行し、特別な裁判所の監督は受けません。手続きが比較的簡素で費用も抑えられるため、健全な財政状態で解散する会社では通常清算が選択されます。
通常清算では清算人が大幅な裁量権を持ち、効率的な清算手続きの実行が可能ですが、その分清算人の責任も重くなります。債権者への公告・催告や財産の換価処分、残余財産の分配まで清算人の判断で実行します。
特別清算の仕組みと選択理由
特別清算は債務超過の疑いがある場合や、清算の遂行に著しい支障がある場合に裁判所に申立てを行って開始される清算手続きです。裁判所が選任した監督委員の監督下で清算が行われ、重要な行為については裁判所の許可が必要となります。
特別清算では協定による債務の減免や分割弁済が可能であり、債権者の同意があれば債務の一部カットも実現できます。破産手続きと比較して会社の信用毀損を抑えられる利点があります。
清算方法の選択基準
清算方法の選択は主に会社の財産状況によって決まります。資産が負債を上回る場合は通常清算が適用され、債務超過の場合は特別清算または破産手続きの選択となります。
清算方法の選択では費用対効果の検討が重要であり、残余財産の見込み額と清算費用を比較して最適な方法を決定する必要があります。特に中小企業では費用負担能力が限定的であるため、現実的な選択が求められます。
| 項目 | 通常清算 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 適用条件 | 債務超過でない場合 | 債務超過または清算に支障がある場合 |
| 監督機関 | なし(清算人の自主執行) | 裁判所および監督委員 |
| 債権者保護 | 公告・催告による | 協定による債務減免可能 |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡素 | 複雑(裁判所許可必要) |
| 費用 | 低額 | 高額(監督委員報酬等) |
まとめ
清算人は会社解散後の清算手続きにおいて中心的な役割を果たす重要な機関であり、債権の回収や債務の弁済、残余財産の分配など、会社の最終的な整理業務を担当します。清算人の選任には株主総会決議、法定清算人、定款指定、裁判所選任の4つの方法があり、それぞれ異なる特徴と適用場面があります。
清算人には善管注意義務や忠実義務をはじめとする厳格な法的義務が課せられており、義務違反があった場合には個人責任による損害賠償を負う可能性があります。そのため、清算業務の執行にあたっては関係法令の遵守と慎重な判断が不可欠です。また、清算人選任の登記から清算結了登記まで、各段階で適切な手続きと期限管理が求められます。
会社解散と清算は、企業の重要な最終手続きです。清算人の適切な選任と業務執行により、債権者保護と株主利益を確保しつつ、円滑にプロセスを進めることができます。また、M&Aを含む事業承継戦略の検討には、専門家による的確なサポートが不可欠です。M&Aや経営課題でお悩みの際は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。