協調性とは?ある人の特徴や採用時に見極める方、育成法を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
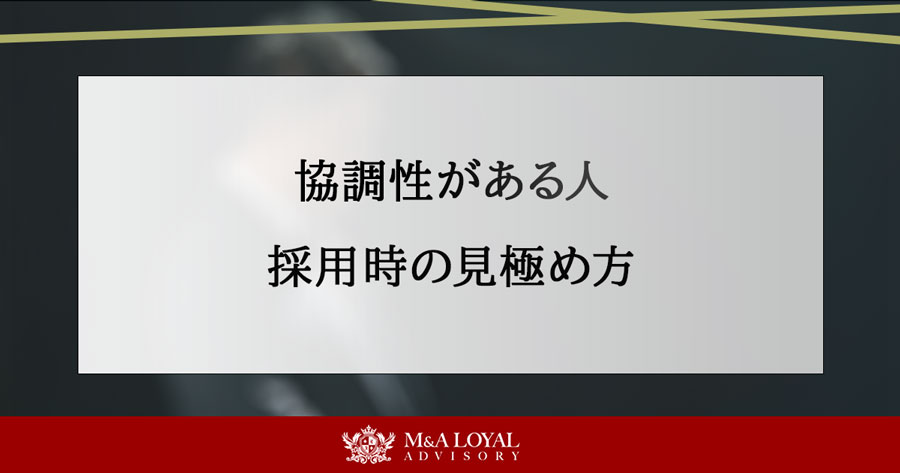
協調性とは、個々のメンバーが互いに協力し合い、共通の目標を達成するために必要とされる能力です。職場においては、チームワークを促進し、効果的なコミュニケーションを取るために欠かせない要素です。協調性がある人は、他者の意見を尊重し、多様な考え方を受け入れることができるため、円滑な人間関係を築くことができます。
これにより、個々の能力を最大限に活かすことができ、生産性の高いチームを作る基盤となります。本記事では、協調性とは何か基本的な意味からコミュニケーション能力との違い、仕事における重要性についてわかりやすく解説します。
目次
協調性とは
協調性の意味と似た言葉の違いを解説します。
協調性の意味
協調性とは、周りの人と力を合わせて物事を進められる能力のことを意味します。 例えば、仕事で何かを一緒に取り組むときに、意見の違いや考え方のズレが生まれることは珍しくありません。意見の違いや考えのズレが生じた場面で「自分だけが正しい」と突き進むのではなく、「相手はなぜそう考えるのか」を受け止め、最も良い方法を一緒に探していく姿勢がまさに協調性の表れです。
協調性は「人間関係の潤滑油」であり、仕事や学校、家庭などあらゆる場面で重要視されています。
協調性とコミュニケーション能力の違い
「協調性」と「コミュニケーション能力」はよく似た言葉ですが、役割が異なります。
コミュニケーション能力は、相手に自分の考えをわかりやすく伝えたり、相手の話を正確に理解したりするスキルのことをいいます。 一方、協調性は、意見が異なる相手とも円滑に関係を築き、共通の目的に向かって協力する力です。思いやりや柔軟さ、感情のコントロールなどが含まれます。
例えば、コミュニケーション能力が高くても、相手を尊重せず自分の意見ばかり押し通す人は「協調性が低い」とされます。逆に、自分の意見を伝えることが苦手でも相手と歩調を合わせながら、円滑な関係を保てる人は「協調性が高い」といえます。
協調性と社交性の違い
協調性と社交性はどちらも「人との関わり」に関する性質ですが、本質は異なります。社交性は、初対面の人とも積極的に関わり、関係を築いていける性格を指します。明るい、懐っこい、話しかけやすいといった「外向的な行動力」が中心です。 協調性は「関係を保つ力」であり、社交性は「関係を広げる力」といえます。
協調性とチームワークの違い
チームワークとは、メンバー同士が役割を分担し、協力して目標を達成する仕組みのことです。個々が自分の責任を果たしながら、全体の成果につなげる「組織的な動き方」を重視します。
つまり、チームワークは「仕組み」であり、協調性はその中で発揮される「心の姿勢」といえます。どちらか一方だけでは十分ではなく、役割を果たすチームワークと個性を生かす協調性の両立が、組織を強くする鍵といえるでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



協調性の重要性とメリット
協調性が仕事をする上で重要視される理由とメリットは、次のとおりです。
- 個人の業務効率が向上する
- 個人の成長をサポートできる
- 職場での人間関係のトラブルが軽減される
- 組織の成果を最大化できる
- 組織の持続的発展に貢献する
それぞれを詳しく解説します。
個人の業務効率が向上する
協調性がある人が多い職場では、情報共有が円滑に行えます。お互いの業務内容や進捗(しんちょく)を自然に把握できるため、連絡漏れや認識のずれといったトラブルが減り、コミュニケーションロスを最小限に抑えられます。 結果的に確認作業や手戻りの時間が減少し、個々人の作業効率が格段に向上する点が大きなメリットです。
また、協調性がある人が多いと、業務分担の最適化も実現しやすくなります。メンバーが互いの得意分野やスキルを尊重し合い、自然と「この仕事は自分がやる」「ここは任せよう」といった調整ができるためです。
個人の成長をサポートできる
協調性がある人は、周囲との関係を良好に保ちながら業務に取り組めるため、上司や同僚からのサポートを受けやすい点も大きな利点です。
職場で信頼され相談しやすい存在になることで、仕事の進め方や課題への対応など、さまざまな場面で的確なアドバイスをもらえる機会が増えます。結果的に業務理解が深まり、スキルアップのスピードも加速します。
また、協調性を発揮する中で生まれる日常的なコミュニケーションは、対人スキルを育てる基礎です。相手の立場を考えた言葉選びや、タイミングを見て意見を伝える経験を重ねることで、柔軟な人間関係の築き方が自然と身につきます。
職場での人間関係のトラブルが軽減される
協調性がある人が多い職場では、人間関係の摩擦やトラブルが起こりにくい点が特徴です。互いの立場や考え方を尊重する姿勢があるため、意見の食い違いがあっても感情的にならず、冷静に話し合って解決できる環境が生まれます。
小さな誤解や衝突が大きな問題に発展する前に対話で調整できるため、ストレスの少ない職場づくりにもつながります。結果として、チーム全体の雰囲気が穏やかになり、仕事への集中力やモチベーションも高まります。
組織の成果を最大化できる
協調性が高い職場では、個人の能力が単に足し合わされるのではなく、「1+1=3」になるようなチームワークを実現できます。お互いの強みを生かし合い、弱点を補い合うことで、一人では成し得ない成果を生み出せるためです。
協調性のある人はチーム全体の目標を意識しながら、自分の役割を果たすと同時に周囲を支える行動が取れます。結果的に、意見交換や情報共有が活発になり、課題解決のスピードも上がります。また、信頼関係が深まることで、挑戦的なアイデアも受け入れられやすくなり、チームとしての創造性が高まります。
協調性は単なる人間関係の調整にとどまらず、組織全体の成果を最大化し、より大きな価値を生み出す力となるのです。
組織の持続的発展に貢献する
協調性が根付いた職場では、メンバー同士が互いに支え合い、組織全体の成長を持続的に促す土台が形成されます。まず、風通しの良いコミュニケーションが生まれることで、経験やノウハウといったナレッジの蓄積と継承が進み、新しい人材がスムーズに業務を引き継げる環境が整います。
さらに、協調的な関係性が築かれている組織は従業員が孤立しにくく、離職リスクを分散できる点も大きな強みです。人間関係のストレスが軽減されることで、安心して長く働ける職場づくりにつながります。
協調性が高すぎることのデメリット・注意点
協調性は基本的に長所ですが、意識しすぎると次のようなデメリットが生まれる可能性があるため、注意が必要です。
- 意思決定が遅れる
- 責任が曖昧になる
- 革新的なアイデアが出にくい
- 強いリーダーシップを発揮できない
- 職場での人間関係にストレスがたまる
それぞれを詳しく解説します。
意思決定が遅れる
協調性はチームの調和を保つ上で欠かせない要素ですが、全員の意見を尊重しすぎるあまり、意思決定が遅れてしまうデメリットがあります。
周囲の反応を気にしてなかなか結論を出せなかったり、対立を避けるために無難な選択をしてしまったりするケースも少なくありません。特にプロジェクトや業務の進行においては、スピード感が求められる場面も多く、過度な協調姿勢がかえって生産性を下げてしまいます。
責任が曖昧になる
協調性を重んじるあまり、誰が最終的な責任を負うのかが不明確になるという問題が起こることがあります。 全員で意見を出し合い、合意を重視する体制は一見理想的に見えますが、結果的に「みんなで決めたことだから」と責任の所在が曖昧になり、トラブル時に迅速な対応ができなくなるケースがあります。
協調性は大切ですが、役割と責任の線引きを明確にした上で発揮することが重要です。互いを尊重しつつも、最終的な判断者や担当範囲をはっきりさせることで、チーム全体の信頼と成果を両立できます。
革新的なアイデアが出にくい
協調性が強く働く環境では、全員の調和を優先するあまり、斬新な意見や挑戦的なアイデアが出にくくなることがあります。 周囲との関係を崩したくないという意識が働き、「波風を立てない意見」や「多数派に合わせた発言」が増えると、結果的に新しい発想が生まれにくくなります。
特に日本の組織文化では、上下関係や空気を読む風潮が強く、協調性が高い人ほど自分の意見を控えてしまう傾向があります。しかし、イノベーションには時に議論や対立が必要です。互いを尊重しながらも自由に発言できる環境を整えると、チームの結束を保ちつつ新しい価値を生み出す力が育つでしょう。
強いリーダーシップを発揮できない
協調性を重視しすぎると、リーダーが強い決断を下しにくくなる点も課題です。 全員の意見を尊重しようとするあまり衝突を避けたり、場の雰囲気を壊さないように配慮しすぎたりして、結果的に方向性が曖昧になります。特に重要な判断を迫られる場面で、意見の調整に時間をかけすぎるとチャンスを逃してしまいます。
リーダーシップは、独断で進めることではなく、意見を聞いた上で最終的な判断を下す力です。協調性とリーダーシップのバランスが大切です。
職場での人間関係にストレスがたまる
協調性を意識しすぎると人間関係に必要以上の気遣いをしてしまい、精神的な負担が大きくなる点もデメリットです。常に周囲の意見や感情を気にかけて行動するため、自分の本音を押し殺したり、納得できないことにも同調してしまいがちで、知らず知らずのうちにストレスがたまります。
特に、職場で「波風を立てない人」や「空気を読む人」として評価されるほど、自分の意見を言い出しにくくなり、無理をしてしまいます。協調性は大切ですが、他者に合わせるだけでなく、自分を守るバランス感覚も必要です。
協調性がある人の特徴
協調性がある人の特徴は、次のとおりです。
- 傾聴力が高い
- 洞察力がある
- 全体最適を考える
- 感謝を言葉にできる
- 他者から学ぶ意欲がある
それぞれをわかりやすく解説します。
傾聴力が高い
協調性のある人は、相手の話を遮らず、一言一句に真剣に耳を傾ける姿勢を持っています。相手の話を聞く誠実な姿勢は、相手に「自分を大切に扱ってくれている」という安心感を与え、信頼関係を深めるきっかけの一つです。また、傾聴力の高い人は、意見が異なる場面でも感情的にならず、まずは相手の考えを受け止めた上で自分の意見を伝えます。そのため、話し合いが対立ではなく建設的な意見交換へと発展します。
傾聴力は、まさに協調性を形にする第一歩であり、人との信頼を築く基盤といえるでしょう。
洞察力がある
協調性がある人は、相手の言葉だけでなく、表情や態度、声のトーンなどの微妙な変化から感情や意図を読み取る洞察力に優れている点も特徴です。
人や状況の背景にある本質を見抜き、「今この場で何が最も求められているか」を瞬時に判断できます。そのため、トラブルを未然に防いだり、チームの雰囲気が悪化する前に改善策を講じたりといった行動が自然に取れるのです。
洞察力は、周囲との信頼を深める上で欠かせない力であり、協調性をより実践的に発揮するための知的感受性といえます。
全体最適を考える
協調性がある人は、常に自分だけでなくチーム全体の利益や成果を意識して行動できる人です。自分の意見や立場に固執せず、「今この選択が全体にどんな影響を与えるか」を考えながら判断を下します。そのため、組織の目標と個人の役割をうまく両立させ、バランスの取れた行動が取れます。
また、全体最適を考える人は、短期的な成果よりもチーム全体の長期的な成功を重視します。自分の仕事だけでなく、他のメンバーの状況や業務の流れも理解し、必要であればサポートに回る柔軟さがあります。結果的に、チーム内での連携が深まり、自然と信頼関係が築かれるのです。
感謝を言葉にできる
協調性のある人は、周囲の支えや協力を当たり前と思わず、感謝の気持ちをきちんと言葉で伝えられます。「ありがとう」の一言を惜しまない姿勢は、相手に安心感や喜びを与え、チーム全体の雰囲気を温かくします。どんなに小さな助けや気配りにも感謝を示すことで、相手のモチベーションを高め、良好な関係を長く維持できるのです。
感謝を伝える力は協調性の象徴であり、人とのつながりを深め、チームの結束力を高める最もシンプルで効果的なコミュニケーションといえます。
他者から学ぶ意欲がある
協調性がある人は、他人の意見や経験を素直に受け入れ、自分の成長につなげようとする姿勢を持っています。 相手をライバルではなく学びの対象として見られるため、「この人の方法を取り入れてみよう」「この考え方は新しい」と柔軟に吸収できます。そのため、常にアップデート可能です。
また、失敗を恐れずに質問し、教えてもらったことに感謝できるため、信頼関係が自然と深まります。結果として、チーム内での知識共有が活発になり、組織全体の成長にもつながります。他者から学ぶ意欲は、協調性を「受け身の優しさ」から「成長を促す力」へと高める重要な資質です。
協調性がない人の特徴
協調性がない人の特徴は、次のとおりです。
- 他人に無関心
- 自分の考えを言葉にすることが苦手
- 臨機応変に対応できない
- 学ぶ姿勢がない
- 感情の起伏がある
それぞれを詳しく解説します。
他人に無関心
協調性がない人に多く見られる特徴が、他人や周囲の状況への関心の薄さです。自分の業務や成果だけに意識が向き、チームの動きや仲間の気持ちには無頓着な傾向があります。そのため、困っている人がいても気づかない、助けを求められても対応しないなど、結果的に周囲との信頼関係を築けなくなってしまいます。
自分の考えを言葉にすることが苦手
協調性がない人は、自分の考えや気持ちをうまく言葉にできない傾向があります。何を考えているのかが相手に伝わらないと誤解やすれ違いが生じやすく、結果としてチーム内での意思疎通が滞ってしまいます。まず「一言伝えられる」「相手の話に一言添えられる」など、小さなコミュニケーションをきちんととられることが大切です。
臨機応変に対応できない
協調性がない人は、予想外の出来事や他人の考え方の変化に柔軟に対応できない傾向があります。自分のやり方やルールに強くこだわり「正しい」と思い込んでしまうため、環境の変化やチームの方針転換を受け入れられず、結果として衝突や混乱を招いてしまいます。
「自分の考えも一つの意見にすぎない」と捉え、相手の意見や新しい方法にも価値を見いだす姿勢が必要です。
学ぶ姿勢がない
協調性がない人は、他人から学ぼうとする意欲が乏しく「自分のやり方が一番正しい」と思い込みがちです。そのため、周囲からの助言やフィードバックを素直に受け入れられず、せっかくの改善のチャンスを逃します。結果として、仕事の質が伸び悩むだけでなく、社内での関係性が悪くなり、次第に孤立してしまいます。
感情の起伏がある
協調性がない人は、感情の起伏が激しく、状況に応じて冷静に対応することが苦手な傾向があります。ささいなことで怒ったり、気分の浮き沈みが激しかったりすると、周囲は気を遣いすぎてしまい、健全なコミュニケーションが難しくなります。感情的な態度はチーム全体の雰囲気を悪化させ、結果として人間関係の摩擦や誤解を招く原因の一つです。
協調性を身につけさせる方法
企業が社員に協調性を身につけさせる方法は、次のとおりです。
- 新入社員へ研修を実施する
- コミュニケーション促進の仕掛けを作る
- 人事評価で重視する
- 経営層が模範的な行動をする
それぞれを詳しく解説します。
新入社員へ研修を実施する
協調性は、経験や環境によって育まれる後天的なスキルでもあります。そのため、企業は新入社員の段階から意識的に協調性を育てる教育を行うことが重要です。特に、入社直後は社会人としての考え方や行動の基礎を形成する大切な時期であり、入社後すぐに「チームで働く力」を身につけることが、将来の成長に大きく影響します。
例えば、グループワークやロールプレイ研修を行えば、他者の意見に耳を傾けながら議論を進めたり、役割を分担して課題を解決する体験を積めます。
コミュニケーション促進の仕掛けを作る
協調性を育むためには、社員同士が自然に交流し、意見や情報を共有しやすい環境を作る工夫が欠かせません。コミュニケーションの機会が少ないと、互いの考えや状況が見えづらくなり、誤解や距離感が生まれやすいです。そのため、企業が意図的に話すきっかけをつくることで、信頼関係の構築や協力体制の強化が進みます。
例えば、上司と部下が本音で話せる定期的な1on1面談を設ければ、意見交換やフィードバックの習慣が生まれます。また、異なる部署が連携する部門横断プロジェクトを推進すれば、多様な視点を学び、組織全体の一体感を高められます。さらに、気軽に交流できる社内SNSや雑談スペースを設置したり、リラックスした雰囲気で関係を深めるオフサイトミーティングやチーム懇親会も効果的です。
人事評価で重視する
協調性を組織に根づかせるためには、評価制度の中にその重要性の明確な位置付けも大切です。例えば、評価項目に「チームへの貢献度」「他部署との連携力」「周囲へのサポート姿勢」などを加えることで、社員は「協調的に行動することが成果につながる」と実感できます。実際に、チームで成果を上げる姿勢が報われるようになると、自然と互いを支え合う風土が広がります。
経営層が模範的な行動をする
協調性を組織全体に浸透させるためには、経営層や管理職が率先して模範を示すことが重要です。どれほど制度や仕組みを整えても、リーダーが協調的でなければ、社員は協調性の価値を実感できません。上層部の言動は組織の文化を形づくる力を持っており、日々の姿勢が社員の行動指針です。
例えば、経営層が現場の声に耳を傾け、相手の意見を尊重して意思決定を行う姿勢を見せれば、社員も自然と同じ価値観を共有できます。こうしたリーダーの行動が「協調的に働くことが評価される職場」というメッセージを発信し、組織全体の意識を変えるために重要です。
協調性のある人を採用するための見極め方
協調性がある人を採用するステップは次のとおりです。
- 採用要件の明確化(協調性の定義を組織内で統一)
- 書類・事前情報での一次スクリーニング
- 面接での質問設計(行動事例を掘り下げる)
- グループディスカッション・ワークでの観察
- 適性検査・心理測定による補完評価
- 内定後・試用期間での最終確認
それぞれのフローをわかりやすく解説します。
採用要件の明確化(協調性の定義を組織内で統一)
協調性のある人を採用するには、「自社における協調性とは何か」を明確に定義することです。多くの企業が、協調性=人当たりの良さや従順さと混同しがちですが、それでは本質を見誤ります。例えば、「協調性とは単に周囲に合わせることではなく、他者の意見を受け止めながら建設的に意見を交わし、共通の目的に向かって行動できる力を指す」といったように明確にしましょう。
また、職種ごとに求められる協調性の形を具体的に示すことも重要です。例えば、営業職では「関係構築力」や「顧客との信頼形成力」、開発職では「共同解決力」や「情報共有の積極性」といったように、役割に応じた定義を設定します。
さらに、採用評価項目に「チームでの行動」「他者との連携姿勢」といった観点を加え、採用担当者間で判断基準を共有しておき、面接のばらつきを防ぐ工夫も大切です。
書類・事前情報での一次スクリーニング
書類や事前情報での一次スクリーニングでは、まず応募者がチームの中でどのように貢献してきたかに注目します。
職務経歴書やエントリーシートには「自分がどう成果に寄与したか」が具体的に記されているかを確認し、単なる結果報告ではなく過程における協働姿勢を見極めます。また、「○○と協働して」「○○の意見を取り入れて」といった他者との関係性を示す表現が含まれているかも重要な判断材料です。
さらに、職歴や活動履歴に一貫性があり、部活動や長期プロジェクトなどチームに継続的に関わった経験が見られるかも評価します。自己PR文のトーンについても、自分の成果を誇るだけでなく「チーム全体での成果志向」が感じられるかどうかを重視します。
面接での質問設計(行動事例を掘り下げる)
面接では、応募者の協調性をより深く把握するために、行動事例を掘り下げる質問設計が重要です。
STAR面接法(状況・課題・行動・結果)を用いて、「チームで意見が分かれたとき、どのように対応しましたか?」など、実際の経験に基づいた具体的な行動を尋ねます。さらに、他者の視点を確認する質問として「そのとき、周囲はどう感じていたと思いますか?」を加えることで、相手の立場を考える姿勢を測れます。
また、「納得できない意見にどう対応しましたか?」「なぜその行動を選びましたか?」といった問いを通して、感情面と行動面の両方から判断することも有効です。加えて、自己評価ではなく「周囲からどんな人だとよく言われますか?」と他者評価を尋ねることで、本人の認識と周囲の評価のギャップを確認できます。
これらの質問の狙いは、協調性の有無を「考え方」だけでなく、「他者への配慮が行動として表れているか」で見極める点にあります。
グループディスカッション・ワークでの観察
グループディスカッションやワークでは、発言量よりもその質を重視して観察します。場を支配しようとする発言や、逆に沈黙し続ける姿勢ではなく、チーム全体にとって建設的な発言をバランスよく行えているかがポイントです。
また、他者の意見に対してどのように反応するかも重要で、「受け止めた上で自分の意見を加える」姿勢があるかどうかを見極めます。さらに、自然に議論を整理したり、他のメンバーの発言を促したりするなど、ファシリテーション的な行動が見られるかも確認します。
加えて、態度や表情といった非言語的要素も観察対象です。相手の発言にうなずいたり、穏やかな表情や相槌で場の雰囲気を和らげたりするなど、チームに安心感を与える振る舞いができているかが鍵です。協調性は言葉だけでなく会話の流れや雰囲気の中に自然と現れるため、グループディスカッションはその特性を見抜く上で最も有効な場といえます。
適性検査・心理測定による補完評価
適性検査や心理測定は、面接やディスカッションで得た印象を補完し、より客観的に協調性を評価する手段として有効です。例えば、EQ(感情知能)テストでは自己認識力や共感力、人間関係管理の指標から、他者への配慮や感情コントロールの傾向を把握します。また、性格特性を分析するBig Five理論における「協調性(Agreeableness)」のスコアを確認し、協力的・寛容・利他的といった性向の度合いを測定します。
さらに、チーム志向性や対人配慮を評価できる行動特性診断(DISCや16PFなど)も活用し、行動傾向からチーム内での適応力を把握します。 ただし、これらのテスト結果はあくまで参考値として扱い、面接など他の評価結果との整合性を重視して最終判断を行うことが重要です。
内定後・試用期間での最終確認
内定後や試用期間中には、実際の職場環境で協調性がどのように発揮されるかを最終的に確認します。まず、短期プロジェクトやチーム課題を通じて、応募者がどのように他者と協働し、課題に取り組むかを観察します。単に成果を上げるだけでなく、周囲との意見交換やサポートの姿勢など、実践的な協働力が問われます。
また、先輩社員からのフィードバックへの受け止め方を確認します。さらに、本人からの連絡・相談の頻度やタイミングを見て、主体的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢があるかを把握します。加えて、チームメンバーに対して「一緒に働いてやりやすいと感じるか」を尋ねる印象アンケートを実施し、周囲からの評価も合わせて確認します。
協調性がない社員を活躍させる方法
協調性がない社員=能力が低いというわけではありません。協調性がない社員を活躍させる方法は、次のとおりです。
- 個人プレーが活きる仕事にアサインする
- 明確なゴールと裁量を与える
- 個人の成果が全体に貢献する設計にする
それぞれをわかりやすく解説します。
個人プレーが活きる仕事にアサインする
協調性が低い人は、「チーム調整より自分の技術・知識を磨くこと」にモチベーションを感じるタイプです。そのため、無理にチームワーク中心の仕事を任せるよりも、個人で成果を出せる環境を整えると効果的です。例えば、データ分析や研究開発、デザイン、プログラミングなど、集中力や専門性が求められる職種で強みが存分に発揮されます。
また、個人プレー型の社員は、評価の基準が明確であるほど力を発揮します。「成果が正当に評価される仕組み」や「得意分野を生かせる役割分担」をすれば、自発的に高いパフォーマンスを発揮しやすいでしょう。
明確なゴールと裁量を与える
協調性が低い人は、他人から細かく指示されることを強いストレスに感じやすい傾向があります。そのため、マネジメント側は仕事の「進め方」を細かく管理するのではなく、「最終的に達成すべきゴール」の明示が重要です。特に「ここまでは自分の判断で決めて良い」という裁量範囲を設定しておくと、責任感とやる気が一気に高まります。
また、進捗(しんちょく)確認の際も逐一報告を求めるより、成果や課題にフォーカスした対話型のミーティングが効果的です。自由度と責任のバランスを取ることで、協調性が低い人でも自立的に活躍し、結果的にチームの総合力向上にもつながります。
個人の成果が全体に貢献する設計にする
協調性が低い社員でも、自分の成果が組織全体にどう貢献しているかを実感できれば、自然とチーム意識が芽生えます。例えば、個人が担当した分析結果がマーケティング戦略に活用されたり、開発したシステムが他部署の業務効率化につながるなど、「自分の成果が誰かの役に立つ構造」が有効です。本人のモチベーションが高まるだけでなく、「自分もチームの一員として貢献している」という意識が自然と育ちます。
また、成果共有の場を設けて、個人の成果をチーム全体で称賛・共有する文化をつくるのも効果的です。自分の努力が認められ、他者の成果も尊重できる環境を整えれば、協調性が低い社員でも無理なく組織とのつながりを感じながら活躍できます。
協調性を人事評価する際の着眼点
協調性を正しく評価するには、表面的な印象ではなく、行動の質と職場への影響に注目する必要があります。特に注目するべき点は、次のとおりです。
- コミュニケーションの姿勢と質
- チーム貢献・協力行動
- 意見調整力・対立対応力
- 感情知能(EQ)・他者配慮
- 成長意欲・学習姿勢
それぞれを詳しく解説します。
コミュニケーションの姿勢と質
協調性を評価する上で、まず着眼するべき点は、会話の量ではなく対話の質です。「大人しい=協調的」「よく話す=協調的」とは限りません。発言が少なくても、相手の意見を丁寧に聞いて理解を示しながら適切な言葉で返せる人は、信頼される協調的なタイプといえます。
また、会話の中で一方的に意見を押しつけるのではなく、相手の考えを尊重しながら建設的に意見を交換できているかも重要な判断基準です。感情的な反応を控え、冷静に対応できる人ほど、周囲との関係を安定的に築けます。言葉のやり取りを通じて信頼を築けているかどうかを見極めることが、人事評価における本質的なポイントといえます。
チーム貢献・協力行動
協調性を評価する際に重要なポイントは、人間関係の良さではなく「チームの成果にどれだけ貢献しているか」です。
例えば、自分の担当外の業務でも必要とあれば進んでサポートしたり、同僚が困っているときにフォローに回ったりする行動は、直接的な成果以上にチーム全体の力を底上げする重要な貢献です。表立って目立たなくても周囲を支え、全体のパフォーマンスを高める人は組織に欠かせません。
成果の裏にある支援や協力の姿勢までしっかり評価することが、人事評価の精度を高めます。
意見調整力・対立対応力
意見の違いが一切ない職場は、一見平和に見えても、本音を言えない閉鎖的な環境になっている可能性があります。例えば、議論の場で自分の意見を主張しながらも、相手の考えを否定せずに折り合いをつける姿勢やチーム内で対立が起きたときに冷静に双方の意見をまとめられる人は、優れた協調性を持っています。
重要な点は、事実と目的を軸に判断し、全体最適の視点で合意形成を図れるかどうかです。人事評価では、対立をどう乗り越えたか、乗り越える過程でどんな姿勢を示したかを見極めることが大切です。
感情知能(EQ)・他者配慮
協調性を支える重要な要素の一つが、感情知能(EQ)と他者への配慮力です。EQが高い人は、自分の感情を冷静にコントロールしながら、相手の気持ちや状況を的確に察せられます。意見が異なっても、相手の立場を尊重した言葉選びや態度を取ることで、信頼関係を崩さずに意見交換を進められるのです。また、他者配慮とは「優しく接すること」だけではなく、相手の成果を支えるために自ら行動できる姿勢も含まれます。
人事評価では、こうした感情面での成熟度や相手を思いやる姿勢を重視することが大切です。
成長意欲・学習姿勢
協調性の高い人ほど、他者から学ぼうとする姿勢や成長への意欲を持っています。そのため、人事評価では、学びに対してどれだけ前向きか、他人の知見を吸収しようとしているかの丁寧な見極めが重要です。具体的には、業務改善への提案や他部署との情報共有、上司・同僚からのアドバイスを生かした行動変化などが挙げられます。
協調性の本質は「チームとともに成長する姿勢」にあります。つまり、自分の成長が他者や組織の成長につながると理解して行動できる人こそ、真に協調的な人材といえるのです。
協調性に関するQ&A
最後に協調性に関するよくある質問とその回答を紹介します。
自己PRで協調性をアピールする応募者が多い場合、どう差別化するべきか
「協調性」は応募者の多くが使うキーワードであるため、「具体的にどんな行動で発揮したか」に注目しての差別化が大切です。例えば、「チームで協力して成功させました」だけでは抽象的すぎます。「意見の対立を整理し、全員が納得できる方針をまとめた」など、調整力や実行力の裏付けがあるかを確認しましょう。
また、成果の大小よりも「課題をどう解決したか」「他者をどう巻き込んだか」に焦点を当てると実践的な協調性を見抜けます。
協調性がない人の自己PRにはどんな傾向があるか
協調性が低い人は、自己PRの中で「個人の努力」や「自分の実績」ばかりを強調する傾向があります。文章中の主語が「私」に偏り、「チーム」「協力」「連携」といった言葉が少ない点が特徴です。
主語が「私」に偏る応募者は、チームよりも個人成果を優先する傾向があり、入社後に周囲との摩擦を生む可能性が高いです。また、他人との関わりを避けるような語り口「一人で最後までやり切った」が目立つこともあります。
リモート環境で協調性をどう育てるべきか
リモートワークでは、物理的な距離が「心理的な距離」を生み、協調性の低下を招く傾向があります。対策として、意図的にコミュニケーションの機会を設計することが重要です。例えば、定期的な1on1ミーティングや雑談チャンネルの設置、オンライン朝会などを通じて、信頼関係の基盤を作ることが効果的です。
さらに、成果だけでなくプロセスを共有する仕組みを設けることで、「個人の成果」から「チームの成果」へと意識を転換できます。
一般社員と管理職に求められる「協調性」の違いはあるか
一般社員に求められる協調性は、チームの一員として連携・協力し、円滑に業務を進める協調性です。一方で管理職に求められるのは、異なる意見を調整し、チームを一つの方向に導く協調性です。単に調和を保つのではなく、対立を建設的に扱い、最適な意思決定を下すリーダーシップが求められます。どちらも組織の成果を高める上で欠かせない資質です。
まとめ
協調性は、企業経営において重要な要素であり、組織全体の活力を支える基盤となります。経営者は、どのようにして従業員の協調性を引き出すかを考えることで、チームの生産性を向上させることができます。
まず、従業員が互いの意見を尊重し合える環境を整えることが重要です。意見交換の場を設け、共通の目標に向かって協力する姿勢を育むことで、協調性は自然と高まります。また、オープンなコミュニケーションを促進することも効果的です。これにより、従業員は自らの役割を理解し、組織全体の目標達成に向けて自発的に動くようになります。経営者として、協調性を大切にする文化を築くことで、組織はより強固になり、長期的な成功を収めることができるでしょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。










