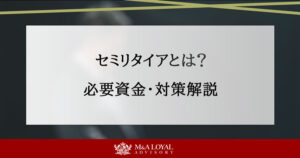住民税の計算方法は?いくら・いつ払う?市民税との違いな徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
住民税の計算は「複雑で、どのように納税額が決められているのかわからない」と考えている人は少なくないでしょう。住民税は毎年の所得に応じて各自治体へ納める身近な税金であり、給与からの天引きや納付書による支払いなど、働き方によって納付方法が変わります。
本記事では、住民税の基本構造や計算方法、納付方法、非課税要件、注意点などをわかりやすく解説します。
目次
住民税とは
まず、住民税の基本的な情報を詳しく紹介します。
住民税の概要
住民税は、居住している地域の自治体へ納める地方税で、市区町村分と都道府県分を合わせたものを指します。
実際の納付は市区町村に一本化されており、受け取った市区町村が後に都道府県分を分配します。徴収された税金は、学校・福祉サービスや上下水道の維持管理、ごみ収集、消防や救急体制など日常生活を支える幅広い行政サービスの財源です。
納付先は「その年の1月1日時点で住民登録のある自治体」と定められており、年度途中で引っ越しても、当該年の住民税を支払う自治体は変わりません。
市民税との違い
結論からいうと、住民税は「総称」であり、市民税は「住民税の内訳の一つ」という関係です。
前述のとおり、住民税は、都道府県が課す「県民税(都民税)」と、市区町村が課す「市民税・区民税・町民税・村民税」の二つで構成されています。
名称は自治体によって異なり、政令指定都市などでは「市民税」、東京23区では「区民税」、町村では「町民税・村民税」と表記が変わりますが、いずれも市区町村分の住民税を指しています。
税率や控除の仕組みは共通です。市民税だけが独自に増減したり、別のルールで課税されることはありません。
所得税との違い
所得税は国に納める「国税」で、収入があった年のうちに源泉徴収や確定申告で精算します。
一方の住民税は都道府県や市区町村に納める「地方税」で、前年の所得に基づき翌年6月から支払いが始まる後払い方式です。
また、税率の仕組みも異なり、所得税が累進課税で収入が多いほど税率が上がるのに対し、住民税は原則一律10%の比例税率に均等割を加えて算定します。
このように、同じ所得課税でも、性質や徴収タイミングに明確な違いがあります。
住民税の申告期限
住民税申告とは、前年の所得や控除の内容を市区町村へ届け出る手続きのことです。この申告によって自治体が住民の所得状況を把握し、6月から翌年5月までの住民税額が決まります。
給与所得者の多くは年末調整で所得情報がそろうため、申告が不要なケースが一般的です。しかし、給与以外の収入がある人、年末調整で処理できない控除(医療費控除や雑損控除など)を適用したい人、あるいは無収入であっても住民税や国民健康保険料の算定に所得状況の確認が必要な人は、住民税申告を行う必要があります。
住民税の申告期間は所得税とほぼ同じ時期に設定されています。所得税は国に納める税で、前年の所得について毎年3月15日までに確定申告を行い、給与所得者であれば年末調整によって精算が完了します。
一方、住民税も同様に前年分の所得を基に申告しますが、その受付期間は通常2月16日から3月15日までです。
住民税の定額減税とは
物価高が続く中、政府は家計の負担を和らげるため複数の支援策を進めています。その一つが、2024年の税制改正で導入された「定額減税」です。
この制度では、納税者本人と同一生計の配偶者・扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円が差し引かれ、1人当たり合計4万円の減税効果が生じます。夫婦とも納税者であれば双方が対象となりますが、合計所得金額が1,805万円を超える場合(給与のみなら2,000万円超)は対象外です。
主に給与所得者と個人事業主、公的年金受給者が減税の適用対象となり、徴収方法によって控除の扱いが異なります。また、住民税が均等割のみの人は減税を受けられません。控除しきれない場合は「調整給付金」として不足分が支給される仕組みも設けられています。
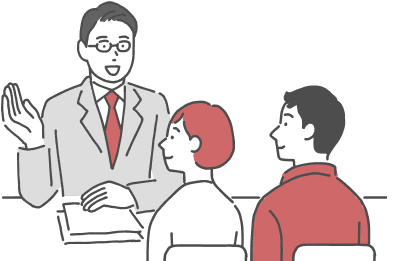
THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。

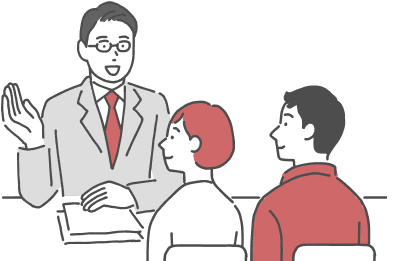
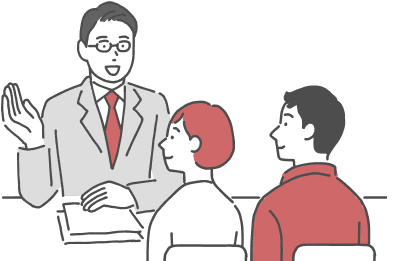
住民税の税率
住民税の税率は、次の二つの要素で構成され、それぞれに異なる計算ルールがあります。
- 所得割
- 均等割
それぞれを分かりやすく解説します。
所得割
所得割の税率は、前年の所得額に応じて負担が増減します。
標準的な税率は合計10%で、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%の割合が基本です。これは全国共通の枠組みで、地方自治体の財源を均等に支えるよう設計されています。
一方で、政令指定都市では役割分担が通常の自治体と異なるため、市区町村分が8%、都道府県分が2%へと配分が変更されます。これは都市部の行政サービスが市側に集中しているため、その負担を税率に反映させているためです。
所得割は、所得から各種控除を差し引いた「課税所得」を基準に計算されるため、収入だけでなく控除の有無によっても税額が変動します。前年の収入が多いほど翌年度の住民税が高くなる仕組みです。
均等割
均等割は、所得の高低にかかわらず、一定額を全ての納税者が負担する仕組みです。
所得割のように前年の収入によって金額が変わることはなく、自治体が定めた固定額が毎年同じように課される点が特徴です。住民として行政サービスを受ける以上、最低限共通して負担すべき費用という位置付けで導入されています。
均等割の標準的な額は、都道府県分が1,000円、市区町村分が3,000円の合計4,000円です。これに加え、令和6年度からは森林保全を目的とした国税「森林環境税」1,000円が一律で上乗せされるため、年間の負担額は合計5,000円となる見込みです。
なお、均等割には、条例で減免措置を設けている自治体もあり、生活保護受給者や一定の所得以下の世帯では負担が免除される場合があります。
住民税の計算方法
住民税は、前述のとおり「所得割」と「均等割」を合算して求めますが、その計算にはいくつかのステップがあります。
- 総所得金額の算出
- 所得控除の適用
- 課税所得の確定
- 所得割額の計算
- 均等割の加算
それぞれを分かりやすく解説します。
総所得金額の算出
住民税の計算は、まず年間の所得を正しく把握することから始まります。
「総所得金額」とは、1月から12月までに得た収入から、その収入を得るために必要だった支出や法令で認められた各種控除を取り除いた金額のことです。
確定申告を行っている人であれば、申告書の合計所得金額欄を確認すればこの数値が分かります。青色申告の場合は、青色申告特別控除を差し引く前の金額が基準です。一方、給与所得者で確定申告をしていない場合は、源泉徴収票に記載されている「課税給与所得金額」が総所得金額として扱われます。
また、前年以前の赤字を繰り越して控除できる制度を利用している場合には、その控除分を反映させた後の金額が最終的な総所得となります。
所得控除の適用
総所得金額を算出した後は、住民税の計算において認められている各種の「所得控除」を差し引きます。
住民税に設けられている控除の種類は所得税とほぼ共通していますが、控除額の水準は所得税とは異なるケースが多く、住民税独自の金額が設定されている点が特徴です。
主な控除の対象は、次のとおりです。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- ひとり親控除
- 障害者控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
会社員の場合、これらの控除の多くは年末調整を通じて反映されますが、医療費控除や雑損控除といった一部の控除は年末調整では扱われないため、自分で確定申告を行わないと住民税の計算に反映されない点に注意が必要です。
課税所得の確定
次に把握すべきなのは「課税所得」です。
課税所得とは、住民税の税率を実際に掛ける対象となる金額であり、最終的な住民税額を決定する上で欠かせない基準です。計算は、総所得金額から自分に適用できる所得控除の合計を差し引くことで求められます。控除が多いほど課税所得は小さくなり、結果として所得割の負担も低く抑えられます。
課税所得は、あくまでも「税額を算出するための調整後の所得」であり、収入そのものを表しているわけではありません。収入から必要経費を差し引き、さらに所得控除を反映した後に残る金額が課税対象になるため、控除の有無によって同じ収入でも課税所得は大きく変わります。
「課税所得=総所得金額−所得控除額の合計」という計算式はシンプルですが、住民税の負担を理解する上で非常に重要なステップといえます。
所得割額の計算
課税所得が確定したら、その金額に住民税の標準税率である10%を乗じて、まず「所得割の基礎額」を求めます。ここで算出される金額はあくまで概算であり、この段階ではまだ調整前の数値です。
住民税では、この後に税額控除と呼ばれる仕組みが適用され、一定の条件を満たす場合には所得割から直接金額を差し引けます。代表的なものとして、ふるさと納税などの寄附金税額控除や、所得税側で控除しきれなかった住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除などがあります。これらを適用すると、最終的な所得割の負担額が調整されます。
さらに、制度改正によって生じる税額の急な増加を抑えるため、「調整控除」という追加の仕組みが設けられており、対象となる場合には所得割額が一定程度減額されます。
均等割の加算
所得割の計算が終わったら、最後に「均等割」を合算して住民税の年額を確定します。
前述のとおり、標準的な金額は都道府県分1,000円と市区町村分3,000円の合計4,000円とされており、自治体に共通する基本的な部分として位置付けられています。
「住民税=所得割+均等割」というシンプルな計算式ですが、均等割は毎年必ず発生するため、住民税の構成要素として重要な役割を持っています。
住民税の具体例
年間で500万円の総所得があるケースを想定して、住民税の計算手順を見ていきます。ここでは、住民税の所得控除額が合計150万円、税額控除はないものとして計算します。
まず、総所得額から所得控除150万円を差し引くことで課税所得が求められます。
500万円 − 150万円 = 350万円
この350万円が、所得割の算定に使われる基礎の金額です。
続いて、課税所得に住民税の標準税率10%を掛けると、所得割額が算出されます。
350万円 × 10% = 35万円
税額控除がないため、この35万円がそのまま所得割の金額です。
ここに、住民税のもう一つの構成要素である均等割5,000円(自治体分4,000円と森林環境税1,000円)を加算すると、年間の住民税額が確定します。
35万円 + 5,000円 = 35万5,000円
なお、実際の計算では多くの人に「調整控除」が適用されますが、ここでは計算の流れを理解しやすくするため省略しています。
住民税の納付方法【基本】
住民税は申告のタイミングは共通ですが、納める方法は納税者の働き方や収入形態によって異なります。住民税の納付方法について詳しく解説します。
普通徴収
普通徴収は、自分で住民税を納める方法で、市区町村から送られてくる「納税通知書」に基づき、決められた期日までに銀行・役所窓口・コンビニなどで納付します。
多くの場合、納付期限は6月・8月・10月・翌年1月の年4期に分かれており、負担を分散しながら支払える仕組みです。
希望すれば、6月に全額をまとめて支払うことも可能で、一部の自治体では早期納付をした場合に「前納報奨金」と呼ばれる割引制度が設けられていました。ただし、前納報奨金は廃止している自治体も多く、現在は実施状況に差があります。
特別徴収
特別徴収は、勤務先が給与から住民税を天引きし、納税者の代わりに自治体へ納付する方式です。
給与所得者は原則として特別徴収が適用され、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から控除されます。給与とその他の所得がある場合、両方を特別徴収で納めることも、給与分だけを特別徴収にして残りを普通徴収にすることも選択できます。
住民税の納付方法【ケース別】
退職した場合など、ケース別の住民税の納付方法についてわかりやすく解説します。
退職した場合
勤務先の給与から住民税を天引きされていた人が退職すると、それ以降の納付方法が変更されます。どの方法になるかは、退職した月によって決まります。
| 退職した月 | 納付方法 |
| 1~5月に退職した場合 | 年度末までの未納分を、退職時の給与や退職金からまとめて差し引く「一括徴収」が一般的です。 |
| 6~12月に退職した場合 | 原則として普通徴収へ切り替わり、自治体から送られる納付書で自分で納めます。希望すれば一括徴収も選べます。 |
なお、退職後すぐに次の勤務先が決まっている場合は、手続きをすることで新しい会社に住民税の特別徴収を引き継いでもらうことも可能です。
海外に長期滞在する場合
海外赴任や留学などで日本を長期間離れる場合、住民税の扱いは住所の状態で異なります。
- 1年以上海外で生活し、1月1日時点で日本に住所がない場合
→その年度の住民税は課税されません。
- 住所を日本に残したまま渡航する場合
→国内居住者として扱われるため、住民税の納付が必要です。
課税対象者には住民税決定通知書が送られてくるため、海外滞在中でも毎年6月頃の通知の有無を確認することが重要です。非課税の人には通知が届かない点にも注意が必要です
公的年金を受け取っている場合
年金収入が一定額を超えると、住民税の対象となります。その際は、会社員の給与天引きと同様に、住民税が年金の支給時に自動で差し引かれる「特別徴収」という方式が適用されます。
年金を受け取るたびに税金が天引きされるため、自身で納付に出向く必要はありません。
ただし、課税されるかどうか、またその金額は、受給している年金額やその他の所得額によって異なります。
毎年6月頃には住民税の計算結果を示す通知書が届くため、必ず内容を確認し、自分の税負担がどのように決まっているか把握しておくことが大切です。
住民税はいつから支払うか
住民税はいつから払うのか分かりやすく解説します。
給与所得者
給与所得者は社会人2年目の6月から住民税の支払いがスタートします。
会社で働き始めた最初の年には、住民税がかからない人がほとんどです。これは、住民税が「前年の所得」を基準に計算される仕組みのため、入社1年目は課税対象となる前年所得が存在しないためです。
1年目の年末に会社で年末調整が行われると、その年の正式な所得額が確定し、自治体が翌年度分の住民税を計算します。そして、翌年の6月から翌々年の5月までの12カ月にわたり、毎月の給与から決められた金額が天引きされる形で納付します。
ボーナスからは引かれず、端数がある場合は6月分で調整されます。
個人事業主・フリーランス
独立して働く人は、自身で確定申告を行った翌年の6月に住民税の支払いが始まります。
税務署と自治体の間で所得情報が共有されるため、申告をしていないと別途自治体への住民税申告が必要になることがあります。
毎年初夏になると「住民税決定通知書」と納付書が自宅へ届き、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4期に分けて支払います。納付方法は金融機関やコンビニの他、自治体によってはクレジットカード払いやスマホ決済も利用できます。一度にまとめて納める選択肢や口座振替によって支払いを自動化する方法もあります。
事業を廃止した場合でもその年の所得は課税対象となるため、翌年の住民税は通常どおり納付する必要があります。事業を途中でやめても、その年の所得に対する住民税は翌年度にかかる点に注意しましょう。
住民税が非課税となる条件
住民税には「所得割」と「均等割」がありますが、一定の条件を満たすと、これらの負担が免除される仕組みがあります。
所得割・均等割の両方が非課税となるケース
住民税は「所得割」と「均等割」で構成されていますが、一定の条件に該当すると両方とも課税されません。生活状況や所得水準への配慮を目的とした制度で、以下のいずれかに当てはまる場合は住民税全体が免除されます。
●生活保護を受けている
生活扶助を受けている場合は、生活基盤を守る観点から住民税は原則として課税されません。
●未成年者・障害者・寡婦(夫)・ひとり親で、前年の所得が135万円以下の場合
属性と所得の両方を基準に判定され、生活負担に配慮して非課税となります。
●所得が自治体の定める基準以下の場合
各自治体には独自の「非課税となる所得基準」があり、それを下回る場合も全額非課税となります。例として、東京都23区の基準は以下のとおりです。
- 単身者:合計所得が45万円以下
- 扶養がある場合:35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円以下
これらの要件に該当すると、所得割・均等割のいずれも課されず、いわゆる「住民税非課税世帯」として扱われます。
所得割のみが非課税となるケース
住民税には「所得割」と「均等割」がありますが、所得割だけが免除となるケースも存在します。これは、前年の収入が自治体が定める一定水準を下回った場合に適用される仕組みです。
●単身者の場合
前年の合計所得が 45万円以下 であれば、所得割は課税されません。
●扶養がいる世帯の基準(東京都23区の例)
扶養家族の人数に応じて基準額が変動し、
35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円以下
であれば所得割が非課税となります。
なお、この基準を満たして所得割が免除されても、「均等割」については対象外のため、年額5,000円程度(自治体により異なる)は納める必要があります。
住民税が高くなる理由
住民税が高くなる主な理由は、次のとおりです。
- 前年より所得が増えている
- 所得控除が減った
- 住民税の非課税ラインを超えた
- 副業や事業所得の増加
- 一時的な収入があった
それぞれを詳しく解説します。
前年より所得が増えている
住民税は、当年ではなく「前年の所得額」を基に税額が決まる仕組みです。そのため、給与のベースアップや残業時間の増加、賞与の増額といった通常の収入アップだけでなく、副業収入や不動産所得、雑所得などが増えた場合も翌年度の住民税に反映されます。
一時的に得た収入であっても、確定申告で所得として計上されれば課税対象となるため、「収入は増えたが実感がないのに税金だけが増えた」と感じるケースも珍しくありません。
また、前年との収入差が大きいほど課税所得が増えやすく、それに比例して住民税の負担も重くなる点に注意しておきましょう。
所得控除が減った
住民税は「所得から各種所得控除を差し引いた金額(課税所得)」を基に計算されるため、控除額が前年より小さくなると、その分だけ課税所得が増え、最終的な住民税額も高くなります。
控除が減る理由は、次のとおりです。
- 扶養親族の人数が減った
- 生命保険料控除・医療費控除などの申告漏れ
- 支払った社会保険料が前年より少ない
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金が減少した
このように、収入が変わっていなくても、控除の内容や金額が前年より小さくなっただけで課税所得が増加し、結果として住民税が上がることがあります。
住民税の非課税ラインを超えた
前述のとおり、住民税には所得が一定以下の場合に税負担を免除する「非課税制度」が設けられています。しかし、前年の所得がこの基準をわずかでも超えると、翌年度から住民税の課税対象となります。
そのため、これまで住民税がかからなかった人にとっては急に納税通知書が届き、「なぜ突然住民税が発生したのか」と驚くケースが多く見られます。
特に影響を受けやすいのは、高齢者や学生、パートタイムの労働者など、所得が非課税基準付近にある人です。少し収入が増えただけでも基準を超えることがあり、結果として均等割(年額5,000円)だけでなく所得割も発生します。
また、自治体ごとに非課税となる所得ラインは異なるため、自分が住んでいる地域の基準を確認しておくことも大切です。基準を超えると住民税の負担が一気に生じるため、収入が増えるタイミングでは住民税の変動にも注意が必要です。
副業や事業所得の増加
本業とは別に、副業収入やフリーランスとしての収入が増えると、その分も含めて前年の所得が合計されます。住民税は「全ての所得を合算した金額」を基に計算されるため、給与以外の収入が増えれば、その増加分も課税対象に加わり、結果として税額が上がります。
会社員であっても例外ではありません。例えば、雑所得(副業の報酬やネット収入)、事業所得(個人事業の利益)、不動産所得(家賃収入)などが前年より増えた場合、その分だけ課税所得が大きくなるため、住民税の負担も増加します。
こうした追加収入は、確定申告によって税務署に申告され、その情報が市区町村にも共有されることで、翌年度の住民税に反映される仕組みです。
副業を始めた年や事業収入が大きく伸びた年は、翌年の住民税が上がることを見越して資金計画を立てましょう。
一時的な収入があった
臨時的な収入がある場合でも、住民税の計算では原則として全て課税対象に含まれます。
例えば、競馬や競輪の払戻金、パチンコなどで得た利益、一時的に受け取った謝礼や臨時ボーナス、事業で偶然生じた特別な利益、株式売却益、仮想通貨の売買による利益などが該当します。ただし、競馬や競輪の払戻金は一定の条件下で非課税となる場合があるため、その点に注意が必要です。
こうした収入は継続的な所得ではなくても、その年の総所得に加算されるため、結果として課税所得が増え、翌年度の住民税額が上昇する要因となります。また、株や暗号資産の売却益は金額が大きくなりやすく、住民税に与える影響も無視できません。
住民税を安くする方法
住民税を安くする方法は、次のとおりです。
- ふるさと納税を活用する
- iDeCo・小規模企業共済など掛金控除を利用する
- 医療費控除・生命保険料控除などを確実に申告する
それぞれを詳しく解説します。
ふるさと納税を活用する
住民税の負担を軽くしたい場合、最も取り入れやすい方法が「ふるさと納税」です。応援したい自治体へ寄附をすると、自己負担の2,000円を除いた金額が翌年度の住民税から差し引かれる仕組みで、節税と地域貢献を同時に行えます。
寄附先の地域から名産品などの返礼品を受け取れる点も人気の理由です。
ただし、控除される金額には上限があり、年収や家族構成によって大きく変わります。上限額を超えて寄附をすると、その超過分は税金控除の対象にならず、純粋な寄附として扱われます。そのため、寄附前にシミュレーションで適用上限を確認することが重要です。
iDeCo・小規模企業共済など掛金控除を利用する
将来の備えをしながら住民税の負担を抑えたい場合に有効な方法が、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済といった制度です。
これらの制度に拠出した掛金は、その全額が所得控除として扱われます。控除が増えるほど課税の対象となる所得が小さくなるため、結果として翌年度の住民税が下がります。
特に個人事業主やフリーランスは掛金上限額が大きく、サラリーマン以上に節税効果が高まりやすい点が特徴です。会社員の場合でも、企業年金の有無に応じて一定額まで積立が可能で、無理のない範囲で老後資金を準備しながら税負担を軽減できます。
加入の際は、拠出限度額や運用リスクも含めて総合的に検討しましょう。
医療費控除・生命保険料控除などを確実に申告する
住民税を抑えるためには、適用できる控除を漏れなく反映させることが欠かせません。特に「医療費控除」や「生命保険料控除」は、多くの人が対象になるにもかかわらず、申告し忘れてしまうことが少なくありません。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に使える制度で、病院代だけでなく、治療に関連する交通費なども対象となる点が特徴です。また、生命保険料控除は、加入している生命保険・医療保険・介護保険などの保険料に応じて控除が受けられます。
これらの控除は年末調整だけでは反映されないケースも多いため、必要に応じて確定申告が必要です。申告により控除額が増えると課税所得が減り、その分翌年度の住民税が軽くなります。
住民税のよくあるトラブル・注意点
住民税のよくあるトラブル・注意点は、次のとおりです。
- 退職・転職すると住民税の支払い方法が変わる
- 引っ越した年は旧住所に住民税の納付書が届くことがある
- 住民税を滞納すると負担額が大きくなる
- 副業がバレる
それぞれを分かりやすく解説します。
退職・転職すると住民税の支払い方法が変わる
仕事を辞めたり転職したりしても、その年の住民税の支払い義務が急になくなるわけではありません。むしろ、退職をきっかけに納付方法が変わることで、想定外の請求が届きやすい点に注意が必要です。
例えば、在職中は給与から毎月天引きされていた住民税(特別徴収)も、退職後は自分で納める普通徴収へ切り替わることが一般的です。また、退職した時期によっては、未払分を最後の給与や退職金からまとめて差し引く「一括徴収」が行われる場合もあります。
こうした取り扱いは退職のタイミングによって変わるため、事前に会社の担当者へ確認し、どの方法が適用されるのか把握しておくことが大切です。
引っ越した年は旧住所に住民税の納付書が届くことがある
住民税は、その年の1月1日に住んでいた自治体が課税・徴収を担当する仕組みになっています。つまり、年度の途中で別の地域へ引っ越した場合でも、住民税の案内や納付書は新住所ではなく、元の住所へ送られます。
引っ越し後に納付書が届かないまま気付かずにいると、納期限を過ぎて督促状が届いてしまう可能性があります。
転居の際は、郵便局で旧住所宛ての郵便物を新住所に転送する手続きを行い、住民税の通知を確実に受け取れるようにしておきましょう。
住民税を滞納すると負担額が大きくなる
住民税を期限どおりに納めないまま放置すると、税額とは別に延滞金が加算されます。
延滞金は遅れた日数に応じて増えていくため、時間がたつほど支払う総額が大きくなる仕組みです。また、納付が行われない状態が続くと、「督促状」の発送や、銀行口座・給与などの差し押さえといった強制徴収の手続きに進むこともあります。
結果として、本来よりも大きな負担につながるリスクが高まります。もし納付が難しい状況であれば、早めに自治体へ相談し、分割払いなど無理のない方法を検討することが大切です。
副業がバレる
副業で得た収入を確定申告すると、その分だけ合計所得が増えるため、翌年度の住民税額も高くなります。
住民税は原則として勤務先を通じて天引きされるため、市区町村が計算した住民税額が会社へ通知される仕組みです。その結果、給与に対して不自然に高い住民税が適用されると、会社側が「副業収入があるのでは」と気づく可能性が生じます。
副業の事実を職場に知られたくない場合は、確定申告の際に副業分の住民税を自分で納める「普通徴収」を選ぶことが重要です。普通徴収を選択すれば、会社には本業分のみの住民税が通知され、副業による増加分は勤務先に知られずに自分で納付できます。
住民税に関するQ&A
最後に、住民税に関するよくある質問とその回答を紹介します。
住民税はアルバイトやパートでも支払う必要があるか
アルバイトやパートといった働き方であっても、年間の所得が一定額を超えると住民税の納付が必要です。学生であっても、主婦のパート勤務であっても、「収入が非課税基準を上回ったかどうか」で判断されるため、雇用形態そのものは課税の有無に影響しません。
一般的に、給与所得だけで生活している場合は、年収がおおむね百万円台前半を超えると住民税がかかるケースが多いとされています。
これは、住民税の基礎控除や給与所得控除を差し引いた後の所得額が自治体の非課税基準を上回るためです。基準の細かな数字は自治体によって多少の差がありますが、収入が増えるほど翌年度の住民税が発生しやすくなります。
住民税の申告は確定申告と何が違うのか
住民税の申告と確定申告は、どちらも前年の所得を自治体や税務署に知らせるための手続きですが、目的や扱われ方には明確な違いがあります。
確定申告は国税である所得税の計算を確定させるための制度で、税務署へ提出します。これに対して住民税申告は、地方税である住民税の課税額を自治体が決めるための手続きで、市区町村へ提出します。
確定申告を行った人は、その内容が自治体へ自動的に共有されるため、改めて住民税申告を行う必要はありません。一方、確定申告が不要であっても、給与以外の収入がある人や、扶養控除・医療費控除などの適用を受けたい人は市区町村へ住民税の申告を行わないと正しい税額が計算されません。申告をしないままにしておくと、所得があるのに「収入がない」とみなされ、非課税判定や行政サービスの受給に影響が出る場合があります。
つまり、確定申告は所得税の確定のために行う国への申告で、住民税申告は住民税の算定のために行う自治体への申告です。どちらが必要かは収入形態や控除の有無によって異なります。
年間20万円以下なら住民税の申告は不要なのか
「年間20万円以下の副業収入は申告不要」という話を聞くことがありますが、これは所得税の制度であり、住民税には適用されません。
住民税は、所得の種類や金額に応じて正しく課税するため、20万円以下の副業収入であっても原則として自治体への申告が必要です。特に給与以外の所得(雑所得・事業所得・不動産所得など)がある場合、その金額に関係なく住民税の申告書を提出しなければ、税額が正しく計算されません。申告をしないまま放置すると、後から修正を求められたり、未申告扱いとなるリスクもあります。
住民税は分割で支払えるか
住民税は、一度に全額を支払う必要はなく、原則として年4回に分けて納付できる仕組みです。納付書が届くと、6月・8月・10月・翌年1月の4期に分割されており、家計の負担を平準化しながら支払えます。
また、経済的な事情で期日どおりの納付が難しい場合は、自治体に相談することで、支払期限の延長や追加の分割に応じてもらえることがあります。このような措置は、事前に相談した場合に限り認められることが多く、何も連絡しないまま滞納すると延滞金が上乗せされるため注意が必要です。
負担が大きいと感じたときは早めに自治体へ相談し、自分に合った支払い方法を調整することが大切です。
住民税が給与から天引きされないのはなぜか
住民税が給与から天引きされない場合は、勤務先で「特別徴収」の手続きが行われていない可能性が高いです。
特に転職後まもないタイミングでは、前職からの情報が自治体に引き継がれる前で手続きが間に合っていないことがあります。また、企業の規模や事務体制によっては、従業員の住民税をあえて普通徴収(自分で納める方式)にしているケースも存在します。このような状況では、自宅へ住民税の納付書が届くため、自分で期限内に納付する必要があります。
まずは会社の給与・人事担当者に確認し、特別徴収へ切り替えられるかどうかを早めに相談しましょう。
住民税の督促状はいつ届くのか
住民税の督促状は、納付期限を過ぎてからおおむね20日以内に発送されることが一般的です。
普通徴収の場合は6月・8月・10月・翌年1月の4期に納付期限がありますが、いずれかの期日に遅れると速やかに督促状が送付されます。自治体によって時期に多少の差はありますが、法律上「期限後20日以内に督促」と定められているため、期限直後に届くことも珍しくありません。
また、督促状の後も支払いが確認できなければ、「催告書」や「差押予告通知」が順次届く場合があり、延滞金も増えていきます。
扶養に入ると住民税はどうなるか
扶養に入るかどうかで、扶養される側・扶養する側の住民税の扱いは変わります。
まず扶養に入る本人については、収入が一定以下であれば住民税の非課税基準を満たしやすく、結果として住民税がかからないケースが多いです。学生やパート収入が少ない配偶者が非課税となる典型的な理由がこれにあたります。
一方、扶養する側(親や配偶者など)は、家族を扶養していることで「扶養控除」や「配偶者控除」「ひとり親控除」などの各種控除が適用されます。控除額が増えると課税所得が小さくなるため、住民税の負担が軽減される仕組みです。
つまり、扶養に入ると本人は非課税になりやすく、扶養する側は控除によって住民税が下がる可能性があるという双方に影響が及びます。
ボーナスからも住民税は引かれるか
住民税は、1年間の税額を12カ月に分割して毎月の給与から差し引く「月割り方式」で運用されています。そのため、夏や冬に支給されるボーナス(賞与)から住民税が天引きされることはありません。
会社員の方が受け取るボーナスには、所得税は源泉徴収されますが、住民税はあくまで通常の給与で負担する仕組みです。「ボーナスが増えたのに住民税が変わらない」のは、そのためであり、賞与額に連動することはありません。
住民税が増減するのは、前年の所得全体が変動した場合や、控除内容に違いが出た場合のみです。
まとめ
住民税の計算方法は少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解することで、どのように税額が決まるのかを把握できるようになります。住民税は前年の所得に基づいて計算され、所得割と均等割という2つの部分から成り立っています。計算における重要なポイントは、所得控除の適用や課税所得の確定です。
住民税の負担を軽減するためには、ふるさと納税やiDeCoなどの制度を活用することを検討してみましょう。また、納付方法についても自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
これらの情報をもとに、自分の住民税がどのように計算されているのかを確認してみてください。もし不安や疑問がある場合は、自治体の窓口で相談するのも一つの手です。次に何をすべきか明確にし、適切な対応を取ることで、住民税に関する不安を解消していきましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。