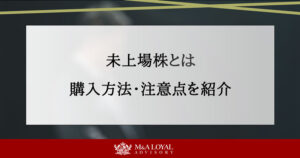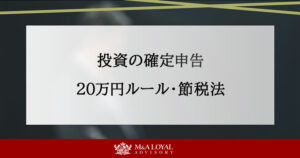反対売買とは?意味やメリット、差金決済、空売りをわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
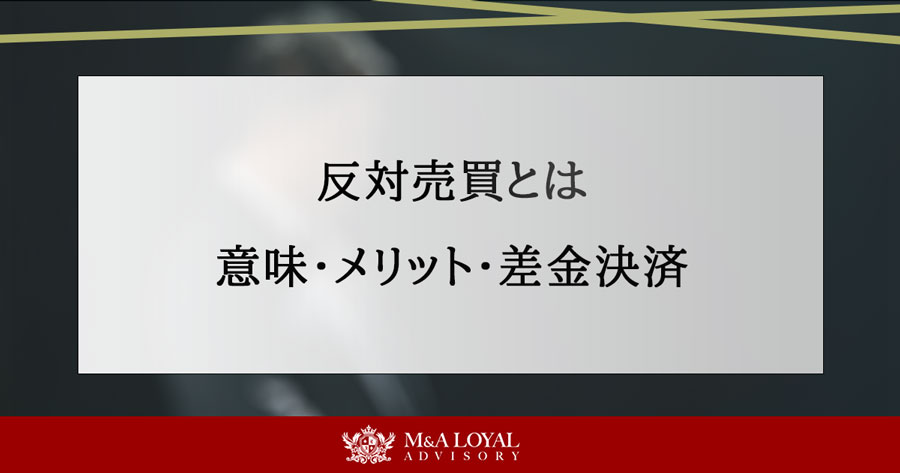
反対売買とは、買ったものを売り、売ったものを買い戻すことで取引を完結させ、最終的な損益を確定する方法です。現物株の売買では意識しづらい概念ですが、信用取引やデリバティブ取引(先物・オプション)では日常的に用いられています。
本記事では、反対売買の基本的な仕組みから、差金決済や手仕舞い、建玉といった関連用語の解説まで、初心者の方でも理解しやすいように整理しました。
さらに、信用取引における反対売買の具体的な流れ、強制決済や追証のリスク、現引・現渡といった他の返済方法との違いも紹介します。これから信用取引を始めたい方や、投資知識を体系的に学びたい方はぜひお役立てください。
目次
反対売買の意味とは?
まず反対売買の概要について説明します。
反対売買の概要
反対売買とは、信用取引や先物・オプションといったデリバティブ取引において、当初の取引と反対の売買を行うことでポジションを解消し、決済する仕組みを指します。
現物取引の場合は、買った株を長期にわたり保有することが可能ですが、信用取引や先物取引には最終決済期日が存在し、その期日までに必ず反対の売買を行ってポジションを解消する必要があります。信用取引には通常6カ月の返済期限があり、これを「絶対期日」と呼びますが、その期日までに反対売買を行わなければなりません。
逆に絶対期日に売買を行うことを満期決済といいます。ポジションについては後述します。
差金決済とは
信用取引では、投資家が証券会社から資金や株券を借りて取引を行うため、買い建ての場合は担保となっている株式を転売して資金を返済し、売り建ての場合は担保となっている売却代金で株券を買い戻すことで取引を終了させます。
このときの決済は株券や代金の総額ではなく、買い代金と売り代金の差額で精算され、証券会社と顧客の間で損益が授受される仕組みです。このように、現物の受け渡しを伴わずに売買差額のみで清算する方法を「差金決済」と呼びます。
差金決済は信用取引や先物・オプション取引などのデリバティブ取引に広く用いられており、少額の証拠金や担保で大きな取引を行える点が特徴です。現物株式の売買のように株券や資金を実際にやり取りする必要がないため、資金効率が高い反面、短期間で大きな損益が発生しやすい点には注意が必要です。
手仕舞いとは
手仕舞いとは、株式や先物、オプションなどの取引において、保有しているポジションを決済して取引を終了させることをいいます。
例えば、株式を買い建てていた場合には売却して決済し、逆に売り建てていた場合には買い戻して決済することで、損益が確定します。投資家が利益を確定させたいときや損失を限定するために取引を終わらせたいときに行われ、市場からいったん撤退することを意味します。
手仕舞いの代表的な方法の一つが「反対売買」であり、当初の取引と逆方向の売買を行うことでポジションを解消し、差額で損益を清算する仕組みです。「利確」「損切り」なども同じ意味で使用されます。
建玉とは
建玉(たてぎょく)とは、投資家が株式や先物、オプション、FXなどで新規に売買注文を行い、その結果としてまだ決済されていない未了の契約を指す言葉です。「ポジション」ともいいます。つまり、取引を開始した段階で「買い」あるいは「売り」の形で保有している状態を建玉と呼びます。例えば株式を信用取引で買い建てた場合は「買い建玉」、売りから入った場合は「売り建玉」と表現されます。
建玉は、後に反対売買などによって決済されるまで維持され、その間は含み益や含み損が発生します。投資家にとっては、建玉の管理が損益の管理に直結するため、どの銘柄をどれだけ保有しているか、どの価格で建てたかを把握しておくことが非常に重要です。
ちなみに「建玉」という言葉に含まれる「玉(ぎょく)」の語源にはいくつかの説があります。その中でも有力とされるのが、かつて芸者や料亭で渡すご祝儀を「玉代(ぎょくだい)」と呼んでいたことに由来するという説です。
また、「建玉整理」とは両建している買建玉と売建玉を、同数量で相殺する注文方法です。また、建玉を翌営業日に持ち越すことを「ロールオーバー」といいます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



反対売買が行われる取引の種類
反対売買が行われる取引は次の2つに大別されます。
- 信用取引
- デリバティブ取引
それぞれを解説します。
信用取引
信用取引とは、投資家が証券会社から資金や株券を借りて行う取引のことです。
投資家は自己資金だけでなく証券会社からの借り入れを利用することもできるため、レバレッジを効かせて大きな取引が可能になります。ただし、借りた資金や株券は最終的に返済しなければならず、期日までに反対売買を行ってポジションを解消し、損益を差金決済で清算する必要があります。
具体的には、買い建てた場合は売却(転売)によって、売り建てた場合は買い戻しによって建玉を整理します。このように信用取引における反対売買は、借り入れた資金や株券を清算するための基本的な仕組みとなっています。
デリバティブ取引(先物取引・オプション取引)
デリバティブ取引とは、先物やオプションといった金融派生商品を対象とする、比較的新しい金融商品の取引の総称です。
先物取引では、あらかじめ定められた期日に、あらかじめ約定した価格で資産を売買する契約を結びます。買い建てた場合は期日前に市場で売却し、売り建てた場合は市場で買い戻すことで決済が行われ、当初の約定価格と反対売買時の価格との差額が損益として確定します。
これに対し、オプション取引は「将来、特定の価格で売買する権利」を取引するものであり、必ずしも行使する必要がない点が特徴です。投資家は買った権利を市場で転売することもでき、また売り建てた権利を買い戻して消滅させることもできます。
信用買いポジションを反対売買で決済する流れ
信用買い(空買い)から取引を開始し、反対売買を実行する流れは次のとおりです。
- 信用買いで建玉を持つ
- 決済タイミングを判断する(利確・損切り)
- 信用売り注文を出す(売埋)
- 反対売買で差金決済が成立する
- 損益が確定する
- 強制決済の可能性
それぞれの手順を分かりやすく解説します。
信用買いで建玉を持つ
「信用買い」とは証券会社から資金を借り入れて株式を購入する取引で、投資家は実際に株式を所有しますが、その資金は借り入れによって賄われています。
現物取引と違い、自分の手持ち資金以上の株式を購入できるため、少ない資金で大きな取引が可能になる点が大きな魅力です。
ただし同時に返済の義務も生じるため、必ず期日までに建玉を整理する必要があります。この段階で投資家は「いずれ売却して借入資金を返済しなければならない」という前提を抱えて取引を進めます。
決済タイミングを判断する(利確・損切り)
信用買いの建玉を保有している間、株価は常に変動します。投資家は株価の動きを注視しながら、「どの時点で手仕舞いを行うか」を判断します。
株価が買値より上昇している場合は利益を確定するチャンスであり、いわゆる「利確」の局面です。一方で株価が下落して含み損が拡大している場合には、これ以上の損失を避けるために「損切り」を決断する必要が出てきます。
どちらの場合でも、反対売買による決済は投資家の戦略的な選択であり、利益追求とリスク管理のバランスを取る重要な意思決定プロセスといえます。
信用売り注文を出す(売埋)
決済のタイミングを決めた投資家は、証券会社を通じて「信用売り注文」を発注します。これは当初の信用買いに対して逆方向の取引を行うもので、業界用語では「売埋(うりうめ)」と呼ばれます。
売埋によって、投資家は借り入れた資金で購入した株式を市場で売却することになり、ポジションを解消する準備が整います。
反対売買で差金決済が成立する
信用買いを売埋で決済すると、反対売買が成立します。
この決済は株券そのものの受け渡しではなく、買い付け時の価格と売却時の価格の差額だけをやり取りする「差金決済」で行われます。
証券会社はこの差額を投資家の口座に反映させると同時に、借り入れていた資金の返済を清算します。現物取引のように株券を持ち続けるわけではなく、あくまで差額のやり取りで完結する点が信用取引における大きな特徴です。
損益が確定する
反対売買が成立すると、投資家の損益が確定します。
株価が上昇していた場合は利益を手にでき、逆に下落していた場合は損失を受け入れることになります。この時点で投資家の建玉は解消され、信用買いポジションはゼロになります。
いわゆる「手仕舞い」が完了した状態です。ここで得られた経験や結果は、次の投資戦略を考える上での重要な材料です。
強制決済の可能性
なお、投資家が自ら反対売買を行わず、返済期日を過ぎてしまった場合には、証券会社が投資家に代わって建玉を決済する「強制決済」が行われます。
また、株価下落により担保として預けている保証金が不足し、追証(追加証拠金)の入金がなされない場合も、証券会社が強制的に売埋注文を執行することがあります。
これにより、投資家は望まないタイミングで損失を確定させられることになるため、常に建玉と保証金の状況を把握しておくことが求められます。
信用売りポジションを反対売買で決済する流れ
逆に信用売り(空売り)から取引を開始し、反対売買を実行する流れは次のとおりです。
- 信用売り(空売り)で建玉を持つ
- 株価動向を見て買い戻しのタイミングを判断
- 信用買い注文を出す(買埋)
- 反対売買で差金決済が成立する
- 損益が確定する
それぞれの手順を解説します。
信用売り(空売り)で建玉を持つ
信用取引の大きな特徴の一つが「信用売り(空売り)」です。投資家は証券会社から株券を借りて市場で売却し、売却代金を証券会社に担保として預けます。これにより、手元に株を持っていなくても「売りから取引を始める」ことが可能です。
投資家は後日、その株券を買い戻して証券会社に返却する必要があるため、必然的に反対売買で決済する流れが生じます。信用売りの建玉を持った段階で、投資家は株価が下がれば利益、逆に上がれば損失というポジションを取っていることになります。
株価動向を見て買い戻しのタイミングを判断
信用売りを行った後、投資家は株価の動きを注視しながら買い戻しのタイミングを探ります。株価が下落していれば、売却価格と買戻し価格の差額が利益となるため、利益確定のために決済を検討します。
一方で、株価が予想に反して上昇すれば、損失が拡大するリスクを抑えるために損切りを決断しなければならない場合もあります。
信用買い注文を出す(買埋)
決済を行うと決めた投資家は、市場に「信用買い注文」を出します。
これは当初の信用売りに対して反対方向の取引を行うものであり、業界用語では「買埋(かいうめ)」と呼ばれます。買埋によって投資家は市場から株券を調達し、それを証券会社に返却することで、借りていた株券の義務を解消する準備が整います。
反対売買で差金決済が成立する
投資家が信用買い注文を出し、買埋によって建玉を解消すると反対売買が成立します。このときも現物株の受け渡しは行われず、売却時の価格と買戻し時の価格との差額だけが清算されます。証券会社はこの差額を投資家の口座に反映させ、同時に借りていた株券の返却処理を行います。
損益が確定する
反対売買が成立した時点で投資家の損益が確定します。株価が下落していれば利益が発生し、上昇していれば損失を抱えることになります。信用売りポジションはここで完全に解消され、建玉はゼロになります。これによって、投資家は市場から撤退し、次の取引に備えられます。
信用売りポジションの反対売買でも強制決済の可能性があります。
反対売買以外の返済の方法
反対売買以外には次のような返済方法があります。
- 現引(品受)
- 現渡(品渡)
それぞれを分かりやすく解説します。
現引(信用買い→現物株受渡し)
現引(品受)とは、信用買いで取得した株式の返済方法の一つです。通常の信用買いでは、期日までに反対売買(=売埋)を行い、差金決済によって建玉を解消します。しかし現引を選択すると、投資家は自分の資金を新たに証券会社に差し入れることで、信用取引で購入した株式をそのまま現物株として受け取れます。
これにより、信用取引の返済義務は消滅し、投資家は現物株主となります。信用期日の制約を回避できる一方で、追加の資金が必要となるため、資金繰りに余裕がある場合や長期保有を目的とする場合に利用されます。
現渡(信用売り→手持ち株式を差し入れ)
現渡しとは、売り建てた株式を通常のように買い戻して差額で清算するのではなく、あらかじめ手元にある、あるいは別の手段で入手した同一銘柄・同一株数の株式を差し入れることで決済する方法です。
制度信用取引では6カ月という返済期限が設けられており、その期間中に株価が下落せず買い戻しが難しい場合に、代替手段として利用されることがあります。
なお、現渡しは「つなぎ売り」と呼ばれる取引で活用されるケースもあります。つなぎ売りとは、保有している株式を売却せずに同じ銘柄を空売りすることで、株価下落時の評価損を空売りによる利益で相殺しようとするリスクヘッジの手法です。
追証とは
次に追従の概要について解説します。
追証の概要
追証(おいしょう/追加証拠金)とは、信用取引や先物取引などで建玉を保有している際に、相場の変動によって評価損が膨らみ、証券会社に預けている保証金(証拠金)が必要な水準を下回った場合に、追加で差し入れを求められる証拠金のことをいいます。
信用取引では、建玉を維持するために「委託保証金率」や「委託保証金維持率」と呼ばれる一定の比率が定められており、この基準を下回ると追証が発生します。投資家は、指定された期限までに不足分を入金しなければなりません。追証に応じられない場合、証券会社は投資家の判断を待たずに建玉を強制的に反対売買し、ポジションを整理する「強制決済(ロスカット)」を行うことになります。
追証は、レバレッジをかけた取引に伴うリスクを象徴する仕組みであり、元本以上の損失を抱える可能性を示す重要な概念です。そのため、信用取引や先物取引を行う投資家にとって、保証金の水準や追証の仕組みを理解し、余裕資金で取引を行うことが極めて大切です。
委託保証金率・委託保証金維持率とは
委託保証金率とは、信用取引で新しく建玉を持つ際に必要となる保証金の割合を示すもので、約定代金に対してどれだけ保証金を預ける必要があるかを表します。法律上は、約定代金の30%以上かつ30万円以上の保証金を差し入れなければならないと定められています。
例えば、信用取引で1,000万円分の株式を買い付ける場合、最低でも約定代金の30%にあたる300万円を保証金として用意する必要があります。実際の保証金率は証券会社ごとに基準が設けられています。ただし、銘柄ごとの信用取引規制や証券会社の判断によっては、基準が引き上げられる場合もあります。
追従が必要になる状況
信用買いで株価が下落した場合
信用買いは、証券会社から資金を借りて株式を購入する取引で、株価が上昇すると利益が得られます。しかし、株価が購入時よりも下落すると含み損が発生し、その損失は保証金の価値を直接的に減少させます。
委託保証金維持率が基準(一般的には30%程度)を下回ると、証券会社は追証を請求します。信用買いは現物取引に比べてレバレッジがかかっているため、株価が大きく下がらなくても保証金不足に陥ることがあり、損失拡大に伴う追証リスクは常に存在します。
信用売りで株価が上昇した場合
株価の上昇が続けば含み損が膨らみ、証券会社に預けている委託保証金(担保金)の評価額が相対的に小さくなっていきます。その結果、委託保証金維持率が規定の基準を下回った場合、証券会社は投資家に追加保証金(追証)の差し入れを求めます。
特に株価が急騰する場面では短時間で大幅な損失が生じる可能性があり、追証リスクが最も高い取引の一つといえます。
担保としている有価証券の値下がり
信用取引では、現金だけでなく保有している株式や投資信託などを「代用有価証券」として保証金に充当できます。しかし、代用有価証券の価格が下落すると、その評価額も減少し、保証金維持率が低下することになります。
これによって建玉の規模に対して保証金が不足する状態になり、追証が発生することがあります。代用有価証券は市場環境の影響を直接受けるため、投資家が想定していない局面でも追証が必要になる点に注意が必要です。特に株式市場全体が下落している局面では、建玉の含み損と担保の評価減が同時に進行し、追証のリスクが一気に高まります。
信用取引の種類
信用取引は次の2種類に大別できます。
- 制度信用
- 一般信用
それぞれを分かりやすく解説します。
制度信用
制度信用取引とは、証券取引所や日本証券金融が取引条件を定めている信用取引の一種です。取引可能な銘柄はあらかじめ取引所によって指定されており、それ以外の銘柄で制度信用取引を行えません。
この取引の大きな特徴の一つが返済期限で、最長6カ月と定められています。そのため、現物株のように無期限で保有し続けることはできず、長期間損失を抱えたまま塩漬けにするリスクを避けられる点は投資家にとってメリットといえます。
一方で、制度信用取引にはデメリットも存在します。特に注意が必要な点が「逆日歩(品貸料)」です。信用売り(空売り)が買い建てを上回り、市場で株が不足した場合、不足分を調達するためのコストが発生します。この調達コストは売り建てを行っている投資家が負担する仕組みであり、これが逆日歩の支払いとして現れます。逆日歩がついた場合、投資コストが増大し、想定外の損失につながることもあります。
一般信用
一般信用取引とは、制度信用取引とは異なり、取引条件を証券会社が独自に決定する信用取引のことです。取引可能な銘柄は証券会社ごとに選定されるため、制度信用取引では扱えない銘柄であっても、一般信用取引であれば取引できる場合があります。
返済期限についても制度信用取引とは大きく異なり、証券会社によっては無期限での取引を認めているケースもあります。このため、長期的にポジションを保有したい投資家にとって有利な仕組みといえます。
また、制度信用取引と違って逆日歩(品貸料)が発生しない点も、投資コストを安定させたい投資家にとって大きなメリットです。
ただし、デメリットも存在します。証券会社が貸し出せる株式を十分に保有していない場合、信用売り(空売り)ができなくなる可能性があります。また、一般信用取引では金利や貸株料などの費用体系が制度信用取引と異なる場合が多いため、取引を始める際には事前に証券会社ごとの条件を確認しておくことが重要です。
信用取引のメリット
そもそも信用取引にはどんなメリットがあるのでしょうか。主なメリットは次のとおりです。
- レバレッジ効果
- 1日に何度も取引できる
- 「売り」から始められる
それぞれを解説します。
レバレッジ効果
信用取引の最も大きなメリットは、レバレッジ効果によって手元資金以上の取引ができることです。現物取引では、自分が用意した資金の範囲内でしか株を購入できません。ところが信用取引では、証券会社に委託保証金を差し入れることで、その数倍の規模の取引が可能です。
例えば委託保証金率が30%の場合、100万円の保証金を預ければ、約300万円分の株式を取引できるわけです。このように、少額の元手でも大きな取引を可能にする仕組みがレバレッジ効果です。
この効果により、投資家は相場の小さな値動きでも大きな利益を得られる可能性が高まります。例えば、現物取引で100万円分の株を買い、株価が10%上昇した場合、利益は10万円にとどまります。しかし信用取引で同じ100万円を保証金として300万円分の株を購入すれば、10%の値上がりで30万円の利益を得られます。
1日に何度も取引できる
信用取引のもう一つの利点は、1日に何度も取引を行えることです。現物取引では同じ日に同じ資金で同じ銘柄を2回以上売買することはできません。株を売却しても、その代金が再び使えるようになるまでに受渡期間が必要となるため、資金の回転効率が制約されてしまいます。
一方で信用取引は、保証金を担保にして取引を行うため、受渡を待たずに即座に新しい取引を行うことが可能です。午前中に信用買いで建てた銘柄を売却して利益を確定し、その後すぐに別の銘柄で新規建てを行うといったこともできます。短期売買やデイトレードと非常に相性が良く、相場の値動きを細かく捉えながら効率的に資金を運用できる点は大きな魅力です。
特に、相場の値動きが大きい日にはこのメリットが最大限に活かされます。短時間で大きく上下する銘柄に対して、素早く売買を繰り返す「デイトレード」や「スキャルピング」といった手法を取りやすくなるため、短期的な値幅取りを狙う投資家にとって信用取引は非常に有効な手段といえます。
「売り」から始められる
現物取引では株を保有していなければ売却できないため、基本的には「買ってから売る」という順序しか取れず、株価が上昇したときにしか利益を得られません。そのため、下落局面ではただ含み損に耐えるしかなく、戦略の幅も限られます。
一方で信用取引では、証券会社から株券を借りて先に売却し、株価が下がったときに買い戻して返却する「信用売り(空売り)」が可能です。例えば1株1,000円で100株を空売りした後に株価が800円に下がれば、200円×100株=2万円の利益を得られます。
株価の下落によって利益を狙えるのは信用取引ならではの大きな利点であり、投資戦略の幅を飛躍的に広げられます。
この仕組みを使えば、決算発表などで悪材料が出て株価の下落が予想される銘柄に「売り」で参入する、または相場全体が下落局面にあるときにインデックス銘柄を空売りする、といった戦略を取れます。
信用取引のデメリット
逆に信用取引のデメリットは次のとおりです。
- 保有期限がある
- 維持コストがかかる
- 損失も拡大しやすい
それぞれを解説します。
保有期限がある
信用取引には、現物取引のように無期限で株を持ち続けられる仕組みはなく、必ず返済期限が設けられています。この返済期限は「信用期日」と呼ばれ、期日までに決済を行わなければなりません。制度信用取引の場合、最長6カ月と明確に定められており、期限を超えると自動的に決済されます。
一方で、一般信用取引の返済期限は証券会社ごとに異なり、無期限で保有可能なケースまで幅広い設定があります。取引を始める際には、必ず利用する証券会社のルールを確認し、自分の投資スタイルに合った期限を選ぶことが重要です。
維持コストがかかる
信用取引では、建玉を保有している間にさまざまなコストが発生します。代表的なものとして、信用買いでは「金利」、信用売りでは「貸株料」、制度信用売りでは「逆日歩(品貸料)」などがあります。逆日歩は市場の需給関係で信用売りが買いを上回った場合に発生する追加コストで、日証金の発表は取引終了後に行われるため、事前に正確な予測は難しい点が実情です。
さらに、管理費や名義書換料といった費用も状況に応じてかかります。特に信用売りでは配当落調整金を支払わなければならない点には注意が必要です。
これらの費用は証券会社によって金額や条件が異なり、長期保有を続ければ続けるほどコスト負担は大きくなります。そのため、信用取引は短期売買に向いているといわれています。
損失も拡大しやすい
信用取引は保証金の約3.3倍まで取引できるため、少ない資金で大きな利益を狙える点が魅力です。しかしその裏返しとして、損失も同じ倍率で拡大してしまうというリスクがあります。株価が思惑と反対に動いた場合、現物取引よりも損失が急速に膨らみやすく、最悪の場合は元本以上の損失を抱えてしまうこともあります。
このような状況では証券会社から追加保証金(追証)の差し入れを求められ、期限までに対応できなければ強制決済が行われます。信用取引は資金効率を高める強力な手段ですが、その分リスクも大きいため、レバレッジは自身の許容範囲内に抑えること、そして常に損切りのルールを持って取引に臨むことが欠かせません。
空売りの注意点
信用売り(空売り)のリスクは次のとおりです。
- 踏み上げに注意
- 上昇トレンドの株を狙わない
- 「買いは家まで、売りは命まで」
それぞれを分かりやすく解説します。
踏み上げに注意
空売りの最大のリスクの一つが「踏み上げ」です。
信用取引で空売りを仕掛けた投資家が、予想に反して株価が上昇すると損失を抱えることになります。含み損が大きくなれば、証券会社から追加の保証金(追証)を求められるケースもあり、それに耐えられなくなった投資家が買い戻しに動きます。さらに、その買い戻し注文が新たな需要を生み、株価を一段と押し上げる結果となってしまいます。これが踏み上げの典型的な流れです。
特に、空売り残高が多い銘柄や、相場全体が強気に傾いている局面では踏み上げが起こりやすく、短期間で急騰することも珍しくありません。ニュースや材料が出た際に「売り方」が一斉に手仕舞いを迫られ、株価が一気に跳ね上がるケースもあります。空売りを行う際は、その銘柄の空売り残高や市場全体のムードも確認し、踏み上げリスクを意識しておくことが不可欠です。
上昇トレンドの株を狙わない
もう一つの注意点は、上昇トレンドが明確な銘柄に安易に空売りを仕掛けないことです。相場が上昇基調にあるとき、多少の値下がりは多くの投資家から「押し目買いのチャンス」と見なされます。そのため、売りを狙ってもすぐに買い勢力に吸収され、結果として株価はさらに高値を目指す展開になりがちです。
例えば、好決算や業績上方修正、将来性のあるテーマ性で注目を集めている銘柄は、多少の調整があっても再び上昇するケースが多く見られます。このような株に空売りを仕掛けることは賢明ではありません。
空売りは下降トレンドがはっきりと確認できる銘柄に絞り、「勢いに逆らわない」ことを徹底することが安全策です。
「買いは家まで、売りは命まで」
最後に覚えておきたいのが「買いは家まで、売りは命まで」という相場の格言です。これは空売りの危険性を端的に表しています。
現物株を購入する場合、最悪でも投資額がゼロになるだけで、損失の上限は購入金額です。例えば100万円で買った株が倒産して無価値になっても、失うのは100万円です。
一方で空売りは、株価が下落すれば利益になりますが、株価が上昇した場合には損失が青天井で膨らみます。100万円で売った株が1,000万円になれば、差額の900万円を損失として支払わなければなりません。
反対売買に関するQ&A
最後に、反対売買に関するよくある質問とその回答を紹介します。
反対売買は必ず行わなければならないか
信用取引や先物取引を行った場合、建玉を解消するためにもっとも基本的で標準的な方法が反対売買です。信用買いなら「売埋(うりうめ)」、信用売りなら「買埋(かいうめ)」を行うことで建玉をゼロに戻し、差金決済によって損益が確定します。
もちろん、例外として現引や現渡といった返済方法もありますが、利用者は一部に限られ、実際にはほとんどの取引が反対売買によって決済されています。
現物株の取引でも反対売買はあるか
現物株には反対売買はありません。反対売買は信用取引やデリバティブ取引における決済方法です。現物株には返済期限がないため、数年でも数十年でも持ち続けられます。
現物株の世界での「買ってから売る」「売ってから買う」といったシンプルな流れが、信用取引における反対売買の基本概念につながっています。
反対売買で発生する損益はどう計算されるか
損益の計算は非常にシンプルで、新規建て時の約定価格と反対売買時の約定価格の差額で決まります。
信用買いなら「売値-買値」、信用売りなら「売値-買戻値」です。例えば1株1,000円で買った株を1,200円で売れば200円の利益、逆に800円で売れば200円の損失になります。
信用取引の場合は原則的に差金決済が行われるため、株券や売買代金の全額が動くわけではなく、差額分だけが精算されます。この効率性が信用取引のメリットでもありますが、逆に差額が大きくなると短期間で損失も大きくなるため注意が必要です。
反対売買で節税できるか
反対売買自体に節税効果があるわけではありませんが、損益通算に活用できます。
例えば含み損を抱えている銘柄を年末にあえて反対売買して損失を確定させれば、その年に得た利益と相殺でき、課税額を抑えられます。さらに確定した損失は最長3年間繰り越して、翌年以降の利益と通算することも可能です。
こうした手法を「節税対策」として用いる投資家も多く、特に年末には「損出し」と呼ばれる反対売買が頻繁に行われます。ただし、節税効果だけを狙って不必要な取引を増やすと手数料やリスクが増えるため、慎重に利用する必要があります。
反対売買とロスカットの違いは何か
反対売買とは、単純に新規建ての取引と逆方向の取引を行い、建玉を解消する行為そのものを指します。
一方でロスカットとは、損失が一定の水準に達したときに反対売買を用いて建玉を強制的に解消し、損失を限定することです。
つまり、反対売買は「手段」であり、ロスカットは「目的」と捉えると理解しやすいでしょう。
NISA口座で反対売買はできるか
NISA口座では信用取引を行うことはできません。NISA制度は現物株式や投資信託などが対象であり、信用取引や先物・オプションといったデリバティブ取引は制度の対象外です。そのため、信用取引で購入した株式を現引きしてもNISA口座に受け入れることはできません。
また、NISA口座で保有している株式をそのまま現渡しに利用することもできません。現渡しを行う場合は、いったんNISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に振り替える必要があります。この移管手続きには日数がかかる場合があり、方法やスケジュールは証券会社によって異なるため、事前に確認することが大切です。なお、NISA口座から課税口座へ移した場合、移管までの評価益部分については非課税です。
さらに、信用取引では現金以外に株式や国債を「代用有価証券」として担保に差し入れることが可能ですが、NISA口座にある株式をそのまま代用有価証券にすることは認められていません。担保に利用したい場合は、やはりNISA口座から課税口座に払い出す必要があります。ただし、この場合も非課税投資枠を再利用することはできず、NISA特有の非課税メリットを失う点に注意が必要です。
まとめ
反対売買について理解が深まったでしょうか。反対売買は、株式投資や信用取引などで非常に重要な概念です。特に、信用取引やデリバティブ取引では、ポジションを適切に管理し、損失を最小限に抑えるために欠かせない手法です。この記事を通じて、反対売買の基本的な仕組みやメリット、差金決済などについて学ぶことができたと思います。
これから投資を始める方は、まずは少額から始めて、反対売買の流れを実際の取引で体感してみてください。そして、リスク管理をしっかり行い、無理のない範囲で取引を楽しみましょう。さらに詳しい情報や具体的な取引戦略については、専門書やセミナーも活用してみると良いでしょう。これにより、より深い理解が得られ、投資の成功に繋がる可能性が高まります。次のステップとして、実際の取引に挑戦してみてください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。