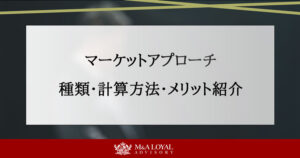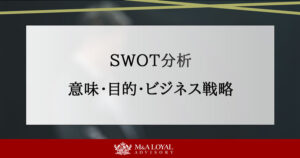新規事業の立ち上げを成功に導く7つの手順とは?必要なスキルも解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
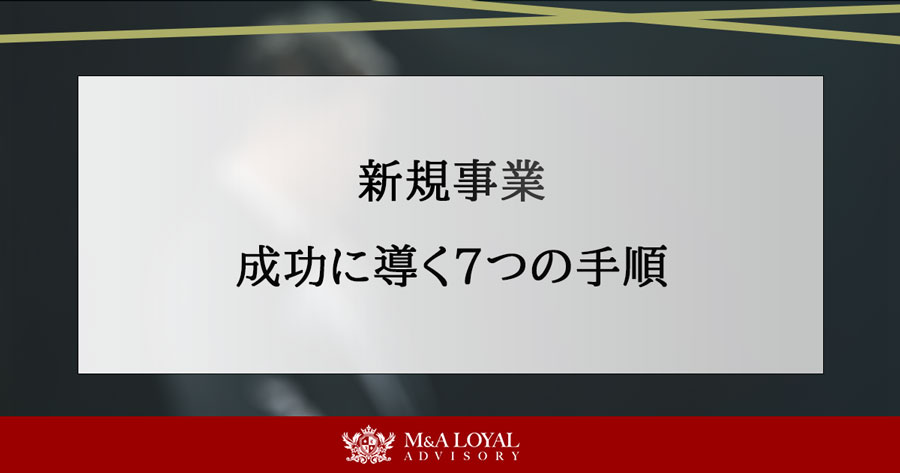
新規事業の立ち上げは、企業の成長や競争力強化を実現するだけでなく、リスク分散や人材育成といった多面的な効果をもたらす重要な取り組みです。
一方で、新規事業の立ち上げを成功に導くには市場理解や自社の強みの活用、組織づくり、経営者のコミットメントなど多くの要素が求められます。
本記事では、新規事業の意義や具体的な立ち上げプロセス、成功のポイント、先進企業の事例、さらにはよくある疑問への回答まで網羅的に解説します。新たな挑戦を始める方に実践的な指針をお届けします。
目次
新規事業とは
新規事業とは、これまでになかった新しい商品やサービスを開発し、市場に提供することです。
これは単に新しい商品を発売するだけでなく、これまで関わっていなかった顧客層や市場を開拓していく活動全体を指します。新規事業は、既存の事業を強化したり、社会が抱える問題を解決したりするために行われます。
例えば、大企業がこれまで培ってきた技術力や資金力を生かして、新しい分野の事業に乗り出すことがあります。自動車メーカーが電気自動車の開発に乗り出したり、食品会社が医薬品の市場に参入したりするケースがこれにあたります。
一方で、小さなチームや個人が、独自のアイデアや技術で社会の課題を解決しようと立ち上げることもあります。こうしたスタートアップは、市場のニーズに素早く対応し、これまでの常識を覆すような革新的なサービスを生み出すことが特徴です。
いずれにしても、新規事業を成功させるためには市場のニーズを徹底的に調べ、具体的な事業計画を立て、それを実行していく力が必要不可欠です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



会社に新規事業が重要な理由
新規事業が必要な主な理由は次のとおりです。
- 成長と競争力強化
- リスク分散
- 人材の育成
それぞれを詳しく解説します。
新規事業による成長と競争力強化
新規事業は、企業が持続的に発展していくための大きな原動力です。
既存事業だけでは市場の成熟や競合の増加により、成長率が鈍化してしまう可能性があります。そのような状況において、新しい分野に進出することで、売り上げや利益の柱を増やし、企業全体の成長を押し上げられます。
さらに、新規事業は単に売り上げを増やすだけではなく、企業に新しい知識やノウハウをもたらす点でも重要です。新しい市場での挑戦は、顧客ニーズの把握や新技術の習得を通じて、組織全体の競争力を底上げします。
競合より早く新市場に参入できれば、先行者としてブランド認知や顧客基盤を確立するチャンスにもなります。その結果、企業は他社との差別化を実現し、長期的な優位性を築けます。
新規事業によるリスク分散
どれほど強固に見える事業であっても、時代の変化や外部環境の影響から完全に逃れることはできません。例えば、消費者の嗜好(しこう)変化や、技術革新による代替サービスの登場、規制強化、景気の変動などは、既存事業の収益性を急激に低下させるリスクを含んでいます。
新規事業を展開することは、こうした不確実性に備えるための重要な手段です。複数の事業を持つことで収益構造を多角化し、特定の事業が不振に陥った場合でも他の事業が支えとなり、企業全体の安定性を確保できます。
これは投資の世界で「ポートフォリオを組む」ことと同じ発想であり、事業経営においてもリスクを分散する仕組みが必要です。結果として、新規事業は企業を外部環境の変化に強い体質へと導き、持続可能な経営を支える役割を果たします。
新規事業による社内メンバーの育成
新規事業は、企業の外部環境への対応だけでなく、内部資源である人材の成長にも大きな意義を持っています。
社員が新しい事業に取り組むことで、従来の枠にとらわれない発想や柔軟な思考力を養えます。未知の分野に挑戦する過程で得られる経験は、社員にとって貴重な学びとなり、個々の成長を促します。さらに、新規事業を任されることは社員にとって挑戦の場であり、大きなモチベーションにつながります。こうした機会は優秀な人材の流出を防ぎ、長期的に組織に定着してもらう効果も期待できます。
加えて、新規事業の推進は組織全体にイノベーション文化を根付かせます。失敗を恐れず試行錯誤する姿勢が組織に広がることで、既存事業の改善や新しいアイデアの創出にもつながり、企業全体の競争力を強化する好循環を生み出します。
新規事業の形態
新規事業の形態は主に次の4パターンです。
- 既存市場で新規サービスを展開
- 既存サービスを新規市場で展開
- 多角化
- 事業転換
それぞれを分かりやすく解説します。
既存市場で新規サービスを展開
既存市場において新しいサービスや商品を投入する方法は、比較的リスクが低く、成長を目指しやすい新規事業の形態です。
既に顧客基盤や販売チャネル、ブランド認知が整っているため、ゼロから市場を開拓する必要がありません。そのため、市場調査やマーケティングにかかるコストを抑えつつ、新しい収益の柱を作りやすい点が特徴です。
例えば、飲食チェーンが既存の顧客層に向けて新しいメニューを導入したり、通信会社が既存の携帯電話契約者に向けて動画配信サービスを展開したりするケースが該当します。
既存顧客との接点を活用してクロスセルを促進できる反面、差別化が不十分だと市場での競合が激しくなり、思うような成長につながらないリスクもあります。従って、自社の強みを生かした付加価値の創出が成功の鍵です。
既存サービスを新規市場で展開
既存のサービスや商品を未開拓の市場に持ち込む方法は、新規事業の中でも「地理的な拡大」や「顧客層の拡大」といった形で行われるケースが多いです。サービス自体は実績があり、ビジネスモデルも確立されているため、開発コストやリスクを抑えつつ成長を目指せます。
典型例としては、国内市場で成功した商品やサービスを海外展開するパターンが挙げられます。あるいは、都市部で人気のサービスを地方市場に展開するケース、もしくは大人向けの商品を若年層にアレンジして販売するケースも同様です。
このアプローチのメリットは、既に存在する「勝ちパターン」をスケールさせられることです。ただし、文化や消費習慣が異なる市場では、そのままでは受け入れられにくく、ローカライズやマーケティング戦略の調整が求められる点が課題です。
多角化
多角化は、既存の市場やサービスを維持しつつ、新しい分野に進出するアプローチです。企業にとって大きな成長機会をもたらす一方で、既存事業と新規事業を並行して進める必要があるため、高度なマネジメント力が求められます。
例えば、飲料メーカーが化粧品や健康食品に進出する、IT企業が教育や医療分野に新サービスを展開する、といったケースが当てはまります。この戦略は収益源を増やしてリスク分散を図れる一方、シナジー効果を見込める領域を選ばなければ、経営資源の分散によりどちらの事業も中途半端になるリスクがあります。
従って、多角化戦略の成功には「既存事業との関連性の有無」「新事業が持つ成長ポテンシャル」「経営資源を適切に配分できる体制」の3点が特に重要です。うまくいけば企業全体の競争力を大きく底上げできる手法です。
新規事業による事業転換
事業転換は、既存市場や既存サービスから撤退し、全く新しい分野にシフトする大胆な方法です。既存事業の収益性が大幅に低下し、将来的な成長が見込めないと判断された場合に選択されることが多く、企業の生き残りをかけた意思決定といえます。
事業転換には高いリスクが伴います。既存の顧客基盤やブランド資産を手放す必要があり、新市場での競争環境や成功の可能性は不確実だからです。
しかし、転換に成功すれば企業は新しい収益モデルを確立し、急速な成長を実現できます。特に市場構造が大きく変化する時代には、事業転換こそが企業存続の唯一の選択肢になる場合も少なくありません。
新規事業立ち上げの手順と業務で必要なこと
新規事業を立ち上げる際のステップは次のとおりです。
- アイデア創出
- マーケット調査
- コンセプト設計
- プロトタイプ作成
- ビジネスプラン策定
- ローンチ
- スケール
順番に解説していきます。
アイデア創出
新規事業の出発点は、まず「どんなことをやるか」というアイデアを生み出すことです。アイデアは単なるひらめきではなく、市場のトレンドや顧客の未解決課題、テクノロジーの進化、自社の強みなど多様な観点から検討されるべきです。
例えば、既存顧客が抱える小さな不便を解消するものや、社会的に注目されているテーマ(脱炭素・健康志向・DXなど)を取り入れることも有力候補です。
この段階では「質より量」を重視し、ブレインストーミングやワークショップ形式で多くの候補を出すことが望ましいといえます。
マーケット調査
次に、出てきたアイデアが実際に事業として成立しうるかを見極めるために、リサーチを行います。
市場規模や成長性、競合の状況、ターゲット顧客のニーズを分析し、事業機会が本当に存在するのかを確認します。単なるデータ分析にとどまらず、顧客インタビューやアンケートを通じて一次情報を得ることが重要です。
この段階で「顧客が本当に困っていることは何か」「既存の選択肢では解決できていないのはなぜか」という問いに答えられるかどうかが、後の成否を分けます。また、ビジネスモデルキャンバスを使って、収益の流れやコスト構造を簡易的に整理し、仮説を立てるのも有効です。ビジネスモデルキャンバスについては後述します。
コンセプト設計
リサーチで事業機会を確認したら、具体的な事業コンセプトを設計します。
ここでは「誰に」「何を」「どのように」提供するかを明確化することがポイントです。ターゲット顧客をできるだけ具体的に描き、その顧客に対してどんな価値を提供するのかを定義します。
また、収益モデル(サブスクリプション型、広告モデル、ライセンス販売など)や、販売チャネル(オンライン、代理店、直販など)、必要なリソース(人材、技術、パートナー企業)も合わせて整理します。ここで作成したコンセプトが、その後の実証実験や事業計画の土台です。
プロトタイプ作成
新規事業は不確実性が高いため、いきなり大規模に展開すると大きな損失につながる可能性があります。
そのため、まずは最小限の機能を備えた試作品(MVP=Minimum Viable Product)を作り、小規模な市場でテストを行います。この段階では「机上の理論」ではなく「実際の顧客行動」から学ぶことが大切です。
例えば、アプリであれば簡易版をリリースし、どの機能が使われているのかを確認します。サービスであれば限定エリアや限定顧客で試験提供し、満足度や改善点を把握します。小さく始めることで、失敗してもダメージが限定的であり、素早く改善サイクルを回せます。
ビジネスプラン策定
プロトタイプで一定の手応えを得られたら、本格的な事業化に向けた計画を策定します。
市場規模の推定や売り上げ予測、必要な投資額、採算ラインの見極めなど、財務的な側面を明確にします。また、事業を運営するための組織体制や役割分担、人材採用の計画も検討します。
この段階で経営層や投資家に説明できるレベルの計画を整備することが不可欠です。計画にはリスクシナリオや代替案も盛り込み、「何がうまくいかなかった場合にどうするか」をあらかじめ示すことで、社内外からの信頼を得やすくなります。
ローンチ
計画が整ったら、いよいよ正式に市場へ投入します。この「ローンチ」段階では、プロモーションや営業活動を強化し、初期顧客を獲得することが最大の目標です。
マーケティング施策は、デジタル広告やSNS、既存顧客へのクロスセルなど多方面から展開されます。
ここでは「完璧な状態で出す」よりも「市場に出して反応を見ながら改善する」姿勢が重要です。ローンチ後も顧客のフィードバックを迅速に収集し、サービス内容やオペレーションを柔軟に調整していくことで、成長の軌道に乗せやすくなります。
スケール
事業が市場に受け入れられたことを確認できたら、次は拡大フェーズに移行します。販売チャネルを広げ、地域やターゲット層を拡張し、シェア拡大を目指します。人員体制も強化し、専任チームや事業部として独立させるケースもあります。
また、この段階では単なる売り上げ拡大だけでなく、収益性や効率性を高める取り組みも重要です。システム投資や業務プロセスの最適化により、スケールに耐えられる基盤を構築することで、安定した事業運営が可能です。
新規事業立ち上げ成功のポイント
新規事業の立ち上げを成功させるポイントは次のとおりです。
- 市場を理解し価値を提供する
- 自社の強みを活用する
- 変化を楽しめる人材を集める
- 実行と改善を重視する
- 経営者がコミットする
それぞれを詳しく解説します。
市場を理解し価値を提供する
新規事業を立ち上げる際の出発点は「どの市場に入り、誰の課題を解決するのか」を徹底的に理解することです。市場規模がどれほど大きいのか、将来的に成長が見込める分野なのか、既にどのような競合が存在するのかを調査することは欠かせません。
そして、ただ市場に参入するだけではなく「顧客が本当に求めている価値は何か」を掘り下げることが重要です。顧客インタビューやアンケート調査、実際の利用行動の観察などを通じて、顧客の不満や不便を具体的に理解し、それを解決する方法を見つける必要があります。
さらに、価値を提供し続けるには持続可能な収益モデルが必要です。単発的な売り上げに依存するのではなく、定期的な利用や継続的な購入につながる仕組みをどう作るかも検討すべきです。環境変化や顧客ニーズの変化に合わせて柔軟に見直せる仕組みが整っていれば、長期的に安定した事業成長を見込めます。
自社の強みを活用する
市場や顧客を理解することに加え、自社の強みをどう新規事業に結びつけるかは極めて重要です。ゼロから全てを作り出すのではなく、既存の資産を有効に活用することで成功確率を高められます。
例えば、製造業であれば長年培った技術力や生産ノウハウを新しい分野に応用できるかもしれません。流通業であれば、既に持っている販売ネットワークや顧客接点を生かすことで、新規事業を効率的に立ち上げられます。
ブランド力や信頼性がある企業であれば、それ自体が新事業の信頼獲得に直結します。逆に、自社の強みを生かせずに全く無関係な分野に手を広げると、資金や人材が分散し、成功の可能性は下がります。そのため、自社の持つ強みを棚卸しし、それを核として事業を設計することが不可欠です。
変化を楽しめる人材を集める
新規事業は既存事業とは異なり、不確実性やリスクを前提に進めなければなりません。そのため、必要とされるのは従来の延長線上のスキルだけではなく、多様な知識と柔軟な発想を持つ人材です。
特に、変化を楽しみ、挑戦を恐れない人材が多いほど、新規事業は活性化します。また、失敗を厳しくとがめる文化では、誰も新しい挑戦をしなくなります。むしろ、失敗から学びを得て次に生かす姿勢を奨励する文化を作ることが大切です。
さらに、特定の部署だけで事業を進めるのではなく、組織横断的に人材を集め、多角的な視点を持ち込むことも効果的です。新規事業は孤立して進めるものではなく、組織全体で支える体制を整えることが成功の条件です。
実行と改善を重視する
どれほど優れたアイデアや計画があっても、実行力が伴わなければ成果は出ません。
新規事業の初期段階では、まず小さく試し、顧客に実際に触れてもらい、その反応を観察することが効果的です。サービスや商品を限定的に提供し、顧客がどのように利用するのかを見ながら改善点を見つけていきます。
この際に重要なことが「PDCAサイクル」です。これは Plan(計画を立てる)→ Do(実際に試す)→ Check(結果を評価する)→ Act(改善する) という流れを繰り返す考え方です。
特に新規事業では、長期間かけて一度だけ大規模な計画を実行するよりも、小さな試行を短期間で行い、その結果を基に迅速に軌道修正することが成功につながります。
また、資金や人材、時間は常に限られているため、それらを効率的に配分し、無駄を省きながら進めることも求められます。スピード感を持った実行力と、改善を重ねる柔軟性の両方を兼ね備えることが、成長への道筋を作ります。
経営者がコミットする
新規事業を成功に導くうえで最も根幹にあるのは、経営者自身の姿勢です。
新しい事業は短期的に利益が出にくく、試行錯誤や失敗が前提です。そのため、経営者が長期的な視点を持ち、失敗を許容しながらも粘り強く支援し続ける姿勢が不可欠です。資金や人材の確保、既存事業とのバランス調整などは経営層の意思決定がなければ進みません。
また、トップが本気で取り組む姿勢を示すことで、社員も安心して挑戦でき、組織全体に「新しいことに挑戦して良い」という文化が浸透します。経営者が中途半端な関わり方をしてしまうと、現場も消極的になり、せっかくの新規事業が形だけで終わってしまう危険性があります。
新規事業立ち上げに有益なフレームワーク
新規事業の立ち上げに活用できる、有名なフレームワークは次のとおりです。
- ビジネスモデルキャンバス
- リーンキャンバス
- SWOT分析
- 3C分析
- アンゾフの成長マトリクス
それぞれを分かりやすく解説します。
ビジネスモデルキャンバス
ビジネスモデルキャンバスは、アレックス・オスターワルダー氏によって提唱されたフレームワークで、新規事業の全体像を1枚のシートで整理できる点が大きな特徴です。事業を構成する要素を「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「顧客との関係」「収益の流れ」「主要リソース」「主要活動」「パートナー」「コスト構造」の9つに分け、それぞれを記入していきます。
新規事業の初期段階では、個々の要素を細かく精緻にするよりも、事業全体の輪郭を描き、欠けている部分やリスクとなる部分を見える化することが大切です。このキャンバスを使えば、経営層やチームメンバーが同じ視点を持ちやすくなり、議論がスムーズに進みます。
また、定期的に更新することで「どの仮説が有効で、どこが修正すべきか」を可視化できるのも利点です。注意点としては、シンプルにまとめやすい反面、表面的な整理に終わってしまうリスクがあるため、実際の顧客検証や数値データと併せて使うことが求められます。
リーンキャンバス
リーンキャンバスは、ビジネスモデルキャンバスをスタートアップや新規事業向けに改良したものです。特に「課題」や「独自の優位性」といった新規事業に不可欠な要素を強調している点が特徴です。
このフレームワークを使うと、短期間で仮説を整理し、実際に検証を進める流れを作りやすくなります。例えば「どんな課題を持つ顧客に対して」「どのような解決策を提供し」「その解決策は他社と比べてどう優れているのか」を明確にできます。
これにより、実行後に客観的に評価できる基準を持てるため、無駄な方向に進むリスクを減らせます。特にスピード感が求められる新規事業では、リーンキャンバスを繰り返し更新することで「顧客課題と解決策がフィットしているか」を磨き上げられます。
SWOT分析
SWOT分析は、古くから戦略立案の基本とされるフレームワークで、自社の内部要因(Strength:強み、Weakness:弱み)と外部要因(Opportunity:機会、Threat:脅威)を整理します。新規事業においては「どの市場に参入すべきか」「自社はどこで戦うべきか」を判断する材料として活用できます。
例えば、自社の強みが「ブランド力」と「既存顧客基盤」であれば、これを生かせる市場を選ぶことが合理的です。一方で「技術力不足」や「人材不足」といった弱みがあるなら、それを補うために外部パートナーと連携する戦略が考えられます。
また、市場における「新しい需要の拡大」や「規制緩和」といった機会を逃さず捉えることも重要です。さらに「競合の参入」や「法規制の強化」といった脅威をあらかじめ想定し、リスク対応策を組み込むことで失敗の確率を減らせます。SWOTはシンプルですが、「内部資源と外部環境をどう結びつけるか」を考えるうえで極めて有効です。
3C分析
3C分析は「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の三つの視点から事業環境を分析する手法です。新規事業では、まず「顧客が何を求めているか」を深く理解することが最優先です。そのうえで、同じ市場にいる競合がどのように顧客ニーズを満たしているかを調べ、自社がそこにどう差別化要素を打ち出せるかを考えます。
例えば、顧客が「便利さ」を求めている市場で、競合が「低価格」を売りにしている場合、自社が「スピード」や「安心感」といった別の価値を提供できれば競争優位を築けます。
3C分析の強みは、外部(顧客・競合)と内部(自社)の関係性を整理できる点にあり、「自社の立ち位置」を明確にするのに役立ちます。新規事業の方向性が「顧客にとって意味のある差別化」につながっているかを確認するために非常に有用です。
アンゾフの成長マトリクス
アンゾフの成長マトリクスは、既存・新規の「市場」と「商品・サービス」の組み合わせから、事業成長の方向性を四つに分類するフレームワークです。
- 既存市場 × 既存商品=市場浸透(シェア拡大)
- 既存市場 × 新商品=新商品開発
- 新市場 × 既存商品=新市場開拓
- 新市場 × 新商品=多角化
新規事業を考える際、このマトリクスを活用すると「自社がどの方向に進もうとしているのか」「その選択はどの程度リスクを伴うのか」を明確にできます。
例えば、既存市場に新商品を投入するのは比較的リスクが低い一方、新市場に新商品で挑む多角化はリスクも高いが大きなリターンも期待できます。経営層が新規事業にどの程度のリスクを取る覚悟があるかを判断する材料としても有効です。
新規事業の立ち上げが活発な企業例
新規事業の立ち上げが活発な企業を紹介します。
サイバーエージェント
サイバーエージェントは、新規事業創出を制度化している企業としてよく知られています。
例えば「CAKK制度」では、各事業や子会社を成長ステージや将来的な利益規模で分類し、経営資源の配分や新規事業の立ち上げを計画的に進めています。また「あした会議」などの仕組みからは数多くの子会社や新規事業が生まれています。
さらに、失敗しても再挑戦できる文化を育てることで、社員が安心して新しい事業に取り組める環境を整えています
ラスクル
ラクスルは、印刷ECを軸に成長してきた企業ですが、その基盤を生かして新たな領域に挑戦しています。
印刷事業の顧客データから見えたニーズを基に、アパレル・ユニフォーム事業を立ち上げた例は有名です。
既存の仕組みや顧客接点を生かしながら、隣接領域に事業を広げることで収益機会を拡大してきました。さらに2025年には「ラクスルバンク」という金融サービスにも参入し、印刷や広告だけでなく経営支援全般へと事業を拡張する見込みです。
ガイアックス
ガイアックスは「人と人をつなげる」というミッションの下、スタートアップスタジオとして若い起業家を輩出し、社内外への起業支援や投資を通じて社会課題の解決に挑んでいます。
起業スタイルは多様で、スキルを磨いてから挑戦する人、副業的に準備を進める人、新卒からすぐに起業する人など、自分に合った道を選べます。各事業部は独立採算制を導入し、投資や人材戦略の決定を自ら行い、働き方や報酬も自由に設定できるため、実践的に経営者視点を養えます。
また、3カ月ごとのマイルストーンセッションでライフプランと事業の方向性を確認し、目標や働き方を自分で定められる仕組みがあります。
さらに、カーブアウトオプション制度によって社内事業を独立法人化し、ストックオプションを発行して経営メンバーに付与することも可能です。独立後は資金調達や経営判断を自ら行い、本格的に事業を推進できます。
富士フイルム
富士フイルムは、主力であった写真フィルム事業の衰退をきっかけに、大胆な事業転換を図った企業として知られています。同社はフィルム開発で培ってきた素材技術や化学技術を改めて分析し、その強みを新たな分野に応用することで活路を見いだしました。単なる多角化ではなく、既存の技術を異分野に生かす「技術転用」を軸に事業を展開した点が大きな特徴です。
具体的には、写真フィルム研究を通じて積み上げてきた技術の中から、コラーゲン研究、抗酸化技術、光解析技術、ナノ化技術の四つを強みとして抽出しました。これらの技術を美容領域へと応用する過程で、美容成分アスタキサンチンのナノ化に成功し、2007年には化粧品ブランド「アスタリフト」を誕生させました。このブランドは、富士フイルムが持つ科学的な知見と高度な研究力を背景に成長を遂げ、同社の新たな事業の柱となっています。
新規事業の立ち上げに関するQ&A
最後に、新規事業立ち上げに関するよくある質問とその回答を紹介します。
新規事業で活用できる補助金はあるか
新規事業への進出によって企業の成長・拡大を図る中小企業が活用できる補助金に「中小企業新事業進出補助金」があります。
「新事業進出補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より委託された「株式会社博報堂を主幹事としたコンソーシアム(株式会社博報堂、アクセンチュア株式会社、株式会社ヴァリアス・ディメンションズ、株式会社博報堂プロダクツ)」が事務局業務を運営しています。
概要は次のとおりです。
- 従業員数と補助金額
- 従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円)
- 従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円)
- 従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円)
- 従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)
- 補助率:1/2
- 基本要件
- 新事業進出要件
- 付加価値額要件
- 賃上げ要件
- 事業場内最賃水準要件
- ワークライフバランス要件
- 金融機関要件
- 賃上げ特例要件
- 補助対象経費
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
新規事業が思いつかない時はどうすれば良いか
アイデアが浮かばないときには、「オズボーンのチェックリスト」や「SCAMPER法」といった発想支援のフレームワークを使うと効果的です。
オズボーンのチェックリストは「転用できないか」「応用できないか」「変更できないか」「拡大できないか」「縮小できないか」「代用できないか」「再配置できないか」「逆転できないか」といった視点から既存の事業や商品を見直し、新しい切り口を発見する手法です。
また、SCAMPER法は「Substitute(代える)」「Combine(組み合わせる)」「Adapt(応用する)」「Modify(修正・拡大する)」「Put to other use(他用途に転用する)」「Eliminate(取り除く)」「Reverse(逆にする)」の7視点で考えるもので、既存アイデアの延長からでも発想を広げられます。
こうした体系的な問いかけを行うと、ゼロからの発想よりも効率的に新規事業のヒントを見つけられます。
新規事業は誰に相談すれば良いか
新規事業を構想する際には、まず社内の経営層や事業開発部門に相談して方向性をすり合わせることが一般的です。それに加えて、営業やカスタマーサポートなど顧客に近い部門の社員に話を聞くと、実際の顧客ニーズに即した発見が得られます。
さらに、社外のスタートアップ経営者や業界専門家、ベンチャーキャピタルの投資家なども有力な相談相手です。
また、日本政策金融公庫や各地の商工会議所・商工会にも中小企業の経営全般を相談できる窓口があります。
多様な人の視点を取り入れることで、机上の空論に陥らず現実的な新規事業に近づけます。
新規事業に重要なスキルは何か
新規事業に必要なスキルの一つとして特に注目されていることが「デザイン思考」です。
デザイン思考とは、元々製品デザインの現場から発展した問題解決の方法論で、顧客の立場に立って課題を深く理解し、試作と検証を繰り返しながら解決策を磨き上げていくアプローチです。一般的には「共感」「問題定義」「アイデア創出」「試作」「テスト」という五つのプロセスで構成され、直線的に進むのではなく、必要に応じて何度も行き来しながら改善していく点に特徴があります。
新規事業の立ち上げは不確実性が高く、最初から正解を見つけることは困難です。そのため、顧客に徹底的に寄り添い、観察やインタビューを通じて本質的な課題を把握することが不可欠です。デザイン思考の「共感」や「問題定義」のステップはまさにその作業にあたり、表面的なニーズではなく潜在的な課題を明らかにします。さらに「アイデア創出」や「試作」「テスト」のステップでは、小さな試みを素早く行い、その反応を基に改善を重ねることで、事業の方向性を現実に即したものへと近づけられます。
もちろん財務分析やマーケティングといった専門的なスキルも新規事業には重要ですが、それ以上に「試す」「学ぶ」「修正する」という反復的な思考と行動の柔軟さこそが、新しい価値を生み出すための土台になります。デザイン思考はそのプロセスを体系的に支える枠組みであり、不確実性の中でも着実に前進するための有効な手法といえるでしょう。
新規事業にはどんな人が向いているか
不確実な状況を楽しめる人、変化に柔軟に対応できる人が向いています。新規事業には正解がなく、失敗から学び続ける姿勢が欠かせません。
そのため、挑戦心と粘り強さを持ち、自ら行動して情報を取りに行ける主体性を備えている人が成功しやすいといえます。
また、周囲を巻き込み協力を得られるコミュニケーション力も必要です。リーダーとしてチームをけん引する人だけでなく、支える立場でも自らの役割を積極的に見つけられる人材が新規事業の現場で活躍します。
新規事業のリスク分析はどのようにするか
リスクを整理する際には「PEST分析」を活用すると有効です。これは「Politics(政治・制度)」「Economy(経済)」「Society(社会・文化)」「Technology(技術)」の4観点から外部環境を分析する方法です。
例えば、新しいサービスが法規制の影響を受けないか、景気変動で需要が左右されないか、社会的価値観の変化で受け入れられるか、技術の進化に追いつけるかといったリスクをあらかじめ想定できます。
PEST分析と組み合わせて、自社の資金・人材・組織体制といった内部リスクも整理すれば、事業全体のリスクを体系的に把握できます。
まとめ
新規事業の立ち上げは多くの課題がありますが、それを乗り越えることで大きな成功を収めることができます。重要なのは、しっかりとした市場調査を行い、正確なビジネスプランを立てることです。自社の強みを活かし、変化を楽しむことのできる人材を集めることも成功の鍵です。また、経営者自身がプロジェクトに深く関与することが、チーム全体のモチベーションを高め、プロジェクトの成功率を上げるでしょう。
新規事業の立ち上げを考えている方は、まず小さなステップから始めてみてはいかがでしょうか。そして、専門家の助言を仰ぎながら、必要なスキルや知識をどんどん取り入れていくことをお勧めします。これからの一歩を踏み出すために、まずはこの記事で紹介した手順やポイントを参考に、自分のビジネスアイデアを具体化してみましょう。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。