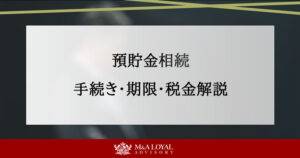相続不動産の売却で税金はいくら?3つの節税方法と手続き方法も解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
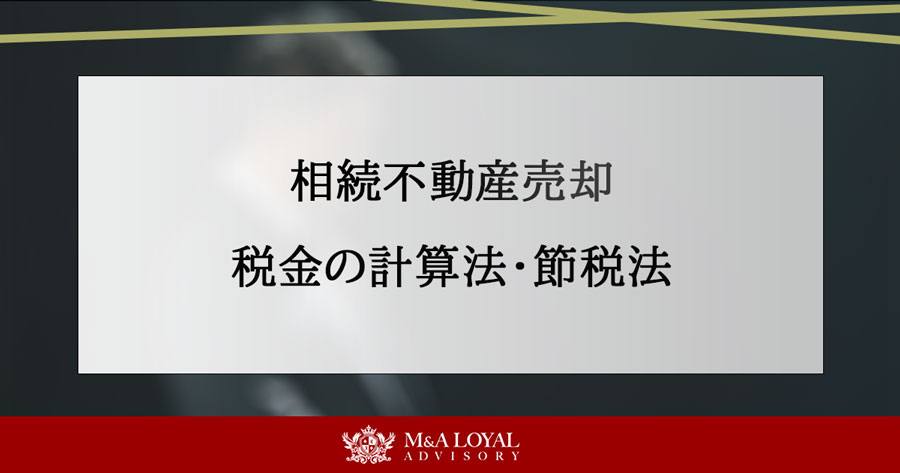
相続で取得した実家や土地を売却する際、多くの方が税金の負担に不安を感じています。実際に相続不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税など複数の税金が発生します。これらは「譲渡所得」に対して課税されるものであり、場合によっては譲渡所得の20%以上が税金として徴収されることもあります。
しかし、適切な知識と対策があれば、相続不動産に関わる税負担を大幅に軽減できます。3,000万円の特別控除や取得費加算の特例など、様々な節税制度を活用することで、数百万円単位で相続不動産の税金を減らせるケースも少なくありません。
本記事では、相続不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法や節税対策、売却手続きの流れまでを解説します。特に、多くの方が見落としがちな特例の併用制限や、重要な期限についても詳しく説明していきます。相続不動産の売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧いただき、賢い税金対策を実践してください。
目次
相続不動産の売却で税金はどれくらいかかるか
相続不動産を売却する際にかかる税金は、主に譲渡所得税・住民税が中心となりますが、それ以外にも印紙税や登録免許税などの税金が発生します。税金の総額は売却価格や物件の取得経緯によって大きく異なり、数十万円から数百万円になるケースも珍しくありません。
相続不動産の売却では、通常の不動産売却とは異なる特別なルールが適用されるため、事前に税金の仕組みを理解しておくことが重要です。
譲渡所得税と住民税の基本的な仕組み
相続不動産の売却で最も大きな負担となるのが、譲渡所得税と住民税です。これらの税金は、不動産を売却して利益が出た場合にのみ課税されます。
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
税率は不動産の所有期間によって大きく異なります。
・長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
・短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
相続不動産の場合、所有期間は被相続人が取得した日から引き継いで計算します。重要なのは、所有期間が5年を超えるか否かは「売却した年の1月1日時点」で判定されるという点です。例えば、親が30年前に購入した不動産を相続後1年で売却した場合、所有期間は31年となり長期譲渡所得扱いとなります。
※参照:
・国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
・国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
印紙税・登録免許税などその他の税金
譲渡所得税・住民税以外にも、以下の税金が発生します。
印紙税は売買契約書に課税される税金で、売却価格に応じて税額が決まります。2027年3月31日まで軽減措置が適用されています。例えば、売却価格が1,000万円超5,000万円以下の場合、軽減措置により印紙税は1万円となります。したがって、売却価格が3,000万円でも5,000万円でも印紙税は1万円です。
登録免許税は、主に2つの場面で発生します。
1.相続登記(必須):売却の前提として、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」が法律で義務化されています。この際にかかる登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%」です。例えば評価額が3,000万円の場合、12万円の税金がかかります。
2.抵当権抹消登記:売却する不動産に住宅ローンなどが残っている場合、その抵当権を抹消する登記が必要です。税額は不動産1個につき1,000円です。
また、2037年まで復興特別所得税が課されます。これは、算出された所得税額に対して2.1%を乗じて計算されるもので、譲渡所得税の税率に単純に加算されるものではありません。例えば長期譲渡所得の場合、所得税率15%に対する復興特別所得税は0.315%(15% × 2.1%)となり、所得税と合わせた実質的な国税の税率は15.315%となります。
※参照:
・国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
・国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
相続税との関係性と二重課税の注意点
相続不動産の売却では、相続税と譲渡所得税の両方が課税される可能性があります。しかし、これは二重課税ではありません。相続税は相続時の財産価値に対して課税され、譲渡所得税は売却による利益に対して課税されるためです。
ただし、相続税を支払った場合は「相続財産譲渡時の取得費加算特例」を活用できます。この特例では、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できるため、譲渡所得を減らして税負担を軽減することが可能です。
相続から3年10ヶ月以内に売却した場合にのみ適用できるため、売却を検討している場合は期限を意識することが大切です。また、他の特別控除との併用には制限があるため、どの特例を使うのが最も有利かを慎重に検討する必要があります。
※参照:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



相続不動産を売却した際の税金計算方法
相続不動産の売却で最も重要なのは、正確な税金計算を行うことです。計算方法を理解することで、事前に税負担を予測でき、適切な節税対策を講じることが可能になります。
相続不動産の税金計算には、通常の不動産売却とは異なる特殊なルールが適用されるため、計算の各ステップを詳しく理解しておきましょう。
譲渡所得の計算式と取得費の考え方
相続不動産の譲渡所得は、以下の基本計算式で求めます。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
この計算で最も複雑なのが「取得費」の算定です。相続不動産の取得費は、被相続人が物件を購入した時の価格を基準とします。建物部分については、購入価格から減価償却費を差し引く必要があります。
相続不動産の取得費計算で問題となるのは、購入時の書類が見つからないケースです。この場合、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とすることができます。例えば、3,000万円で売却した場合の概算取得費は150万円となります。
ただし、概算取得費を使うと譲渡所得が大きくなり、税負担が重くなる可能性があります。昭和40年代以降に購入された不動産では、実際の取得費の方が概算取得費より高くなることが多いため、可能な限り実際の取得費を証明する書類を探すことが重要です。
建物の減価償却費計算は、居住用不動産の場合、以下の式で求めます。
減価償却費 = 建物購入価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
長期譲渡と短期譲渡の税率の違い
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。相続不動産の場合、所有期間は被相続人の取得日から計算される点が重要です。
長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得(所有期間5年以下)の税率は以下の通りです。
・長期譲渡所得:所得税15.315%+住民税5%=20.315%
・短期譲渡所得:所得税30.63%+住民税9%=39.63%
税率の差は約19%と非常に大きく、短期譲渡所得の場合は税負担がほぼ倍になります。相続不動産では、親が長年所有していたケースが多いため、ほとんどの場合で長期譲渡所得の税率が適用されます。
例えば、親が30年前に購入した不動産を相続後1年で売却した場合、所有期間は31年となり長期譲渡所得として計算されます。
税金の実際の計算例とシミュレーション
具体的な計算例で税金額を確認してみましょう。
【計算例】
- 売却価格:4,000万円
- 被相続人の購入価格:2,500万円(30年前)
- 建物部分:1,000万円(木造住宅)
- 譲渡費用:200万円
まず、建物の減価償却費を計算します。
減価償却費=1,000万円×0.9×0.031×30年=837万円
取得費=2,500万円-837万円=1,663万円
課税譲渡所得=4,000万円-(1,663万円+200万円)=2,137万円
税額=2,137万円×20.315%=約434万円
このケースでは、約434万円の譲渡所得税がかかることになります。
もし概算取得費(5%)を使った場合は、取得費が200万円となり、課税譲渡所得は3,600万円、税額は約731万円となり、約300万円も多く税金を支払うことになります。このように、正確な取得費の把握は節税において非常に重要です。
※参照:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
相続不動産の売却時に税金を減らす3つの方法
相続不動産の売却で税負担を軽減するには、適用可能な特例制度を的確に活用することが重要です。税制では、不動産売却時の負担を軽減するための様々な制度が用意されており、適用条件を満たせば大幅な節税効果を期待できます。
ここでは、相続不動産売却時に特に効果的な3つの節税方法について、具体的な適用条件と節税効果を解説します。適用できる特例を見逃すと、数百万円の税負担増になる可能性もあるため、事前の確認が欠かせません。
3,000万円特別控除を適用する
最も大きな節税効果が期待できるのが「3,000万円特別控除」です。相続不動産の場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」が適用できる可能性があります。
この特例では、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金をゼロにできます。例えば、譲渡所得が2,500万円の場合、本来であれば約508万円の税金がかかりますが、この特例により税負担がなくなります。
適用の主な条件は以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・被相続人が相続開始直前まで一人で住んでいたこと
※ただし、要介護認定などを受けて老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象となる可能性があります。
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
・売却時に耐震基準を満たしているか、解体して更地での売却であること
・売却価格が1億円以下であること
ただし、令和6年1月1日以降の売却で相続人が3人以上の場合は、控除額が一人当たり2,000万円に減額される点に注意が必要です。
※参照:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
取得費加算の特例を活用する
相続税を支払った場合に活用できるのが「取得費加算の特例」です。この特例では、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算することで、譲渡所得を減らすことができます。
相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に適用可能で、相続税額のうち売却した不動産に対応する部分を取得費に加算できます。例えば、1,000万円の相続税を支払い、そのうち500万円が売却不動産に対応する場合、取得費を500万円増やすことができます。
具体的な節税効果を見てみると、取得費が500万円増加することで譲渡所得が500万円減少し、約101万円の税額軽減につながります(長期譲渡所得の場合)。
注意点として、この特例は空き家の3,000万円特別控除との併用ができないため、どちらを適用するかは慎重な検討が必要です。
注意点として、この特例は空き家の3,000万円特別控除との併用ができません。どちらが有利かは、「実際に納付した相続税額」によって大きく異なります。単純に譲渡所得の金額だけで判断するのではなく、両方の特例を適用した場合の税額を個別に計算し、より節税効果の高い方を選択することが重要です。
ふるさと納税で所得税・住民税を軽減する
不動産売却で譲渡所得が発生した年は、ふるさと納税を積極的に活用することで追加の節税効果を期待できます。ふるさと納税では、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されます。
譲渡所得により所得税・住民税の負担が増加した年であれば、通常よりも多くの寄附が可能になる場合があります。例えば、年収500万円の会社員が通常であれば5万9,000円程度のふるさと納税枠ですが、譲渡所得により税負担が増えれば、より多くの寄附が可能になります。
ふるさと納税の控除上限額は所得や家族構成により異なるため、事前にシミュレーションサイトで確認することが重要です。また、譲渡所得がある年は確定申告が必要になるため、ワンストップ特例は利用できない点にも注意が必要です。
これらの節税方法を組み合わせることで、相続不動産の売却における税負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、特例の適用条件は複雑で、併用できないものもあるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続不動産の売却手続きと必要書類
相続不動産の売却を成功させるには、適切な手続きの流れを理解し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。手続きが複雑で時間もかかるため、事前に全体像を把握して計画的に進める必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、相続から3年以内に登記を完了させることが法的義務となりました。これにより、相続不動産の売却においても、より迅速かつ確実な手続きが求められるようになっています。
相続登記から売却完了までの手順
相続不動産の売却は、以下の手順で進行します。
1.相続人の確定と必要書類の収集
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。相続人が複数いる場合は、各相続人の戸籍謄本も必要になります。
2.遺産分割協議の実施
不動産の相続について相続人全員で協議し、誰が不動産を取得するかを決定します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
3.相続登記の申請
法務局に相続登記を申請します。2024年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを完了させる必要があります。登録免許税は不動産価額の0.4%がかかります。
4.不動産会社の選定と売却活動
相続登記が完了したら、信頼できる不動産会社を選定し、売却活動を開始します。査定、媒介契約の締結、販売活動、購入者との交渉を経て、売買契約を締結します。
5.決済・引渡し
買主から売買代金を受領し、不動産の引渡しを行います。同時に、買主への所有権移転登記も実施されます。
この一連の流れは、相続開始から売却完了まで通常6ヶ月から1年程度かかります。税制上の特例を活用したい場合は、期限内に売却を完了させることが重要です。
確定申告の時期と準備すべき書類
相続不動産を売却した場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。申告が必要となるのは、譲渡所得が発生した場合や、特例の適用を受ける場合です。
確定申告に必要な主な書類
・確定申告書第一表・第二表
・確定申告書第三表(分離課税用)
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・売買契約書のコピー
・取得時の売買契約書のコピー(取得費証明用)
・諸費用の領収書(仲介手数料、印紙税など)
・登記事項証明書
特例適用時の追加書類
空き家の3,000万円特別控除を適用する場合は、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書または取壊し証明書などが必要になります。
取得費加算の特例を適用する場合は、相続税の申告書の写しや相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書が必要です。
確定申告の準備は売却決定時から始めることをおすすめします。特に、被相続人の購入時の書類は紛失しやすいため、相続開始後早期に確認・保管することが重要です。
相続不動産で複数相続人がいる場合の合意形成
複数の相続人がいる場合、不動産売却には全員の合意が必要です。合意形成のプロセスには特に注意が必要で、以下のポイントを押さえる必要があります。
合意形成における重要なポイント
・相続人全員の参加と同意が必須
・売却価格、売却時期、費用分担について事前協議
・売却代金の分配方法の明確化
・代表者の選定と権限の明確化
遺産分割協議では、不動産を共有で相続するか、特定の相続人が単独で相続するかを決定します。共有で相続した場合、売却時には共有者全員の同意が必要となり、手続きが複雑になります。
売却を前提とする場合は、代表者一人が相続して売却し、売却代金を相続人で分配する方法が効率的です。ただし、この場合は遺産分割協議書に売却と分配について明記しておかないと、贈与税の問題が発生する可能性があります。
トラブル回避のための対策:
・早期の情報共有と協議開始
・専門家(司法書士、税理士)への相談
・書面による合意内容の記録
・相続登記期限(3年以内)を意識したスケジュール管理
相続人間で意見が対立した場合は、家庭裁判所での調停や審判による解決も可能ですが、時間とコストがかかります。話し合いによる円満な解決を目指し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。
相続不動産の売却は、法的手続きと税務手続きが複雑に絡み合うため、早期の準備と専門家のサポートを活用することで、スムーズな売却を実現できます。
相続不動産売却でよくある税金の失敗と対策
相続不動産の売却では、知識不足や準備不足により、本来であれば避けられたはずの高額な税負担や手続き上のトラブルが発生することがあります。これらの失敗は、適切な知識と事前準備があれば十分に防げるものです。
ここでは、相続不動産売却で特に多く見られる4つの失敗パターンと、その対策方法について解説します。これらの失敗を避けることで、数百万円単位の節税効果を得られる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
特例の併用ができず高額な税金を払ってしまった
最も多い失敗の一つが、複数の特例制度の存在を知らずに、最適ではない特例を選択してしまうケースです。特に「空き家の3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」は併用できないため、どちらを選択するかで税負担が大きく変わります。
失敗例:譲渡所得4,000万円の相続不動産を売却する際、相続税1,000万円を支払ったにもかかわらず、取得費加算の特例(節税効果約200万円)のみを適用し、空き家の3,000万円特別控除を見逃してしまった。結果として約600万円多く税金を支払うことになった。
対策:売却前に必ず複数の特例制度を比較検討することが重要です。一般的には、譲渡所得が3,000万円以下なら空き家特例を、3,000万円を超える場合は各特例の節税効果を試算して最適なものを選択します。税理士への相談により、最適な特例選択と節税戦略を立てることをおすすめします。
取得費の証明書類を用意せず概算取得費で損をした
相続不動産では、被相続人が数十年前に購入した不動産の取得費を証明する書類が見つからないケースが多くあります。この場合、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を適用することになりますが、実際の取得費よりもかなり低くなり、税負担が重くなってしまいます。
失敗例:5,000万円で売却した不動産で、実際の取得費は2,000万円だったにもかかわらず、売買契約書が見つからずに概算取得費250万円(5,000万円×5%)を適用。譲渡所得が1,750万円増加し、約355万円多く税金を支払うことになった。
対策:相続開始直後から、被相続人の重要書類を整理し、不動産関連の書類を探すことが重要です。売買契約書が見つからない場合でも、以下の方法で取得費を証明できる場合があります。
・購入時の住宅ローン契約書(借入額から購入価格を推定)
・購入した不動産会社への問い合わせ
・市街地価格指数を用いた取得費の推計
・不動産鑑定士による鑑定評価
これらの方法により、概算取得費よりも有利な取得費を証明できる可能性があります。
相続不動産の売却時期を誤って税率が高くなってしまった
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年を境に大きく変わります。相続不動産では被相続人の所有期間を引き継ぐため、通常は長期譲渡所得(20.315%)の税率が適用されますが、まれに短期譲渡所得(39.63%)になってしまうケースがあります。
失敗例:被相続人が不動産を購入して3年後に亡くなり、相続人が相続から1年後に売却した場合、所有期間は通算4年となり短期譲渡所得の税率が適用された。長期譲渡所得との税率差により、約200万円多く税金を支払うことになった。
対策:売却前に必ず所有期間を正確に計算することが重要です。所有期間の起算日は被相続人が不動産を取得した日ですが、長期か短期かの判定は「売却した年の1月1日時点」で行われます。この1日を過ぎるだけで税率が約半分になる可能性があるため、所有期間が5年に近い場合は、年明けまで待ってから売却するなど、売却時期の調整が極めて有効な節税策となります。
所有期間が5年に近い場合は、売却時期を調整することで長期譲渡所得の税率を適用できる場合があります。ただし、特例の適用期限(相続から3年など)との兼ね合いも考慮する必要があります。
相続から3年10ヶ月を過ぎて取得費加算の特例を逃した
取得費加算の特例は、相続開始から3年10ヶ月以内に売却することが適用条件です。この期限を過ぎてしまうと、相続税を支払っていても特例の適用を受けることができません。
失敗例:相続税1,200万円を支払ったにもかかわらず、売却時期が相続から4年後となり、取得費加算の特例を適用できなかった。本来であれば約300万円の節税効果があったが、期限切れにより恩恵を受けられなかった。
対策:相続が発生したら、早期に不動産売却の検討を始めることが重要です。売却を決断した場合は、以下のスケジュール管理を徹底します。
・相続開始日の正確な記録
・3年10ヶ月後の期限日の把握
・遺産分割協議の早期完了
・相続登記の迅速な実施
・不動産会社の早期選定
特に、複数相続人がいる場合は合意形成に時間がかかることが多いため、相続開始後すぐに協議を開始することが重要です。売却活動自体にも3~6ヶ月程度かかることを考慮し、余裕を持ったスケジュールで進めることが成功の鍵となります。
これらの失敗を避けることで、相続不動産売却における税負担を大幅に軽減し、より多くの手取り金額を確保することができます。不明な点がある場合は、早めに税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|相続不動産を売却する際は税金対策を忘れずに
相続不動産の売却では、適切な税金対策により数百万円単位の節税が可能です。成功のポイントは、譲渡所得税の仕組み理解、3,000万円特別控除や取得費加算の特例など節税制度の活用、そして各種期限を意識した計画的な手続きです。特に取得費加算の特例は相続から3年10ヶ月以内、空き家特例は3年以内の売却が条件となります。税金対策を怠ると本来の手取り額が大幅に減少するため、早期の準備と専門家への相談が重要です。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。