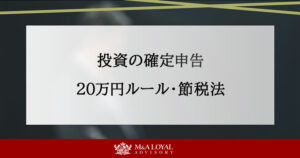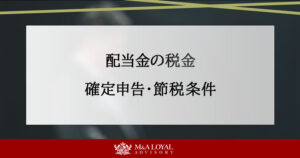配当控除とは?計算法やデメリット、住民税、確定申告が必要かを解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
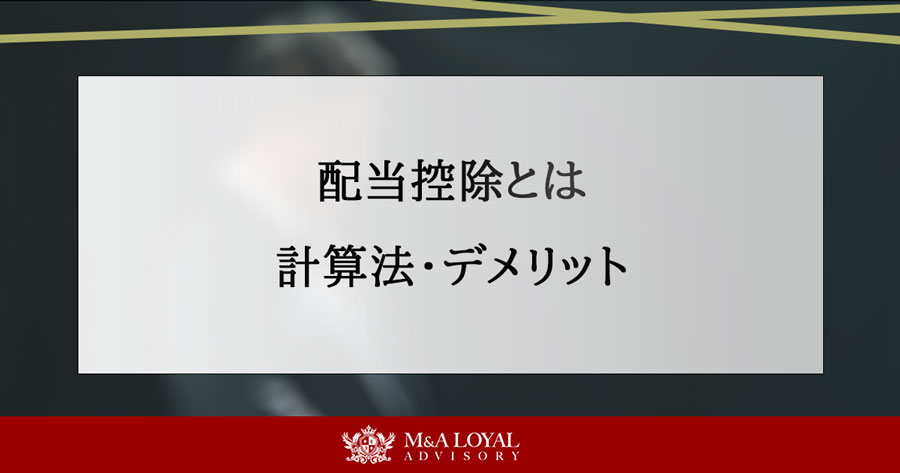
株式投資で得られる配当金には、所得税や住民税といった税金がかかります。ただし、一定の条件を満たすことで「配当控除」という仕組みを利用でき、実際に支払う税額を軽減することが可能です。
配当控除は税金面で大きなメリットがある一方で、選択方法によってはかえって納税額が増えたり、各種制度で不利になるケースもあるため注意が必要です。
本記事では、配当控除の基本的な仕組みから対象となる配当金の種類、具体的な計算式やシミュレーション方法、確定申告の要否、メリット・デメリットまでを詳しく解説します。さらに、M&Aや法人税務における配当金の扱い、よくある質問も取り上げ、実務や投資判断に役立つ知識を整理しています。
目次
配当控除とは?基本をわかりやすく解説
まず配当控除とは何なのか基本知識を紹介します。
配当控除の概要
配当控除とは、個人が株式などから受け取った配当金に対して課税される際に、二重課税を調整するための税額控除制度のことです。
株式の配当金は、企業が利益から法人税を支払った後に株主へ分配されます。つまり、同じ利益に対して「法人税」と「所得税」の二重課税が起きる構造になっています。この不公平を緩和するために設けられている制度が配当控除です。
具体的には、確定申告で「総合課税」を選択した場合に利用でき、配当金額の一定割合が所得税や住民税から控除されます。その結果、配当金にかかる実質的な税負担が軽減される仕組みです。
総合課税については後述します。
税額控除とは?例をもとに説明
税額控除とは、課税所得に税率をかけて計算された所得税額から、一定の金額を直接差し引く仕組みです。例えば、課税所得が300万円で税率が20%の場合、本来の所得税額は60万円となりますが、税額控除が15万円あれば、納める税金は60万円から15万円を差し引いた45万円となります。
一方、所得控除は税額ではなく、税額を計算する前の課税所得から控除を行います。課税所得300万円から15万円を差し引き、285万円に税率をかけて所得税額を算出する仕組みです。
同じ控除額で比較した場合、税額控除は計算済みの税金から直接差し引くため、所得控除よりも節税効果が大きくなることが多いといえます。この違いを理解しておくことで、各制度の性質や効果をより明確に把握できます。
配当金にかかる税金
上場株式の配当金については、支払時に源泉徴収が行われ、その税率は合計20.315%です。内訳は、所得税15.315%(この中には復興特別所得税が含まれています)と住民税5%となっており、証券会社の口座で受け取る段階で既に税金が差し引かれる仕組みになっています。
これに対して、非上場株式の配当金や、上場株式であっても発行済み株式総数の3%以上を保有するいわゆる大口株主が受け取る配当金は取り扱いが異なります。この場合、源泉徴収の対象は所得税のみで、税率は20.42%です。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



配当控除の対象
配当控除の対象になる配当控除と、ならない配当金がありますので、それぞれを解説します。
配当控除の対象になる配当金
配当控除を受けられる配当所得とは、日本国内に本店を置く法人から受け取る剰余金の配当や利益の配当、または剰余金や金銭の分配、さらに証券投資信託の収益分配などが対象です。ただし、これらであっても確定申告において総合課税を選択した場合に限られます。
一方で、外国法人から受け取る配当や、利子所得や雑所得として扱われる分配金は配当控除の対象外です。法人税が既に国内で課されており、二重課税調整が必要となる所得に限定して配当控除が認められる仕組みであるためです。
配当控除の対象にならない配当金
次の配当などは配当控除の対象ではありません。
- 基金利息
- 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
- 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
- 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
- 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
- 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
- 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
- 特定目的会社から支払を受けるべき配当等
- 投資法人から支払を受けるべき配当等
- 確定申告不要制度を選択したもの
- 申告分離課税制度を選択したもの
確定申告不要制度と申告分離課税制度については後述します。
配当控除の計算方法
次に配当控除の計算方法を紹介します。
課税所得金額が1000万円以下
課税所得金額が1000万円以下の場合、所得税の控除の割合は次のとおりです。
- 剰余金の配当等に係る配当所得:10%
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得:5%
- 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配:2.5%
課税所得金額が1000万円以下の場合、住民税の控除の割合は次のとおりです。
- 剰余金の配当等に係る配当所得:2.8%
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得:1.4%
- 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配:0.7%
課税所得金額が1000万円超え
課税所得金額が1000万円超えの場合、所得税の控除の割合は次のとおりです。
- 剰余金の配当等に係る配当所得:5%
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得:2.5%
- 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配:1.25%
課税所得金額が1000万円超えの場合、住民税の控除の割合は次のとおりです。
- 剰余金の配当等に係る配当所得:1.4%
- 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得:0.7%
- 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配:0.35%
配当控除の所得税の四つのパターン
所得税の配当控除の四つのパターンを紹介します。
パターン①
配当所得以外の所得が500万円、剰余金の配当による配当所得が100万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得が100万円あるとします。この場合、合計所得は700万円となり、課税総所得金額は1,000万円以下です。
従って、剰余金の配当100万円に対しては10%の控除が適用され10万円、証券投資信託の分配金100万円に対しては5%の控除が適用され5万円となります。
両者を合計すると、控除額は15万円です。
パターン②
配当所得以外の所得が500万円、剰余金の配当による配当所得が100万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得が500万円あるとします。この場合、合計所得は1100万円となり、課税総所得金額は1,000万円超え、かつ、課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額は1,000万円以下です。
従って、剰余金の配当による配当所得の100万円に対しては10%の控除が適用され10万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得の500万円のうち、課税総所得金額1000万円以内の400万円に対しては5%の控除が適用され20万円、残りの100万円に対しては2.5%が適用され2.5万円となります。
それぞれを合計すると、控除額は32.5万円です。
パターン③
配当所得以外の所得が800万円、剰余金の配当による配当所得が400万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得が200万円あるとします。この場合、合計所得は1400万円となり、課税総所得金額は1,000万円超え、かつ、課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額も1,000万円超えです。
従って、剰余金の配当による配当所得の400万円のうち、課税総所得金額1000万円以内の200万円に対しては10%の控除が適用されて20万円、残りの200万円に対しては5%が適用されて10万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得の200万円に対しては2.5%が適用されて5万円となります。
それぞれを合計すると、控除額は35万円です。
パターン④
配当所得以外の所得が1200万円、剰余金の配当による配当所得が100万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得が100万円あるとします。この場合、配当所得以外の所得単体で1000万円を超えています。
従って、剰余金の配当による配当所得の100万円に対して5%の控除が適用されて5万円、証券投資信託の収益分配金による配当所得の100万円に対して2.5%の控除が適用されて2.5万となります。
それぞれを合計すると、控除額は7.5万円です。
配当控除のデメリット
配当控除を利用する際の注意点は次のとおりです。
- 総合課税を選択する必要があり手間がかかる
- 納税額がかえって増える場合がある
- 各種制度で不利になる場合がある
それぞれを詳しく解説します。
総合課税を選択する必要があり手間がかかる
配当控除を受けるには、確定申告で「総合課税」を選択することが必須です。
証券会社で「特定口座・源泉徴収あり」を利用している人であれば、通常は税金の計算や納付が全て自動で完結し、申告の必要がありません。しかし、配当控除を適用したい場合は、あえて確定申告を行わなければならず、申告書の作成や添付書類の準備など、余分な手間がかかります。
特に、株式の配当だけでなく給与や事業所得など複数の所得がある人は計算が複雑になりやすく、配当控除を活用するために税理士へ依頼する必要が出てくるケースもあります。そのため、手間やコストを考慮した上で利用するかどうかを判断する必要があります。
納税額がかえって増える場合がある
総合課税を選択すると、配当所得は給与や事業所得などと合算され、累進課税の対象となります。日本の所得税は「所得が増えるほど税率が高くなる仕組み」になっているため、配当所得を合算することで課税所得が大きくなり、高い税率の区分に移ってしまう可能性があります。
その結果、配当控除で税額を軽減できるはずが、逆に税率上昇による負担増の方が大きくなり、源泉徴収で済ませた場合より納税額が増えるという逆効果が起きてしまいます。
配当控除の損得分岐点は課税所得695万円とされています。この金額を境にして、695万円未満の人であれば総合課税を選択して配当控除を受ける方が有利になりやすいといえます。
各種制度で不利になる場合がある
配当所得を総合課税に含めると、合計所得金額が増加します。合計所得金額はさまざまな制度の判定基準として使われているため、その影響は広範囲に及びます。
例えば、配偶者控除や扶養控除は合計所得金額が一定額を超えると適用されなくなり、家族の税負担に直接響くことがあります。また、住民税の非課税判定から外れることで、医療費の自己負担割合が上がったり、福祉サービスの利用料が増えたりする可能性もあります。
さらに、国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料は合計所得金額を基に計算されるため、総合課税によって配当所得を合算した結果、翌年度の保険料が高くなるケースも見られます。
このように、配当控除を選ぶことが必ずしも得になるとは限らず、所得全体の状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
配当金の確定申告が不要な場合
配当金の確定申告が不要なパターンは次のとおりです。
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)で20万円未満の利益
- NISA(少額投資非課税制度)を利用
それぞれを分かりやすく解説します。
特定口座(源泉徴収あり)
証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる場合、配当金や譲渡益にかかる税金は証券会社が自動で計算し、源泉徴収まで行ってくれます。そのため、投資家は自ら確定申告をする必要がありません。
いわば「手間なく課税関係を完結させる仕組み」であり、投資初心者や申告の手間を省きたい人に広く利用されています。ただし、医療費控除など他の理由で確定申告をする場合には、配当所得を申告に含めて課税方式を選択することも可能です。
特定口座(源泉徴収なし)で20万円未満の利益
「特定口座(源泉徴収なし)」を利用している場合、本来は自分で損益計算をして確定申告が必要です。しかし、年間の配当金や売却益など給与所得以外の所得が20万円未満であれば、「申告不要制度」が適用され、申告しなくても良いことになっています。
これはあくまで給与所得者向けの特例であり、個人事業主など確定申告が必須の人には原則として当てはまらない点に注意が必要です。
NISA(少額投資非課税制度)を利用
NISA口座を利用して購入した株式から得られる配当金は、非課税で受け取れます。非課税枠の範囲内であれば、受け取った配当金に対して税金はかからないため、確定申告は不要です。
NISAは配当金だけでなく譲渡益も非課税になる制度であり、長期投資や節税を意識する投資家にとって非常に有効な仕組みです。ただし、NISA枠を超えた投資や通常の課税口座で受け取った配当については、別途課税対象です。
配当金の確定申告が必要な場合
配当金の確定申告が必要なパターンは次のとおりです。
- 特定口座(源泉徴収なし)で20万円以上の利益
- 非上場株式または大口株主が配当を得た
それぞれを分かりやすく解説します。
特定口座(源泉徴収なし)で20万円以上の利益
「特定口座(源泉徴収なし)」を選んでいる場合、証券会社は年間取引報告書を作成してくれますが、実際の納税手続きは投資家自身が行わなければなりません。
年間の配当金や株式譲渡益など、給与所得以外の所得が20万円以上となると、給与所得者でも必ず確定申告が必要です。20万円以下の給与所得者であれば「申告不要制度」が使えますが、それを超えると自分で所得を合算して申告・納税しなければならない点に注意が必要です。
非上場株式または大口株主が配当を得た
非上場株式から受け取る配当金や、上場株式でも発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主が受け取る配当金は、課税方式が異なります。これらは源泉徴収の対象が所得税のみで、住民税は別途申告により課税されるため、確定申告を通じて処理しなければなりません。さらに、大口株主の場合には総合課税のみが適用され、申告分離課税や申告不要制度を選択できません。つまり、保有株式の規模や性質によっては、自動的に確定申告が必須となるのです。
配当金の確定申告の方法
配当金の確定申告の方法には次の三パターンがあります。
- 申告不要制度
- 総合課税
- 申告分離課税
それぞれを分かりやすく解説します。
申告不要制度
特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当金は、証券会社が源泉徴収により納税まで完結させているため、原則的に確定申告をしなくても問題ありません。
これを「申告不要制度」と呼びます。投資家自身が申告する手間を省ける点がメリットですが、配当控除や損益通算といった節税効果は得られません。あくまで「簡便さを優先した方法」といえます。
総合課税
総合課税を選択すると、配当所得は給与所得や事業所得など他の所得と合算され、累進課税の対象になります。この際、配当控除を利用できるため、一定の範囲では税負担を軽減できます。
課税所得が695万円未満の人は配当控除の恩恵を受けやすく、有利になる可能性が高いです。ただし、課税所得が増えることで医療費控除や配偶者控除などに影響が出たり、住民税や社会保険料の負担が増える場合もあるため、総合的な判断が必要です。
申告分離課税
申告分離課税では、配当所得を給与や事業所得と切り離して申告します。税率は一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で、証券会社が源泉徴収する税率と同じです。
ただし、確定申告を行うことで、株式譲渡損失との損益通算や繰越控除が可能になります。株式投資で損失が出ている人にとっては、税負担を減らす有効な方法となります。
申告分離課税を選択するメリットは次の項目で詳しく解説します。
配当金を確定申告(申告分離課税)するメリット
配当金を確定申告(申告分離課税)することのメリットは次のとおりです。
- 損益通算
- 繰越控除
ただし、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
損益通算
複数の証券口座を利用して株式投資を行っている場合、ある口座では売却損が出ていても、別の口座で配当金や売却益による利益が出ているケースがあります。このようなときに申告分離課税を選択して確定申告を行えば、口座ごとの損益を合算できる「損益通算」が可能です。
損益通算とは、同じ年に発生した上場株式などの譲渡損失を、他の口座で得た上場株式の配当所得や譲渡益から差し引く仕組みです。これにより、利益が出ている口座で既に源泉徴収されている税金が還付される場合があります。
繰越控除
申告分離課税を選んで確定申告を行うと、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、最大3年間繰り越して翌年以降の売却益や配当と相殺できます。
例えば株式の売却で大きな損失が出た場合、配当と損益通算することで、配当に対して源泉徴収されていた税金が還付される可能性があります。さらに、当年で使い切れなかった損失は翌年以降の利益に充てられるため、将来の税負担を軽減する効果も期待できます。
そのため、上場株式で損失を抱えている投資家にとっては、申告分離課税を利用して確定申告を行うことが有利になるケースが多いといえます。
法人・M&Aにおける配当金
法人やM&Aに関連する配当金について解説します。
法人にかかる税金
法人税法には「受取配当等益金不算入」という制度が設けられています。これは、法人が他の法人から配当等を受け取ったとき、その一定割合を益金に含めないことで二重課税を防ぐ仕組みです。個人が配当控除を受けられるのと同様の考え方です。
受取配当等の益金不算入額は、受け取った配当金額に「不算入割合」を乗じて計算します。不算入割合は持株比率によって変わります。完全子法人(持株比率100%)や関連法人(持株比率3分の1超)の場合は100%が不算入です。その他の法人で持株比率が5%超3分の1以下の場合は50%が不算入、非支配法人(持株比率5%以下)の場合は20%が不算入とされています。
みなし配当とは
みなし配当とは、法人税法で定められた「剰余金の配当」には形式的には当たらないものの、実質的には配当と同じ性質を持つ株主の利益を指します。実際に通常の配当金を受け取っているわけではありませんが、税務上の整合性を図るために配当の一種として扱われます。
具体例としては、次のようなケースが挙げられます。
自己株式を会社が買い取る場合
自己株式とは、その会社自身が発行した株式のことです。会社が既存の株主から自己株式を取得する際には、株主に対価を支払います。その支払額が、株主が当初出資した金額より大きければ、その差額は株主の利益とみなされ、みなし配当として課税の対象となります。
会社の解散や清算に伴う残余財産の分配
会社を解散・清算するとき、残った財産は株主に分配されます。その残余財産には事業活動によって生じた利益が含まれるため、株主に渡す分配金は事実上の配当と考えられます。従って、この分配もみなし配当として処理されます。
資本剰余金からの配当
資本剰余金とは、株式発行などの資本取引で得た出資金のうち、資本金に計上されなかった部分です。企業は通常、利益剰余金から配当を行いますが、資本剰余金から株主に分配することも可能です。
これにより業績が振るわない時期でも配当を継続できるという利点があります。ただし、株主の立場からすれば、自ら出資した資金の一部が戻ってきただけともいえるため、通常の配当とは異なり、特別な税務上の扱いが必要です。
子会社株式の譲渡と組み合わせた節税
特別配当は、本来は企業の業績が非常に好調なときに臨時で支払われる追加配当を指します。ところがM&Aの場面では、税務上の調整手段として利用されることがありました。
例えば親会社が完全子会社を売却する場合、配当を行わずに株式を売却すると「売却価額-簿価」の差額がそのまま課税対象です。これに対して、売却前に子会社が特別配当を実施すると、その配当金は親会社で「益金不算入」として非課税扱いになり、結果的に株式売却益が圧縮され、税負担を抑えられます。
この仕組みには双方にメリットがあります。親会社(譲渡側)は実質的な受取総額を減らさずに税金を軽くでき、買収する側(譲受側)は余剰資金が配当として事前に出されるため、買収に必要な資金を少なくできるのです。
ただし課題もあります。配当を行うと子会社の純資産が減り株価も下がりますが、その配当は親会社で非課税になるため、この性質を利用して「意図的に損失を作り出す」スキームが行われることがあります。国際的なM&Aでも同様の仕組みが租税回避につながる可能性があるとして懸念されていたのです。
こうした状況を受け、令和2年度税制改正大綱では特別配当を活用した節税スキームが取り上げられました。現在では、従来のように税負担を軽減する方法として利用することは難しくなり、将来的には租税回避を目的とした使い方は認められなくなると見込まれています。
配当金を得るメリット
そもそも配当金を得るメリットは何なのでしょうか。それらは主に次のとおりです。
- 不労所得による経済的自立
- 投資知識・経済観の向上
- インカムゲインとキャピタルゲインの両取り
それぞれを解説します。
不労所得による経済的自立
配当金生活の大きな魅力は、株式を保有しているだけで不労所得を得られる点にあります。毎月の給与と異なり、働かなくても企業が生み出した利益の一部を現金として受け取れるため、経済的な自立度が高まります。
生活の一部、あるいは全てを配当金で賄えるようになれば、会社に依存しない生き方が可能になり、早期リタイア(FIRE)を目指す人にとっては特に重要な収入源です。また、定期的に現金収入があることで精神的な余裕が生まれ、仕事や生活における選択肢が広がる点もメリットです。
投資知識・経済観の向上
配当金生活を送るためには、配当を安定的に支払う企業を選ぶ必要があるため、自然と企業の財務状況や配当方針、業界の動向などを調べる習慣がつきます。その過程で投資の知識やスキルが磨かれ、経済全体の仕組みにも詳しくなっていきます。
こうして身につけた知識は、配当株投資だけでなく、株式売買や不動産投資、さらには起業や副業など他の分野にも応用できる可能性があります。配当金生活は単なる収入源にとどまらず、投資家としての成長を促すきっかけになるのです。
インカムゲインとキャピタルゲインの両取り
配当金は、株式を持っているだけで得られる「インカムゲイン」です。安定して得られる現金収入は生活の基盤を支えますが、配当金生活の魅力はそれだけではありません。
保有している株式の株価が上昇すれば、売却時に「キャピタルゲイン」としてさらに利益を得られる可能性があります。つまり、配当金生活では安定収入と値上がり益の両方を狙えるのです。特に優良企業の株を長期保有している場合、時間の経過とともに配当金は増配され、株価も成長することで、二重のリターンが期待できます。
配当金を得るデメリット
一方で配当金を得ることにはデメリット・注意点もあります。それらは主に次のとおりです。
- 減配・無配のリスク
- 株価下落による資産価値の減少
- 多額の資金が必要
- 精神的な負担
- 高配当株は株価成長が期待しにくい
それぞれを解説します。
減配・無配のリスク
配当金はあくまで企業の利益から支払われるため、業績が悪化すれば減配や無配に直結します。利益が減少すると、まずは内部留保や事業投資を優先せざるを得なくなり、そのしわ寄せとして株主への配当が削減されるのです。
生活費を配当金に頼っている場合、このような突然の収入減は生活設計を大きく狂わせる要因となります。実際に、リーマンショックなどの経済危機では、長年安定配当を続けていた有名企業ですら減配や無配に踏み切った例があります。従って、どんなに「安定配当」を掲げる企業であっても、完全に減配リスクを避けることはできず、投資家はその不確実性を織り込んでおく必要があります。
株価下落による資産価値の減少
配当を受け取り続けていても、株価の下落によって資産全体の評価額が大きく減少する可能性があります。例えば年間で100万円の配当収入を得ていても、その間に保有株式の評価額が1,000万円下落した場合、トータルでは大きな損失です。
特に配当金生活を実現するためには高額の株式を保有していることが多いため、数%の株価変動でも数百万円規模の資産変動が起きやすくなります。
配当金に着目するあまり株価の下落リスクを軽視すると、資産全体のバランスが崩れ、精神的な負担も増大するため、長期的な視点で資産価値を維持する工夫が欠かせません。
多額の資金が必要
配当金だけで生活を賄うには、相当な投資元本が必要です。
例えば、毎月30万円、年間で360万円の生活費を配当金でカバーする場合、配当利回りが3%であれば必要資金は1億円を超え、一般的な個人投資家にとってはかなり高いハードルです。また、不動産投資と違い、株式投資ではローンが組みにくいという特徴があります。
さらに、利回りが安定して続く保証はなく、業績や株価によって変動する点も無視できません。そのため、現実的には「生活費の全てを配当で賄う」よりも「生活費の一部を配当で補う」という段階的な戦略を取る人が多くなります。
精神的な負担
株価や配当の動向は日々変化するため、配当金生活を送る投資家は常に市場の動きに目を向ける必要があります。決算発表や経済ニュースのたびに、配当が維持されるかどうか、株価が急落しないかといった不安に直面し、心が休まらないケースも珍しくありません。
特に多額の資産を投じている場合、数%の値動きでも資産の増減は数百万円単位となり、精神的なプレッシャーは計り知れません。資産規模が大きくなるほど、このストレスを冷静に受け止めるメンタルコントロールが求められます。
高配当株は株価成長が期待しにくい
高配当株の多くは成熟企業であり、安定した収益力を持つ一方で、事業拡大の余地が限られているケースが少なくありません。そのため、配当収入は安定しても株価自体の大幅な成長は望みにくいことが実情です。高配当銘柄に集中投資すると、短期的には配当収入で安心感が得られますが、長期的な資産形成という視点では成長力の鈍化につながります。
また、高配当株は景気変動や金利動向の影響を受けやすく、配当の持続性が危ぶまれる場面もあります。従って、配当金生活を目指す場合でも、成長株や海外株、ETFなどを組み合わせ、分散投資によって全体のバランスを保つことが欠かせません。
配当控除に関するQ&A
最後に、配当控除に関連するよくある質問とその回答を紹介します。
配当金はいつ、どのように受け取れるのか
国内株式の配当金は、銘柄ごとの権利確定日時点の保有株数に応じて計算され、支払いは通常2~3カ月後に行われます。受け取り方法はいくつか用意されており、それぞれの特徴や受取場所が異なります。
一般的な方法が「株式数比例配分方式」で、証券会社の口座に直接入金される方法です。この場合、保有残高に応じた配当金が当社証券総合口座に振り込まれます。また、「登録配当金受領口座方式」を選ぶと、全ての配当金をあらかじめ指定した金融機関の口座にまとめて受け取れます。
従来方式としては、「配当金受領証方式」があり、会社から郵送される配当金領収証を持参し、郵便局などの窓口で現金を受け取る仕組みです。さらに「個別銘柄指定方式」を利用すれば、銘柄ごとに振込先の金融機関を指定し、その口座に配当金を振り込ませることも可能です。
なお、実際の支払日程(配当金支払開始日)は、各発行会社の決算短信に記載される配当金支払開始予定日や、企業ホームページなどで確認する必要があります。
配当金に種類はあるか
配当金にはいくつかの種類があります。
最も基本的なのは、決算期末に支払われる「期末配当」です。加えて、企業が期中に業績や資金繰りを勘案して行う「中間配当」もあります。
さらに、利益が想定以上に出たときに臨時的に支払われる「特別配当」、企業の周年記念や上場記念など特別な出来事に合わせて支払われる「記念配当」などもあります。
配当の種類は企業の方針や財務状況によって異なり、安定配当を重視する企業もあれば、臨時配当を柔軟に実施する企業もあります。投資家にとっては、こうした配当方針を理解することが投資判断の材料の一つです。
配当利回りとは何か
配当利回りとは、株式投資において受け取れる配当金の水準を株価との関係で示した指標です。
計算式は「1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100」で求められ、パーセンテージで表示されます。例えば、株価1,000円の株に対して年間50円の配当があれば、配当利回りは5%です。
利回りが高いほど投資収益性が高いように見えますが、必ずしも「高配当=安心」とは限りません。業績が一時的に好調なだけで継続性がないケースや、株価下落によって見かけ上利回りが高くなっている場合もあるため、企業の配当性向や財務の健全性も併せてチェックすることが大切です。
配当金とキャピタルゲインの違いは何か
配当金は、企業が株主に対して利益を分配することで得られる「インカムゲイン」であり、株式を保有している限り定期的に受け取れます。
一方、キャピタルゲインは株式の売買によって得られる「値上がり益」であり、売却時にのみ実現します。投資家にとって、配当金は安定収入をもたらす一方、キャピタルゲインは相場環境に左右されやすく、リスクとリターンの変動が大きい点が特徴です。
長期投資では、配当金を再投資して複利効果を狙う戦略がよく使われますが、キャピタルゲインを重視する短期売買型の投資家も存在します。両者をどう組み合わせるかによって投資スタイルが変わってくるのです。
配当可能限度額とは何か
配当可能限度額とは、会社が株主に配当できる上限額を意味し、会社法に基づいて計算されます。
具体的には、利益剰余金をベースに、資本金や準備金、未処理損失などを考慮して算出されます。この制度の目的は、過剰な配当によって会社の資金繰りが悪化し、債権者や従業員に不利益が及ぶのを防ぐことにあります。
例えば、業績が一時的に好調であっても、配当可能限度額を超えて配当することは法律上認められていません。投資家にとっては、企業がどの程度の資金余力を持って配当を行っているのかを見極めるための重要な指標となります。持続的に高配当を維持できる企業は、健全な財務基盤と安定した収益力を有している可能性が高いと考えられます。
まとめ
配当控除は、株式投資で得た配当金にかかる税金を軽減する重要な仕組みです。しかし、選択肢を誤ると、かえって税金が増えるリスクもあります。そのため、配当控除を利用する際は、自分の所得状況や投資計画に合った選択をすることが大切です。特に、総合課税や申告分離課税などの選択肢を理解し、適切に確定申告を行うことで、最大限のメリットを享受できます。また、配当控除の影響は所得だけでなく、住民税や他の税制優遇にも関わるため、トータルでの税負担を考慮する必要があります。この記事を参考に、配当控除を上手に活用し、賢い投資を実現してください。次に、具体的な控除額や確定申告の手続きについて、税理士に相談することもおすすめです。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。