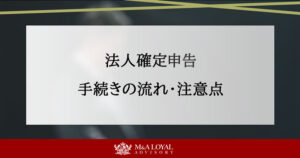赤字の場合の法人税はどうなる?免除される税金の種類や条件を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
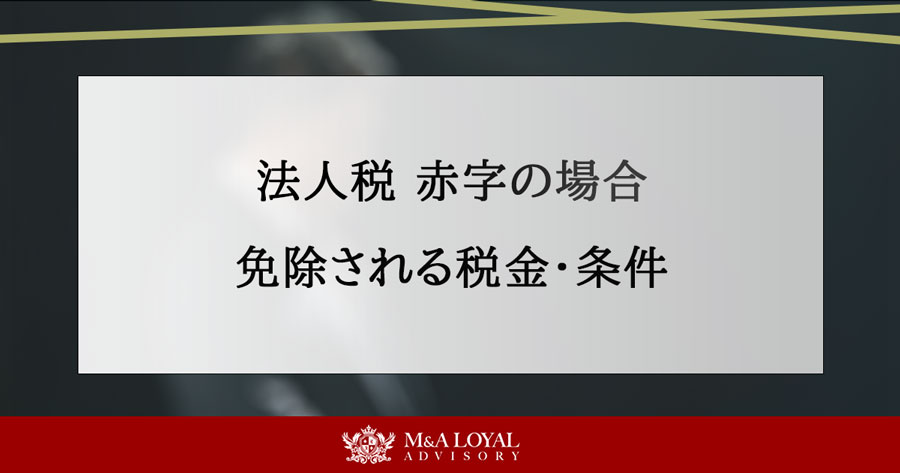
法人が赤字決算となった場合、多くの経営者が気になるのが法人税など税務上の取り扱いです。「赤字なら税金は一切かからないのか」「どの税金が免除されて、どの税金は支払う必要があるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。実際には、赤字決算でも全ての税金が免除されるわけではありません。法人税は免除されますが、消費税や法人住民税の均等割など、赤字でも納付が必要な税金があります。また、赤字決算には繰越欠損金の活用や法人税の還付といったメリットもある一方で、金融機関からの信用低下などのデメリットも存在します。
本記事では、赤字の場合の法人税の取り扱いを中心に、免除される税金と課税される税金の種類、赤字を活用した税金対策の方法について詳しく解説します。
目次
赤字決算の基本と税務上の取り扱い
赤字決算とは、法人の収入が支出を下回り、損失が生じた状態を指します。会計上では「当期純損失」として処理され、損益計算書において最終的な利益がマイナスとなる状況です。
税務上の赤字の判定は、会計上の赤字とは必ずしも一致しません。法人税法では「課税所得がマイナス」の状態を指し、各種調整を経て算出される所得金額がゼロ以下となる場合を税務上の赤字とします。
会計上の赤字と税務上の赤字の違い
会計上は赤字でも税務上は黒字となるケースがあり、この場合は法人税の納付義務が発生します。主な要因として、減価償却費の損金算入限度額の違いや、役員報酬の損金不算入項目、引当金の繰入限度額などが挙げられます。
例えば、会計上は任意償却が認められている減価償却費も、税務上は法定償却方法による計算が必要となります。 また、役員に対する過度な報酬や賞与は、税務上の損金として認められない場合があります。
赤字決算のメリット・デメリット
赤字決算には税務上のメリットがある一方で、経営面でのデメリットも存在します。税務上のメリットとしては、課税所得がないため法人税が発生しないことや、繰越欠損金控除を活用して将来の税負担を軽減できる点が挙げられます。また、過剰に支払った予定納税が還付されるケースもあります。
一方のデメリットは、金融機関からの信用低下による融資条件の悪化、債務超過に陥るリスクの増加、株主や取引先からの評価低下などがあります。特に継続的な赤字決算は、企業の存続性に対する疑念を生じさせる可能性があり、経営の早期改善が求められます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



赤字でも課税される税金の種類と詳細
赤字決算であっても、全ての税金が免除されるわけではありません。利益の有無に関係なく課税される税金が複数存在し、これらは企業活動を継続している限り納付義務が発生します。
主な課税対象となる税金は、消費税、法人住民税の均等割、一定規模以上の法人に適用される法人事業税の外形標準課税部分です。これらの税金は、それぞれ異なる課税根拠に基づいて徴収されます。
消費税の納付義務
消費税は事業者が消費者から預かった税金を国に納付する仕組みであるため、法人の利益の有無に関係なく納付義務が発生します。課税売上高が1,000万円を超える事業年度の翌々事業年度から課税事業者となり、消費税の納付が必要です。
赤字決算であっても売上があれば消費税の課税対象となります。ただし、課税売上高が5,000万円以下の中小企業は簡易課税制度を選択でき、みなし仕入率(業種別に設定された一定の割合)を適用することで消費税額を簡便に計算することが可能です。
法人住民税の均等割
法人住民税の均等割は、法人が地方自治体内で事業活動を行うことに対する対価として課税される税金です。資本金等の額と従業員数に応じて税額が決定され、利益の有無に関係なく課税されます。均等割の税額は地方自治体ごとに条例で定められていますが、標準税額が適用されることが一般的です。
例えば、資本金1,000万円以下で従業員50人以下の法人の場合、年額7万円が標準的な税額です。資本金や従業員数が増加するにつれて税額も段階的に上昇し、最大で資本金50億円超の法人に対して年額300万円が課されます。
法人事業税の外形標準課税
資本金1億円超の大法人には、法人事業税において外形標準課税が適用されます。これは所得割に加えて、付加価値割と資本割による課税が行われる制度です。
付加価値割は報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計額に対して課税され、資本割は資本金等の額に対して課税されます。これらは利益とは無関係に算定されるため、赤字決算であっても納付義務が発生します。
| 税金の種類 | 課税根拠 | 赤字時の課税 |
|---|---|---|
| 消費税 | 預かり金の性質 | 課税あり |
| 法人住民税(均等割) | 地方自治体利用の対価 | 課税あり |
| 法人事業税(外形標準) | 事業活動の規模 | 課税あり(資本金1億円超) |
赤字で免除される税金
赤字決算の場合に納付義務が発生しない主な税金は、課税所得に基づいて課税されるものです。課税所得がゼロ以下となった場合、法人税、地方法人税、法人住民税の法人税割、中小法人における法人事業税の所得割については納付義務が発生しません。これらの税金は、企業の利益に応じて課税される仕組みとなっています。
法人税の免除条件
前述のとおり、法人税は課税所得に対して課税される税金であるため、赤字決算により課税所得がゼロ以下となった場合は納付義務が発生しません。ただし、税務上の所得計算は会計上の利益計算とは異なるため、会計上赤字でも税務上黒字となる場合があります。
法人税の計算における主要な調整項目として、減価償却費の損金算入限度額、役員報酬の損金不算入、交際費の損金算入限度額、引当金の繰入限度額などがあります。これらの調整により、最終的な課税所得が決定されます。
地方法人税の取り扱い
地方法人税は法人税額を課税標準として課税される税金です。法人税額がゼロの場合は地方法人税も課税されません。税率は法人税額の10.3%に設定されており、法人税と同様の取り扱いとなります。
地方法人税は平成26年度税制改正により創設された比較的新しい税金で、地方自治体間の税収格差是正を目的としています。
法人住民税の法人税割
法人住民税は均等割と法人税割の2つの部分から構成されています。法人税割は法人税額を課税標準として課税されるため、法人税がゼロの場合は法人税割も課税されません。
法人税割の税率は、標準税率として都道府県民税が1%、市町村民税が6%の合計7%とされています。ただし、実際の税率は自治体ごとに条例で定められており、標準税率から変更されている場合もあります。法人税額に税率を乗じて算出されますが、法人税額がゼロの場合は計算結果もゼロとなります。
中小法人の法人事業税
資本金1億円以下の中小法人における法人事業税は、所得割のみが適用されます。所得割は課税所得に対して課税されるため、赤字決算の場合は課税されません。
中小法人は外形標準課税の適用対象外であるため、赤字決算の場合は法人事業税の納付義務が一切発生しません。これは中小企業にとって重要な税制上の優遇措置の一つです。
| 免除される税金 | 課税標準 | 免除理由 |
|---|---|---|
| 法人税 | 課税所得 | 所得ゼロ以下のため |
| 地方法人税 | 法人税額 | 法人税額ゼロのため |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額 | 法人税額ゼロのため |
| 法人事業税(中小法人) | 課税所得 | 所得ゼロ以下のため |
赤字を活用した税金対策の方法
赤字決算は単なるマイナス要因ではなく、適切に活用することで将来的な税負担軽減や資金繰り改善につなげることができます。主要な活用方法として、繰越欠損金控除制度と法人税還付制度があります。
これらの制度を効果的に活用するためには、青色申告の継続や適切な申告手続きが必要となります。また、制度の適用要件や期間制限についても正確に理解しておく必要があります。
繰越欠損金控除制度の活用
繰越欠損金控除制度は、当期の赤字を将来10年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することで法人税を軽減できる制度です。この制度により、一時的な赤字が将来の税負担軽減に寄与します。
制度の適用を受けるためには、赤字が発生した事業年度に青色申告を行い、その後も継続して確定申告を提出する必要があります。申告を怠った事業年度がある場合、その事業年度以前の欠損金は繰越控除の対象外となります。
なお、繰越欠損金の控除限度額は、中小法人(資本金1億円以下等)の場合は所得金額の全額、大法人の場合は所得金額の50%に制限されています。この制限により、大法人では一度に全ての欠損金を控除することができない場合があります。
法人税還付制度の仕組みと計算
法人税還付制度は、前期に納付した法人税等の一部を当期の赤字により還付を受けることができる制度です。中小企業が対象となり、資金繰りの改善に大きな効果をもたらします。
還付制度の適用要件は、資本金1億円以下の青色申告法人であること、前期が黒字で当期が赤字であること、還付請求書を確定申告書と同時に提出することです。これらの要件を満たした場合、前期法人税額等のうち当期の欠損金に対応する部分が還付されます。
還付額の計算は、前期の法人税額等に「当期の欠損金額÷前期の所得金額」を乗じて算出されます。ただし、還付額は前期に納付した法人税額等を上限とし、当期の欠損金額を超えることはありません。
戦略的な赤字活用の注意点
税金対策を目的とした意図的な赤字作りは、金融機関や取引先からの信用低下を招く可能性があります。特に継続的な融資を受けている企業の場合、格付けの悪化により金利上昇や融資条件の厳格化につながる恐れがあります。
役員報酬の増額による赤字作りは、役員個人の所得税および社会保険料負担の増加を伴うため、総合的な税負担を考慮した判断が必要です。また、過度な節税対策は税務調査のリスクを高める可能性もあります。
中小企業における赤字対策の実務ポイント
中小企業が赤字決算を迎えた場合の実務対応では、税務面での対策と経営面での改善策を並行して検討する必要があります。税務上の優遇措置を最大限活用しながら、将来の業績回復に向けた取り組みを行うことが重要です。
中小企業には大企業にはない税制上の優遇措置が数多く用意されており、これらを適切に活用することで税負担の軽減と資金繰りの改善を図ることができます。
中小企業特有の優遇措置
中小企業は外形標準課税の適用対象外であるため、赤字決算の場合は法人事業税の納付義務が発生しません。また、法人税還付制度の適用対象でもあり、前期黒字・当期赤字の場合に還付を受けることができます。
さらに、中小企業の軽減税率制度により、年800万円以下の所得に対しては15%の軽減税率が適用されます。繰越欠損金控除制度においても、中小企業は控除限度額の制限を受けないため、欠損金の全額を将来の所得と相殺することが可能です。
均等割課税対象外となる条件
法人住民税の均等割は、原則として全ての法人に課税されますが、一定の条件を満たした場合に免除されることがあります。主な免除対象は、収益事業を行っていない公益法人、解散して清算手続中の法人、事務所や事業所を廃止して休眠状態にある法人などです。ただし、免除を受けるためには、収益事業を行っていないことや休眠届の提出など、法令や自治体の条例で定められた要件を満たす必要があります。
単純な赤字決算だけでは均等割の免除対象にはなりません。事業活動を継続している限り、赤字であっても均等割の納付義務が発生することに注意が必要です。
黒字倒産リスクへの対応
税務上は黒字であっても資金繰りが悪化し、黒字倒産に至るケースがあります。これは売上債権の回収遅延、在庫の滞留、設備投資による資金流出などが原因となります。
黒字倒産を回避するためには、損益管理だけでなく資金繰り管理を重視し、キャッシュフロー計算書による資金の動きを定期的に把握することが重要です。また、金融機関との良好な関係維持により、必要時に適切な資金調達を行える体制を整えておく必要があります。
税務調査対応の準備
赤字決算が継続している法人や法人税還付を受けた法人は、税務調査の対象となる可能性が高くなります。適切な帳簿書類の保存と、調整項目の根拠資料の整備を行っておくことが重要です。
特に減価償却費の計算、役員報酬の損金算入の適否、交際費の区分、引当金の計上根拠などについて、明確な説明ができるよう準備しておく必要があります。税理士等の専門家と連携し、適切な税務処理を行うことが税務リスクの軽減につながります。
地方自治体ごとの違いと注意事項
法人住民税の均等割や法人事業税の税率は、地方自治体ごとに異なる設定がなされています。企業が複数の自治体で事業を行っている場合、それぞれの自治体の税制を理解し、適切な税務処理を行う必要があります。
また、自治体独自の減免制度や優遇措置が設けられている場合もあり、これらの制度を活用することで税負担の軽減を図ることができる場合があります。
均等割の地域差
法人住民税の均等割は、都道府県民税と市町村民税の合計額で構成され、各自治体が条例により税率を設定しています。標準税率は全国共通ですが、自治体によっては制限税率の範囲内で独自の税率を設定している場合があります。
例えば、東京都の場合は都民税として一括徴収されますが、他の道府県では都道府県民税と市町村民税を別々に納付する必要があります。また、政令指定都市では市民税の税率が一般市町村と異なる場合があります。
事業所所在地による課税関係
法人が複数の都道府県に事業所を有している場合、法人事業税は各都道府県に分割して申告・納付する必要があります。分割基準は従業員数が基本となりますが、一部の業種では異なる基準が適用されます。
分割法人の場合、本店所在地の都道府県が主たる申告先となり、他の都道府県への分割申告を行います。各都道府県の税率や減免制度が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
地方自治体の減免制度
一部の地方自治体では、中小企業の経営支援を目的とした独自の減免制度を設けている場合があります。例えば、創業間もない企業や被災企業に対する均等割の減免、環境対策を行った企業に対する事業税の軽減などがあります。
これらの減免制度は申請主義となっているため、該当する可能性がある場合は積極的に情報収集を行い、適切な申請手続きを行うことが重要です。申請期限が設けられている場合が多いため、早めの対応が必要となります。
電子申告・納税システムの活用
地方税の申告・納税手続きは、eLTAX(エルタックス)による電子申告・納税システムの利用が推奨されています。全国の地方自治体に対して統一的なシステムで手続きを行うことができ、事務効率の向上につながります。
電子申告を利用することで、申告書の作成支援機能や過去データの活用、申告状況の確認などが可能となります。また、納税についてもダイレクト納付やインターネットバンキングを利用した電子納税が利用できます。
まとめ
赤字決算の場合の法人税は、課税所得がゼロ以下となるため納付義務が発生しません。同様に、地方法人税、法人住民税の法人税割、中小法人における法人事業税についても免除されます。
一方で、消費税、法人住民税の均等割、大法人における法人事業税の外形標準課税部分については、赤字決算であっても納付義務が継続します。これらの税金は利益とは異なる課税根拠に基づいているためです。
赤字決算は繰越欠損金控除制度や法人税還付制度を活用することで、将来的な税負担軽減や資金繰り改善につなげることができます。ただし、これらの制度を活用するためには青色申告の継続が必要であり、適切な税務処理と申告手続きが重要となります。企業の税務戦略や資金繰りの最適化を図る際は、専門家のアドバイスを活用することをお勧めいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。