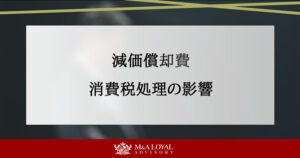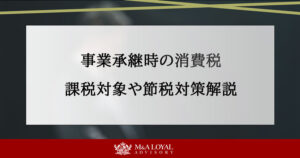法人にとっての消費税は?課税の対象となる取引や対応方法
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
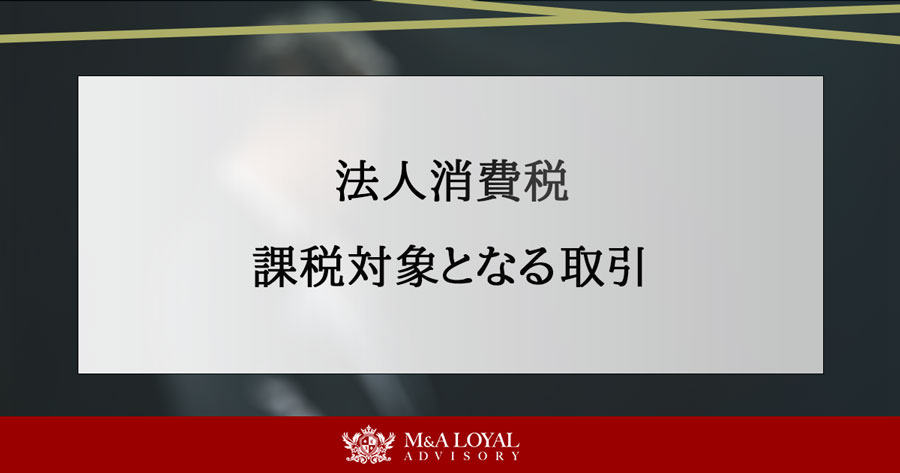
法人にとって消費税は、事業活動を行う上で避けて通れない重要な税金の一つです。近年のインボイス制度の導入により、法人の消費税対応はより複雑化しており、適切な理解と対応が求められています。 消費税は消費者が最終的に負担する間接税ですが、法人は課税事業者として消費税の納税義務を負う場合があります。 また、M&Aにおける事業譲渡では消費税が課税されるケースもあり、 法人経営者にとってその知識は経営戦略を立てる上でも不可欠な要素となっています。 本記事では、法人が知っておくべき消費税の基本的な仕組みから、課税対象となる取引、具体的な対応方法まで、幅広く解説していきます。
目次
法人における消費税の基本的な仕組み
消費税は間接税として位置づけられており、商品やサービスの提供に対して課税される税金です。法人は消費者から消費税を預かり、国に納付する役割を担っています。 消費税率は標準税率10%(うち地方消費税2.2%)と軽減税率8%(うち地方消費税1.76%)に区分されており、取り扱う商品やサービスによって適用される税率が異なります。
消費税の計算は、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いた差額を納付する仕組みとなっています。この仕組みにより、法人は売上で受け取った消費税から仕入で支払った消費税を差し引いた金額を国に納付します。これにより、最終消費者が負担した消費税相当額のみが国庫に入ることになります。
課税事業者と免税事業者の区分
法人の消費税納税義務は、基準期間における課税売上高と資本金の額によって決定されます。基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。課税売上高が1,000万円を超える法人は課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
また、資本金1,000万円を超える法人は設立初年度から課税事業者となります。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ資本金が1,000万円以下の法人は免税事業者となり、原則として消費税の納税義務はありません。
特定期間判定による課税事業者判定
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間判定により課税事業者となる場合があります。特定期間は、法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月の期間を指します。 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間判定により課税事業者となる場合があります。特定期間は、法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月の期間を指します。この特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、または給与等支払額が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。
特定期間判定は、急激に売上が伸びた法人に対する課税漏れを防ぐための制度として設けられています。法人設立から2年目以降は、この特定期間判定も含めて課税事業者判定を行う必要があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



法人が消費税課税対象となる取引
法人の消費税課税対象となる取引は、国内における資産の譲渡等と輸入取引に大別されます。資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供を指します。法人の売上の大部分は課税対象取引に該当します。
課税対象となる取引の判定は、取引の性質や内容によって決まります。商品の販売、サービスの提供、不動産の賃貸、機械の売却など、事業として行われる取引は原則として課税対象となります。ただし、一定の取引については非課税取引や免税取引として特別な取り扱いが設けられています。
課税取引の具体例
法人の課税取引には、商品の販売、製品の製造販売、サービスの提供、不動産の賃貸(住宅用を除く)、機械設備の売却、特許権等の無形資産の譲渡などが含まれます。また、事業譲渡では、建物、機械、棚卸資産、のれんなどの課税資産の譲渡が課税対象となります。
事業譲渡では、のれん代は課税資産として扱われます。 一方、土地の譲渡、有価証券の譲渡、債権の譲渡などは非課税取引として扱われ、消費税は課税されません 。
非課税取引と免税取引
非課税取引は、政策的配慮や課税技術上の問題から消費税を課税しない取引として法律で定められています。主な非課税取引には、土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子、保険料、医療費、学校の授業料などがあります。
免税取引は、輸出取引など国際競争力の観点から消費税率をゼロ%とする取引です。輸出取引については、輸出免税が適用され、仕入控除税額の計算では課税売上として扱われるため、仕入に係る消費税額の控除が可能です。これにより、輸出企業は消費税の税額還付を受けることができます。
消費税申告と納付の実務対応
課税事業者となった法人は、消費税申告書を作成し、納付期限までに消費税を納付する必要があります。法人の消費税申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされています。申告方法には一般課税と簡易課税制度があり、事業の規模や性質に応じて選択することができます。
消費税の計算は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した金額を納付税額とします。この計算において、仕入控除税額の計算が重要なポイントとなり、適格請求書(インボイス)の保存が控除の要件となっています。
一般課税による計算方法
一般課税では、実際の課税仕入に係る消費税額を仕入控除税額として計算します。課税売上に係る消費税額から仕入控除税額を差し引いた金額が納付税額となります。仕入控除税額の計算には、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書の保存が必要です。
適格請求書発行事業者登録番号(T番号)制度により、取引先が適格請求書発行事業者でない場合は、段階的に仕入控除税額が制限されることになります。2023年10月1日から2026年9月30日までは控除割合80%、2026年10月1日以降は控除割合50%となり、最終的には仕入控除税額の控除ができなくなります。
簡易課税制度の選択
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の法人は、簡易課税制度を選択することができます。簡易課税制度では、課税売上高に業種別のみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算するため、実際の課税仕入に係る消費税額の計算や適格請求書の保存は不要です 。
業種別のみなし仕入率は、第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業等)80%、第三種事業(製造業等)70%、第四種事業(その他の事業)60%、第五種事業(サービス業等)50%、第六種事業(不動産業)40%に設定されています。ただし、簡易課税制度を選択した場合は仕入控除税額の還付を受けることができないため、設備投資が多い事業年度などでは不利になる場合があります。
インボイス制度への対応方法
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、法人の消費税実務に大きな変化をもたらしました。インボイス制度では、仕入控除税額の控除を受けるために、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書の保存が必要となります。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署への登録申請が必要です。登録を受けると、適格請求書発行事業者登録番号(T番号)が付与され、この番号を記載した適格請求書を交付する義務が生じます。法人が課税事業者である場合は、取引先からの要請に応じて適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。
適格請求書の要件と記載事項
適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した消費税額等および適用税率、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が必要です。これらの記載事項が不備な場合は、仕入控除税額の控除を受けることができません。
適格請求書の保存は、仕入控除税額の控除を受けるための法定要件であり、税務調査時にも重要な証拠書類となります。 電子データによる保存も認められていますが、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
免税事業者との取引における対応
取引先が適格請求書発行事業者でない免税事業者の場合、経過措置期間中は一定割合の仕入控除税額を控除することができます。2023年10月1日から2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%の控除が可能です。
この経過措置により、免税事業者との取引を継続しながら段階的にインボイス制度に対応することができます。ただし、長期的には免税事業者との取引条件の見直しや、適格請求書発行事業者である新たな取引先の開拓なども検討する必要があります。
事業譲渡における消費税の取り扱い
事業譲渡は、法人が事業の全部または一部を他の法人に譲渡するM&Aスキームの一つです。事業譲渡では、譲渡する資産に応じて消費税が課税される場合があります。課税資産の譲渡については消費税が課税され、非課税資産の譲渡については消費税は課税されません。
事業譲渡における消費税の計算は、課税資産の価額に消費税率10%を乗じて算出されます。課税資産には、建物、機械設備、車両、器具備品、棚卸資産、のれん、特許権、商標権などが含まれます。一方、土地、有価証券、債権などは非課税資産として扱われ、消費税は課税されません。
課税資産と非課税資産の分類
事業譲渡における資産の分類は、消費税額の計算に直接影響するため、正確な判定が必要です。課税資産には有形固定資産(土地を除く)、無形固定資産、棚卸資産、のれんが含まれます。特に、のれんは課税資産として扱われるため、事業価値が高い場合は消費税額が大きくなる可能性があります。
事業譲渡価格が10億円で、そのうち課税資産が8億円、非課税資産が2億円の場合、消費税額は8億円×10%=8,000万円となります。この消費税額は売り手が買い手から受け取り、消費税申告時に納付することになります。
| 資産の種類 | 課税区分 | 具体例 |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 課税(土地除く) | 建物、機械、車両、器具備品 |
| 無形固定資産 | 課税 | 特許権、商標権、ソフトウェア |
| 棚卸資産 | 課税 | 商品、製品、原材料、仕掛品 |
| のれん | 課税 | 顧客基盤、ブランド価値、ノウハウ |
| 有価証券 | 非課税 | 株式、社債、国債 |
| 債権 | 非課税 | 売掛金、貸付金、預託金 |
会社分割との消費税の違い
事業譲渡と異なり、会社分割(新設分割・吸収分割)では消費税は課税されません。会社分割は組織再編行為として扱われ、資産の譲渡に該当しないためです。この違いにより、M&Aスキームの選択によって消費税負担が大きく異なることになります。
特に、のれん代が大きい場合や課税資産の割合が高い場合は、事業譲渡よりも会社分割の方が消費税負担を軽減できる可能性があります。ただし、会社分割には他の税制上の要件や手続きが必要となるため、総合的な検討が必要です。
消費税還付の仕組みと注意点
法人が課税仕入に係る消費税額が課税売上に係る消費税額を上回る場合、消費税の還付を受けることができます。これは主に、設備投資を大幅に行った場合や、輸出売上の割合が高い場合に発生します。消費税還付は、法人の資金繰りにプラスの影響を与える重要な制度です。
ただし、簡易課税制度を選択している法人は、実際の課税仕入に係る消費税額に関係なく、みなし仕入率による計算を行うため、消費税の還付を受けることができません。このため、大きな設備投資を予定している法人は、簡易課税制度の選択について慎重に検討する必要があります。
輸出取引における消費税還付
輸出取引は免税取引として扱われ、消費税率0%が適用されます。輸出企業は、国内での仕入に係る消費税額を支払っているにも関わらず、輸出売上からは消費税を受け取らないため、この差額について消費税の還付を受けることができます。
輸出取引の免税適用を受けるためには、輸出許可書等の証明書類の保存が必要であり、適切な書類管理が還付を受けるための重要な要件となります。また、輸出取引に該当するかどうかの判定も重要であり、国外への資産の移転や国外での役務の提供などが対象となります。
設備投資による消費税還付
法人が機械設備、建物、車両などの固定資産を大量に取得した場合、課税仕入に係る消費税額が課税売上に係る消費税額を上回ることがあります。この場合、超過した消費税額について還付を受けることができます。
設備投資による消費税還付を適切に受けるためには、適格請求書の保存や固定資産台帳の整備など、証拠書類の管理が重要です。また、還付申告書の作成においては、課税仕入の分類や仕入控除税額の計算に誤りがないよう注意が必要です。
法人設立時の消費税対応
法人設立時の消費税対応は、その後の事業展開に大きな影響を与えるため、適切な判断が必要です。資本金1,000万円を超える法人は設立初年度から課税事業者となりますが、資本金1,000万円以下の法人は原則として2年間は免税事業者となります。
ただし、設立初年度から課税事業者を選択することも可能であり、設備投資が多い場合や輸出取引が中心の場合は、課税事業者を選択することで消費税の還付を受けることができます。課税事業者選択届出書は、原則「課税期間開始の日の前日」までに提出する必要があります 。
基準期間がない法人の特例
設立初年度および設立2年目の法人は基準期間がないため、原則として免税事業者となります。しかし、設立初年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上の場合は、設立初年度から課税事業者となります。
法人設立時の資本金設定は、消費税の納税義務判定に直接影響するため、事業計画と合わせて慎重に検討する必要があります。特に、設備投資計画がある場合は、課税事業者となることで消費税還付を受けられる可能性があることも考慮すべきです。
特定新規設立法人の判定
設立2年目の法人において、その基準期間がない場合でも、特定新規設立法人に該当する場合は課税事業者となります。特定新規設立法人とは、その事業年度の開始の日において、他の者によりその法人の株式等の50%超を直接または間接に保有され、かつ、その他の者の基準期間の課税売上高が5億円を超える法人をいいます。
この規定により、大企業のグループ会社として設立された法人は、設立当初から課税事業者として扱われることになります。グループ会社設立時は、この特定新規設立法人の判定についても確認が必要です。
まとめ
法人にとって消費税は、事業運営における重要な税務上の義務です。課税事業者となる法人は、売上高要件や資本金要件に基づいて判定され、消費税申告と納付の義務を負います。
インボイス制度の導入により、適格請求書の保存と発行が仕入控除税額の控除要件となり、法人の実務対応はより複雑化しています。取引先との関係や事業の性質を考慮して、適格請求書発行事業者への登録を適切に判断することが重要です。
事業譲渡などのM&A取引では、課税資産に対して消費税が課税されるため、取引スキームの選択が税負担に大きな影響を与えます。法人経営者は、消費税の基本的な仕組みを理解し、専門家と連携して適切な税務対応を行うことで、事業の発展と税務リスクの軽減を両立させることができるでしょう。
M&Aにおける消費税の取り扱いや適切な事業承継スキームの選択については、税務・法務・財務の専門知識が必要です。M&Aロイヤルアドバイザリーでは、豊富な実績と専門知識を活かして、お客様の事業価値向上と最適な取引実現をサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。