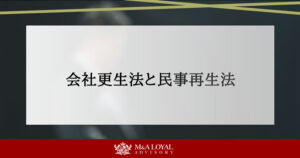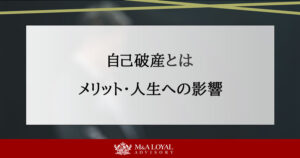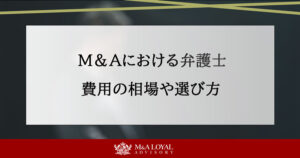民事再生手続きとは?利用の条件やメリット、流れを分かりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
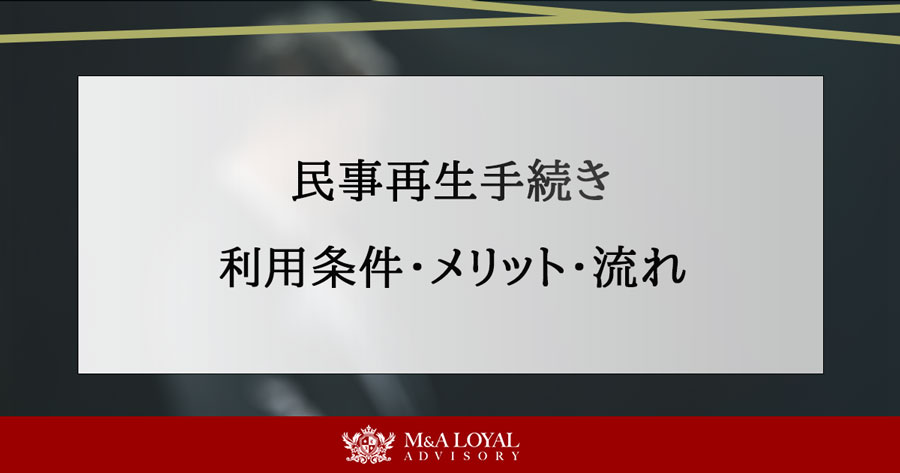
企業が債務超過に陥った際、事業を継続しながら経営再建を図る方法として民事再生手続きがあります。この手続きは破産手続きとは異なり、会社を存続させながら債務を圧縮し、分割返済によって経営の立て直しを目指す法的制度です。 本記事では、経営危機の際の選択肢として重要な位置を占める民事再生手続きとは何か、その仕組みや条件、メリット・デメリット、具体的な流れまで詳しく解説します。適切な専門家のサポートを得ながら進めることで、企業の存続と再生への道筋を見つけることができるでしょう。
目次
民事再生手続きとは何か
民事再生手続きとは、債務超過に陥った企業や個人が裁判所の認可を得て再生計画を実行し、債務を圧縮・分割返済しながら事業継続を目指す法的制度です。 民事再生法に基づく倒産法の再建型手続きとして位置づけられ、企業の経営再建による存続と債権者への一定の回収機会の確保を目的としています。
この制度の最大の特徴は、経営者が主導権を保ちながら事業を継続できる点です。破産手続きのような会社清算ではなく、債務圧縮と分割弁済で経営再建を図ります。
民事再生法の基本的な仕組み
民事再生法は、経済的に困窮した債務者の事業や経済生活の再生を目的として制定され、債務者自身が手続きを主導できる点が最大の特徴です。裁判所の監督の下で債権者との間で再生計画案を作成し、債権者の同意を得た上で計画を実行していきます。
手続きの開始によって、債権者による個別の取り立てや強制執行が停止され、債務者は事業継続に必要な資金を確保しながら再建に向けた準備を進めることができます。監督委員が選任されることで、手続きの適正性と透明性が確保されます。
他の倒産手続きとの基本的な違い
民事再生手続きと他の債務整理方法との違いを理解することは、適切な選択をする上で重要です。破産手続きは事業を清算して会社を消滅させるのに対し、民事再生は事業を継続しながら再建を図ります。
| 手続き名 | 目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 民事再生 | 事業を再建して存続 | 経営者主導、債務圧縮・分割返済 |
| 破産手続き | 事業を清算して消滅 | 資産換価・全財産喪失、債務全額免除 |
| 会社更生手続き | 大企業の再建 | 管財人主導、担保権制限 |
| 任意整理 | 借金整理 | 裁判所不介入、債権者との交渉 |
会社更生手続きとの違いは、民事再生では経営者が経営権を維持できる点にあります。任意整理は裁判所の関与なく債権者と直接交渉する方法ですが、法的拘束力に限界があります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



民事再生手続きの利用要件
民事再生手続きを利用するためには、法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。申立ての段階で裁判所がこれらの要件を審査し、手続き開始の可否を判断します。
基本的な申立て要件として、債務者が破産手続き開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことが挙げられます。
法人の申立て要件
法人が民事再生手続きの申立てを行う場合、破産手続き開始原因である支払不能または債務超過の状態にあること、またはそのおそれがあることが必要です。支払不能とは、債務者が資金不足により、支払期限が到来している借金を継続的に返済できない状態を指します。
債務超過については、資産の合計額が負債の合計額を下回っている状態を意味します。ただし、継続的な経営困難が前提で、一時的な資金繰りの悪化は対象外です。申立て手続きでは、これらの状況を具体的な財務資料で疎明(法的事実を証明すること)する必要があります。
個人事業主の申立て要件
個人事業主の場合も法人と同様に、支払不能またはそのおそれがある状態が民事再生手続きの要件となりますが、個人再生手続きとの選択も可能です。事業規模や債務額、収入見込みを考慮し、適切な手続きを選ぶことが重要です。
民事再生では、事業の継続を前提とした再生計画の策定が必要で、事業の採算性や継続可能性が重要な判断材料となります。一方、個人再生手続きは生活再建を目的とし、債務額が5,000万円以下という制限があります。
どの手続きを選ぶべきかは、事業の状況や収入の安定性をふまえ、専門家の助言を受けて判断することが推奨されます。
再建可能性の要件
民事再生手続きでは、単に債務超過や支払不能の状態にあるだけでなく、将来的な事業再建の可能性があることが重要な要件となります。裁判所は申立て時に提出される事業計画書や再建見込みを詳細に審査します。
再建可能性の判断では、営業利益を確保できる事業体制の構築、公平で履行可能な再生計画案の策定、必要に応じたスポンサー企業の確保などが重要な要素となります。これらの要素が不十分な場合、手続きの開始が認められないか、開始後に破産手続きへ移行する可能性があります。
民事再生手続きのメリット
民事再生手続きには、他の債務整理方法と比較して独特のメリットがあります。特に事業を継続しながら経営再建を図りたい企業にとって、これらのメリットは大きな魅力となります。
最大のメリットは、会社を清算することなく事業を継続できる点です。従業員の雇用を維持し、取引先との関係を保ちながら、段階的な経営改善を進めることができます。
経営権の維持と事業継続
民事再生手続きでは、経営者が経営権を維持しながら事業を継続できるため、経営ノウハウや取引先との関係を活かした再建が可能です。会社更生手続きとは異なり、管財人による経営権の剥奪がないため、迅速な意思決定と改革が行えます。
事業継続により、従業員の雇用を原則として維持できる点も大きなメリットです。ただし、スポンサー企業の意向や事業部門の清算が必要な場合には、一部リストラが発生する可能性があります。
債務の圧縮と分割弁済
民事再生手続きでは、債権者集会での決議を経て債務の大幅な圧縮が可能となります。 一般的には債務額の20%から30%程度まで圧縮され、残りの債務は3年から5年程度の分割弁済となります。
この債務圧縮により、月々の返済負担が大幅に軽減され、営業活動から生み出される利益を事業の再建と成長に振り向けることができます。弁済禁止決定により、手続き中は既存債務の弁済を停止できるため、手元資金の確保も可能となります。
資産と取引関係の保全
民事再生手続きの開始により、債権者による個別の強制執行や仮差押えが中止され、事業に必要な資産が保全されます。これにより、銀行預金の差押えを回避し、運転資金を確保しながら事業を継続することが可能です。
また、民事再生手続きは破産手続きと比べて信用失墜の程度が小さく、重要な取引先との関係を維持しやすい点が特徴です。ただし、一時的な信用不安は避けられないため、再建計画の具体的な内容や事業継続の見込みを丁寧に説明し、取引先の理解を得ることが重要です。
民事再生手続きのデメリットと注意点
民事再生手続きには多くのメリットがある一方で、重要なデメリットと注意点も存在します。これらを十分に理解した上で、手続きの利用を検討することが必要です。
最も深刻なデメリットは、社会的信用の失墜とブランド力の低下です。民事再生手続きの申立てが公になることで、取引先や金融機関からの信用が大きく損なわれる可能性があります。
社会的信用とブランド価値の低下
民事再生手続きの申立てにより、企業の社会的信用は大幅に低下し、これまで築き上げてきたブランド価値にも深刻な影響を与える可能性があります。新規取引先の開拓が困難になり、既存取引先との取引条件も厳しくなることが予想されます。
金融機関からの新規融資は極めて困難となり、信用保証協会の保証も受けられなくなります。取引先からは現金決済を求められることが多く、運転資金の調達に苦労する場面も出てきます。この信用回復には長期間を要するため、事業計画においても慎重な検討が必要です。
担保資産の処分と債務免除益課税
民事再生手続きでは、担保権者の権利は「別除権」として扱われるため、担保に供している不動産や設備などが処分される可能性があります。事業継続に不可欠な資産については、担保権者との交渉により処分を回避できる場合もありますが、相応の対価が必要となることが一般的です。
また、債務が圧縮(減額)されることで生じる「債務免除益」は法人税の課税対象となります。ただし、債務超過など一定の条件を満たせば課税の繰延べが認められる場合があります。そのため、税務専門家との連携を通じて課税負担を正確に把握し、総合的な収支計画を慎重に策定することが重要です。
手続き失敗時の破産リスク
民事再生手続きが失敗した場合、破産手続きへ移行することになります。再生計画案が債権者集会で否決された場合や、認可決定までの期間中に事業が維持できなくなった場合などが想定されます。
破産手続きへの移行により、会社は清算され、経営者は全ての経営権を失うことになるため、民事再生手続きの申立て前に十分な準備と検討が必要です。 特に再生計画の実現可能性と債権者の同意獲得の見込みについて、専門家と詳細に検討することが重要です。
民事再生手続きの具体的な流れ
民事再生手続きは複数の段階を経て進行し、各段階で重要な手続きと判断が求められます。申立て手続きから再生計画の実行まで、通常6ヶ月から1年程度の期間を要します。
手続きの全体像を理解することで、各段階での準備と対応を適切に行うことができます。特に債権者との関係構築と再生計画案の策定は、手続きの成功を左右する重要な要素となります。
申立てから手続き開始まで
民事再生手続きは、債務者の申立てから始まり、裁判所での審査を経て手続き開始決定が下されます。申立てには、財産目録、債権者一覧表、事業計画書などの資料が必要です。
裁判所が要件を満たしていると判断した場合、保全処分を発令し、債権者による強制執行や財産処分を禁止します。これにより、事業継続に必要な資産が保全され、再建計画の準備が可能となります。
手続き開始決定とともに監督委員が選任され、業務や財産管理を監督し、手続きの透明性を確保します。
債権調査と財産評定
手続き開始後、債権者に対して債権届出の機会が与えられます。債権届出・認否書提出期限は裁判所が定めた期間内に行われ、すべての債権について確定作業が進められます。
同時に債務者は財産評定報告を作成し、会社の資産状況を詳細に報告します。この財産評定により、再生計画案の基礎となる配当率や弁済方法が検討されることになります。
債権者との間で債権額に争いがある場合には、債権査定の申立てにより裁判所が判断を行います。この段階で債権額が確定し、再生計画案の具体的な内容検討に移ります。
再生計画案の策定と決議
債権調査が完了した後、債務者は再生計画案を作成し、債権者集会での決議に付します。再生計画案には、債権の分類、弁済方法、弁済期間、事業再建の具体的方法などが詳細に記載されます。
債権者集会での可決には、議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意が必要となるため、事前の債権者との調整と理解の獲得が重要です。特に大口債権者の同意は手続きの成否を左右するため、十分な説明と交渉が必要となります。
再生計画案が可決された場合、裁判所による認可決定を経て確定します。認可決定により、再生計画に記載された内容が法的拘束力を持つことになり、計画の実行段階に入ります。
民事再生を成功させるための重要なポイント
民事再生手続きを成功に導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらのポイントを押さえることで、手続きの成功確率を大幅に向上させることができます。
最も重要なのは、営業利益を安定的に確保できる事業体制の構築です。債務圧縮後の弁済を確実に履行するためには、継続的な利益創出が不可欠となります。
営業利益の確保と事業体制の構築
民事再生の成功には、債務圧縮後の分割弁済を履行できる営業利益の確保が最も重要であり、そのための事業体制の抜本的な見直しが必要です。不採算部門の整理、コスト構造の改善、営業体制の強化など、総合的な経営改革が求められます。
市場環境の変化に対応した事業戦略の再構築も重要です。従来の事業モデルに固執せず、収益性の高い分野への事業転換や新たな収益源の開拓を検討する必要があります。
人員体制についても、適正規模への調整と同時に、中核人材の確保と育成に注力することが重要です。再建過程で優秀な人材が流出することを防ぎ、組織力の維持と向上を図る必要があります。
現実的で履行可能な再生計画の策定
再生計画案は現実的で履行可能な内容でなければ、債権者の同意を得ることはできません。 過度に楽観的な売上予測や非現実的なコスト削減計画は、かえって信頼を失うことになります。
弁済計画についても、確実に履行できる範囲での設定が重要です。通常3年から5年の分割弁済期間を設定しますが、事業の特性や市場環境を考慮した適切な期間設定が必要です。 民事再生計画遂行の成功は、この現実性にかかっています。
スポンサー企業の確保と専門家の活用
自力での再建が困難な場合には、スポンサー企業の確保が重要となります。同業他社、取引先企業、投資ファンドなど、様々な候補先との交渉を並行して進める必要があります。
専門家への相談ポイントとして、民事再生に精通した弁護士、公認会計士、税理士などの専門家チームを早期に組成し、総合的なサポートを受けることが成功の鍵となります。各専門家の連携により、法的手続き、財務分析、税務対策などを包括的に進めることができます。
民事再生手続きの費用相場
民事再生手続きには相当額の費用が必要となるため、事前の資金準備と調達計画が重要です。主な費用として裁判所への予納金と専門家への報酬があり、これらを合わせると数百万円から数千万円の費用が必要となります。
費用の規模は債務額や事業規模によって大きく異なるため、申立て前に詳細な見積もりを取得し、資金調達の目処を立てることが必要です。
裁判所予納金の相場
東京地方裁判所の予納金相場は、負債総額5,000万円未満で200万円、1億円未満で300万円、50億円未満で600万円、1,000億円以上で1,300万円とされています。この予納金は監督委員の報酬や手続き費用に充てられ、申立て時に一括で納付する必要があります。
予納金額は地方裁判所ごとに異なる場合があるため、事前に基準を確認することが重要です。また、事案の複雑さや手続きの長期化により追加の予納金が必要になる場合もあります。余剰が発生した場合には一部返還されることもあるため、資金計画を慎重に立てることが求められます。
専門家報酬と関連費用
弁護士費用は、予納金と同程度またはそれ以上の金額が必要となることが一般的です。事案の複雑さや債権者数、手続き期間に応じて報酬額が決定されるため、契約前に着手金や成功報酬を含めた詳細な見積もりを取得することが重要です。
また、公認会計士や税理士などの専門家報酬も必要となり、総費用は予納金の2倍から3倍程度になることが多いです。これらの費用は、財務分析や税務対策の正確性を確保し、再建計画の信頼性を高めるための投資として位置づけられます。適切な専門家の選定と費用対効果の検討を行うことが、手続きの成功に繋がります。
手続き費用の調達方法
民事再生手続きの費用調達は、通常の融資が困難な状況で行う必要があるため、創意工夫が求められます。経営者の個人資産の活用、親族や知人からの借入れ、取引先からの前払い等による資金調達が考えられます。
スポンサー企業が決まっている場合には、手続き費用の支援を受けることも可能です。ただし、費用支援の条件や将来の関係について事前に明確な合意を形成しておくことが重要です。
まとめ
民事再生手続きは、債務超過に陥った企業が事業を継続しながら経営再建を図る有効な法的制度です。経営者が主導権を維持し、債務を圧縮・分割弁済することで会社の存続を可能とする一方、社会的信用の低下や手続き失敗時の破産リスクなど重要なデメリットも存在します。
手続きの成功には、営業利益を確保できる事業体制の構築、現実的で履行可能な再生計画の策定、債権者の理解と協力の獲得が不可欠です。相当額の費用が必要となるため、事前の資金調達計画も重要な準備事項となります。
中小企業が民事再生手続きを検討する際には、業種特性や事業規模に応じた戦略立案と、民事再生に精通した専門家との連携が成功の鍵となるでしょう。経営危機の早期段階から適切な対応を取ることで、企業存続への道筋を見出すことが可能となります。
経営危機に直面した際の選択肢として民事再生手続きをご検討の場合は、M&A等の事業再生手法も含めた総合的な解決策について専門家にご相談されることをお勧めします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。