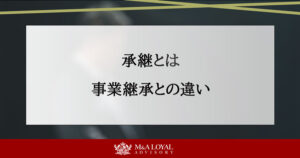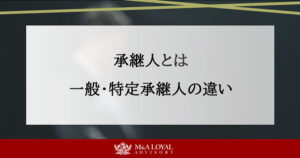事業承継信託とは?スキームやメリット・デメリット、税金を徹底解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
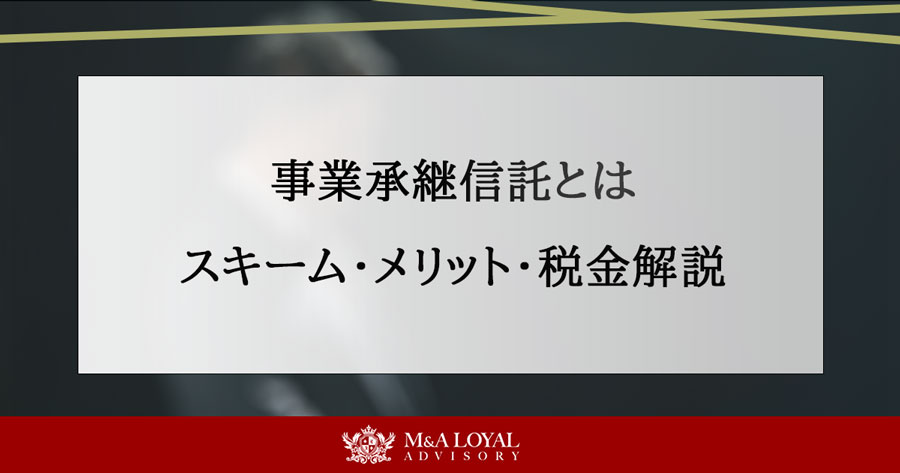
事業承継信託は、経営者が自社株式などの重要な財産を、信託という形で後継者に円滑に引き継ぐための制度です。
信託銀行などの金融機関を活用し、相続に伴う混乱や後継者不在による経営空白のリスクを抑える手段として、「確実に引き継ぐ」仕組みである事業承継信託の活用が注目されています。
この記事では、事業承継信託の基本的な仕組みや民事信託・商事信託との違い、種類別の特徴、メリット・デメリット、契約方法、税制上のポイントまで網羅的に解説します。
目次
事業承継信託とは
まず、事業承継信託に関する基本的な知識について解説します。
事業の承継を後継者へ円滑に行うための資産運用
事業承継信託とは、自社株を信託することで、企業の経営権を後継者へスムーズに引き継ぐ仕組みです。経営者が生前に株式を信託しておくことで、経営の空白期間や親族間の争いを防ぐことができます。
信託では、株式の所有者である「委託者」が、信頼できる「受託者」に株式を託し、「受益者」がその利益を受け取ります。信託契約によって、株式の議決権を誰が行使するかや、後継者への経営権移転の条件を柔軟に設定することが可能です。これにより、経営権を円滑に移転することができます。
相続や贈与に比べて自由度が高く、トラブルを避けやすいため、特に中小企業の事業承継において注目されています。事業承継信託は「民事信託」の一種として活用されることが多く、個別の事情に応じた柔軟な対応が可能です。
商事信託とは
商事信託とは、信託銀行や信託会社などの金融機関が受託者となり、委託者から信託された財産を管理・運用する営利目的の信託です。事業承継における商事信託では、経営者が保有する自社株を信託し、あらかじめ定めた条件で後継者に承継させる「自社株承継信託」として利用されます。
受託者となる金融機関は、信託財産に対する管理責任を負い、その見返りとして信託報酬を受け取ります。商事信託は専門的な知識と実務対応力があるため、契約の内容や管理体制が厳格に整備されており、信頼性が高い点が特徴です。
財産の管理をプロに任せたい経営者には、商事信託が適しています。
民事信託とは
民事信託とは、家族や親族など身近な人物を受託者として選び、資産を管理・承継する仕組みです。特に、家族間での信託契約を通じて資産を管理・承継する「家族信託」は、民事信託の一形態として注目されています。
商事信託とは異なり、民事信託では信託報酬が発生しない場合が多く、費用を抑えつつ契約内容を柔軟に設定できる点が特徴です。ただし、契約の作成や運用に際して弁護士や司法書士など専門家の助言を受けることが一般的であり、その際には一定の費用がかかる場合があります。
民事信託は、中小企業の事業承継や資産管理の手段として活用されており、2006年の信託法改正により制度が整備されて以降、その利用は増加傾向にあります。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事業承継信託の代表的な種類
事業承継信託には、承継の目的や受益者の構成に応じて複数のタイプが存在します。代表的なものは次のとおりです。
- 遺言代用信託
- 他益信託
- 後継ぎ遺贈型受益者連続信託
それぞれを分かりやすく解説します。
遺言代用信託
遺言代用信託とは、経営者が生前に信託銀行や信託会社と契約を結び、自社株を信託する仕組みです。「遺言代用型信託」とも呼ばれることがあります。生前は経営者自身が受益者となり、株式の配当を受け取りますが、死亡後には契約で指定した後継者が受益者となり、受益権を取得します。
受益権には、配当金の受領権が含まれ、議決権の指図権についても、信託契約で定めることで実質的な事業の支配を可能にします。議決権を受託者に委ねるか、後継者に指図権を与えるかは、契約内容に応じて柔軟に設定できます。
遺言書と異なり、遺言代用信託は契約時点で効力を発生させるため、経営者が生前に承継計画を確認できる点が特徴です。また、検認手続きが不要であるため、相続手続きがスムーズに進められます。さらに、議決権の分散を防ぎつつ、承継先を明確に定められるため、相続時のトラブルを未然に防ぐ有効な手段とされています。
他益信託
他益信託とは、委託者である経営者が後継者を受益者とする信託契約です。この信託によって、後継者は配当金などの経済的利益を受け取る権利を得ます。一方、議決権や経営権については、信託契約で柔軟に設定することが可能であり、経営者が指図権を保持して実権を維持する形や、受託者や受益者が議決権を行使する形など、契約内容によって幅広い設定が可能です。
信託期間は、経営者の死亡や一定期間経過後など、任意に設定できます。他益信託を活用することで、後継者の正当な立場を明確にしながら、経営者が実権を手放さずに事業承継を計画的に進めることが可能です。
経営権を保持しつつ後継者の地位を確保できる点で、他益信託は柔軟な事業承継手段として注目されており、実務でも幅広く活用されています。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、経営者の死亡後に指定された後継者が受益者となり、その後さらに次の後継者へと受益権を承継できる信託です。
後継者が高齢または体調不良の場合など、万一に備えて次順位の受益者を指定できる点が特徴です。
ただし、信託法第91条により、信託の期間が30年を超える場合には、受益権の承継は一度しか認められません。従って、三世代以上にわたる承継を予定する場合は、信託期間を30年以内に設定するなどの工夫が求められます。
事業承継信託のメリット
事業承継信託のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 経営者が理想とする事業承継ができる
- 後継者争いやトラブルを回避できる
- 経営者不在の心配がなくなる
- 課税のタイミングをコントロールできる
それぞれについて解説します。
経営者が理想とする事業承継ができる
事業承継信託の大きなメリットは、経営者が理想とする形で事業承継を設計できる点です。信託では、委託者である経営者が後継者や承継条件をあらかじめ指定でき、事業の方向性や価値観を反映させた承継が可能です。
また、議決権に関する指図権と配当などの財産権を分離できるため、経営権を保持しつつ後継者に経済的利益を与えるなど、柔軟な設計が可能です。
相続による承継では、相続人間の協議が必要となるため、経営者の意思と異なる形で株式が分散する恐れもあります。事業承継信託を用いることで、経営者が指名した後継者に確実に株式を移し、承継時期や条件も制御できます。
事業承継信託は後継者争いやトラブルを回避できる
事業承継信託は、あらかじめ後継者を明確に定めることができるため、親族間や株主間での争いを未然に防ぐ有効な手段です。一般的な相続では、複数の相続人に自社株が分散し、経営権が不安定になる可能性がありますが、信託契約を利用することでこのリスクを回避できます。
事業承継信託では、経営者が信託契約により特定の人物を後継者として指名し、その人物に株式や議決権を集中させることが可能です。例えば、「長男のみに株式の受益権を与える」と信託契約で明確に定めておけば、他の相続人が異議を唱えた場合でも、信託契約が法的に有効である限り、裁判所で承継内容の正当性が認められる可能性が高く、トラブルを防ぎやすくなります。ただし、遺留分侵害額請求が発生する可能性があるため、これを回避するための配慮が求められます。
さらに、信託を利用した承継では、金融機関や専門家といった第三者が関与するため、透明性が高まり、社内外からの信頼を確保することにもつながります。
事業承継信託は経営者不在の心配がなくなる
事業承継信託は、万が一経営者が急逝した場合でも、すぐに後継者へ経営権を移行できる体制を整えられる点が大きな利点です。
一般的な相続では、遺産分割協議や相続手続きに数カ月以上かかることもあり、その間に経営の空白期間が生じるリスクがあります。経営者が不在となれば、重要な意思決定が滞るほか、取引先や従業員に不安を与える可能性も高まります。
事業承継信託を設定しておけば、経営者の死亡や意思判断能力の喪失と同時に、指定された後継者に受益権や議決権が引き継がれるため、混乱を最小限に抑えられます。不測の事態に備えた承継体制を構築することは、企業の存続と安定経営にとって極めて重要な要素です。
課税のタイミングを調整できる
事業承継信託は、贈与や遺言による承継に比べて、承継の時期と方法を調整できるため、税務上の計画性を高めることが可能です。信託を活用して財産移転のタイミングを設計することで、税負担の最適化を図る手段として注目されています。
例えば、自社株を後継者に贈与すると贈与税が発生し、売却による承継では譲渡所得税や買取資金の確保が課題となります。また、遺言では経営権の移転が死亡後に限定され、相続税が発生する可能性があります。
一方、信託を活用した自益信託では、設定時点での贈与税を回避し、経営者の死亡後に受益権が移転することで相続税の対象とする設計が可能です。さらに、遺言代用信託を利用すれば、生前に経営を維持しつつ、死後に円滑に権利が承継される仕組みを構築できます。
ただし、他益信託などの設計によっては贈与税が課税される場合があるため、制度の利用にあたっては税務上のリスクとルールを正確に理解し、専門家の助言を受けることが不可欠です。
事業承継信託のデメリット・リスク
事業承継信託は多くのメリットを持つ一方で、制度特有の課題や法的な不確実性も存在し、次のようなデメリット・リスクがあります。
- 経営者の死亡が前提となる
- 遺留分侵害額請求への対応が難しい
- 内容によってはトラブルになる場合がある
それぞれについて解説します。
事業承継信託経は営者の死亡が前提となる
事業承継信託は、現経営者の死亡をきっかけに承継が行われる仕組みが基本です。そのため、生前に一線を退き、後継者へ経営権を委ねたいと希望しても、事業承継信託は原則として利用できません。
存命中に引退して事業を譲りたい場合は、株式の贈与や売買といった別の手段を検討する必要があります。ただし、贈与や売買は課税や資金調達の負担が伴うことがあり、後継者にとってはハードルが高くなりがちです。
事業承継信託は遺留分侵害額請求への対応が難しい
事業承継信託を用いる場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点に注意が必要です。遺留分とは、民法上の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)が最低限保障される遺産の割合であり、これを侵害された相続人は金銭での補填を請求する権利があります。
ただし、信託財産が遺留分侵害額請求の対象となるかどうかについては、法的な解釈が分かれており、未確定な部分があります。一部の見解では、信託法を民法の特別法と解釈し、遺留分請求が認められないとする立場がある一方で、他の相続人の法定権利を保護する観点から信託財産も請求対象になるとする立場も存在します。
そのため、契約によって受益権を取得した後継者が、遺留分侵害額請求を受け、金銭的な補償を求められるケースもあり得ます。遺留分の請求を回避するためには、他の相続人にも最低限の遺産を残すなどの配慮が必要です。また、事業承継信託の設計段階で相続人全員の合意を得たり、専門家の助言を受けたりすることが推奨されます。
内容によってはトラブルになる場合がある
事業承継信託は長期にわたって効力を持つ契約であるため、設定内容によっては将来的なトラブルを招く可能性があります。
例えば、後継者として指定した人物が後に不適任であると判明した場合でも、信託契約に解任や変更の条項がなければ、経営の立て直しが困難になることがあります。また、契約時には想定していなかった外部環境や事業内容の変化により、信託の内容が実情と合致しなくなるリスクもあります。
信託契約を設計する際には、後継者の変更や解任、信託の終了条件などについても柔軟に対応できる仕組みを取り入れることが重要です。将来を見据えた慎重な制度設計が求められます。
事業承継信託の導入における注意点
事業承継信託を円滑に活用するには、制度の特徴だけでなく、次の点に注意する必要があります。
- 専門家に相談する
- 親族の理解を得る
- 税制上の優遇を受けられないケースがある
それぞれについて解説します。
専門家に相談する
事業承継信託は、信託契約の内容や受益者の設計次第で、さまざまな法的・税務的リスクを伴うことがあります。そのため、導入を検討する際には、信託に精通した弁護士・税理士・公認会計士などの専門家に事前に相談することが不可欠です。
専門家の助言を得ることで、トラブル回避や制度の適切な活用につながります。
親族の理解を得る
事業承継信託を導入する際の重要な注意点は、親族や関係者の理解を得ることです。信託制度自体がまだ広く浸透しておらず、「信託とは何か」「なぜ株式を信託するのか」といった基本的な疑問を持たれることも少なくありません。
特に親族間での相続意識が強い場合、信託による承継に対して誤解や反発が生じる可能性があります。経営者自身の説明だけでは不十分なこともあるため、信託会社や税理士などの専門家の協力を得て、制度の意義や仕組みを丁寧に伝えることが重要です。
信頼できる第三者からの説明により、客観性が担保され、周囲の納得を得やすくなります。トラブルを未然に防ぐためにも、早期かつ十分な説明機会を設けるべきです。
税制上の優遇を受けられないケースがある
事業承継信託では、自社株式を信託財産とする場合、税制上の優遇措置(事業承継税制)が適用されない点に注意が必要です。事業承継税制は、一定の要件を満たした場合に相続税や贈与税について納税の猶予や免除を受けられる制度ですが、この特例は信託財産には適用されません。
信託契約により自社株式が信託の管理下に置かれると、税務上は「相続」や「贈与」とはみなされず、事業承継税制の対象外となります。特に、後継者が受益者となる他者信託を設定した場合、株式の所有権が受託者に移るため、税制の特例を利用することができません。
そのため、後継者の税負担を軽減したい場合は、信託による承継ではなく、直接の贈与や相続を選択する方が適しているケースもあります。ただし、信託を活用する場合でも、贈与や相続と併用する形で事業承継信託を設計することで、税負担の軽減を図ることが可能です。具体的な状況に応じて、専門家の助言を受けながら承継計画を検討することが重要です。
事業承継信託を設定する方法
事業承継信託を活用するには、目的や状況に応じて適切な設定方法を選ぶことが重要です。主な方法として、次の三つが挙げられます。
- 信託契約を締結する
- 遺言書に信託を記載する
- 自己信託によって宣言する
それぞれについて解説します。
信託契約を締結する
事業承継信託の最も一般的な設定方法は、信託契約の締結です。この方法では、委託者である現経営者と、受託者となる信託銀行や信託会社との間で契約を交わし、契約締結と同時に信託の効力が発生します。受託者は信託財産を管理・運用する責任を負い、後継者である受益者は信託財産から生じる利益を受け取る権利を持ちます。
信託契約には、信託の目的、信託財産、受益者、終了条件に加え、管理方法や議決権の扱いなどを明記する必要があります。これにより、信託の運用が円滑に進むとともに、後継者の権利や経営権への関与の範囲が明確になります。
遺言書に信託を記載する
事業承継信託は、遺言書に内容を記載することで設定することも可能で、この場合、信託の効力は委託者(経営者)の死亡時に発生します。遺言書方式はシンプルな仕組みが特徴ですが、生前に内容を確認・修正することはできないため、作成時に慎重な検討が必要です。
一方、生前から信託を機能させたい場合は、信託契約方式が適しています。契約締結時点で効力が発生し、経営者が内容を確認・修正しながら承継計画を進めることが可能です。ただし、契約の変更には手続きや条件を満たす必要があります。
状況に応じて適切な方式を選ぶことが重要であり、専門家の助言を活用することが推奨されます。
自己信託によって宣言する
自己信託とは、委託者と受託者を同一人物とし、自ら信託の設定を宣言する方法です。
2007年の信託法改正によって可能となった制度で、経営者が自社株などの財産を信託財産として管理・運用する際に用いられます。自己信託では契約を締結する相手が存在しないため、「信託宣言」と呼ばれる単独の意思表示によって成立します。
自らが管理する信託となるため柔軟な運用が可能ですが、信託内容の適正性や管理責任は全て経営者自身が負います。法的・税務的な検討も必要であるため、自己信託を活用する場合には専門家の関与が不可欠です。
事業承継信託にかかる税金
事業承継信託にかかる税金について解説します。
原則として受益者が課税対象となる
事業承継信託では、「受益者課税の原則」に基づき、信託財産から経済的利益を受け取る受益者が課税対象とされます。これは、税務上、受益者が実質的に財産を所有しているとみなされるためです。
例えば、後継者が受益者として信託から配当金などを受け取る場合には、その金額に対して所得税が課されます。
信託の種類ごとにかかる税金
事業承継信託では、信託の設計や受益者の設定によって、贈与税・相続税・所得税などの課税関係が異なり、それぞれの税金が発生するタイミングや課税対象も変わります。
他益信託
委託者と受益者が異なる場合、信託設定時に受益権が確定していれば贈与税が課税される可能性があります。委託者の死亡後に受益者が確定する設計では相続税が課税対象となります。また、信託財産からの利益(配当など)は受益者の所得として所得税が課されます。
自益信託
委託者と受益者が同一人物の場合、信託設定時点で財産移転がないため、贈与税や相続税は原則課税されません。ただし、収益を受け取った場合は所得税が課されます。死亡後に受益権が他者へ移転する場合は相続税が発生します。
自己信託
委託者が受託者を兼ねる自己信託は、課税関係が自益信託とほぼ同様です。設定時点で贈与税や相続税は発生しませんが、信託財産からの利益には所得税が課されます。死亡後に受益者が変更される場合は相続税が課税されます。
いずれの場合も設計次第で課税関係が異なるため、専門家の助言を受けることが不可欠です。
事業承継信託を取り扱う金融機関
事業承継信託を取り扱う主な金融機関は次のとおりです。
- りそな銀行
- みずほ信託銀行
- SMBC信託銀行
それぞれの銀行が提供している事業承継信託の特徴について解説します。
りそな銀行
りそな銀行の事業承継信託は、「遺言代用型」と「議決権留保型」の2種類があり、経営権のコントロールと財産権の移転を柔軟に切り分けることが可能です。信託期間は原則10年以内で、契約変更や中途解約には制限があります。審査や手数料が必要ですが、円滑な事業承継を目指す中小企業オーナーに適したサービスです。
みずほ信託銀行
みずほ信託銀行では、経営者の事業承継ニーズに応じた多様な信託商品を展開しています。資産を「つかう」「まもる」「のこす」といった目的別に管理できる仕組みが特徴で、贈与の実行や受取人の指定、解約制限など、柔軟な設計が可能です。
「家族用受取機能」や「暦年贈与機能」などの実務的な機能も整備されており、相続対策や税務対策に役立つ総合的な信託サービスが提供されています。また、信託設定時点での権利の移転時期に応じて、「遺言代用タイプ」(委託者の死亡時に効力発生)と「生前贈与タイプ」(生前に効力発生)の2種類が用意されています。
SMBC信託銀行
SMBC信託銀行が提供する事業承継信託には、「遺言代用信託」と「受益者連続信託」の2種類があります。これらの信託は、自社株式を信託財産として設定し、事業承継を円滑に進めることを目的としています。
さらに、単独運用指定信託(DPM)や有価証券管理信託、美術品信託などの特約として付加する形で提供される場合もあり、柔軟な運用が可能です。これにより、事業承継信託を活用しながら、財産管理や承継計画を多様なニーズに応じて設計することができます。
その他
事業承継信託は、信託銀行だけでなく、地方銀行や証券会社、信用金庫などでも利用可能です。一部の金融機関では、提携する信託銀行を通じてサービスを提供することもあります。普段から取引のある金融機関であれば、会社の財務状況や経営者の意向を把握しているため、より実情に即した提案が期待できます。
また、こうした金融機関では、事業承継信託だけでなく、相続対策や経営支援などを総合的にサポートする体制が整っている場合も多くあります。信託の設計には一定の時間と手続きが必要なため、事業承継を意識し始めた段階で早めに相談することが重要です。
親族以外への事業承継方法
親族以外への事業承継には、次のケースがあります。
- 従業員への承継
- 第三者への承継(M&A)
それぞれについて解説します。
従業員への承継
従業員への承継は、社内の幹部や右腕人材に経営を引き継ぐ方法です。企業内部の実情を理解し、現場の信頼も厚いため、移行が比較的スムーズに進みます。なお、従業員が株式を買い取り、経営権を取得する「従業員による企業買収」は、「エンプロイーバイアウト(EBO)」と呼ばれます。
一方で、後継者となる従業員が株式を取得するための資金を用意できない、経営者としての責任や個人保証に対する不安を抱えるといった課題も多く、実際の実行には時間と準備が必要です。
第三者への承継(M&A)
親族や社内に後継者が見つからない場合は、第三者への承継、すなわちM&Aによる事業承継が選択肢に挙げられます。外部の企業や投資家に自社株式を譲渡し、経営を引き継いでもらうことで、現経営者はまとまった資金を得て引退後の生活に備えられます。
ただし、買い手企業との条件交渉や従業員の雇用継続、取引先との関係性の維持など、多方面への配慮と調整が必要なため、慎重かつ計画的に進める必要があります。
事業承継信託に関するQ&A
最後に、事業承継信託に関するよくある質問とその回答を紹介します。
事業承継信託には手数料などの費用がかかるか
事業承継信託を利用する際には、契約の締結や管理に関する費用が発生することが一般的です。具体的な金額や内訳は、各信託銀行や契約内容によって異なり、定額の手数料のほか、契約時・解約時・管理期間中に応じた報酬体系が設定されているケースもあります。
例えば、契約金額に応じて段階的に料率が設定される場合や、特定の追加サービスに対して別途費用が発生することもあるため注意が必要です。信託契約を検討する際は、必ず各金融機関に直接問い合わせ、詳細な費用の見積もりを取り寄せることが大切です。
事業承継信託は途中での解約は可能か
事業承継信託は、承継計画に基づいて中長期的に運用される契約であり、原則として途中解約はできません。ただし、契約当事者にやむを得ない事情が生じた場合に限り、契約内容や信託法の規定に基づき、金融機関や関係者の判断で中途解約が認められることがあります。
「やむを得ない事情」には、経営者本人の急病や後継者事情の大幅な変更などが該当する可能性がありますが、その具体的な範囲や判断基準は金融機関や契約内容によって異なります。解約の条件や可能性については、契約時点で金融機関に確認するとともに、信託に詳しい専門家の助言を受けることが重要です。
事業承継税制とは何か
事業承継税制とは、中小企業の円滑な事業承継を目的に設けられた税制優遇制度です。一定の条件を満たした非上場会社の後継者が株式を相続または贈与によって取得した際、その株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予されるしくみとなっています。
さらに、後継者が一定期間会社経営を継続するなどの要件を満たせば、最終的に納税が免除される点も特長です。
みなし相続財産とは何か
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、相続や遺贈と同様の経済的効果があると見なされ、相続税の課税対象とされる財産です。代表例として、死亡保険金、死亡退職金、死亡前3年以内に贈与された財産などが含まれます。これらは遺産分割の対象ではありませんが、税務上は相続財産として扱われます。ただし、死亡保険金や死亡退職金には一定の非課税枠が適用されることがあります。
事業承継信託では、被相続人(経営者)が委託者かつ受益者で、死亡後に後継者が受益者となる場合、信託財産がみなし相続財産とみなされることがあります。具体的な課税関係は信託契約や税法に依存するため、専門家の助言を受けることが重要です。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、父母)が最低限保障される財産の割合を定めた制度です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分の対象は被相続人の財産の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)で、法定相続分に基づいて按分されます。
遺留分を侵害された相続人は、侵害額を請求する権利があり、交渉や調停を経て解決を試み、必要に応じて家庭裁判所に「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
相続税や贈与税の節税対策にはどのような手法があるか
事業承継においては、相続税や贈与税の負担を軽減するため、複数の節税対策を組み合わせることが重要です。
代表的な手法の一つが生命保険の活用で、経営者が死亡保険に加入し、法人や後継者が保険金を受け取ることで、相続発生時の納税資金や遺産分割資金を確保できます。法人契約であれば、保険料を損金算入することで法人税の圧縮も可能です。
また、退任時に役員退職金を支給することで、法人は損金算入による節税、経営者個人は退職所得控除と分離課税の適用による軽減効果が得られます。さらに、不動産を法人で取得し減価償却する、あるいは相続税評価額が低い不動産を生前贈与することで、資産移転時の課税負担を抑えることも有効です。
これらは税務リスクを伴うため、税理士など専門家の助言を受けながら進めることが不可欠です。
相続時精算課税制度とは何か
相続時精算課税制度は、生前贈与を促進する目的で創設された税制で、主に親や祖父母から子や孫への早期資産移転を可能にする仕組みです。60歳以上の親または祖父母が、18歳以上の子や孫に対して贈与を行う場合に適用され、累計で2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されますが、贈与財産は将来の相続時に相続財産として合算され、相続税の課税対象となります。この制度により、贈与時点では贈与税の負担を抑えつつ、最終的な課税は相続時に調整される仕組みとなっています。
ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できず、以後は暦年課税制度(年間110万円の非課税枠)を利用できません。また、本制度を利用して取得した宅地等には、小規模宅地等の特例が適用できないなどの制約があるため、適用には慎重な判断が求められます。
後継者に経営権を譲りつつコントロールする方法は他にあるか
生前に後継者へ経営権を譲渡しつつ、自らの影響力を一定程度維持したい場合、株式の種類や権利内容を工夫する方法が有効です。
代表的な手法として「黄金株(拒否権付種類株式)」があります。これは、重要事項に対してのみ拒否権を行使できる特別な株式で、たとえ少数保有であっても経営の根幹に関わる決定を阻止する力を持ちます。
また、「議決権制限株式」も活用できます。後継者に対しては議決権のない株式を交付し、配当などの経済的利益のみを付与することで、経営判断には関与させず、段階的な承継が可能です。
これらの仕組みにより、現経営者は事業承継を進めつつ、重要な局面では一定のコントロールを維持できます。
遺言信託とは何か
遺言信託とは、公正証書遺言の作成から保管・執行まで、信託銀行などが一貫してサポートするサービスです。相続人間のトラブル防止や遺言者の意思の確実な実現を目的としています。信託銀行は遺言執行者として財産の調査、目録作成、名義変更を行うため、相続手続きの負担を軽減できます。
利用にあたっては、遺言者が生前に信託銀行と契約を結び、相続開始後は指定の死亡通知人からの連絡を元に遺言が執行されます。原則として公正証書遺言が前提であり、自筆証書遺言は扱えない点や、手数料が発生する点に注意が必要です。複雑な遺言内容や第三者への財産配分など、遺言信託は柔軟な対応が可能な仕組みです。
自社株が分散するとどのようなトラブルが起きるか
自社株が分散すると、経営の安定性や意思決定に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
例えば、相続や贈与によって株式が親族間に分散すると、経営に関与していない株主が多数を占める事態になりかねません。このような場合、会社の方針に対して意見の対立が起こりやすく、取締役の選任や重要な決議がスムーズに進まなくなる恐れがあります。
また、経営権を巡る争いが顕在化し、会社の運営が停滞するリスクもあります。さらに、株主間の信頼関係が崩れた場合、株式の買い取り要求や持分売却による第三者への株式流出などが起き、会社の支配構造が不安定化する要因とされます。
M&A・事業承継のご相談はM&Aロイヤルアドバイザリーへ
企業の経営権を後継者へスムーズに引き継げる事業承継信託は、特に中小企業経営者に向いている有効な対策です。もし、自社で事業承継など経営課題に関してご検討している場合は、ぜひM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。貴社の成長と成功を全力でサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。