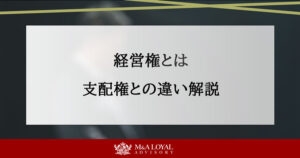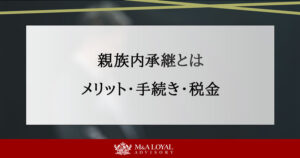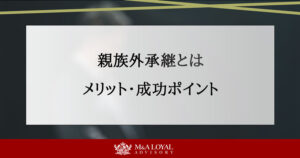事業継承と事業承継の違いは?意味や使い方をわかりやすく解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
事業承継と事業継承の違いを理解し、使い分けている方はどれほどいるでしょうか。事業承継と事業継承はどちらも「事業を引き継ぐ」という意味で似ていますが、使用される文脈や意味合いが異なります。本記事では、承継と継承の違いから使い分け、具体的に引き継がれるものや手続きまでわかりやすく解説します。
目次
事業承継と事業継承の違いとは?基本的な意味を解説
事業承継と事業継承は、混同されて使われることもありますが、両者は似ているようで意味や使い方に違いがあります。ここでは、「承継」と「継承」の違いについて説明します。
- 承継とは
承継とは、事業や経営理念、ビジョン、精神などの目に見えない抽象的な要素を次の世代に引き継ぐことを指します。承継は法律や契約などビジネスの場面で頻繁に使用されます。
- 継承とは
継承とは、物理的な地位や財産、権利義務を受け継ぐことを意味します。例えば、王位継承や地位継承などがあります。日常的な場面では継承が使われることも少なくありません。
- 伝承とは
伝承とは、慣習や文化、伝統、技術、知識などを世代から世代に受け継ぐことを指します。口頭で語り継がれることが多く、地域性が高いことも特徴です。
- 相続とは
相続とは、故人の財産を受け継ぐことを指します。法律に則った手続きによって進められ、対象者(相続人)も法律で決められています。
事業承継と事業継承の使い分けと公的表記
承継と継承の違いをまとめると、「承継」は主に抽象的な価値を引き継ぐことに焦点を当てており、特にビジネスや経営の場面で使われます。一方、「継承」は財産や地位を受け継ぐことに重きを置いています。
事業の引き継ぎでは、無形財産と有形財産の両方が移転するケースが一般的です。そのため、承継と継承の両方の要素が含まれますが、実際には「事業承継」という用語が広く使われています。事業継承も誤りではありませんが、公的な文書や法律、契約関係では「事業承継」が一般的であることを覚えておくと良いでしょう。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



事業承継で引き継ぐ3つの経営資源
事業承継で引き継ぐ経営資源は大きく3つに分類されます。これらの資源は、事業の継続と発展において不可欠な要素であり、それぞれ異なる性質と役割を持っています。
経営資源は以下の3つに分類されます。
- 人(経営権)
- 資産
- 知的資産
それぞれについて解説します。
人(経営権)の承継
事業承継における人(経営権)の承継は、事業の継続と成長を支える経営資源の一つです。経営権とは、会社の意思決定や経営方針の決定権を指し、後継者がこれを適切に引き継ぐことで、事業の安定した運営が可能となります。経営権の承継は単なる身分や役割の移転にとどまらず、経営者としての責任や企業文化の継承も含まれます。
そのため、後継者の選定は事業承継の成否にも直結します。経営者の資質や経営に対する理解度、リーダーシップ能力を評価し、会社の将来を託せる人物を選ぶことが求められます。また、後継者が経営権を円滑に承継できるように、必要に応じて育成やサポートも行うこともあるでしょう。
経営権の承継に際しては、以下のポイントに注意しましょう。
- 早期から後継者候補の育成と準備を行うこと
- 経営権の移転に関わる法律や契約の専門家に相談し、適切な手続きを行うこと
- 経営者と後継者の間で経営方針やビジョンを明確に共有すること
- 経営権の承継に伴うリスクや課題を事前に把握し、対策を講じること
これらのポイントを踏まえ、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることで、経営権の承継は円滑に行われ、事業承継全体の成功へとつながります。
資産の承継
事業承継における資産の承継とは、事業運営に必要な有形・無形の資産を適切に引き継ぐことを指します。資産には設備や不動産、在庫といった有形資産だけでなく、ブランド価値や顧客リストなどの無形資産も含まれます。
資産の種類別に承継のポイントと必要な手続き、注意点をまとめます。
| 資産の種類 | 承継のポイント | 必要な手続き・契約 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 有形資産(設備・不動産・在庫等) | ・正確な資産評価と所有権の明確化 ・譲渡登記や引渡しの実施 | ・譲渡契約書の作成 ・不動産登記や名義変更手続き | ・評価額の適正性 ・登記漏れや権利移転の遅延に注意 |
| 無形資産(ブランド・顧客リスト・契約関係) | ・価値の適正評価と権利関係の整理 ・契約譲渡の明確化 | ・譲渡契約書の締結 ・関係者への通知と承認取得 | ・評価の難しさ ・契約条件の変更や制限に注意 |
資産の承継においては、まず譲渡対象となる資産の種類と範囲を明確にし、それぞれの資産を適切に評価することが重要です。特に無形資産は価値の把握が難しいため、専門家の助言を得て評価を行うことが望ましいです。また、契約書には譲渡内容や条件を明確に記載することもトラブル防止に繋がります。
知的財産の承継
事業承継における知的財産の承継とは、企業が保有する特許権、商標権、著作権、技術ノウハウなどの知的財産権を引き継ぐことを指します。知的財産は企業の競争力の源泉であり、適切な知的財産の承継は、事業の持続的な発展と成功に繋がります。
知的財産の種類には以下のようなものがあります。
| 知的財産の種類 | 特徴 | 承継時のポイント |
|---|---|---|
| 特許権 | 新規性や進歩性のある発明を独占的に利用できる権利。 | 特許の譲渡登録や使用許諾契約の確認が必要。技術内容の正確な把握と権利範囲の明確化が重要。 |
| 商標権 | 商品やサービスのブランドを識別するための権利。 | 商標の譲渡登録と契約の整備が必要。ブランド価値の維持と管理がポイント。 |
| 著作権 | 文学、音楽、図面などの創作物に対する権利。 | 著作権の譲渡や利用許諾契約の確認が重要。権利の範囲と期間を明確にすること。 |
| 技術ノウハウ | 企業独自の技術や運用方法などの非公開情報。 | 秘密保持契約(NDA)や技術移転契約の締結が必要。情報漏洩防止と管理体制の強化が求められる。 |
知的財産の承継には、法律に基づく権利の譲渡手続きや契約の締結が不可欠です。特に特許権や商標権は登録制度があるため、承継後に正式な名義変更を行わなければ第三者に対抗できません。
また、著作権や技術ノウハウについても契約書による権利範囲の明確化が重要です。権利の範囲や有効期限の確認、契約条件の遵守、情報漏洩や権利侵害の防止策を講じることが大切です。
事業承継で引き継ぐ経営資源
| 経営資源の種類 | 内容の概要 | 引き継ぎ時のポイント |
|---|---|---|
| 人(経営権) | 経営者や後継者など、事業を運営するための意思決定権や経営権を指します。経営のリーダーシップやビジョンの継承が重要です。 | 後継者の選定や育成、経営権の円滑な移転が成功の鍵となります。 |
| 資産 | 事業運営に必要な有形資産(設備、建物、在庫など)や無形資産(ブランド、顧客リスト、契約関係など)を含みます。 | 資産の正確な評価と法的手続きを経た権利移転が重要で、契約書の整備も欠かせません。 |
| 知的財産 | 特許権、商標権、著作権などの知的財産権を指し、技術やノウハウの保護・継承に不可欠です。 | 知的財産の適切な管理と法的保護、契約による権利の明確化がポイントとなります。 |
これらの経営資源は、それぞれ異なる側面を持ちながらも、相互に連携して事業の持続的な発展を支えます。事業承継を成功させるためには、それぞれの特徴を理解し、計画的に引き継ぐことが大切です。
事業承継の3つの方法
事業承継の方法にはいくつかの種類があります。ここでは事業を承継する際の代表的な3つの手段について解説します。
- 親族内承継
- 従業員・役員への承継
- 第三者承継(M&A)
それぞれについて解説します。
親族内承継
親族内承継は、経営者の家族や親族に事業や経営権を引き継ぐ方法であり、日本の中小企業において最も一般的な事業承継の形態です。この承継方法の大きなメリットは、経営者と後継者の信頼関係が強く、経営理念や企業文化の継承がしやすいという点にあります。経営者の意思やビジョンを深く理解している後継者に事業を託すことで、事業の安定的な継続が期待されます。
しかし、親族内承継には注意すべきデメリットも存在します。後継者の能力や意欲が経営の成否に直結するため、適切な後継者の育成が不可欠です。
また、複数の候補者がいる場合、家族間の感情的なもつれや意見の対立が、事業運営に悪影響を及ぼすリスクもあります。こうした問題を回避するためには、早期から準備を始め、必要に応じて専門家の相談を受けることが大切です。
親族内承継のメリットと注意点は以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 信頼関係の強さによりスムーズな意思決定が可能 | 後継者の能力や意欲に依存しやすい |
| 経営理念や企業文化の継承が容易 | 家族間の感情的対立やトラブルのリスク |
| 長期的な視点での経営安定が期待できる | 事業と個人の財産管理の分離が難しい場合がある |
親族内承継の成功には、後継者の早期育成が欠かせません。また、家族間の問題を未然に防ぐために、第三者の専門家によるアドバイスを受けながら進めることも大切です。事業承継は法律や税務の複雑な問題を含むため、専門家への相談を積極的に行い、計画的に準備を進めることが成功のポイントとなります。
従業員・役員への承継
従業員や役員への承継は、経営者が自社の従業員や役員に対して事業や経営権を引き継ぐ方法であり、組織の内部から後継者を選ぶ形となります。この方法は、社内のノウハウや企業文化を維持しやすい点が特徴です。
従業員・役員への承継の主なメリットと注意点は以下の通りです。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 企業文化や組織風土を引き継ぎやすい | 後継者の経営経験不足によるリスクがある |
| 従業員のモチベーション向上や定着率の改善につながる | 適切な後継者の育成が必要で準備期間が長くなることがある |
| 外部に比べて信頼関係が構築しやすい | 経営方針の転換が難しく変革に時間がかかる可能性がある |
従業員や役員への承継は、能力を見ながら段階的に引き継ぎができる点です。例えば、子会社の経営を任せて経験を積ませ、時期を見て本社の経営を任せるといった方法もあります。一方で、従業員・役員への承継にはいくつかのリスクや注意点も存在します。資金調達の問題や社内の人間からの反発といったトラブルが生じる可能性もあり、後継者の能力評価や他の役員や従業員とのコミュニケーションなど早期から計画的な準備が大切です。
第三者承継(M&Aなど)
親族や社内に後継者が不在の場合の第三の選択肢が第三者承継です。これは、外部の企業や投資家に経営権や資産を譲渡し、事業を引き継ぐ方法です。M&Aもこのカテゴリーに含まれます。M&Aは身近に適切な後継者がいない場合だけでなく、新たな資金調達や経営資源の強化を図りたい場合にも選択されることが多い方法です。
第三者承継の最大の特徴は、経営権の譲渡によって経営のリーダーシップが外部に移る点にあります。これにより、経営方針や事業戦略が大きく変わる可能性があるため、従業員や取引先への影響も考慮しながら慎重に進める必要があります。
第三者承継のメリットと注意点は以下のとおりです。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 新たな資金や経営資源の獲得により事業基盤の強化が可能 | 経営方針の大幅な変更による社内混乱のリスク |
| 後継者不足の問題を解消できる | 従業員の不安や反発が生じる可能性がある |
| 市場環境の変化に柔軟に対応できる | 企業文化の継承が困難になる場合がある |
第三者承継を成功させるためには、専門家と連携し、適切な手続きを踏むことが大切です。譲渡契約の詳細な内容の確認や、権利義務の明確化、税務面での対応など、多岐にわたる準備が必要となります。また、従業員や取引先への情報提供とコミュニケーションもポイントです。
事業承継の3つの方法の比較
| 方法の種類 | 概要 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 経営者の家族や親族に事業や経営権を引き継ぐ方法 | 信頼関係が強く、長期的な安定が期待できる。経営理念や文化の継承がしやすい。 | 後継者の能力や意欲に依存しやすい。家族間のトラブルが発生する可能性がある。 |
| 従業員・役員への承継 | 従業員や経営陣に経営権を譲渡し、事業を継続する方法 | 社内のノウハウや組織文化を維持しやすい。従業員のモチベーション向上につながる。 | 適切な後継者育成が必要。経営経験不足によるリスクがある。 |
| 第三者承継(M&Aなど) | 外部の第三者企業や投資家に経営権や資産を譲渡する方法 | 資金調達や経営資源の強化が可能。市場環境の変化に柔軟に対応できる。 | 経営方針や企業文化の変化リスク。従業員の不安や反発が生じる場合がある。 |
これらの方法にはそれぞれにメリットとデメリットがあり、事業の状況や将来のビジョンに応じて適切な選択が求められます。また、契約や法律面での手続きも異なるため、専門家の助言を受けながら準備を進めることが推奨されます。
事業承継の流れ
事業承継を成功させるためには、段階的かつ計画的に進めることが不可欠です。ここでは、事業承継の基本的な流れを紹介します。
| 段階 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.経営状況と課題の整理・把握 | 現状の経営状況を詳細に分析し、事業の強み・弱みや課題を明確にする。 | 財務状況や市場環境を正確に把握し、課題を具体的に洗い出すことが重要。 |
| 2.後継者の選定 | 適切な後継者を選び、経営権の移転準備を進める。 | 後継者の資質や意欲を評価し、早期に育成計画を立てることが成功の鍵。 |
| 3.事業承継計画の策定 | 承継の具体的な計画を策定し、ステークホルダーと共有する。 | 計画には財務・税務面の対策や承継スケジュールを含めることが重要。 |
| 4.経営資源の移転 | 経営権や資産、知的財産などの経営資源を正式に移転する。 | 契約書の整備や法的手続きを確実に行い、トラブルを防ぐ。 |
| 5.承継後のフォローアップ | 承継後の経営状況をモニタリングし、必要な支援や改善策を講じる。 | 承継後の課題把握と迅速な対応が事業の安定化に寄与する。 |
それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.経営状況と課題の整理・把握
事業承継の最初のステップが、経営状況や課題の整理と把握です。この段階では、現状の財務状況や市場環境を多角的に分析し、事業の強み・弱みを明確にすることが大切です。自社の経営状況の把握は、後続の後継者選定や事業承継計画の策定に直接結びつき、事業承継のプロセス全体に影響を与えます。
具体的には以下のようなポイントで経営状況と課題を整理します。
| 分析項目 | 内容 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 財務状況 | 売上高、利益、キャッシュフロー、負債の状況などを詳細に把握する。 | 過去数年分のデータを比較し、収益性や資金繰りの傾向を分析することが重要。 |
| 市場環境 | 競合状況、顧客動向、業界の成長性や規制環境などを調査する。 | 外部環境の変化が事業に与える影響を評価し、将来のリスクやチャンスを見極める。 |
| 経営課題 | 人材不足、技術継承の問題、設備の老朽化、販路の拡大など具体的な課題を整理する。 | 課題は具体的かつ優先順位をつけて明確にすることで、解決策の策定がスムーズになる。 |
経営状況と課題を整理する際は、単にデータを集めるだけでなく、経営者や経営陣、従業員からのヒアリングも行い、多角的な視点での分析を心掛けることが効果的です。また、分析結果をもとに現状の課題を明確化し、これを後継者選定や事業承継計画の策定に反映させることが大切です。
2.後継者の選定
自社分析を終えた後は、後継者選定を行います。後継者は単に経営権を引き継ぐだけでなく、企業の将来を担う存在であり、その資質や能力、経営に対する意欲が事業の持続的発展を左右します。経営状況の整理を踏まえた上で、適切な人材を見極め、育成計画を立てる必要があります。
後継者選定の評価ポイントとして以下が挙げられます。
| 評価ポイント | 内容 | 具体例・注意点 |
|---|---|---|
| 資質・適性 | 経営者としてのリーダーシップや判断力、倫理観などの基本的な資質 | 企業文化や経営理念に共感し、適切な意思決定ができるか |
| 経営能力 | 財務管理、戦略立案、組織運営などの実務的な経営スキル | 必要な知識や経験の有無、外部研修や教育の活用もポイント |
| 意欲・コミットメント | 経営者としての強い意欲や長期的な経営へのコミットメント | 経営に対する熱意や困難時の対応力を評価 |
| 人間関係・信頼 | 社内外との良好な関係構築能力 | 従業員や取引先からの信頼を得られるか |
選定後は早期に後継者育成を開始し、経営に必要な知識やスキルの習得、企業文化の理解を深めることが重要です。育成計画を立てて段階的に準備を進めることで、スムーズな経営権の移転が期待できます。
後継者選定におけるポイントをまとめると以下のとおりです。
- 複数の候補者を比較検討し、評価基準を明確にする
- 経営者本人や取締役会、外部専門家の意見を取り入れる
- 後継者候補の意欲や能力を早期に把握し育成計画を立てる
後継者選定は事業承継計画の中核であり、計画的に進めることが成功の鍵です。親族や社内に適した人材がいない場合は第三者への承継を検討します。その場合には、M&A仲介会社など専門家が持つネットワークを活用して、承継相手を選定します。
3.事業承継計画の策定
後継者の選定が完了した後には、具体的な事業承継計画の策定を行います。事業承継計画は、経営権や資産、知的財産などの経営資源をどのように引き継ぐかを明確に示し、承継プロセスを円滑に進めるための設計図となります。計画の策定が不十分であると、承継時に混乱やトラブルが生じるリスクが高まるため、十分な準備と関係者間の共有が大切です。
事業承継計画の策定ポイントは以下にまとめます。
| ポイント | 内容と具体例 |
|---|---|
| 計画の目的と意義 | 事業の継続性と安定性を確保し、関係者の理解と協力を得るために計画を立てる。経営の方向性や承継の手順を明確にする。 |
| 財務・税務面の対策 | 相続税や贈与税、譲渡税などの税負担を軽減するための対策を講じる。専門家と連携し、最適な節税プランを作成する。 |
| 承継スケジュールの作成 | 承継の各段階を時期ごとに整理し、準備から実行、フォローアップまでのスケジュールを具体的に設定する。 |
| リスク管理と対応策の検討 | 承継に伴う法的リスクや経営リスクを洗い出し、それぞれに対する対応策を計画に盛り込む。 |
| ステークホルダーとの共有 | 従業員、取引先、金融機関など関係者への説明や合意形成を図り、円滑な承継を支援する。 |
また、事業承継計画は一度作成して終わりではなく、経営環境や事業状況の変化に応じて見直しを行うことが大切です。特に税制改正や市場環境の変化に対応できる柔軟性を持たせることが、長期的な成功に繋がります。
4.経営資源の移転
経営資源の移転は、計画段階で定めた方針に基づき、経営権や資産、知的財産といった経営資源を後継者に引き継ぐ段階です。ここでは、法律や契約に則った正確な手続きが求められます。
経営権・資産・知的財産のそれぞれの移転手続きの注意点をまとめます。
| 経営資源の種類 | 移転手続きの概要 | 重要なポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 経営権 | 株式譲渡、役員交代手続き、取締役会や株主総会での承認を経て正式に経営権を移転。 | 適法な契約書作成と法的手続きの厳守。後継者の意思確認と社内外への周知徹底が重要。 |
| 資産 | 有形資産は譲渡契約書作成や所有権移転登記、無形資産は契約譲渡や名義変更手続きが必要。 | 資産評価の正確性と権利移転の漏れ防止。税務対応や費用負担の確認も重要。 |
| 知的財産 | 特許権や商標権の譲渡登録、著作権の譲渡契約、技術ノウハウは秘密保持契約(NDA)締結。 | 権利範囲の明確化と法的保護の徹底。情報漏洩防止や契約条件の遵守が成功の鍵。 |
この段階での注意点としては、契約書の内容確認や法的手続きの漏れがないかを専門家とともに慎重にチェックすること、税務面での影響を考慮した対応を行うことが挙げられます。これらを怠ると、後々のトラブルや事業の継続に支障をきたす恐れがあるため、十分な準備と確認が必要です。
また、経営資源の移転後は関係者間での調整や情報共有も必要です。取引先や従業員、金融機関などに対して適切な説明を行い、信頼関係を維持しながら進めることで、事業承継の円滑な実現につながります。
5.承継後のフォローアップ
経営資源の移転が完了した後も、円滑な事業運営と持続的な成長を実現するためには、承継後のフォローアップが大切です。この段階では、承継後の経営状況を継続的にモニタリングし、発生する可能性のある課題や問題を早期に発見・対応することが求められます。
フォローアップが不十分だと、事業承継後に経営の安定が損なわれ、リスクが顕在化してしまう恐れがあるため、計画的かつ積極的な取り組みが重要です。
具体的なフォローアップのポイントを以下に述べます。
- 経営状況のモニタリング:売上や利益、キャッシュフローなどの経営指標を定期的にチェックし、承継後の経営状況を把握します。異常値やトレンドの変化に注意を払い、早期発見に努めます。
- 課題の早期発見と対応:従業員の意見聴取や顧客からのフィードバックを積極的に収集し、経営上の問題や改善点を速やかに把握して対策を講じます。
- 関係者とのコミュニケーション:取引先や金融機関、従業員などのステークホルダーと継続的に情報共有を行い、信頼関係の維持と協力体制の強化を図ります。
- 必要な支援の実施:経営者や後継者が直面する課題に対して、専門家の助言や公的支援制度の活用を促進し、適切なサポートを受けられる環境を整えます。
- 継続的な改善策の導入:経営環境の変化や新たな課題に対応するため、柔軟かつ持続的な改善策を計画的に実施し、事業の競争力を維持・強化します。
- トラブル防止とリスク管理:契約内容や権利関係の再確認、情報漏洩リスクの管理など、法的・経営的リスクに対する継続的な対応を行います。
- 専門家の活用:税理士、弁護士、コンサルタントなどの専門家と連携し、法務、税務、経営面での課題解決を図ることが成功のポイントです。
承継後のフォローアップは、単なる事後対応ではなく、事業の持続的発展を支える重要なプロセスです。経営者と後継者が協力して主体的に取り組み、関係者との連携を強化することで、事業承継の成功確率を大きく高めることができます。
適切なフォローアップ体制を構築し、発生しうるリスクや課題に迅速に対応することが、安定した経営継続と企業価値の向上につながるため、計画的かつ継続的に実施しましょう。
事業承継を成功させる5つのポイント
事業承継を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。これまで解説した内容を踏まえつつ、実際に取り組む際に特に留意すべき5つのポイントを紹介します。これらのポイントを意識し、計画的に対応することが事業承継の成功に繋がります。
- 早い段階から準備を開始する
- 自社に適した承継方法を選択する
- 支援施策や補助金を活用する
- 情報漏洩リスクに注意する
- 専門家への相談・サポートを受ける
それぞれのポイントについて解説します。
早い段階から準備を開始する
事業承継を成功させるためには、何よりも早い段階から準備を開始することが重要です。事業承継は経営資源の適切な引き継ぎや後継者育成、法的手続きの整備など多岐にわたる複雑なプロセスを含みます。そのため、時間的余裕を持って計画的に準備を進めることが、リスクを最小限に抑え、承継後の事業の安定と成長を確保するポイントとなります。
早期に準備を始める主な理由は以下のとおりです。
- 後継者の育成期間の確保:経営者としての能力や知識を身につけるためには時間が必要です。早めに後継者の選定と育成を始めることで、経営の現場での実践経験を積ませることができます。
- 資産の評価と整理:事業に関わる資産や負債の把握、評価作業は時間がかかるため、余裕を持って行う必要があります。適切な評価は契約や譲渡手続きの基礎となります。
- 法律や契約の準備:事業承継に伴う契約書の作成や法的手続きは専門的で複雑です。時間をかけて専門家と相談しながら進めることがトラブル防止につながります。
- リスクの事前把握と対策:経営環境の変化や税制改正など、様々なリスクを早期に把握し、計画に反映させることで問題の顕在化を防げます。
- 関係者との合意形成:従業員や取引先、家族など関係者との意思疎通や合意形成にも時間を要します。早期のコミュニケーションが円滑な承継を促進します。
これらの準備を怠ると、承継後に経営の混乱やトラブルが発生し、事業の継続が危ぶまれるリスクが高まります。逆に、早い段階から計画的に準備を進めることで、余裕を持った対応が可能となり、成功確率を大きく高めることができます。
事業承継を検討し始めたら、まずは現状の経営状況を把握し、後継者の選定や育成の計画、資産評価や契約の準備に着手しましょう。専門家への早期相談も、適切な準備に役立つため積極的に活用することをおすすめします。
自社に適した承継方法を選択する
自社の状況に最も適した承継方法を選択することも事業承継を成功させるポイントです。親族内承継、従業員・役員承継、第三者承継はそれぞれ特徴とメリット、注意点が存在します。どの方法が自社に合うかどうかは、経営状況や後継者の有無、将来の経営ビジョンによって大きく異なります。
承継方法の選択にあたっては、以下のようなポイントを検討すると良いでしょう。
| 検討ポイント | 内容の説明 |
|---|---|
| 後継者の有無・適性 | 親族や社内に適任の後継者がいるか。いない場合は第三者承継の検討が必要。 |
| 事業の規模・経営資源 | 中小企業か大企業か、資産や人材の状況によって適した方法が異なる。 |
| 経営の継続性と安定性 | 承継後も安定した経営が可能か。内部承継は文化やノウハウの維持に有利。 |
| 資金調達の必要性 | 第三者承継は資金面でのメリットがあるが、経営方針の変化リスクも伴う。 |
| 企業文化・理念の継承 | 企業の価値観や文化を重視する場合は親族内や従業員承継が適している。 |
| リスクと課題の認識 | 各方法に伴うリスクを理解し、対策を検討することが成功に繋がる。 |
これらの検討ポイントを踏まえ、自社の現状と将来像を明確にしながら、最適な承継方法を選択しましょう。どの承継方法が適しているか判断に迷う場合には専門家の相談窓口を活用することもおすすめです。
支援施策や補助金を活用する
事業承継を実施する際には、国や地方自治体、関連機関が提供する支援施策や補助金を積極的に活用しましょう。これらの制度は、事業承継に伴う資金負担の軽減や専門的なサポートの提供など、多方面での支援を受けられるため、円滑な承継準備と実行に大きく寄与します。
国や地方自治体の支援制度として以下があります。
| 支援施策・補助金の種類 | 概要 | 活用のメリット | 利用時の注意点 |
|---|---|---|---|
| 中小企業庁の事業承継補助金 | 後継者育成やM&A支援、事業承継計画の策定費用などを補助 | 資金負担軽減、専門家のサポートを受けやすい | 申請期間や要件に注意。計画的な準備が必要 |
| 地方自治体の独自支援制度 | 地域の実情に応じた補助金や相談窓口の設置 | 地域特性に合った支援が受けられる | 制度内容は自治体ごとに異なるため確認が必要 |
| 金融機関の事業承継支援ローン | 事業承継に必要な資金を低利で貸付 | 資金調達がしやすく、返済計画を立てやすい | 返済能力の審査があるため、計画的な借入が重要 |
| 商工会議所や中小企業支援センターの相談支援 | 専門家による経営相談や承継計画のアドバイス | 無料または低コストで専門的な助言が得られる | 予約や利用条件に注意。早めの相談が望ましい |
これらの支援施策や補助金を活用することで、事業承継に伴う資金面や手続き面での負担を軽減することができます。ただし、支援制度には申請期限や適用条件があるため、制度の詳細を十分に確認し、必要な準備を怠らないことが重要です。また、支援を受ける際は専門家への相談も併用し、最適な活用方法を検討することをおすすめします。
情報漏洩リスクに注意する
事業承継においては、経営情報や技術、顧客情報など企業の重要な情報を適切に管理し、情報漏洩リスクに注意を払うことが必須です。情報漏洩が起こると、企業の信用低下や競争力の喪失、取引先との信頼関係の崩壊など、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があるためです。
特に事業承継の過程では、後継者や関係者間で機密情報の共有が必要になるため、情報管理の徹底が求められます。ここでは、情報漏洩リスクの種類とそれに対する具体的な対策について解説します。
| 情報漏洩のリスク | ・意図しない外部への情報流出(例:メール誤送信、紛失) ・内部関係者による不正な情報持ち出し ・不適切な情報管理体制による漏洩 |
| 情報管理体制の強化 | ・秘密保持契約(NDA)の締結 ・アクセス権限の適正化 ・情報の暗号化 ・管理者の設置 |
| 情報漏洩対策の具体例 | ・機密情報のデジタル管理システム導入 ・従業員への情報管理教育 ・外部への情報提供時の慎重な確認 ・定期的なセキュリティチェックと監査 |
事業承継に関わる関係者間で秘密保持契約を締結することで、情報の取り扱いルールを明確にし、漏洩リスクを低減します。また、情報の安全管理に関する体制を整備し、情報の不正利用や漏洩を防ぐことも大切です。さらに、契約書には情報の範囲、利用目的、違反時の対応を具体的に定めましょう。
これらの対策を講じることで、事業承継に伴う情報漏洩リスクを最小限に抑え、企業の信用維持と継続的な成長につなげることが可能です。また、万が一情報漏洩が発生した場合は、速やかに影響範囲を特定し、関係者への報告、適切な再発防止策の実施が求められます。専門家の助言を受け、法的対応も検討しましょう。
専門家への相談・サポートを受ける
事業承継は法律や税務、契約など専門的で複雑な要素が絡むため、専門家への早期の相談と継続的なサポートの活用が成功のポイントです。例えば、M&A仲介会社は専門家と連携し、法律的な問題の解決だけでなく、税務対策や資産評価、契約書作成など多岐にわたる支援を行います。
これにより、事業承継後に起こり得るリスクにも適切に対処ができ、トラブルを最小限に抑えることが可能となります。まだ明確に後継者が定まっていない、事業承継について検討中の段階であっても早期に相談することで、見落としていた課題を発見でき、事業を経営しながらも余裕を持った準備ができるようになります。
専門家に相談する際には、サポート内容や費用、実績等などを総合的に判断し、複数の会社を比較検討すると良いでしょう。信頼できる専門家選びも事業承継を成功させる重要なポイントです。
まとめ
本記事では、事業承継と事業継承の違いから、事業承継で引き継ぐ資源、手法について解説しました。事業の未来を考える経営者にとって、どのように承継を進めるかは企業の存続に大きな影響を与えます。そのため、早期の準備と適切な情報収集が鍵となります。また、自社に適した承継方法を選び、必要であれば専門家のサポートを受けることが成功への近道です。
M&Aや事業承継に関する相談はぜひ、M&Aロイヤルアドバイザリーにお問い合わせください。経験豊富なアドバイザーが貴社の目的や状況に応じた最適なプランをご提案させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。