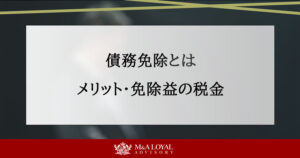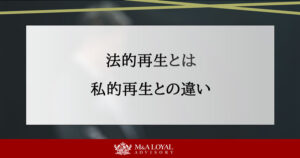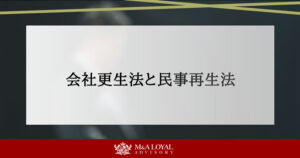自己破産とは?メリット・デメリットやその後の人生への影響を解説
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
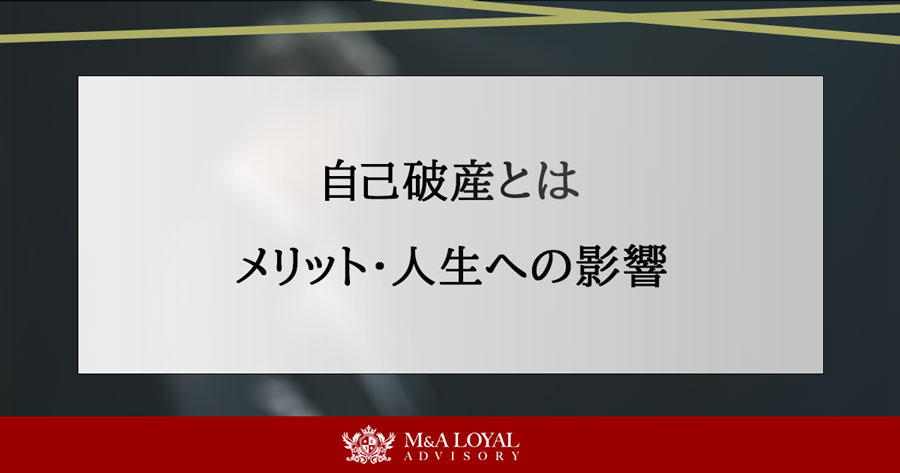
自己破産とは、借金の返済が困難になった人が非免責債権を除く、全ての借金をゼロにする手続きです。自己破産は法律で認められた正当な債務整理手段であり、適切に活用することで経済的な困窮から抜け出し、新しい人生を歩み始めることができます。
中小企業の経営者や個人事業主、会社員の方々が、事業の失敗や収入減少、医療費の負担などにより返済困難に陥った際の解決策として機能していますが、「自己破産=人生の終わり」という誤った認識や、手続きの複雑さから躊躇している方も少なくありません。
本記事では、自己破産とは何かという基本的な仕組みから具体的な手続き、メリット・デメリット、その後の生活への影響まで、専門的な内容をわかりやすく解説いたします。
目次
自己破産とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説
自己破産とは、借金の返済が困難になった個人が裁判所に申し立てを行い、法的に借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。「人生の終わり」といったネガティブなイメージを持たれがちですが、実際には借金問題で苦しむ人を救済し、経済的な再スタートを支援する法的制度として設けられています。
中小企業の経営者や個人事業主、会社員の方でも、事業の失敗や病気による収入減少、予期せぬ出費などにより、どなたでも返済困難な状況に陥る可能性があります。そのような状況を法的に解決する最終的な手段が自己破産制度なのです。
裁判所を通じて「原則として」借金を免除してもらう法的手続き
自己破産は、債務者(借金をしている人)が裁判所に申し立てを行うことから始まります。裁判所は提出された書類や面談を通じて、申立人が本当に支払い不能な状態にあるかを慎重に審査します。
この手続きにより、消費者金融からの借入、銀行ローン、クレジットカードの利用残高、奨学金など、ほとんどすべての借金について法的に支払い義務が免除されることになります。ただし、税金や社会保険料、養育費など一部の債務は免除の対象外となります。 また、奨学金の借りる際に親族を連帯保証人にしている場合は連帯保証人が支払い義務を負うことになります。
重要なのは、自己破産が単なる「借金逃れ」ではなく、経済的に困窮した方の生活再建を支援する法的な制度として位置づけられていることです。
破産手続と免責手続の2つのステップ
自己破産は「破産手続」と「免責手続」という2つの段階で構成されています。この2段階構造を理解することで、手続き全体の流れが明確になります。
まず破産手続では、裁判所が申立人の財産状況を調査し、価値のある財産を換金して債権者(お金を貸した側)に公平に分配します。高額な財産がない場合は「同時廃止」となり、破産手続は即座に終了します。一方、不動産や高価な動産がある場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任されて財産の処分が行われます。
次の免責手続では、破産手続で分配しきれなかった残りの借金について、支払い義務の免除を裁判所に求めます。免責が許可されれば、法的に借金の返済義務がなくなり、経済的な再スタートが可能になります。
支払不能の状態が認められる基準
自己破産が認められるためには、裁判所に「支払不能」の状態であることを認めてもらう必要があります。破産法では、支払不能を「支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義しています。
具体的には、現在の収入や保有財産から考えて、将来にわたって借金を完済することが現実的に不可能な状況を指します。例えば、月収20万円の方が500万円の借金を抱えている場合、生活費を差し引くと月々の返済可能額は限られており、完済には相当な期間を要することから支払不能と判断される可能性が高くなります。
ただし、単純に借金額が多いだけでは支払不能とは認められません。収入の安定性、年齢、健康状態、扶養家族の有無など、総合的な事情を考慮して判断されます。また、一時的な収入減少ではなく、継続的に返済が困難な状況であることが求められます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



自己破産とはどんな条件で認められる?免責の要件を詳しく解説
自己破産は誰でも無条件で利用できる制度ではありません。裁判所が厳格な基準に基づいて審査を行い、一定の条件を満たした場合にのみ借金の免責が認められます。ここでは、自己破産が認められるための具体的な条件と、免責が制限される場合について詳しく解説します。
自己破産を検討している方にとって最も重要なのは、自分の状況が法的要件を満たしているかを正確に把握することです。適切な理解により、手続きをスムーズに進めることができます。
支払不能と認められる具体的な基準
裁判所が支払不能を判断する際は、単純な借金額だけでなく、申立人の総合的な経済状況を慎重に検討します。具体的には、現在の収入、保有財産、年齢、職業、健康状態、扶養家族の状況などが総合的に評価されます。
例えば、年収300万円の会社員の方が借金500万円を抱えている場合を考えてみましょう。生活費として月20万円が必要であれば、借金返済に充てられるのは月5万円程度となり、完済には8年以上を要します。この期間中に収入が維持される保証がなく、病気や失業のリスクも考慮すると、支払不能と判断される可能性が高くなります。
また、生活保護を受給している方や年金収入のみの高齢者の場合は、比較的少額の借金であっても支払不能と認められることがあります。重要なのは、将来にわたって継続的に返済を行うことが現実的に可能かどうかという点です。
免責不許可事由に注意!ギャンブルや浪費でも裁量免責の可能性
破産法では、免責を認めない事由として「免責不許可事由」を定めています。これらに該当する場合、原則として借金の免責は認められません。主な免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- 財産隠し:債権者を害する目的で財産を隠匿・処分した場合
- クレジットカード現金化:換金目的での商品購入とその即座の売却
- 浪費やギャンブル:浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させた場合
- 詐欺的借入:虚偽の情報により債権者を欺いて借入を行った場合
- 過去の免責:過去7年以内に免責を受けている場合
ただし、これらの事由に該当したとしても、必ずしも免責が認められないわけではありません。「裁量免責」という制度により、その他の事情を総合的に考慮して、裁判所の判断で免責が認められるケースが多数存在します。
特にギャンブルや浪費については、その程度や経緯、反省の度合い、今後の生活改善への取り組み姿勢などが評価され、多くの場合で裁量免責が認められています。
税金や養育費など免責されない債務一覧
自己破産により免責が認められても、すべての債務が免除されるわけではありません。以下の債務については、自己破産後も支払い義務が継続します。
- 税金関係:所得税、住民税、固定資産税、自動車税など
- 社会保険料:国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など
- 不法行為に基づく損害賠償債務:①破産者が悪意で加えた不法行為(単なる故意ではなく、積極的な加害の意図を指します)に基づくもの、②破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくもの
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権:意図的に特定の債権者を隠して手続きを行った場合、その債権者への債務は免責されない
- 扶養関係:養育費、婚姻費用、扶養義務に基づく債務
- 罰金・科料:刑事罰として科された金銭的制裁
- 一部の雇用関係債務:従業員の給与、預り金(個人事業主の場合)
これらの債務は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後も返済を継続する必要があります。特に税金や社会保険料については金額が大きくなることもあるため、自己破産を検討する際は、これらの債務についても十分に考慮することが重要です。養育費についても、子どもの福祉を保護する観点から免責の対象外となっています。
自己破産の5つの大きなメリット|借金の重圧から解放される
自己破産に対してネガティブな印象を持つ方も多いですが、実際には借金問題に苦しむ方にとって非常に大きなメリットをもたらす制度です。最も重要なのは、借金の完全な免除により経済的・精神的な重圧から解放され、新しい人生を歩み始めることができる点です。
ここでは、自己破産がもたらす具体的なメリットについて詳しく解説し、この制度が持つ本来の意義について理解を深めていただきたいと思います。借金問題で悩んでいる方にとって、自己破産は決して恥ずべきことではなく、法的に認められた正当な解決手段なのです。
借金の返済義務が完全に免除される
自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責許可を得ることで、非免責債権を除き、原則として借金の返済義務が免除されることです。数百万円、時には千万円を超える借金であっても、法的手続きを経ることで支払い義務がなくなります。
例えば、月収25万円の方が800万円の借金を抱えている場合、月々5万円返済したとしても完済まで13年以上を要し、その間の利息負担も相当な額になります。しかし、自己破産により免責が認められれば、この800万円の返済義務は原則としてなくなり、収入の多くを生活費や将来への備えに充てることができるようになります。
この経済的な効果は、単に数字上の問題だけでなく、生活の質的向上にも直結します。借金返済のために切り詰めていた食費や光熱費、子どもの教育費なども、適切な水準まで戻すことが可能になり、人間らしい生活を取り戻すことができます。
債権者からの取り立てが即座に止まる
弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者に対して受任通知が送付されます。この通知を受け取った債権者は、法律により債務者への直接的な取り立て行為が禁止されます。電話による督促、自宅への訪問、勤務先への連絡など、これまで精神的な負担となっていた取り立て行為が即座に停止されます。
長期間にわたって督促を受け続けている方にとって、この変化は非常に大きな安心感をもたらします。毎日のように鳴る督促の電話におびえることなく、落ち着いて生活することができるようになり、精神的な安定を取り戻すことが可能です。
また、給与や銀行口座の差し押さえといった強制執行も、破産手続きの開始により原則として中止されます。これにより、最低限の生活費も確保できるようになり、手続き期間中も安心して日常生活を送ることができます。
生活に必要な財産は手元に残せる
「自己破産をするとすべての財産を失う」という誤解を持つ方が多いですが、実際には生活に必要な財産については「自由財産」として手元に残すことができます。具体的には、法律で定められた「99万円以下の現金」や「生活に不可欠な家具・家電製品」などは手元に残すことができます。
これらに加え、多くの裁判所では運用上、申立人の生活再建のために一定の財産を手元に残すことを認める「自由財産の拡張」という制度があります。例えば東京地方裁判所の実務では、預貯金(複数口座の合計)、生命保険の解約返戻金、家財道具などの財産項目ごとに、その価値が20万円以下であれば手元に残すことが認められる傾向にあります。ただし、この「20万円」は法律で定められた絶対的な基準ではなく、あくまで裁判所の裁量的な運用の一例です。
また、仕事に必要な道具や書籍なども、基本的には処分の対象外となります。自営業者の方であれば、商売道具一式も継続して使用することができ、破産後の経済活動の基盤を維持することが可能です。
さらに、破産手続き開始後に得た収入や財産については「新得財産」として、完全に自由に使用することができます。つまり、破産手続き中に働いて得た給与は全額自分のものとなり、徐々に経済的基盤を再構築していくことができるのです。このように、自己破産は決して「一文無しになる」制度ではなく、生活再建のための最低限の基盤を保護しながら、借金問題を解決する制度として設計されています。
自己破産のデメリットと対処法|正しく理解して不安を解消
自己破産には大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ただし、これらのデメリットは多くの場合一時的なものであり、正しく理解することで適切な対策を講じることができます。ここでは、主要なデメリットとその具体的な影響、そして可能な対処法について詳しく解説します。
重要なのは、デメリットを過度に恐れることなく、メリットとデメリットを総合的に比較検討することです。多くの場合、借金問題の深刻さを考慮すると、一時的なデメリットを受け入れてでも自己破産を選択することが最適な解決策となります。
ブラックリストに載る期間と生活への影響
自己破産を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。自己破産の情報が信用情報機関に登録される期間は、機関によって異なり、一律ではありません。この違いを理解することが重要です。
| 信用情報機関 | 主な加盟業種 | 自己破産に関する情報の登録期間 |
| CIC | クレジットカード会社、信販会社 | 免責許可決定を加盟会社が確認した日から約5年 |
| JICC | 消費者金融、クレジットカード会社 | 破産手続開始決定の発生日から約5年 |
| KSC(全銀協) | 銀行、信用金庫、保証協会 | 官報で公告された破産手続開始決定日から7年 |
※参照
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・一般社団法人全国銀行協会(KSC)
このように、どの金融機関のサービスを利用したいかによって、影響を受ける期間は異なります。特に銀行系のローン(住宅ローンなど)は、KSCの情報を参照するため、影響が最も長く続く傾向にあります。
具体的な影響として、住宅ローンや自動車ローンの利用ができない、クレジットカードの新規作成ができない、携帯電話の分割払い契約が制限される場合があるなどが挙げられます。また、賃貸物件の契約時に信用情報を確認される場合もあり、一部の物件では入居が困難になる可能性もあります。
ただし、これらの制限は永続的なものではありません。登録期間が経過すれば信用情報は回復し、通常通りの金融サービスを利用できるようになります。また、デビットカードや家族カードの利用、現金での取引には影響がないため、日常生活における大きな支障は避けることができます。
持ち家や車など高額財産の処分
自己破産では、一定額を超える財産については処分して債権者への配当に充てることが原則となります。特に持ち家については、住宅ローンの有無にかかわらず処分の対象となる可能性が高く、多くの場合で転居が必要になります。
自動車についても、査定額が20万円を超える場合は処分の対象となる可能性が高くなります。これは多くの裁判所で採用されている運用基準の一つです。
さらに重要な点として、自動車ローンが残っている場合は、車の価値に関わらず、ローン会社によって車が引き揚げられるのが通常です。これは、ローン完済まで車の所有権がローン会社にあること(所有権留保)、そして自動車ローンだけを優先して返済することが「偏頗弁済」という禁止行為にあたるためです。
ただし、年式が古く価値が低いと判断される車両については、手元に残せる場合もあります。また、仕事上どうしても車両が必要な場合は、裁判所に事情を説明することで配慮を受けられる可能性もあります。
このデメリットへの対処法として、破産前に親族間での任意売却を検討したり、賃貸住宅への住み替えを事前に準備したりすることが考えられます。また、自動車については、処分後に中古車を現金購入することで、破産後速やかに必要な移動手段を確保することも可能です。
一定期間就けなくなる職業と復権までの流れ
自己破産の手続き期間中は、法律により一部の職業に就くことが制限されます。具体的には、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員、公証人などの職業が対象となります。
しかし、この制限は破産手続き期間中のみに限定され、免責許可決定が確定すると「復権」により資格制限は自動的に解除されます。通常、同時廃止事件であれば3か月から4か月程度、管財事件は6か月から1年程度で手続きが完了するため、制限期間は比較的短期間となります。
対象となる職業に就いている方は、手続き期間中の休職や配置転換について事前に勤務先と相談することが重要です。多くの企業では、従業員の個人的な法的手続きに対して理解を示し、可能な範囲で配慮してくれる場合があります。
保証人に迷惑がかかる場合の対応方法
債務者本人が自己破産により借金の返済義務を免れても、保証人や連帯保証人の責任は残り続けます。そのため、債権者は保証人に対して残債務の一括返済を求めることになり、保証人の生活に大きな影響を与える可能性があります。
この問題への対処方法として、まず保証人との事前の十分な相談が不可欠です。状況を正直に説明し、保証人自身も任意整理や個人再生、場合によっては自己破産を検討する必要があるかもしれません。また、保証人が返済を続けられる場合は、債権者との間で返済条件の変更について交渉することも考えられます。
重要なのは、保証人に対する事前の説明と謝罪、そして可能な限りの協力を行うことです。信頼関係を維持するためにも、隠すことなく誠実に対応することが求められます。
自己破産後の生活|よくある不安と疑問に回答
自己破産を検討する際、手続き後の生活がどのように変わるのかという不安を抱く方は非常に多くいらっしゃいます。「普通の生活ができなくなるのではないか」「社会から排除されるのではないか」といった心配をお持ちの方もいるでしょう。
しかし、実際には自己破産後の生活への影響は限定的であり、多くの方が想像するほど深刻な制約はありません。ここでは、自己破産後の生活に関してよく寄せられる質問と、その実際の影響について具体的に説明いたします。
携帯電話やスマートフォンは使い続けられる?
自己破産をしても、携帯電話やスマートフォンの利用には基本的に影響ありません。現在使用している端末代金を完済済みで、月々の利用料金に滞納がない場合は、そのまま継続して使用することができます。
ただし、端末代金を分割払いしている場合は注意が必要です。分割払いも借金の一種として扱われるため、自己破産の対象に含まれ、契約解除となる可能性があります。この場合、端末は通信会社に返却する必要が生じることもあります。
対処法として、破産手続き前に端末代金の残債を一括清算する、または破産後に新たに現金で端末を購入するという方法があります。格安SIMカードを利用することで、月々の通信費を大幅に削減することも可能です。現在では中古端末も豊富に流通しているため、比較的安価で質の良い端末を入手することができます。
海外旅行や出張は可能?パスポートへの影響は?
自己破産をしても、パスポートが没収されることはありませんし、新規取得も可能です。また、破産手続きが完了した後は、海外旅行についての制限も一切ありません。仕事での海外出張も通常通り行うことができます。
ただし、破産手続き期間中については一定の制約があります。管財事件の場合は、裁判所の許可なく長期間居住地を離れることや海外渡航をすることが制限されます。しかし、仕事上必要な出張については、事前に裁判所に申請することで許可を得ることが可能です。
同時廃止事件の場合は、このような移動制限はありません。手続き期間も3か月から4か月程度と短期間であるため、多くの方にとって実質的な影響は軽微となります。海外旅行を計画している場合は、手続き完了後に実行することで何の問題もありません。
職場にバレる?解雇される心配は?
自己破産をしたことが職場に知られる可能性は、一般的には非常に低いと考えられます。裁判所や弁護士が勤務先に連絡することは通常ありませんし、官報に掲載されるといっても、一般の方が官報を定期的にチェックすることはほとんどありません。
しかし、勤務先から借入をしている場合や、会社が保証人となっている借金がある場合は、債権者として破産手続きに関与することになるため、当然知られることになります。また、給与の差し押さえを受けていた場合は、すでに勤務先が状況を把握している可能性があります。
仮に自己破産の事実が職場に知られたとしても、それを理由とした解雇は法的に認められません。自己破産は私的な生活上の問題であり、労働能力や職務遂行能力とは無関係だからです。
ただし、前述した資格制限の対象となる職業の場合は、手続き期間中の配置転換や休職について会社と相談する必要があります。多くの企業では、従業員の個人的な困難に対して理解を示し、可能な範囲で配慮してくれる場合が多いのが実情です。
自己破産の手続きと費用|スムーズに進めるためのポイント
自己破産の手続きは複雑で専門的な知識を要するため、多くの方が弁護士に依頼することを選択します。ここでは、手続きの種類や流れ、必要な費用について詳しく解説し、自己破産をスムーズに進めるためのポイントをお伝えします。
費用面での不安を抱く方も多いですが、多くの法律事務所では分割払いや法テラスの利用など、経済的に困窮している方でも利用しやすい制度を用意しています。適切な準備と理解により、手続きを円滑に進めることができます。
同時廃止なら費用も期間も最小限
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、多くの個人の方は同時廃止事件として処理されます。同時廃止は、処分すべき財産がほとんどなく、免責不許可事由も特に問題がない場合に適用される簡略化された手続きです。
同時廃止事件の場合、裁判所費用は申立手数料1,500円、予納郵券4,950円、官報公告費約12,000円の合計約2万円程度と非常に経済的です。手続き期間も申立から免責許可決定まで3か月から4か月程度と短期間で完了します(借入状況による)。
この手続きでは破産管財人が選任されないため、管財人への引継予納金(通常20万円以上)が不要となり、費用負担を大幅に軽減できます。また、裁判所への出頭回数も最小限に抑えられるため、仕事への影響も少なく済みます。処分すべき財産がない方や、借金の原因が生活費不足など問題のない方は、同時廃止事件として扱われる可能性が高くなります。
弁護士に依頼するメリットと費用の目安
自己破産は本人申立も可能ですが、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいといえます。まず、受任通知により債権者からの督促が即座に停止し、精神的な負担が大幅に軽減されます。また、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて代行してもらえるため、手続きの負担が最小限となります。
弁護士費用の相場は、同時廃止事件で30万円から50万円程度、管財事件で50万円から80万円程度となっています。この金額は一括払いが困難な方でも、多くの法律事務所で分割払いに対応しており、月々2万円から3万円程度の支払いプランを組むことができる場合があります。
また、収入や資産が一定基準以下の方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用の立替払いを受けることができます。この制度では、立替費用は月5,000円から10,000円程度の分割返済が可能となります。
ただし、注意すべき点として、この立替援助は、管財事件になった場合に裁判所へ納める「引継予納金」(通常20万円以上)は原則として対象外です。弁護士費用は法テラスで立て替えられても、この予納金は別途自分で用意する必要があるため、事前に確認が不可欠です。
手続きに必要な書類と準備期間
自己破産の申立には多数の書類が必要となり、準備には通常1か月から3か月程度の期間を要します。主要な書類として、破産申立書、陳述書、家計収支表、資産目録、債権者一覧表などの法的書類に加え、住民票、課税証明書、給与明細書、預金通帳のコピー、保険証券などの添付書類が必要です。
特に重要なのが債権者一覧表で、すべての借入先を正確に記載する必要があります。漏れがあると後々問題となる可能性があるため、借入先の調査には十分な時間をかけることが重要です。クレジットカード会社、消費者金融、銀行、信用金庫、親族や知人からの借入など、あらゆる債務を洗い出す必要があります。
書類収集において困難な場合は、弁護士が代理で取得できるものもあります。また、一部の書類については裁判所の運用により省略可能な場合もあるため、効率的な準備のためにも専門家のサポートを受けることをお勧めします。準備期間中は新たな借入を避け、家計の見直しを行うことで、手続き後の生活再建の基盤を整えることも大切です。
まとめ|自己破産で借金問題を解決し、新たな人生をスタート
自己破産は、返済困難な借金問題を法的に解決し、経済的な再出発を可能にする重要な制度です。「人生の終わり」ではなく「新しい人生の始まり」として位置づけられる手続きであり、多くの方がこの制度を利用して借金の重圧から解放され、充実した生活を取り戻しています。
確かに一定のデメリットは存在しますが、それらは多くの場合一時的なものであり、借金問題を放置することのリスクと比較すれば、適切な選択肢といえる場合が多いのが実情です。重要なのは、正しい知識に基づいて冷静に判断することです。
自己破産により借金の返済義務が免除されれば、収入をすべて生活費や将来への備えに充てることができるようになります。家族との時間を大切にし、趣味や自己投資にも時間とお金を使えるようになり、人間らしい豊かな生活を取り戻すことが可能です。
M&Aや経営課題に関するお悩みはM&Aロイヤルアドバイザリーにご相談ください。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。