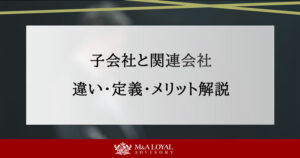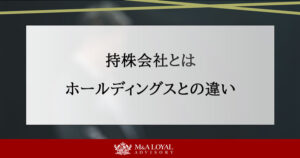関連会社とは?定義やメリット、関係会社との違いを紹介
着手金・中間金無料 完全成功報酬型
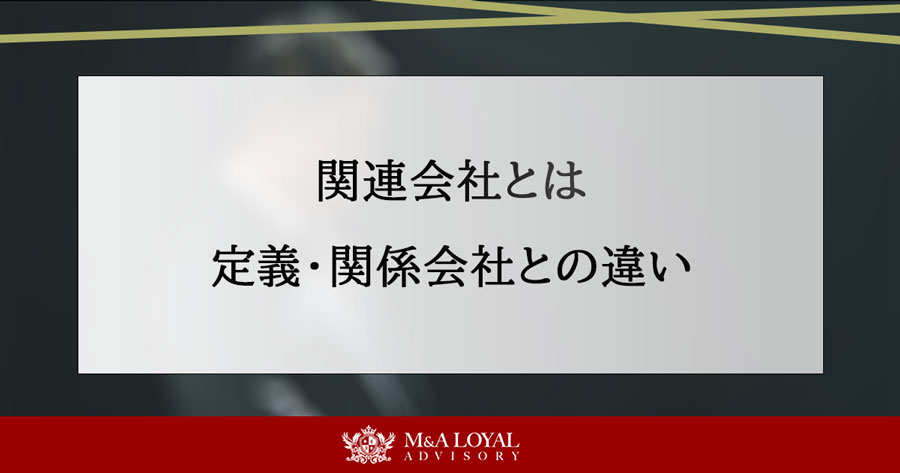
企業の株式保有や資本関係を示す用語として「関連会社」という言葉を耳にすることは多いでしょう。しかし、関連会社と子会社、あるいは関係会社との違いを正確に理解している経営者は意外と多くないのが実情です。
関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を所有し、経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社を指します。この定義は会社法や会計基準に基づくものであり、単なる取引先や業務提携先とは明確に区別されます。会社売却やM&Aを検討する際には、自社がどのような資本関係にあるのかを正確に把握することが重要です。
本記事では、関連会社の定義や判断基準、子会社や関係会社との違い、さらには関連会社を設立するメリットとデメリットまで、中小企業のオーナー経営者が知っておくべき知識を体系的に解説します。
目次
関連会社の定義
関連会社を正しく理解するためには、まず法的な定義と判断基準を押さえる必要があります。ここでは、関連会社とはどのような会社を指すのか、そしてどのような条件を満たせば関連会社と認められるのかを詳しく見ていきましょう。
関連会社の基本的な定義
関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を所有し、その会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社のことを指します。この定義は、会社法および企業会計基準に基づいて定められており、単に株式を保有しているだけでなく、実質的に経営に影響力を持つことが要件となっています。
また、関連会社は子会社とは異なり、親会社による完全な支配関係にはありません。あくまで「重要な影響を与えることができる」という関係性であり、日常的な経営判断は関連会社自身が独立して行うことができます。この点が、後述する子会社との大きな違いとなります。
議決権比率による判定の原則
関連会社かどうかを判定する際の最も基本的な基準は、議決権保有比率です。原則として、親会社が対象会社の議決権保有比率の20%以上を所有している場合、その会社は関連会社とみなされます。
ただし、議決権比率が50%以上になると、その会社は関連会社ではなく子会社として分類されます。子会社は親会社の支配下にあると考えられ、連結財務諸表の作成において全く異なる会計処理が求められるため、この境界線は非常に重要です。
また、複数の投資家が共同で出資している場合や、株式の持ち合いがある場合など、議決権比率の計算が複雑になるケースもあります。こうした場合には、実質的な支配関係や影響力を総合的に判断する必要があり、単純な数値だけでは判定できないこともあります。
議決権比率が20%未満でも関連会社になる場合
議決権比率が20%未満であっても、一定の要件を満たす場合には関連会社として扱われることがあります。これは、形式的な議決権比率だけでなく、実質的な影響力を重視する考え方に基づいています。
具体的には、議決権比率が15%以上20%未満の場合に、以下のいずれかの要件に該当すると関連会社とみなされます。まず、親会社の役員や従業員が対象会社の代表取締役や取締役、監査役などの役員に就任している場合です。役員の派遣は、経営に直接関与することを意味し、議決権比率以上の影響力を持つと判断されます。
次に、親会社が対象会社に対して重要な融資を行っている場合も該当します。資金提供を通じて経営に影響を及ぼすことができるためです。さらに、親会社が重要な技術を提供している場合や、販売・仕入などの重要な取引関係がある場合も、経営方針の決定に重要な影響を与えていると判断されます。
これらの要件は、財務諸表等規則や会計基準において明確に定められており、企業が関連会社の範囲を判定する際には慎重な検討が必要です。特にM&Aや事業再編を行う際には、これらの実質的な影響力の有無が取引の評価や会計処理に大きく影響するため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

THANK YOU
お問い合わせが
完了しました
ご記入いただきました情報は
送信されました。
担当者よりご返信いたしますので、
お待ちください。
※お問い合わせ後、
2営業日以内に返信がない場合は
恐れ入りますが
再度お問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い致します。
お急ぎの場合は
代表電話までご連絡ください。



関連会社と関係会社の違い
企業グループに関する用語として「関連会社」と「関係会社」はしばしば混同されますが、実は明確な違いがあります。ここでは、両者の定義と範囲の違い、法的根拠の違いについて詳しく解説します。
関係会社の定義と範囲
関係会社とは、親会社、子会社、関連会社を総称する用語です。つまり、関係会社という大きなカテゴリーの中に、子会社と関連会社が含まれるという関係性になります。この定義は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)第8条第8項に明確に規定されています。
関係会社は法的に定義された用語であり、単なる慣用表現ではありません。企業が財務諸表を作成する際には、関係会社株式を貸借対照表に記載する必要があり、投資家や債権者に対して企業グループの構造を開示する重要な情報となります。
関係会社の範囲には、直接的な資本関係だけでなく、間接的な支配関係も含まれます。例えば、親会社が子会社を通じて別の会社を支配している場合、その会社も関係会社に含まれます。このように、企業グループ全体の構造を把握するための包括的な概念が関係会社なのです。
関連会社と関係会社の使い分け
関連会社と関係会社の使い分けは、話題にしている企業の資本関係の範囲によって決まります。特定の会社について、親会社が20%以上の議決権を持ち、実質的な影響力を行使できる場合、その会社を「関連会社」と呼びます。一方、企業グループ全体を指す場合や、子会社、関連会社を含めた幅広い資本関係を指す場合には「関係会社」という用語を使います。
実務上、企業の有価証券報告書や決算短信では、「関係会社の状況」という項目で子会社と関連会社の一覧が記載されます。この場合の「関係会社」は、子会社と関連会社の両方を包括する意味で使用されています。個別の会社について言及する際には、「当社の関連会社である株式会社○○」というように、より具体的な「関連会社」という用語が用いられます。
また、会計処理の文脈では、「関係会社株式」という勘定科目が使われますが、これは子会社株式と関連会社株式を合わせた総称です。このように、文脈によって使い分けが必要であり、正確な理解が求められます。
関連会社と関係会社の会計上の取り扱いの違い
会計上、関連会社と関係会社では勘定科目の表示方法が異なります。貸借対照表において、子会社株式と関連会社株式は「関係会社株式」としてまとめて表示されることが一般的ですが、注記において内訳を開示する必要があります。
関連会社株式については、持分法による会計処理が適用されます。持分法とは、関連会社の純資産や損益のうち、親会社の持分に相当する額を親会社の財務諸表に反映させる方法です。具体的には、関連会社が利益を上げた場合、その利益のうち親会社の出資比率に応じた金額を「持分法による投資利益」として親会社の損益計算書に計上します。
一方、子会社の場合は連結財務諸表の作成が義務付けられており、子会社の資産、負債、収益、費用のすべてが親会社の連結財務諸表に合算されます。これは、子会社が親会社の支配下にあり、実質的に一体として事業を営んでいると考えられるためです。このように、関連会社と子会社では会計処理の方法が根本的に異なり、財務諸表への影響も大きく変わってきます。
関連会社と子会社の違い
関連会社と子会社は、いずれも親会社との資本関係を持つ会社ですが、その支配の程度や会計処理において大きな違いがあります。ここでは、両者の具体的な違いについて詳しく見ていきましょう。
議決権比率と支配関係の違い
子会社と関連会社の最も基本的な違いは、議決権比率と支配関係の程度です。子会社は、親会社が議決権の50%超を保有している会社を指します。この場合、親会社は株主総会における普通決議を単独で成立させることができ、取締役の選任や解任、重要な経営判断を実質的に支配することができます。
関連会社は議決権の20%以上50%以下を保有する会社であり、親会社は経営に重要な影響を与えることはできますが、完全な支配関係にはありません。関連会社の経営陣は、親会社の意向を尊重しつつも、独立した経営判断を行う余地が残されています。
また、子会社の判定においても、議決権比率が50%以下であっても実質的に支配している場合には子会社とみなされることがあります。例えば、親会社の役員が対象会社の取締役会の過半数を占めている場合や、重要な財務及び営業の方針の決定を支配する契約が存在する場合などです。このように、形式的な議決権比率だけでなく、実質的な支配関係も判定の重要な要素となります。
関連会社と子会社の会計処理の違い
関連会社と子会社では、会計処理の方法が根本的に異なります。子会社については、親会社が連結財務諸表の作成を義務付けられており、親会社と子会社の財務諸表を合算して作成します。この際、親会社と子会社間の内部取引は相殺消去され、企業グループ全体があたかも一つの企業であるかのように表示されます。
一方、関連会社については持分法による会計処理が適用されます。持分法では、関連会社の純資産のうち親会社の持分に相当する額を「関連会社株式」として貸借対照表に計上し、関連会社の当期純利益のうち親会社の持分に相当する額を「持分法による投資損益」として損益計算書に計上します。
この違いは、財務諸表に与える影響が大きく異なることを意味します。連結決算では子会社の全資産・全負債が親会社の連結貸借対照表に反映されるため、総資産や負債総額が大きく増加します。一方、持分法では関連会社への投資額と投資損益のみが親会社の財務諸表に反映されるため、その影響は限定的です。
経営上の関与の違い
子会社に対しては、親会社が取締役の選任を通じて直接的な経営管理を行うことができます。また、親会社の経営方針や事業戦略を子会社に対して指示することができ、グループ全体として統一的な経営を推進することが可能です。多くの場合、親会社から取締役や監査役が派遣され、定期的な経営会議や報告体制が整備されます。
関連会社に対しては、親会社の影響力は限定的です。重要な経営事項について意見を述べたり、提案したりすることはできますが、最終的な決定権は関連会社の経営陣にあります。ただし、取締役を派遣している場合や、重要な取引関係がある場合には、実質的な影響力は大きくなります。
M&Aの文脈では、この違いは非常に重要です。会社売却を検討する際、自社が他社の子会社である場合は親会社の承認が必須となりますが、関連会社の立場であれば、より独立した判断が可能になります。また、買収する側から見ても、対象企業が他社の子会社か関連会社かによって、買収後の経営統合の難易度が大きく変わってきます。
| 比較項目 | 子会社 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 議決権比率 | 50%超 | 20%以上50%以下 |
| 支配関係 | 完全な支配関係 | 重要な影響を与える関係 |
| 会計処理 | 連結法(親会社と子会社の財務諸表を合算) | 持分法(持分相当額のみ反映) |
| 経営への関与 | 直接的な経営管理が可能 | 影響力は限定的 |
| 財務諸表への影響 | 全資産・全負債が反映 | 投資額と投資損益のみ反映 |
関連会社を設立するメリット
企業が成長を続ける中で、グループ経営の一環として「関連会社」を設立するケースが増えています。関連会社を設立することで、本体企業の経営資源を有効に活用しながら、事業リスクの分散や新規分野への進出が可能になります。ここでは、関連会社を持つことで得られる主なメリットを具体的に解説します。
経営資源の効率活用とリスク分散
関連会社を活用する最大のメリットは、経営資源の効率的な活用とリスク分散です。関連会社として別会社を設立することで、人材、設備、技術などの経営資源を企業グループ内で共有しながら、各社の独立性を保つことができます。これにより、柔軟な事業運営と迅速な意思決定が可能になります。
経営戦略上のメリットとして、新規事業や異業種への進出を関連会社という形で行うことで、既存事業へのリスクを限定できます。万が一、新規事業が失敗した場合でも、本体企業への影響を最小限に抑えることができます。
シナジー効果の創出
関連会社を通じた事業提携や協業は、シナジー効果を生み出す重要な手段となります。例えば、製造業であれば部品供給会社を関連会社とすることでサプライチェーンを強化できますし、サービス業であれば補完的なサービスを提供する会社と関連会社関係を結ぶことで顧客への提供価値を高めることができます。
税務面での最適化
税務面でのメリットもあります。利益が出ている事業と赤字の事業を別会社として運営することで、法人税の実効税率を最適化できる可能性があります。具体的には、赤字の会社が利益を上げている会社とグループ内で連携し、適切な方法で税務戦略を立てることで、全体的な税負担を軽減することが可能です。ただし、税務上の損益通算には制限があるため、特に税務組織や関連会社間での取引に関する規制を考慮する必要があります。したがって、税理士などの専門家に相談することが重要です。
事業承継への活用
事業承継の観点からも、関連会社の活用は有効です。後継者候補に関連会社の経営を任せることで、段階的に経営経験を積ませることができます。また、複数の後継者がいる場合には、それぞれに異なる関連会社を承継させることで、相続における公平性を保ちながらスムーズな事業承継を実現できます。
関連会社を設立するデメリット
関連会社の設立は、経営資源の効率的な活用やリスク分散といった多くのメリットをもたらす一方で、注意すべきデメリットも存在します。グループ経営を進めるうえでは、単に事業領域を広げるだけでなく、管理体制や方針の整合性を保つことが求められます。ここでは、関連会社を持つ際に押さえておくべき主なデメリットと注意点について解説します。
経営管理の複雑化
関連会社を持つことのデメリットとして、まず挙げられるのが経営管理の複雑化です。複数の会社が存在することで、意思決定のプロセスが複雑になり、迅速な経営判断が難しくなる場合があります。特に、親会社と関連会社の間で利害が対立した場合、調整に時間とコストがかかることがあります。
利益配分と経営方針の対立
利益配分を巡る問題も発生しやすいデメリットです。出資比率に応じた配当を行う場合、関連会社の業績が好調であっても親会社が受け取れる配当は出資比率に応じた部分のみとなります。また、他の株主との間で配当政策や利益の再投資について意見が分かれることもあります。
経営方針の違いから生じる意見対立も、デメリットの一つです。関連会社は完全な支配下にないため、経営陣の独自の判断で親会社の意向と異なる方針を採用することがあります。これが企業グループ全体の戦略と矛盾する場合、調整に大きな労力が必要になります。
経営リスクの連鎖
経営リスクの連鎖も重要な注意点です。関連会社の一社が経営不振に陥った場合、その影響が企業グループ全体の信用力に波及する可能性があります。特に、関連会社が取引先や金融機関との関係で問題を起こした場合、親会社にも責任を求められることがあります。
設立・運営コストの増加
設立や運営にかかるコストも考慮が必要です。関連会社を設立するには、登記費用や資本金の拠出が必要です。また、運営を開始すれば、独立した法人として税務申告や決算書の作成が必要になり、管理コストが増加します。特に中小企業の場合、これらのコストが経営の負担になることがあります。
関連会社と混同されやすい会社形態
企業グループに関する用語は多岐にわたり、関連会社以外にもさまざまな呼称が使われています。ここでは、関連会社と混同されやすい会社形態について、それぞれの定義と特徴を明確にしていきます。
グループ会社と持株会社
グループ会社とは、親会社、子会社、関連会社を含む企業グループ全体を指す総称です。法的な定義があるわけではなく、慣用的に使われる表現です。企業が対外的に「当社グループ」や「○○グループ」という表現を使う場合、それがグループ会社を指しています。
持株会社は、他の会社の株式を保有し、その会社の経営を支配することを主な事業とする会社です。純粋持株会社と事業持株会社の2種類があり、純粋持株会社は株式保有と経営管理のみを行い、自らは事業を営みません。一方、事業持株会社は自らも事業を営みながら、他社の株式も保有して経営管理を行います。
持株会社は、企業グループ全体の戦略立案や経営資源の最適配分を行う司令塔としての役割を果たします。大企業では、みずほフィナンシャルグループ、野村ホールディングス、セブン&アイ・ホールディングスなど、多くの持株会社が存在します。中小企業でも、事業承継や組織再編の手段として持株会社を設立するケースが増えています。
兄弟会社と完全子会社
兄弟会社とは、同一の親会社を持つ子会社同士の関係を指す用語です。法的な定義はありませんが、企業グループ内での関係性を表現する際に広く使われています。兄弟会社間では、親会社の方針のもとで協力関係を構築することが多く、相互に製品やサービスを提供し合うことでシナジー効果を生み出します。
完全子会社とは、親会社が発行済株式の100%を保有している子会社のことです。完全子会社は親会社の完全な支配下にあり、親会社の経営方針を直接的に実行する役割を担います。意思決定が迅速に行えることや、親会社と完全子会社間の取引において利益相反の問題が生じにくいことがメリットです。
M&Aにおいては、既存の会社を完全子会社化することで、100%の経営権を獲得し、抜本的な事業改革や組織再編を行うことが可能になります。また、完全子会社化により、連結納税制度を活用した税務上のメリットを最大限に享受できるようになります。
連結子会社と特定子会社
連結子会社とは、親会社の連結財務諸表に含まれる子会社のことを指します。原則として、親会社が議決権の50%超を保有する会社、または実質的に支配している会社が連結子会社となります。連結財務諸表では、親会社と連結子会社の財務諸表を合算し、企業グループ全体の財務状況を開示します。
特定子会社は、親会社にとって特に重要性の高い子会社を指す会計上の概念です。具体的には、親会社の売上高、総資産、資本金などの一定割合(通常は10%から30%)以上を占める子会社が特定子会社とされます。特定子会社については、有価証券報告書などで個別に詳細な情報開示が求められます。
特例子会社は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて設立される子会社です。一定の要件を満たす特例子会社を設立することで、親会社と特例子会社を合算して障害者雇用率を計算できるため、企業の社会的責任を果たす手段として活用されています。ただし、特例子会社の設立には設備投資などのコストがかかるため、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。
| 会社形態 | 定義・特徴 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| グループ会社 | 親会社・子会社・関連会社を含む総称 | 慣用表現(法的定義なし) |
| 持株会社 | 株式保有により他社を支配する会社 | 独占禁止法(純粋持株会社解禁) |
| 兄弟会社 | 同一親会社を持つ子会社同士 | 慣用表現(法的定義なし) |
| 完全子会社 | 親会社が株式100%を保有する子会社 | 会社法 |
| 連結子会社 | 連結財務諸表に含まれる子会社 | 連結財務諸表規則 |
| 特定子会社 | 親会社の一定割合以上を占める重要子会社 | 財務諸表等規則 |
| 特例子会社 | 障害者雇用促進を目的とする子会社 | 障害者雇用促進法 |
まとめ
関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を保有し、経営方針の決定に重要な影響を与えることができる会社を指します。子会社との違いは支配の程度にあり、関連会社は親会社の完全な支配下にはなく、持分法による会計処理が適用される点が特徴です。関係会社は親会社・子会社・関連会社を包括する総称であり、企業グループ全体の構造を理解する上で重要な概念です。
関連会社を活用することで、経営資源の効率的な共有、リスク分散、シナジー効果の創出、事業承継の円滑化などのメリットが得られます。一方で、経営管理の複雑化、利益配分の問題、経営リスクの連鎖、運営コストの増大などのデメリットにも注意が必要です。M&Aや事業再編を検討する際には、自社の資本関係や企業グループ内での位置づけを正確に把握することが、戦略的な意思決定の前提となります。
中小企業のオーナー経営者が会社売却やM&Aを検討する際、関連会社や子会社といった資本関係の理解は不可欠です。複雑な企業グループ構造や株式保有関係がある場合、専門家のアドバイスを受けることで、最適な戦略を立案し、円滑な取引実行が可能になります。
CONTACT
お問い合わせ
当社は完全成功報酬ですので、
ご相談は無料です。
M&Aが最善の選択である場合のみ
ご提案させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。